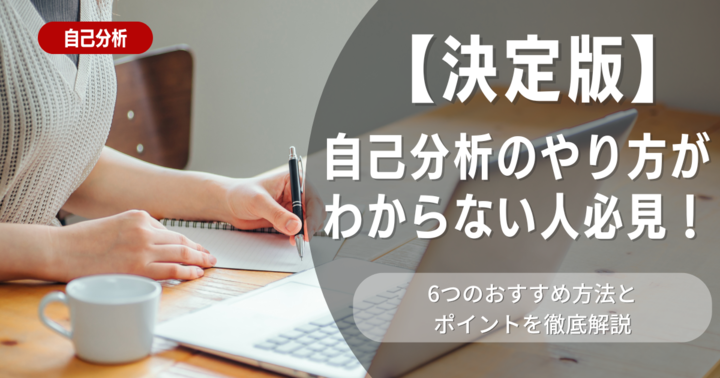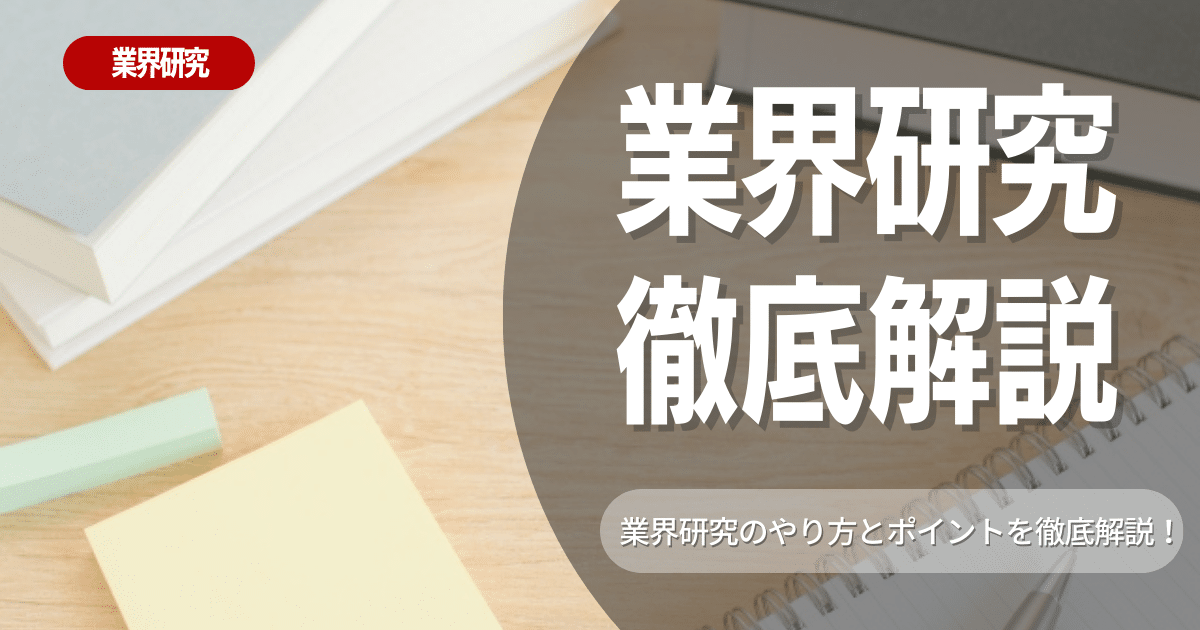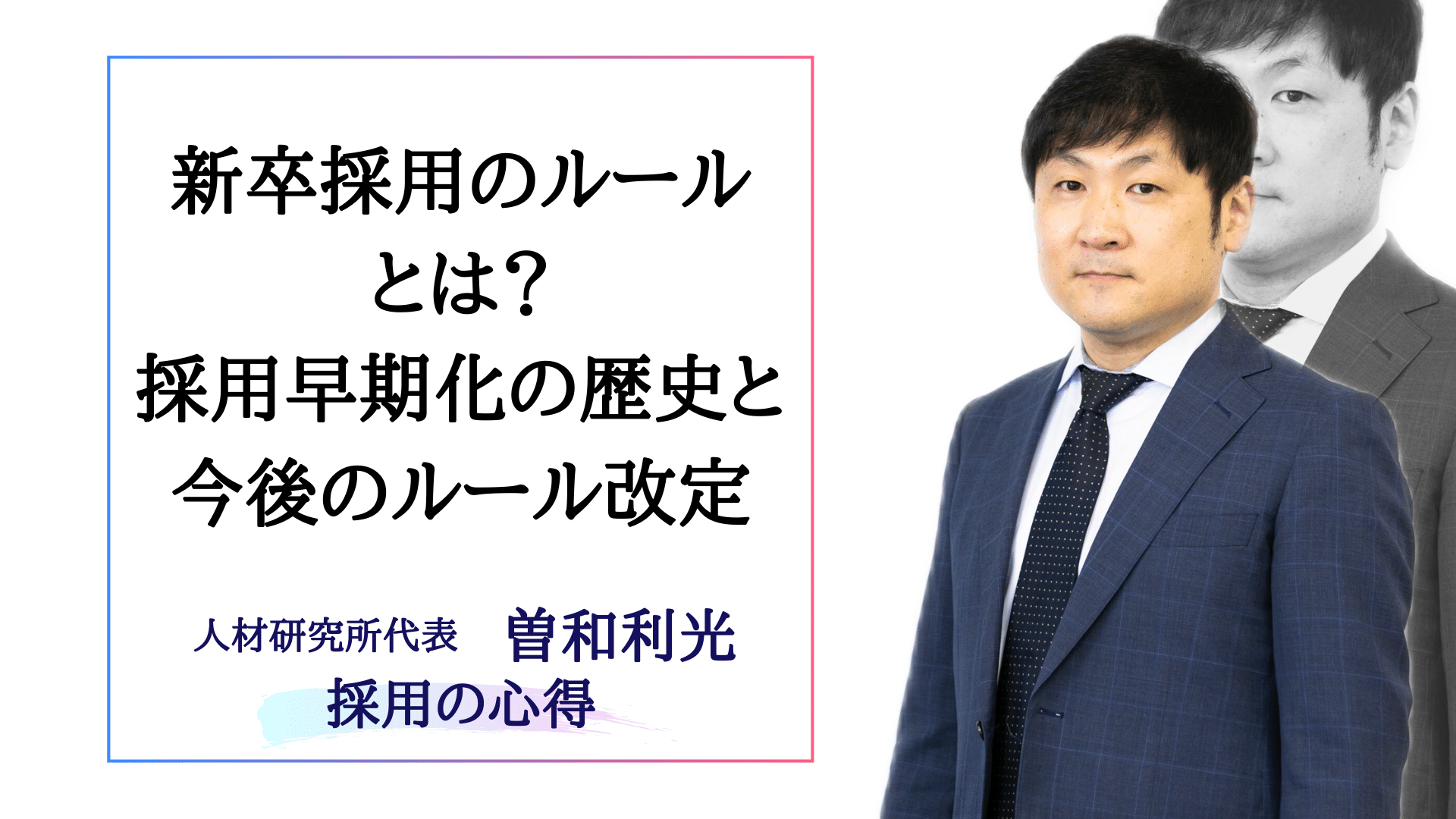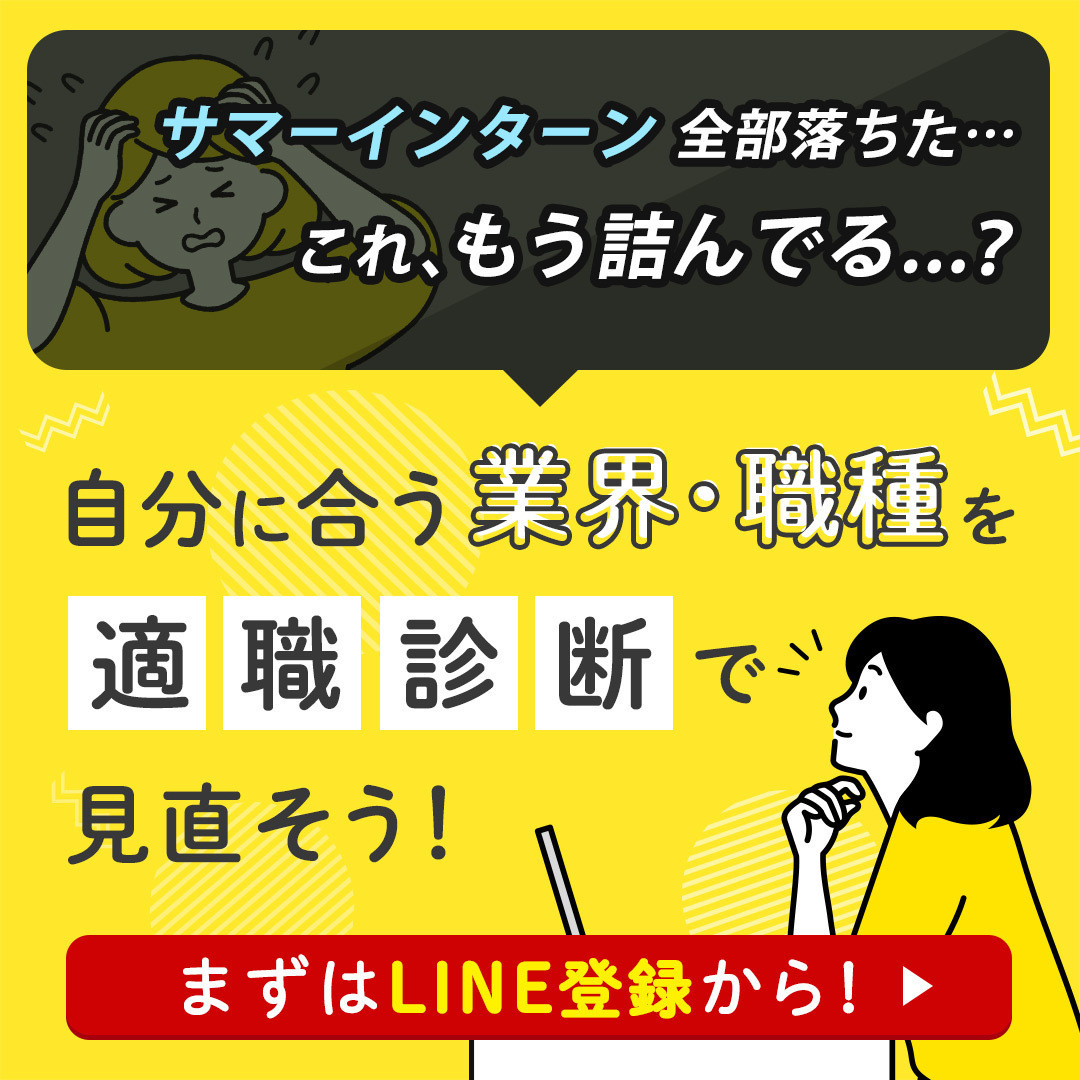【26卒】新卒採用スケジュールを解説!時期別の選考対策も紹介
2024/11/18更新
はじめに
就活を意識し始める新卒者の皆さんの中には、就活の進め方について悩みを抱えている方もいるでしょう。
就活は基本的に1人で進めていくため、周囲の学生に遅れを取らないよう、事前にスケジュールを把握することが重要です。
就活のスケジュールをあらかじめ把握することで、取り組むべき準備についても段階的に実践できます。
この記事では、2026年卒の新卒採用スケジュールについて詳しく解説しています。
新卒採用スケジュールを知りたい以下の就活生を対象に、時期ごとに適した準備事項も紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。
- 26卒の新卒採用スケジュールを知りたい
- 就活中に取り組むべき準備事項を時期ごとに知りたい
上京を志す地方学生ならジョーカツ!
あなたのキャリアを加速させるチャンス!
無料で利用できる快適な個室シェアハウス、
東京までの交通費サポート付き
首都圏の注目企業への就活ならジョーカツ
首都圏の学生ならスタキャリ!
理想のキャリアを実現へと導く第一歩!
あなたにピッタリのキャリアアドバイザーを選び、
自分にマッチする優良企業をご紹介
首都圏企業のES添削から面接対策まで、就活ならスタキャリ
【26卒】新卒採用スケジュール

新卒採用スケジュールは、就活に臨むうえで必ず知っておくべき「就活の生命線」とも言えます。
あらかじめスケジュールを把握しておくことで、就活に乗り遅れることなく、企業説明会やインターンシップ・選考に参加できるでしょう。
ここでは、新卒採用スケジュールを詳しく解説します。
大きく分けて6つの時期があります。
- 夏期(6〜8月)
- 冬季(9〜11月)
- 直前期(12〜2月)
- 採用広報解禁(3月〜)
- 選考時期(6〜9月)
- 内定時期(10〜3月)
1つずつ詳しく見ていきましょう。
夏期(6〜8月)
就活は、新卒者となる年の前年度から取り組み始めます。
4年制大学に通っている場合は、大学4年生が新卒者となるため、前年の大学3年生の夏から就活に取り組み始めるといいでしょう。
特に近年では、企業の「早期に優秀な学生の囲い込みをしたい」という思いと、学生の「早期に内定獲得したい」という思いが重なり、早期化が進んでいます。
就活に乗り遅れることのないよう、早めの段階から就活を意識してください。
6〜8月は夏期休暇に入る大学が多いですが、このタイミングでインターンシップに参加し始める学生が多いです。
また、インターンシップに参加する準備段階として、自己分析に取り組み始める学生が多い時期でもあります。
エントリーシートを用いて選考を実施する企業もあれば、選考を実施せず気軽に参加できる企業など、さまざまな種類のインターンシップがあるのです。
志望する企業のインターンシップについてこまめに情報を確認し、確実に参加するため、自己分析は早めに取り組んでおきましょう。
冬季(9〜11月)
9〜11月は、秋冬インターンシップに参加したり、業界研究・企業分析に専念したりなど、本選考に備えて自分が本当に就職したい企業を見つける時期です。
事前に取り組み始めた自己分析をもとに、就活の軸となる考え方や目標を決めて、自分の目標を達成できる企業選びを行いましょう。
【例①】
- 自分の強み:留学で得た語学力とコミュニケーション能力
- 成し遂げたい目標:語学力を活かした業務で海外出張などグローバルに活躍したい
- 志望する企業:海外事業に力を入れている企業・一定の語学力を採用基準に設けている企業など
【例②】
- 自分の強み:塾講師のアルバイトで培った指導力・計画性
- 成し遂げたい目標:指導力や計画性を活かした教育業界で、生徒の学力やスキル向上を手助けしたい
- 志望する企業:学校などの教育機関・塾を運営する民間企業など
上記のように自分の強みを客観的に理解することで、自分の適性を活かせる業界・企業選びをすることが可能です。
本選考が始まる3月までには、自己分析と企業研究を行い、志望する企業をある程度絞った状態にしておきましょう。
直前期(12〜2月)
企業の採用広報が解禁される3月の直前となる12〜2月は、これまでの企業説明会や、インターンシップで接点を持った企業の早期選考に進む時期です。
採用広報が解禁される前でも、説明会やインターンシップで早期選考の案内を出す企業も多いです。
早期選考に参加することで、本選考が有利に進むなどのメリットがあります。
早い段階から就活に取り組んでいた学生の中には、すでにこの時期に内定を獲得している学生もいるでしょう。
前述したように、企業は早期に優秀な学生を取り込みたいと考え、学生は早期に内定を獲得したいと考えているため、就活の早期化が進んでいるのが現状です。
可能な限り早期に内定を獲得するためにも、大学3年生の6月あたりには就活に取り組み始め、企業の早期選考ルートに乗り遅れないようにしましょう。
採用広報解禁(3月〜)
企業の採用広報が解禁される3月〜5月は、企業の説明会に積極的に参加する学生が増える時期です。
この時期までに、インターンシップや説明会に参加した企業以外に気になる企業があれば、公式HPからエントリーを行いましょう。
エントリーとは、企業に関心があることを意思表示する行為です。
応募とは異なりますが、エントリーすることで説明会や書類選考の案内を受け取れるため、志望企業には必ずエントリーしておきましょう。
また、この時期はさまざまな業界の企業が1つの施設に集まる「合同説明会」も頻繁に開催されます。
関心のある企業や業界が複数に及んでいる場合は、合同説明会も有効活用し、企業選びの判断材料にしましょう。
選考時期(6〜9月)
6月を過ぎると、多くの学生が内定を獲得している状況です。
6月以降に選考を開始するスケジュールを組んでいる大手企業や、金融業界の企業を志望している学生は、この時期から選考に臨むことになります。
この時期になっても1社も内定を獲得できていないと、不安になる学生は多いでしょう。
しかし、焦らず自分が就職したいと思える企業の選考に集中してください。
内定時期(10〜3月)
多くの企業では、10月に内定式を開催します。
そのため、10〜3月までは、内定をもらった企業で開催される内定式への参加、入社前研修・懇親会などへ参加する学生が多いです。
複数の企業から内定をもらっている場合は、できる限り早めに就職する企業を絞りましょう。
内定辞退は、相手企業の採用活動に迷惑をかけることに繋がるからです。
約1年弱に及ぶ就活の幕が閉じ、新社会人としての準備が始まる時期でもあります。
内定を獲得したからといって怠慢な生活を送るのではなく、1人の社会人としての意識を持ち、卒業まで計画的に過ごすことがおすすめです。
新卒採用に向けてやるべき選考対策7選

ここまで新卒採用スケジュールを6つの時期に分けて詳しく解説しました。
近年は、就活の早期化が進んでいます。
早期選考ルートに乗り遅れないためにも、早めの段階で就活の準備を行うことが大切です。
ここでは、就活が本格化する前にやっておくべき準備事項について7つ解説します。
それぞれを早期に取り組んでおくことで、焦らずスムーズに就活を進められるでしょう。
具体的には以下7点です。
新卒採用に向けてやるべき選考対策7選
・自己分析
・業界研究・企業分析
・インターンシップへの参加
・OB・OG訪問
・エントリーシートの作成
・適性試験対策
・面接対策
それぞれ1つずつ詳しくみていきましょう。
自己分析(6〜8月)
自己分析は、就活において基本となる重要な準備事項です。
自己分析を行うことで、これまで自分が経験してきたことや継続してきたことなどを客観的に理解できます。
これらの自分の経験から、自分の強みや長所を見出すことが可能です。
分析した強みや長所は、企業に「自分を採用するメリット」として、自己PRや志望動機でアピールできるでしょう。
また、自分の強みや特徴・得意なことを理解することで、適性を活かせる業界や職種も見えてきます。
自然に「就職したい企業」の軸が出来上がり、企業選びもスムーズに行えるため、ぜひ自己分析は早めに取り組んでください。
準備時期としては、本選考が本格化する3月の前年4〜8月がベストです。
夏期インターンシップの開催が多いこの時期に自己分析に取り組むことで、インターンシップに参加する企業を絞れるでしょう。
また、就活の軸が定まることで、その後の業界研究や企業研究を滞りなく進めることが可能です。
可能な限り早めに自己分析に取り組み、自分の強みと就活の軸を定めておくことがおすすめです。
なお、自己分析には、自分史やモチベーショングラフ・マインドマップなどさまざまな方法があります。
自分が取り組みやすい方法を見つけて、早い段階で自己分析に取り組みましょう。
自己分析の詳しいやり方は以下の記事でも紹介しているので、ぜひ参考にしてください。
業界研究・企業分析(9〜2月まで)
自己分析を終えたら、業界研究や企業分析に取り組んでください。
自分の適性を活かせる職種を見つけても、企業の社風や事業内容が理解できていななければ、自分とマッチする企業かどうかの判断ができません。
以下3つの方法を参考に、業界や業種を絞らず、興味があれば積極的に企業情報を集めましょう。
企業分析を行う前提として、各企業の公式HPには必ず目を通してください。
企業の公式HPには、会社概要や企業理念・ビジネスモデルや新卒者向けの採用ページなど、企業にまつわるあらゆる情報が掲載されています。
一通り目を通すことで、企業の社風や考え方・特徴が理解できるため、自分とマッチしているかを判断する材料にできるでしょう。
また、企業の公式HPで確認した情報をもとに、インターンシップやOB・OG訪問をする必要があります。
企業に関する情報を何も得ていないまま参加して、採用担当者の評価を下げないように注意してください。
企業分析の基本となる事項です。
興味や関心のある企業情報は、必ず公式ホームページで確認しておきましょう。
「ホームページを見てもわからないこと」や「もっと知りたいこと」を明らかにした上で、本格的な情報収集に乗り出してください。
企業分析や業界研究の詳しいやり方が知りたい方は、以下の記事をチェックしてみましょう。
インターンシップへの参加
企業分析の一環として、インターンシップにはぜひ参加しておきましょう。
インターンシップに参加することで、企業に訪問して事業や社風・職場の雰囲気を直接肌で感じることが可能です。
公式ホームページや説明会・資料などの情報ではわからない実際の企業の雰囲気が体感できるため、入社後のギャップを最小限に抑えられます。
近年ではオンライン上でインターンシップを開催する企業も多いですが、インターンシップは採用担当者と直接話せる貴重な機会です。
普段の情報収集ではわからない企業の社風や社員の雰囲気を体感できるため、興味がある企業なら、ぜひインターンシップに参加してみてください。
インターンシップは、前年の6〜8月の夏期に開催される場合と、9〜11月の冬季に開催される場合の2パターンがあります。
インターンシップに参加することで、企業に自分の熱意を伝えられるだけでなく、早期選考ルートに入り込める可能性もあるのです。
就活を有利に進めるためにも、インターンシップ情報をこまめに確認し、積極的に参加しましょう。
インターンシップへの参加方法やメリット、準備や対策について解説している記事もあるので、合わせてご覧ください。
OB・OG訪問
OB・OG訪問では、現役の先輩社員に、直接実際の業務について話を伺うことができます。
ある程度志望企業を絞れても、「実際の働き方ややりがいはどうなんだろう」と疑問に感じる部分も、OB・OG訪問で質問できるでしょう。
企業の公式HPや説明会では得られない、職場の雰囲気や仕事のやりがい・企業の長所や短所など細部に至るまで、実際に働いている人のリアルな意見が聞けます。
就活生にとって非常に有意義な情報となるため、積極的にOB・OG訪問を行いましょう。
また、就活が本格化する3月以降はスケジュール調整が難しくなる可能性もあるため、直前期となる2月までの段階でOB・OG訪問するのがおすすめです。
OB・OG訪問の詳しいやり方に関しては以下の記事も参考にしてください。
エントリーシートの作成
企業に応募する際は、エントリーシートの提出が求められることがほとんどです。
エントリーシートには志望動機の他に、自分の強みや長所・短所などについて記載を求める企業も多く、事前準備が重要です。
就活が本格化する3月までに、下記の3項目に関しては、ある程度作成した状態を目指しましょう。
- 志望動機
- 自己PR
- 学生時代に頑張ったこと
志望動機
志望動機は、どの企業でも確実に聞かれる質問です。
自己分析と企業分析をもとにじっくりと時間をかけて考える必要があります。
エントリーシートの提出を求められてから考えると、提出日までの時間がなくなってしまい、焦りから完成度の低い志望動機となってしまいます。
そのため、あらかじめ志望動機を考えておくことが大切です。
企業は志望者の自社に対する熱意や志望度を測るために、「志望動機」を確認しています。
本命・滑り止め関係なく、どうしてその企業を選ぶのか・その企業でなくてはならない理由を明確に記載し、企業に熱意を伝えましょう。
自己PR
自己PRも、志望動機と同じくほとんどの企業で聞かれる事項です。
準備段階で自己PRをいくつか用意しておくことで、エントリーシートをスムーズに提出できます。
企業は、自社にマッチする人材を採用したいと考えているのです。
企業の特徴と自分の強みをリンクさせて、自分を採用するメリットを述べることが大切です。
企業分析で明らかになった「求める人物像」をもとに、自分の能力やスキルをどのように活かせるかを伝える自己PRを作成しましょう。
単に強みを述べるのではなく、企業の社風や事業内容・求める能力と一致させることで、説得力のある自己PRとなります。
学生時代頑張ったこと
学生時代に頑張ったこと、いわゆる「ガクチカ」も、多くの企業で頻出される質問事項です。
企業は、就活生が「学生時代に頑張ったこと」を聞くことで、就活生の強みや能力から自社に貢献してくれる人材かを確認しています。
学生時代に頑張ったことを伝える際は、以下の順序で伝えると効果的です。
- 頑張ったこと(結論)
- なぜ頑張ったのか(理由)
- どういう経験をしたのか(具体的なエピソード)
- 経験から得たことを入社後どのように活かせるのか
自己分析で明確になった経験や自分の強みを、企業にどのように活かせるのかを考えながら作成することが大切です。
適性試験対策
新卒者が新卒採用スケジュールの間にやっておくべき準備事項として、試験対策があります。
就活が本格化する3月以降は時間に余裕がなくなるため、できる限り早い段階から試験対策にも力を入れましょう。
企業の選考過程では、適性試験やグループディスカッションを取り入れることが多いです。
対策を入念に行い、万全な状態で選考に挑みましょう。
適正試験とは、履歴書やエントリーシートではわからない志望者の能力や、内面を測る試験を指します。
適性検査にはさまざまな種類がありますが、SPIや玉手箱などを取り入れている企業は多いです。
書類選考後や1次面接後に適性検査を実施し、突破できないと最終面接に進めない企業も非常に多いです。
せっかく自己分析・企業分析をしっかり行っても、適性検査で落ちてしまうということがないように、対策を入念に行いましょう。
特に能力検査の出題範囲は幅広く、直前の対策だけでは網羅しきれないため、各試験の参考書や対策アプリを参考に対策することが肝要です。
面接対策
グループディスカッションや面接対策は相手が必要なため、対策に時間や場所の制限がかかります。
こちらもまとまった時間が取りづらくなる3月までに対策しておきましょう。
グループディスカッションや面接対策には、大学のキャリアセンターや就活エージェントの活用がおすすめです。
就活を進める中で、どちらも効率よく活用することで早期に対策できるでしょう。
面接の頻出質問やマナーについて解説している記事もあるので、ぜひチェックしてみてくださいね。
さいごに
本記事では、新卒者向けの採用スケジュールについて詳しく紹介しました。
就活では採用スケジュールを把握して、計画的に準備することが重要です。
この記事で紹介した準備事項に早期から取り組むことで、余裕を持って就活に臨めるでしょう。
特に近年の就活は、早期化が進んでいます。
早期選考ルートで内定を獲得したいなら、大学3年生の春から自己分析やエントリーシートの作成に取り組み、夏や冬のインターンシップに積極的に参加しましょう。
企業ごとに採用スケジュールは異なるため、興味のある企業の最新情報を随時確認しながら時期に合わせた準備を行い、納得できる就活にしてください。
この記事があなたの役に立つことを願っています。