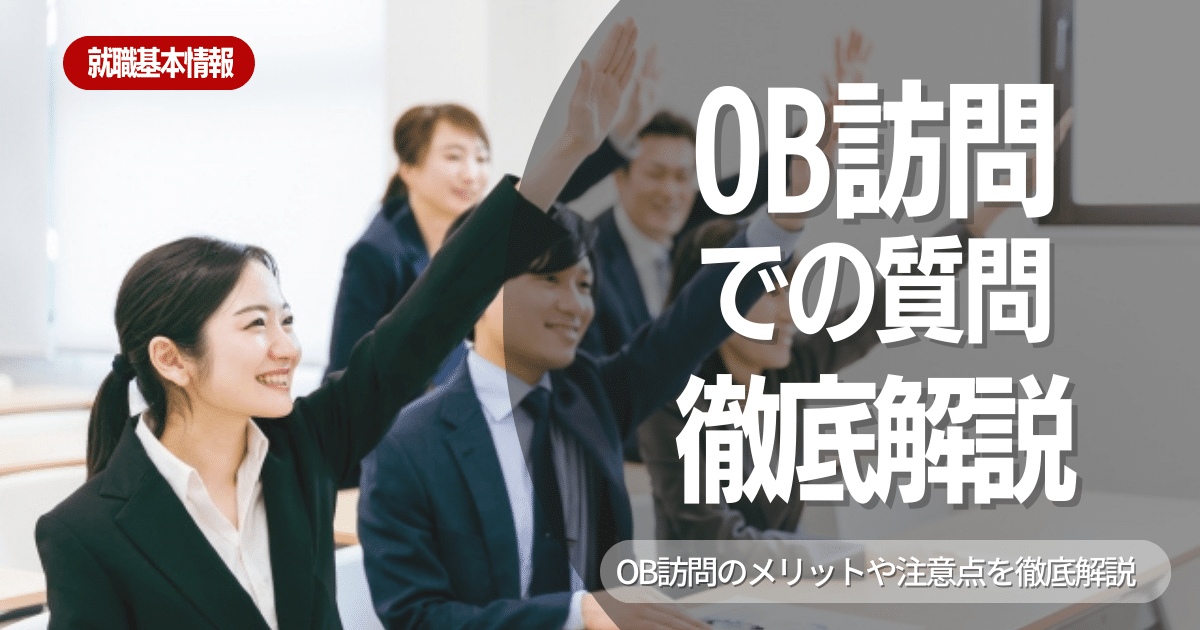【BtoC企業】自分に合った適職が判別できるチェック法
2024/9/25更新
はじめに
会社説明会等で「BtoC」という言葉を聞いたことはありませんか。
しかし、具体的に説明するよう求められても難しいと感じる人もいるのではないでしょうか。
まずはこの記事では、あなたがBtoC企業に向いているかチェックします。
しかし、自分がBtoC企業に向いていても向いていなくても企業研究は進めていく必要がありますね。
就職活動をする上でBtoCやBtoBといったビジネスモデルは知っておきたいビジネス用語になります。
そこで、BtoCの定義についてほかのビジネスモデルと比較しながら、その違いやメリット、デメリットについても解説いたします。
この記事の対象となる人は以下の通りです。
- BtoC企業が自分に合っているか知りたい人
- BtoCの定義について知りたい人
- BtoC以外のビジネスモデルについて知りたい人
- BtoCのメリット・デメリットを知りたい人
この記事を参考にしていただき、BtoC企業について知識を深めるだけでなく、自分が向いているかどうかも知る機会にしてみてください。
上京を志す地方学生ならジョーカツ!
あなたのキャリアを加速させるチャンス!
無料で利用できる快適な個室シェアハウス、
東京までの交通費サポート付き
首都圏の注目企業への就活ならジョーカツ
首都圏の学生ならスタキャリ!
理想のキャリアを実現へと導く第一歩!
あなたにピッタリのキャリアアドバイザーを選び、
自分にマッチする優良企業をご紹介
首都圏企業のES添削から面接対策まで、就活ならスタキャリ
BtoCとは?BtoBとの違いは?

「BtoC」は、Business to Consumerの略称で、企業がモノやサービスを直接個人(一般消費者)に提供するビジネスモデルです。
「B2C」と表されることもあります。
例えば、普段買い物をするスーパーやコンビニエンスストア、家電メーカーやアパレル、デパート、ドラックストア、旅行やホテルも含まれます。
消費者にまず知ってもらうことが重要となるBtoCは、テレビや雑誌、新聞などのマスメディアや広告などを利用し一般消費者に商品やサービスをアピールします。
BtoCは一般消費者に商品やサービスを選んでもらえるかどうかが大切で、多くのBtoC企業は認知度を広げるために努力しています。
一方で、「BtoB」はBusiness to Businessの略称で、簡単にいえば企業同士のビジネスを指す言葉です。
「B2B」と表されることもあります。
このビジネスモデルでは、商品やサービスを売り込むターゲットは限定されているため、BtoC企業のように広告などマスメディアでの認知度は重要ではありません。
取引先はだいたい固定されているため、新規取引先を獲得する場合にはリスティング広告、テレマーケティングなど直接アプローチできるように働きかけます。
アクセンチュアやアビームコンサルティングといったコンサルティング業も、このビジネスモデルの代表です。
2つのビジネスモデルには、企業が商品やサービスを個人消費者に提供するか企業に提供するかの違いがあります。
家電メーカーのように一般消費者に直接提供せずに、家電量販店などを介して提供する場合はBtoCになります。
上記以外にもいくつかビジネスモデルがありますので、解説いたします。
参考にしてみてください。
| ビジネスモデル | 定義 |
| CtoC
(Consumer to Consumer) |
個人が個人に対してモノやサービスを提供するモデルであり、インターネットの普及によって広がった 例)メルカリ、ヤフオク! |
| BtoE
(Business to Employee) |
企業が従業員に対して商品やサービスを提供するモデルで、福利厚生の意味合いが強い
例)従業員向けの食堂や保養所などの福利厚生サービス |
| BtoG
(Business to Government) |
企業が行政(官公庁や地方自治体)に対してモノやサービスを提供するモデル
例)建設コンサルタントなど |
| GtoC
(Government to Consumer) |
行政(官公庁や地方自治体)が個人に対して商品やサービスを提供するモデル
例)ふるさと納税、住民票の電子申請、電子予約 |
| DtoC
(Direct to Consumer) |
メーカーが(卸売業者や店舗を介さず)直接消費者に商品を提供するモデルで、消費者に直接販売することでコスト削減になる
例)自社のECサイト |
「BtoC」と「BtoB」の違い
ここまで定義について解説してきましたが、エンドユーザー以外でも「BtoC」と「BtoB」には特徴や傾向、扱う商材などの違いがあります。
以下にまとめましたので、ご覧ください。
| 区分 | BtoB | BtoC |
| 扱う商材 | 完成品に必要な素材、パーツ、社内ツール | 完成品、完成されたサービス |
| 購入までの期間 | 長いスパン(1カ月~数カ月) | 短いスパン(1日~数日) |
| 意思決定者 | 部署や企業のトップ | 消費者個人 |
| 契約単価 | 高額(6桁を超えることもあり) | 基本的には安価 |
| リピート注文の割合 | 高い | 低い |
| 広告宣伝費ウエイト | 低い | 高い |
| マーケティング手法 | 相手にとって役に立つか、論理性重視 | 消費者の感情に訴えかける、嗜好性重視 |
| 知名度 | 低め | 高め |
| ブランド意識 | 低め | 高め |
扱う商材について、イメージとしてはBtoB企業がつくった商品をBtoC企業が購入し、自動車や日用品などをつくるといったところです。
購入までの期間について、BtoBの場合は意思決定までに複雑なプロセスがあるため商品やサービスの消費にかかる時間は長いです。
契約単価について、BtoBの場合顧客が企業のため安定した収益が期待できます。
BtoCの場合は、一般消費者が手に取りやすい価格になっています。
リピート注文の割合について、BtoBの場合は一度契約が決まるとまた同じところから注文を受けるケースが多いです。
広告宣伝費のウエイトについて、BtoCは一般消費者のニーズ獲得のためにメディアなどでの宣伝にお金をかけます。
マーケティング手法について、BtoBはいかに役に立つ商品かどうかを理解してもらえるようなアピールが必要です。
BtoCの場合、テレビのCMなどのイメージが大切で、消費者の感情に訴えかける傾向が多いです。
知名度について、BtoBは企業との取引が多くなるため一般消費者になじみのあるBtoCに比べると、名前を知られることは少ないでしょう。
ブランド意識について、BtoBの場合はブランド力よりもその商品の本質的な良さが重要で、論理的に売り込みできるかが大切です。
それに比べてBtoCは「この企業だからこの商品を買う」というケースが多く、ブランドは大きく影響します。
BtoC企業に就職するメリット・デメリット
ここまで、BtoC企業についてBtoB企業と比較して解説しました。
しかし、BtoC企業に就職する際のメリットとデメリットは知っておきたいところ。以下でチェックしておきましょう。
BtoC企業に就職するメリット
BtoC企業に就職するメリットは以下の通りです。
- 知名度が高く、仕事のモチベーションが保てる
- 社会の役に立っている実感を得やすい
- 購入スパンが短いため成果が見えやすい
- ブランドを構築する面白さ
- 対象顧客が多い
- 顧客の意見が聞きやすい
BtoC企業のメリットは、何と言ってもBtoB企業に比べて知名度の高い会社が多いことです。
BtoC企業は広く一般大衆にテレビやSNSでCMを流します。
スーパーなどで手にしたことがあったり、実際に購入して使ったりと、比較的一般消費者の目に触れやすい身近な存在に感じます。
企業名や商品名を言えば周りは分かってくれるので、「自分もこの商品に関わっているんだ」と実感がわきやすく、働くモチベーションにつながります。
おのずと知名度が高くなるので、就活の競争率も高くなっていくでしょう。
また、自分が携わった商品がSNSで紹介されたり、商品の感想をダイレクトに聞けたりするのもメリットといえます。
なかでも、お客様からの励ましや喜びの声をいただくと、モチベーションが上がり、やりがいにつながります。
SNSなどでヒアリングした顧客のリアルな意見を、商品やサービスに反映しやすい部分も魅力といえるでしょう。
そういう意味では、世の中に役立っている感が得やすいですね。
また、BtoBでは契約まで何人もの担当者の決裁をまたぐ必要があります。
BtoCでは消費者を直接相手にするため、企業と比べると検討期間も圧倒的に短くて済みます。
相対的に単価は低いですが、顧客数が多く、リスクダメージは低いといえるでしょう。
BtoC企業に就職するデメリット
BtoC企業に就職するデメリットは以下の通りです。
- 知名度が高く就職難易度が高くなる
- 仕事が成果につながらないことがある
- 他社との競争が激しい
- 景気に左右されやすい
- ブランドの影響力が大きい
デメリットとしては、消費者を相手とするビジネスであるがゆえにライバルが多く、景気にも左右されやすいことです。
顧客を逃さないために、いかに消費者のニーズに合わせられるかが重要なカギとなります。
また、テレビCMやSNSなどによるブランディングも不可欠です。
さらに、せっかく完成した商品が消費者にウケないこともこともあり、必ずしも成果につながるとは限りません。
いかに消費者の心に刺さるアピールをするかが重要です。
消費者マインドの変化を敏感に察知し、その変化に対応した適切なマーケティングを仕掛けていくことが生命線だということです。
そして有名企業が多いため興味を持つ学生が多く、それに比例して就職難易度も高くなります。
BtoC企業にこだわるのであれば、他の就活生と差をつけられるように努力する必要があります。
代表的なBtoC企業一覧
実際のBtoC企業の名前を見るとイメージが湧きやすいでしょう。
代表的な企業を紹介します。
| 区分 | 企業名 |
| 食品 | 味の素、伊藤ハム、江崎グリコ、カゴメ、カルビー、キッコーマン、キユーピー、東洋水産、ニチレイ、日清オイリオ、日清食品、日清製粉、日本水産、日本ハム、ハウス食品、マルハニチロ、明治、森永製菓、森永乳業、ヤクルト |
| 飲料 | アサヒ、伊藤園、キリン、サッポロ、サントリー |
| 化粧品・消費財 | 花王、コーセー、資生堂、ユニ・チャーム、ライオン、ポーラ・オルビス |
| 自動車 | いすゞ自動車、川崎重工業、スズキ自動車、SUBARU、トヨタ自動車、日産自動車、日野自動車、本田技研工業、マツダ、三菱自動車、ヤマハ |
| 家電 | NEC、ソニー、富士通、日立製作所、三菱電機、パナソニック |
| 時計 | カシオ計算機、セイコーエプソン |
| タバコ | JT(日本たばこ産業) |
| トイレ | TOTO、LIXIL |
| ゲーム | コナミ、セガサミー、ソニー、任天堂、バンダイナムコ |
| インターネット | Amazon、Google、DeNA、LINEヤフー、楽天、リクルート |
| アパレル・ファッション | ファーストリテイリング |
ただ、中にはパナソニックのように事業分野によっては「BtoB」のビジネスモデルの様相を呈している事業もありますので、ご注意ください。
パナソニックはどうしても家電のイメージが強く、BtoC企業のように思う人もいるかもしれません。
しかし、事業によっては半導体部品や電池などに特化してBtoBがメインとなっています。
企業ごとに行っている事業をしっかり調べておく必要がありますね。
BtoC企業の見分け方
実際に自分で調べていて、BtoC企業かBtoB企業なのかをどのように見分けたらよいのでしょうか。
ここでは、どのようにビジネスモデルを見分けるのかを解説いたします。
主に見分ける方法は以下の5つです。
- 企業のホームページ
- 就活サイト
- 会社説明会
- OB/OG訪問
- インターンシップ
①企業のホームページ
企業のホームページでは、会社の基本情報や事業内容を確認できます。
職種ごとに社員インタビューが掲載されていることもありますので、仕事の魅力ややりがいを通じて見分けられるでしょう。
まず、自分の興味のある業界にどのような企業があるのかを調査し、次に具体的な企業名で調査しましょう。
例えば、インターネット業界に興味があるのであれば「インターネット業界 企業」などと調べるといくつかの企業がヒットします。
➁就活サイト
リクナビやマイナビなどのサイトでは、「営業(個人向け・得意先中心)」「営業(企業向け・得意先中心)」といった具合で、対峙する顧客を軸に企業を抽出することも可能です。
しかし、このような就活サイトを活用する前には、企業についてある程度企業分析を行っておかないと、調べる企業に対するイメージが湧きません。
就活サイトは、見分ける際の1つの材料として考えておくといいかもしれませんね。
具体的な企業分析のやり方については、以下のページに詳しく解説されていますので参考にしてみてください。
③会社説明会
会社説明会に参加して説明を聞いてみるというのも手です。
直接、企業側の説明を聞き、どのような商品を売り出しているのか、どのようなビジネスを行っているのかを具体的に知ることができます。
説明でも分からない場合は、最後の質問コーナーで直接聞いてみましょう。
➃OB/OG訪問
疑問に思うことや不安に感じることがあれば、OB/OG訪問で確認するのがいいでしょう。
実際にその企業で働いている先輩に話を聞くことで、リアルな情報や裏情報を得られます。
会社説明会などでは、質疑応答の時間があっても時間が限られており、ゆっくり話を聞くことは難しいです。
OB/OG訪問ならマンツーマンで時間の許す限り質問でき、じっくりと話を聞けます。
また、OB/OG訪問であれば、大学のサークルや部活の先輩が対応してくれることもあります。
近しい人から情報を知ることができるので、聞きやすさという点ではほかの方法よりいいと考えます。
自分で調べて分からなかったことが明確になるはずです。
OB/OG訪問の際のポイントは以下のページを参考にしてみてくださいね。
➄インターンシップ
インターンシップは企業により内容は異なりますが、「企業や事業の説明」「グループワーク」「仕事体験」「社員との座談会」などが主です。
仕事が疑似体験できるグループワークや、現場で仕事体験ができる機会も多いです。
その業界や仕事が自分に向いているかどうかを見極めるチャンスともいえます。
企業のホームページや口コミなどのネット情報だけでは、企業の本質を理解するのは難しく、実際に会社を訪れて、社員の方と話してみて初めてわかることもたくさんあります。
あなたの理解と実態のズレが少なくなりますので、できるだけたくさんのインターンシップに参加することをおすすめします。
インターンシップについて詳しく知りたい方は以下のページをぜひ参考にしてください。
就活生必見:あなたの適職3軸チェック法

ここまでの解説でBtoCについて知識が深まったと思いますが、自分が実際にBtoC企業に向いているのか向いていないのかわかると就職活動もしやすいですね。
実は、BtoBとBtoCという1軸で適職を判断する行為は、リスクが伴います。
BtoBの中でも新しいものを求める部署や職種もありますし、BtoCの中にも少人数を相手にしたり、逆に大人数を顧客として対応したりする部署や職種があります。
BtoBやBtoCといったビジネスモデルの軸に加えて、「新規客と既存客のどちらがユーザーなのか?」「少人数を相手にするのか、はたまた大人数相手なのか?」 といったほかの要素を軸として加味しながら、立体的に適職を判断したほうが安全です。
式にすると下記のとおりです。
| 3軸の適職判断=(BtoB or BtoC)✖(新規 or 既存)✖(少人数 or 大人数) |
このように立体で捉えないと、BtoB企業に入ったはいいが、「自分に向かない新規開拓の営業を任せられて挫折した」「1人の顧客相手にじっくりと長期間かけて信頼関係を築くことが得意な人が、いきなり大人数を相手にする職種を任せられた」などと自分の強みが活かせないことが起きます。
そうならないためにも、3軸の各要素で適職を判別するほうがリスクは低くなるわけです。
もちろん、軸はほかの要素もいろいろありますが、まずはこの3軸を基本に自分の特性を知っておくことで、大はずしを避けられるでしょう。
以下で、3軸に分けて、それぞれ向く人の特徴をまとめてみましたので、セルフチェックしてみてください。
チェック項目の多い箱があなたの向く区分になります。
【BtoB or BtoCチェック】
| 区分 | 特徴 |
| BtoBに向いている人 | ▢真面目で誠実
▢安定志向 ▢やりがいより給料 ▢年収を上げていきたい ▢スケジュール管理が得意 ▢経営に安定を求める ▢論理的思考が得意 ▢交渉&プレゼン上手 ▢土日休みは大事 ▢刺激的な環境を求める |
| BtoCに向いている人 | ▢会社の知名度が大事
▢扱う商品やサービスの愛着を重視 ▢生活に身近なサービスを提供したい ▢好きなことで働きたい ▢臨機応変さがある ▢平日休みの仕事OK ▢発想力がある ▢論理より感覚派 ▢メンタルが強い ▢人の役に立ちたい ▢目に見える成果がほしい ▢新しいチャレンジが好き |
| 区分 | 特徴 |
| 新規に向いている人 | ▢企画好き
▢ヒラメキが得意 ▢飽き性 ▢チャレンジ思考 ▢話し上手 ▢正確さよりスピード ▢守りより攻めが得意 ▢勢いがある |
| 既存に向いている人 | ▢真面目
▢改善が得意 ▢継続力がある ▢堅実志向 ▢聞き上手 ▢スピードより正確さ ▢攻めより守りが得意 ▢安定感がある |
| 区分 | 特徴 |
| 少人数に向いている人 | ▢じっくりと話を聞く
▢深く考える ▢人間関係は狭く深く ▢長期の付き合いが得意 ▢完璧主義者 ▢真面目で誠実 ▢マルチタスクは苦手 ▢集中力がある |
| 大人数に向いている人 | ▢柔軟性がある
▢スケジュール管理が得意 ▢頭の切り替えが上手 ▢人見知りしない ▢完璧主義者ではない ▢予定を詰めても平気 ▢マルチタスクが得意 ▢人が好き ▢思考が論理的 |
BtoC向きの人でも、「新規✖大人数」向きの人がいるかもしれませんし、「既存✖大人数」向きの人もいるかもしれません。
ここで大事なことは、どの組み合わせが自分に一番向いているかを知ることです。
自分の向き・不向きを知ることで、判断基準を持ちながら、会社説明会で人事の話を聞いたり、質問できますので、その企業が自分に向いているのがどうかのアタリを付けやすくなります。
軸を持たずに企業研究をしたり会社説明会に参加したりすると、ポイントを押さえて効率の良い就職活動をすることができません。
仮に内定を獲得し、就職しても「自分の思っている企業と違った」と後悔することもあります。
ぜひ、3軸チェックで自分の軸を確定させて、自分に向いた企業を発見してくださいね。
さいごに
今回は、BtoCの定義やメリット・デメリット、BtoCに向いている人の特徴や自分に合った企業を見分けるチェック表を解説いたしました。
実際は「BtoC」と「BtoC」を一本の線でクッキリと線引きできる企業は少なく、大手になるほど両方のビジネスモデルを併用しています。
したがって、会社説明会の段階で、どのようなビジネスモデルの部署に配属されるのか、それは新規か、既存客相手なのか、少人数なのか大人数相手なのかをしっかりと見極め、自分の適性を考慮した上で絞り込んでいきましょう。
ここが欠落すると、向いていない業界や職種、ビジネスモデルに就職し、あとになってあえなくスピンアウトする結末を迎えることも否めません。
就職活動は時間が限られていますし、やることも多いですから、効率の良い就職活動をするためにも自分の軸をはっきりさせて方向性を定められるといいですね。
この記事を参考にして、後悔しない就職活動を行い、自分に合った企業に就職できることを心から願っています。