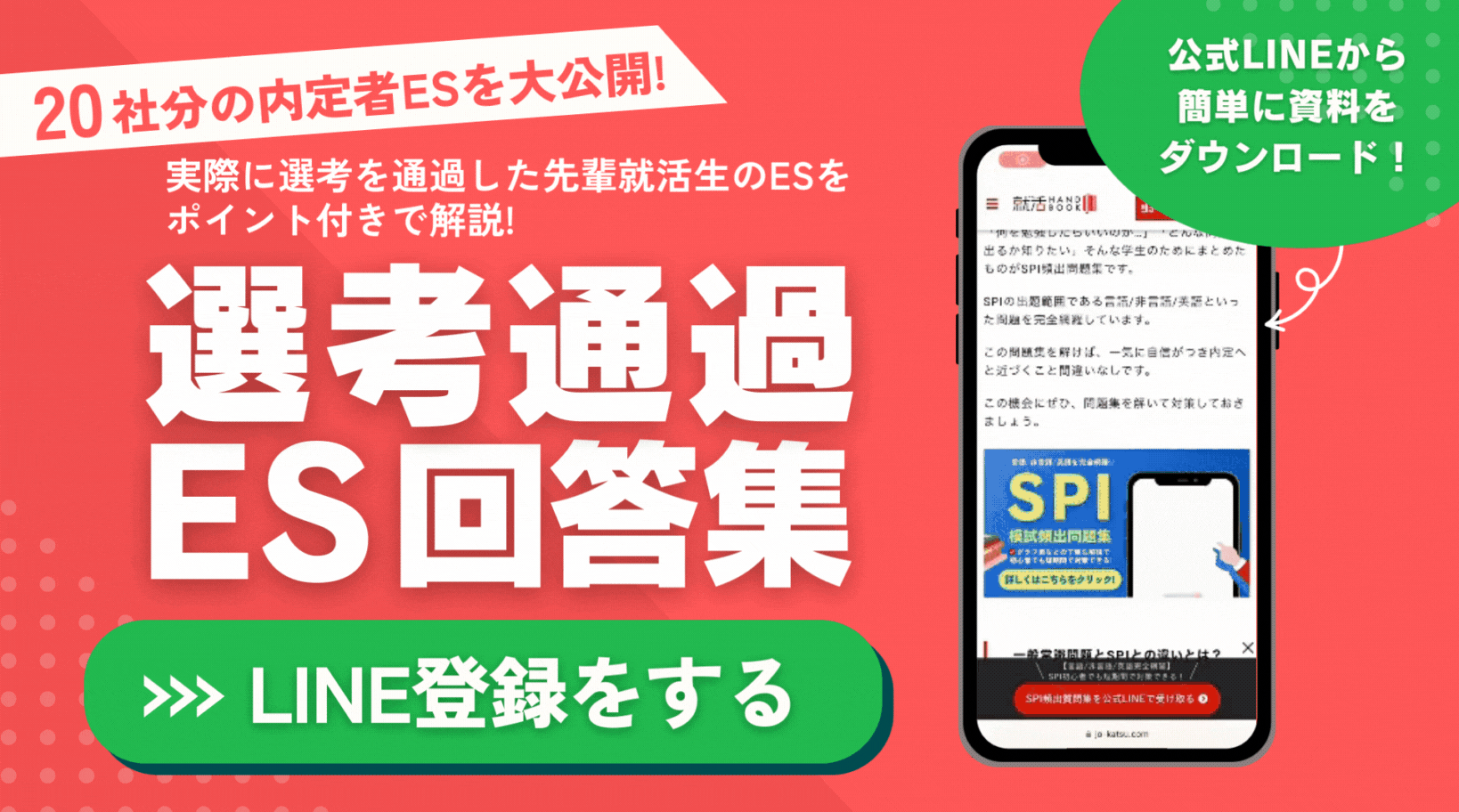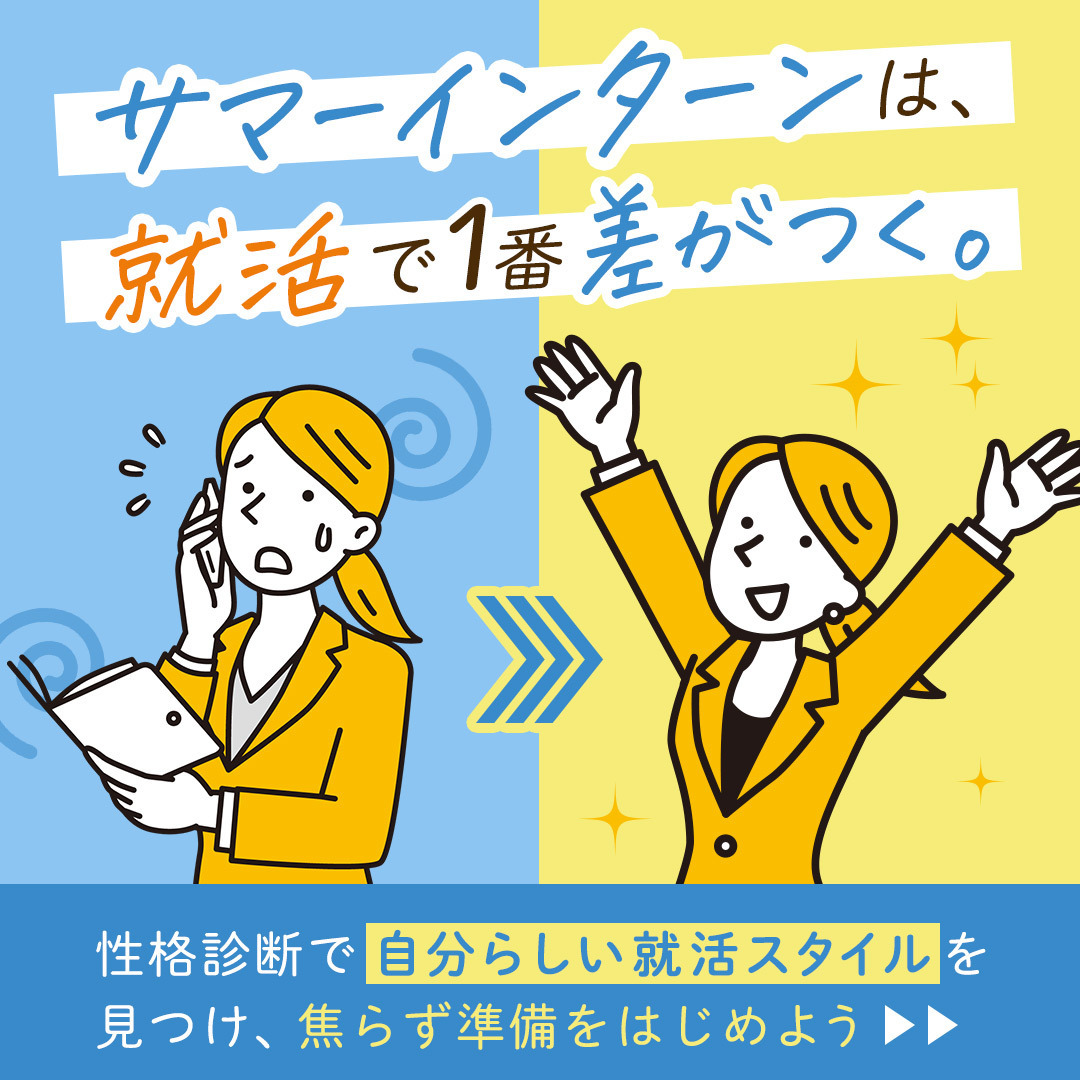総合職と一般職どちらに就職すべき?4つの判断基準を徹底解説
2025/2/22更新
はじめに
就職活動で直面する総合職と一般職の選択は、将来のキャリア形成に重要な影響を与えます。
日本企業の採用制度における主要な区分である総合職と一般職について、それぞれの特徴と選択のポイントを詳しく解説します。
- 総合職と一般職の具体的な業務内容の違い
- 自分に適した職種の見極め方
- 職種を選択する際の具体的な判断基準
- 総合職と一般職それぞれの特性を正確に理解できる
- 自分の適性に合った採用区分を判断できる
- 採用区分の選択に迷わず、効率的な就職活動が可能
就職活動を成功に導くために、採用区分の選択は重要な要素です。
この記事で説明する内容を理解することで、自分に合った就職活動の方向性が見えてくるはずです。
【選考通過したエントリーシートを大公開】先輩就活生のエントリーシートを見れば選考通過のヒントが得られるかも?!
「エントリーシートに正解はあるのか」「書き方が良く分からない…」こんなことを考えたことはありませんか?
就活生にとって、エントリーシートは第一関門ともいえるものです。
今回は、選考を通過したエントリーシートを20社分用意しました。
各エントリーシートにはポイント付きで解説しています。
総合職と一般職の4つの大きな違い
就職活動中、「総合職」「一般職」という言葉を目にする機会は多いでしょう。
しかし、「そもそも総合職とは?」「一般職で就職するのとどう違うの?」という疑問を持つ学生も少なくありません。
ここでは総合職と一般職の大きな違いについて、以下の4点から解説していきます。
- 業務内容・範囲
- 給料・年収
- 異動・転勤
- 昇進(キャリアアップ)
業務内容・範囲
総合職は企業の将来を担う幹部候補生として位置づけられ、企業の中心的な業務を遂行します。
企業は総合職を経営層の育成対象として、計画的な部署異動や高度な業務を任せることで、多様な経験を積ませる育成方針を採用しています。
このような広範な業務範囲と責任の重さは、給与などの待遇面に反映されます。
総合職は以下の2種類に区分されます。
| 職種 | 主な業務内容 | 採用傾向 |
| 事務系総合職 | 総務部門・経理部門・人事部門・企画部門・営業部門 | 文系中心 |
| 技術系総合職 | 研究開発部門・設計部門・品質管理部門 | 理系中心 |
給料・年収
総合職は一般職と比較して、基本給が高く設定されています。
企業の基幹業務を担う総合職は、業務の難度や責任範囲が一般職より広いためです。
厚生労働省が実施した令和5年賃金事情等総合調査によると、55歳時点での年収に以下のような差が見られます。
| 職種 | 55歳時点の年収 |
| 総合職(大卒) | 617万円 |
| 一般職(高卒) | 484万円 |
年収の差は133万円に達しており、30年以上の勤続期間を考慮すると、生涯賃金の差額は極めて大きくなります。
さらに総合職と一般職の給与体系の違いは、長期的な資産形成に大きな影響を与える要素といえるでしょう。
参照ページ
総合職を目指していて、さらに高収入を得たいという方は、ぜひ以下の記事も併せてチェックしてみましょう。
給与の高さは、モチベーション維持にも欠かせない要素です。
新卒でも高い年収を得られる企業もありますので、企業選びの参考にしてください。
総合職で高収入を得るには?業界別の平均年収ランキングを解説!
異動・転勤
総合職と一般職では、人事異動と転勤の範囲に明確な違いがあります。
総合職は幅広い業務経験を積むため、定期的な部署異動や全国規模の転勤が一般的です。
経営幹部候補として、企業全体を理解するために、全国各地の事業所での勤務が求められます。
近年は働き方の選択肢として、エリア総合職という新しい職種を導入する企業が増えています。
エリア総合職は、総合職と同等の業務内容でありながら、転居を伴う転勤がない点も特徴です。
転勤なしで総合職の仕事に挑戦したい方や、家庭の事情で転勤が困難な方に適していますが、給与などの待遇面では総合職より低く設定されています。
一般職は担当業務が特定の範囲に限定されるため、異動の機会は少なく、異動先の部署も限られています。
転勤についても、近隣エリア内での異動が中心です。
転勤による生活環境の変化を避けたい方にとって、一般職は魅力的な選択肢となっています。
転勤に対して、ネガティブな印象を抱いている方は、転勤制度のない企業を探してみましょう。
例えば、以下の記事では東京にある転勤なしのメーカーを紹介しています。
転勤の有無は、将来を考えるうえで重要な要素です。ぜひ確認しましょう。
昇進(キャリアアップ)
総合職と一般職では、昇進スピードとキャリアの伸び方に大きな違いがあります。
総合職は高度で責任を伴う業務を多く担当するため、実績に応じた昇進機会が豊富にあります。
成果重視の企業文化では、入社から数年で管理職に昇進するケースも珍しくありません。
企業説明会では、昇進モデルについて具体的な質問をして理解を深めておくことをおすすめします。
一方で一般職の場合、昇進機会は限定的で、役職への登用は一般的ではありません。
安定した生活基盤を重視し、昇進にこだわらない働き方を望む方には、一般職が適している可能性があります。
ただし、一般職は給与水準や社内での職位が長期的に変化しにくい特徴があることを認識しておく必要があります。
キャリアアップについてもっと詳しく知りたい方におすすめの記事を公開しています。
キャリアプランの立て方や一般職からキャリアアップを目指す方法まで解説しています。
この機会にぜひ参考にしましょう。
総合職と一般職の大きな違いまとめ
総合職と一般職を比較した際の違いをまとめてみました。
| 職種 | 業務内容・範囲 | 給料・年収 | 異動・転勤 | 昇進 |
| 総合職 | 幅広い | 高い | 全国転勤あり | 早い |
| 一般職 | 限定的 | 低い | 限定的 | 遅い |
このように総合職と一般職では仕事の性質が異なるので、将来の人生設計をしっかり考え、就活の軸を持つことが重要です。
4 5


総合職と一般職、どちらで就職すべきか4つの判断基準
ここまで「総合職」「一般職」双方の違いを比較しながら解説してきました。
それを踏まえたうえで、ここでは総合職と一般職どちらで就職すべきかの判断基準を示します。
判断基準となるのは以下の4つです。
- 理想のキャリアプラン(どのように働きたいか)
- 理想のライフプラン
- 自分の得意・苦手なことは何か?
- やりたい仕事かどうか
理想のキャリアプラン(どのように働きたいか)
将来のキャリアを考える際は、30代や40代の自分の働き方を具体的に思い描くことが大切です。
人は現状に満足できなくなる傾向があるため、就職時の職種選択は入念な検討が必要になります。
総合職と一般職の選択に迷う就活生は、自分自身の価値観や人生の方向性について、改めて深く見つめ直すことが有効です。
職種を決める前に、自分が大切にしたい価値観や目標を整理することをおすすめします。
効果的な自己分析の進め方については、関連記事でも詳しく解説していますので、ぜひ参考にしてください。
理想のライフプラン
就職活動では、将来の生活設計を具体的にイメージすることが大切です。
実現したい目標だけでなく、譲れない生活条件を明確にしておく必要があります。
将来の転勤や異動が家族の生活に与える影響について、事前に検討しておくことも重要です。
以下のポイントを考えておきましょう。
- 住宅購入の計画と時期
- 実家の承継に関する家族の意向
- 子どもの教育環境
- 単身赴任の可能性と家族の受け入れ
- 親族の介護への対応方法
総合職の場合、全国規模の転勤が発生するため、希望の勤務地で継続的に働くことは困難です。
転勤によって家族の生活基盤が大きく変化する可能性を考慮する必要があります。
職種の選択は家族の将来に関わる重要な決定になるため、家族全員で十分な話し合いを持ち、共通の理解を得ることがおすすめです。
自分の得意・苦手なことは何か?
自分の「得意」「不得意」を判断基準として、職種を判断するのもひとつの方法です。
「総合職に向いている人」と「一般職に向いている人」の特徴をそれぞれまとめたのでご覧ください。
以下の特徴に当てはまる人は、総合職に向いています。
- 会社の中核的な役割を担い、幅広い業務に携わりたい
- 責任が重くても、やりがいのある仕事がしたい
- 私生活が多少犠牲になったとしても、やりがいや収入の多さを重視したい
- とにかくたくさん収入がほしい
- 仕事で成果を上げてどんどん出世していきたい
- 同じような仕事を続けていくのは苦手だ
- 環境が大きく変わったとき、すぐに順応するのが得意だ
- 全国転勤が苦ではなく、むしろ新しい環境を楽しめる
一方で、以下の特徴に当てはまる人は、一般職に向いています。
- 組織の中心となる人をサポートするような仕事がしたい
- 限定的な範囲の仕事を突き詰めていきたい
- 仕事と私生活のバランスを崩したくない
- 収入よりもプライベートな時間がたくさんほしい
- 転勤で私生活が犠牲になるのは避けたい
- 昇進して責任が重くなるのは避けたい
- 正確さが求められる事務仕事が得意だ
- リーダーシップを発揮するのが得意ではない
- 環境が大きく変わったとき、すぐに順応するのが苦手だ
自己分析の結果を参考に、どの項目に当てはまるかチェックしてみてください。
やりたい仕事かどうか
キャリア選択において、希望する仕事内容との適性は重要な判断材料になります。
自分の興味や適性に合った仕事に就くことで、充実した職業人生を実現できるでしょう。
総合職は将来の経営幹部育成を目的としており、多様な職務経験を通じて自分に合った業務分野を発見できる可能性が高いといえます。
一般職は特定の職務で専門的なスキルを磨くことが求められ、担当業務は限定的になります。
一般職を検討している場合、自己分析と企業研究に十分な時間を使い、明確な志望動機を持つことが重要です。
総合職と一般職に関するよくある質問
総合職と一般職に関するよくある質問をまとめました。
どちらを選ぶか決める前に、内容をしっかり把握しておきましょう。
Q1.総合職を目指すにあたって気をつけるべきことは何?
総合職での就職活動では、志望企業における総合職の具体的な職務内容を理解することが大切です。
面接では、総合職を選んだ理由を明確に伝える必要があります。
そのため、志望企業の総合職の仕事内容を事前に把握し、説得力のある志望動機を準備しましょう。
Q2.一般職を目指すにあたって気をつけるべきことは何?
就職活動で一般職を志望する場合、志望企業における一般職の具体的な業務内容を把握することが重要です。
採用面接では、一般職を選択した理由について明確な説明を求められることが多いでしょう。
一般職の業務が単純そうという印象だけで判断するのは避けるべきです。
自分のキャリアプランや価値観に合った選択をするために、先述の「総合職と一般職の4つの選択基準」をもとに、慎重に検討しましょう。
Q3.就職後に総合職と一般職の職種転換はできるの?
企業の人事制度によって、総合職と一般職の職種転換は可能になっています。
従業員のワークライフバランス重視の傾向を受けて、職種転換制度を導入する企業は年々増加しています。
職種選択に悩む就活生は、職種転換制度が整備された企業選びがおすすめです。
総合職から一般職への転換制度は多くの企業で実績がありますが、一般職から総合職への転換には高い業績と社内試験合格など、厳しい条件が設定されている場合もあります。
一般職から総合職への職種転換は特にハードルが高いことを理解しておきましょう。
Q4.女性にとって総合職はきついって聞いたけど本当?
かつての日本社会では、育児は女性が担うものという固定観念が強く、育児休業の取得が昇進の障壁となり、女性が総合職として活躍することは困難でした。
しかし、現代の企業は育児に対する考え方が大きく変化し、女性総合職が働きやすい職場環境の整備に力を入れています。
企業の採用活動においても、女性総合職の採用数を積極的に増やす傾向が見られます。
例えば、総合商社の丸紅株式会社では、女性総合職の採用比率を2024年までに40〜50%まで引き上げる目標を掲げているのも特徴です。
社会全体で女性の就業環境は着実に改善されており、今後もこの動きは加速するでしょう。
結婚後の生活設計については、夫婦それぞれのキャリアプランを綿密に話し合い、将来の方向性を一致させることが大切です。
おわりに
ここまで総合職と一般職の違いや選択基準について詳しく解説してきました。
就活生にとって、どちらを選ぶかは簡単な判断ではありません。
この記事を読んだ皆さんは、将来のキャリアやライフプランを真剣に考えていることでしょう。
キャリアについて深く考えることは、とても価値のある行動といえます。
就職活動における総合職と一般職の選択は、将来の人生設計に大きな影響を与えます。
自分の目指すキャリアを見据えて、慎重に検討することがおすすめです。
判断に迷った時は、先ほどご紹介した「総合職と一般職の4つの選択基準」が参考になるはずです。
この情報が、就活における道しるべになることを願っています。
さらに総合職と一般職について知りたい方に以下の記事をおすすめします。
職種選択の時点で迷っている方にとって参考になる情報が満載なので、参考にしてください。