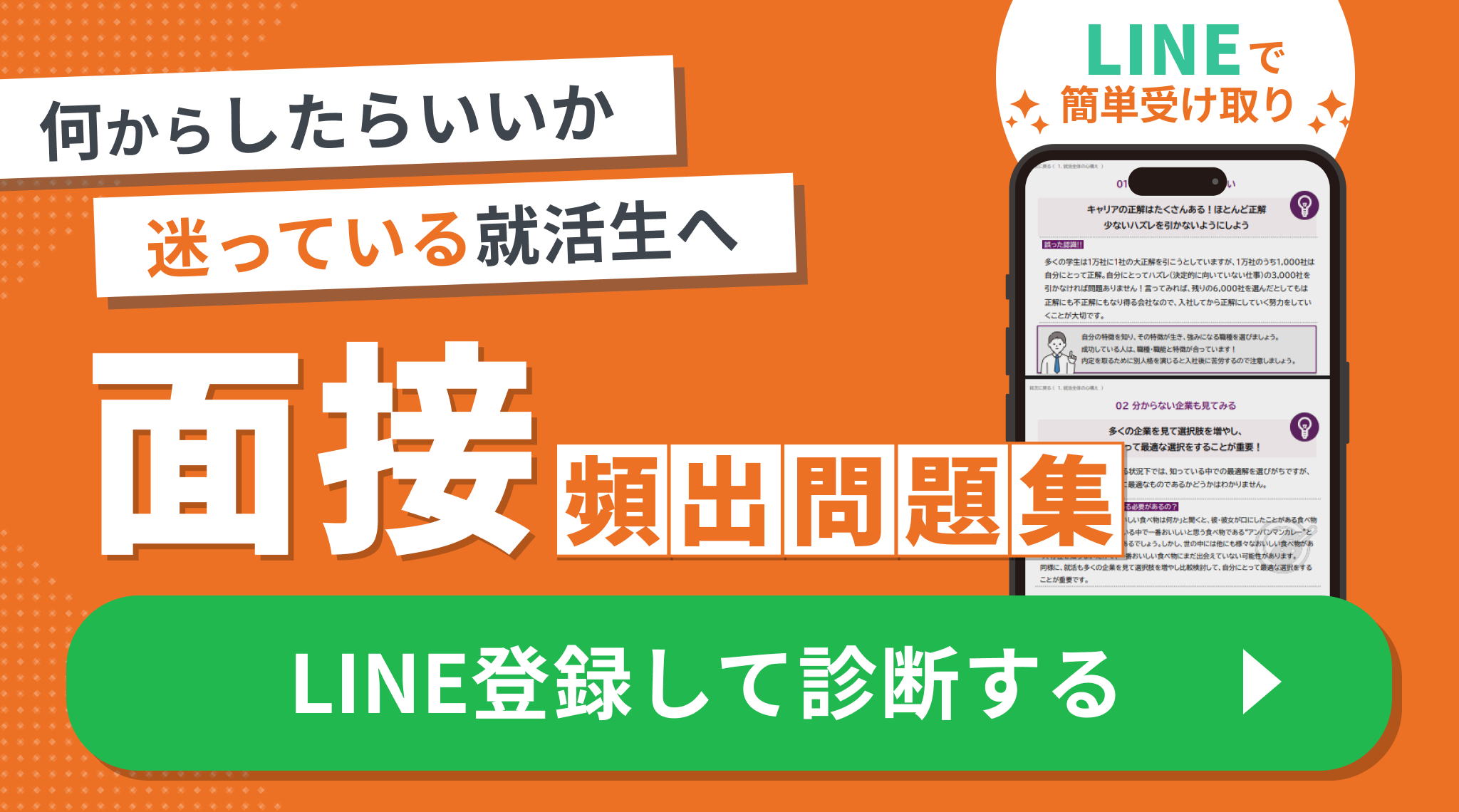薬剤師の将来性は?AI時代でも安定?就活生が知るべき業界のリアル
2025/12/23更新
はじめに
薬学生として就活を迎えるあなたにとって、最大の不安のひとつが「薬剤師として将来性があるのか」という問いでしょう。AIや自動化技術が進歩する中、「将来、薬剤師の仕事は奪われるのではないか」と心配する声もあります。
しかし実際には、薬剤師の役割は「調剤」から「患者支援」「地域医療」「医療チームとの連携」へと拡張しています。変化を正しく理解し、どの職場で、どのスキルを武器にするべきかを知ることが、就活での差別化につながります。
本記事では、厚生労働省の需給推計や最新求人データ、AI導入事例などをもとに、就活生視点で「薬剤師の将来性」「職場選び」「差別化戦略」を体系的に解説します。
読み終える頃には、「自分にとって最適なキャリア方向」と「今からできる準備」が明確になるはずです。
- 職場選びやキャリア戦略を知りたい人
- 将来の働き方やスキルの差別化、資格取得の必要性を検討している人
- AI時代・自動化時代に備えて、自分の市場価値や専門性を高めたい人
薬剤師の将来性は「安定」だけでは語れない
薬剤師という職業は長らく「安定した職業」として知られてきました。しかし、AIやDX(デジタルトランスフォーメーション)の進展により、調剤中心の業務は大きく変わろうとしています。また、少子高齢化や人口減少による将来の薬剤師需要についても、単純に「薬剤師余り」と考えることはできません。本章では、最新の技術動向や人口統計をもとに、就活生として押さえておきたい薬剤師の現実と将来像を整理します。
AI・DXで「調剤中心」の仕事が変化
従来、薬剤師の主な業務は処方薬の調剤と薬歴管理でした。しかし近年、調剤ロボット、自動分包機、処方監査支援システムなどの導入で、定型作業の効率化が進んでいます。これにより、薬剤師が行っていた手作業部分は自動化されつつあります。
一方で、AIには苦手な領域―個々の患者の生活背景や併存疾患を踏まえた判断、複雑処方の最適化―は人間の薬剤師が担う必要があります。実際に一部の医療機関では、薬剤師が医師と協働して処方提案を行う体制が整備され始めています。
このように、薬剤師の職務は「調剤」から「判断支援+対人支援」へとシフトしており、単なる「薬を渡す」役割から、医療チームの一員としての価値が求められる時代になっています。
人口減少で「薬剤師余り」は本当か?
「薬剤師が余る」「就職先がない」といった話はよく聞きますが、これは一部地域・一部職域の話であり、業界全体を代表するものではありません。
厚生労働省の需給推計では、2035年頃に薬剤師過剰の可能性が示唆されていますが、前提には人口動態、処方箋数、卒業薬学生数、離職率などの変動が影響します。都市部では薬局過剰感がありますが、地方・過疎地・在宅医療分野・病院薬剤師には依然として人材不足が存在します。
特に高齢化が進む地方では、在宅医療や介護分野の薬剤師需要が増加する見込みです。薬剤師の将来性は「地域差」と「職域差」によって大きく左右されます。
薬剤師のキャリアパスと将来の選択肢
薬剤師としてのキャリアは、病院や薬局での臨床業務だけに限りません。就職活動を控えたあなたにとって、どの勤務先を選ぶかは将来の働き方やスキルの伸ばし方に直結します。本章では、まず一般的な就職先の特徴を押さえつつ、医療現場以外で活躍できる職種や業界も紹介します。幅広い選択肢を理解することで、自分に合ったキャリアを描くヒントになります。
就活先として一般的な勤務先
薬学生が就職先として検討する主な職場には、調剤薬局・病院・ドラッグストアがあります。それぞれの特徴と将来性をまとめました。
| 勤務先 | 主な仕事内容 | 強み | 将来性の注意点 |
| 調剤薬局 | 処方箋調剤、服薬指導、在宅対応 | 地域に根ざした実務経験、患者と近い立場 | 自動化ツール導入、チェーン間競争 |
| 病院 | 医師との処方連携、入院患者の薬歴管理 | 臨床知識・チーム医療力強化 | 夜勤・専門領域への適合力 |
| ドラッグストア | OTC販売、健康相談 | 接客力・薬以外の相談力 | 自動化・チェーン展開による価格競争 |
| 製薬企業 / 研究 | 新薬開発、臨床試験、品質保証 | 研究好きに適性 | 薬学以外の知識(統計・解析)が必要 |
| 在宅 / 訪問 | 訪問調剤、服薬フォロー | 高齢化社会に対応する専門性 | ICT対応力・医療機関との連携 |
就活時点で「どの薬剤師像を描くか」を意識することが、後の差別化につながります。
医療現場以外の選択肢
薬剤師は、必ずしも調剤薬局や病院だけではありません。製薬企業・CRO・行政・ヘルステック分野も選択肢です。
- 製薬企業
- CRO/SMO
- 行政/保健所
- ヘルスケアベンチャー
製薬企業
製薬業界の主な担当者には、MR、研究開発、薬事申請、品質管理・保証、安全管理(PV)、管理薬剤師などがあります。これらの職種では、新薬開発、承認申請、市販後調査、規制対応などに携わります。薬学・医学の知識だけでなく、ビジネスや経営の知識も活かすことができ、キャリアの幅が広いのが特徴です。初任給は400万円台からで、上は800万円以上になる場合もあり、福利厚生も充実しています。MRは営業色が強い職種ですが、研究職や薬事職の需要も高まっています。
CRO/SMO
CROやSMOでは、CRA(臨床開発モニター)やCRC(治験コーディネーター)が中心です。新薬の臨床試験や治験支援に携わり、薬剤師の知識や臨床経験が活かせます。CRAは病院勤務経験者が歓迎され、キャリアアップやグローバルな活躍の機会もあります。在宅勤務や全国出張も多く、調剤業務からは離れます。報酬は800万円超を目指せる場合もあり、キャリア支援も手厚いです。
行政/保健所
地方公務員(行政薬剤師)は、保健所薬務課などで医薬品・医療機器・化粧品・健康食品の許可・監視・指導や、薬物乱用防止・献血啓発などの公衆衛生業務を担当します。配属は公務員試験合格後の辞令次第で決まります。地域貢献のやりがいがあり、安定した給与(年収約350〜400万円〜経験で上昇)が魅力です。
ヘルスケアベンチャー
医療・ヘルスケア系ベンチャーでは、薬剤師の専門知識を活かして、製品開発・学術企画・営業・カスタマーサポートなど、多様な分野で活躍できます。革新的な事業に関われる裁量の大きさや成長スピードが魅力であり、専門性や関心領域を明確にしたうえで、求人情報を丁寧に確認することが就活成功のポイントです。
\薬剤師を目指すなら「面接力」も未来を左右する!/
「薬剤師は将来性がないって本当?」「就職先の選択肢が減るのでは…」
そんな不安を感じている就活生にこそ、面接での印象が重要になります。
薬剤師の業界も変化の時代。AIや制度改革に左右されない人材として、自己PRや志望動機で“強み”を明確に伝えることがカギです。
そこで、100種類の面接質問と回答例を収録した《面接頻出質問集》を無料でご用意しました。
移動時間にスマホでチェックできるから、対策もラクに続けられます。
将来性に不安を感じる今こそ、“伝え方”で差をつけましょう!
すでに60,000人以上が利用中!
会員登録して「面接回答集」を見てみる(無料)
AI・自動化時代にどう変わる薬剤師業務
AIや自動化技術の進化により、薬剤師の業務は今まさに大きな転換期を迎えています。調剤や在庫管理などの定型作業はシステム化が進む一方で、臨床判断や患者対応といった“人にしかできない業務”の重要性が高まっています。
ここでは、AIに代替されやすい業務と残る業務を整理し、今後の薬剤師に求められるスキルと成長の方向性を就活生の視点から解説します。
代替されやすい業務 vs 残る業務
| 代替されやすい | 在庫管理、仕分け、分包、簡易モニタリング |
| 残る業務 | 服薬指導、複数薬併用の判断、患者フォロー、医療チーム連携 |
AIや自動化の進展により、薬剤師の業務内容も徐々に変化しています。まず、代替されやすい業務として挙げられるのは、在庫管理や薬剤の仕分け、分包作業、簡易的なモニタリングなどのルーチン業務です。これらはAIやロボットによる自動化が進んでおり、作業効率化やヒューマンエラーの軽減に大きく貢献します。
一方で、服薬指導や複数薬の併用判断、患者へのフォロー、医療チームとの連携といった業務は、AIによって完全に代替されることは難しい領域です。特に患者の生活背景や体調変化、他職種とのコミュニケーションに基づく判断は、人間ならではの柔軟性と臨床判断力が求められます。
つまり、AIはあくまで補助ツールとして活用されるものであり、薬剤師自身が専門知識や対人スキルを磨くことで、他者と差をつけられる余地があります。就活生の視点では、「機械に代替されない業務領域での強み」を意識してキャリアプランを考えることが、将来性の高い薬剤師像につながります。
求められるスキル
- デジタルスキル・ITリテラシー
- コミュニケーション力・共感力
- 臨床判断・分析力
- マネジメント・連携推進力
- 継続学習力
デジタルスキル・ITリテラシー
電子薬歴、AIによる処方監査システム、オンライン服薬指導など、新しい医療DXツールを使いこなすITスキルは必須です。また、電子処方箋や患者データの活用など、データ分析力も求められます。
コミュニケーション力・共感力
AIには代替できない「患者ごとの状態・心情をくみ取る共感力」「多様な価値観への傾聴力」など、きめ細かい対人対応が必要です。医療チームとの連携や多文化対応の力も求められます。
臨床判断・分析力
AIが警告を発する薬の相互作用や処方の意図について、自ら判断し、医学的に評価できる専門知識と論理的思考力が重要です。
マネジメント・連携推進力
チーム医療における情報共有や役割調整をリードできるマネジメントスキルも評価されます。
継続学習力
医療技術やAI関連法令、薬剤情報の変化を自ら捉え、学び続ける姿勢が求められます。
差別化の鍵となる資格・経験
薬剤師として就職・キャリアをスタートさせる際、資格や経験の有無は採用担当者の評価を大きく左右します。特に近年は、AI・在宅医療・地域連携など多様な領域で活躍できる人材が求められており、学生のうちにどの分野のスキルを磨くかが重要な差別化ポイントになります。
ここでは、就活段階で有利になる資格・経験、そして資格取得を「費用対効果」の観点からどう考えるべきかを解説します。
就活生に有利な資格・経験
薬剤師を目指す就活生が他と差をつけるためには、「薬剤師国家資格+α」の強みをどう構築するかが鍵になります。就活市場では、同じ薬学生でも「現場で使えるスキル」や「専門性の方向性」が明確な人ほど評価されやすい傾向があります。ここでは、就活で特に有利になりやすい資格・経験を紹介します。
- 登録販売者
- 甲種危険物取扱者
- 放射線取扱主任者
- 食品衛生管理者・監視員/毒物劇物取扱責任者
- 日本化粧品検定
- NR・サプリメントアドバイザー
- 認定薬剤師・専門薬剤師(卒後)
登録販売者
薬剤師資格取得前でも、第2類・第3類医薬品を扱える国家資格で、ドラッグストアや調剤以外の現場経験を積めます。面接時に「販売現場での接客・在庫管理を経験した」と話せるのは強力なアピール材料です。
甲種危険物取扱者
医薬品・化学系企業では安全管理・リスク評価の知識が重視されるため、化学の理解や安全意識を示せる資格として有効です。製薬・研究職志望者におすすめです。
放射線取扱主任者
創薬やバイオ系分野に進みたい学生に人気。研究施設や製薬企業などでの実験・品質管理業務で評価されやすく、専門性の証明になります。
食品衛生管理者・監視員/毒物劇物取扱責任者
食品会社や行政職、公衆衛生系分野を志す人に有利。安全性・衛生管理の基礎知識を持っていることを示せます。
日本化粧品検定
美容・化粧品メーカー志望の学生に人気。薬学的視点で化粧品の成分や効能を説明できる点が評価されます。
NR・サプリメントアドバイザー
健康食品・サプリメント領域の企業志望者におすすめ。近年はドラッグストアでも栄養指導の知識を持つ薬剤師の需要が増えています。
認定薬剤師・専門薬剤師(卒業後)
学生のうちから資格取得を意識し、卒業後に継続的な研修を重ねて取得を目指す姿勢は、成長意欲の高さをアピールできます。
- 学会発表・論文投稿
- 長期インターンシップ・実務実習
- 学外活動・ボランティア
- IT・語学スキル(英語・データ分析)
学会発表・論文投稿
製薬企業や研究職では特に評価が高く、学会でのポスター発表や論文投稿経験は「データを読み解き、科学的に伝える力」の証拠になります。
長期インターンシップ・実務実習
CRO・調剤薬局・企業実習などでの経験は、業務理解と実務能力を示せる貴重な機会です。「どんな現場で何を学んだか」を具体的に説明できるよう整理しておきましょう。
学外活動・ボランティア
ボランティアや地域活動は「対人スキル」「社会性」を評価される要素。地域医療や健康啓発イベントの参加も、面接で話せる印象的なエピソードになります。
IT・語学スキル(英語・データ分析)
デジタルヘルスやAI導入が進む現場では、ExcelやSPSSなどのデータ解析スキル、英語論文を読める語学力も高評価。グローバル展開する製薬企業では必須に近いスキルです。
これらの資格・経験を、自分の志望分野(臨床・企業・行政・ベンチャーなど)と連動させることが重要です。たとえば「在宅医療×認定薬剤師」「研究職×英語力」「ドラッグストア×登録販売者+栄養知識」など、専門性を掛け合わせて“自分ならではの強み”を打ち出すと、採用担当者の印象に強く残ります。
就活は「資格の多さ」よりも、「その資格をどう活かしたいか」が問われます。目的意識を持ち、実務・研究・社会活動の経験と結びつけて伝えることで、他の薬学生との差別化が実現します。
資格取得の費用対効果
資格はキャリア形成における大きな武器になりますが、取得には費用と時間がかかるため、目的を明確にして選ぶことが重要です。たとえば、認定薬剤師などの臨床系資格は実務への反映度が高く、現場での信頼獲得に直結します。一方、MBAや医療経営関連の資格は費用が高めですが、将来的にマネジメントや企画職を目指す場合に有効です。
資格は「現職への即効性」と「将来のキャリア拡張性」の両面から投資対効果を見極めることが、賢い選択につながります。
勤務地選び|都市 vs 地方
薬剤師としての働き方を左右する大きな要素のひとつが「勤務地」です。
都市部と地方では、求人状況・待遇・働き方・生活環境が大きく異なります。
自分のキャリアビジョンやライフスタイルに合わせて、どちらを選ぶかを慎重に見極めることが大切です。
地域の求人傾向
都市部では薬学部の卒業生や転職希望者が集中するため、薬剤師が「供給過剰」になりやすい傾向があります。
一方で地方では慢性的な人手不足が続いており、高年収・住宅補助・引越し支援などの好条件求人が見られます。
ただし、勤務地によっては公共交通の便が限られる場合もあるため、通勤手段や住環境を含めて検討することが重要です。
地方就職の判断基準
地方勤務を検討する際は、単に年収だけでなく、次のような複合的な観点から判断するのがポイントです。
年収差 vs 生活費
地方は年収が高めでも、生活費が低いため可処分所得が増えるケースがあります。
一方、都市部は支出が多くても、研修や転職の機会が豊富というメリットがあります。
通勤・住環境
都市部ではアクセスの良さが魅力ですが、混雑や家賃の高さが課題。
地方は車通勤が主流で、自然環境が豊か・住居が広いなど、生活の質を重視する人に向いています。
家族構成やライフスタイル
結婚・子育てを視野に入れる場合、教育環境や医療機関の充実度も判断材料になります。
単身者でキャリア優先なら都市部、安定重視なら地方勤務を選ぶ人が多い傾向です。
将来のキャリアの広がり
地方では一人薬剤師や管理薬剤師として裁量の大きい仕事を任される機会もあります。
その経験は、将来的なキャリアチェンジや独立の土台になることもあります。
\“選ばれる薬剤師”になるために、面接対策から始めよう!/
薬剤師の未来が不安視される今、求められるのは「専門性」と「対話力」です。
地域医療への貢献、セルフメディケーションの支援、多様な患者との対応など――。
変化する医療現場では、自分の強みを言語化し、面接で明確に伝える力が欠かせません。
そこで、100種類の質問と回答例をまとめた《面接頻出質問集》を無料でご用意しました。
スマホで手軽に確認できるから、スキマ時間でも効率よく準備できます。
未来を切り開く第一歩は、あなたの言葉で“価値”を伝えることです。
すでに60,000人以上が利用中!
会員登録して「面接回答集」を見てみる(無料)
就活実践編|応募・面接で役立つノウハウ
薬剤師の就職・転職活動では、医療機関や企業が求める人物像を正確に把握し、自分の強みを数値や実績で伝えることが重要です。
求人票の読み取り方から履歴書・面接でのアピール方法まで、採用担当者に響くポイントを整理しておきましょう。
求人票・募集要項の見方
求人票は「勤務条件」だけでなく、その職場がどんな薬剤師を求めているかを読み取る資料です。
以下の3点を重点的に確認することで、自分に合う職場かどうかを見極めやすくなります。
- 処方数・在宅件数・調剤量
- 研修制度・キャリアパス
- ICT導入・AI支援ツール
処方数・在宅件数・調剤量
処方箋の枚数や在宅件数は、業務の忙しさや患者層を判断する指標になります。
在宅件数が多い場合はコミュニケーション力が重視され、調剤中心の職場では正確性・スピードが求められます。
研修制度・キャリアパス
新卒・未経験者の場合は、研修内容や教育期間の有無を必ず確認しましょう。
中途採用では「管理薬剤師・エリアマネージャー」などへの昇進ルートやキャリア支援制度があるかも重要なチェックポイントです。
ICT導入・AI支援ツール
電子薬歴やAI監査ツールを導入している職場は、業務効率化や安全性を重視している傾向があります。
これらのツールに慣れておくと、将来のキャリアで大きなアドバンテージになります。
履歴書・面接で強みを示す方法
履歴書や面接では、「何ができるか」ではなく「何をしてきたか」を具体的に伝えることが評価につながります。
以下の4つの視点を意識すると、あなたの強みを効果的にアピールできます。
- 数字で成果を示す
- ツール経験を具体的に記載
- チーム活動やゼミ発表を成果ベースで記述
- 志望動機と経験の関連性を明確にする
数字で成果を示す
たとえば「在宅訪問〇件/月」「処方箋枚数〇枚/日」「新人教育〇名担当」など、実績を定量的に示すと説得力が増します。
ツール経験を具体的に記載
「電子処方システム」「Excelによる在庫管理」など、使用経験を明記することで即戦力としての印象を与えられます。
特にICT導入が進む調剤薬局や企業では、こうしたスキルが高く評価されます。
チーム活動やゼミ発表を成果ベースで記述
学生の場合、ゼミや研究活動を「どんな課題に取り組み、どんな成果を得たか」という構成で記述しましょう。
「課題発見→行動→結果」の流れが明確だと、思考力・行動力が伝わります。
志望動機と経験の関連性を明確にする
「なぜその職場を選んだのか」を、自分の経験や学びと関連づけて説明することが重要です。
たとえば「在宅医療に関心があり、実習で高齢患者と関わる中でチーム医療の重要性を実感したため」など、具体的に述べましょう。
30/90/365日アクションプラン
薬剤師として納得のいく就職・キャリアを実現するためには、早めの情報収集と計画的な行動が欠かせません。
ここでは、就活準備を「30日」「90日」「365日」の3つの期間に分けて、具体的なステップを整理します。
短期・中期・長期のバランスを取りながら、自分の方向性を固めていきましょう。
30日でやること
最初の30日間は、情報収集と方向性の明確化に集中します。
いきなり応募するのではなく、「どんな薬剤師になりたいか」「どんな職場で働きたいか」を整理する準備期間です。
実習・インターン先リスト作成
学内実習や企業・薬局インターンの情報を整理し、自分の興味分野に沿って優先順位をつけましょう。
複数企業のインターンを比較することで、業界全体の特徴もつかめます。
志望地域の求人傾向調査
都市・地方で求人の傾向や待遇に差があるため、希望勤務地の求人倍率や給与相場をチェック。
将来的な生活環境(通勤時間、家賃、交通費)も含めて検討します。
薬局・病院のICT導入状況リサーチ
電子薬歴やAI監査ツールなど、IT化の進んだ職場は今後の主流です。
求人票や企業サイトを確認し、最新技術への対応度を把握しておくと差がつきます。
90日でやること
次の90日間は、現場体験とスキル強化に重点を置く期間です。 実際に行動し、現場を見ることで「自分に合う働き方」が見えてきます。
見学・在宅同行申し込み
薬局や病院の現場見学、在宅訪問の同行などを積極的に申し込みましょう。
現場のリアルな雰囲気や業務フローを体感することで、面接で話せる具体的なエピソードも得られます。
OTC相談や薬局補助アルバイト体験
OTC販売や受付業務などのアルバイト経験は、接客力・実践力のアピールになります。
実務に触れることで、自分が興味を持てる分野や得意分野も明確になります。
電子処方システム基礎学習
Excelや電子処方、薬歴管理ソフトなど、基本的なツール操作を学習しておくと、即戦力として評価されやすくなります。
無料のオンライン講座や動画教材も活用してスキルアップを図りましょう。
365日でやること
1年のスパンでは、資格・キャリアの方向性を固め、実践に結びつける段階です。
短期的な就活対策だけでなく、今後のキャリア基盤を作ることを意識しましょう。
認定資格の勉強開始
「NR・サプリメントアドバイザー」「登録販売者」など、薬剤師+αの資格を計画的に取得していきましょう。
時間をかけて学ぶことで、就活時には“努力を継続できる人”として評価されます。
都市・地方求人比較、志望地決定
半年〜1年をかけて求人動向を追い、給与・待遇・キャリア支援制度を比較検討。
家族やライフプランも含め、長く働ける勤務地を選びます。
自己分析で志望薬剤師像を固める
インターン・実習・アルバイト経験を振り返り、「自分はどんな薬剤師として働きたいか」を明文化しましょう。
自己分析を通じて、志望動機や面接回答にも一貫性を持たせることができます。
よくある不安・FAQ
薬剤師の仕事はなくなる?
薬剤師の仕事が完全になくなる可能性はほとんどありません。ただし、調剤や在庫管理など一部業務はAIや自動化で効率化される可能性があります。重要なのは、服薬指導や患者対応など、人にしかできない領域でスキルを発揮できることです。
学生のうちに資格を取る意味は?
学生のうちに資格を取得することは、就活時の差別化につながります。資格は単なる証明だけでなく、スキルの習得度や学習意欲のアピールにもなります。費用や時間をかける場合は、将来の年収やキャリアへの影響も考慮しましょう。
地方就職して将来困らない?
地方では都市部より高待遇の求人が見つかることもあります。しかし、研修制度や転職の柔軟性を事前に確認しておくことが大切です。地域での勤務経験を活かしつつ、将来のキャリアプランも考慮することが必要です。
まとめ
薬剤師の将来は「安定」だけでは語れません。医療のデジタル化やAIの進化が進む中で、薬剤師の仕事も大きく変化しています。しかしその変化の中には、新しい活躍のチャンスも多くあります。
就職活動では、自分がどんな環境で成長したいのかを見据え、職場の選び方やスキルの磨き方を意識することが大切です。AIはあくまで補助ツールであり、人に寄り添う姿勢や判断力、コミュニケーション力など「人にしかできない領域」で差をつけられます。
また、資格取得や経験の積み方も“費用対効果”を意識しながら、自分のキャリアを投資として考えていく視点が重要です。すぐに大きな結果を求めず、30日・90日・365日と小さな行動を積み重ねることで、自信とスキルは確実に育ちます。
変化の時代だからこそ、自分の可能性を広げながら、未来を選び取れる薬剤師を目指していきましょう。
業界も職種も迷ったら!
30秒で適職タイプを診断
「どんな業界が合っているのか分からない」
「自分の強みって何だろう」
そんな迷いを抱えていませんか?
多くの就活生が活用している適職診断では、わずか30秒であなたの仕事タイプがわかります。
性格や価値観にマッチした職業タイプや具体的な職業がわかるため、自己分析の第一歩として非常に好評です。
就活の軸が曖昧なままだと、エントリー先選びや面接で一貫性のない回答になりがちで、選考に不利になることもあります。
迷っている今こそ最初の一歩を踏み出して、差をつけましょう!

この記事の監修者印出実生(キャリアアドバイザー チーフ)
現在は株式会社ナイモノのキャリアアドバイザーとして、ショーカツ・スタキャリなどの就活支援サービスを担当。社会人1年目で最年少MVP獲得、新卒採用プロジェクトに抜擢されるなど高い評価を得ている。自身の就活経験を活かし、業界・仕事・企業探しから逆算した年内スケジュールの組み立て方まで、二人三脚で就活生に寄り添ったサポートを心がけている。