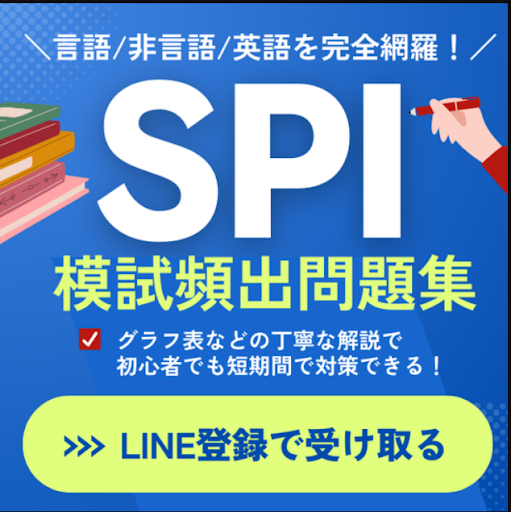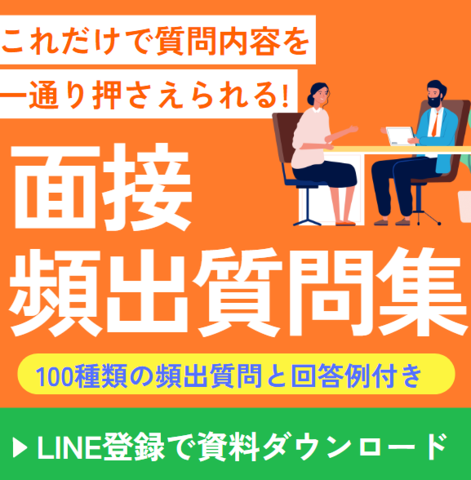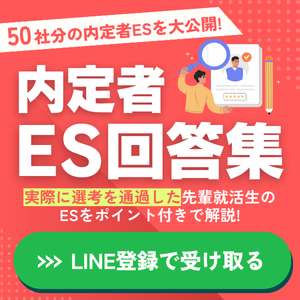10年後になくなる職業7選|安定した職業につく方法も解説
2024/10/21更新
はじめに
就職活動を進める中で「自分の選んだ職業が将来なくなってしまうのでは?」という不安を抱く就活生は多いです。
AIや自動化技術が急速に進化している現代において、この不安は現実味を帯びています。
しかし、どの職業が本当に危機にさらされているのか、将来にわたって安定している職業は何かを知ることで、キャリア選択はより明確になるでしょう。
この記事では、10年後になくなると予測される職業やその特徴、さらには新たに生まれる職業についても、詳しく解説します。
以下のようなお悩みのある学生は必見ですので、ぜひ最後までチェックしてみてください。
- 安定した職業につきたい
- 自分が目指す職業がなくなってしまうか不安
上京を志す地方学生ならジョーカツ!
あなたのキャリアを加速させるチャンス!
無料で利用できる快適な個室シェアハウス、
東京までの交通費サポート付き
首都圏の注目企業への就活ならジョーカツ
首都圏の学生ならスタキャリ!
理想のキャリアを実現へと導く第一歩!
あなたにピッタリのキャリアアドバイザーを選び、
自分にマッチする優良企業をご紹介
首都圏企業のES添削から面接対策まで、就活ならスタキャリ
10年後になくなる職業7選

技術の進化とAIの導入が進む中、将来的に消滅する可能性が高い職業について考えることは、就職活動を進める上で重要です。
以下、10年後になくなると予測される職業を7選紹介します。
- 倉庫作業・ピッキング作業
- 事務作業・データ入力
- スーパーの店員・レジ打ち
- ホテルの接客・受付の仕事
- 工場での組み立て作業
- 路線バスのドライバー
- 警備・ビルのメンテナンス
倉庫作業・ピッキング作業
倉庫でのピッキング作業は、AIやロボット技術の進化により自動化が進んでいます。
現在も、多くの企業がロボットを導入しており、効率的でミスの少ない作業が可能です。
特に、規則的な動きが求められる倉庫作業では、ロボットが人間の労働を代替することが容易です。
このため、将来的には人手がほとんど不要となることが予想されます。
就職活動においては、こうした分野の自動化技術を理解し、それに関連する新しいスキルを習得することが重要です。
事務作業・データ入力
事務作業やデータ入力の業務も、自動化の波に飲まれつつあります。
特にデータ入力は、AIが正確かつ高速に処理できるため、従来の事務員が担っていた仕事は次第に減少していくでしょう。
さらに、RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)と呼ばれる技術が広がり、定型的な作業は、ほぼすべて自動化される可能性があります。
こうした変化に対処するためには、データ解析やITスキルなど、より付加価値の高いスキルを身につけることが求められるでしょう。
スーパーの店員・レジ打ち
スーパーの店員やレジ打ちの仕事も、今後10年で大きく変わることが予想されます。
セルフレジや自動会計システムの導入が進み、消費者自身で会計を済ませる店舗が増加しているからです。
また、AIによる顔認識技術を利用したキャッシュレス決済も普及しつつあり、人手を必要としない仕組みが整いつつあります。
このような環境では、従来の店員の役割が減少することは避けられません。
就職を考える際には、接客業であっても、新しい技術に対応できる柔軟な姿勢が求められます。
ホテルの接客・受付の仕事
ホテル業界においても、受付や接客業務が自動化されつつあります。
チェックインやチェックアウトの手続きが機械化され、ロボットによる案内サービスが導入されるなど、人手を必要としないシステムが広がっています。
特にビジネスホテルでは、効率化を図るためにこうした技術が積極的に取り入れられており、従来の業務が減少しているのです。
就活生にとっては、ホスピタリティ業界であっても、ITスキルや異文化コミュニケーション能力が今後ますます重要になります。
工場での組み立て作業
工場での組み立て作業は、長年にわたり手作業による工程が重要視されてきましたが、近年の技術革新により自動化が進んでいます。
特に、AI搭載のロボットアームや、自動組み立てラインの導入が急速に進んでおり、正確で迅速な生産が可能です。
これにより、人間が担っていた細かな作業も、機械によって行われるようになり、工場労働者の役割が減少することが予想されます。
就活生としては、工場での業務に関心がある場合でも、機械の操作やメンテナンス、AIに関する知識を深めておくことが必要です。
路線バスのドライバー
路線バスのドライバーは、将来的に自動運転技術の進化によって消滅する可能性が高い職業の一つです。
現在、各国で自動運転技術の研究開発が進められており、実験的に無人の自動運転バスが導入されている地域もあります。
安全性の向上や運行コストの削減を目的として、こうした技術が普及すれば、バスの運転手としての仕事は大きく減少することが予想されます。
交通インフラに興味がある就活生は、自動運転技術やそれに関連する法規制に関する知識を深めることが将来的に役立つでしょう。
警備・ビルのメンテナンス
警備やビルのメンテナンス業務も、AIとロボット技術の進展により変化が予想される職業です。
セキュリティカメラの高度化やAIによる監視システムの導入により、人が常駐して監視する必要が減少しています。
ビルのメンテナンスにおいても、ロボットによる清掃や点検が行われるようになり、人手を介さずに効率的に業務を進めることが可能です。
このような背景から、これらの職業も将来的に消滅する可能性が高いとされています。
就職活動中の皆さんは、こうした変化に対応できるように、セキュリティやメンテナンスの技術を身につけることが大切です。
これらの職業が10年後になくなる可能性があることを考えると、将来のキャリア選びでは、技術の進化に対応できるスキルを習得することが大切です。
新しい分野にも柔軟に対応できる力をつけておきましょう。
10年後になくなる職業の特徴

10年後になくなる職業をランキングで紹介しましたが、その特徴を解説します。
単純作業が多い仕事
近年の技術革新により、AIやロボットが人間の単純作業を代替する動きが加速しています。
スーパーのレジ打ちや倉庫でのピッキング作業といった反復的な業務は、既に多くの企業で自動化が進んでいます。
これらの業務は、効率を重視する企業にとって、人件費削減と生産性向上のために真っ先に機械に置き換えられる可能性が高い分野です。
このような傾向は、今後さらに広がり、単純作業を中心とした職種は減少の一途をたどるでしょう。
デジタル処理できる業務が多い仕事
デジタル化の波は、事務作業にも大きな影響を与えています。
例えば、データ入力や書類作成といった業務は、AIによる自動処理が可能となり、少人数で効率的に対応できるようになっているのです。
特に、正確さが求められるデータ処理の分野では、AIは人間よりも高い精度を発揮するため、企業は積極的に導入を進めています。
これにより、今後10年以内に、こうした業務に携わる職種が大幅に縮小することが予想されるでしょう。
担い手が減少している仕事
日本の人口減少により、特に地方での労働力不足が深刻化しています。
地方での路線バスのドライバーやビルのメンテナンス業務など、過酷な労働環境や低賃金が特徴の職種は、若い世代から敬遠されがちです。
その結果、これらの職業は担い手が減少し、やがては職業そのものがなくなる可能性があります。
労働環境の改善が進まない職種は将来的に人手不足に拍車がかかり、消滅の危機に直面するでしょう。
10年後もなくならない職業7選
現代の急速な技術革新に伴い、AI(人工知能)やRPA(ロボットによる業務自動化)によって、多くの職業が影響を受けることが予想されています。
しかし、その中でも、将来にわたって必要とされる職業も存在します。
ここでは、10年後もなくならないと考えられる職業を、ランキング形式で紹介します。
これから就職活動を迎える学生の皆さんは、これらの職業に注目してみてください。
10年後もなくならない職業7選
- 医療・介護職
- デザイナー・クリエイター
- ITエンジニア
- コンサルタント職
- ソフトウェア開発者
- 弁護士・法律専門家
- 心理カウンセラー
医療・介護職
医療・介護分野は、テクノロジーが進化しても、人間の手によるケアが求められる職種の一つです。
特に、患者の状況を正確に判断し、適切な対応を行う能力は、AIには代替できないものです。
また、高齢化社会が進む中で、介護職の需要はますます増加することが予想されます。
医療・介護職は、単なる技術的スキルだけでなく、人間性や共感力が求められるため、長期的に安定した職業といえるでしょう。
デザイナー・クリエイター職
創造力や独創性が求められるデザイナーやクリエイター職は、AIが模倣することが難しい分野です。
デザインの分野では、人々の感情に訴えかける視覚的な表現や、個々のニーズに合わせたカスタマイズが重要とされます。
これらは、AIが自動生成するものとは一線を画し、より人間らしい発想が求められるため、将来的にも需要が続く職業と考えられます。
また、クリエイティブな分野は常に進化しており、新しいトレンドや技術に対応できる柔軟性が重要です。
ITエンジニア
ITエンジニアは、デジタル化が進む現代社会において、ますます重要な役割を果たしています。
システムの開発や保守、セキュリティ対策など、IT分野でのスキルは多岐にわたります。
特に、AIや機械学習の分野での専門知識を持つエンジニアは、今後ますます需要が高まると予想されています。
AI技術そのものの進化を支えるエンジニアリングスキルは、他の分野における自動化の波にも左右されず、長期的にキャリアを築いていけるでしょう。
エンジニアへの就職を考えている方は、以下の記事でエンジニア向けの自己PRを紹介しているので参考にしてください。
コンサルタント職
コンサルタント職は、企業の戦略立案や業務改善に関わる専門職で、経験と知識が重要な役割を果たします。
AIは今後、より多くのデータを分析し、意思決定の支援ができるようになっていくでしょう。
それでも、企業の複雑な問題を解決するための創造的なアプローチや、人間同士のコミュニケーションによる調整は、人間にしかできない仕事です。
コンサルタントは柔軟な思考と高いコミュニケーション能力が求められ、長期的に安定した職業として注目されています。
これらの職業は、技術の進化に左右されず、今後も求められ続ける分野です。
就活生の皆さんは、これらの職業を選択肢に入れ、自分に合ったキャリアを見つけてください。
ソフトウェア開発者
デジタル化が進む中で、ソフトウェアの開発者はますます重要な役割を果たすでしょう。
AIやロボットが普及するにしても、それらを支えるシステムやアプリケーションを作成する人材が必要です。
ソフトウェア開発者は、AIの進化をサポートし、さらに発展させる役割を担い続けることが期待されます。
弁護士・法律専門家
法律の解釈や適用には高度な判断力と倫理的な思考が求められます。
AIは、法律文書の分析や基本的な法的アドバイスを提供できます。
しかし、複雑な法的問題の解決や、個別のケースに応じた戦略的な助言、裁判での弁護などは難しいです。
そのため、今後も人間の弁護士や法律専門家の仕事は必要とされるでしょう。
特に、倫理や人権に関わる問題については、AIには代替できない人間の判断が不可欠です。
心理カウンセラー
メンタルヘルスの重要性が認識される中、心理カウンセラーの役割も重要になっていきます。
AIは多くのタスクを自動化できるものの、個々の感情や精神状態に寄り添い、適切な支援を提供するには人間の共感力と経験が必要です。
特に、ストレスや不安の増加が予想される未来において、心理カウンセリングの需要は今後も続くでしょう。
これらの職業は、AIやロボットが台頭しても、人間ならではのスキルや知識が求められるため、今後もなくならないと考えられます。
10年後もなくならない職業に就職するポイント

せっかく新卒で一生懸命就活をしているのであれば、10年後も安心して働ける職業に就きたいですよね。
そこで以下では、10年後もAIなどにとってかわる可能性の低い職業に就職するためのポイントを紹介します。
- 人間にしかできない仕事を見極める
- デジタルスキルを磨く
- 創造性と問題解決能力を高める
- コミュニケーション力を磨く
- 早めの対策で未来に備える
人間にしかできない仕事を見極める
上記で紹介したように、AIやロボットによる業務自動化が進んでも、依然として人間にしかできない仕事は多く存在します。
例えば、医療や介護の分野では、患者の状態を正確に把握し、臨機応変に対応することが求められるのです。
医師や看護師、薬剤師、介護士、そしてカウンセラーなどがこれに該当します。
これらの職種では人間ならではの共感力や判断力が不可欠であり、AIが完全に代替するのは難しいです。
デジタルスキルを磨く
今後ますますデジタル化が進むと予想される中、ITスキルの習得は不可欠です。
プログラミングやデータ分析などのスキルを持つことで、どの業界でも重宝される人材になることができます。
デジタル技術を活用し、新しい価値を生み出す能力が求められる時代です。
創造性と問題解決能力を高める
デザイナーやクリエイターのように、創造力を必要とする職業も、AIが簡単に取って代わることができない分野です。
アーティストや作家、そして広告や映像制作に関わる職種では、独自のアイデアを生み出し、それを具現化する能力が重視されます。
これらのスキルは、AIではなく人間だからこそ持つユニークな特性です。
コミュニケーション力を磨く
営業職やカスタマーサービスなど、顧客との直接的なコミュニケーションが求められる職種も、AIでは完全に代替できない領域です。
顧客のニーズを的確に引き出し、それに応じた提案をする力は、人間だからこそ発揮できるスキルです。
コミュニケーション能力を高めることで、将来のキャリアにおいても強力な武器となるでしょう。
早めの対策で未来に備える
これからの10年を見据えて早めの対策を取ることが重要です。
時代の変化に柔軟に対応できるように、常に学び続ける姿勢を持ち、自分のスキルセットをアップデートしていくことが求められます。
変化に対応できる力があれば、どのような環境でも自分の価値を発揮できるでしょう。
10年後に新しく生まれる職業4選
未来の職業市場は、技術の進歩や社会の変化によって大きく変わることが予想されています。
特に、AIやデジタル化の進展に伴い、新しい職業が続々と登場するでしょう。
以下、就活生に向けて、10年後に生まれる可能性が高い職業ランキングを紹介します。
仮想店舗シェルパ(案内役)
仮想現実(VR)や拡張現実(AR)の技術が進化する中で、仮想店舗シェルパは、バーチャルショッピング体験をサポートする新しい職業として注目されています。
消費者が仮想空間内で商品を選び、購入する際に、最適なアドバイスを提供する役割を担う職業です。
この職業は、オンラインとオフラインの境界を超えたショッピング体験を提供し、消費者の満足度を向上させることを目的としています。
ファッションや家具、家電製品などの分野で需要が高まると予測されます。
個人情報ブローカー
個人情報の管理と保護がますます重要視される時代に、個人情報ブローカーは、個人データの売買や管理を専門とする職業として浮上しています。
この職業は、個人のデジタルライフを守るために、適切な情報の取引を行うと同時に、データ漏洩や不正使用を防ぐ役割を果たします。
企業や個人が安心してデータを扱えるようにするための専門知識が求められ、情報セキュリティの分野で、新たなキャリアの道が開かれるでしょう。
拡張現実(AR)旅行構築者
AR技術の進展により、旅行業界も新たな形で進化を遂げることが期待されています。
拡張現実旅行構築者は、観光地や歴史的遺産をAR技術を使って再現し、観光客に新しい体験を提供する職業です。
リアルとバーチャルが融合した旅行体験をデザインすることで、観光業界に革命をもたらす存在になるでしょう。
この職業は、クリエイティブなスキルと技術的な知識を兼ね備えた人材にとって、魅力的な選択肢となること間違いありません。
個人記憶キュレーター
デジタルデータの爆発的な増加により、個人の思い出や重要なデータを整理し、保存するニーズが高まっています。
個人記憶キュレーターは、デジタル遺産を管理し、個人の記憶を未来に引き継ぐ手助けをする職業です。
特に、写真やビデオ、メッセージなどのデータを整理・保存し、家族や友人と共有するためのサポートを提供します。
この職業は、デジタルアーカイブや情報整理に興味がある人にとって、新しいキャリアのチャンスとなるでしょう。
10年後、これらの職業が実際に登場するかどうかはまだ未知数ですが、技術革新が進む中で、これらの新しい職業が現実になる可能性は十分にあります。
未来のキャリアに備え、今から新しいスキルを磨くことが、成功への鍵となるでしょう。
さいごに
この記事では、AIや自動化技術の進展に伴い、10年後に消滅する可能性が高い職業ランキングや、その特徴について詳しく解説しました。
単純作業やルーティンワークが多い職業は、これらの技術によって置き換えられるリスクが高いでしょう。
その一方で、創造性や高度な専門知識が求められる職業は、今後も存続し続ける可能性が高いです。
これらの情報をもとに、キャリアをより具体的にイメージし、未来に向けて安心して準備を進める手助けとなれば幸いです。
急速に変化する社会の中で、自分の強みを活かし、長期的に活躍できる職業を見つけ、未来に備えた準備を今から始めましょう。