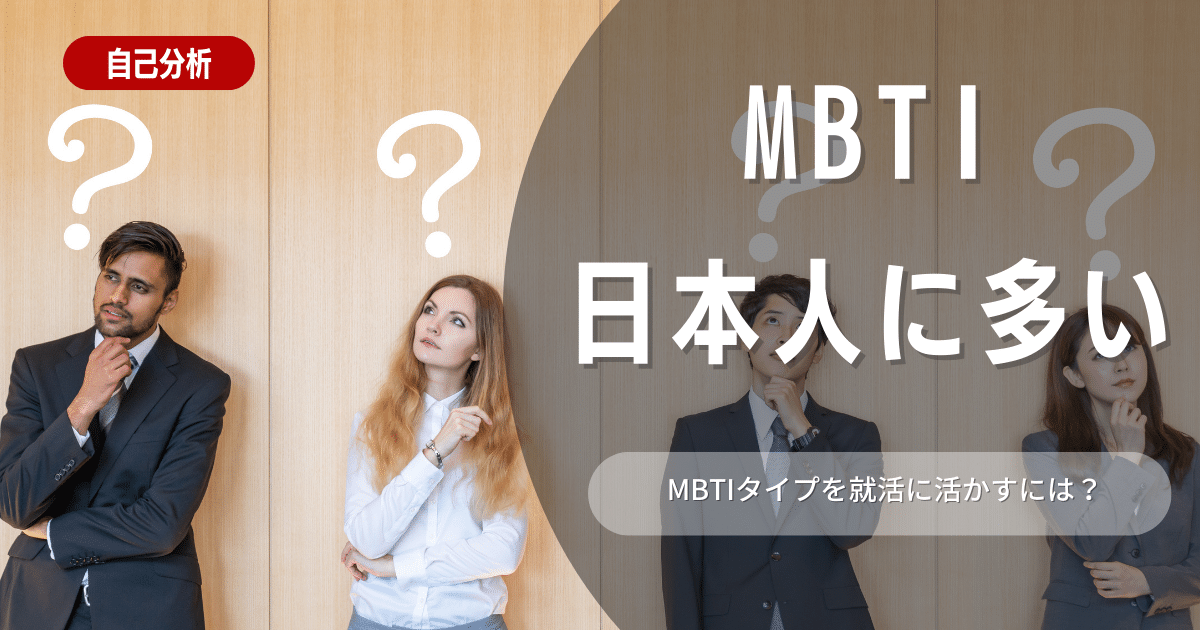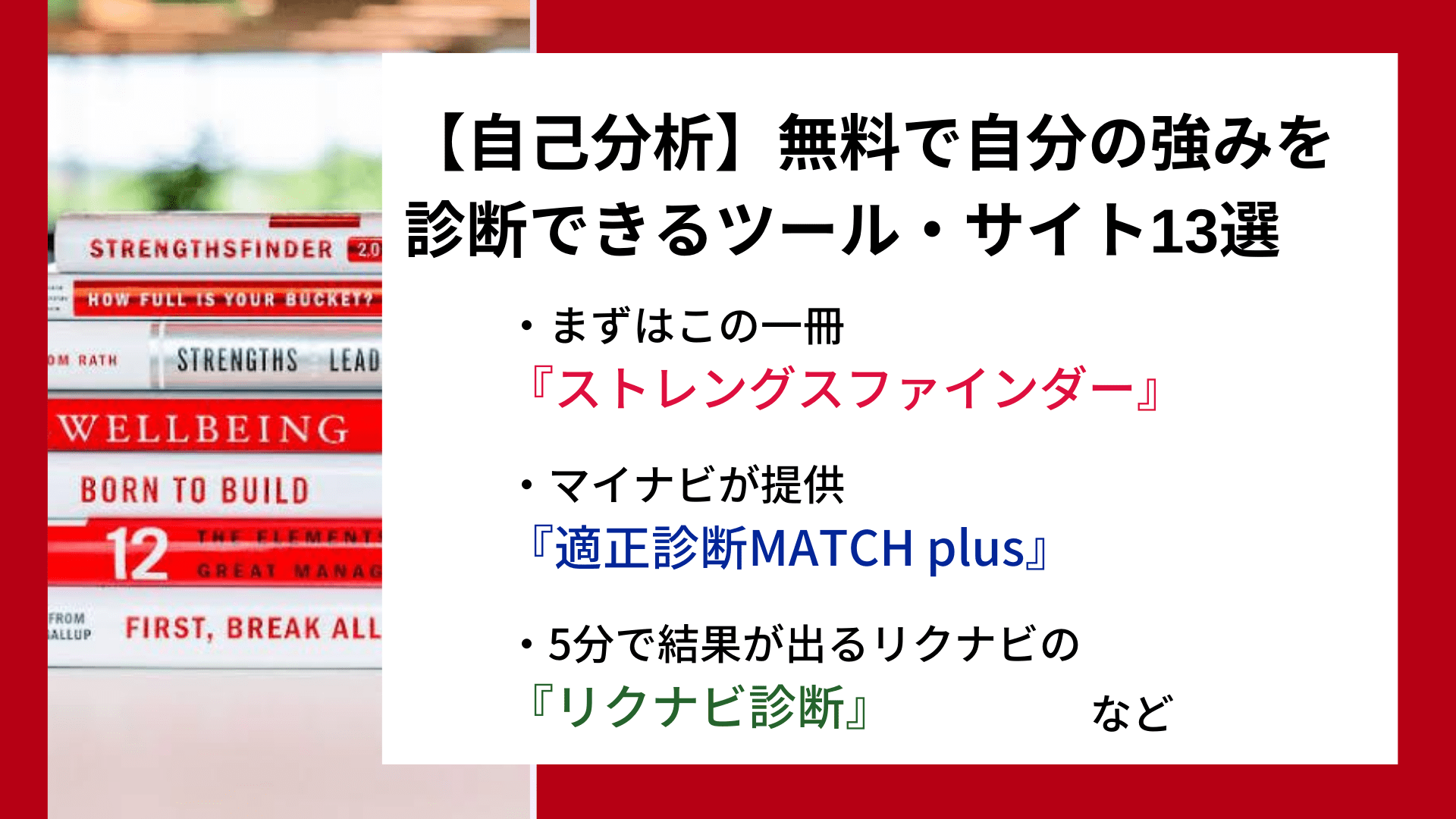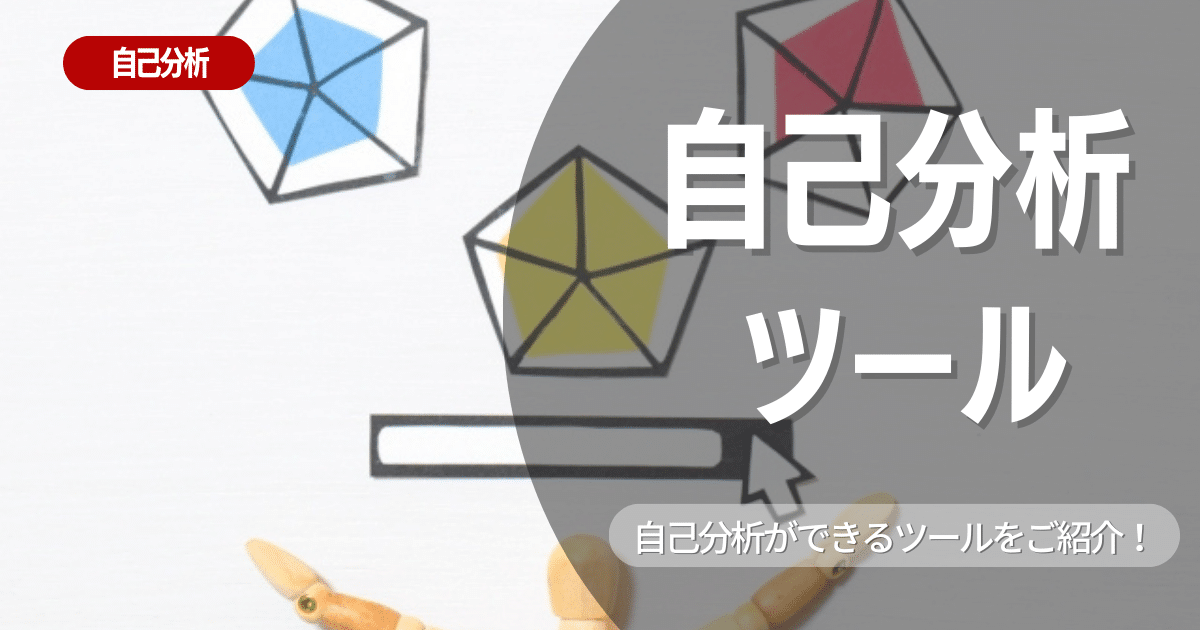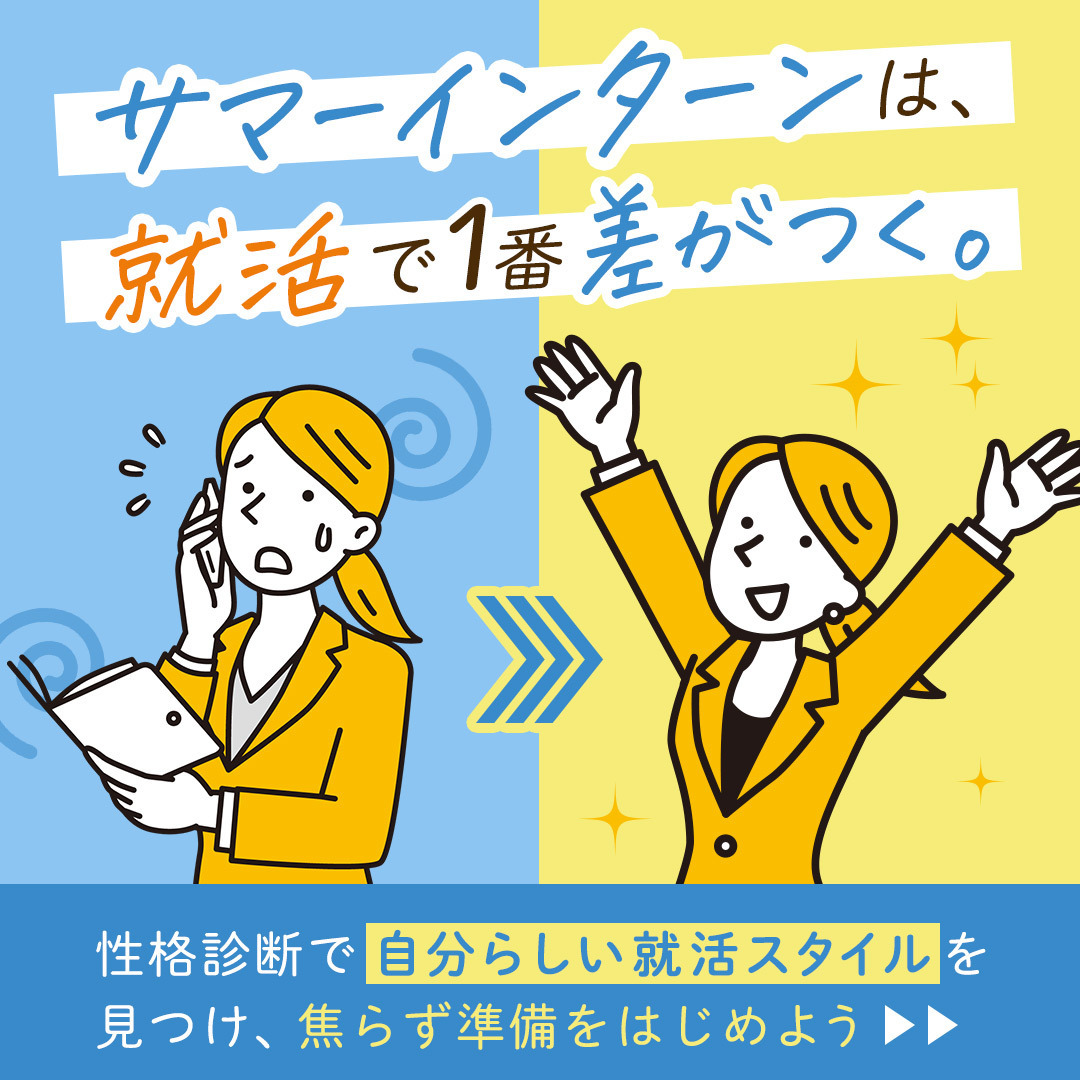やさしく解説!16Personalitiesを就活で活用する方法とは?
2024/10/8更新
はじめに
「自分って一体何者なんだろう?」
「どんな仕事が向いているんだろう?」
そんな疑問を抱えながら、就職活動に臨んでいるのではないでしょうか。
自分の強みや弱みを理解し、企業との相性を把握することは、納得のいく就職活動において非常に重要です。
しかし、自分自身を客観的に見つめることは難しく、自己分析に苦戦している方も多いのではないでしょうか。
今回は、世界中で3億人以上が利用している無料の性格診断テスト「16Personalities」を活用した自己分析術をご紹介します。16Personalitiesを使えば、あなたの隠れた才能や価値観、そして企業との相性を簡単に発見できます。
この記事を読めば、自己PRや企業研究、面接対策まで、16Personalitiesをフル活用して就職活動を有利に進める方法が分かるはずです。
この記事は以下のような方を対象に書いています。
- 16Personalitiesを就活で活用したい
- 自分のアピールポイントがわからない
- 企業選びに迷っている
- 客観的な視点もいれて自己分析をしたい
上記の様な方は、ぜひ以下の記事も合わせてお読みください。
上京を志す地方学生ならジョーカツ!
あなたのキャリアを加速させるチャンス!
無料で利用できる快適な個室シェアハウス、
東京までの交通費サポート付き
首都圏の注目企業への就活ならジョーカツ
首都圏の学生ならスタキャリ!
理想のキャリアを実現へと導く第一歩!
あなたにピッタリのキャリアアドバイザーを選び、
自分にマッチする優良企業をご紹介
首都圏企業のES添削から面接対策まで、就活ならスタキャリ
16Personalitiesとは?

16Personalitiesは、「ユング心理学」と「MBTI性格検査」という、心理学の二つの巨頭に基づいて開発された性格診断テストです。
難しそうに聞こえるかもしれませんが、心配ご無用。会員登録不要、しかも無料で、誰でも気軽に受けることができます。
質問に直感的に答えていくだけのシンプルな形式なので、心理学の知識は一切必要ありません。
簡単10分で診断ができる
16Personalitiesは、その手軽さと信頼性から、世界中で3億人以上が利用しています。
なんと、「世界で最も多くの人が診断を受けたテスト」とも言われているほどです。
この数字からも、その人気の高さと信頼性がうかがえますね。
何度でもチャレンジできる
しかも、16Personalitiesは何度でも無料で受けることができます。
就職活動中に自分の変化や成長を感じたら、再度テストを受けてみるのも良いでしょう。
もしかしたら、新たな自分の側面を発見できるかもしれません。
ただし、診断結果に一喜一憂しすぎるのは禁物。あくまで自己分析の参考として、広い心で受け止めてくださいね。
MBTI診断の指標
16Personalitiesという言葉より、「MBTI診断」と聞いたほうがピンと来る方も多いのではないでしょうか。
MBTI診断は、「Myers-BriggsTypeIndicator」の略称で、心理学に基づいた性格診断テストです。
ユングの心理学理論を基に、人の性格を16のタイプに分類します。
MBTI診断は、以下の4つの指標に基づいて性格を分類していきます。
- E(外向型)対I(内向型)
- S(感覚型)対N(直観型)
- T(思考型)対F(感情型)
この指標の組み合わせによって、16種類の性格タイプが生まれるのです。
たとえあばESTJは外交的で、感覚的で、思考的で、判断型であることを示します。
16Personalitiesを活用するためには「診断結果」を理解しよう
16Personalitiesを活用するためには、まずその性格タイプと診断結果を理解することからはじまります。
16Personalitiesでは、正確タイプを大きく4つのグループに分け、さらに各グループを4つのタイプに細分化してます。
それぞれのタイプは、独自の強みや弱み、価値観、行動パターンを持っているのです。
10分程度で終わる質問に答えていくと、自分の性格や行動パターンが認識され、16種類あるなかの一つの「性格タイプ」が診断されます。
- 分析家
- 外交官
- 番人
- 探検家
16Personalitiesのそれぞれの性格を詳しくみていきましょう。
分析家タイプ
分析家タイプは、知的好奇心と戦略的思考が際立つグループです。
常に新しい知識やアイデアを求め、複雑な問題を論理的に解決することに喜びを感じます。
| タイプ | 性格 | |
| 建築家 | INTJ | 孤独を愛する戦略家。類まれな知性と独創性を持ち、完璧主義な一面も。 |
| 論理学者 | INTP | 知的好奇心旺盛な発明家。複雑な理論や概念を好み、革新的なアイデアを生み出す。 |
| 指揮官 | ENTJ | カリスマ性あふれる指導者。大胆かつ戦略的に物事を進め、目標達成のためには努力を惜しまない。 |
| 討論者 | ENTP | 知的刺激を求める挑戦者。頭の回転が速く、多角的な視点から物事を分析し、議論を活性化させる。 |
外交官タイプ
外交官タイプは、共感力と調和を大切にするグループです。
常に周囲の人々とのつながりを意識し、平和な関係を築くことに力を注ぎます。
| タイプ | 性格 | |
| 提唱者 | INFJ | 静かなる理想主義者。深い洞察力と強い信念を持ち、世界をより良い場所にするために尽力する。 |
| 仲介者 | INFP | 優しく思いやりのある夢想家。豊かな感受性と創造性を持ち、調和と平和を愛する。 |
| 主人公 | ENFJ | 熱意あふれるリーダー。人を鼓舞し、モチベーションを高める才能に長け、チームを成功へと導く。 |
| 広報運動家 | ENFP | エネルギッシュで自由な精神の持ち主。常に新しい可能性を探求し、周囲にインスピレーションを与える。 |
番人タイプ
番人タイプは、責任感と安定を求めるグループです。
伝統や規則を重んじ、計画的に物事を進めることを好みます。
| タイプ | 性格 | |
| 管理者 | ISTJ | 誠実で勤勉な努力家。事実と論理に基づいて行動し、責任を持って任務を遂行する。 |
| 擁護者 | ISFJ | 温かく献身的な保護者。周囲の人々を大切にし、サポートすることに喜びを感じる。 |
| 幹部 | ESTJ | 頼れるリーダー。組織やコミュニティをまとめ、目標達成に向けて尽力する。 |
| 領事官 | ESFJ | 親切で社交的な人気者。周囲との調和を大切にし、温かい雰囲気を作り出す。 |
探検家タイプ
探検家タイプは、自由と刺激を求めるグループです。
型にはまらない生き方を好み、常に新しい経験や挑戦を求めています。
| タイプ | 性格 | |
| 巨匠 | ISTP | 冷静沈着な職人。実践的なスキルと問題解決能力に長け、手先を使う作業を楽しむ。 |
| 冒険家 | ISFP | 五感を大切にするアーティスト。美意識が高く、創造的な表現を通じて自己を表現する。 |
| 起業家 | ESTP | 行動力あふれるリスクテイカー。大胆な決断と行動力で、チャンスを掴み取る。 |
| エンターテイナー | ESFP | 楽しいことが大好きなエンターテイナー。周囲を楽しませ、自分も楽しむことをモットーとする。 |
こうやって全ての性格を見てみると、自分とは全く違う考えを持っている人がいることがわかり、おもしろいものです。
たとえば巨匠タイプのISTPさんは、いつも面白いことをして周りを笑わせようとするエンターテナータイプのESFPさんを見て、「疲れないのかあな」「無理をしているのではないか」と感じることもあるでしょう。
世の中にはさまざまな価値観の人がいて、その人によって向いていることや苦手と感じることも様々であることがわかる診断です。
16Personalitiesを自己分析で活用する方法
ここまで解説した通り、16Personaritiesは自己診断ツールであり、その結果をそのまま受け入れるのではなく、自己分析を探るためのてがかりとして活用することがポイントです。
ここでは、活用するための方法をステップに沿って紹介していきます。
活用するためのステップ
- 自己分析の準備
- 16Personalitiesの診断を受ける
- 結果と自己分析を照らし合わせる
- 診断結果を言語化する
それぞれ詳しくみていきましょう。
自己分析の準備
自己分析は、いわば自分だけの地図を描く作業です。
16Personalitiesに挑戦する前に、まずは自分自身と向き合い、自分の特徴や価値観を深く掘り下げてみましょう。
ポイントは過去の経験を振り返ることです。
過去の経験や具体的なエピソードを振り返ることで、自分の強みや弱みをより明確に認識できます。
例えば、「チームプロジェクトでリーダーシップを発揮して成功に導いた」という経験などもよいでしょう。
あなたのリーダーシップや責任感を裏付ける具体的な証拠となります。
時には、友人や家族など、信頼できる人に自分の印象を聞いてみるのも有効です。
客観的な視点を取り入れることで、自分では気づかなかった新たな一面を発見できるかもしれません。
16Personalities診断を受ける
自己分析である程度の地図が描けたら、いよいよ16Personalitiesの診断に挑戦しましょう。
診断中は、以下のポイントを意識することが大切です。
- 正直に直感的に回答する
- 「どちらでもない」はなるべく避ける
- 診断は何度かやってみる
質問に答える際は、深く考えすぎず、自分の心に素直に従って回答しましょう。
正直な気持ちが反映された結果こそが、真のあなたを映し出す鏡となります。
また、曖昧な回答は、診断結果の精度を下げる可能性があります。
できるだけ、白黒つけることを意識して、なるべく「どちらでもない」の選択肢は避けましょう。
診断結果は、そのときの気分や状況によって変化することもあります。
質問内容がむずかしい(英語を直訳したようなもの)ため「どういう意味だろう?」とそのときの感覚で答えてしまうこともあるでしょう。
何度か挑戦することで、正しい診断結果が見えてきます。
診断結果と自己分析を照らし合わせる
診断結果がでたら、自己分析で出た自分像と照らし合わせてみましょう。
結果と自己分析が一致する部分、異なる部分を見つけることで、新たな発見が生まれるはずです。
診断結果と自己分析が一致した場合、これはあなたが自覚している強みを再認識する良い機会となるでしょう。
もし、診断結果と自己分析の答えが一致しない場合、新たな自己発見のチャンスです。
自己発見と照らし合わせながら自分自身を深く理解するための材料として活用しましょう。
納得がいかない場合は何度もやり直してみるのもアリです。
ただし、何度診断をしても結果がおなじである場合、それがあなたの強みや弱みになります。
友人や家族に「自分のこういった部分があるか」を聞いてみると良いかもしれません。
今まで気づかなかった自分の姿に気づく機会になるかもしれませんよ。
診断結果を言語化する
診断結果と自己分析を比較したら、最後にその内容を言語化してみましょう。
面接やエントリーシートで活用できるように、自分の強みや弱みを具体的な言葉で表す必要があります。
たとえば、自分の強みを具体的に表現し、それがどのように就職後活かせるのかを明確に伝えることが大切です。
弱みとなる部分は隠すのではなく、それを認識して改善・克服するための具体的な努力や計画を考えてください。
前向きな姿勢をアピールできるはずですよ。
16Personalitiesは、自己理解を深める地図として、あなたのキャリアや人間関係を豊かにする可能性を秘めたツールです。
就活における「自己分析」において非常に役立つため、積極的に活用していくとよいでしょう。
16Personalitiesを就活で活用するメリット
16Personalitiesを就活で活用することには、さまざまなメリットがあります。
- 自己理解を深められる
- 相性の良い企業を見つけられる
- コミュニケーションがスムーズになる
それぞれを詳しくみていきましょう。
自己理解を深められる
ここまでも解説してきたように、16Personalities診断を行うことで今まで以上に自分を理解するきっかけになります。
ただの心理テストなどと違い、心理学的タイプ論をもとに分析された結果です。
16Personalitiesは、自己分析をおこなう最も有効なツールだともいえます。
「自分の弱みはわかるけど、強みってなんだろう?」と悩む人は多いはず。
これは謙虚な日本人ならではの特性だともいえます。
自分の強みを客観的に提示してもらうことで、より自信をもって自分の強みを企業に伝えられるはずです。
もちろん強みや弱みだけでなく、自分の興味関心もみえてきます。
第一志望の企業がきまらない就活生にとっても、16Personalitiesは大きなメリットとなるでしょう。
相性の良い企業を見つけられる
16Personalitiesで自己分析を性格に行うことで、相性の良い企業をみつけるきっかけにもなります。
ただし、そのためには企業分析が欠かせません。
企業理念や社風をじっくりと調べ理解することがポイントです。
その上で16Personalities診断を受ければ、自分の適正と企業の求める人材がマッチしているのかを見極めることができます。
たとえば以下の例を参考にしてください。
指揮官タイプ(ENTJ)
| 特性 | リーダーシップがあり、戦略的思考に長ける。目標達成のために積極的に行動し、困難な状況でも決断力を持って対応できる。 |
| 向いている企業 | ベンチャー企業、外資系企業など変化の激しい環境でリーダーシップを発揮できる企業 |
| 向いている職業 | コンサルタント、経営者、弁護士など専門知識を活かせいて戦略的な意思決定が求められる職業 |
仲介者タイプ(INFP)
| 特性 | 理想主義的で、創造性豊か。人の感情に敏感で、共感力が高い。自分の価値観に基づいて行動し、社会貢献に関心がある。 |
| 向いている企業 | NPO、教育機関、福祉施設など、社会貢献性の高い企業 |
| 向いている職業 | カウンセラー、教師、ソーシャルワーカー、アーティストなど、人の心に寄り添い、創造性を活かせる職業 |
擁護者タイプ(ISFJ)
| 特性 | 責任感が強く、献身的。周囲の人をサポートすることに喜びを感じ、調和を大切にする。計画性があり、コツコツと努力できる。 |
| 向いている企業 | 医療機関、介護施設、公務員など、安定した環境で人の役に立てる企業 |
| 向いている職業 | 看護師、保育士、事務職、公務員など、丁寧な仕事ぶりと責任感が求められる職業 |
倫理学者タイプ(INTP)
| 特性 | 知的好奇心が旺盛で、分析能力が高い。複雑な問題を論理的に解決することに喜びを感じ、常に新しい知識を吸収しようとする。 |
| 向いている企業 | 研究機関、IT企業、コンサルティングファームなど、専門知識を活かして分析・問題解決できる企業 |
| 向いている職業 | 研究者、エンジニア、プログラマー、データサイエンティストなど、論理的思考と問題解決能力が求められる職業 |
冒険家タイプ(ISFP)
| 特性 | 自由奔放で、好奇心旺盛。五感を大切にし、美的感覚に優れている。型にはまらず、自分のペースで物事を進めることを好む。 |
| 向いている企業 | クリエイティブ業界、旅行業界、ファッション業界など、個性を活かして自由に働ける企業 |
| 向いている職業 | デザイナー、アーティスト、ミュージシャン、旅行ガイドなど、創造性と感性を活かせる職業 |
いくつか紹介しましたが、あくまで一般的な傾向であり個人の経験やスキル、価値観によって最適な企業や職業は異なります。
かならずしも最適な企業や職業というわけではありません。
一例として参考にし、自分にあった企業を見つけてみてください。
16Personalitiesを自己分析に使う際の注意点

ここまで解説したように、16Personalitiesは、手軽に自分の性格傾向を把握できる便利なツールです。
ただし活用する際にはいくつかの注意点があります。
- 個人に寄り添った結果ではない
- 診断結果は自分の言葉で噛み砕く
それぞれの内容を解説していきます。
診断結果はあくまで一般的な傾向
16Personalitiesは、多くの人々に共通するパターンに基づいて性格を分類しています。
そのため、診断結果はあくまで一般的な傾向を示すものであり、一人ひとりの個性や状況を完全に反映しているわけではありません。
SPIなどの適性検査のように、あなただけに特化した詳細な分析結果を期待はしないことです。
もし、よりパーソナルな診断結果を求めるのであれば、専門機関による有料の性格診断サービスなどを検討する必要があるかもしれません。
しかし、就活生にとって高額なサービスは負担が大きいでしょう。
無料の範囲内で活用できるツールをうまく組み合わせることで、十分に自己分析を深めることができます。
診断結果を自分自身の言葉で
16Personalitiesの診断結果ページには、あなたの性格タイプの特徴や強み、弱みなどが詳しく解説されています。
しかし、これらの解説をそのまま鵜呑みにするのではなく、自分自身の経験や考えと照らし合わせて、自分なりの言葉で解釈することが重要です。
「この特徴は自分にも当てはまると思う」
「この部分は少し違う気がする」
など、診断結果に対して積極的に疑問を持つことも大切です。
自分自身について深く考えることで、より深い自己理解につながります。
納得できない部分を無理に受け入れる必要はありませんが、その背景や文脈を理解しようと努めることで、新たな発見があるかもしれません。
16Personalitiesの活用に関するQ&A
では、最後によくある質問をご紹介します。
疑問点を解消していってください。
Q.診断結果が自分のイメージと違う場合はどうすれば良いですか?
A.診断結果はあくまで一つの視点です。
もし診断結果が自分のイメージと異なる場合でも、無理に自分を当てはめようとする必要はありません。
診断結果を参考にしながら、自分自身について深く考えるきっかけとして活用しましょう。
Q.16Personalitiesの結果を面接で話すのは良いでしょうか?
A.直接的に診断結果を伝えることは控えた方が良いでしょう。
しかし、診断結果を通して得られた自己理解を、自分の言葉で表現することは有効です。
例えば、「私は計画的に物事を進めることが得意です。そのため、プロジェクトのスケジュール管理など、責任を持って取り組める仕事に魅力を感じています」のように、具体的なエピソードを交えてアピールすると効果的です。
Q.16Personalitiesの診断結果は変わることはありますか?
A.はい、診断結果は変わる可能性があります。
時間の経過や経験、環境の変化によって、あなたの考え方や行動パターンが変化する可能性があるからです。
数ヶ月ごと、あるいは大きな変化があったタイミングで診断を再度受けてみることで、自己理解を深めることができます。
Q.16Personalities以外の自己分析ツールも活用したほうが良いですか?
A.もちろんです。16Personalitiesは自己分析のツールの一つであり、他のツールと組み合わせて活用することで、より多角的な視点から自己理解を深めることができます。
興味のある分野や強みに合わせたツールを選んでみましょう。
ぜひ以下の記事もあわせてお読みください。
さいごに
本記事では、16Personalitiesの概要、自己分析における活用方法、注意点、そしてよくある質問への回答を通して、このツールを効果的に利用するための情報を提供しました。
6Personalitiesは自己分析ツールそのものではありませんが、自己理解を深めるための有効な手がかりとなります。
診断結果をそのまま受け入れるのではなく、自分自身と照らし合わせながら深く考察することで、新たな気づきが得られるでしょう。
ぜひ診断結果をきっかけに、自分自身をより深く理解し、納得のいく就職活動につなげてください。