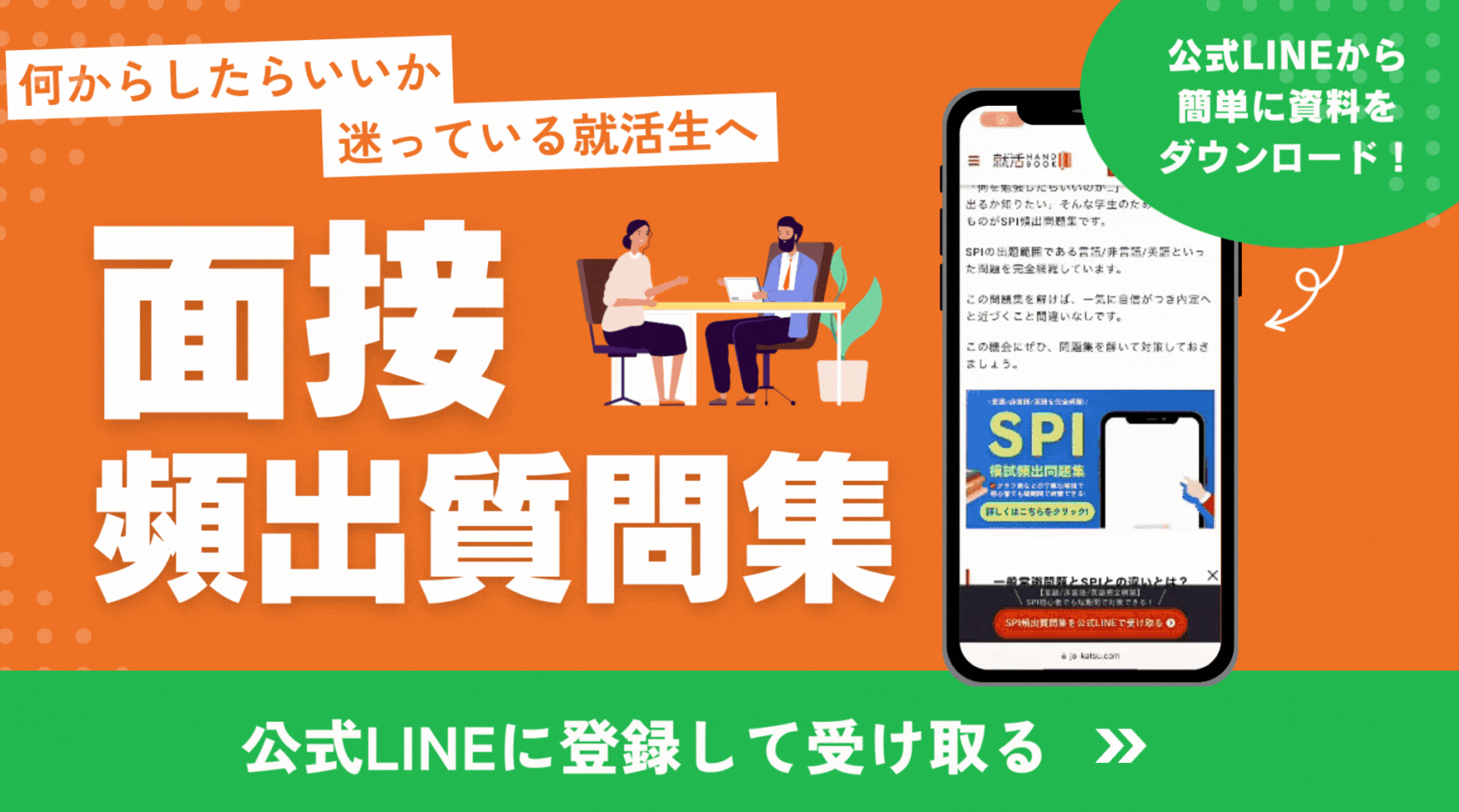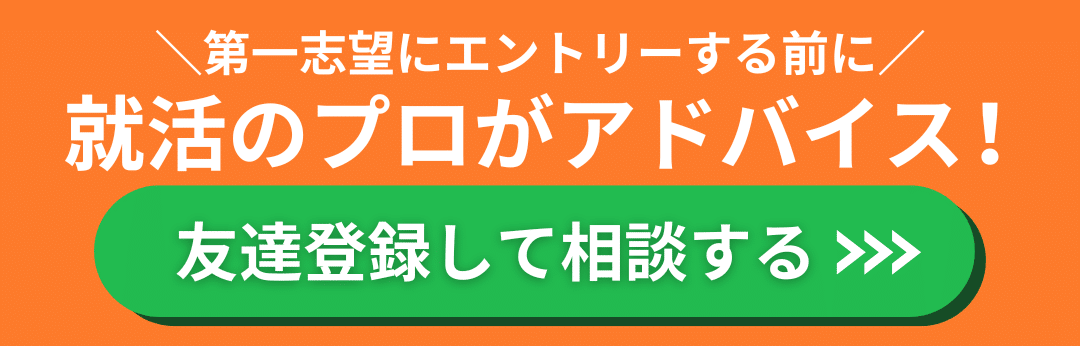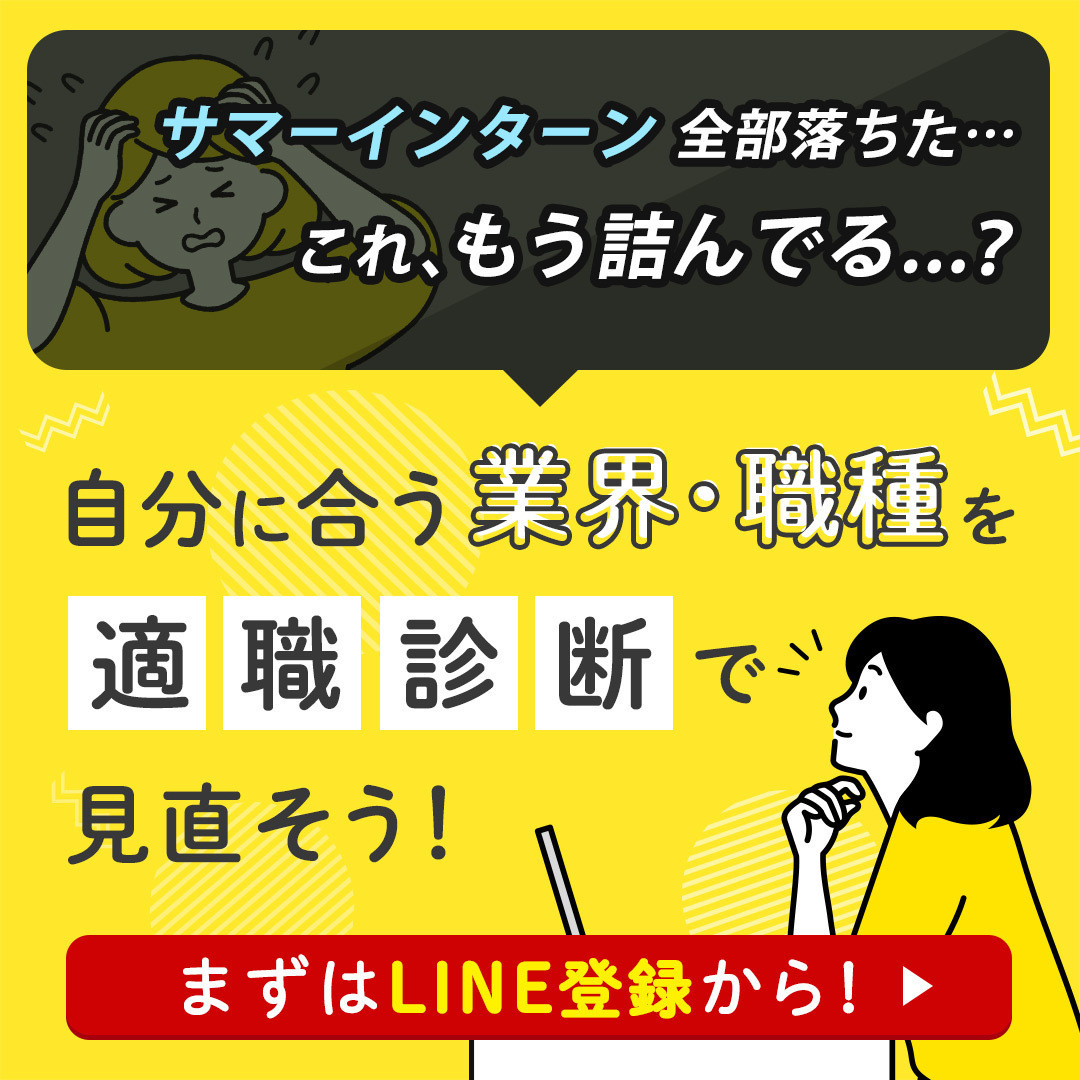住宅手当の相場とは?企業別ランキングや支給条件などもご紹介!
2025/1/31更新

この記事の監修者
杉崎 聖輝(キャリアアドバイザー リーダー)
東京学芸大学卒業後、6年間中学教員として勤務。2000人以上の生徒との関わりで人の良さを見出す力を磨く。ソフトテニス部顧問として部活指導も経験。現在は株式会社ナイモノに転職し、キャリアアドバイザーとして活躍。教育現場での経験を活かし、自己分析から選考対策まで、1人1人の価値観を大切にした就活サポートを提供。適性のある業界・業種の発見や差別化されたガクチカ作りが得意。就活初心者や不安を抱える学生・チャレンジ精神旺盛な20代向けのサポートに力を入れている。
東京学芸大学卒業後、6年間中学教員として勤務。2000人以上の生徒との関わりで人の良さを見出す力を磨く。ソフトテニス部顧問として部活指導も経験。現在は株式会社ナイモノに転職し、キャリアアドバイザーとして活躍。教育現場での経験を活かし、自己分析から選考対策まで、1人1人の価値観を大切にした就活サポートを提供。適性のある業界・業種の発見や差別化されたガクチカ作りが得意。就活初心者や不安を抱える学生・チャレンジ精神旺盛な20代向けのサポートに力を入れている。
はじめに
住宅手当は、従業員の生活に関する負担を軽減することを目的としています。
住宅手当とは、従業員の住宅に関連する補助・手当を支給する福利厚生制度です。
福利厚生には、「法定福利厚生」と「法定外福利厚生」の2種類があり、住宅手当は法定外福利厚生に該当します。
法定外福利厚生は法律による規定がなく、企業が任意で導入するもののため、住宅手当支給有無は各企業で異なります。
住宅手当も含め、住宅関連の補助には家賃補助・社員寮・社宅・引越し手当などが存在します。
本記事では、住宅手当が多く支給される企業ランキングや、住宅手当の一般的な相場について解説していきます。
この記事は、以下のような就活生を対象にしています。
- 住宅手当や家賃補助の相場を知りたい
- 住宅手当が多い企業を知りたい
- 住宅手当が充実している企業の探し方を知りたい
また、住宅手当とはそもそも何なのか、解説している記事は以下になります。
こちらもぜひ参考にご覧ください。
家賃手当(住宅手当)とは?就職活動で押さえておきたいポイントを解説
【面接頻出質問集】100種類の回答例をいつでもスマホからチェックできる!
面接対策に悩んでいる方にピッタリの面接頻出質問集を用意しました。
質問と回答例は、全部で100種類あります。
この記事の結論とは?
先にこの記事の結論からお伝えすると、令和2年度の調査による住宅手当・家賃手当の相場は1万7,800円というデータが出ています。
住宅手当を支給する企業は全体の47.2%程度で、約半数の割合というデータが出ています。
住宅手当は扶養家族の有無や、持ち家・賃貸・実家住まいなどの条件によっても支給額が異なりますが、多い企業であれば約10万円も支給されることもあるようです。
一方、近年は成果主義の拡大や、テレワークの普及などにより、住宅手当という制度そのものが縮小傾向にあるため、一概に住宅手当だけで企業選びをするのもおすすめできません。
次の章からは、住宅手当や家賃補助の相場についてや、住宅手当の多い企業ランキングなどについて、詳しく解説していきます。
住宅手当・家賃補助の一般的な相場

住宅手当・家賃補助の一般的な相場は、厚生労働省 令和2年就労条件総合調査により確認できます。
第19表 諸手当の種類別支給された労働者1人平均支給額(令和元年11月分)
| 令和2年調査計 | 17,800円 |
| 1,000人以上 | 21,300円 |
| 300~999人 | 17,000円 |
| 100~299人 | 16,400円 |
| 30~99人 | 14,200円 |
企業規模によって住宅手当平均支給額は異なり、企業規模の大きさに住宅手当支給額は比例することが見て取れます。
詳細は以下のページを参照してください。
住宅手当がつかない企業もあるの?

住宅手当は法定外福利厚生であるため、支給有無は各企業で異なります。
では、どのくらいの企業が住宅手当を導入しているのでしょうか?
厚生労働省が実施した令和2年就労条件総合調査によると、住宅手当を支給する企業の割合は47.2%です。
半数以上の企業は、住宅手当が支給されない状況にあります。
企業規模が大きければ大きいほど、住宅手当が支給される割合は高くなる傾向があるようです。
一方、大手企業であれば必ず住宅手当が導入されているわけではありません。
従業員1,000人以上の企業でも、住宅手当を支給しているのは全体の61.7%にとどまります。
詳細は、以下のWebページを参照してみてください。
一般的な住宅手当の支給条件

住宅手当が支給される条件は、実施企業が自由に設定できます。
住宅手当導入時の規定や条件に、法的制限はありません。
一律の金額で住宅手当を支給する企業もあれば、従業員の状況に応じて支給額を設定する企業もあります。
すべての企業に当てはまるわけではありませんが、一般的な住宅手当の支給条件は以下のとおりです。
- 正規雇用または非正規雇用
- 扶養家族の有無
- 賃貸または実家暮らし
1つずつ、詳しくみていきましょう。
正規雇用または非正規雇用
勤務条件に差がある場合などは、正規雇用か非正規雇用かで住宅手当の支給条件は異なります。
一般的に非正規雇用には転勤がありませんが、正規雇用には転勤があるため、正規雇用に限り住宅手当を出すというケースも見られます。
しかし、同一の業務内容・勤務条件であれば、同一労働同一賃金制度の観点から住宅制度の支給有無を区別してはいけないことになります。
扶養家族の有無
扶養家族がいれば当然、より広い住居が必要になり、家賃も高くなります。
各状況に応じて、住宅手当を増額することにより従業員の負担を軽減している企業もあるようです。
賃貸または実家暮らし
賃貸物件に住んでいる場合、毎月家賃を支払わなければなりません。
賃貸の場合には住宅手当を支給し、実家暮らしの場合には支給しない企業が多くあります。
住宅手当支給額が大きい企業ランキング

各企業によって住宅手当の有無・支給条件は異なりますが、実際に住宅手当支給額が大きい企業はどのような企業なのでしょうか?
以下では、住宅手当の支給額が大きい企業をご紹介します。
- サントリーホールディングス株式会社 9~10万円
- 株式会社朝日新聞社 9.5万円
- 住友生命保険相互会社 8.5万円
- 日本放送協会(NHK) 8万円
- AGC株式会社(旧旭硝子株式会社) 7.5万円~8万円
- YKK株式会社 7.5万円
- 株式会社三菱UFJ銀行 7万円
- 富士フイルムビジネスイノベーション株式会社(旧富士ゼロックス) 7万円
- 株式会社野村総合研究所 6.5万円
- スリーエムジャパン株式会社 6万円
- 株式会社日立製作所 5万円
- 東日本旅客鉄道株式会社(JR東日本) 5万円
- ピクシブ株式会社 5万円
- 住友重機械工業株式会社 4.5万円
- 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ 4万円~7万円
- 株式会社サイバーエージェント 3万円
- クックパッド株式会社 3万円
- 株式会社MIXI 3万円
- 京セラ株式会社
それぞれ詳しくみていきましょう。
サントリーホールディングス株式会社
サントリーホールディングス株式会社の住宅手当は、9~10万円に設定されています。
基本的には家賃の約80%を支給するとしていますが、上限金額はお住まいの地域によって異なります。
- 住宅手当は約80%を企業側が負担
- 上限額は地域によって異なる
- 地域によっては10万円を超えて補助を受けられる場合もある
- 会社事由で引越しが必要となる場合、従業員自身が選んだ物件を会社名義で契約
- 社員全員が社宅・独身寮を利用可能
株式会社朝日新聞社
株式会社朝日新聞社の住宅手当は、9.5万円を上限として支給されています。
ただし、入社後最長5年間で、その後は上限5万円が支給されます。
- 9.5万円を上限に家賃補助を受けることができる(1つの勤務地について最長5年間・所定の方法により計算)
- 6年目以降は上限5万円
- 所定の計算方法=(家賃-12万)×0.5+6.5万
- 転勤があった場合は期間がリセットされ、再度1年目として扱われる
住友生命保険相互会社
住友生命保険相互会社の住宅手当は、8.5万円を上限として支給されています。
ただし、入社後3年目までで、実家が遠方などの条件が設定されています。
- 8.5万円を上限として住宅補助が支給される
- ただし、3年目まで・実家から会社までの通勤時間が2時間以上の場合のみ
- 社宅制度のほか、東京・大阪地域には独身寮完備
日本放送協会(NHK)
日本放送協会(NHK)の住宅手当は、8万円を上限として支給されています。
実家からの通勤ではない・転勤者用住宅に住んでいないなどの条件が設定されています。
- 住宅手当は8万円が上限
- 転勤者用住宅などに入居する場合・親元から通勤する場合を除く
AGC株式会社(旧旭硝子株式会社)
AGC株式会社(旧旭硝子株式会社)の住宅手当は、7.5~8万円を上限として支給されています。
原則は家賃の50%を支給し、お住まいの地域が首都圏かどうかでも上限金額が変わります。
- 既婚者は外部借上社宅制度あり
- 8万円を上限に家賃の50%を支給・主たる生計維持者であることが条件(首都圏で家賃15万円以上の物件に限る)
- 首都圏以外は、上限6万円
- 単身者向けには、独身寮・社宅あり
YKK株式会社
YKK株式会社の住宅手当は、7.5万円を上限として支給されています。
原則は家賃の70%を支給していますが、独身寮や一戸建ての社宅なども存在します。
- 家賃の70%を企業が負担
- YKKグループは建築物に関わっているため寮・社宅の外観デザインがおしゃれ
- 月々4,000円の負担で済む寮もある
- 完全個室・冷暖房設備・食事提供付きの独身寮あり
- 家族向け一戸建ての社宅あり
- 社宅や寮がない地域には、借上社宅制度導入し、上限7.5万円の家賃補助
株式会社三菱UFJ銀行
株式会社三菱UFJ銀行の住宅手当は、7万円を上限として支給されています。
原則は家賃の70%を支給していますが、お住まいの地域によっても異なります。
- 世帯主の場合、7万円を上限に家賃の70%の補助が受けられる
- 地域によって異なる
- 転勤のない一般職を含む
富士フイルムビジネスイノベーション株式会社(旧富士ゼロックス)
富士フイルムビジネスイノベーション株式会社の住宅手当は、7万円を上限として支給されています。
住宅手当以外にも、借上げ社宅もあります。
- 7万円を上限とする住宅手当に加え、社宅も完備
株式会社野村総合研究所
株式会社野村総合研究所の住宅手当は、6万円を上限として支給されています。
また、独身寮も完備されています。
- 住宅手当の上限は6万円
- 一定条件を満たす場合が対象(実家の所在地は問わない)
- 女子寮1か所・男子寮3か所の独身寮あり(エリア職システムエンジニアは対象外)
スリーエムジャパン株式会社
スリーエムジャパン株式会社の住宅手当は、6万円を上限として支給されています。
- 住宅手当の上限は6万円
株式会社日立製作所
株式会社日立製作所の住宅手当は、5万円を上限として支給されています。
原則は家賃の50%を補助しており、月1.5万円で住める寮もあります。
- 家賃の50%を補助(上限5万円)
- 寮完備(月々1.5万円)
東日本旅客鉄道株式会社(JR東日本)
東日本旅客鉄道株式会社の住宅手当は、5万円を上限として支給されています。
寮や社宅なども完備されており、住環境は非常に充実しています。
- 所有/賃貸住宅援助金
- 寮/社宅
- 独身者・単身赴任者には寮(1人用個室)
- 家族向けには社宅を設置
- 家具設置
- 食堂併設の寮もあり
ピクシブ株式会社
ピクシブ株式会社の住宅手当は、5万円を上限として支給されています。
ただし、配偶者の有無や会社からの距離などの支給条件が設定されています。
- 住宅手当:会社から1.2km圏内であれば月々5万円。配偶者がいれば月々5万円加算
- 在宅手当:月々5,000円
住友重機械工業株式会社
住友重機械工業株式会社の住宅手当は、4.5万円を上限として支給されています。
単身の場合は家賃の65%を補助していますが、複身の場合は最大6.5万円が支給されます。
- 居住地域・単身・複身によって住宅手当支給額は異なる
- 単身(独身):1か月最大4.5万円(家賃の65%)
- 複身:1か月最大6.5万円(家賃の65%)
- 支給期間(年齢・勤続年数)の上限はない
- 社有独身寮あり(31歳未満の社員に限る)
- 女性社員や社有独身寮がない地域の社員については、借上物件を独身寮として提供
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ
株式会社エヌ・ティ・ティ・データの住宅手当は、4~7万円を上限として支給されています。
独身か結婚しているかなどにより、金額は変動します。
住宅手当以外にも、自立支援金などの制度が充実しています。
- 自立支援一時金20万円:入社後3か月までに契約を開始した場合、1回限り支給
- 住宅補助(独身者・首都圏の場合)月々4万円
- 独身の場合、入社3年目終わりまで自立支援金月々2万円を加算
- 住宅補助(独身者以外・首都圏の場合) 月々7万円
株式会社サイバーエージェント
株式会社サイバーエージェントの住宅手当は、3万円を上限として支給されています。
オフィスからの距離などの条件がありますが、勤続5年以上の社員は、どこに住んでいても月々5万円が支給されます。
- 2駅ルール:勤務しているオフィスの最寄駅から各線2駅圏内に住んでいる正社員について月々3万円を補助
- どこでもルール:勤続年数が丸5年を経過した正社員について、場所の条件はなく月々5万円を補助
クックパッド株式会社
クックパッド株式会社の住宅手当は、3万円を上限として支給されています。
会社が指定するエリアに住むことが条件で、そのための引越し代なども補助されます。
- 会社が指定する対象エリアに居住する場合:月々3万円を上限として支給
- 近距離奨励金(引越し手当):対象エリアに引っ越す場合、50万円を支給(対象エリア内での引越しにつき5年ごとに同額支給)
株式会社MIXI
株式会社MIXIの住宅手当は、3万円を上限として支給されています。
こちらも住まいが渋谷駅の近辺であることが条件となっており、引っ越す場合は費用の補助を別途受けられます。
- 住宅手当・住宅賃貸/分譲物件サポート
- 渋谷駅から届出住所まで直線3km以内の場合、月々3万円補助
- 提携先の不動産仲介業者を利用すれば、物件購入・賃貸の契約成立時に社員優待を受けられる
- 転居費用/転居時交通費補助
- 入社のために遠方から引越しする場合、引越し費用を補助(条件・上限金額あり)
京セラ株式会社
京セラ株式会社は、「都市勤務者住宅補助手当」を支給しています。
詳細条件は不明ですが、地方ではなく都市部で勤務する人にだけ住宅手当が支給されるようです。
- 都市勤務者住宅補助手当
- 独身寮あり:寮費月々3,000円~4,000円(光熱費・水道料別)
令和2年の住宅手当・家賃補助の一般的な相場は1万7,800円のため、上記企業の住宅手当の充実さが分かります。
企業の募集要項を確認する限り、家賃補助の正確な金額を公開していない企業は多いです。
また、福利厚生制度内容が変更になることもあります。
あなたが応募する際には、改めて確認しましょう。
住宅手当は規模縮小・廃止傾向

住宅手当は平成12年度以降、減少傾向にあります。
住宅手当や社員寮・社宅が規模縮小・廃止傾向にある理由は、以下の3つです。
- 同一労働同一賃金制度に伴う対応
- 成果主義制度の拡大
- テレワークの普及
それぞれ詳しく解説していきます。
同一労働同一賃金制度に伴う対応
住宅手当の有無は、正社員と非正規雇用従業員との待遇格差につながっています。
特別な理由なく、非正規雇用従業員に手当を認めないことはできません。
これにより、住宅手当を廃止し、手当分を給与に上乗せして支給する企業が増えました。
成果主義制度の拡大
住宅手当は成果の有無に関係なく、一律で支給される手当です。
現在制度が拡大している成果主義や、業務の範囲が明確なジョブ型雇用に反する手当となります。
時代とともに企業を取り巻く環境が変化したことにより、導入される制度も見直されていくでしょう。



テレワークの普及
新型コロナの影響により、国内企業にもテレワークが普及しました。
出社を前提としない働き方が定着し、住む場所が働く場所となっています。
これに伴い、住宅手当よりもテレワーク(在宅勤務)手当を企業は最優先で検討する必要が出てきたのです。
住宅関連費用が法定外福利厚生制度に占める割合は、48.2%となっており、住宅手当は企業にとって大きな負担です。
住宅手当は規模縮小・廃止傾向にあることを念頭に就活を進めていく必要があります。
以下の記事では、テレワーク(フルリモート)で働く仕事について紹介しています。
就職先と住宅手当について検討する際の材料にしてみてください。
フルリモート可能な仕事を紹介
住宅手当が充実している会社を探す方法

住宅手当が支給されるかどうかは、募集要項にて確認できます。
まずは、企業の募集要項の福利厚生欄を確認しましょう。
しかし、住宅手当の有無のみで支給額まで分からない場合など、詳細条件が掲載されていないことがあります。
その際は、口コミサイトを確認してみましょう。
例えば、openworkや転職会議が挙げられます。
加えて、次のような就職エージェントも活用しましょう。
- リクナビ就職エージェント
- doda新卒エージェント
- マイナビ新卒紹介
- ミーツカンパニー
今は住宅手当を廃止する企業も増えているので、住宅手当がなくても応募して問題ありません。
ただし、住宅手当があると、生活費の負担軽減が大きいことは事実です。
住宅手当がない企業でも生活できる?

物価が安い地域・家賃が安い部屋を選ぶなど工夫を行えば、住宅手当がない企業でも生活できるでしょう。
実際に住宅手当がない企業でも生活できるかイメージするためには、1人暮らしに必要な1か月の生活費を把握する必要があります。
総務省 家計調査年報によると、一人暮らしにかかる生活費は、以下のとおりです。
| 食料 | 41,731円 |
| 住居 | 22,118円 |
| 光熱・水道 | 11,383円 |
| 家具・家事用品 | 5,830円 |
| 被服および履物 | 4,843円 |
| 保健医療 | 7,703円 |
| 交通・通信 | 18,916円 |
| 教育 | 8円 |
| 教養娯楽 | 17,654円 |
| その他の消費支出 | 24,860円 |
| 合計 | 155,046円 |
額面の約80%が一般的な手取り額といわれているため、初任給が20万円なら手取り額は約16万円となります。
住居費を除くと、合計132,928円となり、家賃には3万円弱しか充てられません。
住宅手当がなければ余裕ある生活を送ることは困難ですが、住宅手当だけがすべてではないはずです。
「住宅手当が支給されなくても、自分のやりたい仕事に携わりたい」、「住宅手当が支給される条件の場所に無理に住むよりも、プライベートを大切にしたい」というように考える就活生もいるでしょう。
そもそも給与額が大きければ、住宅手当がなくてもその分を補えます。
住宅手当だけに注目することなく、引越し手当・家族手当・赴任手当などの補助も確認しましょう。
長い人生を送るにあたり、結婚・家の購入など次のライフステージも考慮して就活を進めることをおすすめします。
家賃手当について考えるにも、そもそも生活していくのにかかるお金がどれくらいなのか分からないと、適切な判断ができませんよね。
以下の記事では、東京の一人暮らしを想定した諸費用の相場を紹介しています。
こちらもぜひ参考にしてみてください。
【東京】社会人一人暮らしの「家賃相場」と家賃を抑えるコツとは



さいごに
住宅手当は法律で定められた制度ではないため、企業が独自に支給の有無・支給条件を設定できます。
企業規模が大きいほど、住宅手当が支給される割合は高くなるでしょう。
しかし、住宅手当さえあれば優良企業というわけではありません。
住宅手当がつかない場合であっても、ほかの待遇で優れている企業は多くあります。
例えば、ほかの福利厚生が充実しており、住宅手当分を補てんできる・残業が少ない・副業を容認しているなどです。
住宅手当のみにこだわらず、そのほかの待遇や働きやすさを総合的に判断して就活を進めていきましょう。