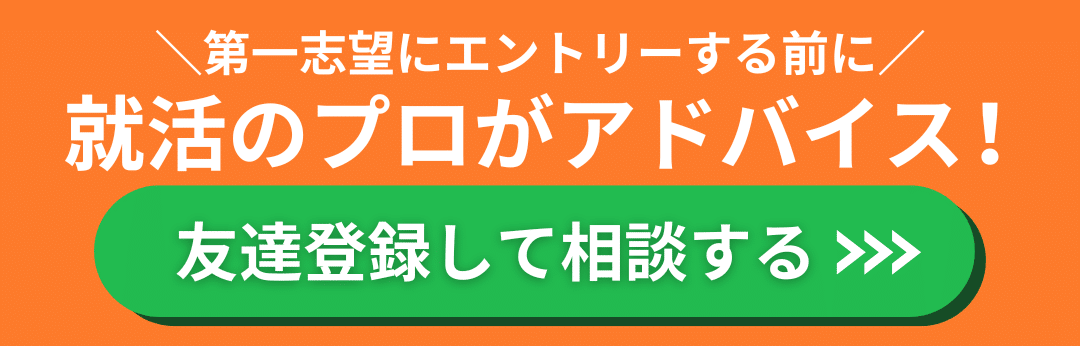【東京】社会人一人暮らしの「家賃相場」と家賃を抑えるコツとは
2025年1月31日更新

この記事の監修者
三好 勝利(キャリアアドバイザー)
新卒で小学校教員となり、学級担任や学年主任などを務め、1000人以上の生徒の指導に携わる。その後、大手教育企業でのコンサルティング営業を経て、現在は株式会社ナイモノのキャリアアドバイザーとして250名以上の学生の就職支援に従事。未経験IT、総合職、人材など幅広い業界への支援実績を持つ。面接対策や自己PRの指導に定評があり、面接官の経験を生かした的確なアドバイスが強み。学生一人一人に寄り添い、ラフな雰囲気で親身に相談に乗ることを心がけている。
新卒で小学校教員となり、学級担任や学年主任などを務め、1000人以上の生徒の指導に携わる。その後、大手教育企業でのコンサルティング営業を経て、現在は株式会社ナイモノのキャリアアドバイザーとして250名以上の学生の就職支援に従事。未経験IT、総合職、人材など幅広い業界への支援実績を持つ。面接対策や自己PRの指導に定評があり、面接官の経験を生かした的確なアドバイスが強み。学生一人一人に寄り添い、ラフな雰囲気で親身に相談に乗ることを心がけている。
はじめに
社会人になって、初めて東京で一人暮らしするときに気になるのが家賃相場。家賃をできるだけ抑えるコツや物件の上手な選び方を紹介します。
東京の企業に無事就職が決まり、都会での一人暮らしに胸を膨らませる社会人も多いでしょう。
そこに立ちはだかる大きな壁が「家賃の高さ」です。
家賃は毎月支払わなければならない「固定費」です。
食費などのように工夫次第で節約できるものではありませんから、家賃はできるだけ抑えておくべきです。
この記事では、東京エリアに焦点を当てて、家賃相場や社会人一人暮らしの家賃相場、生活費シミュレーション、家賃や出費を抑えるコツなどを紹介しましょう。
社会人としてのスタートをよりよいものにするためにも、ぜひ参考にしてみてください。
東京都:社会人一人暮らしの家賃相場
社会人として東京で一人暮らしするためには、まず住居を決めなくてはなりません。
多くの会社が集まっている東京23区の家賃相場を知っておくと予算も決めやすいでしょう。
ここでは社会人が一人暮らしを始めるのに適した「ワンルーム」と「1K」に家賃相場を絞ってみました。
ワンルームは20~25平方メートルの広さで、仕切りがない部屋を指します。
玄関・キッチン・部屋がひとつになっており、生活動線がまとまって作られています。
仕切りがない分、床面積を最大限に使うことができます。
1Kは1部屋と独立したキッチンがある部屋です。
扉があるため料理の煙やにおいなどが部屋に広がらないというメリットがあります。
空間が2つに分離されるため、生活の切り分けができるようになります。
【東京23区のワンルームと1Kの家賃相場】
| 区名 | ワンルーム(万円) | 1K(万円) |
| 千代田区 | 12.3 | 11 |
| 中央区 | 12.2 | 10.3 |
| 港区 | 13 | 11.4 |
| 新宿区 | 8.5 | 11 |
| 文京区 | 8.7 | 9.8 |
| 台東区 | 9.7 | 10.4 |
| 墨田区 | 9.3 | 9 |
| 江東区 | 10 | 9.8 |
| 品川区 | 9.2 | 9.7 |
| 目黒区 | 8.5 | 9.8 |
| 大田区 | 7.3 | 8.3 |
| 世田谷区 | 6.9 | 8 |
| 渋谷区 | 9.8 | 10.5 |
| 中野区 | 7 | 8.6 |
| 杉並区 | 6.3 | 7.5 |
| 豊島区 | 6.6 | 8.4 |
| 北区 | 6.9 | 8.3 |
| 荒川区 | 6.8 | 8.2 |
| 板橋区 | 6.4 | 7.7 |
| 練馬区 | 6.1 | 7.2 |
| 足立区 | 6 | 6.6 |
| 葛飾区 | 6 | 6.9 |
| 江戸川区 | 5.8 | 6.5 |
※家賃相場はCHINTAIネット2024年01月11日現在のものを使用
\家賃相場を把握して、現実的なキャリア設計とESを!/
東京で社会人として一人暮らしを始めるには、エリアによって家賃が大きく異なる現実を理解することが大切です。
家賃は収入の3分の1が目安とされており、勤務地や生活費とのバランスを考えた選択が求められます。
そんな現実を踏まえた志望動機やキャリアプランが書けるかどうかは、ESの通過率にも直結します。
そこでおすすめなのが、実際に選考通過したエントリーシート20社分を収録した《通過ES集》!
今のうちから生活設計と自己分析をセットで考えることが、選考突破への近道になります。
社会人一人暮らしの家賃の目安
おおよその東京23区の家賃相場がわかったところで、どれくらいの家賃が払えるのでしょう。
一般的に「家賃は手取り収入額の3分の1程度にとどめる」と比較的余裕を持った生活ができるといわれています。
ここで注意したいのが「給料」と「手取り」の違いです。手取り収入額とは、給与の総額から所得税や社会保険料(健康保険・厚生年金)などの控除額を引いた後の実際に受け取れる金額を指します。
厚生労働省の「令和2年の賃金構造基本統計調査」では、大卒初任給は226,000円が平均となっています。
初任給とは、本採用後に支払われる所定内賃金月額のことで、住宅手当や家族手当など、入社した会社独自の固定的な手当は含まれますが、通勤手当、時間外手当は除かれます。
したがって、残業したことに対して支払われる時間外手当によって、月の手取り収入額は上下しますので、注意してください。
税金や社会保険料で約2割は持っていかれると仮定すると、初任給が226,000円の場合の手取り収入額は、
⇒手取り収入額=226,000円×0.8=180,800円
家賃の目安を手取り収入額の3分の1とすると、
⇒家賃の目安額=180,800円÷3=60,266円
となるわけです。
ただし、最近では家賃を4分の1程度に抑えている人も多いようです。給料が年々上昇していくという時代ではありません。
また物価の上昇も懸念されます。
家賃は、節約のできない固定費です。
社会人になって最初の家賃は、できるだけ抑えておくことが賢明といえるでしょう。
社会人一人暮らしの生活シミュレーション
毎月どのくらいの収入があって、どのくらいのお金が出ていっているのかを予め知っておくことは大切です。
家賃以外の社会人の一人暮らしの生活費には以下のようなものがあります。
社会人の一人暮らしにかかる生活費「食費」
食費は、人によって大きく変わってきます。
毎食外食やコンビニ弁当にしている人は当然食費の割合が大きくなります。
自炊をしている人は節約できます。
政府の統計によると平均で40,331円。
男性は44,466円で女性は36,729円となっています。
物価高のなか、外食を抑えて自炊をすることで大きく節約できる生活費といえるでしょう。
社会人の一人暮らしにかかる生活費「水道光熱費」
水道光熱費で大きくウエイトを占めるのが「冷暖房」と「入浴」です。社会人の一人暮らしの平均は11,400円となっています。
日中、仕事で会社にいることが多い社会人は、冷暖房の使用頻度は少ないかもしれません。
水道に関してはバスタブにお湯を張る頻度を少なくし、シャワーを使う場合にも流しっぱなしにしないことです。
社会人の一人暮らしにかかる生活費「通信費」
通信費は、携帯電話料金やWi-Fi料金、NHK受信料、動画配信サービス料などを合わせると、平均して10,000円程度かかります。
最も節約効果があるのは、携帯電話の契約会社を格安キャリアに変更することです。また、Wi-Fi利用料が家賃に含まれている物件もあります。
社会人の一人暮らしにかかる生活費「交際費・娯楽費」
社会人になれば、交際費も重要です。交際費・娯楽費の平均は15,000円程度が平均となっていますが、人によって大きく変動する生活費といえます。
飲み会などの頻度を減らすことで生活費を抑えることができます。
社会人の一人暮らしにかかる生活費「雑費」
日用品や雑費は、5,000円程度は確保しておきましょう。
ファッションや美容に関する雑費は、人によって大きく異なります。
女性の方が出費が多いかもしれません。
社会人一人暮らしの家賃を抑える5つのコツ
社会人として一人暮らしを始めるにあたって、まず毎月の固定費である家賃を抑えることが重要です。
家賃を安く抑えることで他の出費に回せることができ、少しでも貯金できる余裕も生まれるでしょう。
家賃を安く抑えるには、以下のようなコツがあります。
- オフシーズンを狙う
- 家賃が安いエリアを狙う
- 駅から遠い物件を狙う
- 条件や設備で家賃を抑える
- 物件選びの優先順位を付ける
1つずつ解説していきましょう
オフシーズンを狙う
家賃を抑える有効な方法としては、「賃貸のオフシーズンを狙う」ことです。
不動産会社の繁忙期は、1~3月と9~10月です。
この時期は、企業や学校などの新年度が始まる時期、人事異動が多い時期に当たります。
繁忙期は物件も多く選びやすい時期ですが、賃貸物件へのニーズが高まりますから、家賃の相場も高くなる傾向があります。
それ以外の時期、とくに夏場には繁忙期に比べて家賃相場が下がる傾向があります。
すべての賃貸物件の家賃が下がるわけではありません。
あまり人気がなく、繁忙期を過ぎても借り手が付かない場合、大家さんも空部屋にしておくわけにはいきません。
こうした賃貸物件は、不動産会社と値下げ交渉してみてもよいでしょう。また、繁忙期が過ぎた時期は、担当者も比較的落ち着いて相談に乗ってくれます。
早めに内定をもらった人は、シーズンオフに物件探しをすると相場よりも安い物件が見つかる可能性が高くなります
家賃が安いエリアを狙う
時期に関わらず確実に安い物件を見つける方法が、「家賃の安いエリアを狙う」です。
同じ間取りや広さの賃貸物件であっても、エリアによって大きく家賃相場が異なります。
たとえば、同じワンルームでも最高値の港区では13万円、最安値の江戸川区では5.8万円となっています。
港区よりも江戸川区エリアの賃貸物件を探せば実に半分の家賃で済むことが可能になります。
東京23区で社会人の一人暮らしの家賃として、相場が低いのは「練馬区」「足立区」「葛飾区」「江戸川区」です。
これらのエリアは下町の風情が残り、商店街なども充実しているので物価も安い傾向にあります。
通勤時間が許容範囲であれば、こうしたエリアの物件を探してみてはいかがでしょう。
- 駅から遠い物件を狙う
賃貸物件の特徴として、駅から遠い物件であればその分家賃が安くなります。
家賃を抑えるためあえて駅から遠い物件を狙ってみるのも手ひとつの方法です。
女性の場合は、防犯上の理由で駅から自宅までの間、商店街のある物件を選ぶと安心です。
また、自転車を使うなどすれば、駅から遠くてもそれほど苦になりません。
- 条件や設備で家賃を抑える
家賃を抑える4つ目のコツは、「条件や設備で家賃を抑える」です。
たとえば、下記のような物件は一般的に家賃が低いです。
- 築年数の長い物件
- 日当たりが悪い部屋
- 鉄筋より木造
- 風呂とトイレが同空間(ユニットバス)
- オートロックなし
- 冷暖房なし
など、設備条件のハードルを下げると家賃を低く抑えられます。
とはいえ、「快適性」は当然落ちますので、「どこまで妥協できて、ここからは絶対譲れない」という自分なりのボーダーラインを設けておくことが望ましいでしょう。
- 物件選びの優先順位を決める
賃貸物件を選ぶとき、優先順位を決めておくことも家賃を安くするコツのひとつです。
誰でも「駅近で、広くて、新しくて、設備の充実した部屋」が理想です。
しかし社会人の一人暮らしの家賃には制限があります。
物件を選ぶときには「これだけは譲れない」「ここは妥協できる」という優先順位をメモしたものを持参するとよいでしょう。
たとえば、
1位:駅から5分以内
2位:南向き
3位:2階以上
4位:スーパーが近い
5位:電車の乗り換え1回
このように優先順位をつけておけば「あれもこれも」と迷うことも少なく、気持ちに整理がつくため物件の最終決定に迷いがなくなります。
不動産会社の担当の人にとっても、優先順位を示すことによって、理想に近い物件を探しやすくなります。
\家賃の工夫もES対策も、“戦略的に動く力”が武器になる!/
社会人の一人暮らしでは、エリア選びや物件条件の工夫で家賃を抑えることが大切です。
駅からの距離や築年数、時期を見極めることで、固定費を賢くコントロールできます。
この「戦略的な選択力」は、実はエントリーシートでも重要な評価ポイント。
そんな就活生のために、実際に選考を通過した20社分のESと通過ポイントを解説した《通過ES集》を無料公開中!
“情報を分析し、行動に活かす力”を、今ここから身につけましょう。
何を優先に物件を選ぶ?こだわりポイントとは
優先順位をつけて物件選びをすることが家賃を抑えるコツです。
しかし、初めての一人暮らしの場合、その優先順位すらイメージできないというケースもあるでしょう。
そのようなときには、他の人の優先順位を参考にしてみましょう。
【日当たり】
健康のためにも日当たりは大切です。
日当たりが悪いと部屋がジメジメしてカビやダニなどの繁殖にもつながります。
日当たりがよいと洗濯物も乾きやすく、冬でも太陽の日差しで日中は暖房を使わなくても済みます。
【バス・トイレが別】
お風呂とトイレを別々にしたいというこだわりを持つ人も多いようです。
お風呂とトイレが一緒のユニットバスでは、お風呂を使ったあとに床がビショビショになってしまいます。
また、トイレが一緒になっていることで衛生面に不満を持つ人もいます。
【駅からの距離】
駅周辺には商店街も多く存在し、買い物にも便利です。
駅から近ければ通勤にも便利で、通勤時間の短縮にもなります。
また、防犯上も駅からの距離が近ければ安心できます。
当然駅から近い物件だと家賃も高くなります。利便性と家賃のバランスをよく考えて決めましょう。
【キッチン】
自炊をする人にとって、重要なポイントとなるのがキッチンです。
キッチンが広ければ、冷蔵庫や冷凍庫を設置することができます。
食器や食材も管理しやすいでしょう。
【セキュリティ】
都会での一人暮らしに防犯上の不安を覚えるという人も多くいます。
とくに女性はセキュリティに対して敏感です。
セキュリティの代表はオートロックです。
オートロック付きの物件であれば、集合ポストの郵便物を誰かに見られるという可能性も低くなります。
【騒音・治安】
周辺の環境も大切です。
メイン通り沿いの物件では、夜中に人の大声や車のエンジン音が響く可能性もあります。
木造アパートでは周囲の生活音が気になる可能性が高くなり、トラブルの原因になります。
【収納】
ファッションを楽しみたいという人は、大きなクローゼットはこだわりのポイントになるのではないでしょうか。
十分な収納スペースがない場合には、部屋が散乱して生活空間が狭くなってしまいます。
【築年数】
基本的に築年数が浅ければ浅いほど家賃は高くなります。
しかし、家賃が安いからといって古い物件を選んでしまうと、立て付けが悪く隙間風などが入ってしまうこともあります。
ただし古い築年数の物件でもしっかりリフォームがされているものも少なくありません。実際に見に行って状態を調べてみましょう。



ベストマッチ物件を探す方法
一人暮らしの社会人がどうやって物件を探したのか気になりませんか?
ニフティ不動産の「新社会人にきいた!家賃相場はどのくらい?
新社会人の一人暮らし事情」の記事では下記のようなアンケート結果が示されています。
- 不動産屋会社 42%
- インターネット 32%
- 就職した会社の紹介 16%
- 知人の紹介 5%
- インターネット検索後、不動産屋へ行った 5%
まず新卒の場合「会社が物件を探してくる、あるいは指定してくる」パターンと、「自分で探す」パターンに分かれます。
このデータによると不動産会社とインターネットが8割弱を占め、大勢を占めています。
今はインターネットで気軽に物件を探すことができます。
不動産情報サイトはこまめにチェックしておきましょう。
ただし、不動産情報サイトには掲載されていない非公開物件というものも存在しています。
この非公開物件は、実際に不動産会社に足を運ばなければ知ることができません。
よりよい賃貸物件を探すためには、担当者とコミュニケーションを密にして、要望に合った物件が出た場合にすぐに連絡してもらえるようにお願いしておくとよいでしょう。
ムダな出費を回避するための5か条
「収入ー出費=残額」です。収入は残業の多少で変化する場合がありますが、毎月大きく変わるものではありません。
また、毎年の昇給と言っても、新入社員の頃は微々たるものなので、あまり当てにできません。
そうなると、出費を抑えるしか、社会人の一人暮らしを継続することができません。
ただ、「欲望」は大きなエネルギーなので、「これを買いたい」「これを手に入れたい」と思うと、理性ではなかなかブレーキがかけにくいものです。
最後に、そんな厄介な欲望と対峙するために必要な5か条をお届けして、本記事を締めくくりたいと思います。
【ムダな出費を回避するための5か条】
第1条 その商品やサービスを購入するのに最低30日間、待ったか?
第2条 この買い物は借金にならないか?
第3条 「欲しい」ではなく、「必要か?」
第4条 他の投資よりリターンが高いか?
第5条 1年後にこの買い物を正しいと思えるか?



おわりに
本記事は、初めて東京で一人暮らしする社会人向けに家賃の相場や物件を探す際のポイントについて解説してきました。
生活費は節約することで出費を減らすことができますが、家賃は固定費ですから節約はできません。
初任給はすでに分かっているので、そこから手取り収入額を算段して、家賃を除く出費を差し引いた残高から家賃をいくらに設定すべきなのかを逆算して考えることが肝要です。
住まいは毎日帰る場所であり、仕事の疲れを癒す場でもあります。安易に決めてしまうと不満も募ってストレスがたまってしまいます。
そうならないためにも、自分なりの物件選びの優先順位を付けて、これだけは譲れないという「こだわりポイント」を明確にしておきましょう。
本記事があなたの物件選びのお役に立てば、幸いです。
今回も最後までお読みいただき、ありがとうございました。
引っ越しをして初めての一人暮らしをする方は、もろもろの費用や生活スタイルなど、心配事が絶えませんよね。本サイトではそんな不安を少しでもカバーすべく、新生活に役立つ記事を掲載しております。以下にいくつか例示しますので、ご興味があれば、ぜひご確認ください。
上京引越しにかかる費用と節約法を知って、しっかり準備しよう!
【就活中もしっかり遊びたい方へ】効率・節約重視!俺的オススメサービス7選
女性限定就活シェアハウスも!?選び方やおすすめサービスを紹介