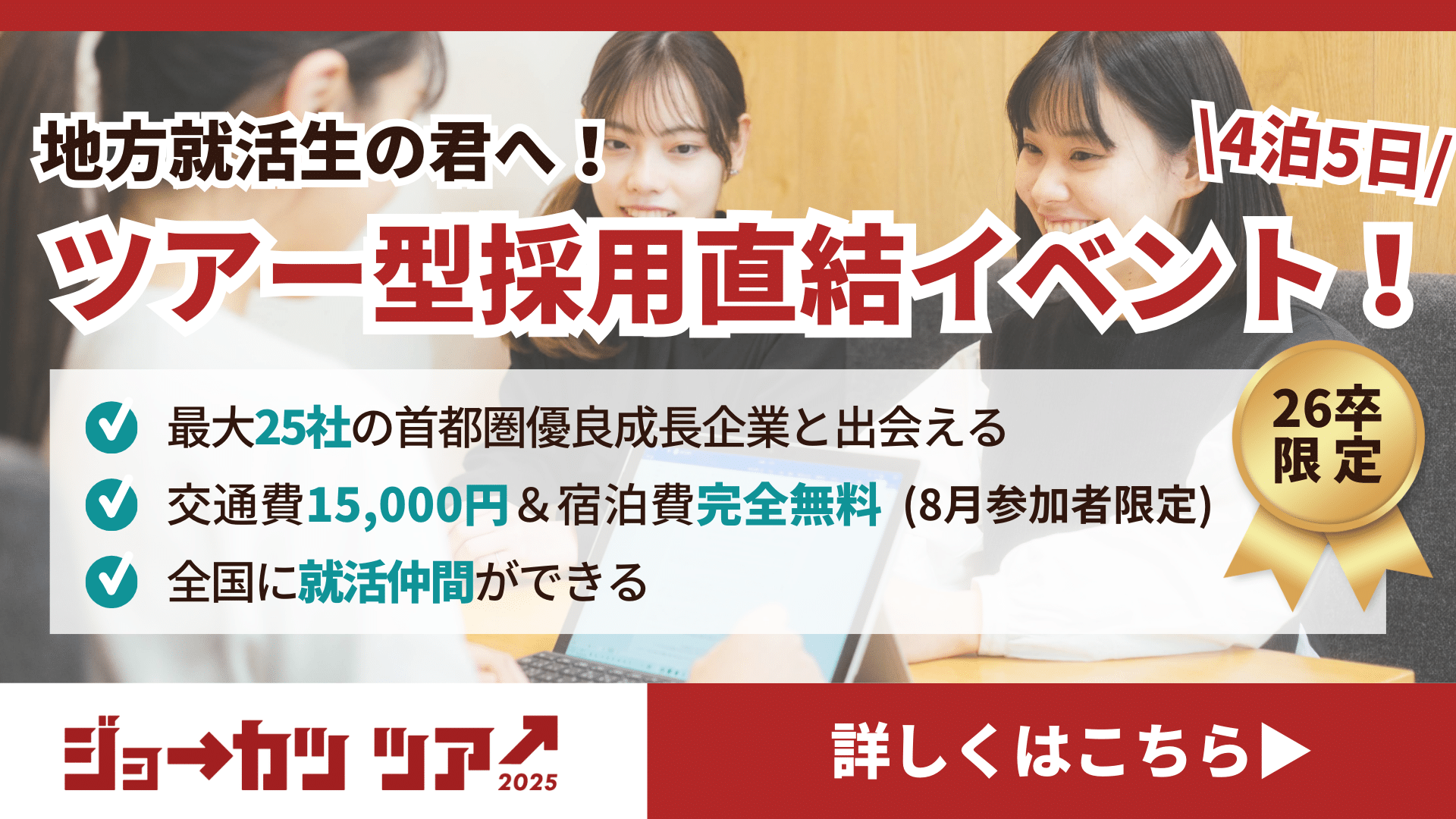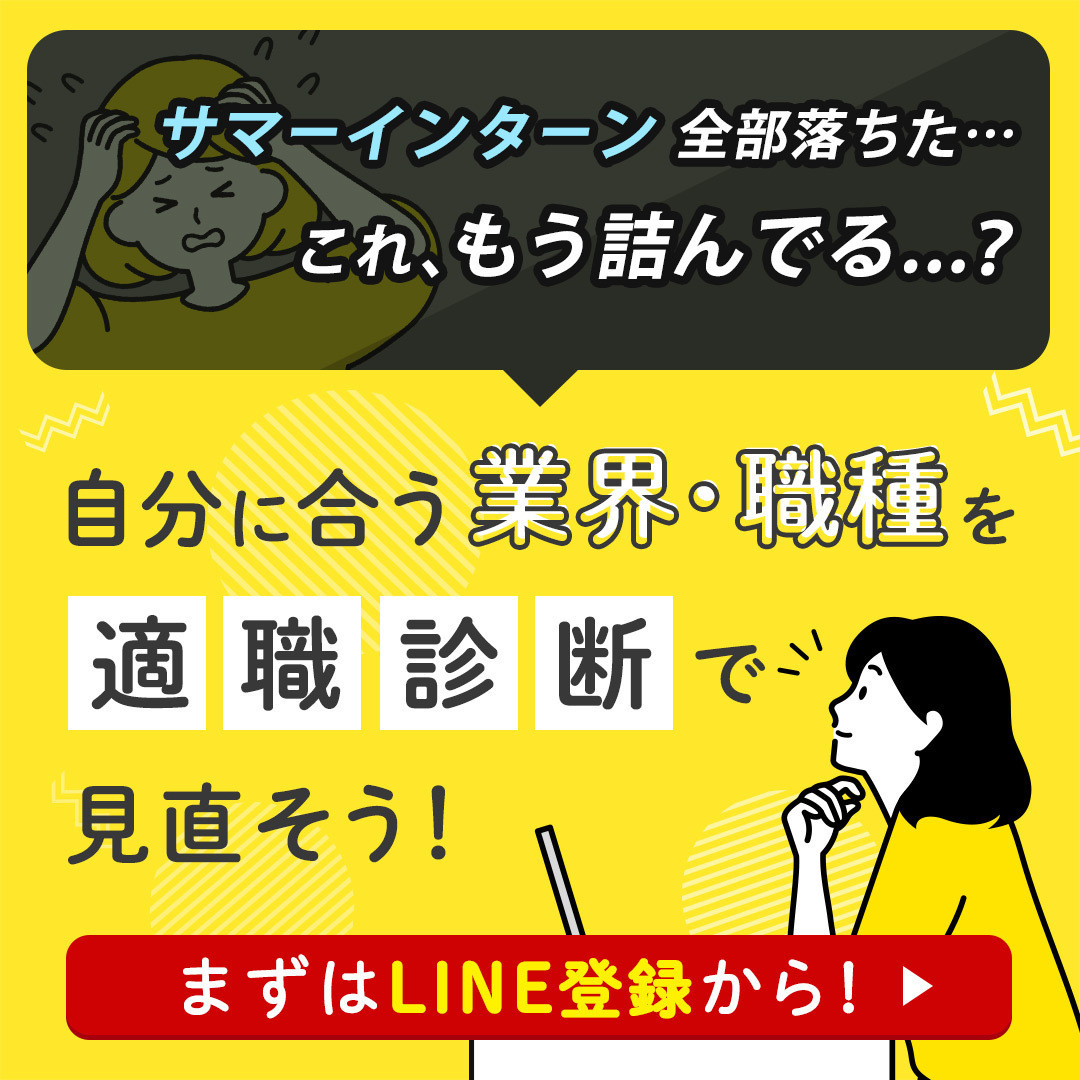【例文付き】大学で学んだことの見つけ方・伝え方を解説(面接・ES)
2025/2/1更新
はじめに
就活の面接やESで問われることの多い「大学で学んだこと」をどう表現すべきか、悩んでいる就活生も多いでしょう。
本記事では、大学で学んだことについて、人事が就職面接で聞く理由や伝えられる内容、伝えるポイントのほか、内容を考える流れ、についての説明となります。
また、理系や文系などの学部・分野別の例文・ポイントも合わせて参照ください。
本記事が対象は、以下のような方々に向けた内容です。
- 学んだことをどう活かすかについて考えたい方
- 面接やESで経験をどう表現するかを知りたい方
- 具体的な例文をみて伝え方の参考にしたい方
次の章より、なぜ大学で学んだことを企業が知りたいか、どのように伝えるかについて具体的に紹介しますので、ぜひ最後までお読みください。
【言語/非言語/英語完全網羅】SPI初心者でも対策できる資料配布中!
SPIなどに自信がない。
SPIが原因で選考に進められない。
そんな学生のためにまとめたものがSPI頻出問題集です。
SPIの出題範囲である言語/非言語/英語といった問題を完全網羅しています。
丁寧な解説付きなので、今から勉強する人でも安心して取り組めます!
企業が大学で学んだことを聞く理由
企業が就活生に「大学で学んだこと」を確認するのには、以下のような理由があります。
大学で学んだことから企業は何を確認する?
- 人間性を確認するため
- 能力を把握するため
- 業務に活かせるかを確認するため
それぞれ、具体的に内容を確認していきましょう。
人間性を確認するため
大学生活において「学び」は、本来最も優先されるべきものです。
そのため、優先度が高い学びとどのように向き合ってきたかを確認することで、人間性を確認しようとしています。
人間性と一言で言っても、2つの要素を確認しようとしています。
1つ目は、人柄です。
あるいは、性格とも言えます。
大学の授業や活動に対してどのようにとらえているか、大学での学びが自分自身の経験や知識にどのように落とし込まれているかについて、企業は興味があります。
真面目に講義に参加して、こまめな講義ノートを取れる人もいるでしょう。
ちょっと他人任せにしつつも、短期集中の勉強方法や、知り合いやサークルの仲間など人脈を駆使して課題を乗り越えたという人もいるでしょう。
どの側面を自己アピールに使うかは重要ですが、みなさんが課題に取り組む姿勢は、大学の学びも、社会人の仕事ぶりも基本は同じです。
2つ目は、自社とのマッチング具合です。
この要素は他の質問でも測っていますが、学びとの向き合い方も社風とのマッチングを測るひとつの指標になるでしょう。
マッチングは企業ごとに異なり、評価軸を知ることはできません。
もしかしたら、真面目に講義に出る人より、講義はサボり気味でも人脈を駆使して効率的に単位を獲得できる人のほうが「求めている人材」だと感じる会社もあるかもしれません。人間性を「良く見せよう」ではなく、「自分らしさ」に重点を置いたほうがよいといえます。
能力を把握するため
「学び」に関する質問を通じて、企業で働く上で必要な能力を確認している側面もあります。
大学で学んだ専攻が、そのまま希望する業界や会社の実務に直結しない場合も、新卒採用では多い事でしょう。
しかし、学業に真摯に取り組んでいれば、論理的思考力やコミュニケーション力が必然的に身に付いているはずです。
また、直接的に能力に結びつかないような質問に感じるからこそ、就活生の本音を垣間見ることができるでしょう。
学びの概要だけではなく、得た能力を交えて話す必要が伺えます。
業務に活かせるかを確認するため
「学び」は、モノによっては業務に直接活かすこともあります。
例えば、理系の「学び」の場合には分かりやすくイメージできるでしょう。
就職先や配属部署によるものの、研究室の研究がそのまま活かせるケースが多々あります。
また、文系の場合にも経営論やビジネス論など、実務に活用できる情報は決して少なくありません。
実際にどのような業務をするかは、就職し配属されるまでわからない場合も多く、あなたの考える「仕事」と「学び」の結びつきが正しくないケースもあります。
しかし、大事なのは「正解を知っている」ことよりも、自分で思考した結果こう成り立つのではないかと、考える力と伝え方です。
「大学で学んだこと」で伝えられる内容3選
「大学で学んだこと」を伝えられる、3つのポイントを解説します。
専攻している授業
大学で専攻している授業で得た知識は、分かりやすく伝えられる内容のひとつです。
専攻の授業内容やテーマを挙げて、どのような知識を得たかを説明しましょう。
その知識が社会やどのように役立てられるか、ビジネスでどのように実践に活かすかをアピールすることが重要なポイントです。
就職しようとする業界や業務が専攻と直接結びつかない場合は、いかに抽象化できるかがポイントになります。
どのような分野でも「人がどう動くか・どう動かしたか」「課題と解決のきっかけ」「その界隈の成功」などは、応用しやすい話題です。
自分の学びと業界研究を隅々まで点検し、どこかでつながるかを常日頃から考えていく必要があります。
ゼミや研究室
ゼミや研究室での活動は、専門的な学びを効果的にアピールできるテーマです。
研究テーマやプロジェクトに取り組んだ経験を具体的に説明し、その取り組みがどのように役立てられたか、チームに貢献できたかを伝えましょう。
大事なポイントは、専門用語をかみ砕いて論理的に説明し、専門外の面接官にも理解できるように説明することです。
実際のビジネスでは、専門的な内容を顧客に分かりやすく説明することが求められるため、簡潔かつ分かりやすく伝えることを心掛けることが重要です。
学内イベント
学内イベントに参加した経験も、学びの一部として伝える方法があります。
例えば、学園祭の運営やクラブ活動を牽引した経験は、リーダーシップや組織運営能力としてアピールが可能です。
学内イベントを通じて得た学びを、どのように仕事に活かせるかを具体的に伝えてください。
エピソードや心掛けていたことなどを具体的に説明することで、面接官に説得力あるアピールができるといえるでしょう。
こうした経験は、成功でも失敗でも構いません。
成功したというエピソードでは、成功に至った正しい分析ができている必要があります。
失敗のエピソードは、その失敗に対してどのような学びがあり、次につながるアイディアが求められます。
アピールの難易度としては、ポイントが明確な「失敗エピソード」のほうがわかりやすく、しかもインパクトも出しやすいです。
失敗したという赤裸々な話が苦手な人もいるかもしれませんが、そういったエピソードにこそ、あなたの本質が見えやすいといえるでしょう。
「大学で学んだこと」をES・面接で伝える3つのポイント
では、「大学で学んだこと」をESや面接で伝える3つのポイントについて説明していきます。
学んだことを端的に伝える
まず、学んだことを端的に伝えましょう。
もちろんどのように、なぜといった理由や興味を持ったきっかけを伝えることは大切ですが、はじめに結論となる学びを端的に伝えることが大切です。
イメージとしては、以下のような話の流れになります。
まずは結論を伝える:
「私は~~について学びました」
↓
実際にしたことと、得た結果を伝える:
「私は~~ということをして、~~という結果を得ました」
↓
具体例を示す:
「私は、具体的には~~~をしました」
↓
社会人としての学びの活かし方を伝える:
「私はこの学びを、~~~で活かしていきたいと考えています」
最後の学びの活かし方に関しては、必ず企業に入って活かせるという保証はありません。
しかし、自分自身の目線で考え、その理由を伝えることが大切なのです。
その論理の道筋が自然で納得のできる流れになっていれば、あなたの実力や人柄を伝えるのに十分なアピールとなります。
学びに興味を持った理由を伝える
ただ学んだことを伝えるのではなく、なぜその学びに興味を持ったのかを積極的に伝えることが大切です。
学びの起点となるのは、過去の経験やその人の人柄が現れていることが多いため、人事に自分自身の人柄を伝える手段として有効です。
自分がこれまでに何に興味を持ってきたか、それぞれのきっかけが何だったかを思い返すことで、あなた自身の自己分析も深まってくることでしょう。
また、きっかけとなる事象を通して、どのような場面でモチベーションを感じる人なのかを伝えることも可能です。
自分自身が何があれば興味を持つことができるのかなどが、伝わるエピソードトークを選んでみてはいかがでしょうか。
学びをどう活かすかを伝える
ただ学んだだけではなく、社会人としてどのように学びを活かそうと考えているのかもぜひ伝えましょう。
「自分の学びは専門性が高く、社会人としては活かすことができない…」と考える人がいるかもしれませんが、そんなことはありません。
学んだことが直接的に活かせる場合には、そのまま伝えるのが良いです。
しかし、直接的に活かせない場合には、学びを通じて得たことを伝えるのがおすすめです。
対人関係で学んだことや、学びを推し進めるとプロジェクト推進に近しい要素があることから、スケジュール管理なども伝えることができるかもしれません。
「学び」という言葉に縛られず、柔軟な発想で回答することが大切です。
例えば、どの様な学びにも、目標や成果があり、成功と失敗がうまれます。
どのような目標に向かって、そのためにどういう段取りを行ってきたか、それは振り返ってみて成功だったか失敗だったか。
成功なら、どういった要素や考慮が想定通りの効果を生み出したか、失敗なら、どう対処をすることで、適切な、またはより良い成果を生み出すことができたか。
このような考え方は社会では常に求められるので、その予行演習として自分の経験や行動を振り返ってみるのも良いでしょう。
「大学で学んだこと」の内容を考える方法・流れ【3ステップ】
ここでは、学びの内容を整理するための具体的な手順を3ステップで紹介します。
1.学んだことを一覧にする
はじめに、これまでに学んだことをリストアップします。
授業やゼミ、研究室の活動のほか、学内イベントなど、大学生活全般をもれなく一覧にすることで、気づきにくい学びも抽出しましょう。
例えば、「授業」「ゼミ」「研究室の活動」「学校イベント」を大分類とし、その分類に属する項目を中分類として整理し、一覧表を作成してみてください。
2.視点別に学習内容を分類する
一覧を作成したら、学んだ内容を異なる視点で分類してみましょう。
それぞれの項目に対して、「専門知識」「経験・体験」「人間関係の学び」などに分けることで、どの学びが志望企業にアピールできるかが見えてきます。
この視点を「1.学んだことを一覧にする」で作成した一覧表の小分類として整理し、ひとつの表にまとめることもおすすめです。
ただし、この分類分けはこだわるとキリがなく、広げ過ぎると収拾がつかなくなってしまう場合もあります。
一つの例としては分類軸を2種類(マトリックス)にして配置してみる方法があります。
「専門知識」の高低と、「人間関係の学び」の高低を示す4つの枠のあるマトリクスを作り、1で抽出した学びがどこに配置するかを考えてみる方法です。
こうして、自分の学びの分類を整理していきましょう。
3.志望企業や職種にマッチした内容を選定する
最後に、志望する企業や職種に適した学びを選びます。
そのためには、志望企業の事業内容や志望職種を理解し、その企業が求めるスキルや価値観にマッチする学びを選ぶことが重要です。
必ずしも、これまでの知識や経験が完全に合致していなくても、基本的には問題ありません。
どのように知識を応用して活かすか、あるいはこれまで得た知識をベースに、どのように知識をつけていくかなど、自分の考えを説明できることが重要です。
これをこなすためには、志望企業の企業情報サイト、採用ページや就活サイトの紹介内容、企業地図や業界解説の書籍などを用いて、積極的に情報収集しましょう。
上場企業であれば、IR資料、特に有価証券報告書をみると、詳しい企業状況や現状の課題点などが明確に記載されています。
【文系・理系・分野別】「大学で学んだこと」の説明内容と例文・トーク例を紹介

ここでは、大学で学んだことの例文・トーク例を文系・理系、分野別にポイントとともに解説します。
例1:【文系】経営学部
経営学部の学生は、企業経営やマーケティング、財務管理など、経営全般に関する知識をアピールすることが重要です。
たとえば、ケーススタディを通じて得た分析力や戦略策定能力をどのように活かせるかなど、具体的に説明することが効果的です。
志望企業を分析した結果などを説明することで、志望度の高さをアピールすることもできます。
【経営学部の例文・トーク例】
私は、経営学部でマーケティング戦略の授業を通じて、実際の商店街を対象にした経営改善プロジェクトに取り組みました。
過去の売り上げ分析や商店街の集客力やスーパーなどの競合分析、他の商店街の成功事例分析など、商店街の市場調査やデータ分析を行いました。
そして、このデータ分析から、商店街の課題抽出や戦略の方向性を検討し、経営改善の具体策を提案することができました。
この経験で得たスキルは、分析に基づく意思決定の重要性と、戦略的なマーケティングの実践力です。
今後は、貴社の成長戦略に貢献できるよう、これらのスキルを活かしていきたいと考えています。
例2:【文系】経済学部
経済学部の学生は、マクロ経済学やミクロ経済学の知識をどのようにビジネスに活かせるかを伝えると効果的です。
たとえば、経済学の理論を用いて、地域の経済発展について分析したことなど、理論をどのようにビジネスに活かしたかを具体的に説明することも有効でしょう。
【経済学部の例文・トーク例】
私は、経済学部で、日本の少子高齢化が経済に与える影響について研究してきました。
この研究において、〇〇のモデルを用い、有効な項目を選定のうえで、消費動向や労働市場への影響を予測し、これを基に、プロジェクトとして政策案を策定しました。
こうした経験を通じて、理論に基づく分析力や社会経済問題に対する洞察力を養うことができました。
今後は、貴社でこの分析力を活かし、経営戦略や市場予測など、経済分野で貢献したいと考えています。
例3:【文系】法学部
法学部の学生は、法律の知識や法的思考力を強調することがポイントです。
具体的なケーススタディや法的分析を行った経験をベースに、その過程で習得した論理的思考力や問題解決能力をアピールすると良いでしょう。
例えば、直近で報道されている出来事について、過去の判例や大学で学んだ知識を活かした所見を伝えるなどの受け答えも効果がありそうです。
【法学部の例文・トーク例】
私は、法学部で契約法の学習に力を入れてきました。
授業では、契約の有効性や解除に関するケーススタディを行い、ビジネス上起きうるリスクを考慮し、取引上、有効な契約のあり方や進め方など、法的なプロセスを理解することができました。
もともとマニュアルなどの、規約を整然とまとめた文書を読み込むことが得意で、大学生活の中でも他の人の推敲を手伝うことや、アドバイスすることを得意としていました。
今後は、企業の契約業務や法務部門でこれらのスキルをベースに、さらなる理解を深めていき、貴社の法務戦略に役立てられるよう貢献したいと考えています。
例4:【理系】情報学部
情報学部の学生は、プログラミングやデータ解析のスキルを中心に話すと良いでしょう。
特に、大学でアプリケーションを開発した経験を目的から開発経緯まで説明し、その技術力がどのように志望企業に貢献できるかを具体的に伝えます。
AI技術など、革新的に進化しているIT技術に、どのように向き合っているかなどを訴求することも重要です。
【情報学部の例文・トーク例】
私は大学でエンジニアリングや機械学習を学びました。
大学では広範な技術を学び、異なる領域の人々とのコミュニケーション力を養いましたが、さらに高い専門性と学びの実践ができる環境を求め、インターンにも参加しました。
インターンでは、開発者とユーザーの視点を整理する重要性を学び、一方で、技術の進歩に対応するための継続的な学習の大切さも実感しました。
今後も、経営環境の変化や技術革新に対応できるように学び続け、貴社に貢献したいと考えています。
例5:【理系】工学部
工学部の学生は、実験や設計に関する学びを伝えることが重要になります。
たとえば、ある機械の設計プロジェクトに参加し、その過程で得たチームワークや問題解決に寄与した経験を伝えてみましょう。
工学分野で必要な能力やマインドをアピールできます。
【工学部の例文・トーク例】
私は、工学部での研究プロジェクトにおいて、エネルギー効率を向上させる新しい機械設計に取り組みました。
このプロジェクトの主な成果は、複数の素材を組み合わせた構造を設計し、エネルギー効率を20%向上させたことです。
このプロジェクトでは、多角的な分析の下、試行錯誤を経てチームと協力しながら、課題を解決する力を養うことができました。
貴社に入社しこの分析力と協働力を活かし、世の中に役立つ革新的な製品を生み出すことに貢献したいと考えています。
例6:【その他】学内イベント
学内イベントでの経験も、価値ある学びとして伝えることが可能です。
たとえば、学園祭の実行委員を通じて得たリーダーシップや運営のスキルなどは、組織運営スキルをアピールできる材料になります。
企業には、必ず組織がありますので、チームワークを発揮する組織運営能力は評価される重要な項目のひとつです。
【学内イベントの例文・トーク例】
私は学校祭実行委員の活動を通して、主体性の重要性を学びました。
メンバーのモチベーションにばらつきがあるなか、私が行ったのは、各メンバーの得意分野をヒアリングし、活動への貢献の意義を伝えて共通認識を明確にするよう導いたことです。
それによりメンバーが個性を活かし、それぞれが主体性を持って行動することで対応の柔軟性と課題解決の素早さが評価された体制となりました。
こうした主体性が周囲のやる気を引き出し、自分自身も積極的に行動する重要性を実感しました。
「大学で学んだこと」が分からない場合にすべきポイント3点
「大学で学んだこと」が分からない場合に有効な3つの方法をご紹介します。
これまでの学びについて整理する
まず行うべきは、これまでの学びを整理することです。
授業などで得た学びについてはシラバスをもう一度読み返してみましょう。
それ以外の学びについては、大学に入ってから取り組んだことを時系列で洗い出してみるのがおすすめです。
できる限り細かな内容も洗い出すことで、自分が忘れていた「学び」に気付けるかもしれません。
専門性が高い学びを抽出する
学びの中で、最も専門性を持てたことから考えてみるのもおすすめです。
研究などを深くしていなかったとしても、自分にとって活き活きと語ることができる学びであれば、そのことを題材にするのもおすすめです。
学びの深さは大事ですが、自分自身が伝えたいと思うことでなければ意味がありません。
自分の気持ちに正直に、学びを抽出するのもおすすめです。
もしそれも少し難しい場合は、そもそもその学びを選んだ最初のきっかけを思い出してみましょう。
印象深かった授業を中心にトークを展開する
これまでの授業の中で、最も印象深い授業は何でしょうか?
そのことや、授業内での生徒や先生とのエピソードを学びとして話すのもひとつの方法です。
プロジェクト型の授業やゼミなど、周囲との関わりが求められる授業では学びが得やすいほか、言語や一般教養の授業などでも面白さを感じることがあるでしょう。
必ずしも自分の専門領域と一貫していなくてもかまいません。
理由が明確にあるのであれば、自分が真っ先に思い出すことができる内容を選ぶのが手です。
さいごに
本記事では、大学で学んだことについて、人事が就職面接で聞く理由や伝えられる内容、伝えるポイントのほか、内容を考える流れ、理系や文系などの学部・分野別の例文・ポイントを解説しました。
「大学で学んだこと」を面接やESで効果的に伝えるには、今まで学んだことを整理し、企業にマッチした内容を訴求することが重要です。
本記事を参考に、自身の学んだことを棚卸のうえ、自身が志望企業にどう貢献できるかを明確化し、「大学で学んだこと」を効果的にアピールしてください。
次の記事では、学生時代に力を入れたことについて詳しく解説していますので、併せて参考にしてください。
4泊5日の上京就活を応援!満員御礼の就活イベントを今年も開催!
宿泊費完全無料、東京までの交通費補助で負担を減らせます!
最大25社の優良成長企業と就活仲間に出会えるので、今から就活する学生は必見です!
首都圏の学生ならスタキャリ!
理想のキャリアを実現へと導く第一歩!
あなたにピッタリのキャリアアドバイザーを選び、
自分にマッチする優良企業をご紹介
首都圏企業のES添削から面接対策まで、就活ならスタキャリ