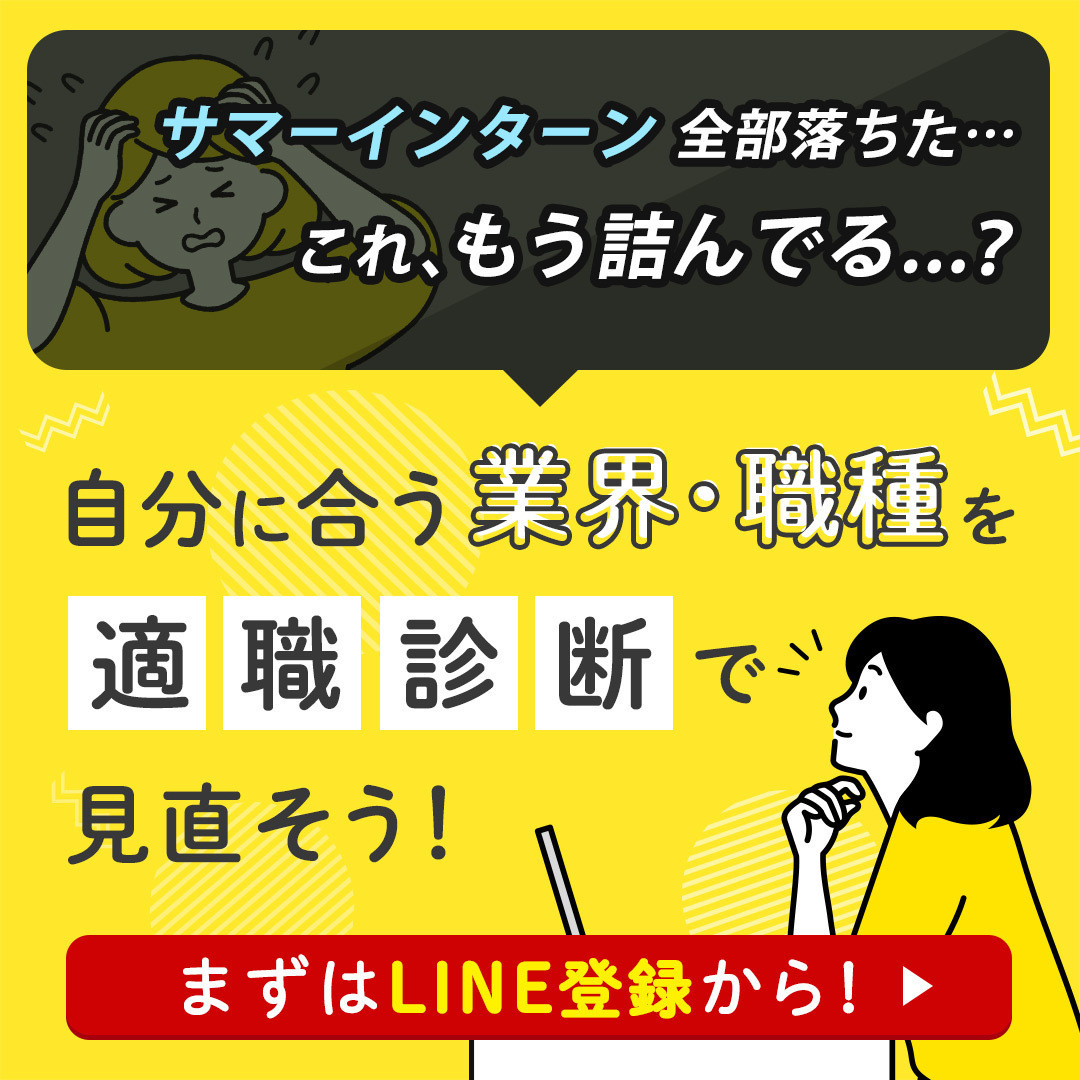【営業マン向け】面接対策を時期ごとに解説します!
2024/9/24更新
はじめに
就活において、面接は重要な選考フローです。
特に、営業を志望している場合は、人柄やコミュニケーション能力が重要になってくるため、面接のウエイトは他の職種よりも重いでしょう。
本記事では、以下のような営業マンを目指す就活生を対象に、面接対策を解説します。
- 営業職を目指している就活生
- 面接対策を期間ごとに把握したい就活生
- 面接官に人柄をアピールしたいと考えている就活生
期間ごとに解説するため、初めて面接対策をする就活生でも、簡単に取り組めるでしょう。
さらに、営業職に向いている人の特徴もまとめていますので、営業マン向けに面接対策をチューンアップしたい方は、ぜひ最後までご覧ください。
また、面接の必勝法については下の記事でも紹介していますので、興味があればこちらも合わせて読んでみてください!
上京を志す地方学生ならジョーカツ!
あなたのキャリアを加速させるチャンス!
無料で利用できる快適な個室シェアハウス、
東京までの交通費サポート付き
首都圏の注目企業への就活ならジョーカツ
首都圏の学生ならスタキャリ!
理想のキャリアを実現へと導く第一歩!
あなたにピッタリのキャリアアドバイザーを選び、
自分にマッチする優良企業をご紹介
首都圏企業のES添削から面接対策まで、就活ならスタキャリ
初期:面接までたっぷり時間がある時期

まずは就活の初期段階、面接までの時間がある状況での対策を解説します。
以下の3つのポイントをおさえて、内定獲得に向けた早めの対策を行いましょう。
まずは『全体像の把握』を行う
面接対策をするうえで、まず最初に行うことは「全体像の把握」です。
と言っても、明確なイメージを持ちにくい方もいるかと思いますので、学校の定期試験を例にとって考えてみましょう。
例えば、大学であまり興味がない授業を受講していたとします。
あまり興味がない授業の定期試験が3日後に迫ってきた時、まず最初に「最終的に何を、どのレベルで仕上げないといけないか」を分析する必要があります。
分析する方法としては、講座の過去問を他の人から入手したり、授業の口コミ情報を集めるなど色々な方法が挙げられるでしょう。
上記の流れを就活に置き換えてみると、「最終的に何を、どのレベルで仕上げないといけないか」ということは、「どこを目指し、そのために何を身につけておかないといけないのか」ということに置き換えられます。
上記の言葉をもっとシンプルなものにすると、「夢を見つけましょう、そのために何が必要か考えましょう」とも言えるでしょう。
面接対策において、ゴールから逆算し、今何が必要なのかを考える思考法は重要です。
例えば、「夢」の達成のために就職を目指す場合を、逆算してみると、下記のようになります。
「夢」の達成のための就職
- ゴール:「夢」の達成
- 「夢」の達成に必要なこと:「就職試験への合格」
- 「就職試験への合格」のために必要なこと:「筆記で合格、面接で合格」(理系職、専門職は除く)
上記のステップにおける「就職試験への合格」のために必要なことが、「どうすれば「面接で合格」できるのか という「面接対策」であり、多くの就活生を悩ませる行程であると言えるでしょう。
「どうすれば面接で合格できるのか」の部分は、ゴールを達成するための第一歩ですから、しっかりと準備する必要があります。
そのため、就職活動を成功するためには、「面接対策」の部分に時間をかける必要があると言えるでしょう。
手持ちの武器を強化!面接に向けた武装
ゴール達成のためには、まず第一歩として面接対策をしっかりとし、きちんと「武装」することが大切です。
この時に意識したいのは、「どの会社にも使える、または対応できること」と、「広く浅く、汎用性のある面接対策にすること」です。
なぜ、この時期の面接対策は「広く浅く」でないといけないのか?
上記の疑問をスポーツを例に挙げて解説します。
例えば、あるスポーツで世界大会を目指すことにした人がいたとします。
この人は、どのスポーツで世界を目指すのか、まだ決めていません。
そのため、世界を目指すための手段が野球かもしれないし、サッカーかもしれない状態であると言えるでしょう。
ただ、まだ思考が定まっていない状態でとりあえずバットの素振りを始めてみたとしても、あとになって「やぱりサッカーで世界を目指したい!」と考えが変わる可能性も、十分にあるわけです。
となると、せっかく長い時間バットの素振りを一生懸命やっていたとしても、その時間が無駄になってしまいます。
つまり、まだ思考が定まりきっていない状態では、どのスポーツにするか絞って練習するべきではありません。
この時期に注力すべきなのは、どのスポーツをやるにしても必要となってくる「基礎体力」を作ることなのです。
就活、ひいては面接対策にしても、全く同じことが言えます。
まだ面接本番までたっぷりと時間があるのに、第一希望の1社、あるいは専門的な業界にだけ通用する面接の練習だけしてしまう行為はリスクが高いです。
なぜなら、希望の業界が変わった場合、あるいはそこにもし落ちてしまった場合、また最初からやり直さなくてはならないからです。
ですので、準備できる時間がたっぷりとあるこの時期には、どの業界にも通用する基礎的な面接スキルを身につけることが大事になります。
自己分析を極める
それでは、広く浅い、汎用性の高い面接対策とは、一体何をすればよいのでしょうか?
答えは、「自分のことを話せるようになる」ことです。
「自己紹介をしてください」など面接でよく聞かれる自己PRは、どこの会社でも必須事項です。
加えて、志望動機でさえも、自分のことを分かっていないと書きづらい傾向があります。
つまり、自分のことを話せるようになることが、面接において基本となってくるのです。
そして、「自分のことを話せるようになる」ためには、逆算して考えると自己分析が必要になってきます。
やり方はシンプルです。
以下の3ステップを、ひたすら突き詰めて考えていきましょう。
ステップ
- 自分は○○になりたい
- なんでなりたいんだろう
- なってどうするんだろう
これを繰り返していくと、本当に自分の目標が○○なのかとか考える場になります。
また、自身の深掘りができているので、面接で想定外の質問がきたとしても自然と答えられるようになるでしょう。
「自己分析をしなさい」と言われることは多いと思いますし、いい加減聞き飽きた方もいるかもしれません。
ただ『自分のことを話せるようになる』には自己分析が必要不可欠です。
自己分析を通して、自分の夢の再確認&具体化、さらには質問対策能力を身につけることで、どの企業にも通用する基礎能力を向上させることが可能です。
(自己分析の大切さについては、こちらの記事でも紹介されています。)
中期:「ホットリーディング」で面接相手の情報を調べる

納得のいくまで自己分析ができたら、次に必要なのは「ホットリーディング」です。
「ホットリーディング」とは、相手のことを事前にしっかりと調べておき、よく理解しておくことです。
ホットリーディングをすることで、下記のようにさまざまなメリットが得られます。
- 面接相手への質問が自然と浮かんでくる
- より説得力のある志望動機が作れるようになる
面接という試合に臨む前に、相手のことが少しでもわかっておくと、具体的な対策が練りやすくなります。
面接に臨む前に、面接相手のことを徹底的に調べ上げましょう。
特に、相手企業がベンチャーである場合や、企業風土がオープンな企業であると、このホットリーディングはかなり有効です。
というのも、自分の面接を担当する可能性のある社員の情報や、興味のある情報がFacebookやX(旧:Twitter)で推測できるため、面接中に聞かれる可能性のある質問も、ある程度予測することが可能だからです。
つまり、どれだけ成功率の高い面接ができるかというのは、ホットリーディングの精度の高さが肝になってくるのです。
直前期:いよいよ面接本番!

「自己分析」で自分を理解、そして「ホットリーディング」で相手を理解したら、続いて「ファーストインプレッション」を良くし、「オープナー」を意識して面接に臨みましょう。
この2つの組み合わせは、 面接開始前〜開始1分以内に効果をもたらします。
「ファーストインプレッション」を良くしよう
「ファーストインプレッション」とは第一印象のことです。
アメリカの心理学者、アルバート・メラビアンが提唱した「メラビアンの法則」によると、人間は初めて会った人間に対して抱く印象は、会ってからわずか3〜5秒で決まると言われています。
つまり、相手が自分へ抱く印象は、その大半を視覚情報のみに依存している、ということになります。
上記の法則は面接にも活用でき、、面接で大切なのは「面接官と顔を合わせてからの3〜5秒」ということが言えるでしょう。
最初に面接官の目に映るのは、就活生であるあなたの 「身だしなみ」 です。
面接官にとってだらしない印象とならないよう、以下の項目に注意して、身なりをきちんと整えましょう。
- シャツにしわはついていませんか?
- ネクタイは印象の良いものを用意できていますか?
- 匂いは気になりませんか?
- 革靴は色が剥げていませんか?
- 肌荒れは許容できるレベルですか?
- 爪は清潔ですか?
- 髪に清潔感はありますか?
- さかむけのケアは万全ですか?
- 姿勢は背筋が伸び、胸を張っていますか?
私が就活していた時は、上記に記載した項目よりもっとたくさんのことに注意を払っており、「毎回最高コンディション」 を作り上げていました。
ちょっと気をつけるだけでも、印象を良くすることが出来るのですから、やらないと損です。
意識がけを習慣化するようにしましょう。
初対面での会話が鍵「オープナー」戦略
「オープナー」とは、相手と交わす初めての会話のことで、視覚情報と並んでとても重要です。
例え第一印象が良くても、声が小さすぎて何を言っているか聞こえなかったり、モゴモゴと何を言っているか聞き取れなかったら、印象が悪くなってしまいます。
初対面の友達と話しているのではなく、相手は面接官であるため、こちら側が何をどのように話すのかを、シビアに観察しています。
就活面接である以上、会話のトピックは限られてしまいますが、少しでも「笑顔で」「ハキハキと」話すように心がけましょう。
自分のセールスポイントをどう置くかによっても変わりますので、この2つが逆効果になってしまうケースもあるかもしれません。
ですが、おそらく基本的に、この2つを意識することで最初のハードルはクリアするはずです。
企業の多くは、チームワークを大切にしているため、気持ちよく相手と接することができる人材を欲しています。
なので、少しでも入社後のチームワークを良くする人材であることをアピールするためにも、最初の挨拶から好印象を残しましょう。
営業職に向いている人の特徴とは?
営業職に向いている人の特徴は以下の通りです。
- コミュニケーション能力が高い
- 聞き上手である
- ポジティブな姿勢
- 自発的に行動できる
- 人間関係を築くのが得意
- 結果志向である
- ストレス耐性がある
上記の特徴を面接対策に取り入れることで、営業職の面接対策をより効果的に行えるでしょう。
ここでは、各項目ごとに営業職に向いている人の特徴を解説しますので、営業職を志望している就活生はぜひ参考にしてみてください。
コミュニケーション能力が高い
営業職の本質は「人と関わる仕事」です。
そのため、自社の商品やサービスの価値を的確に伝え、相手に理解させる説明力や、相手の話を引き出しながら効果的なコミュニケーションを取れる対話力を、面接時にチェックされることも少なくありません。
面接対策時には、論理的な話の構成や、相手の話を聞く姿勢などに気を配りましょう。
聞き上手である
優れた営業は、顧客の本音を引き出すために、顧客の心を開くための質問力も重要です。
加えて、最適な提案をするためには、相手が何を必要としているか、どのような課題を抱えているかを丁寧に聞き出すことが必要になります。
そのため、面接時にはうまく話すことばかり意識するのではなく、きちんと聞き上手である立ち回りを意識しましょう。
ポジティブな姿勢
営業は多くの失敗や拒絶に直面することがあるため、失敗を糧にし、次の成功につなげられる前向きな姿勢を持つ人が求められます。
また、問題に直面したときにそれを克服するための工夫や努力ができることも、営業の成功に直結するため、問題解決への意欲をアピールすることも効果的です。
自発的に行動できる
営業は成果が数値として求められる職種であり、常に新しい取引先や顧客との関係構築が必要です。
そのため、目標に向かって自ら計画を立て、行動する「自己管理能力」や上司からの指示を待つのではなく、自発的に行動し、新しいチャンスをつかむことができる「目標志向の行動」が求められます。
人間関係を築くのが得意
営業は信頼関係を構築し、長期的に維持することが求められます。
特にBtoBの営業では、顧客と継続的にやり取りをし、信頼される存在になることが重要です。
信頼される存在になるためには、ごまかしたり、無理に売り込んだりするのではなく、相手にとっての利益を第一に考える「誠実さ」が大切です。
質問には正直に答えるなど、誠実な行動を心がけましょう。
結果志向である
営業は成果が明確に数値化される職種です。
売上や契約数といった目標を達成するために、常に結果にこだわる姿勢が重要です。
そのためには、目標を達成するために、どうアプローチするかの戦略を立てる「戦略的思考」が求められます。
面接でエピソードを話す際には、具体的な数値を元に行動をしたなど、戦略的思考に関する行動を加えましょう。
ストレス耐性がある
営業はプレッシャーやストレスが多い職種です。
ノルマや顧客からのクレームなど、精神的な負荷に耐えられる力が求められます。
そのため、エントリーシートや面接では、失敗や拒絶を経験してもすぐに気持ちを切り替え、次の機会に集中できる人柄であることをアピールすることが効果的です。
さいごに
この記事では、営業マン向けの面接対策を解説しました。
効果的な面接対策を講じるためには、時期ごとに適切な対策を講じる必要があります。
しっかりと時間を確保したうえで、論理的に面接対策をすることによって、多くの企業から内定を獲得できるようになるでしょう。
また、営業職に求められる人材の傾向をつかむことも、面接対策として効果的です。
この記事を参考に、営業職になるための計画を立ててみてはいかがでしょうか。