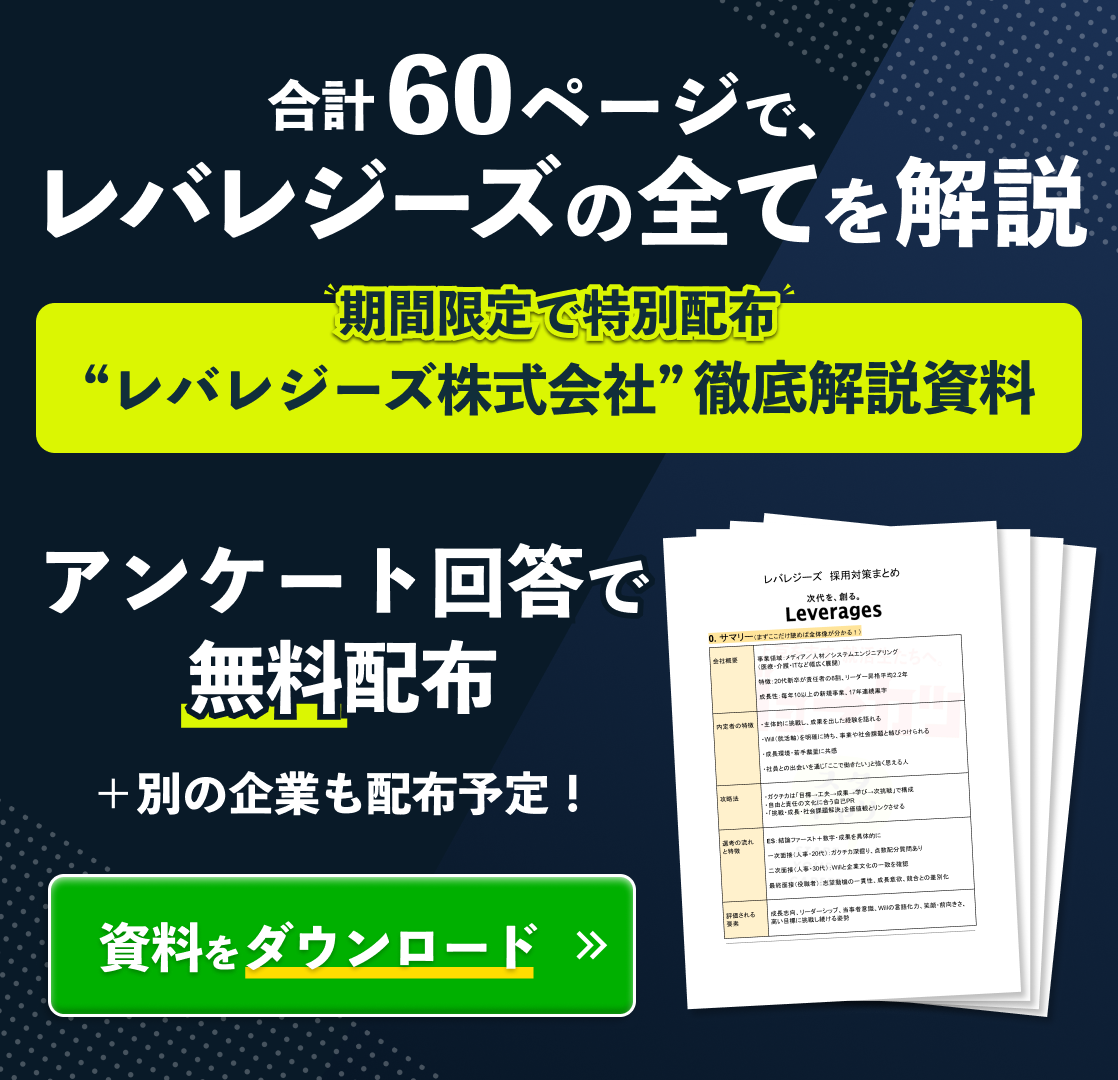Webテストのカンニングは危険!?バレる可能性はあるのかリスクを紹介
2024年1月25日更新
はじめに
ペーパーテストと違いWebテストならカンニングがバレないと思っている就活生は多いのではないでしょうか。
もちろんWebテストであってもカンニングがバレるケースが多いです。
この記事では「Webテストのカンニング」についてわかりやすく解説しています。
- Webテストのカンニングはバレるの?
- Webテストでカンニングしたときにリスクはあるの?
- なぜカンニングをしたとバレるのか?
といった上記のような疑問を抱く就活生を対象に有益な情報をまとめていますので、ぜひ参考にしてください。
また、業界一覧については、以下の記事で概観しているので、ぜひご覧ください。
上京を志す地方学生ならジョーカツ!
あなたのキャリアを加速させるチャンス!
無料で利用できる快適な個室シェアハウス、
東京までの交通費サポート付き
首都圏の注目企業への就活ならジョーカツ
首都圏の学生ならスタキャリ!
理想のキャリアを実現へと導く第一歩!
あなたにピッタリのキャリアアドバイザーを選び、
自分にマッチする優良企業をご紹介
首都圏企業のES添削から面接対策まで、就活ならスタキャリ
Webテストにおけるカンニング方法
Webテストのカンニングに当てはまる行動は次の3つのことをいいます。Webテストであってもカンニングはバレるため次の3つの行動はしてはいけません。
インターネットで検索しながら解答する
Webテストはインターネットで行うため、テスト画面を開きながら別のWebページを開くことができます。
そのため、解答を検索しながらテストを受けることも可能です。
家で受験する場合は、近くに採用担当者がいないため同じパソコンを使用しなくても、別のタブレットを用意し検索しながらWebテストを受けることできます。
企業が指定した会場でWebテストを行う場合は、採用担当者が定期的に試験会場を徘徊しているため、インターネットで検索しながら解答することは非常に困難でしょう。
もちろんインターネットでなくても、参考書やカンニングペーパーを見ながら解答するのもカンニングです。
代行者に解いてもらう
企業は指定した会場でWebテストを行う場合、この方法でカンニングすることはできません。
自宅受験では、別の人にテストを受けてもらうことが可能です。
一般的なWebテストは受検者の顔を確認できないため、別の人がテストを受けることができます。
Zoomなどを利用して顔を確認しながらWebテストを行う場合は、替え玉方式で受けることができません。
複数人で協力しながら解く
替え玉方式のカンニング行為と似ていますが、複数人で協力してテストを受けるのもカンニング行為です。
Zoomやビデオ電話などを利用して、複数人で答えを共有しながらテストを受けることもできます。
テストは一人で受検するものなので、このような行為も行わないようにしましょう。
Webテストでカンニングした場合のリスク

カンニング行為がバレた場合、それ相応の処罰を受けることになります。
内定が取り消しになる
Webテストでカンニングがバレた場合、内定が取り消しになることが多いです。
不正行為を行った人を入社させることは、企業にとってもリスクになります。
Webテストで不正行為を行うということは、入社した後に、社内でも不正行為を行う可能性が高いです。
そのようなリスクを背負ってまで、その就活生を入社させる必要はないため、Webテストでカンニングをした場合、内定取り消しになります。
もちろん選考途中でカンニングが発覚した場合でも、その選考を継続することはできません。
ブラックリストに入る
Webテストでカンニングがバレた場合、ブラックリストに登録させるケースもあります。
ブラックリストに登録された場合、その企業に再度挑戦することはできません。
またその企業の子会社や関連会社にも情報が伝わるため、就職することはできないでしょう。
業界というものは広く見えて意外と狭いこともあり、同じ業界内の企業と情報を共有していることもあります。
そのため、場合によっては不正を行った企業の同業界にも情報が行きわたり、断られる可能性もあります。
一度に多くの企業の選考資格を失ってしまうため、カンニングした場合のリスクは大きいです。
カンニングがバレた場合、自分だけでなく他者にも迷惑をかけるケースもあります。
たとえば、自分の名前がブラックリストに登録されるだけでなく、自分の在籍している大学もブラックリストに登録される可能性もゼロではありません。
大学が損害を講じることになれば、卒業にも影響が出るなどさまざまなところで不利益を生じることになるので覚えておきましょう。
他の選考に悪影響を及ぼす
Webテストでカンニングを行い、第一選考を通過できたとしても、そのあとの面接などに悪影響を及ぼします。
なぜならWebテストのカンニング行為がバレてしまうのではないかと、常に罪悪感や不安を感じながら選考を受ける必要があるからです。
罪悪感や不安を感じながら選考を受けたとしても、自分の実力を発揮することができないため、選考に落ちてしまうリスクが高くなります。
入社後に苦労する
もし選考時にカンニングがバレなかったとしても入社後に苦労することが多いです。
Webテストは就活生の基礎学力や性格、考え方などを把握するために行います。
仮にWebテストでカンニングを行い100点満点だった場合、その就活生の基礎学力は非常に高いことになります。
実際の自分の学力と相反するものがあるため、入社後に自分の基礎学力に見合った行動を行うことができません。
企業側が求めるレベルと、自分の能力の間にギャップができてしまうため、企業側の評価が下がってしまいます。
また自分も能力差についていけず、仕事を続けることが困難になります。
カンニングしてまで入社したにもかかわらず、結果的に早期退職となってしまう可能性が高いです。
逆に時間がかかって時間切れになる
インターネットで検索したり、参考書を見たりして答えを探しながら解答することは可能です。
しかし、解答を探すことに時間がかかってしまい、最後まで設問を解くことができなくなってしまいます。
とくに玉手箱のような問題数が多く、一つの問題に充てる時間が少ないWebテストは、返って損をすることが多いです。
「罪悪感の対義語は?」といった設問であれば、答えを検索することが簡単ですが、文章問題や計算問題などは検索してもすぐに見つかるわけではないため、検索時間がかかってしまいます。
自分の実力であれば100問中90問は解けた場合でも、検索することによって50問しか解けないこともあるので、時間切れになるリスクは大きいです。
Webテストでカンニングがバレる理由
一見バレなさそうに感じるWebテストですが、バレる可能性は高いです。
ではなぜ、自宅でテストを受けているにも関わらずバレてしまうのか理由を見ていきましょう。
解答速度が不自然
世の中にはWebテストの解答が載っているカンニングペーパーが、有料で出回っています。
自分で検索していると時間切れになりますが、カンニングペーパーの答えに沿って入力するだけであれば、時間内に解くことが可能です。
しかし、カンニングペーパーに沿って答えを入力すると、解答速度が早すぎるため不自然になってしまいます。
カンニングをせずに、通常60分かかるテストが15分で終わることは、まずあり得ません。
そのため、解答速度が不自然なのでバレてしまいます。
では、解答速度が早くなりすぎないようにある程度調整した場合はどうでしょうか。
結論からいえば、この場合もバレるケースが多いです。
たとえば、問題数が60問あり制限時間60分のWebテストがあったとします。
早く解答しすぎないように1分につき1問、答えを入力し制限時間ギリギリまで解答したとします。
「解答速度が早すぎる」という不自然さはありませんが、多種類の問題を均一の時間で解答している、という不自然さが出るためバレる可能性が高いです。
何も考えずにまばらに調整したとしても不自然が生じる可能性があります。
たとえば、最初に「1+1=2」を5秒で解答したとして、後に出てきた問題で「5+4=9」を1分かけて解答した場合、似たレベルの問題であるのに解くまでのスピードが違いすぎる、という不自然が発生します。
近年ではAIの技術力が進化しているため、自分では気が付かないようなレベルでも不自然さを見抜かれてしまうため、バレる可能性が高いです。
正答率が高すぎる
答えをカンニングすれば当然、正答率が高くなります。
Webテストで満点を取れる人は非常に稀であるため、カンニングをして満点を取った場合、怪しまれることは避けられないでしょう。
では先ほど同様に調整した場合を考えてみましょう。
満点では怪しまれるため正答率80%程度を目安に解答したとします。
正答率が高すぎると怪しまれますが、正答率80%が高いのか低いのか自分で判断することができません。
そのWebテストが難しく、正答率のボーダーラインが40%であった場合、正答率80%は非常に高いため怪しまれます。
逆も然りで、正答率60%程度にしたとしても、そのWebテストが簡単で正答率のボーダーラインが70%であれば平均以下になるため、バレはしませんが選考を通過できるかわかりません。
また、これはWebテスト全体の正答率の話をしていますが、各設問ごとの正答率も同じことが考えられます。
正答率の低い設問ばかりを自分だけ正解していても不自然ですし、逆に正答率の高い設問ばかり自分だけ不正解であっても不自然です。
このように自分で調整したつもりであっても、最新技術をもったAIの前では無能であるため、カンニングがバレてしまいます。
面接官とのやり取りでバレる
カンニングがバレるのはAIだけではありません。
Webテストの後に控えている面接でのやり取りでバレることも多いです。
当然ですが、面接官は就活生のWebテストの解答を熟知しています。
言語・非言語のテストであればどの分野が苦手なのか、性格テストであればどんな性格をしているのか、といった情報を持っています。
カンニングを行っていた場合、Webテストの解答結果と面接官と話している内容に違和感が生じる可能性が高いです。
たとえば、性格テストで「保守的な傾向がである」と診断されているにもかかわらず「自分は何事にも積極的に挑戦し、みんなを引っ張っていきたいです」とアピールしていれば、真逆のことを言っていることになります。
また、Webテストの正答率が高いということは、基礎学力が高いことと同じです。
そのため、面接官との対話も必然的にレベルの高い内容になります。
しかし、正答率を偽っているため、面接官の対話レベルに追いつかず「語彙の意味がわからない」「間違えた表現をしている」など、レベルに見合った対話をすることができない可能性が高いです。
面接官も採用のプロであるため、違和感を感じた場合、その違和感に対する質問を投げかけてくるため、次第に就活生のカンニングがバレてしまいます。
AI監視型のテストが増えている
近年ではAI監視型のテスト(TG-Web eye、C-GAB plus、Remoty AI+など)の導入が増えています。
パソコンのカメラを通してAIが就活生の動きを観察し、不正行為と思わしき行動が合った場合は企業に報告されるシステムです。
AIの判断が100%正しいとは限らないため、最終的な判断は試験監督者が行います。
AI監視型テストの中でもとくに注目度の高いのは「TG-Web eye」について見ていきましょう。
オンライン監視型のWebテストについて詳しく知りたい人は「オンライン監視型Webテストとは?注意点と対策法を徹底解説! | 就活ハンドブック (jo-katsu.com)」こちらの記事も参照してください。
TG-Web eyeとは
TG-WEB eyeは、替え玉受験やカンニングを検知する機能を持ったAIが兼ね備えられたWebテストです。
従来のマークシート方式、WEBテスト方式、テストセンター方式、オンライン監視型Web会場方式に続く第5の受験方式として注目されました。
100社以上がTG-WEB eyeを導入しており、ANA、三井不動産、日本テレビ、大正製薬、大塚製薬、森永といった大手企業も導入しています。
TG-WEB eyeの監視システム
TG-WEB eyeがどのような監視システムを持っているのか簡単にまとめたので見ていきましょう。
|
Webテストはカンニングせずに自分の力で解く

Webテストでカンニングをしても自分のためにはなりません。
カンニングを行うとデメリットばっかりであるため、自分の力でWebテストに挑みましょう。
Webテストのおすすめの対策方法を4つ紹介しますので、参考にしてください。
出題率の高いSPIを勉強する
Webテストといえば、SPI・玉手箱・TG-Web、CAB、GABなどがありますが、多くの企業で採用されているのが、SPIです。
もし、志願する企業のテストが何を採用しているのかわからない場合はSPIの対策を行っておきましょう。
SPIであれば参考本や無料で練習問題ができるサイト、アプリなどさまざまな方法で対策することが可能です。
SPIの知識は他のWebテストでも活かせる場面があるので、勉強しておいても損はありません。
もし、志望する企業が明確である場合は、まずはその企業が採用しているテストを調査し、採用しているテストの対策から始めましょう。
志望する企業のテスト形式を調べておく
先ほども述べましたが、まずは自分の志望する企業がどのテストを採用しているのか調べておきましょう。
テストの種類がわかれば、そのテストの形式・特徴を知ることが大切です。
たとえば、玉手箱は問題数が多く制限時間が短いので1問あたりにかける時間は短いです。
また1つの問題形式に1種類しか出題されないないので、1問目が「四則逆算」であれば、残りもすべて「四則逆算」の問題が出る、という特徴があります。
Webテストの種類と特徴について詳しく知りたい人は「適性検査の種類と特徴について解説!対策方法付きで完全攻略 | 就活ハンドブック (jo-katsu.com)」こちらの記事を参照してください。
練習企業を設けて実際にテストを受ける
本番形式で練習したい人は練習企業を設けて実際にテストを受けてみてもいいでしょう。
実戦形式に慣れていると本番でも焦らずに実力を発揮することができます。
とくに監視型のWebテストの場合、見られている感覚を感じることもありますが、事前のテストを受けていればその心配がありません。
より本番に近い形で対策する場合は、本番の企業と同じWebテストを実施している企業を選択しましょう。
ただし、練習企業を設ける場合はある程度、選考にゆとりがある人が望ましいです。
練習企業といえばエントリーシートなどを提出する必要があるため、余分な時間を費やすことになります。
そのため、選考に時間のない人にはあまりおすすめできません。
過去問を繰り返し解く
Webテスト対策としてとくに行ってほしいことが「繰り返し問題を解くこと」です。
Webテストによって形式や特徴が異なるので、繰り返し問題を解くことで慣れておくことが重要です。
玉手箱のような問題量の多いWebテストは、問題を見ただけでぱっと答えがわかるくらいやりこむ必要があります。
また繰り返し問題を解くことで時間配分を身につけることも可能です。
時間切れにならないためには、どれくらいのスピードで問題を解けばいいか感覚をつかむことができます。
まとめ
Webテストでカンニングをしても「解答速度が不自然」「正答率が高すぎる」といった理由からバレます。
また近年ではAI監視型テストも増えており、取り締まりも厳しくなっています。
Webテストはカンニングをせず、自分でしっかり対策して挑みましょう。