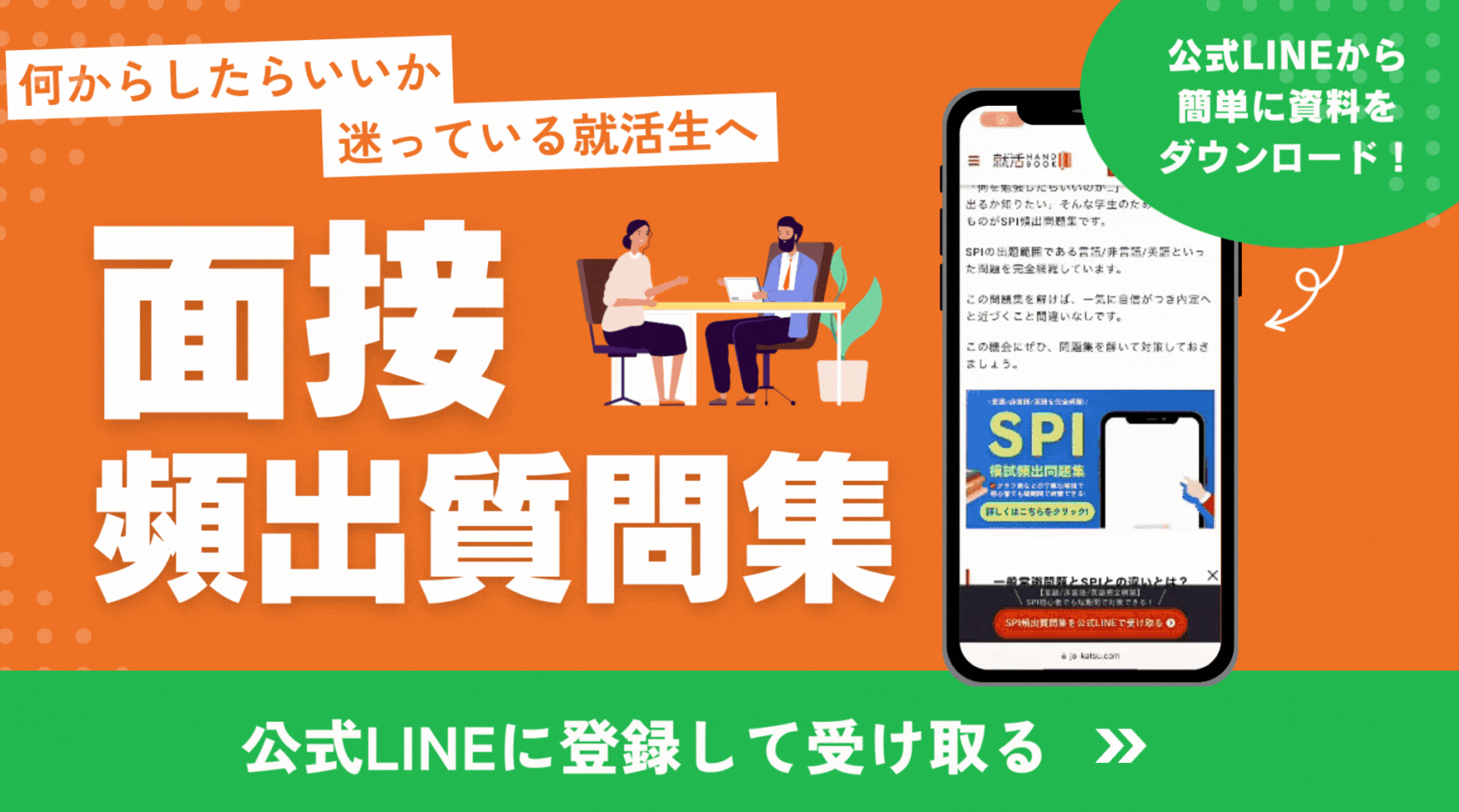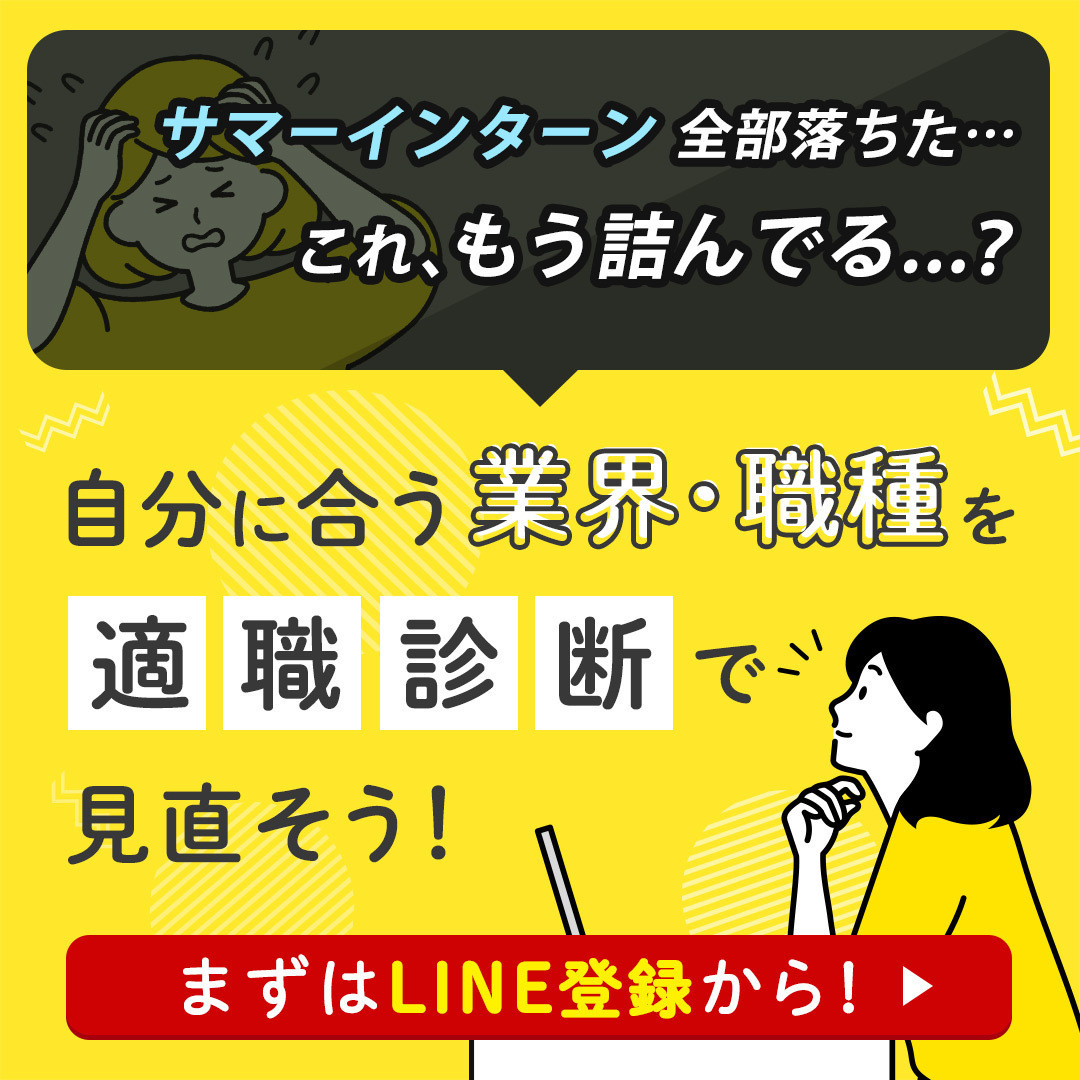就活で「苦手なこと」を好印象に回答する方法は?コツを解説
2024/9/30更新
はじめに
就活面接時に、「あなたの苦手な点(短所)はどんな点ですか?」と聞かれ、回答に困ったことはありませんか?
私自身、短所に関する質問にどう対応するべきか悩んでしまい、結局納得がいく回答ができずに面接後に凹んだ経験が何度もあります。
しかしその経験をきっかけに「苦手なことをどう答えたら好印象になるか」という点を時間をかけて考え、実践していった結果、面接時に自信をもって回答ができるようになり志望企業から内定をもらうことができました!
そのため本記事では就職活動において「苦手なこと(短所)」を考える上で有益な情報を紹介していきます。
- 企業側が「苦手なこと」を質問する意図
- 就活で使える「苦手なこと」の探し方
- 回答する際のポイント
- 「苦手なこと」の回答例3選
また結論として、企業が苦手なことを聞く理由は「問題解決能力」「客観的思考力」の精度などを確認するためです。
そのため、質問する意図を踏まえたうえで「自分史」「長所からの逆算」などを通して、自分なりの回答を考えていくことが重要でしょう。
「選考落ちするのが怖くて苦手なことが上手く答えられない…」
「面接官にプラスの印象を与える回答ができるようになりたい!」
という学生はぜひ最後まで読んでみてください!
【面接頻出質問集】100種類の回答例をいつでもスマホからチェックできる!
面接対策に悩んでいる方にピッタリの面接頻出質問集を用意しました。
質問と回答例は、全部で100種類あります。
面接時に「苦手なこと」が質問される理由

面接官はなぜ、学生が答えづらいような「苦手なこと」に関する質問を行うのでしょうか。
「苦手なこと」の質問に対して面接官を納得させる回答をするためには、まず面接官がネガティブな質問を行う「意図」を把握する必要があるでしょう。
そして、実際に苦手なことを質問する意図は以下4点が考えられるため、1つずつ解説していきます。
- 問題解決能力を見極める
- 自身を客観的に分析できているかを確認する
- 社風と著しく相違していないかを把握する
- パーソナリティーを理解する
問題解決能力を見極める
苦手なことを質問する理由の1つ目は、問題解決能力を見極めるためです。
苦手なことやネガティブなことに対して、できれば向き合いたくないと思う方は少なくないはず。
しかし社会人として働く以上は仕事でミスやトラブルは起きてしまうもので、ミスしてしまった場合はその仕事に対して苦手意識を持ってしまうケースも想定されます。
そんな時でも下を向かずにしっかりと苦手なことに向き合いながら解決策を考え、苦手の克服に努められる人材が持つ「伸びしろ」は計り知れません。
そのため面接官は、下記のような「問題解決能力」を見極める意図があると考えます。
- 苦手なことをどのように捉えるか。
- 苦手なことの解決のためにどのようにアクションを起こすか。
自身を客観的に分析できているかを確認する
苦手なことを質問する理由の2つ目は、自身を客観的に分析できているかを確認するためです。
仕事で結果を残すうえで、客観的思考力は必要なスキルの1つになるでしょう。
なぜなら仕事は社員の方々と協力して進めていき、そしてお客様に対しては顧客の視点で接していくといった「対人関係」が伴うためです。
チームとして成果を出すためには「自分はどのような立ち回りを行っていくべきか」、またお客様に営業する際には「どのように接していけばお客様が心を開いてくれるか」などを客観的に考えていくことが欠かせません。
そして客観的に考えることは良好な人間関係に繋がり、結果的に会社を盛り立ててくれる人材になると判断することができます。
社風と著しく相違していないかを把握する
苦手なことを質問する理由の3つ目は、社風と著しく相違してないかを把握するためです。
例えば体育会系な社風で飛び込み営業を積極的に行う企業の場合は、エネルギッシュで行動力に満ち溢れた社員が結果を残しやすい傾向があるでしょう。
一方そのような環境下にも関わらず、コミュニケーションや主体的な行動がとても苦手な学生を入社させてしまっては、社風にストレスを感じ結果を残せず、早期退職してしまう可能性が高くなります。
そのためまず学生がどのようなことに苦手を感じるかを把握し、苦手なことが働く上で致命症にならないかを確認する意図があります。
パーソナリティーを理解する
苦手なことを質問する理由の4つ目は、パーソナリティーを理解するためです。
苦手なことについてはできれば向き合いたくないですし、そもそも他者に説明することもおっくうですよね。
しかしそんな中でも自身の苦手を打ち明け、改善に努めようとする「素直さ」や「誠実さ」があれば苦手を克服し、成長できるはず。
また話したくない内容でも勇気をもって話すことは「信頼できる!」と受け手に感じさせることにも繋がり、人間関係も良い方向につながっていくでしょう。
そのため面接官は苦手に関する質問をあえて行い、学生の素直さや誠実さを理解しようとしていると考えられます。
面接で使える「苦手なこと」の探し方
「自身の苦手なこと」についてぼんやりと把握しているものの、いざ就職活動で話すとなると「的確な内容が見つからない」と悩む学生は少なくありません。
そのため、今回は「苦手なこと」の探し方について3点紹介します。
- 自身の過去を振り返る
- 長所から逆算
- 他己分析の活用
自身の過去を振り返る
苦手なことの探し方の1つ目は、自身の過去を振り返ることです。
そして具体的に自身が行ったことは「自分史の作成」でしたので、紹介していきます。
自分史とは
自分史とは、今までの自身の経験を年表形式で言語化していくことです。
具体的には、記憶に残っている事実やその時の感情などを時系列に沿って、下記のような形でまとめていきます。
- (0歳) 3人兄弟の長男として生まれる。
- (幼稚園)外遊びと昆虫採集が大好きな少年だった。性格はとてもシャイで、幼稚園に行く度に緊張していた。
- (小学生)スポーツが好きで、柔道・サッカー・水泳・野球など色んなスポーツを習っていた。とにかく負けず嫌いな性格。
それ故勉強でもスポーツでも良い結果を残すことができていたが、プライドが高く冗談が通用しない人間に。
人間関係もうまく行かない時があった。
これによりどのような時期に独自の価値観が生まれ、何が得意で何が苦手に感じるようになったか、などを根拠となる経験をもとに流れで把握することができます。面接で話す際には「エピソードを裏付ける根拠」や「一貫性」が大事。
自分史で過去を深ぼることで、長所や短所における一貫性のあるエピソードを掘り起こすことができるため、自分史の作成はオススメです。
なお「自分史」は下記でさらに詳しく説明しているため、気になる方はぜひ参考にしてみてください。
長所からの逆算
長所と短所は紙一重と言われることがあります。
それはどんなに自身にとっては「良い」と考えられることでも、場面によってはそれが悪い側面として足を引っ張るケースがあることを意味します。
そのため、まずは自身が得意なことや長所として考えられることを見つけ、その事象における負の側面を考えることも一つの手といえるでしょう。
同じような意味でも印象が真逆の言葉の例
| 良い面 | 悪い面 |
| ポジティブ | 楽観視しすぎる |
| サポートが得意 | 主体性がない |
| 素直 | 人の意見を聞きすぎる |
| 臨機応変に動ける | 計画性がない |
| 協調性がある | 反対意見を言えない |
他己分析の活用
より客観的な意見を把握することができる点が、他己分析のメリットになります。そのため家族や仲のいい友人など自身と深い関係性のある方、また自身の仕事ぶりを把握しているバイト仲間に他己分析の協力を依頼してみましょう。
面と向かって他己分析をしてもらう場合、回答者によっては本音で回答しづらいと感じることもあると思います。
その場合は、例えばマイナビの他己分析(お願い!他己分析 – 就活準備 – マイナビ2025) のような非対面で回答できるツールを用いるのもオススメです。
他己分析について興味を持った学生は、ぜひ下記記事も参考にしてみてください。
「苦手なこと」を答える時のポイント

苦手なことを答える際は、答え方やエピソードの質で面接官の印象が大きく左右されます。
そのため、実際に面接で回答する際に意識するべきポイントを紹介していきます。
- ポジティブな面もアピールできる内容を選ぶ
- 克服できるエピソードを選ぶ
- 結論→根拠→改善策の順で話す
ポジティブな面もアピールできる内容を選ぶ
先ほどは苦手なことの見つけ方の1つに「長所からの逆算」を挙げましたが、エピソード選びでも有効活用できます。
具体的には自身の強みだと認識する内容のネガティブな側面を「苦手なこと」として面接官に話しましょう。
また自身の長所が裏目に出たエピソードを裏付けて話せればより質問の回答として質の高いものになるため、この視点も参考にしながら事前に回答を考えてみてください。
克服できるエピソードを選ぶ
実際に苦手なことを質問する側の面接官含め、誰にでも苦手なことはあります。
そんな中で苦手なことに対する回答が悪い印象に繋がる理由の1つに、「解決策を提示できない」点が挙げられます。
そのため全く解決できないような苦手エピソードをあえて選ぶ必要はなく、しっかりと克服できるような内容を選びましょう。
結論→根拠→改善策の順で話す
回答する時のテクニックに関する内容です。
まず第一に「実際にどのような点が苦手か」の結論部分を話しましょう。
理由は、聞き手がおおよその話の展開をイメージでき、ストレスなく話を聴くことができるためです。
また話し方としては「~な点が苦手です」というよりも「~な点があります」というように、なるべくネガティブな印象を与えないような言葉選びも重要です。
そして結論の次にはその根拠を話し、最後には必ず解決策を提示しましょう。
デキる社会人はこのように結論ファーストで話し、かつ細かい言葉選びができる特徴があるため、デキる学生であることを面接官に連想させるべくテクニック面も磨いていきましょう。
4 5


プラスの印象を与える「苦手なこと」回答例3選
上記で紹介した内容を踏まえ、「苦手なこと」の回答例を3つ紹介します。
- 苦手なこと→判断すること
- 苦手なこと→断ること
- 苦手なこと→冷静に考えること
苦手なこと→判断すること(長所で言う場合→協調性がある)
私は、時に判断に時間を要してしまうことがあります。
大学ではサークル長を務めていますが、合宿のスケジュールを決める際により皆の意見を尊重したいという意志が先行してしまい決断ができず、幹部間の打ち合わせで多くの時間を使ってしまったことがあります。
そのため現在は期日から逆算して優先して考えるべき事項を定め、細分化した計画をメンバーと共有したうえで話し合いを行うようにしています。
苦手なこと→断ること(長所で言う場合→相手の気持ちを考える)
時に自分よりも他人を優先してしまう点です。
現在私は塾講師のアルバイトをしていますが、夏期講習など人手不足な時期に塾長から出勤を懇願され、テストの勉強をする計画を立てていたのにバイトを優先してしまいました。
その結果、肝心のテストもイマイチな結果に。
そのため、現在は他人からの依頼は即断即決するのではなく、優先順位を再度確認した上で依頼を引き受けるべきかを考える時間を設け、改善に努めています。
苦手なこと→冷静に考えること(長所でいう場合→行動力、積極性がある)
時に、自身が良いと思ったら考える前にすぐに行動してしまうことがあります。
現在はカラオケ屋さんでアルバイトをしていますが、その際にご高齢の方から「この写真の息子を探しているため、似た人物が来たら連絡ください」と言われ、すぐに承諾しました。
その後マニュアルを確認した結果、その場合は承諾する前に警察に連絡するべきだったことを知り、リスクの部分含め目の前のことを様々な視点で考える重要性に気付きました。
そのため現在は臨機応変な行動を冷静に行うべく、特にイレギュラーな事象に対しては先に他者への相談を行うなど、行動をする前に考えることを意識し、最適解を見つけ出すことに努めています。
【面接頻出質問集】100種類の回答例をいつでもスマホからチェックできる!
面接対策に悩んでいる方にピッタリの面接頻出質問集を用意しました。
質問と回答例は、全部で100種類あります。
さいごに
今回は、就活で「苦手なこと」を好印象に回答するために必要な情報を掲載してきましたが、いかがだったでしょうか?
記事の内容を簡単にまとめます。
- 企業が苦手なことを質問する理由は4つある。
- 苦手なことは「長所から逆算する」などして見つけるといい。
- 苦手なことを答える際は、必ず克服できるエピソードを選ぶ。
- また必ず「改善策」を添えてエピソードを展開することも重要。
- 回答する際は「結論ファースト」を徹底すべき。
苦手なことや短所に関する質問に対しては苦手意識を抱く学生が多いですが、だからこそ質問に対して的確に対応できる学生は好印象で、評価が上がっていくはずです。
準備をしっかり行えばその分良い回答ができる内容と考えられるため、本記事を参考にしながら対策を行っていきましょう!
なおジョーカツでは「就活対策」として、内定獲得のために有益な記事を多数掲載しているため、ぜひ下記サイトにも目を通してみてください。