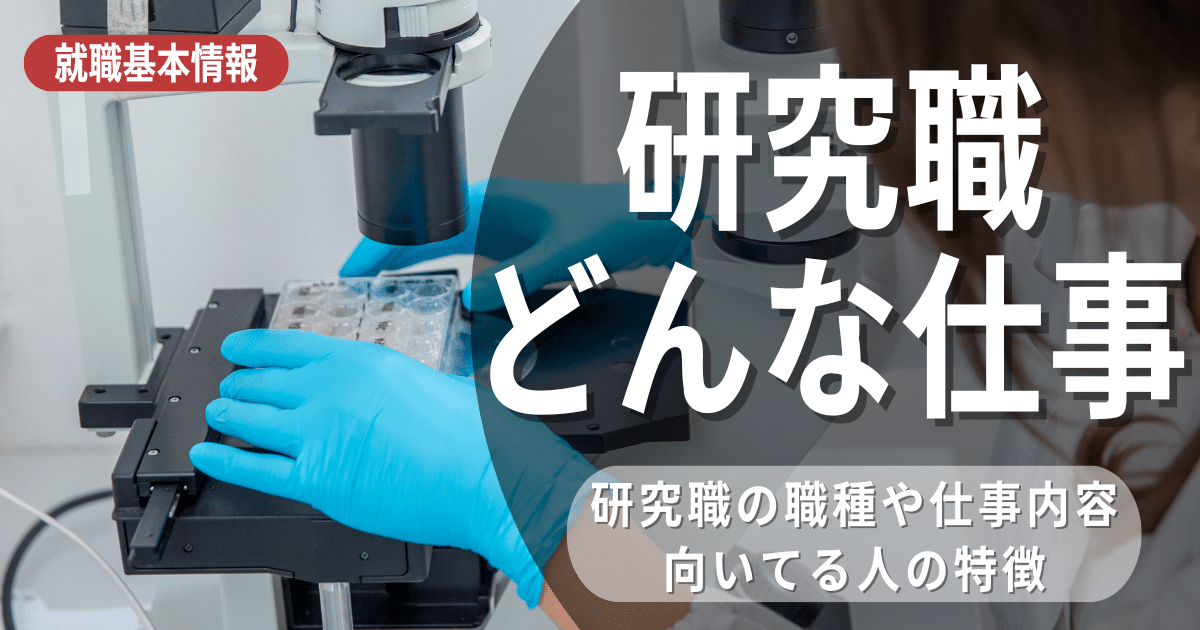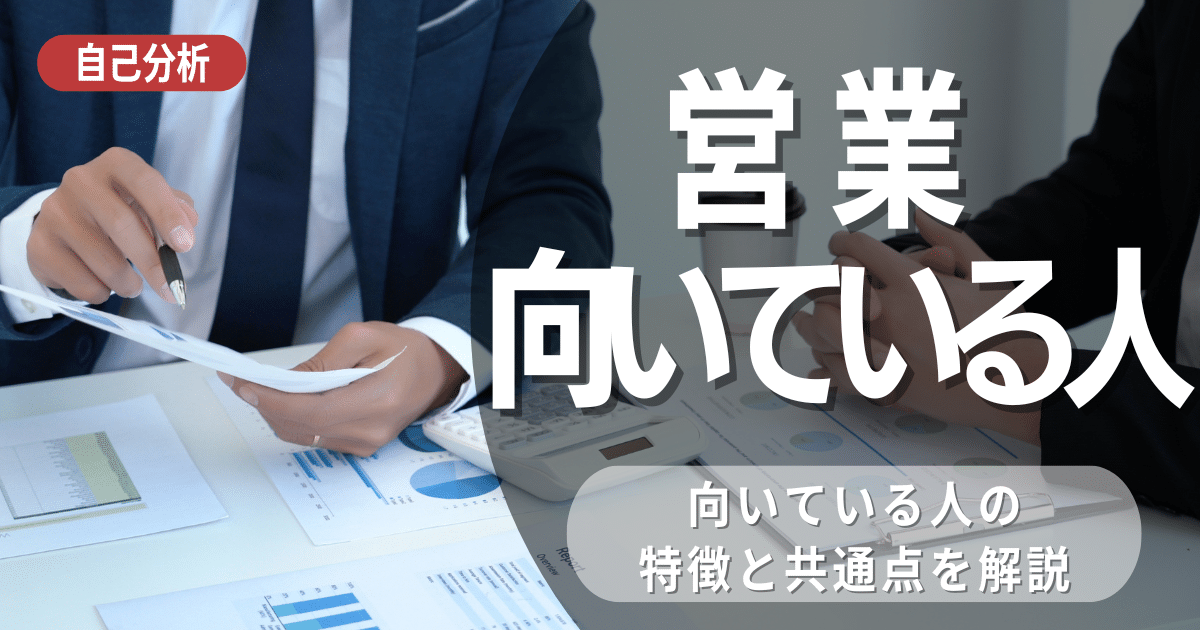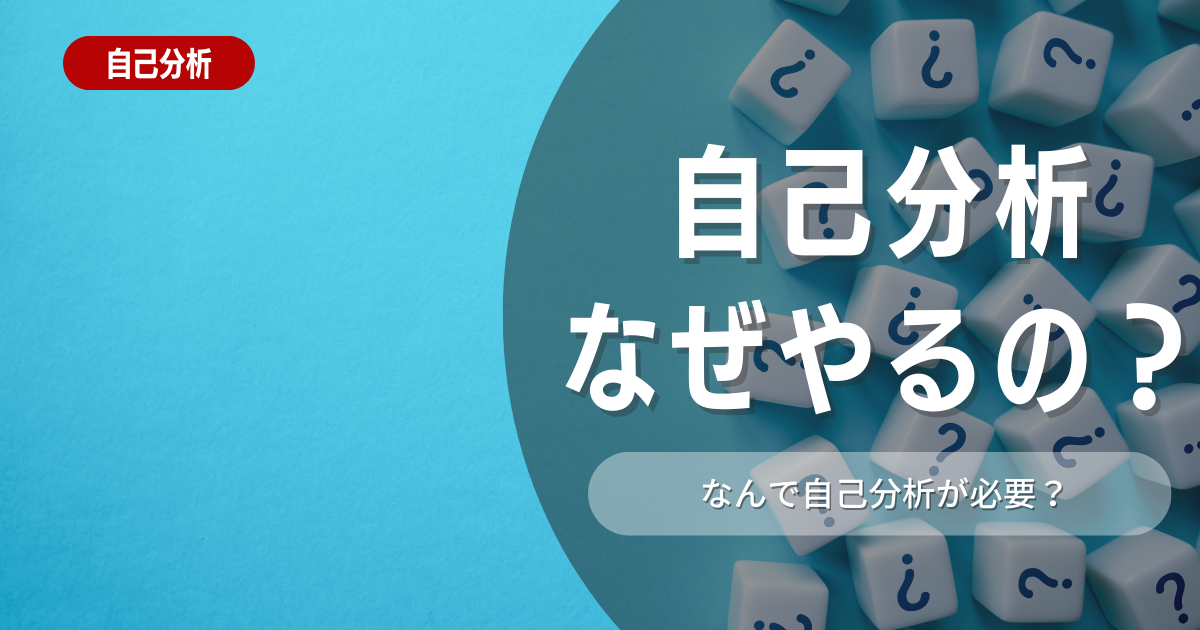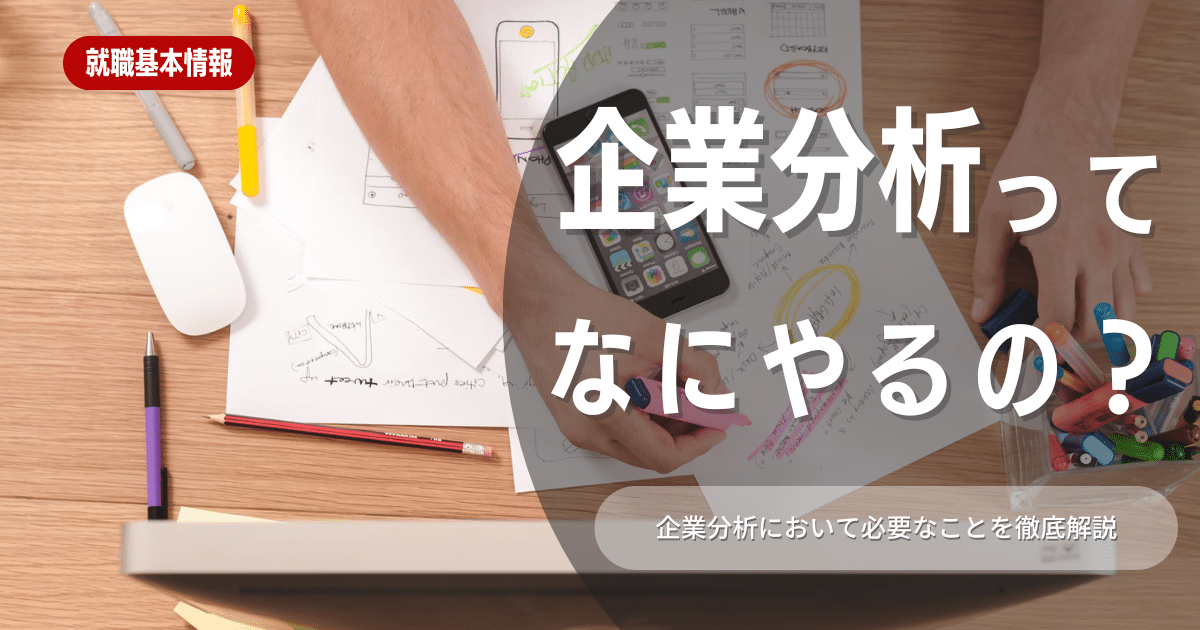農学部は農家になるべき?就職業界や内定獲得のポイントを解説
2024/9/30更新
はじめに
みなさんは農学部の学生がどのような企業に就職していくかご存じですか?
農学部は農学を学ぶ学部のため、詳しい内容は知らず、
「農学部は農家にしかなれない」
「農家のことしか学べないため就職も難しい」
といったイメージを持つ方も少なくありません。
就職が難しければ人気も低いと予想されますが、実際に農学部は人気学部で、理系学部としては珍しく女性の学部生も多いのが現状です。
そのため本記事では農学部生の就活状況を分析し、本当に農学部は就職が難しいのかを明らかにしていきます!
- 農学部生の就活の現状
- 農学部生にオススメ業界、職種
- 内定獲得のポイント など
また結論として、農学部生の就職業界・職種は幅広いため、潰しの利く学部と言えるでしょう。
農学部の就活生はぜひ本記事を最後まで読んでみてください!
上京を志す地方学生ならジョーカツ!
あなたのキャリアを加速させるチャンス!
無料で利用できる快適な個室シェアハウス、
東京までの交通費サポート付き
首都圏の注目企業への就活ならジョーカツ
首都圏の学生ならスタキャリ!
理想のキャリアを実現へと導く第一歩!
あなたにピッタリのキャリアアドバイザーを選び、
自分にマッチする優良企業をご紹介
首都圏企業のES添削から面接対策まで、就活ならスタキャリ
「農学部=農家?」農学生の就職活動の現状

就活面ではネガティブな噂も聞くこともある農学部ですが、実際に農学生の就職活動の現状はどうなっているのでしょうか。
結論として、農学部生は就活を心配する必要はありません!
「大学通信オンライン」の調査によると、就職率はここ数年で常に90%超えを達成しており、理工学部などとともに安定して高い数値を誇っています。
また就職先も幅広く、いわゆる「潰しの効く」学部といえるほど。
理由の1つとしては、農学部は学べる幅が広い点が挙げられます。
農学はもちろんのこと、食品や生物・化学・環境学など扱う学問が多様化しています。
そしてその幅は理系学問にとどまらず、農業における「経営学」「経済学」「歴史学」といった文系的な学問にまで拡大。
またかつては「農業は先祖代々から家業として引き継がれていく仕事」というイメージが定着していましたが、現在は「アグリテック」「スマート農業」のように農業とIT技術を融合させるビジネスが注目を集めるなど、農業ビジネス自体も広がりを見せ、農業の知識を重宝する他業界・企業も増えています。
そのため、多くの企業で農学部出身者の活躍の場があると言っても過言ではありません。
なお、近年では「銀の匙」など、農業高校を舞台にしたアニメが流行ったこともあり若者からも人気で、農学に対するイメージが老若男女問わず大きく変わっています。
農学部生の主な就職業界4選
では実際に、農学部生はどんな業界に就職することが多いのでしょうか。
今回は農学部の卒業生の主な就職業界について紹介していきます。
- 農業業界
- 食品業界
- 製薬業界
- IT業界
農業業界
農学部生の主な就職先の1つ目は、農業業界です。
農学部での学びが直接仕事で活かせる業界のため、活躍する学生は多いです。
また「農業業界」は実際に様々な分野に分割でき、国内外で活躍している企業も多いため魅力的ですね。
具体的には農業、畜産、酪農、種苗、農業資材会社などに分類できます。
一般的に農業業界は「体力が必要」や「働き方がブラック」などマイナスのイメージを持つ方もいますが、例えば野菜や果物の種子を扱う「種苗業界」は高給で残業が少ない「隠れホワイト企業」と呼ばれるなど、イメージと異なる良い働き方ができる企業も多く存在していますよ。
そのため、就職先に悩む農学生はまず農業業界を調べてみることをおすすめします。
- サカタのタネ
- タキイ種苗
- カゴメ
- クボタ
- ヤンマー
農業業界についてもっと知りたい学生は、ぜひ下記記事にも目を通してみてください。
食品業界
農学部生の主な就職先の2つ目は、食品業界です。
そもそも食品に興味があって農学部を志望するケースも多く、また農学生の学ぶ内容は直接食品に関わるものが多いため、農学と食品業界はとても相性が良いといえるでしょう。
食品メーカーの研究職として自身が大学時代に研究した分野に関わる研究を続けていく学生もいれば、食品の品質管理や工場管理、また食品を直接消費者に提供していく営業職に就くなど、食品業界では活躍できる職種が多いのも農学部生が食品業界を志望する理由の1つと考えられます。
- 味の素
- 明治
- 日本ハム
- 日清食品
- マルハニチロ
食品メーカーを就活目線で解説した記事も掲載してますので、気になる方はぜひ確認してみてください。
製薬業界
農学部生の主な就職先の3つ目は、製薬業界です。
農学部では農業に加えバイオサイエンス・生物・化学などの分野を学ぶこともでき、そこで得た学びは製薬業界でも活かすことができます。
そのため食品業界と同様に研究開発から品質管理・営業など選ぶことができる職種の幅も広いです。
また大手製薬会社は残業が少ないのに年収が高い企業が多い特徴があり、ワークライフバランスを追求できる業界といえるでしょう。
- 中外製薬
- 日本新薬
- アステラス製薬
- 住友ファーマ
- 塩野義製薬
なお製薬業界に興味のある学生は、ぜひ下記のURLをクリックしてみてください。
IT業界
農学部生の主な就職先の4つ目は、IT業界です。
人手不足の問題やコロナウイルスの感染拡大などが影響し、農業業界は現在「変化」が欠かせません。
そんな中近年は「スマート農業」や「アグリテック」という言葉が台頭しており、IT技術を農業に生かし、効率的に農作物を作っていく動きに注目が集まります。
例えばNTT東日本ではAI技術やICT・ロボティクスを活用して「次世代施設園芸」の実証を実施。
人手不足などの問題を解決し農業経済が上手く循環していくためには、ITと農業の融合が不可欠で、それ故IT業界における農業需要が高まり、IT企業に就く農学部生も増えているといえるでしょう。
現に明治大学農学部卒業生の進路は、製造業に次いで2番目に「情報通信業」への就職が多く、2022年度には全体の「16.5%」の農学部生がIT企業へ就職しています。
- NTTデータ
- 日本IBM
- 富士通
- NEC
- Sky
IT業界の向き・不向きについて下記で解説しているため、IT業界を志望しようか迷う学生はぜひ参考にしてみてください。
農学部生が就く主な職種4選

農学をはじめとした理系の学問に加え、文系の分野まで幅広く学べる農学部は選べる職種も多彩です。
そのため農学部生が就く主な職種について、以下で紹介していきます。
- 研究開発
- 品質管理
- 営業・企画
- 生産者
研究開発
農学部生が就く主な職種の1つ目は、研究開発です。
名前の通り、企業の研究機関で新たな商品や技術を見つけるために研究する職種。世の中でまだ見つかっていない新たなことを自身の手で発見をし、それが社会への貢献に繋がれば大きなやりがいを感じることができる仕事でしょう。
学生時代に学んだ学問の中で興味のある分野を見つけることができた場合に、その分野を推している企業の研究職として仕事ができれば、より楽しさを感じながら取り組めるはずです。
研究開発をさらに詳しく知りたい学生は、ぜひ下記記事も参考にしてみてください。
品質管理
農学部生が就く主な職種の2つ目は、品質管理です。
業務内容としては、下記の通りです。
- より不良品を出さないような作業工程を考える。
- 品質を保ちながら生産コストを減らす方法を見つける。
- 商品を届ける上で、高品質を保ちながら安全に運ぶ輸送手段の選定。
- 品質検査の実施。
- 商品が常に「適量」準備されるような在庫管理。
会社の業績を大きく左右する業務が多く、責任が伴う分上手くいったときにより達成感を感じることができます。
営業
農学部生が就く主な職種の3つ目は、営業です。
文系の学生が多く就く職種ですが、その中で農学部の学生が営業として働く強みは、「大学で学んだ専門的な内容を顧客に直接説明できる点」でしょう。
例えばメーカーの営業に文系学生が就いた場合は、入社後にはじめて専門的な内容を学びます。
そしてお客様から商品の専門的な内容について質問があった場合は、知識を有してないため即答せずに社内に持ち帰って確認する段取りが通常。
しかし、農学部生が学生時代に研究した分野に関わる営業ができれば、お客様の質問に即座に回答ができるケースが生まれ、他の営業マンに比べ高い評価を獲得できるはずです。
自身のコミュニケーション能力を活かしたい農学部生は、営業も検討してみることをおすすめします。
なお営業職については下記で徹底解説しているため、営業職を志望しようか悩んでいる農学生はぜひチェックしてみてください。
生産者
農学部生が就く主な職種の4つ目は、生産者です。
生産者とは、農家として実際に農作物を育てる仕事です。
実際に農家を営んでいる家系の学生が、家業を継ぐために農学部を選んでいるケースも少なくありません。
現場で実際に作物を生産していくため体力が必要ですが、自身の技術で育てた野菜や果物によって、消費者が笑顔になる姿を見ることができたときの喜びはこの上ないでしょう。
現在は農業にICTやAI技術などを融合させ、自動化や効率性を生み出す技術の開発を目指す動きが盛んなため、今後は従来に比べ働き方が徐々に改善されていくことが予想されます。
農学部生が内定をもらうためのポイント
農学部での学びは様々な業界で生かされ、また多様な職種を選ぶことができるからこそ、自身が魅力に感じた企業からはどうにか内定を獲得したいですよね。
今回は農学部生が就職活動を進めていくうえで重要になるポイントを3つ紹介するので、参考にしてみてください!
- 「なぜ」その業界・企業を志望するかを自身の経験や価値観をもとに説明する
- 競合他社ごとで違いを理解する
- 自身の「良いところ」が会社でどう生かされるかを明確にする
「なぜ」その業界・企業を志望するかを自身の経験や価値観をもとに説明する
就職活動をするうえで、「この企業良いな!」また「なんかこの企業には魅力を感じないな」など、企業ごとに抱く印象は細かく変わっていくものです。
そして一般的にはその志望度に基づいて、第一志望とする企業などの順序を自分なりに決めていきます。
そんな中で志望企業に内定をもらえる学生は、「なぜその企業が第一志望なのか」という点を明確に言語化できていることが要因に。
最初は「なんとなく良い企業だなと思った」というような抽象的な理由がきっかけで興味を持つことも多く、それは全然問題ありません。
重要なのは、その普段言語化しないような「なんとなく」の感情や思考をしっかり説明できるように努められるかどうかです。
決断や思考の発生には必ず理由があるはず。
そしてその感情や思考は、自身の経験やそれによって生まれた価値観が大きく関係しています。
そのため、志望理由の根拠となる部分は「自身の経験や価値観」を織り交ぜながら話していければとても良いです。
また自身の経験や価値観をより知っていくためには、自身が思い浮かんだことに対して常に「なぜそう思った?」と質問していきましょう。
時間をかけて行けば、一貫性のある内容が見つかっていくはずです。
競合他社ごとで違いを理解する
せっかく志望理由を自身の経験や価値観をもとに上手く話せても、「それって他の会社でも実現できるよね?」と面接官に返されてしまうような内容だったら本末転倒です。
そのためビジネスモデルや社風、座談会やOB・OG訪問での社員の印象などで、競合他社ごとでその企業にしかない特徴を見つけ出しましょう。
企業ごとの特徴の見つけ方の一例を以下に記載します。
- 企業HPや就活サイト・転職サイトなどの情報で差別化できそうなポイントを洗い出す。
- その内容をもとに自分なりに志望動機(エントリーシート)を作成。
- 座談会やOB・OG訪問で社員の方に志望動機(エントリーシート)を添削してもらう。
ネットは情報があまりにも多く存在し、中には誤った内容の記載がある可能性もあるため、実際の社員の方に確認する機会を設けることがおすすめです。
自身の「良いところ」が会社でどう生かされるかを明確にする
どの企業にも共通している内容として、企業は「会社をよりよくしてくれる学生」の採用を希望しています。
そのため「強み」やガクチカを話すことで、面接官にしっかりと自身が将来会社で活躍していることを連想させることができたら、内定が一気に近づくこと間違いなしでしょう。
またエピソードに加え、話し方・話の聞き方や姿勢など外見的な要素も面接官に好印象を与えるうえで重要になります。
そのため「自身の良いところ」がいかに企業に合致しているかを、様々な形で表現できるようにしっかり準備しましょう。



さいごに
今回は「農学部生」の就職活動について解説してきましたが、いかがだったでしょうか?
記事の内容を簡単にまとめます。
- 農学部は「潰しの利く」学部。
- アグリテック・スマート農業など他業界と農業が融合する事業も多い。
- 農業だけでなく、食品・IT・製薬業界を志望する学生も少なくない。
- 農学部生は選べる職種も幅広い。
- 内定獲得のための志望動機のポイントをおさえることが重要。
農学部での学びは、農業系の企業ではもちろんのこと、IT業界や食品業界など多くの業界で役立たせることができます。
そして色んな選択肢があるからこそ、どの選択が一番自分に合っているかを徹底的に考えることが大切です。
自分に合った企業を見つけ、その企業から内定をもらえるように粘り強く行動していきましょう!
なお、自身に合っている業界・企業を選ぶための「自己分析・企業分析」のノウハウは下記で紹介しているため、ぜひ参考にしてみてください。