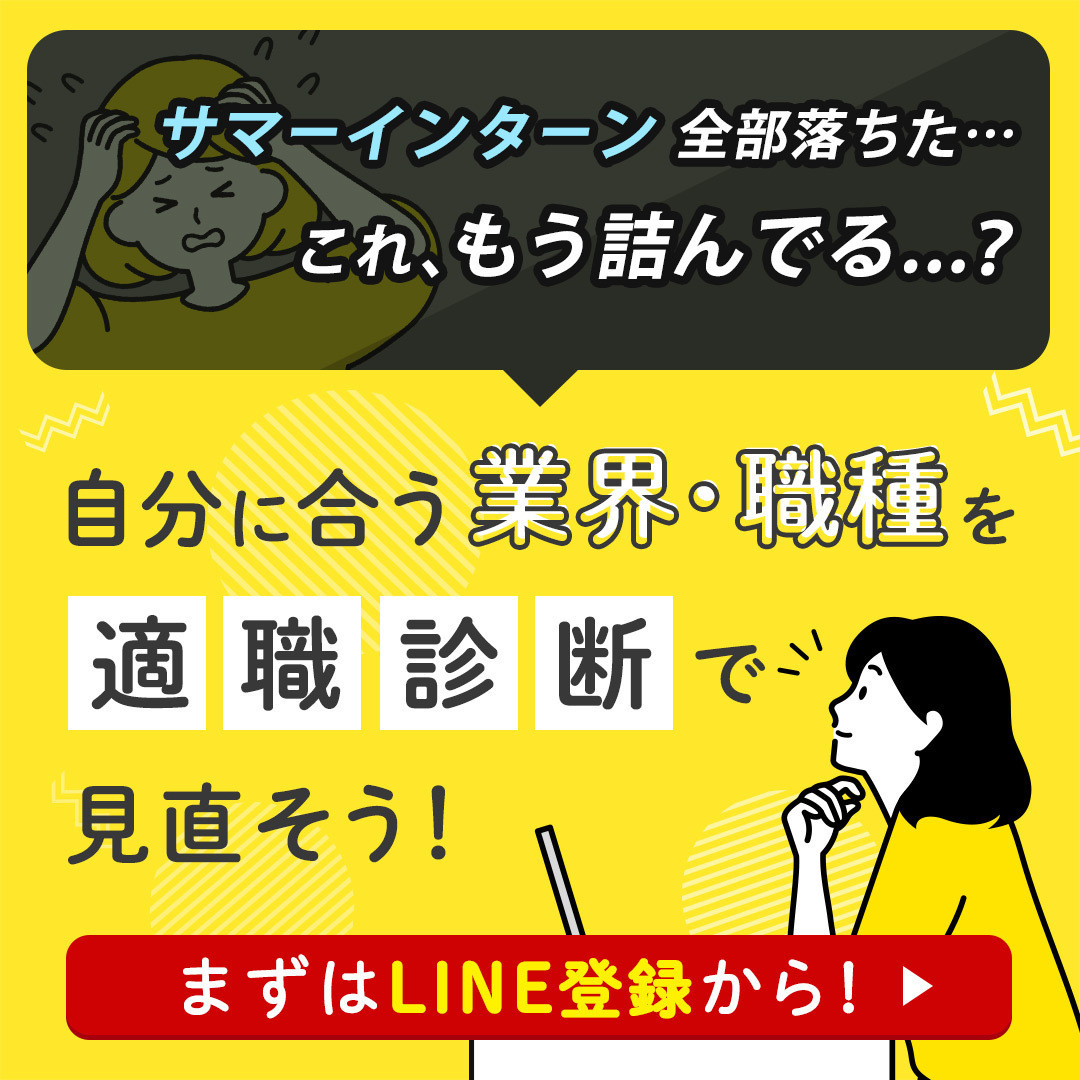【例題あり】SPI熟語の成り立ち頻出問題を瞬時に解くコツ5選
2024/9/27更新
はじめに
就活で内定を獲得するために突破しなければならない第一関門がSPI試験です。
なかでも「熟語の成り立ち」問題は、日本語の熟語に関する知識と理解を問われることから頻出の問題となっています。
本記事では、以下のような就活生に向けて、SPIの「熟語の成り立ち」問題に対する対策方法や解答のコツを具体的に紹介します。
- 熟語の成り立ち問題を素早く解けるようになりたい
- 熟語の成り立ち問題でできるだけ点を稼ぎたい
- 効率的な対策法や問題を解くコツを知りたい
さらに、熟語のパターンや例題、おすすめの勉強ツールなどを余すことなく紹介していきます。
本記事を読むことで、SPIの「熟語の成り立ち」問題に自信を持って臨めるようになりますので、ぜひ最後までご覧ください。
また、以下の記事でSPI試験について詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。
【言語/非言語/英語完全網羅】SPI初心者でも対策できる資料配布中!
SPIなどに自信がない。
SPIが原因で選考に進められない。
そんな学生のためにまとめたものがSPI頻出問題集です。
SPIの出題範囲である言語/非言語/英語といった問題を完全網羅しています。
丁寧な解説付きなので、今から勉強する人でも安心して取り組めます!
SPI「熟語の成り立ち」問題とは

SPIは、就職活動で広く使用される適性検査です。
なかでも、「熟語の成り立ち」問題はSPIの言語分野で出題され、日本語の熟語に関する知識と理解を問われる問題形式です。
与えられた熟語がどのように成り立っているのかを理解し、正しい解答を選ぶ必要があります。
また、「熟語の成り立ち」問題は、SPIの中でも比較的頻繁に出題される問題形式となっています。
この問題は、言語問題のはじめに出題されることが多いです。
SPI試験のスタートダッシュを切れるようにしっかりと対策しておきましょう。
SPI「熟語の成り立ち」に出る熟語一覧

SPIの「熟語の成り立ち」問題は以下の5つのパターンに分けることができます。
パターン
- 似た意味を持つ漢字を重ねた熟語
- 反対の意味を持つ漢字を重ねた熟語
- 主語と述語の関係にある熟語
- 動詞の後に目的語をおく熟語
- 前の漢字が後の漢字を修飾する熟語
パターンを知っておくことで、素早く解答することが可能となります。
以下で5つのパターンや例を紹介しますので、チェックしてください。
パターン1:似た意味を持つ漢字を重ねた熟語
まずはパターンの1つ目として、「似た意味を持つ漢字を重ねた熟語」があります。
これは例を見てもらったほうが早いので、以下で確認してみてください。
【似た意味を持つ漢字を重ねた熟語の例】
| 豊富、永久、禁止、生産、道路、岩石、隠蔽、柔軟、永久、恩恵、絵画、装飾、隔離、河川、崩壊、岩石、誤謬、陥没、緩慢、寒冷、奇怪、変換、犠牲、基礎、豊富、温暖、脅威、携帯、増加、堅固、減少、行進、幸福、娯楽、錯誤、山岳、思考、邪悪、赦免、出発、安穏、辛苦、辛酸、学習、選択、潜伏、隠匿、恥辱、超越、彫刻、墜落、停止、媒介、悲哀、比較、扶助、返還、妨害、幼稚、漏洩、老衰 など |
日頃はそこまで考えませんが、よく見ると似た意味の漢字が続くことにより、熟語を構成していますね。
似た意味を持つ漢字を重ねた熟語は、比較的わかりやすいので取りこぼさないようにしましょう。
複数回練習問題をこなし、間違ったものだけをチェックしてミスを繰り返さないようにすれば十分です。
パターン2:反対の意味を持つ漢字を重ねた熟語
次に「反対の意味を持つ漢字を重ねた熟語」のパターンです。
【反対の意味を持つ漢字を重ねた熟語の例】
| 因果、往復、強弱、呼応、虚実、首尾、真偽、開閉、緩急、乾湿、高低、出没、寒暖、吉凶、起伏、親疎、粗密、栄枯、及落、去就、左右、屈伸、苦楽、好悪、功罪、縦横、衆寡、授受、上下、送迎、損得、諾否、男女、抑揚、哀歓 など |
反対の意味を持つ漢字を重ねた熟語のパターンも得点しやすいといえるでしょう。
一つひとつの漢字の意味をしっかり押さえておくと解答しやすいです。
パターン3:主語と述語の関係にある熟語
次のパターンは「主語と述語の関係にある熟語」です。
「主語」「述語」というワードが出てくるのでとっつきにくく感じますが、ポイントを押さえれば迷わず解答できますよ。
【主語と述語の関係にある熟語の例】
| 骨折、人為、腹痛、天授、民営、官営、円高、円安、官製、日照、県立、国立、私立、市立、都立、日没、地震、神授、人造、頭痛、年少、年長、雷鳴 など |
漢字と漢字の間に「が」を入れて文章を作ってみましょう。
例えば骨折であれば、「骨が折れる」のようなイメージです。
違和感なく作ることができれば、主語と述語の関係にある熟語といえるでしょう。
パターン4:動詞のあとに目的語をおく熟語
パターンの4つ目が「動詞のあとに目的語をおく熟語」です。
パターン3と同様に、熟語を分解して文章を作ってみましょう。
【動詞のあとに目的語をおく熟語の例】
| 握手、越冬、読書、在宅、閲兵、徹夜、脱帽、登校、開門、避難、渡米、加熱、造幣、忍苦、観劇、潜水、求人、享楽、止血、修業、殉難、叙勲、除湿、洗顔、遭難、閉店 など |
先頭の文字に送り仮名を付け、後の漢字に「に」や「を」を付けてみるのがおすすめです。
握手であれば「手を握る」というように、動詞のあとに目的語がきていますね。
パターン5:前の漢字があとの漢字を修飾する熟語
最後は「前の漢字があとの漢字を修飾する熟語」です。
修飾語が登場し、ややこしそうなイメージを抱きますが安心してください。
以下でコツを紹介しているのでチェックしましょう。
【前の漢字があとの漢字を修飾する熟語の例】
| 辛勝、暗示、屋外、机上、直角、屋内、微笑、温泉、併記、概観、頻発、仮定、廉価、過程、奇遇、既成、貴賓、急逝、強風、曲線、虚像、深紅、偶発、鶏卵、新年、傑作、再会、猛獣、厳封、上空、後退、酪農、黒板、互譲、最悪、最高、実施、俊足、上流、直線、洋画、予知、和食 など |
これも「辛勝」というように、前の漢字があとの漢字を修飾しており、勝利の内容を読み取ることができます。
あとの漢字が「どのような状況なのか」という観点で考えてみると、スムーズに解答できるはずです。
このようにSPIの「熟語の成り立ち」問題は5パターンあります。
この5つのパターンを見抜ければ、正答に近づくわけです。
SPI熟語の成り立ち頻出問題を解くコツ5選

ここからは、「熟語の成り立ち問題」を瞬時に解く方法を5つ紹介します。
以下のコツを押さえれば、スピードや正答率を上げることができるので、しっかりチェックしてくださいね。
- 熟語の接頭辞や接尾辞の意味や役割に注目する
- 5パターンの熟語を把握する
- 1問10秒以内で回答する
- 過去問や問題集を使って熟語を覚える
- 熟語を日常の文章や会話で使いながら覚える
①熟語の接頭辞や接尾辞の意味や役割に注目する
SPIの「熟語の成り立ち」問題を解く際に、単語の接頭辞や接尾辞に注目してみましょう。
接頭辞は熟語の前に付けられ、接尾辞は熟語のあとに付けられます。
以下に接頭辞と接尾辞の例をいくつか挙げてみます。
- 「非(ひ)」:非常識、非常勤
- 「再(さい)」:再利用、再生産
- 「無(む)」:無意識、無知
- 「超(ちょう)」:超高層、超音速
- 「共(きょう)」:共感、共同
- 「的(てき)」:感情的、本格的
- 「化(か)」:国際化、変化
- 「者(しゃ)」:学者、読者
- 「性(せい)」:活動性、多様性
- 「度(ど)」:高度、重度
これらは、日本語の熟語でよく使われる接頭辞と接尾辞の一部です。
接頭辞は単語の前に付いて意味を変えたり、強調したりする役割を果たします。
また、接尾辞は単語の後ろに付いて、意味を補完したり、名詞を形容詞や動詞に変えたりする役割を担います。
したがって、単語の接頭辞や接尾辞に注目することで、SPI「熟語の成り立ち」問題における熟語の意味や構造をより正確に把握できるのです。
実際の文脈で使用される単語や熟語を読み取り、接頭辞や接尾辞の影響を考える練習を行うと、日常的に訓練することができますよ。
②パターンを把握する
先ほどもお伝えしたとおり、SPIの「熟語の成り立ち」問題は、前述した5パターンのいずれかを問う問題です。
この5パターンとそれに付随する熟語を覚えておくことで、素早く解答できるわけです。
ただし、熟語は無数に存在していますので、無理に暗記しようとせず、パターンを把握することを意識してください。
③1問10秒以内で回答する
SPIの「熟語の成り立ち」問題は、言語問題の最初に出題される問題です。
最初でモタモタしていると、あとの問題に費やす時間がなくなってしまいます。
つまり、速攻で抜け切る必要がありますので、熟語を見た瞬間に即決できるように日々鍛錬しておきましょう。
また、迷ってしまった場合は、いくら悩んでも同じです。
悩んだ場合は、割り切って次に進みましょう。
④過去問や問題集を使って熟語を覚える
SPIの「熟語成り立ち」問題は、意味や構造を理解できているかどうかで勝負が決まります。
したがって、「習うより慣れろ」的なアプローチが功を奏します。
そのために、日頃から1つでも多くの熟語に接点を持っておくことが大切です。
SPIの過去問や問題集で、なるべく引き出しを増やしておくようにしてください。
⑤熟語を日常の文章や会話で使いながら覚える
就活生は、SPIの学習やエントリーシート、面接対策など多忙を極めます。
そんな就活生におすすめなのが、熟語を日常の文章や会話で使いながら覚える方法です。
種類は問わないので、気になる熟語を日常の文章や会話の中で使ってみましょう。
熟語を使いながら覚えることで、その熟語の意味や使い方を実践的に学ぶことができます。
日常の文章や会話で使うことで、熟語が記憶に残りやすくなりますので、ぜひやってみてください。



SPI「熟語の成り立ち」の練習問題&解説

それでは、SPIの「熟語の成り立ち」問題の練習を通じて、熟語の成り立ち方に関する理解を深めましょう。
以下に5つの問題を用意しましたので、トライしてみてください。
また、最後に答えと解説を加えましたので、解き終わったら答え合わせを行っておきましょう。
それぞれの熟語の成り立ち方として、当てはまるものをA~Dの中から1つずつ選んでください。
【問題1】
熟語:絵画
A:反対の意味を持つ漢字を重ねる
B:主語と述語の関係にある
C:動詞の後に目的語をおく
D:上記のどれにも当てはまらない
【問題2】
熟語:悲喜
A:反対の意味を持つ漢字を重ねる
B:主語と述語の関係にある
C:動詞の後に目的語をおく
D:上記のどれにも当てはまらない
【問題3】
熟語:止血
A:反対の意味を持つ漢字を重ねる
B:主語と述語の関係にある
C:動詞の後に目的語をおく
D:上記のどれにも当てはまらない
【問題4】
熟語:頭痛
A:反対の意味を持つ漢字を重ねる
B:主語と述語の関係にある
C:動詞の後に目的語をおく
D:上記のどれにも当てはまらない
【問題5】
熟語:後退
A:反対の意味を持つ漢字を重ねる
B:主語と述語の関係にある
C:動詞の後に目的語をおく
D:上記のどれにも当てはまらない
【解答と解説】
| 問題 | 答え | 解説 |
| 問題1 | D | この熟語では、「絵」と「画」という漢字が同じ意味を持ちながら重ねられています。 |
| 問題2 | A | この熟語では、「悲」と「喜」という漢字が反対の意味を持ちながら重ねられています。 |
| 問題3 | C | この熟語では、「止」という漢字の後に「血」という漢字が置かれ、目的語の役割をはたしています。 |
| 問題4 | B | この熟語では、「頭」と「痛」という漢字が主語と述語の関係を表しています。 |
| 問題5 | D | この熟語では、「後」という漢字が「退」という漢字を修飾しています。 |
全問正解できましたか?
繰り返し練習し、パターンを覚えてしまいましょう。
おすすめの問題集とアプリを紹介

最後に、おすすめの問題集とアプリを紹介していきます。
SPI試験対策の問題集は数多く存在します。
自分の学習スタイルに合った問題集やアプリを利用し、効率的に学習を進めましょう。
これが本当のSPI3だ! 2026年度版
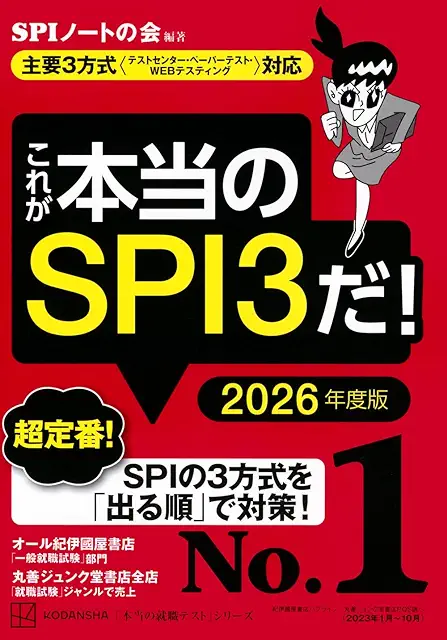
出典元:これが本当のSPI3だ! 2026年度版 | Amazon
ペーパーテスト、テストセンター、Webテスティングの3タイプの受検方法に対応しており、この一冊をこなすことで出題傾向を把握することができます。
さらに、解説が充実しているので、基礎的な国語や数学をしっかり学び直しにおすすめです。
2026最新版 史上最強SPI&テストセンター超実戦問題集
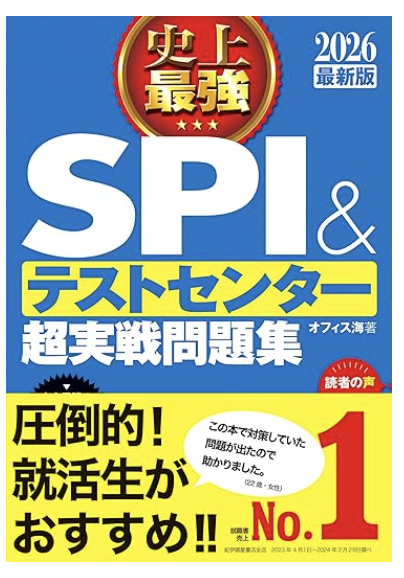
出典元:2026最新版 史上最強SPI&テストセンター超実戦問題集 | Amazon
「二語の関係」「文の並べ替え」「空欄補充」「長文読解」「英語【ENG】」等の言語能力分野での徹底した対策が可能です。
またスピードに特化した解法を紹介しており、実践を想定して学習するのであればおすすめの1冊といえるでしょう。
2026年版 ダントツSPIホントに出る問題集
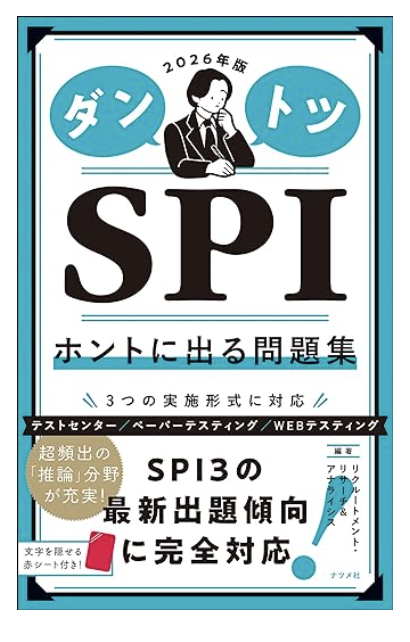
出典元:2026年版 ダントツSPIホントに出る問題集|Amazon
実際に出題されている問題を高い精度で再現。
頻出問題を1,067題収録するという圧倒的ボリュームで、試験突破をサポートしてくれます。
また、上記のようなボリュームを誇っているにも関わらず、コンパクトなサイズ感なので、通学時などでもしっかり学習することができるのでおすすめです。
SPI言語|しっかり解説の資格試験問題集

出典元:SPI言語|しっかり解説の資格試験問題集|App Store
本アプリは言語分野に特化したアプリとなっています。
「熟語の成り立ち問題」についても、しっかりと練習することができるのでおすすめです。
ミスした問題を重点的に復習することができる機能もついており、効率的に学習を進めることができるでしょう。
アプリ内で課金が発生するケースがあるので、利用機能と問題集を買う値段を比較して検討してください。
SPI言語・非言語就活問題集-適性検査SPI3対応-

出典元:SPI言語・非言語 就活問題集 -適性検査SPI3対応-|App Store
言語分野に特化したアプリではありませんが、このアプリを使えば総合的にSPI対策を行うことができます。
しかも無料で利用できるのでメリットは大きいです。
無料で利用できるので、試しにダウンロードしてみましょう。
さいごに
本記事では、SPIの「熟語の成り立ち」問題について解説しました。
熟語の成り立ちを理解するためには、記事内で紹介した5つのパターンをしっかり把握することが大切です。
また、「熟語の成り立ち」問題に対する対策としては、熟語の暗記やパターンの把握が重要なので、問題集やアプリを使って熟語の意味や成り立ちを繰り返し学習しましょう。
本記事で紹介した内容をしっかりと理解し、SPIの「熟語の成り立ち」問題に取り組むことで、解答の正確性やスピードを向上させることができますので、ぜひ活用してくださいね。