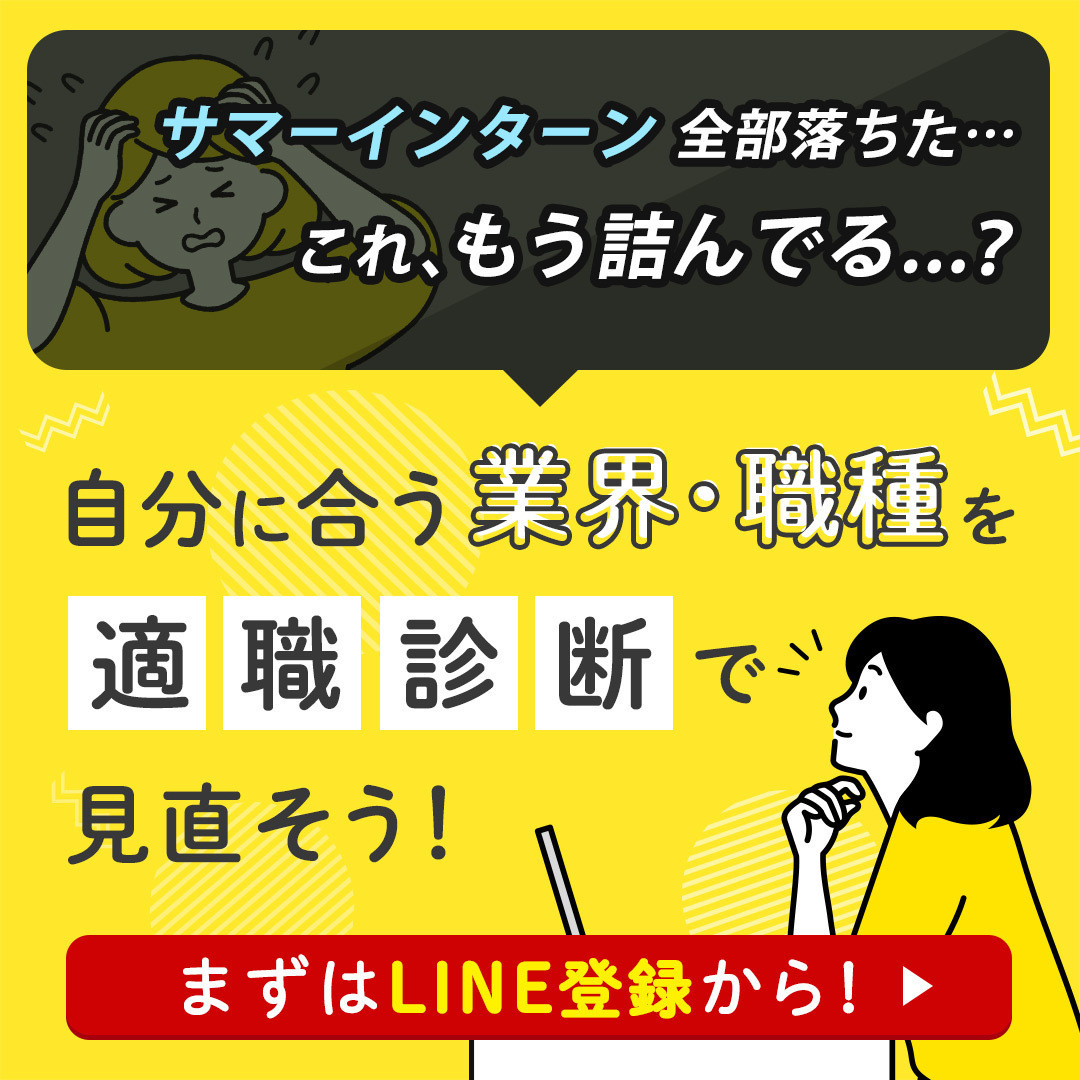「フレキシブルタイム」と「フレックス」をわかりやすく解説!
2024/9/27更新
はじめに
就職活動を進めていく中で、企業ごとの働き方の違いに気づくことが多いのではないでしょうか。
同じような業界や雰囲気の企業であっても、働き方や勤務時間の考え方には意外と差があるものです。
そのため、企業の働き方の多様性に驚く方も多いかもしれません。
そんな中で「フレキシブルタイム」という言葉を耳にしたことはありませんか?
「フレキシブルタイムとフレックの違いって一体何?」
と聞き慣れない言葉に対して、疑問を抱く方も多いのではないでしょうか。
そこでこの記事では、「フレキシブルタイム」の基本的な意味や特徴、「フレックスタイム制」との違いについて詳しく解説していきます。
- 就職活動中で、企業の働き方について理解を深めたい方
- フレキシブルタイムとフレックスタイムの違いを知りたい方
- 自分に合った働き方を探している方
- 企業の勤務制度や柔軟な働き方に興味がある方
- 働き方改革やワークライフバランスに関心がある方
- フレキシブルな勤務時間制度を導入している企業で働きたいと考えている方
ぜひ以下の記事もあわせてお読みください。
上京を志す地方学生ならジョーカツ!
あなたのキャリアを加速させるチャンス!
無料で利用できる快適な個室シェアハウス、
東京までの交通費サポート付き
首都圏の注目企業への就活ならジョーカツ
首都圏の学生ならスタキャリ!
理想のキャリアを実現へと導く第一歩!
あなたにピッタリのキャリアアドバイザーを選び、
自分にマッチする優良企業をご紹介
首都圏企業のES添削から面接対策まで、就活ならスタキャリ
フレキシブルタイムとフレックスの違い

フレキシブルタイムとは、フレックス制のなかにある始業・就業時間を自由に決められる時間帯のことをさします。
ここでは、それぞれがどういった意味を持つ言葉なのかを解説しますので、その違いを確認してください。
フレキシブルタイムとは?
フレキシブルタイムとは、フレックスタイム制において、従業員が自分の都合に合わせて始業・終業時刻を自由に決められる時間帯のことです。
フレックスタイム制の導入企業では、一般的にフレキシブルタイムが設けられていますが、企業ごとのルールによっては、フレキシブルタイムがない場合もあります。
フレキシブルタイムとフレックスタイム制の関係性
フレキシブルタイムとフレックスタイム制は、密接な関係にあります。フレックスタイム制とは、一定期間の総労働時間を満たす限り、従業員が日々の始業・終業時刻や労働時間を自分で決められる制度です。
フレックスタイム制と聞くと、「勤務時間すべてを自由に決められる」と誤解する人もいるかもしれません。
しかし、多くの場合、フレックスタイム制には「コアタイム」と呼ばれる、必ず勤務しなければならない時間帯が存在します。
このコアタイムを除いた、従業員が自由に働ける時間がフレキシブルタイムです。
つまり、フレキシブルタイムこそが、フレックスタイム制の真髄といえるでしょう。
ただし、コアタイム・フレキシブルタイムの概念がない「スーパーフレックス制」という制度も存在します。
しかし、多くの日本企業で導入されているフレックスタイム制は、完全に自由な勤務時間とはいえないのが現状です。
働き方改革については、ぜひ以下の記事もあわせてお読みください。
フレックスタイム制にフレキシブルタイムが導入される理由
では、なぜフレックスタイム制にはフレキシブルタイムが設けられているのでしょうか。
フレキシブルタイムが導入される理由を2点紹介します。
- 勤務時間を自由に選択できるようにするため
- MTGなどに支障が出ないようにするため
①勤務時間を自由に選択できるようにするため
フレキシブルタイムの導入により、従業員は自身のライフスタイルや業務状況に合わせて、勤務時間を柔軟に調整できます。
多くの場合、フレキシブルタイムは始業時と終業時の両方に設定され、日中のコアタイムと呼ばれる必須勤務時間帯を除き、自由に時間を管理できます。
フレキシブルタイムを活用すれば、始業時間を遅らせたり、終業時間を早めたりすることが可能です。
ただし、月間の総労働時間が所定の基準を満たすよう、各自が責任を持って業務を管理する必要があります。
②会議に支障が出ないようにするため
フレキシブルタイムが設定されているということは、同時にコアタイムも設定されているということです。
フレックスタイム制において、時間をこのように分けているのは、部署やチーム、そして顧客とのコミュニケーションを円滑に進めるためです。
スーパーフレックスタイム制のように、すべての勤務時間を自由に選択できる制度は、従業員にとって自由度が高く魅力的に映るかもしれません。
しかし、会議などの全員参加が必須のイベントを調整することが難しくなり、結果としてコミュニケーションに支障をきたす可能性があります。
このような問題を避けるため、必ず業務を行う必要があるコアタイムと、自由に勤務時間を選択できるフレキシブルタイムを設けることで、勤務時間の自由度を確保しつつ、組織としてのまとまりを維持できるよう工夫されているのです。
フレキシブルタイムとフレックス「働き方」の違いとは
ここまでフレキシブルタイムについて詳しく解説してきましたが、フレキシブルタイムの有無によって、実際の働き方はどのように変わるのでしょうか?
具体的な例を挙げて、フレキシブルタイムがある場合とない場合の働き方の違いを比較してみましょう。
フレックスタイム制を導入していない場合
フレックスタイム制を導入していない企業では、フレキシブルタイムという概念がないため、全従業員が一斉に始業することが求められます。
終業時間も明確に定められており、それを超えて働く場合は残業扱いとなります。
全員が同じ時間帯で勤務するため、コミュニケーションにかかる負担や配慮を最小限に抑えることができます。
このような勤務形態では、1日の勤務時間が7.5~8時間であることが一般的です。
決められた時間内は業務に集中することが求められるため、休憩時間も12~13時など、特定の時間帯に固定されていることが多いです。
勤務時間が固定されていることで、毎日の生活リズムを一定に保てるというメリットがあります。
特に新入社員にとっては、決められた時間で働くことで、社会人としてのリズムを早く掴める可能性があります。
また、管理職にとっても部下が全員同じ時間帯で働いているため、労働時間を細かく管理する必要がなく、負担を軽減できます。
スーパーフレックスタイム制の場合
スーパーフレックスタイム制では、勤務時間全体がフレキシブルタイムとなるため、自分の好きな時間に働くことが可能です。
言い換えれば、コアタイムという概念がないため、従業員によって働く時間が大きく異なることが予想されます。
1日の勤務時間を短く抑える日と長く働く日を組み合わせる人や、一見フレックスタイム制には見えないような一定の勤務時間で毎日働く人もいるでしょう。
そのため、「全員を同じ時間に集めて会議をする」といったことが難しくなる可能性があります。
全員の勤務時間が揃うよう調整する必要が生じるため、コミュニケーションの負担が増える可能性があることを理解しておきましょう。
また、管理職にとっても、部下の勤務時間を管理しにくくなるため、個別に詳細な業務報告を求めるケースも出てくるかもしれません。
自由には責任が伴うことを理解し、自分に合った制度を見極めることが重要です。
フレキシブルタイムを導入している企業の特徴

では、フレキシブルタイムを導入している企業にはどのような特徴があるのでしょうか。
ポイントとなるのは以下の点です。
- 柔軟な姿勢で働き方を変化させている
- リモートワークがしやすい
- 管理職とメンバーの信頼関係がある
①柔軟な姿勢で働き方を変化させている
フレキシブルタイム、つまりフレックスタイム制を導入している企業は、働き方に対して柔軟な姿勢を持っていることが多いです。
従業員が働きやすい環境づくりに積極的に取り組み、効果的な制度があれば積極的に導入する傾向があります。
「企業の姿勢を見極めるにはどうすればいいの?」と疑問に思うかもしれませんが、企業説明会や求人情報を確認してみるのがおすすめです。
フレックスタイム制に限らず、福利厚生や各種手当が充実している企業は、フレキシブルタイムを導入している可能性が高いでしょう。
②リモートワークがしやすい
積極的にリモートワークを導入している企業も、フレキシブルタイムを採用している可能性が高いといえます。
フレキシブルタイムは、出社が多い企業では通勤ラッシュを避けるなどのメリットがありますが、リモートワークと組み合わせることで、さらに勤務時間の自由度が高くなるのです。
リモートワークでは、いつもより少し長く家事をしてから仕事を始めるなど、多様な働き方が可能になります。
そのため、リモートワークを導入している企業は、フレキシブルタイムも導入している可能性が高いといえるでしょう。
ただし、近年はコロナ禍の影響で、多くの企業がリモートワークを導入しています。
リモートワークの有無だけで判断せず、本当にフレキシブルタイムが導入されているか、しっかりと確認することが大切です。
③管理職とメンバーの信頼関係がある
フレキシブルタイムは従業員にとって大きなメリットがありますが、管理職にとっては部下の勤務時間管理という新たな負担が生じます。
特にリモートワークと組み合わせる場合、部下の勤務状況を常に把握できないため、管理職とメンバーの間には確かな信頼関係が不可欠です。
「常に見張っていなくても、責任感を持って働いてくれる」
「自分で時間を管理し、質の高い成果を出してくれる」
このような信頼関係がなければ、フレックスタイム制はうまく機能しません。
管理職とメンバーの関係がフラットで、成果を重視した評価制度を導入している企業は、フレックスタイム制を導入している可能性が高いといえるでしょう。
フレックスタイム制で働く際の注意点
フレックスタイム制は、従業員の自律性と柔軟性を高める一方で、いくつかの注意点も存在します。
- コミュニケーション不足になる
- 業務管理が難しくなる
- 孤独感や孤立感を感じやすい
それぞれの内容を詳しくみていきましょう。
①コミュニケーション不足になる
フレックスタイム制では、従業員の出社・退社時間がばらばらになるため、顔を合わせる機会が減ります。
よってチーム内のコミュニケーションが不足しがちになる点がデメリットです。
重要な情報共有の遅れや、連携がうまく取れずに業務効率の低下につながります。
特に、急な会議や相談が必要な場合、全員の予定を調整するのが難しく、迅速な対応が困難になることも考えられます。
②業務管理が難しくなる
管理職にとっては、従業員一人ひとりの労働時間を正確に把握し、適切に管理することが難しくなります。
これもデメリットのひとつです。
フレックスタイム制では、従業員が自分の裁量で働く時間を決めるため、従来のような一律の管理体制では対応できません。
また、個々の進捗状況の確認や評価も、従来の勤務体制に比べて、よりきめ細やかな配慮と工夫が必要となるでしょう。
③孤独感や孤立を感じやすくなる
フレックスタイム制を利用して、コアタイム以外に働く従業員は、ほかの従業員との交流が減り、孤独感や孤立感を抱く可能性があります。
会社においては、チームの仲間と一緒に仕事をしていくことがモチベーションを保つひとつの要素ともなりえます。
フレックスタイム制でチームで働く一体感や会社への帰属意識が薄れることで、モチベーションの低下や最悪の場合、離職につながることも懸念されるでしょう。
特に、新入社員やコミュニケーションを重視する従業員にとっては、大きなストレスとなる可能性があります。
フレックスタイム制が向いている人
フレックスタイム制は、働く時間帯を自分で調整できるため、特定のライフスタイルやワークスタイルを持つ人に向いています。
以下に、フレックスタイム制が特に向いていると考えられる人を4つのタイプにまとめ、解説します。
- 自己管理能力が高い人
- ライフスタイルにあわせて働きたい人
- 集中しやすい時間帯に働きたい人
- 通勤ラッシュを避けたい人
自己管理能力が高い人
フレックスタイム制では、労働時間を自分で管理し、業務の進捗状況を把握しながら働く必要があります。
締め切りを守り、計画的にタスクをこなせる自己管理能力の高い人が、この制度を最大限に活用できるでしょう。
例えば、集中力が高い時間帯に重要なタスクを割り当てたり、休憩時間や終業時間を調整してプライベートの予定を組み込むなどの能力が必要です。
主体的に時間を管理することで、効率的かつ充実した働き方を実現できます。
ライフスタイルにあわせて働きたい人
フレックスタイム制は、育児や介護、趣味、自己啓発など、仕事以外の時間を大切にしたい人にとって最適な制度です。
自分のライフスタイルにあわせて働く時間帯を調整できるため、ワークライフバランスを実現しやすくなります。
朝に家事を済ませてからゆっくり出社したり、子どものお迎えにあわせて早めに退社したり、空いた時間に資格取得の勉強をするなどが可能です。
フレックスタイム制は多様な働き方をサポートします。
集中しやすい時間帯に働きたい人
朝型、夜型など、人によって集中しやすい時間帯は異なります。
フレックスタイム制であれば、生産性が高い時間帯に仕事をすることで、効率的に業務を進めることがで可能です。
例えば、朝早く出社して静かなオフィスで集中して作業したり、夜遅くまで残業してクリエイティブな仕事に取り組んだり、自分のパフォーマンスが最大限に発揮できる時間帯を選ぶことができます。
通勤ラッシュを避けたい人
フレックスタイム制を活用すれば、混雑する通勤ラッシュの時間帯を避けて出社・退社できます。
満員電車でのストレスを軽減し、快適に通勤したいと考えている人にとって、最適な選択肢です。
例えば、少し早めに家を出てカフェで朝食を摂ってから出社したり、遅めの出社で混雑を避けたり、フレックスタイム制は通勤のストレスを軽減してくれるでしょう。
心身ともに健康な状態を保つのに役立ちます。
上記以外にも、フレックスタイム制が向いている人はたくさんいます。
企業の制度や自身の状況をよく理解し、フレックスタイム制が自分に合っているかを見極めることが大切です。
よくある質問
最後に、フレキシブルタイムについて多く寄せられる質問とその回答をご紹介します。
フレキシブルタイムは企業によって異なる?
フレキシブルタイムは、企業によって設定されている時間が異なります。具体的な例を見てみましょう。
| A社の場合 | B社の場合 | |
| フレキシブルタイム | 7:00~10:00 15:00~20:00 | 7:00~11:00 14:00~20:00 |
| コアタイム | 10:00~15:00 | 11:00~14:00 |
A社とB社では、フレキシブルタイムとして設定されている時間帯の幅が大きく異なることがわかります。
この時間設定は、企業規模や特定の職種の従業員数など、さまざまな要因によって異なるもの。
例えば、エンジニアなど夜間に業務を行うことが多い職種が多い企業では、遅めの始業時間を許可したり、コアタイムを短く設定する傾向があります。
「コアタイムは長いほうが良いのか?」と疑問に思う人もいるかもしれません。
コアタイム周辺は多くの従業員が働いている時間帯であるため、実際の勤務時間にはそれほど大きな影響を与えないことが多いです。
重要なのは、コアタイムやフレキシブルタイムの有無そのものだと捉え、制度全体を評価することが大切です。
新入社員でもフレキシブルタイムを駆使できる?
フレキシブルタイムという制度があっても、入社したばかりの新入社員がそれをフル活用するのは難しいでしょう。
前述の通り、フレックスタイム制は企業と従業員、そして上司と部下の間に信頼関係があるからこそ成り立つ制度です。
新入社員は、まだ仕事を任せてもらえる立場ではなく、信頼関係は時間をかけて築いていくものだといえます。
そのため、入社直後にフレックスタイム制をフル活用しようと焦るのではなく、「自分の業務を完了させるのに必要な時間」や「求められた成果に対して適切な仕事ができているか」といった基準で勤務時間を判断することが大切です。
業務に慣れてくれば、「自分にとって快適な勤務時間」も見えてくるはずです。
まずは焦らず、成果を出すことに集中して社会人生活をスタートしましょう。
さいごに
「フレキシブルタイム」とは何か、そして「フレックスタイム制」との関係性など「違い」についてを詳しく解説してきました。
フレキシブルタイムとは、フレックスタイム制において、従業員が自分の都合に合わせて始業・終業時刻を自由に決められる時間帯のことです。
そのなかで必ず勤務しなければならない時間帯を「コアタイム」と呼びます。
フレキシブルタイムが導入されている企業は、働き方に対する自由度が高いといえます。
もちろん、企業を選ぶ際には、働き方だけで判断することはできません。
自分が働きやすいと感じる環境をイメージしながら、理想の企業を探してみるのも良いでしょう。
この記事を参考に、適切な働き方のできる企業をみつけてみてください。