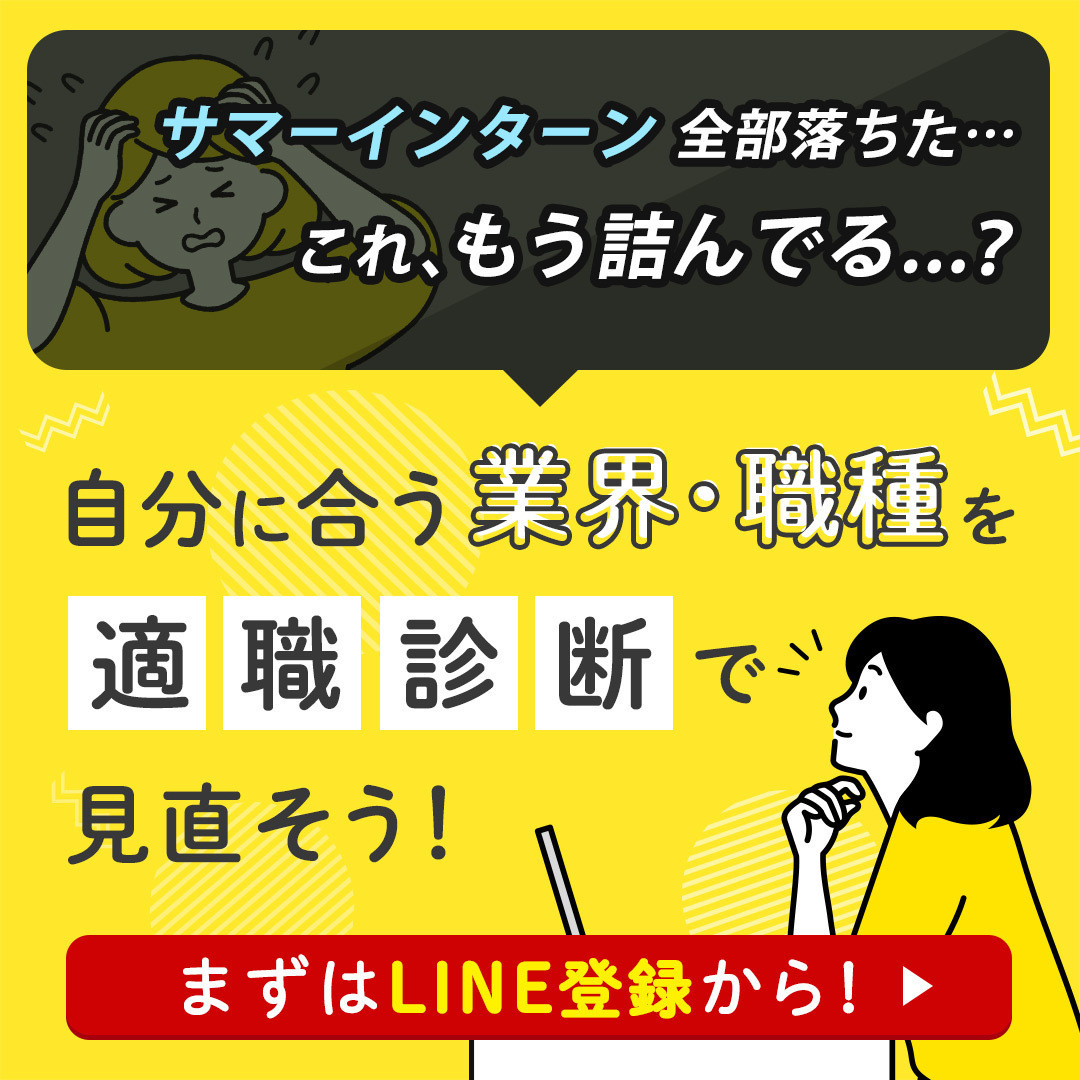【決定版】就活に必須の8業界総覧と志望業界を決める際のポイント3つ
2023年11月28日更新
はじめに
業界選びは就職活動の最初のステップで、自分の将来のキャリアに大きく影響します。
しかし、業界という言葉は聞いたことがあっても、具体的にどんなものなのかわからない方も多いのではないでしょうか。
本記事では、あなたのキャリアにとって最適な業界や企業を見つけるための業界研究のやり方と、志望業界を決めるポイントを解説します。
最後まで読み進めることで、自分に合った業界を見つけるヒントが得られるでしょう。
業界とは?
「業界」とは、同じ種類の事業やサービスを提供する企業群のことを指します。
例えば、電通株式会社は「サービス業」という業種に属しながら「広告業界」と呼ばれ、トヨタは「輸送用機器業」という業種に属しながら「自動車メーカー業界」と呼ばれます。
就活生の業界一覧
業界は、「メーカー」「商社」「小売」「金融」「サービス」「ソフトウエア・通信」「広告・マスコミ」「官公庁・公社・団体」の8つに大別することができます。
業界によって、就職活動の難易度や競争率、待遇や働き方などが異なります。
自分の適性や興味、将来の目標などを考えながら、業界の特徴や動向を調べることが大切です。
| 業界 | 役割 | 分類 |
| メーカー | モノを作る | 自動車、家電、食品、医薬品、鉄鋼、繊維、電子部品、OA機器、医療機器、プラント設備 |
| 商社 | モノを動かす | 総合商社、専門商社 |
| 小売 | モノを売る | 百貨店、スーパーマーケット、コンビニエンスストア、オンラインショップ |
| 金融 | お金を動かす | 銀行、証券、保険 |
| サービス | 形のないものを売る | 旅行、教育、建設、土木、人材、運送 |
| ソフトウエア・通信 | 情報技術を売る | ソフトウェア、インターネット、通信 |
| 広告・マスコミ | 情報を売る | 広告、放送、新聞、出版 |
| 官公庁・公社・団体 | 公的な事業を行う | 裁判所、国会、日本銀行、公社、経団連、政治団体 |
就活生の業界ランキング
2024年3月卒業予定の約2,000名弱の全国大学4年生及び院2年生を対象に、就職先として前向きに検討されている業界のTOP10を見てみましょう。
これらの業界の評価は、日本だけでなく世界的なトレンドや経済動向、技術進化、環境意識の高まりなど、多様な要因に影響されています。
それぞれの業界が注目されている背景や理由を記載していますので、興味のある分野を見つけるための参考としてください。
①ソフトウエア・情報処理・ネット関連
- 世界的に進むデジタルトランスフォーメーションの流れの中で、ソフトウェア開発や情報処理、インターネットサービスへの需要が高まっています。
- AI、ビッグデータ、IoTなどの新技術がビジネスモデルを変革し、新たな雇用を生み出しています。
②食品・農林・水産
- 食品安全や国産食材への関心の高まりが、この業界への評価を高めています。
- 農林水産業は、地方創生や環境保全などの課題に取り組むことで、社会貢献ややりがいを感じられます。
③官公庁・公社・団体
- 公務員や公的機関は安定した雇用と良好な労働条件が期待でき、長期的なキャリア形成が可能です。
- 公的セクターでの仕事は、社会貢献や公共の福祉に直結しており、社会的意義が高いです。
④精密・医療機器
- 高齢化社会を迎えた日本では、医療技術の進歩が求められており、医療機器やヘルスケア分野への投資が増加しています。
- 精密機器や医療機器は、高度な技術力や専門性が求められる分野であり、やりがいや成長性が感じられると考えられています。
⑤通信
- 通信インフラの重要性が認識され、リモートワークやオンライン教育の普及で、通信インフラへの依存度が高まっています。
- 5Gなどの新しい通信技術の導入がビジネスや生活に革新をもたらすと期待されています。
⑥銀行・証券
- 不安定な経済状況の中で、金融業界の安定性が再評価されています。
- フィンテックの発展により、伝統的な金融業界にも新たなイノベーションの動きが期待されています。
⑦繊維・化学・ゴム・ガラス・セラミック
- 伝統的な製造業が新技術を取り入れ、新しい材料や製品を開発している点が評価されてます。
⑧電子・電子機器
- 日本の電子業界は高い技術力と製品品質で知られており、就職先としての魅力があります。
⑨鉄道・航空
- 交通インフラは日本経済にとって不可欠であり、常に需要のある安定した職業として認識されています。
⑩自動車・輸送用機器
- グローバル競争の中で、日本の自動車産業は世界市場で強い競争力を持っており、安定したキャリアを求める就活生にとって魅力的です。
業界研究の重要性とやり方
ここからは、業界研究の重要性と、そのやり方について解説していきます。
業界研究を行うことで、具体的に以下のようなメリットがあります。
メリット1. 自分に合った業界や企業を見つけることができる
業界研究をすることで、自分の適性や興味、価値観などと業界や企業の特徴を照らし合わせることができます。
自分に合った業界や企業で働くことで、仕事に対するモチベーションや満足度が高まり、キャリアの発展にもつながります。
メリット2. 選考で有利になることができる
業界研究をすることで、業界の現状や課題、将来性などを理解することができます。
これらの知識は、選考での志望動機や自己PR、面接などで役立ちます。
業界に関する知識や関心を示すことで、企業に対する熱意や適性をアピールすることができ、採用担当者の印象にも残りやすくなります。
メリット3. 就職後の活躍にも役立つことができる
業界研究をすることで、業界の動向や競合他社の情報、顧客のニーズなどを把握することができます。
これらの情報は、就職後の業務にも役立ちます。
業界の状況に応じて柔軟に対応したり、自社の強みや差別化を考えたり、新しい提案や改善策を考えたりすることができます。
業界研究を行うには、以下の4つのステップを踏むことがおすすめです。
ステップ1. 業界の種類や特徴を把握する
業界は大きく分けて8つの業種に分類することができ、それぞれの業種には、さらに細かい業界が存在します。
業界の種類や特徴を把握することで、自分が興味を持つ業界や、自分に合う業界を見つけやすくなります。
業界の種類や特徴を把握するためには、インターネットや書籍、業界団体のホームページなどの情報源を活用しましょう。
ステップ2. 業界のビジネスモデルを理解する
次に、興味のある業界のビジネスモデルを理解することが重要です。
ビジネスモデルとは、業界や企業がどのように収益を得ているか、どのような価値を提供しているか、どのような顧客やパートナーと関係を築いているかなどを表す概念です。
ビジネスモデルを理解することで、業界や企業の強みや弱み、戦略や方針、競争環境や市場規模などを把握することができます。
ビジネスモデルを理解するためには、企業のホームページやIR資料、業界レポートやニュースなどの情報源を活用しましょう。
ステップ3. 業界の課題や将来性を考える
さらに、業界の課題や将来性を考えることも大切です。
業界の課題とは、業界が直面している問題や課題、改善すべき点などを指します。
業界の将来性とは、業界の成長の見込みや可能性、変化の方向性などを指します。
業界の課題や将来性を考えることで、業界に対する関心や志向を深めることができます。
また、業界の課題や将来性に対する自分の考えや意見を持つことで、選考での志望動機や自己PR、面接などで差別化することができるでしょう。
業界の課題や将来性を考えるためには、業界団体や専門家の意見、業界の動向やトレンド、社会的なニーズや問題点などの情報源を活用しましょう。
ステップ4. 業界の働き方や待遇を比較する
最後に、業界の働き方や待遇を比較することも必要です。
業界の働き方とは、業界で働く人の勤務時間や休日、残業や転勤の有無、働き方の多様性や柔軟性などを指します。
業界の待遇とは、業界で働く人の平均年収やボーナス、福利厚生や昇給・昇進の制度などを指します。
業界の働き方や待遇を比較することで、自分の希望するライフスタイルやキャリアプランと合致する業界や企業を見つけることができます。
志望業界を絞る3つのポイント
業界研究のメリットとやり方については、前章で説明しましたが、具体的にどのようにして志望業界を決めるべきでしょうか。
ここでは、志望業界の決め方とそのポイントについて、3つの観点から解説します。
①志望業界は早期に決定する
業界を知ることは就活において重要ですが、それだけに時間を費やすのは得策ではありません。
なぜなら、就活の準備には、業界研究の他にも、企業研究や志望動機の作成、適性検査やES、面接など、多くの課題があるからです。
また、早期に決定することで、後から別の業界に興味が出ても、柔軟に対応できるというメリットがあります。
焦る必要はありませんが、志望業界を絞り込む意識を持つことが大切です。
②安易に絞り込み過ぎない
一方で、業界を絞り込む際には、あまり狭くしないことも重要です。
業界を絞り込み過ぎると、就活が上手くいかなかった場合に、選択肢がなくなってしまう可能性があります。
そのような場合には、「A業界がダメでも、B業界がある」というように、別の業界に目を向けることができれば、精神的にも余裕が持てますし、リスクを分散できます。
また、一つの業界に固執すると、その業界の研究や応募に時間を取られてしまい、他の業界についての知識や情報が不足してしまうこともあります。
もし、一つの業界の就活がうまくいかなかった場合には、別の業界についての研究や応募を一から始める必要があり、時間的にも労力的にも負担が大きくなります。
自分が志望する業界に集中することは大切ですが、もしものために選択の幅を広げておくことも、戦略的に有効です。
③「業界」×「職種」の視点を持つ
就活を進めるにあたっては、「業界」だけでなく、「職種」も考慮する必要があります。
近年は、企業側も欧米型のJOB型雇用を取り入れたインターンシップや採用活動を行っているケースが増えています。
JOB型雇用とは、特定の分野や職種に特化した採用の仕方で、これまでの「総合職」や「一般職」という区分ではなく、「職種」という概念で採用する形態です。
職種とは、営業、人事、経理、開発など、仕事の種類を指します。
このような採用環境の変化に対応するためには、学生側も業界だけでなく、職種についても意識しておく必要があります。
自分がどのような仕事をしたいのか、自分に合った職種は何なのか、ということを考えることが求められます。
さらに、将来的に転職を視野に入れている学生も多いと思います。
転職では、これまでの経験やスキルといった「キャリア」が査定されます。
その際に、「業界経験」でアピールするのか、「職種経験」でアピールするのか、どちらかを軸に転職活動を行う必要があります。
したがって、自分のキャリアプランを逆算して考えるときには、「業界」と「職種」という両面を意識することが重要です。
就活の段階から、それらを見据えて志望業界を決めることが賢明です。
以上の3つのポイントを踏まえて、志望業界を決めることができれば、就活の成功率は高まるでしょう。
自分の適性や目標に合った業界を見つけるために、ぜひ参考にしてください。
まとめ
以上、本記事では8つの業界を紹介するとともに、業界を知るメリットや志望業界を決める際のポイントを3つ解説してきました。
記事内でも説明してきましたが、業界を絞り込むときは、自身の先入観や思い込みだけで狭く絞り込むのではなく、業界の全体像を把握した上で絞り込むことがポイントになります。
たとえば、「業界地図」という書籍では、業界全体を網羅したうえで、集約的にポイントを押さえてまとめられているので、効率の良い業界研究が可能になります。
「広く捉えて、深く掘る」、志望する業界が決まったら、深く掘って欲しいと思います。
本記事を起点として、業界研究の足掛かりになれば、幸いです。
今回も最後までお読み頂き、ありがとうございました。