【必見】インターンの応募社数を目的から割り出す逆算法
2024/9/9更新
はじめに
インターンの応募社数の平均は「7社」です。
周りの同級生がインターンに応募したと聞くにつけ、
「何社ぐらいインターンに参加したらいいの?」
「たくさんインターンに応募すると手一杯になるし…」
「そもそもインターンに参加しないといけないの?」
とザワザワと何とはなしに焦りますよね?
マイナビの「2023年卒大学生インターンシップ調査~中間総括~」によると、マイナビ2023会員のうち「2023年春」に卒業予定の大学生・大学院生が平均7.0社のインターンシップ・1Day仕事体験に応募しているという調査結果が明らかになっています。
一方で、実際に参加した社数が4.4社なので、応募した会社のうち半分以上のインターンに参加していることがうかがわれます。
さて、この数字をみて
「みんながそれぐらい応募するなら、オレ(私)も7社ぐらい応募しよう!!」
と考えている人は考えが浅いです。
それは、「インターンの目的」がおざなりになっているからです。
そもそも何社に応募するかは目的によって異なり、目的が曖昧で周りの動向になびいて何の気なしにインターンに応募するのは、かなり危険です。
そこで本記事では、インターンの応募について下記内容を解説していきます。
- 長期・短期インターンごとの適切な応募者数
- インターンが開催される目的
- インターンを探す方法
「事前に知っておいて良かった」と胸を撫で下ろす状態になりますので、10分ぐらいで最後までお読みくださいね。
上京を志す地方学生ならジョーカツ!
あなたのキャリアを加速させるチャンス!
無料で利用できる快適な個室シェアハウス、
東京までの交通費サポート付き
首都圏の注目企業への就活ならジョーカツ
首都圏の学生ならスタキャリ!
理想のキャリアを実現へと導く第一歩!
あなたにピッタリのキャリアアドバイザーを選び、
自分にマッチする優良企業をご紹介
首都圏企業のES添削から面接対策まで、就活ならスタキャリ
これだけ違う企業側と学生側のインターンの意味
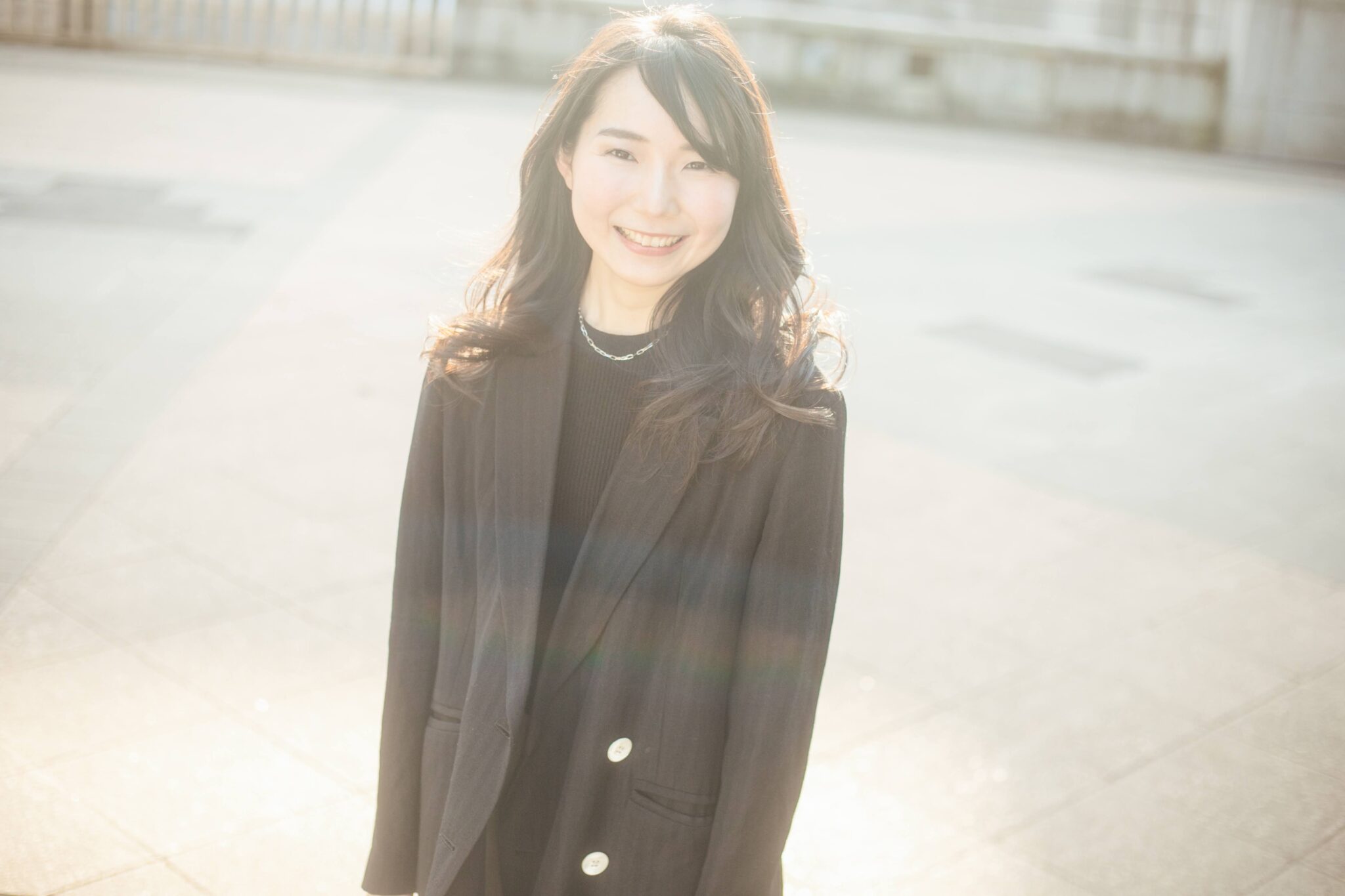
まずはインターンを主催する企業側と参加する学生側では、目的がまったく異なるので、そこから押さえておきたいと思います。
企業側がインターンを行う意味
企業がわざわざ人件費や労力を投入して、学生と接触する機会であるインターンを開催する目的は大きく2つあります。
学生の職業体験を実現するという謳い文句は表面的で、真の目的は下記の2つです。
- 優秀層の早期囲い込み
- 企業の広報活動
1つ目の「優秀層の囲い込み」ですが、特にサマーインターンなどの長期インターンが象徴的です。
インターンという合法的な名目を使って学生の連絡先を入手しておき、実際に仕事をやらせたりして、いわゆる「できる人材」を早期に見極め、内定まで囲い込むという目的です。
なかにはインターンが選考になっている会社もあり、そもそもインターンに参加しないと内定をゲットできないというケースもあります。
次に「企業の広報活動」です。
企業側としてはできるだけたくさんの学生に本番でエントリーしてもらい、できるだけ効率的に優秀層を採用したいという思惑があり、そのために会社をより多く学生に知ってもらう必要があるため、インターンがその広報活動の一環として使われています。
やはり、就活サイトでの広報は文字情報に終始し、どの会社も似たような情報なので埋没してしまう危険性があります。
一方で、インターンであれば実際に顔を突き合わせながら、リアルで話ができるので記憶に残りやすく、親近感が醸成されるのでエントリーしてもらえる確率が高まるわけです。
要は、インターンは企業側が学生に顔を売る絶好の場なのです。
学生側がインターンに参加する意味
次に学生側がインターンに参加する意味について考えていきましょう。
先ほどの調査では「時間が取れなかった」、「選考対策ができなかった」などの理由で、11.4%の学生がインターンに応募していない結果となっています。
別にインターンに参加しなくても、内定をゲットしている学生はいます。
なのになぜ、あなたはインターンに参加するんですか?
インターンに参加する意味は人によって違うと思いますが、主に下記内容が多くの学生に当てはまるでしょう。
- 色々な業種の理解が深まるから
- 自分の適性がわかるから
- 第1志望の会社の雰囲気を知りたいから
- 本選考に向けて練習になるから
- インターンに参加しないと内定がもらえないから
- 採用担当者に顔を覚えてもらいたいから
あなたがインターンに参加する目的は何ですか?
これから説明する応募社数にも関連してきますので、あなたにとってのインターンの意味を把握しておいてください。
インターンの種類
次に、インターンと一言で言っても「長期」と「短期」のインターンにわかれ、それぞれ開催される目的が異なってきますので、理解を深めておきましょう。
- 長期インターンの目的
- 短期インターンの目的
長期インターンの目的
長期インターンとは、1〜3カ月間、その会社で働いてみるインターンで、なかにはそれ以上の期間の場合も珍しくありません。
普通の社会人のようにフルタイムで働くわけではなく、週に数回とか、学業に影響が出ない土日や大学の合間を縫って行われます。
ただし、企業は通常「平日朝~夕方」で通常業務を行い、インターン先によっては大学を休んででもインターンに来るように要請される場合があるため、受入れ先によっては学業に支障が出ることがある点に注意しましょう。
また、長期インターンの場合は「給料」が出ることが多いです。
最近では有給のインターンに学生が集まりやすい傾向があり、採用活動にもプラスに働くため、先行投資として企業側も給料を出す会社が増えてきています。
長期インターンの場合は企業側からすると、実際に働いて能力を見極める目的が第一義のため、普段から働いている社員と同じような仕事をすることが多いです。
長期インターンはベンチャーやスタートアップなど、起業して数年のまだ若く歴史も浅いような企業が多いです。
とはいえ、採用のミスマッチを防ぐために、今後ますますインターンを適性の見極めに行う機会として活用する企業が増えてくるため、優秀人材を早期発見→囲い込みを行いたい大企業も積極的に参入してくるのは確実です。
短期インターンの目的
短期インターンとは、1日から1週間程度で実施されるインターンです。
最近は新型コロナの影響で、オンラインで半日インターンを開催している会社もちらほら増えてきています。
短期インターンの会社側の目的は、就活生に自社の良さを知ってもらい、就活時に良い人材にエントリーをしてもらうためです。
内容としては会社説明会やグループワークのようなゲーム感覚で参加できるイベントという形式で進める場合が多いです。
基本的に春休みの短期インターンは4年生向けで会社側がラフな形で最後のアピールを行う場として活用され、夏休みのインターンは3年生狙いで早い段階で企業が翌年の新卒採用を行うための会社のアピールの場として実施されます。
基本的に業界の雰囲気を知るためやその企業の雰囲気を知る点では短期インターンの方が効率が良いのですが、実際に働いてみたい企業があるとか、自分のスキルを活かせるか試したいのなら、長期インターンの方がオススメです。
長期と短期インターンの適切な応募社数

それでは目的に応じたインターンの応募社数の割り出し方を見ていきましょう。
便宜上、「長期インターン」と「短期インターン」に層別して、それぞれのケースで何社応募すれば適正なのかを解説していきます。
- 長期インターンの適切な応募社数
- 短期インターンの適切な応募社数
長期インターンの適切な応募社数
これまで説明してきたとおり、長期インターンに参加する目的は下記の3つでしたね。
- 実際に入りたい企業の実態を知りたい
- 自分のスキルを活かせるか試したい
- インターンシップ経由でないと内定がもらえない
したがって、ある程度、業種なり職種なりが絞られている前提が成り立ちます。
一方で、企業側にとっては「優秀な学生に早い段階で自社への入社を決めてもらう」ことが第一義の目的なので、選考アリのインターンシップがほとんどです。
そのため長期インターンにたくさん応募したにもかかわらず、すべて選考で落ちて参加できる企業が1社もないといった先輩方も散見します。
先ほどのマイナビ調査でも応募したが参加できなかった学生の割合が9.1%あがっており、いみじくも1割の学生が辛酸をなめるといった不甲斐ない結果が出ています。
したがって、長期インターンの場合は合格率から逆算して応募社数を決めることが現実的です。
では、合格率ってどのぐらいなのか?
就活ジャーナルによれば、インターンシップで書類選考を行う企業は52.9%ですが、書類選考通過率は60%だそうです。
また、面接選考を行う企業は28.4%ですが、面接通過率は59.1%だそうです。
さらに、参加通知が届いた会社は55.4%ということなので、2社エントリーすれば1社は届く計算になります。
したがって、平均的に見ると、2社応募しておけば、1社は長期インターンに参加できるという計算が成り立つわけです。
ただし、選考倍率の高い人気業界や企業になると、合格率20%というような会社もザラです。
このケースだと5社受けて、1社から招待状が届く計算になりますが、業界や企業群によって倍率は異なりますので、あらかじめ合格率から逆算した上で応募社数をはじき出すことが賢明でしょう。
いずれにしても、長期インターンの場合は1度に何社も参加できないので、1社に参加できれば御の字です。
1社から招待状をもらうために何社応募しないといけないのかといった観点で応募社数を決め込みましょう。
短期インターンの適切な応募社数
短期インターンの主な目的は、下記の3つでしたね。
- 業界や仕事を知る
- データにはないその会社の特徴を知る
- その会社の雰囲気を知る
短期インターンは文字通り短期で終了するので、複数社に同時並行的に参加できるのが特徴です。
そのうえで、短期インターンの応募を何社ぐらいすればいいのかですが、「業界×複数社(2~3社)」を目安にするといいと思います。
なぜ複数社にすべきかというと、一定の基準をもとにして企業を比較できるからです。
たとえば、あなたが商品を買うときに、なかには商品を見て一発で買う男気のある人もいるかもしれませんが、たいがいの場合は複数の商品を比較して選択するはず。
また比較する際に用いる基準は、値段だったり、色や素材、口コミ、特典、その他、ポイントやアフターサービス、営業担当者の人柄だったりで、何かと何かを比較して購買決定を行っているはずです。
会社選びもそれと同じで、1つの会社だけだと比べようがないので、基準もなく、その会社のどこが良くて、どこが悪いのかなど相対的に物事を判断することができません。
したがって、あなたが志望する業界が2つあれば4〜6社(2業界×2〜3社)、3業界であれば6〜9社(3業界×2〜3社)応募することが1つの目安となります。
ただし、複数社といってもあまりにも参加社数が増えすぎると、スケジュール管理が煩雑になったり、ダブルブッキングしてしまったり、本業の勉学に勤しむ時間がなくなったりします。
仮にインターンに参加する企業の日程が被ってしまった場合は優先順位の低い会社に必ずキャンセルの連絡を入れてください。
なぜなら、キャンセルを入れない無礼を犯してしまうと、あなたの印象が悪くなるだけでなく、大学側の心証も損ね、ひいてはあなたの大学の後輩に迷惑をかけることになります。
面倒くさいし、ばつが悪いかもしれませんが、必ずメールあるいは電話でキャンセルの連絡を入れておきましょう。
インターンシップの探し方5つ
インターンシップの探し方は5つあるため、1つずつ解説していきます。
- 企業のホームページ
- 大学のキャリアセンター
- 大手の就職サイトを利用する
- インターンシップ専門の求人サイトを活用する
- 逆求人サイトでインターンの指名を待つ
企業のホームページ
1つ目の方法は、もしあなたに行きたい企業があるのであれば、企業のホームページから直接参加申し込みするのがいいでしょう。
就活サイト経由ではなく、企業のホームページを見てエントリーするわけなので、あなたの志望度や熱意が企業側に直接伝わります。
なかにはホームページに募集情報がなくても、インターンシップを実施している企業もあるので、どこにも見当たらない場合は直接人事に連絡してみてください。
大学のキャリアセンター
大学のキャリアセンターでは、インターンの情報サイトには掲載されていない情報を得られる可能性があります。
大学とつながりのある企業や卒業生のいる会社に関する情報もあり、大学ならではの貴重な情報に触れられるチャンスがあります。
また、大学によってはインターン参加が単位として認定されることもありますので、就職課やキャリアセンターに確認してみましょう。
大手の就職サイトを利用する
インターンを探す定番といえば、やはりマイナビやリクナビなどの大手就職サイトを利用する手です。
就職サイトは選考のエントリーができるだけでなく、各地の大企業から中小企業まで様々なインターン情報が掲載されています。
なかには、大手の就職サイトのみでインターンを募集している会社もあります。
なので、大手の就職サイトをメインでまわしながら、他の手段を併用することが取りこぼしがなくなるので安全ですね。
インターンシップ専門の求人サイトを活用する
効率的にインターンを探すなら、インターンシップ専門のサービスを利用するのがおすすめです。
インターンの専門サイトでは、1Day仕事体験はもちろん、3か月以上の長期プログラムの情報も多数掲載されているほか、就活サイトにはないプログラムもあり、大手からベンチャーまで幅広い企業のインターン情報がチェックできます。
業種や職種、勤務地などの希望条件で検索できるので、一瞬であなたの希望に合ったインターン先を発見できます。
インターンシップ専門のサービスによりインターンシップの合同説明会なども開催されている場合もありますので、志望業界や志望企業が絞り切れていない場合は、このようなサービスを利用するのもアリでしょう。
逆求人サイトでインターンの指名を待つ
最後の方法は、逆求人サイトに登録して、網を張っておくという方法です。
逆求人サイトはプロフィールを登録しておくだけで、企業側からスカウトが届きます。
しかも、シッカリとプロフィールを読んだうえで「この学生は自社に会う」と判断して、スカウトを送ってきてくれるので、自分のと相性がいい企業とつながれる点ではメリットが大きいですね。
そんな逆求人サイトですが、インターンシップのスカウトも届き、自分では探すことができない会社や隠れホワイト企業に出会えるチャンスも拡大しますので、逆求人サイトに登録しておくことも重要です。
「インターンにちゃんと応募しているのに全然参加できない…」学生の対策ポイント

本記事ではインターンの応募者数は「7社」、そしてインターンには実際に「4.4社」参加するというマイナビの調査結果を紹介しました。
一方で先ほども記載した通り、インターンには「選考」を通して参加する学生の絞り込みが実施されるケースも少なくありません。
そのため学生によっては、上記で記載した平均値を大きく下回ることも十分に考えられるでしょう。
そのためここで、「平均程度のインターンに応募しているのに参加までたどり着けない」学生向けに、インターン選考のフローごとで対策方法を紹介します。
自己分析・企業研究
自己分析をすることで、自身の長所・短所、または自身の価値観を客観的に把握でき、企業に自身のどんな点をアピールすべきかが明確になります。
そして自己分析で見つけた「自身ならではの特徴」を踏まえて、志望企業の求める人物像にできる限り合致する内容で自身をアピールできるよう対策していきましょう。
また業界研究や企業分析をする目的は、「業界内での志望企業の立ち位置や、競合他社との相違点を把握するため」です。
そして志望企業が所属する業界以外の気になる業界・企業も調べることは、より志望企業を客観的に分析できることに繋がります。
「競合他社ではなくなぜ志望企業なのか」という点を自身の経験や価値観を踏まえて明確に説明できるよう、時間をかけて考えていきましょう。
自己分析・志望動機を考える際の方法として、自身が行ったのは主に下記3点のため参考にしてみてください。
- 前田裕二著「メモの魔力」の1000の質問に対して、ノートに回答を書く
- OB訪問や座談会で自身の作成した仮の志望動機やガクチカを添削してもらい、また社員の方がなぜ企業を志望したかを聞き、自身と一致する部分があれば内容を模倣する
- 転職口コミサイトを徹底的に閲覧し、企業の良いところと悪いところを考察するなど
エントリーシート作成
上記で紹介した自己分析や業界・企業研究の内容を踏まえてエントリーシートを作成していきます。
過去にエントリーシートで出題された内容については「就活会議」「ワンキャリア」などの就活サイトで「選考体験記」という項目で紹介されているため、ぜひ確認してみてください。
また自身で作成した後は、必ず友人や先輩、志望企業のOB・OGの方に添削をしてもらい、客観的に見ても優れているエントリーシートになっているか提出前に確認するようにしましょう。
面接・グループディスカッション対策
エントリーシートを突破したら次に面接やグループディスカッションが行なわれるため、その対策も入念に行いましょう。
面接に関してはエントリーシートに記載した内容をもとに質問をしていくため、「面接官との会話のキャッチボール」を意識して、簡潔かつ理論的に回答していけるように事前に面接の練習をしておくことがおすすめです。
またグループディスカッションに関しては、リーダー・タイムキーパー・調整役などグループ内での「自身の役割」を全うし、高い評価を得ていく必要があります。
そのため「グループディスカッション」が経験できるイベントに参加し、自身が最も適している役割を事前に把握しておくと良いでしょう。
さいごに
今回はインターンシップの応募社数をテーマに解説してきましたが、いかがだったでしょうか?
記事の内容を簡単にまとめます。
- インターンを行う目的は優秀層の早期囲い込み・企業の広報活動
- インターンには「実務経験を積める」など様々なメリットがある
- インターンは時期によって長期・短期で分類
- 長期・短期で適切な応募社数の解釈が異なる
- インターンを探す方法は5つ
- 選考対策を十分に行わないとインターンに参加できないこともある
何事も「数」ではなく、「目的」ありきです。
逆を言うと、「目的」が明確に定まってさえいれば、「数」は後からついてきます。
ぜひ今回のやり方を参考にして、充実したインターンシップを過ごせますことを祈念しています。
なお、インターンシップが本選考に与える影響については下記で解説しているため、気になる方はぜひ目を通してみてください!









