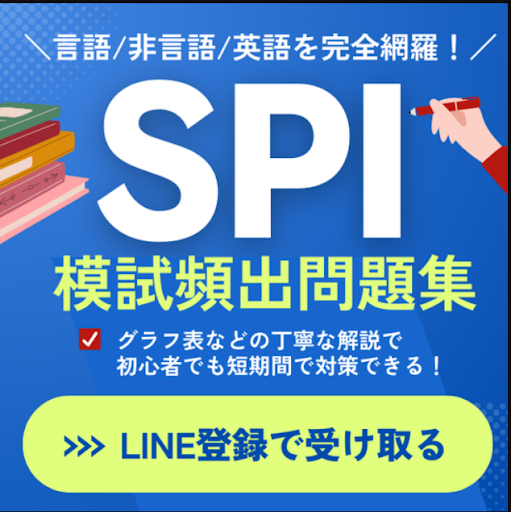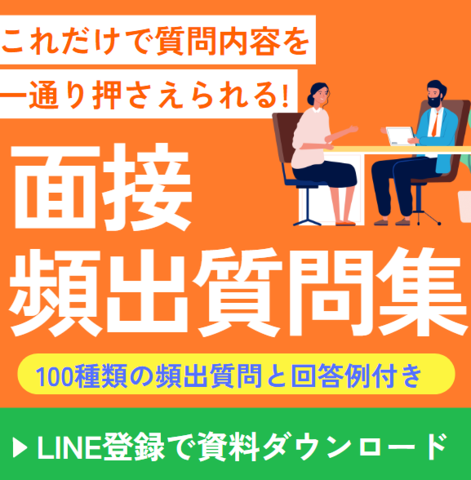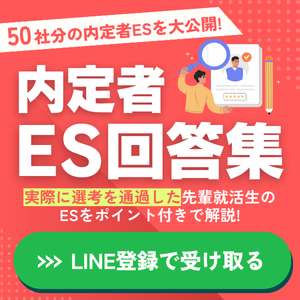就活でFBをする目的と模擬練習で見てもらうべきポイント
2024/8/30更新
はじめに
面接の最後に採用担当者から「今回の面接のフィードバックをお伝えします」と言われた経験はありませんか?
面接でのフィードバックは合否に関わるのか、そもそもなぜフィードバックをするのか気になるところ。
本記事では就活でフィードバックをする目的と、フィードバックの内容から自分が見直すべきポイントを解説します。
以下のようなお悩みのある学生は必見ですので、ぜひ最後までチェックしてみてください。
- フィードバックの意味や実施する理由を知りたい
- 学生からフィードバックをもらいたいか聞いてもいい?
- フィードバックの内容を次に活かしたい
上京を志す地方学生ならジョーカツ!
あなたのキャリアを加速させるチャンス!
無料で利用できる快適な個室シェアハウス、
東京までの交通費サポート付き
首都圏の注目企業への就活ならジョーカツ
首都圏の学生ならスタキャリ!
理想のキャリアを実現へと導く第一歩!
あなたにピッタリのキャリアアドバイザーを選び、
自分にマッチする優良企業をご紹介
首都圏企業のES添削から面接対策まで、就活ならスタキャリ
そもそも「FB」はどんな意味?

FB(フィードバック)とは「行動に対する評価を相手に返すこと」の意味で使われる言葉です。
就活における「フィードバック」の場合は、就活生の面接に対して企業側がアドバイスすることを指します。
形式は様々であり、面接後すぐにフィードバックを受けるケースもあれば、電話やメール、または後日企業を訪問し、直接話すケースなどがあります。
しかし、フィードバックはすべての企業が行なっているわけではありません。
「自分だけ連絡が来なかった…」と焦る必要はないので安心してください。
面接官が就活生にFBする4つの目的
フィードバックは、就活生全員に行うわけではありません。
業務と並行して採用活動を行う企業にとって、就活生一人ひとりにフィードバックを行うことは、かなりの時間と労力がかかるからです。
そんな貴重な時間を割いてまで行われるフィードバックには、以下のような目的があります。
- 志望度を上げてほしいから
- 次の選考に期待をしているから
- 入社するまでにスキルをアップしてほしいから
- 人の意見に聞く耳をもてる人材なのかを把握したいから
企業の目的をしっかりと理解し、フィードバックの時間を無駄にしないようにしましょう。
志望度を上げてほしいから
就活生に対して企業への志望度を上げてほしいため、フィードバックをすることがあります。
もしあなたが、複数社面接を受けているとして、その内の1社だけが「フィードバックを行いたいのですが」と連絡してきたらどうでしょう。
その企業に対して「他社よりも丁寧な対応を行なっている」と感じ、印象が良くなるのではないでしょうか。
「学生の考えを聞き取り、丁寧な選考を行なっている会社」などといったポジティブな印象を就活生に与えることで、自社の志望度をあげてもらう狙いがあります。
次の選考に期待をしているから
前回の選考で評価され、面接官の「次回も結果を残してほしい気持ち」から、フィードバックを行うこともあります。
大手企業のように、複数回選考がある場合、毎回担当者が異なることが一般的です。
そのため、1度目の選考で高い評価を受けたとしても、次も同じ評価を受けるとは限りません。
面接官が「優秀だ」と判断した就活生には、次の選考も突破できるようアドバイスを送り、入社までのフォローをする場合があります。
このような場合は、よかった点だけでなく改善点を伝えられることもありますが、前向きに捉えて、マイナス面を改善できるようにしましょう。
入社するまでにスキルをアップしてほしいから
就活生に対して、入社までに伸ばしてほしいスキルや、改善点を事前に伝えることで、スキルアップを望んでいるケースがあります。
無事面接を突破し、入社に至った場合は「新入社員」となります。つまり「一人の戦力」となるわけです。早々に戦力として力を発揮してもらうために、学生時代のうちから準備をしてほしい意図が隠れています。
もしフィードバックの機会があるならば、入社までに最低限身につけてほしいスキルや、入社後に取得してほしい資格があるのかを質問してみるのもよいでしょう。
人の意見に聞く耳をもてる人材なのかを把握したいから
フィードバックでは、意見を受け取った後の反応を見られています。あえてネガティブな意見をぶつけ、どんな反応をするのかを試すようです。
その場合、不機嫌になったりショックを受けて動揺したりなど、あからさまな態度を示すのは避けた方が良いでしょう。「指摘されたのを受け止めて、真摯に話を聞くことができない」と判断されてしまいます。
フィードバックも選考と同様に「見られている意識」を持って臨むのが重要です。
就活でFBを受けた際の取るべき姿勢
フィードバックを受けている姿勢も、就活生の印象を左右します。
企業の貴重な時間をもらっている自覚を持って、素直に受け取る姿勢が大切です。
例えば「途中で反論しない」「最後まで話しを聞く」「感謝を伝える」などの基本的な聞く姿勢をみせることは、最低限のマナーです。
そして可能であれば、メモを取るようにしましょう。
熱心にメモを取る姿は、話に耳を傾けていることを示すアピールにもなります。
しかしメモを取る際は、事前に許可をとるのがおすすめ。漏洩のリスクを避けるためにメモを禁止している場合があるからです。
「メモを取っても良いでしょうか」と一言断っておくと好印象に繋がります。
面接でFBを受けたら選考通過なのか?

結論から言うと「フィードバックがあった=合格」ではありません。
フィードバックをする目的は、企業によって異なりますので、合否を見極めることは難しいといえるでしょう。
反対に、不合格と決まっている学生に対して、今後の就活がうまくいくようにとフィードバックを伝える企業もあるようです。
フィードバックを受ける際は、結果を気にするよりも、話しを聞くことに集中したほうが良い結果を招くのかもしれません。
逆質問ではFBを求めないのが得策
面接の最後には、学生からの「逆質問」を受ける時間が用意されています。
しかし、この時間に「私の受け答えはどうでしたか」と、自分からフィードバックを求めることは避けましょう。「この時間は、他社の面接に向けた練習だったのか?」と悪い印象を与えてしまう恐れがあるからです。
このような誤解を与えないためにも、面接官には自分からフィードバックを求めないのが得策といえます。
FBがほしいなら模擬面接でもらう
もし、フィードバックを必要としているのであれば、模擬面接を利用することをおすすめします。
本命の面接で失敗しないためにも、下記のようなサービスを検討してみてください。
- 大学のキャリアセンター
- 新卒向け就活エージェント
大学のサービスであるキャリアセンターを利用するのが一番簡単な方法です。
キャリアセンターには、大学周辺企業の傾向を熟知しているアドバイザーがいるので、周辺企業を受ける就活生にとっては非常に適しています。
就活のプロであるエージェントを利用するのも一つの方法です。
面接対策やフィードバックまで無料で行なっています。実際の採用に携わるコンサルタントの的確な意見をもらうことができ、自己分析にも役立ちます。
大切な面接の場で「緊張しすぎて言葉が出てこなかった」「本当にこれであっているのか?」といった疑問があるのではないでしょうか。これから迎える本番で失敗しないためにも、フィードバックは模擬面接の段階で受けるのが最適です。
また最近では、Web面接のスタイルも多くなってきています。
画面の写りや声の聞こえ方は適切かなどの、Webに特化した対策も行うと良いでしょう。
Web面接に関する注意点やポイントは以下の記事でも紹介されているので、ぜひご覧ください。
模擬面接でFBしてもらうべきポイント

模擬面接は、細かな点までフィードバックしてもらえることが利点です。
ビジネスマナーなどの所作に関しては、面接前に身につけるべきであり、知らないまま企業を訪問するのは失礼にあたります。
企業に対して悪い印象を与えないよう、以下のポイントに注目しながら、練習を行なってみてください。
- 結論から話せているか
- わかりやすく伝わっているか
- 立ち振る舞いはできているか
たとえ模擬面接であっても気を抜かず、本番さながらの面接を意識することが重要です。
結論から話せているか
面接では、質問に対して的確に答えを伝える必要があります。フィードバックをもらう際は「話し始めに結論をおいているか」を見てもらうと良いです。
ここで、二人の就活生の回答を比較してみます。
(質問例)「あなたの長所を教えてください」
(Aさんの回答)
私の長所は、コミュニケーション力が高いところです。インターンに参加した際は、そこで出会った仲間と協力しプレゼン準備に挑みました。短期間でしたが…
(Bさんの回答)
どんな環境でも友達をつくることができ、協力しあえるので、私はコミュニケーション力が高いところが長所だと思います。インターンでは…
どちらもコミュニケーション力について話していますが、結論から述べているAさんの方が、わかりやすいのではないでしょうか。
面接やプレゼンで話す際の構成は「結論→理由」の流れで話し、結論を簡潔に述べましょう。
わかりやすく伝わっているか
「結論→理由」の構成を理解したら、次は内容です。結論に対する理由に、矛盾がないかを確認してもらうと良いです。
また、声の大きさや、話し方のスピードも、わかりやすく伝えるための大切なテクニックです。
緊張状態では、自分が思っている以上の速さ、かつ小さな声で話してしまいがちです。
できるだけ堂々と、普段よりもゆっくりを心がけて話すと、心地よいスピードになります。
相手にかぶさるような話し方や長い沈黙がないように、会話の間も意識してください。立ち振る舞いはできているか
ビジネスマナーに沿った立ち振る舞いができているかについては、最低限のマナーとして見られています。
間違った所作を行なっていないか、事前にフィードバックを受けておくと安心です。
姿勢はあまり深く腰掛けず、背筋を伸ばすだけで凛とした印象になります。
メモをとるときに前かがみになりすぎないなど細かな点にも気を配るとさらに良くなります。
そして忘れがちなのは、入退場の場面です。特に退場は、面接後の一番気が抜けるタイミングでもあるので、意識が途切れないよう注意してください。
さいごに
フィードバックでは、時に指摘されることもあります。
あまり踏み込まれたくないことを言われ、落ち込んでしまう方もいるかもしれません。
しかし、フィードバックの根本はポジティブなものであり、あなたを良くするためのアドバイスです。
大切なのは、フィードバックを受けることではなく、その後の行動です。
フィードバックを活かせるかで、面接官に与える印象が左右されます。
良い点も悪い点もあなたの個性なので、たとえうまく話せなくとも、自信をもって自分をアピールしてみてください。