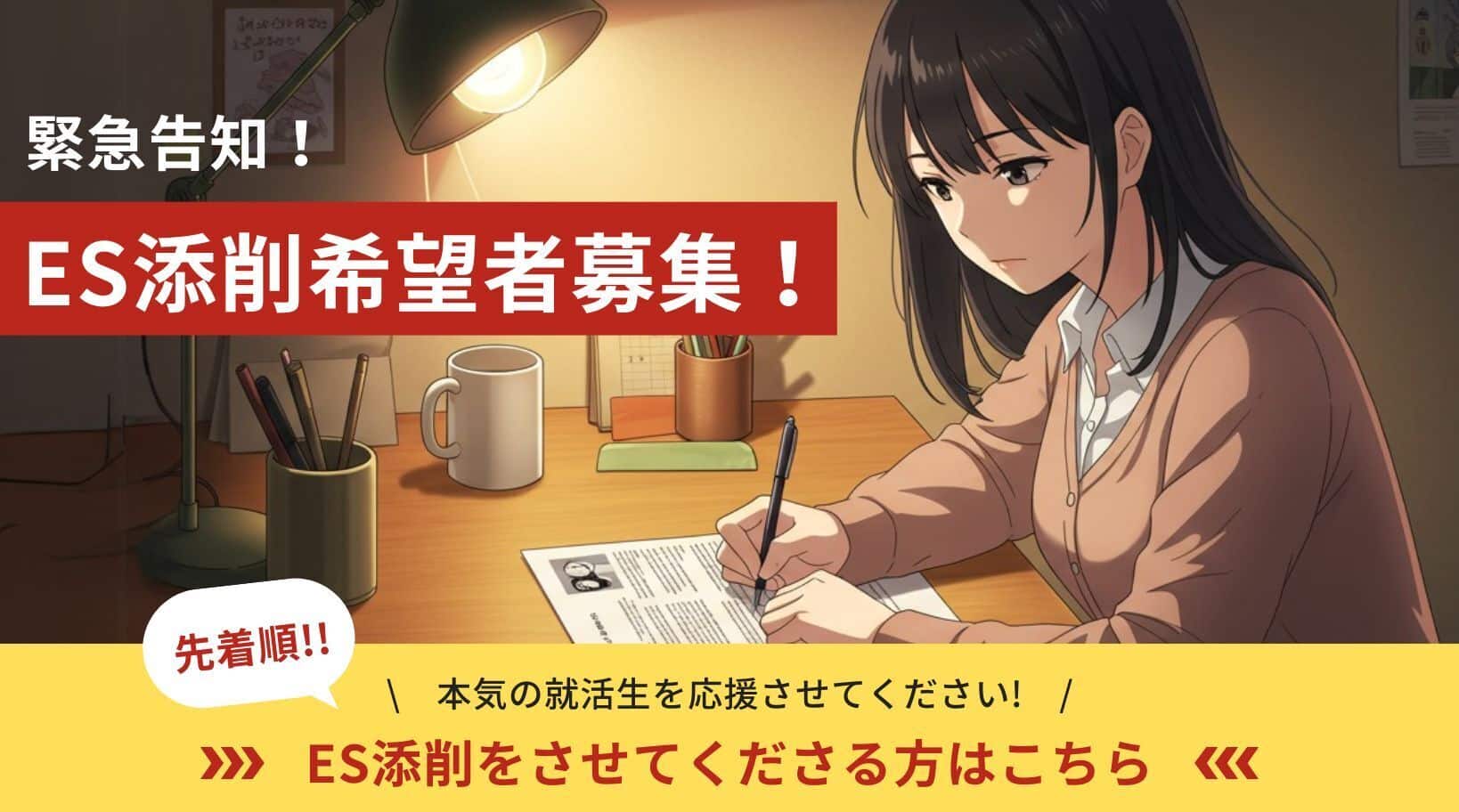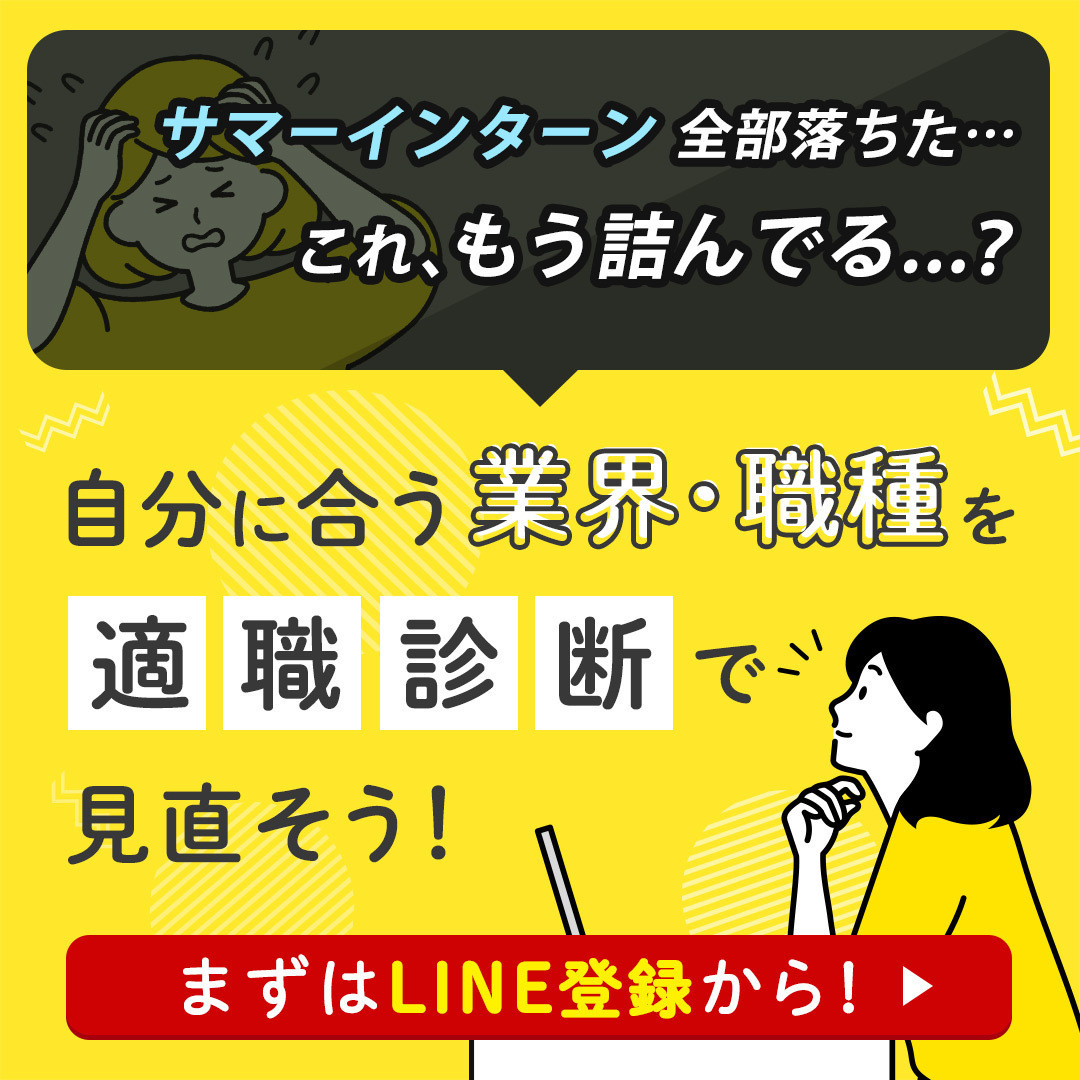就活でエントリーシートは何社提出する?企業数の注意点を解説
2025/2/5更新
はじめに
就活を始める上でまず立ちはだかる関門なのがエントリーシート。
提出数が多すぎても少なすぎても就活で不利になる場面があるため、適切な提出数をおさえておく必要があります。
またエントリーシートを作成するためには時間も労力もかかるので、効率良く書くコツが分かれば効率的に就活を進められるでしょう。
そこで本記事ではエントリーシートを何社分提出すべきか、エントリーの際の注意点もあわせて解説します。
以下のようなお悩みのある学生は必見ですので、ぜひ最後までチェックしてみてください。
- エントリーシートは何社提出すべき?
- エントリー数多すぎ・少なすぎのメリットデメリットが知りたい
- エントリーシートを効率的に書くコツを知りたい
就活生の平均エントリー社数
それではさっそく就活生がどれくらいの会社にエントリーしているのかを見ていきましょう。
データはマイナビ2022年卒 学生就職モニター調査 8月の活動状況の結果を使用しますが、性別および文理別に区分した数値は下記のとおりです。
| 文系男子 | 理系男子 | 文系女子 | 理系女子 | |
| エントリーした社数 | 31.4 | 17.1 | 32.7 | 21.2 |
| エントリーシート提出社数 | 20.3(100) | 12.3(100) | 20.9(100) | 15.0(100) |
| エントリーシート通過社数 | 13.6(67) | 8.4(68) | 13.2(63) | 9.4(63) |
| 面接受験社数(WEB含む) | 11.5(57) | 7.1(58) | 11.4(55) | 8.0(53) |
| 内々定の数 | 2.4(12) | 2.1(17) | 2.4(11) | 2.3(15) |
※( )内の数値はエントリーシート提出社数を100とした場合の数値
この数字を見る限り、文系学生のエントリー数が多いですが、学業が比較的忙しい理系よりも就活を活発におこない、内定後も活動を継続する人が多いことがうかがわれます。
また、理系の学生は一般応募だけでなく、学校推薦や教授推薦を通じて就職するケースもあり、文系よりもエントリー数が少なくなっている事態も考慮する必要があります。
内々定の数字をみるとエントリーシートを仮に10社提出すれば、1〜2社から内々定をもらえると計算できます。
つまり、10社未満のエントリー数では内々定をゲットできないリスクが高まることが、このデータから推定できるわけです。
エントリーが多い・少ないのメリット・デメリット
ここでエントリーが多い場合のメリットとデメリット、少ない場合のメリット・デメリットを事前に知っておいたほうがいいと思うので紹介しておきます。
下表がそれぞれのケースのザックリとしたメリット・デメリットです。
| エントリー社数 | メリット | デメリット |
| 多い場合 | ・視野が広がりやすい ・落ちても手持ち駒があるので安心できる ・想定していなかった企業とマッチングする可能性がある | ・スケジュールが煩雑になる ・1社ごとの対策時間が減る |
| 少ない場合 | 1社にかけられるエネルギー量が大きい | ・自分の可能性を狭める確率が高くなる ・手持ち駒がなくなった場合に焦る |
エントリー社数が多いと、さまざまな業界や職種に出会う機会が増え、内定のチャンスも広がります。
しかし、過剰なエントリーはスケジュールが重なり、疲労や集中力低下を招く可能性があります。
一方で、エントリー数が少ないと適職との出会いが限られ、不合格が続くと精神的な負担が大きくなりますが、1社ごとに充実した準備ができるため、内定の確率が上がります。
自分のメンタルや体力に合った適切なエントリー数を見極めることが大切です。
エントリーすべきかどうか迷ったときの基準

エントリーをどの企業にするか決めるときに、自分の中に基準がなければ、やたらと迷いが生じます。
逆に一定の基準さえあれば、効率的に取捨選択ができるものです。
ここでは取捨選択するためのヒントを3つ紹介しますので、エントリーするさいの参考にしてくださいね。
プレエントリーする企業数を決める
まずプレエントリーする企業の数をあらかじめ決めておくことです。
アレもコレもと手を広げ過ぎて無制限にエントリーすると、「気付けば100社」なんてこともあります。
仮に100社エントリーしてもすべての企業にエントリーシートを提出するのは骨が折れますし、説明会のスケジュールを管理するのも煩雑すぎます。
目安としては、先ほどのデータでもありましたが文系であれば30社、理系であれば20社程度エントリーしておけば、平均的に2〜3社から内々定をもらえる計算になります。
エントリーしない業種を予め決めておく
エントリーする業種を絞り込むためには、あらかじめ「この業種は避けたい」とネガティブな視点で業種を排除するのが効果的です。
日本標準産業分類などの資料を使って、興味がない業種を消去していくと、自然と可能性のある業種が浮かび上がります。
また、業種に記号を付けて優先順位を決めておく方法もあります。
ネガティブな判断要素で選択肢を狭めることで、効率的にエントリー業種を決定できるでしょう。
エントリーしない職種を決めておく
ジョブ型採用が増えてきた今、職種を選ぶ際に「絶対にやりたくない仕事」をあらかじめ決めておくのも有効です。
たとえば、「営業は避けたい」や「事務は向いていない」など、自分の嫌な職種を厚生労働省の職業分類表を参考にして消去していくと、自然と向いている職種が絞りやすいです。
日本ではまだ総合職採用が主流ですが、この作業を行うことで自分のやりたい仕事が見えてきやすくなり、今後のキャリア選択にも大いに役立つでしょう。
エントリーシートを効率よく量産するためのコツ
エントリーシートを効率的に量産するためには、エントリーシートで頻出する質問をおさえておくことが重要です。
たとえば、エントリーシートでよく出てくる設問は下記のとおりです。
- 自己PR
- 学生時代に力を入れてきたこと
- あなたの強み・弱み
- 学生時代の成功体験・挫折体験
- 志望動機
- 企業選びの軸・ポイント
- 業界の現状への意見
- 将来のキャリア
- 最近気になったニュース
- 最近読んだ本と感想
これぐらいの設問の回答文章を準備しておけば、エントリーシートの8割はカバーできます。
あとは、その企業特有の設問の回答を考えればいいだけなので、非常に楽ですね。
ただし、気を付けなければいけない点が1つあります。
それは何かというと、エントリーシートの文章を準備したからといって、どの企業にも同じエントリーシート文章を使いまわしてはいけないということです。
なぜなら、企業によって求める人物像が異なりますので同じエントリーシート文章だと、ある企業には響くけど、他の企業には1ミリも刺さらないという現象が起きるからです。
したがって、求める人物像というのはだいたい数種類ですから、何パターンかの文章を作っておけば対応できるわけです。
各社が求める人物像は大きく下記の5つに分けられます。
- チャレンジ系(受け身でなく自ら考えチャレンジする力)
- 柔軟系(状況に応じて柔軟に思考・行動する力)
- 外向系(外に目を向け、新しいマーケットやビジネスを発見する力)
- チームワーク系(組織のアウトプットを最大化する力)
- アイディア系(従来の枠にとらわれず独自の発想ができる力)
この5つのパターンと先ほどの「エントリーシートによく出る設問例」をかけ合わせた文章を準備しておけば事足りるということですね。
作る際の注意点としては、それぞれの題材を変えるのもアリだし、そこまでエピソードがない場合でもそのエピソードの中にたとえば、チャレンジ要素はないか、アイディア要素はないかを探っていって、それにスポットを当て拡大させてアピールできると悩まなくて済みます。
何事も一気に作ろうとすると骨が折れるので、お尻に火がつくと動き出すタイプの人はエントリーの際に1つずつ作っていって貯めていき、徐々に転用可能な状態を作るほうが気が楽かもしれませんね。
具体的なエントリーシートの書き方については以下の記事で紹介しているので、ぜひ参考にしてください。
就活でエントリーする際に気をつけるべき注意点

最後にエントリーする前に注意してほしいことが3つありますので、それを解説して本記事を締めくくりたいと思います。
エントリー数をあまり気にし過ぎない
まず1つ目はエントリー数にあまり神経質にならないということです。
エントリーはあくまでも手段です。
就活の目的は「あなたにピッタリの会社から内定をゲットすること」ですよね。
なので、入口のところでムダに労力を費やすのではなく、企業分析や自己分析、エントリーシート作成、面接練習など就活に必須の本質的なスキルにそのエネルギーを充ててほしいと思います。
先述のとおり、10社で大丈夫と思える人もいますし、50社エントリーしてもまだ心配というようにメンタルに個人差があることも否めません。
平均データをある程度目安にしながら、自分の居心地のいいエントリー社数を決めてほしいと思います。
迷ったらエントリーしておく
迷うぐらいだったらエントリーしておくことをおすすめします。
なぜなら、エントリーさえしておけば、その会社の経営状況や採用情報が説明会などで入手でき、知識量が多くなると判断しやすくなるからです。
もちろん、企業情報が入れば、その会社の志望度が下がることもあります。
そうすれば、「早く知っててよかった」とエントリーシートを出さなければいいだけなので、手間が省けてかなりレバレッジが高いですよね。
大手ばかりを選び過ぎない
就活生のなかには大手や有名企業ばかりにエントリーする学生もいます。
ご存じのとおり、そのような企業は人気がありますので、競争倍率もかなり高くなります。
そうなると当然、不合格になる確率も高くなるわけです。
結果として、持ち駒がすべてなくなって振出しに戻るという恐れがありますので、大手ばかりでなく、リスク分散という形で中小企業にもエントリーしておいたほうがいいでしょう。
日本では知名度はないけど、世界に誇る独自技術を保有していたり、世界でトップシェアを誇る中小企業もあります。
優良中小企業の具体的な見つけ方は以下の記事を参考にしてください。
就活のエントリーシート提出数に関するよくある質問
最後に就活のエントリーシート提出数に関するよくある質問をまとめたので、ここで疑問点や不安なことを解消しておきましょう。
就活で10社しかエントリーしないのは少ない?
就活生は平均20ほど受けているため、10社しかエントリーしないのは少ないと言えます。
今回紹介したデメリットのように、エントリー数が少なすぎると自分の可能性を狭めるだけでなく選考に落ちてしまったときに手駒が少なくなってしまうので要注意です。
就活で平均何社落ちる?
就活では平均して10~20社エントリーすると1~2社内定するという結果があります。
つまり、就活においては平均8~18社は落ちるのが一般的です。
さいごに
今回は就活でいくつエントリーシートを提出すべきか、エントリーのポイントや量産のためのコツを解説しました。
就活生の平均エントリー数は約20社なので、この数字を参考にエントリーする企業数を決めておくようにしましょう。
もしどこにエントリーすべきか分からない場合はプレエントリーする企業数や興味関心の無い業界・職種をあらかじめ決めておくのがポイントです。
今回紹介した内容を踏まえて、効率的に就活を進めて内定を勝ち取りましょう!