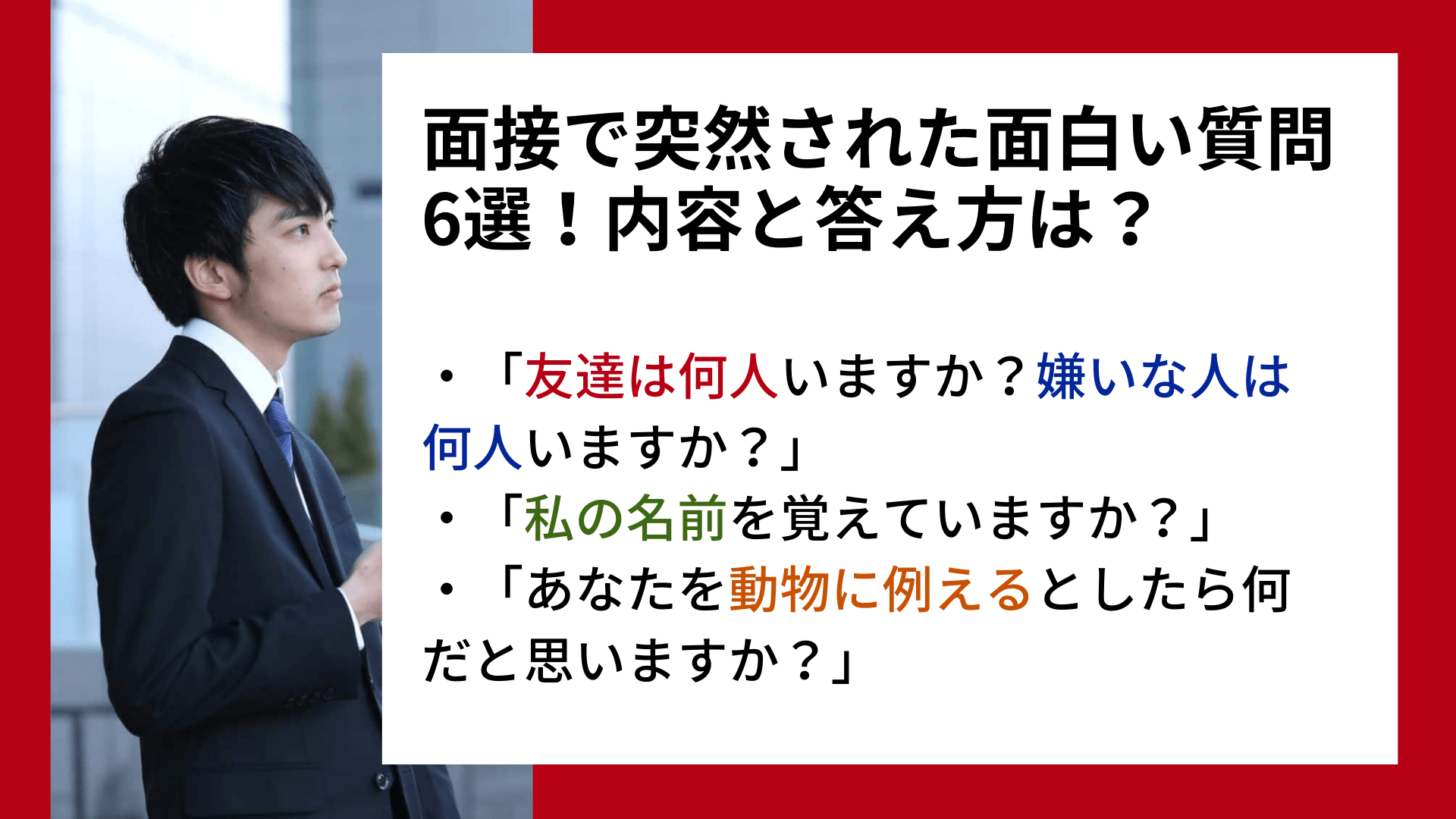【就活】年間休日って何?何日くらいあるの?
2024/8/19更新
はじめに
求人情報を見て、こんな疑問を持ったことはありませんか。
「年間休日って何を意味するの?」
「有給休暇とかも含まれるの?」
「平均ってどのぐらいなの?」
年間休日の意味や相場観は、意外にわからないものです。
本記事では、就活生気になる可能性のある6つの疑問に、Q&A形式で明快に答えていきます。
最初から順番に読んでいってもいいですし、とりあえず気になる点だけをチェックしても良いです。
この記事を読むだけで、今まで悶々としていた頭がクリアになり、次回からは求人情報を見た時、瞬時に理解できるでしょう。
求人情報の意味と水準を見据えながら就活を進めることができます。
この記事は、以下のような点を知りたい就活生が対象です。
- 年間休日って何?
- 年間休日数の平均は?
- 面接で休日のことを聞いてもいいのか?
年間休日について興味がある方は、ぜひ最後までご覧ください。
上京を志す地方学生ならジョーカツ!
あなたのキャリアを加速させるチャンス!
無料で利用できる快適な個室シェアハウス、
東京までの交通費サポート付き
首都圏の注目企業への就活ならジョーカツ
首都圏の学生ならスタキャリ!
理想のキャリアを実現へと導く第一歩!
あなたにピッタリのキャリアアドバイザーを選び、
自分にマッチする優良企業をご紹介
首都圏企業のES添削から面接対策まで、就活ならスタキャリ
Q1:年間休日って何?

A1:年間休日とは会社が定めている年間の休日合計数です。
その日数は、会社や事業所によって異なります。
労働基準法(以下、労基法)さえ守っていれば、年間休日は会社の判断に委ねられています。
年間休日の内訳について見ていきましょう。
そもそも年間休日は、下記のとおり労基法で定められている「法定休日」と、会社が任意に定めることのできる「法定外休日」で構成されています。
| 年間休日=法定休日+法定外休日 |
それでは、労基法が定める最低ラインの「法定休日」は何日でしょうか。
法的な最低ラインの休日数は、105日です。
算出方法について見ていきましょう。
労基法の中で年間休日数に言及している条文はありません。
ですが、労基法の休日に関する規定は第35条の中で、「法定休日は毎週少なくとも1日、または4週間を通じて4日以上」と明記されています。
となると、1年間は52週(365日÷7日)なので、年間休日52日を付与すれば問題ないと考えてしまいがちです。
その一方で、労基法32条には「労働時間の上限が週40時間」「1日に8時間を超えて労働させてはいけない」と規定されています。
以上の労働時間に関する情報を考慮すると、「会社が確保すべき年間休日の最低日数」が見えてくるでしょう。
①まず週40時間(上限労働時間)を使用して年間の上限労働時間を算出。
→365日÷7日×40時間=2,085.7時間
➁年間の上限労働時間を1日の上限労働時間で割り、年間の上限労働日数を算出。
→2,085.7時間÷8時間=260.7日
➂1年365日から年間の上限労働日数を引き、年間の最低休日数を算出。
→365日ー260.7日=104.3日≒105日
このように、労基法では年間休日数について明言していないものの、労働時間から逆算すると法的な最低ラインの年間休日数(105日)が算出できます。
求人情報を見たら年間休日が105日未満の会社がありますが、法律違反というわけではありません。
上記の例は、一日の所定労働時間8時間を前提としています。
仮に7時間だった場合は、上記の計算にならって計算すると年間休日は68日となるでしょう。
2085.7時間÷7時間=297.9日
365日ー297.9日=67.1日≒68日
年間休日68日は随分少なく感じますが、法定の週休1日を確保し、1日の労働時間8時間以内、土曜日をたとえば午前中勤務にすることができます。
そうすれば、週の所定労働時間40時間以下以内を遵守していますので、基準はクリアできるのです。
つまり、1日の所定労働時間を短縮すれば、年間休日数を少なくできるということです。
一方で、年間休日の中には、国民の祝日や年末年始休暇、夏季休暇など、会社が独自に導入できる休日(=法定外休日)が含まれています。
しかし、あくまで法定休日さえ確保しておけば、会社には休日を付与する義務はありません。
したがって、法律を上回る水準の休日法定外休日は、法律の水準を超える休日だと捉えてください。
まとめると、年間の法定休日は105日となりますが、それ未満の企業もあります。
年間休日は、法定休日と法定外休日を合わせた日数です。
Q2:年間休日数はどのくらいあるの?平均は?
A2:平均は「110. 5日」です。
以下は、令和3年に厚生労働省が公表している事業規模別の平均年間休日数です。
全体平均は110. 5110. 5日ですが、表からは、企業規模が大きくなるほど年間休日数が多いことがわかります。
反対に、事業規模が小さいと年間休日数も少なくなっている状況がわかるでしょう。
| 企業規模 | 平均年間休日数 |
| 1,000人以上 | 116.8日 |
| 300~999人 | 115.2日 |
| 100~299人 | 112.9日 |
| 30~99人 | 109.0日 |
| 令和33年調査計 | 110.5日 |
業種別に年間休日数を見ていくと、「情報通信業」「学術研究、専門・技術サービス業」「金融業、保険業」が118日を超えています。
それに対し、「宿泊業、飲食業」は97.1日と、年間休日数が3桁を切っている業種もあります。
| 順位 | 業種 | 年間休日数 |
| 1 | 情報通信業 | 118.8日 |
| 2 | 学術研究、専門・技術サービス業 | 118.8 |
| 3 | 金融業、保険業 | 118.4 |
| 4 | 電気・ガス・熱供給・水道業 | 116.8 |
| 5 | 教育、学習支援業 | 112.7 |
| 6 | 製造業 | 111.4 |
| 7 | 複合サービス業 | 110.4 |
| 8 | 不動産業、物品賃貸業 | 109.6 |
| 9 | 医療、福祉 | 109.4 |
| 10 | サービス業(他に分類されないもの) | 109.0 |
| 11 | 卸売業、小売業 | 105.7 |
| 12 | 生活関連サービス業、娯楽業 | 104.6 |
| 13 | 建設業 | 104.0 |
| 14 | 鉱業、採石業、砂利採取業 | 103.8 |
| 15 | 運輸業、郵便業 | 100.3 |
| 16 | 宿泊業、飲食サービス業 | 97.1 |
もし、あなたが志望する企業の年間休日数が多いのか少ないのか判断できない場合は、この企業規模や業種別の年間休日をチェックしてください。
だいたいのレベルが把握できるでしょう。
Q3:休日と休暇ってどう違うの?
A3:年間休日に含まれる休暇と、そうでない休暇があります。
求人情報を見ると、年末年始休暇や有給休暇、慶弔休暇など様々な休暇が記載されており、これらが年間休日に含まれるかどうか気になるでしょう。
まず、休暇には一定の基準を満たした場合に付与しなければいけない「法定休暇」と、会社が独自に設けている「特別休暇」の2種類があります。
下記の通り、法定休暇は年間休日の枠外ですが、「特別休暇」の中には年間休日に含まれる休暇と、そうでない休暇があります。
| 区分 | 休暇例 | 年間休日該当区分 |
| 法定休暇 | 有給休暇、育児・介護休業、看護休暇、産前産後休暇 | 年間休日に含まれない休暇 |
| 特別休暇 | 国民の祝日、夏季休暇、年末年始休暇 | 年間休日に含まれる休暇 |
| 特別休暇 | 慶弔休暇、病気休暇、リフレッシュ休暇、誕生日休暇、結婚休暇 | 年間休日に含まれない休暇 |
まず、法定休暇は年間休日には含まれません。
法定休暇は、有給休暇以外に本人の申し出があれば取得できる産前産後休暇や、育児休業、介護休業、子の看護休暇などがあります。
続いて、特別休暇についてです。
毎週の休日に加え、国民の祝日をはじめ、年末年始休暇や夏季休暇、ゴールデンウィーク休暇、創業記念日など、公休日の場合は年間休日に含まれます。
一方で、有給休暇は年間休日に含まれるのか気になるでしょう。
結論からいえば、有給休暇は年間休日の枠外です。
有給休暇は労基法第39条で定められている法的な休暇であるものの、会社休日とは別の概念です。
同じ会社の同僚でも、勤続年数によって1年間で付与される日数は異なります。
また、取得するタイミングも個人差があるため、年間休日の枠外だと捉えましょう。
さらに、年間休日や法定休暇とは別に会社が独自に定めている特別休暇があります。
例えば、慶弔休暇やリフレッシュ休暇、誕生日休暇などは特別休暇です。
まとめると、会社で取得できるお休みは、下記のように年間休日以外に法定休暇や特別休暇が上乗せされて構成されています。
| 会社で取得できるお休み=年間休日+法定休暇+特別休暇 |
ただし、「法定休暇」と「特別休暇」は一律に付与される年間休日とは異なり、ある一定の基準を満たした場合や、本人の申し出があった場合に適用されます。
Q4:完全週休2日制と週休2日制って違うの?
A4:全く違う制度です。
「完全週休2日制」と「週休2日制」は言葉は似ていますが、全く違う概念です。
「完全週休2日制」とは、毎週必ず2日の休日がある制度です。
休みの2日を土日にあてる会社が多いですが、下記のとおり土日以外も2日間設定することができます。
- 完全週休2日制(土・日)
⇒ 毎週土曜と日曜が必ず休み - 完全週休2日制(水・日)
⇒ 毎週水曜と日曜が必ず休み - 完全週休2日制(日・他1日)
⇒ 毎週日曜と他の曜日1日が必ず休み
一方で、「週休2日制」は、下記のように1か月の間に週2日の休みのある週が一度以上ある制度を指します。
- 週休2日制(日、第2・3・4水曜)
⇒毎週日曜と第2・3・4水曜が必ず休み - 週休2日制(日、月2回土曜日)
⇒毎週日曜と月2回土曜が必ず休み - 週休2日制(土・日 ※年4回土曜日出社日あり)
⇒基本的に毎週土曜と日曜が休み(ただし、年に4回土曜出社日あり)
飲食やアパレルなどのサービス業の求人情報でよくみかける「週休2日制(月7日 シフト制)」では、休日は会社のシフトによって決まり、月によって異なります。
ただし、毎月7日の休みがあること、月に1回以上2日休める週があり、他の週は1日以上の休みがあることは確定しています。
具体的な休みの曜日は月のシフトで決まるということです。
完全週休2日制と週休2日制はまったく異なる制度なので、求人票をチェックする時は注意しましょう。
Q5:年間休日125・120・110・105日は長い?短い?
A5:下記でそれぞれ説明します。
125日、120日は休日が多いと言えるでしょう。
110日、105日は比較的少ないと言えます。
まず「年間休日125日」のイメージを出します。
| 土日休み | 104日 |
| 祝日休み | 13日 |
| 夏季休暇 | 2日 |
| 年末年始休暇 | 6日 |
| 計 | 125日 |
もちろん上記はあくまでも例示なので、異なる会社もあります。
完全週休2日で、祝日もフルに休めて夏季や年末年始の休暇もあり、有給休暇と組み合わせれば、大型連休も可能です。
年間休日の水準が高い優良企業といえるでしょう。
このような企業を狙えれば、十分なお休みが獲得できます。
続いて、「年間休日120日」のイメージです。
| 土日休み | 104日 |
| 祝日休み | 13日 |
| 年末年始休暇 | 3日 |
| 計 | 120日 |
年間休日120あれば、基本的に完全週休2日制の企業が多いです。
中には祝日を出勤にし、その代わりを夏季休暇に充てて、ゴールデンウィーク休暇などを設ける企業もあります。
年間休日の平均から比べれば、上位の企業にあたります。
このレベルでも十分満足できる人は多いです。
次に「年間休日110日」のパターンです。
| 土日休み | 104日 |
| 祝日休み | 3日 |
| 年末年始休暇 | 3日 |
| 計 | 110日 |
さすがにこのレベルの年間休日数になると、祝日をフルに休むことが物理的に不可能です。
中には週休2日制で月に何日か土曜日出勤があり、その振替として、夏季休暇やゴールデンウィーク休暇などの休日に振り向ける企業もあります。
平均からみると下位の企業です。
最後に「年間休日105日」のパターンです。
| 日曜休み | 52日 |
| 土曜休み | 40日(※月1回土曜出勤) |
| 祝日休み | 13日 |
| 計 | 105日 |
1日8時間の勤務で考えた場合、労基法ギリギリの年間休日数です。
週6日勤務の週と週5日勤務の週とが混在する働き方で、あくまでも最低ラインだと考えましょう。
世間から見ると、年間休日の水準はかなり劣位です。
やり遂げる自信があるか、そこまでしてやりたい仕事かどうか、選考を受ける前に改めて考えておきましょう。
年間休日を把握することで、休みのレベル感を掴むことができます。
Q6:面接で休日のことを聞いたらマズいの?

A6:あまり印象はよくありません。
2つの理由で心証を害します。
1つ目は、面接の場で聞く質問としてはふさわしくないからです。
「その類の質問は会社説明会で済ませとけよ」
「ネットで調べればわかるんじゃん」
「それって面接の場で聞くような質問じゃないよね」
と人事は感じるでしょう。
面接の場での質問は、会社説明会やネットでは調べられず、マネージャーや幹部でないと答えられないような専門的な質問をするのがおすすめです。
「よくそこまで調べてきたね」
「よく調べてきたね」
「その角度からの質問があったか…」
など、思わず面接官を唸らせるレベルの質問に限定してください。
例:
「御社が今後の成長を目指すうえで、最も重要な課題は何でしょうか?」
「最近の製品開発で特に誇りに思われているものは何ですか?」
このような質問をすると良いでしょう。
2つ目の理由は、権利ばかりを主張してくる就活生に見えるからです。
企業は、次のような質問をする就活生のほうを好みます。
例:
「入社5年目の先輩方で優秀な方はどのような働き方をされていますか?」
「入社前に学習しておいたほうがいいことは何ですか?」
「私自身、英語を使った仕事に興味があり、御社の海外トレーニー制度にかなり関心があるのですが、具体的にどのような制度で何を学べるでしょうか?」
こうした前向きで成長意欲をうかがわせるような質問がベターです。
一方で、
「毎年どのくらい昇給してるのですか?」
「ボーナスはどのぐらいもらえますか?」
「有給休暇は取りやすいですか?」
など、自らの権利ばかりを確認してくる学生は、印象が悪くなるでしょう。
なぜなら、入社後に自分の仕事を棚に上げて自分の権利ばかりにこだわっているように見えるからです。
自分の権利ばかり主張する人は、企業にとって面倒くさそうな人物に見えます。
福利厚生なども同じような質問のジャンルになるでしょう。
休みや給与面の疑問については、できるだけOB/OG訪問や会社説明会など、就活初期の段階で解消してください。
OB/OG訪問や会社説明会では、このような質問をしにくいと感じる就活生もいますが、疑問に思うなら積極的に質問しましょう。
面接時に聞くほうが減点になってしまい、不利になるからです。
ミスマッチを防ぐためにも、疑問は早いうちに解消しましょう。
まとめ
以上、年間休日の気になるポイントについてQ&Aで解説してきました。
年間休日について、休日と休暇について、面接について、様々な角度から説明してきました。
年間休日とは、会社が定めている年間の休日合計数で、平均は「110. 5日」です。
休日と休暇には、年間休日に含まれる休暇と、そうでない休暇があります。
完全週休2日制と週休2日制は、まったく違う制度です。
面接で休日のことを聞くのは避けたほうがいいでしょう。
このように、年間休日については、知っておくべき前提知識がいくつか存在します。
入社後に、「こんなに休日が少なくてブラックだとは思わなかった」なんてことにならないように、今回の記事を参考にしてもらえば幸いです。
なお、たとえ年間休日数が多くても、やりがいのない仕事なら苦痛に感じるでしょう。
反対に、年間休日数が少なくても、やりがいのある仕事なら満足して働ける可能性があります。
年間休日数だけで将来の仕事を決めるのはリスクが高いです。
年間休日数は、あくまで参考としましょう。
大切なのは、自分がその企業で意欲的に働けるか、長く働けそうか、企業の求める人物とマッチしているかなど、総合的に考えて決めることです。
本当に自分がしたい仕事か、やりがいを持って長く働けそうかを優先して考えましょう。
判断材料として、年間休日数をチェックすると良いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。