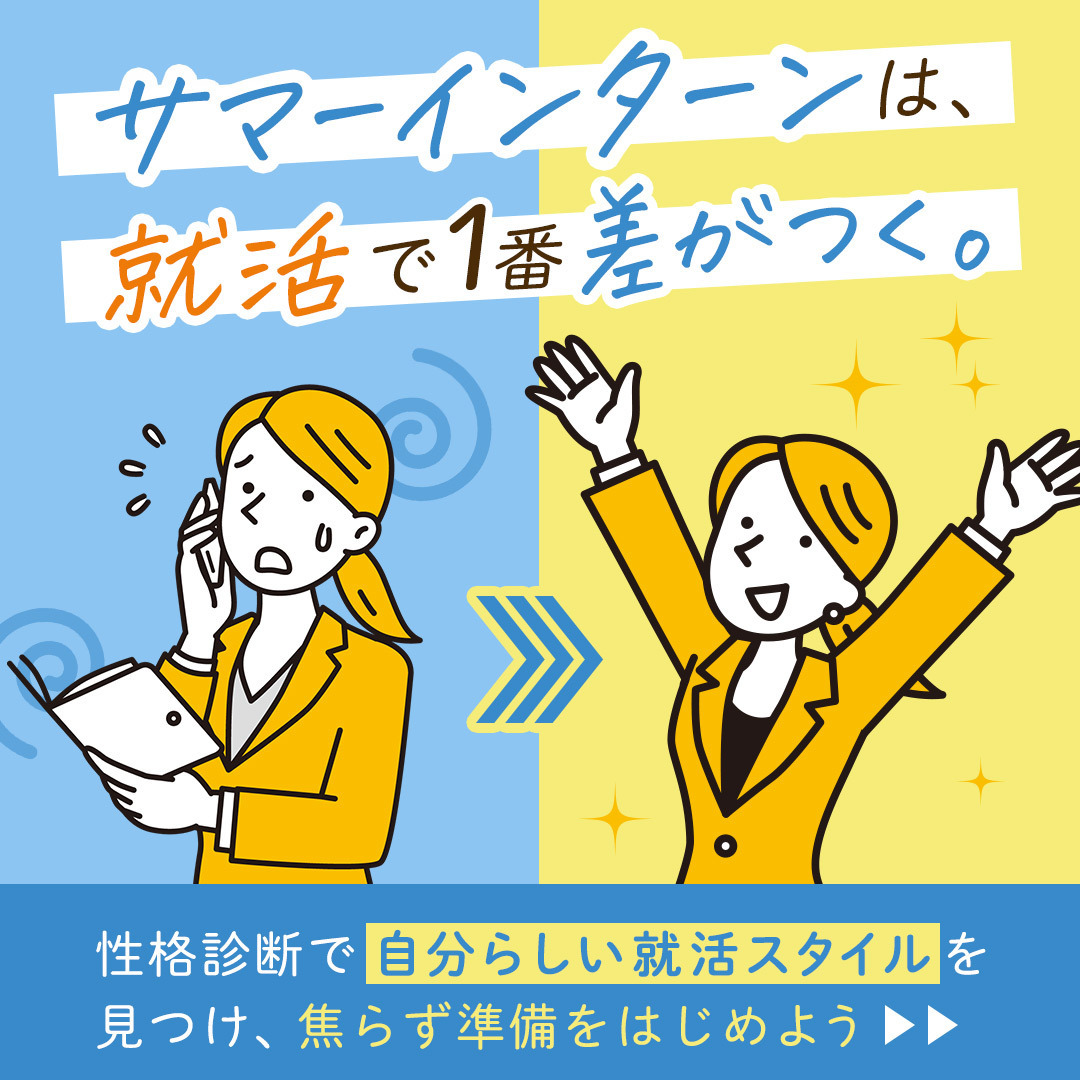グループディスカッションの役割とは?テーマ毎のコツをつかもう
2024/10/8更新
はじめに
就活生の多くは、グループディスカッションに対して不安や疑問を抱えているでしょう。
- どんなテーマが出題されるのか?
- どのように準備すればいいのか?
- 評価のポイントは何なのか?
こういった悩みは、ほとんどの就活生が経験するものです。
近年の就職活動では、グループディスカッションが重要な選考方法として定着しており、多くの企業が採用しています。
しかし、初めて経験する就活生にとっては、何から始めればいいのか分からず、不安が募る一方かもしれません。
この記事では、グループディスカッションのテーマ傾向を4つに分類し、それぞれの対策方法を具体的に解説します。
さらに、評価のポイントや当日の立ち回り方など、先輩就活生が苦労して得たノウハウを一挙に公開します。
また、効果的な準備方法や、自信をつけるためのトレーニング方法も紹介するので、ぜひ参考にしてください。
この記事を通じて、皆さんがグループディスカッションに自信を持って臨めるよう、しっかりとサポートしていきます。
グループディスカッションの役割や特徴が知りたい人は、以下の記事をチェックしてみてください。
上京を志す地方学生ならジョーカツ!
あなたのキャリアを加速させるチャンス!
無料で利用できる快適な個室シェアハウス、
東京までの交通費サポート付き
首都圏の注目企業への就活ならジョーカツ
首都圏の学生ならスタキャリ!
理想のキャリアを実現へと導く第一歩!
あなたにピッタリのキャリアアドバイザーを選び、
自分にマッチする優良企業をご紹介
首都圏企業のES添削から面接対策まで、就活ならスタキャリ
グループディスカッションの目的
企業の人事担当者が選考の序盤にグループディスカッションを行なう理由は以下の3つです。
- チームで働く時の動きが見たい
- コミュニケーション能力を把握したい
- 複数人をまとめて評価できる
チームで働く時の動きが見たい
あなたが置かれている立場や状況に応じてどのような対応をするのかを見て、主体性や協調性を評価します。
コミュニケーション能力を把握したい
ここで言うコミュニケーション能力とは単に誰とでもすぐに打ち解け話すことができる等という能力の事ではなく、論理的に話すことができるか、他者の意見を聞き議論することができるかというような能力の事です。
複数人を一度に評価できる
選考の序盤に行なう理由がここにあり、裏を返せば上の2つの能力が一定の水準を満たさない人をふるいにかけるために行なっているのです。
つまり、就活生1人1人のこれまでの経験や知識・スキルを知りたいのではなく、単にチームで働き、貢献することができる人間であるかどうかを企業側は測りたいのです。
グループディスカッションテーマ一覧【厳選10個】

グループディスカッションで扱われるテーマは、応募者の思考力や発言力を見極めるための重要な要素です。
この章では、実際のグループディスカッションで使用される可能性が高いテーマを10個厳選して紹介します。
- 社会問題に関するテーマ3つ
- ビジネス課題に関するテーマ4つ
- 学生生活に関するテーマ3つ
これらのテーマを詳しく見ていきましょう。
社会問題に関するテーマ3つ
社会問題に関するテーマは、応募者の社会への関心や問題解決能力を測るのに適しています。
1つ目は「高齢化社会における労働力不足の解決策」というテーマです。
このテーマでは、少子高齢化が進む日本社会の課題と、その解決策について議論することができます。
2つ目は「デジタル化の進展による個人情報保護の在り方」です。
テクノロジーの発展に伴い、個人情報の取り扱いがますます重要になっている現状を踏まえたテーマで話せます。
3つ目は「地球温暖化対策と経済成長の両立」というテーマを挙げます。
環境保護と経済発展のバランスという、現代社会が直面する難しい課題について考えを深められます。
これらのテーマについて、自分なりの意見を持っておくと良いでしょう。
ビジネス課題に関するテーマ4つ
ビジネス課題に関するテーマは、応募者のビジネス感覚や問題解決能力を評価するのに適しています。
1つ目は「テレワークの導入による生産性向上と課題解決」というテーマです。
コロナ禍で急速に広まったテレワークの利点と課題について、具体的な解決策を議論できます。
2つ目は「AI技術の導入による業務効率化と人材育成の両立」です。
AI技術の活用と人材の役割について、バランスの取れた視点で議論することが求められます。
3つ目は「グローバル展開における現地化戦略とブランド統一」というテーマを挙げます。海外進出時の現地適応と企業理念の維持という、相反する課題についての解決策を探ります。
4つ目は「顧客満足度向上とコスト削減の両立」です。
サービス品質の向上と経営効率化という、企業が常に直面する課題について議論できます。これらのテーマについて、具体的な事例を交えて意見を述べられるよう準備しておきましょう。
学生生活に関するテーマ3つ
学生生活に関するテーマは、応募者の身近な経験や視点を活かした議論ができます。
1つ目は「大学教育のオンライン化のメリットとデメリット」というテーマです。
コロナ禍で急速に進んだオンライン授業について、学生の立場から意見を述べることができます。
2つ目は「インターンシップの意義と課題」です。
就職活動の一環として広く行われているインターンシップについて、その効果と問題点を議論できます。
3つ目は「大学生のアルバイトと学業の両立」というテーマを挙げます。
多くの学生が経験するアルバイトと学業の両立について、具体的な方策を提案できます。
これらのテーマについて、自身の経験を踏まえつつ、客観的な視点も加えて意見を述べられるよう準備しておきましょう。
グループディスカッションのねらいとは

グループディスカッションは、応募者の多面的な能力を評価するための重要な選考方法です。
ここでは、企業や団体がグループディスカッションで評価しようとしている4つの主要なポイントについて解説します。
- コミュニケーション能力の評価
- 論理的思考力の確認
- リーダーシップの観察
- 協調性の把握
これらのポイントについて、詳しく見ていきましょう。
コミュニケーション能力の評価
グループディスカッションでは、参加者のコミュニケーション能力が重要な評価対象となります。
企業は、応募者が自分の意見を明確に伝えられるか、また他者の意見を適切に理解できるかを見ています。
効果的なコミュニケーションには、話す力だけでなく、聴く力も不可欠です。
相手の話を途中で遮らず、適切なタイミングで自分の意見を述べることが高評価につながります。
また、非言語コミュニケーション、例えば表情やジェスチャーなども評価の対象となります。
これらの要素を意識し、バランスの取れたコミュニケーションを心がけましょう。
論理的思考力の確認
グループディスカッションでは、参加者の論理的思考力も重要な評価ポイントです。
企業は、応募者が問題を適切に分析し、論理的な解決策を提案できるかを確認しています。論理的思考力は、意見の構成や主張の裏付けとなる根拠の提示などで評価されます。
また、他者の意見に対して適切な質問や反論ができることも、論理的思考力の表れとして見られます。
抽象的な議論に終始せず、具体例を交えながら論理的に意見を展開することが重要です。
論理的思考力を示すためには、日頃から社会問題やビジネス課題について考える習慣をつけておきましょう。
リーダーシップの観察
グループディスカッションでは、参加者のリーダーシップも重要な評価対象となります。
企業は、応募者が議論をリードし、グループ全体の意見をまとめる能力があるかを見ています。
ただし、リーダーシップは必ずしも強引に自分の意見を押し通すことではありません。
他のメンバーの意見を尊重しながら、議論を建設的な方向に導くことが真のリーダーシップです。
時間管理や議論の進行役を買って出ることも、リーダーシップの一つの形として評価されます。
また、議論が停滞したときに新しい視点を提供し、話し合いを活性化させる行動もリーダーシップの表れです。
協調性の把握
グループディスカッションでは、参加者の協調性も重要な評価ポイントとなります。
企業は、応募者がチームの一員として適切に機能できるかを確認しています。
協調性は、他のメンバーの意見を尊重し、建設的な態度で議論に参加することで示されます。
自分の意見を主張するだけでなく、他者の意見を取り入れ、グループ全体の合意形成に貢献することが重要です。
また、議論が対立した際に、双方の意見を調整し、妥協点を見出す能力も協調性の表れとして評価されます。
ただし、協調性を示すあまり、自分の意見を全く言わないのは望ましくありません。
適度なバランスを保ちながら、協調性と自己主張を両立させることがグループディスカッションでは求められます。
グループディスカッションで高評価を得るコツ
グループディスカッションで高評価を得るには、単に自分の意見を述べるだけでは不十分です。
ここでは、評価者の目に留まり、好印象を与えるための重要なコツを4つ紹介します。
- 積極的な発言と傾聴
- 論理的な意見の組み立て方
- 協調性を示す態度
- タイムマネジメントの重要性
これらのコツを意識して実践することで、グループディスカッションでの評価を大きく向上させることができます。
積極的な発言と傾聴
グループディスカッションでは、積極的に発言することと、他者の意見をしっかり聞くことのバランスが重要です。
まず、議論の初期段階で自分の意見を述べることで、存在感を示すことができます。
しかし、発言の量だけでなく、質も重要です。
他のメンバーの発言をよく聞き、それを踏まえた上で自分の意見を述べることで、議論の深化に貢献できます。
また、他者の意見に対して適切な質問をすることも、積極性と傾聴の姿勢を示す良い方法です。
聞き役に徹しすぎず、かといって話しすぎず、バランスの取れた参加を心がけましょう。
論理的な意見の組み立て方
論理的な意見の組み立ては、グループディスカッションで高評価を得るための重要なスキルです。
まず、主張したい結論を明確にし、それを支持する理由や根拠を2〜3点挙げます。
例えば「〇〇すべきだと思います。なぜなら、第一に〜、第二に〜、第三に〜だからです」という構成です。
また、具体例や数字を用いて説明することで、説得力が増します。
抽象的な表現は避け、できるだけ具体的な言葉で説明することを心がけましょう。
反対意見にも言及し、それを踏まえた上で自分の意見を述べることで、より説得力のある主張になります。
協調性を示す態度
グループディスカッションでは、個人の能力だけでなく、チームの一員としての適性も評価されます。
他のメンバーの意見を否定せず、「〜さんの意見に賛成です。さらに付け加えるとすれば…」といった表現を使いましょう。
また、議論が行き詰まった際に、「ここまでの議論をまとめてみましょう」と提案することも有効です。
さらに、発言の少ないメンバーに「〜さんはどう思いますか?」と意見を求めることで、協調性をアピールできます。
ただし、協調性を示すあまり自分の意見を言わなくなるのは避けましょう。
適度に自己主張しつつ、全体の議論に貢献する姿勢が求められます。
タイムマネジメントの重要性
グループディスカッションでは、限られた時間内に結論を出すことが求められます。
そのため、時間を意識しながら議論を進めることが重要です。
例えば、「残り時間が15分なので、そろそろ結論に向けて議論をまとめましょう」と提案することができます。
また、議論の序盤、中盤、終盤でどのような内容を話し合うべきかを提案することも有効です。
時間配分の提案をすることで、リーダーシップを発揮することができます。
ただし、時間を意識するあまり、他のメンバーの発言を遮ったり、結論を急いだりするのは避けましょう。
適度なペース配分で、全員が納得できる結論に導くことが理想的です。
さいごに
このグループディスカッション対策の記事は、就職活動や入社試験に臨む学生や若手社会人向けの実用的なガイドです。
具体的なテーマ例や評価ポイント、高評価を得るコツを詳しく解説しています。
コミュニケーション能力、論理的思考力、リーダーシップ、協調性など、企業が重視する要素を理解し、それらを効果的に示す方法を学べます。
積極的な発言と傾聴のバランス、論理的な意見の組み立て方、協調性を示す態度、タイムマネジメントの重要性など、実践的なアドバイスも提供しています。
この記事を参考に準備することで、自信を持ってグループディスカッションに臨めるでしょう。