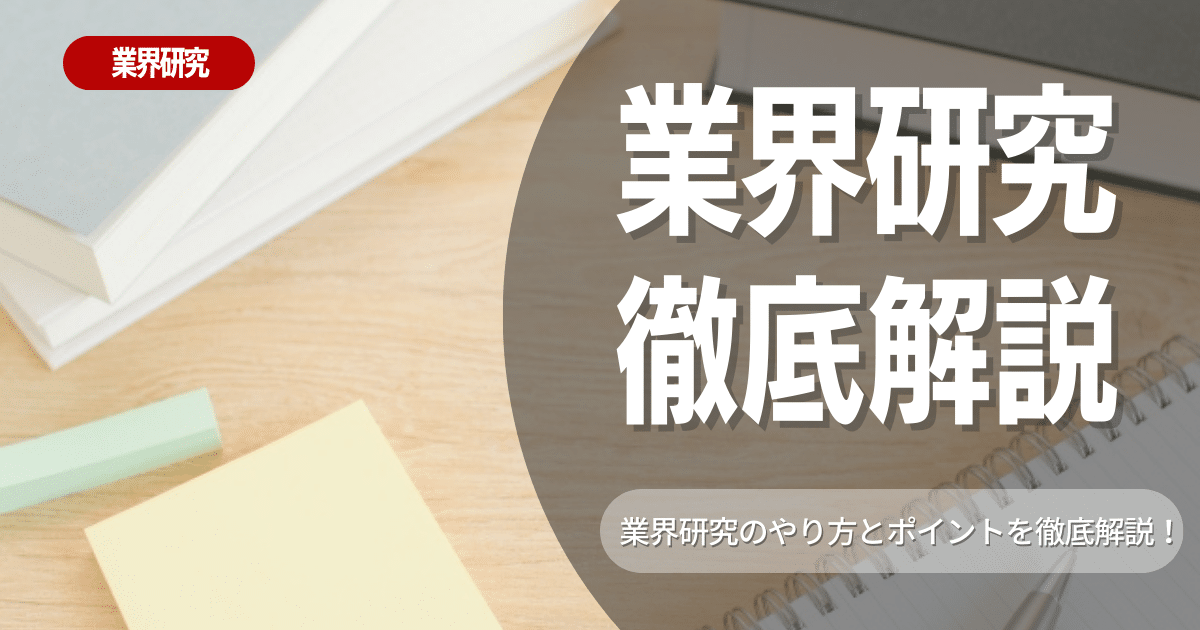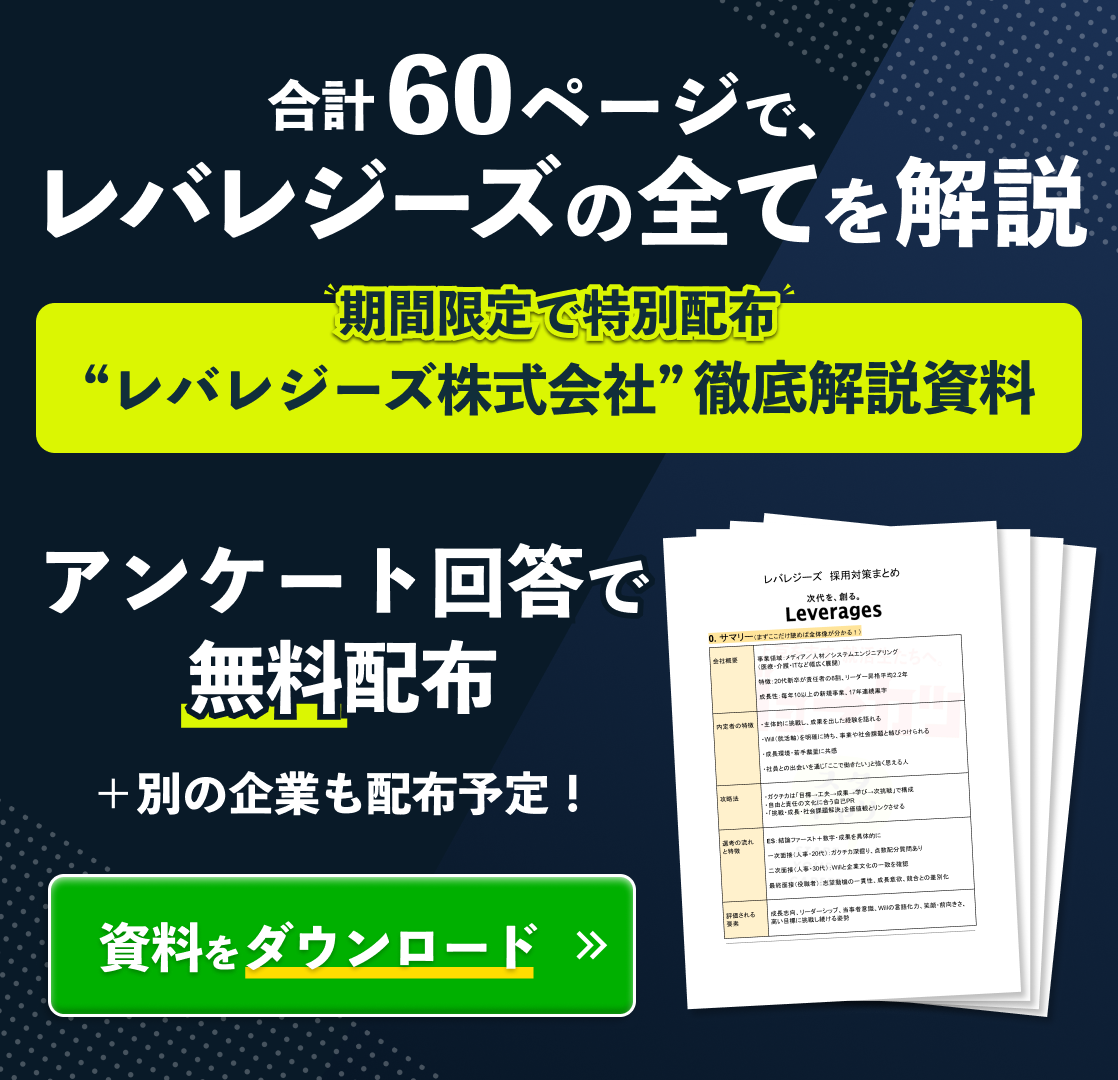業界を絞らず就活しても大丈夫?メリット・デメリットもご紹介!
2024/6/21更新
はじめに
就職活動で大切なのは、「どんな仕事に就きたいか」という就活の軸を明確にすることです。
そうした「就活の軸」と決める際に大切になってくるのが、「業界を絞ること」。
しかし、就活生の皆さんの中には「なかなか志望業界が絞れない」、「業界を絞らず就活してはダメ?」という悩みを抱えている人も少なくありません。
業界を絞るメリットも多いですが、業界を絞らないことで思ってもいなかった企業と出会い、理想の就職先を見つけられるでしょう。
そこで本記事では、業界を絞らずに就活することのメリット・デメリットや、業界の絞り方のコツなどをご紹介します。
この記事は以下のようなことを知りたい就活生が対象です。
- 業界を絞って就活した方がいいか知りたい
- 業界を絞らない就活のメリット・デメリットを知りたい
- 業界の絞り方を知りたい
ぜひ最後までお読みいただき、参考にしていただけたら幸いです。
上京を志す地方学生ならジョーカツ!
あなたのキャリアを加速させるチャンス!
無料で利用できる快適な個室シェアハウス、
東京までの交通費サポート付き
首都圏の注目企業への就活ならジョーカツ
首都圏の学生ならスタキャリ!
理想のキャリアを実現へと導く第一歩!
あなたにピッタリのキャリアアドバイザーを選び、
自分にマッチする優良企業をご紹介
首都圏企業のES添削から面接対策まで、就活ならスタキャリ
この記事の結論
先にこの記事の結論からお伝えすると、就職活動の初期から業界を絞る必要はありません。
ただし、業界を絞っていくメリットも多いため、就職活動を進めていくうち、興味のない業界を除外し、最終的に3〜5つほどの業界に絞っていくのがおすすめです。
もちろん、「自分は絶対にIT業界で活躍したい」、「食品メーカーで働くのが小さい時からの夢だった」など、確固たる信念があって就職活動を進めていく人もいます。
しかし、業界を1つだけに絞るのも複数のデメリットがあるため、あらかじめデメリットや注意点を理解した上で就職活動に挑むのが大切です。
次の章からは、業界を絞らずに就活することのメリット・デメリットや、自分に合った業界の絞り方のコツについて、わかりやすく解説していきます。
業界を絞らず就活するメリット

通常、就職活動は自己分析などで「やりたいこと」や、「譲れない条件」などを見極め、次に職種や業界を絞ってからエントリーする企業を決定するという流れが一般的です。
始めから「この業界にしか興味ない」という人であれば迷うことはありませんが、多くの就活生の皆さんは「なかなか業界が絞れない」という人も多いでしょう。
しかし、あえて業界を絞らずに就職活動をすることで得られる、以下のようなメリットもあります。
- 広い視野で志望する企業を見つけられる
- より自分に合う企業に出会える可能性が上がる
- 選択肢が増える
- 「職種」を優先して選びやすい
- リスク分散ができる
以下では、こうしたメリットについて詳しくご紹介します。
広い視野で志望する企業を見つけられる
業界を絞らずに志望企業を探すことで、説明会や就活イベントといった場で、より多くの企業と出会えます。
広い視野を持って就職活動をすることで、さまざまな企業の価値観や理念、業界の特性などを知ることができ、新たな発見に繋がるかもしれません。
また、就職活動の目的は理想の職場を見つけることではありますが、社会勉強という側面があるのも事実です。
さまざまな業界について知ることで、社会全体の仕組みを知り、社会人になった後も役立つ知識が身につくかもしれません。
より自分に合う企業に出会える可能性が上がる
1つに絞って就職活動を進めると、視野が狭くなり、自分に合った企業を見落としてしまう可能性があります。
例えば、IT企業を志望していた学生が、「自分はITに限らず、『モノづくり』が好きかもしれない」と気づきを得ることで、メーカーなどにチャレンジしたくなる、ということも考えられます。
「自分にはこの業界は合わない」という固定概念を取り払うことで、より自分に合った企業と出会えるチャンスが増えるかもしれません。
選択肢が増える
総務省統計局の調査によると、令和3年6月1日時点で企業等の数は368万企業にも上るとされているのです。
この中で、例えば建設業の企業数は42万6,155で、全体の11.6%を占めます。
これは裏を返せば、建設業界に絞って就職活動をすると、残りの約90%の企業は選択肢から除外されてしまうということです。
より多くの選択肢から、エントリーする企業を選ぶことで、最終選考まで進む企業の数も増えます。
つまり、より多くの会社から内定をもらえる可能性が上がり、納得のいく就職活動になりやすいとも言えるでしょう。
「職種」を優先して選びやすい
もし、「営業職をやりたい」、「経理事務に就きたい」など、譲れない職種がある場合であれば、業界を絞らずに職種を優先して選ぶのもおすすめです。
仮に「IT業界の営業をやりたい」と「業界・職種」のどちらも絞り切ってしまうと、選択の幅が非常に狭くなってしまいます。
特にこだわりがない場合は、業界をあえて絞らないことで理想の仕事を見つけることができるかもしれません。
リスク分散ができる
1つの業界に絞って就活を進めてしまうと、世界情勢の変化や突発的な要因により、業界全体の営業不振が起きてしまうなど、突発的なトラブルに対応できません。
複数の業界を志望することで、「ある業界が不況になり募集人員を減らす事態に陥っても、他の業界も受けていたから大丈夫」という風に、リスク分散ができるはずです。
また、業界に固執するあまり、実は自分自身にその業界が合っていなかったと遅れて気づいた場合、就職活動の方向性をゼロから変えなければなりません。
広い視野を持って複数の業界を見ておくことで、こうしたトラブルを避けることができるのです。
業界を絞らず就活するデメリット

業界を絞らずに就職活動をすることで、広い視野を持ってさまざまな選択肢の中から企業を選ぶことができますが、一方で業界を絞らないデメリットも存在。
以下では、業界を絞らずに就活するデメリットについてご紹介します。
- 業界研究が大変になる
- 業界の理解が浅くなる可能性がある
- 志望度の高さをアピールしにくい
- 優先順位がつけにくくなる
一つずつ解説していきましょう。
業界研究が大変になる
当然ながら、業界を絞らずに就職活動をするということは、その分たくさんの業界研究をしなければなりません。
業界は、大きく分けて以下の8つに区分可能です。
- メーカー
- 商社
- 小売
- 金融
- サービス
- マスコミ
- ソフトウエア・通信
- 官公庁・公社・団体
さらに「メーカー」の下には、「食品メーカー」、「化粧品メーカー」、「自動車メーカー」などがあり、つくるものによって業界の特性が変わることもあります。
まったく絞らないということは、こうした膨大な数の業界研究に追われるということであり、負担が増えてしまうのがデメリットです。
業界の理解が浅くなる可能性がある
業界研究の大変さに通じることですが、たくさんの業界を研究しなければならない関係上、一つひとつの業界についてじっくり研究する時間が取れず、理解度が浅くなってしまう可能性があります。
業界研究は、面接などで「どうしてこの業界を選んだのか」という質問を切り抜けるだけでなく、就職後に後悔しないための企業選びのためにも欠かせないものです。
また、たくさんの就活生の中から内定を獲得するために、業界理解が乏しいと大きく不利になってしまうのもデメリットと言えるでしょう。
志望度の高さをアピールしにくい
選考過程で必ず聞かれる「志望動機」ですが、「私は○○業界に絞って就活をしています」などと記載し、実際に業界への理解が深いと、企業の担当者は「志望度が高い」と判断する可能性が高くなります。
絞らずに就活することで、「なぜこの業界なのか」という回答の軸が作りにくくなり、個別の対策が必要になるかもしれません。
優先順位がつけにくくなる
業界を1つ、または3つ程度に絞っていると、「第一志望はこの業界、第二志望はこの業界」など、優先順位がつけやすくなり、エントリーする企業が選びやすくなります。
しかし、業界を絞らないで就職活動を進めると、こうした優先順位がつけづらくなり、エントリー先の企業選びが難航してしまうかもしれません。
エントリー企業は、スピーディーかつ効率よく選ぶことでエントリーシートや面接対策にかける時間を増やすことができるでしょう。
業界の軸が定まっている就活生よりも、遅れをとってしまうかもしれないというデメリットがあることは、覚えておくべきです。
業界を絞るなら3〜5業界程度がおすすめ!
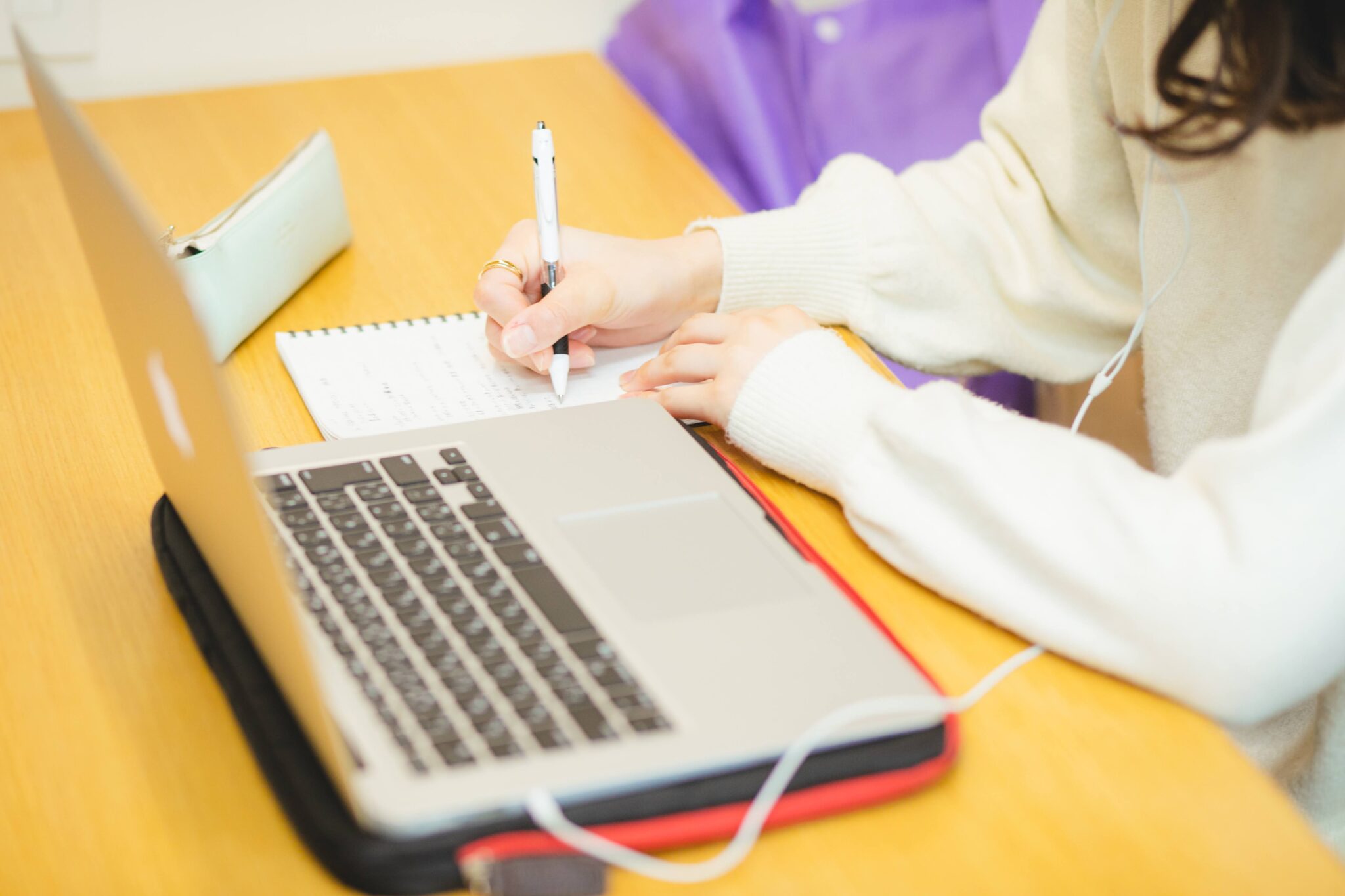
「少しでも就活の負担を軽くしたい」と思う一方で、「でも、業界を1つに絞るのは不安だ」という人も多いようです。
しかし、就職活動の際は必ずしも1つの業界に絞って行う必要はありません。
むしろ、無理のない範囲で業界をまたいで就職活動を行う事で、知見を広げたり、思わぬ優良企業を見つけることができるかもしれません。
以下では、業界を絞る際のコツやポイントをご紹介します。
- 業界研究関連の書籍を読む
- インターネットで調べる
- 就活イベントに参加する
- 企業説明会に参加する
- OB・OG訪問で理解を深める
一つずつ解説していきます。
業界研究関連の書籍を読む
書店の就活関連のコーナーにいくと、業界研究の書籍が数多く並んでいます。
中でも東洋経済新聞社の「業界地図」や、日本経済新聞社の「日系業界地図」は、毎年最新版が更新され、発売されている人気シリーズです。
業界ごとの働きやすさのランキングや、業界ごとの景況を分かりやすく解説するコーナーなどがあり、業界研究の入門書として非常に優秀な一冊になっています。
インターネットで調べる
特定の業界について詳しく知りたい場合は、インターネットで調べてみましょう。
その業界で名の知れたトップ企業や上場企業が分かれば、直接ホームページを見に行ってみるのもいいかもしれません。
また、経済産業省のサイトにある「統計」のページでは、各産業の動向を定期的にまとめて公開しているため、興味がある人は調べてみると良いでしょう。
就活イベントに参加する
就活イベントは、一度に多くの業界の企業を見て比較ができるため、非常に便利です。
中でも業界研究セミナーは、各業界のリアルな情報を集められるだけでなく、直接担当者に質問ができるなど、表面的な部分から深いところまで知ることができるでしょう。
具体的な希望業界がない場合でも、積極的に参加してみてください。
企業説明会に参加する
より深く業界のことが知りたい場合、その業界の代表的な企業の説明会に参加してみるのもいいでしょう。
いくつかの企業説明会に参加すると、大体の業界傾向や特徴が見えてきます。
ただし、1社ずつ説明会に参加するというのは、時間的なコストもかかるため、ある程度企業選びの方向性が定まった状態で参加することがおすすめです。
OB・OG訪問で理解を深める
就活の初期段階でOB・OG訪問を利用するのは、あまり得策ではありません。
しかし、業界研究が進み、ある程度興味のある業界が出てきたら、該当する企業のOB・OG訪問を通して、業界への理解をより深めるのも有効な手段です。
業界を絞らずに就活する際の注意点

- 自己分析をしっかりする
- 企業のネームバリューやイメージに惑わされない
- 合わない業界は選択肢から外す
- 外資系企業は選考が早いため、注意する
自己分析をしっかりする
就職活動の基本ではありますが、エントリー企業を選ぶ際には自己分析は欠かせません。
「とにかく自分がワクワクする仕事がしたい」、「ワークライフバランスを重視して働きたい」、「頑張り次第で収入がアップする仕事がしたい」など、自分の価値観を突き詰め、それに合った企業を探す必要があります。
この軸がブレていなければ、業界をまたいで就職活動をしても、内定後に後悔する可能性はぐんと下がるでしょう。
逆に、この軸がはっきりしないまま企業選びをしてしまうと、合格率が下がることはもとより、後悔の残る就活になってしまうかもしれません。
企業のネームバリューやイメージに惑わされない
業界を絞らない就活は、幅広い選択肢を持てるのが魅力になります。
しかし、「有名企業だから、クリーンだろう」、「この業界は仕事がキツいイメージがある」という理由でエントリーをしたり、逆にエントリーを避けたりするのは、非常にもったいないです。
「実際に企業を訪ねてみたら、思っていたイメージと違った」ということは、就活では珍しくありません。
先入観をもたず、事前にしっかりと情報収集をしたり、積極的に企業説明会を受けるなど、知見を広げながら徐々に業界を絞っていきましょう。
合わない業界は選択肢から外す
就活を進めていくうちに、最初は業界不問で調べていても、だんだんと興味の強い業界が出てくるものです。
反対に、「自分の就活の軸とは合わないかもしれない」と感じた業界は、少しずつ選択肢から外していきましょう。
外資系企業は選考が早いため、注意する
数ある業界の中でも、外資系の企業は他の業界に比べて非常に早い時期から選考をスタートする傾向です。
そのため、業界を絞らずに外資系も選択肢に入れる場合、早めに準備をしないと選考ルートに乗り遅れてしまう可能性があります。
メーカーやIT業界など、外資系企業も多い業界を少しでも志望する場合は、選考の時期も頭に入れるようにしましょう。
以下の記事では、早期選考を実施する業界についてご紹介しています。
ぜひ参考にしてみてください。
まとめ
本記事では、業界を絞らずに就活する際のメリット・デメリットや、注意点についてご紹介しました。
業界をある程度絞ることで、業界への理解を深めながらも就活の「軸」を定めることができるはずです。
しかし、必ずしも1つの業界に絞らなくても大丈夫ですので、最初は業界を絞らず色々な企業を見た上で、最終的に3〜5つ程度の業界に絞っていくと良いでしょう。
もちろん、「どうしても企画職がやりたい」、「広報として活躍したい」など、やりたい職種が定まっている場合は、この限りではありません。
しかし、「職種軸」で就活する場合も、面接では必ずと言っていいほど「どうしてこの業界を選んだか」は聞かれるため、選考を受ける企業の業界研究は怠らないようにしましょう。
また、業界研究の詳しいやり方については、以下の記事でご紹介しています。
ぜひ参考にしてみてください。