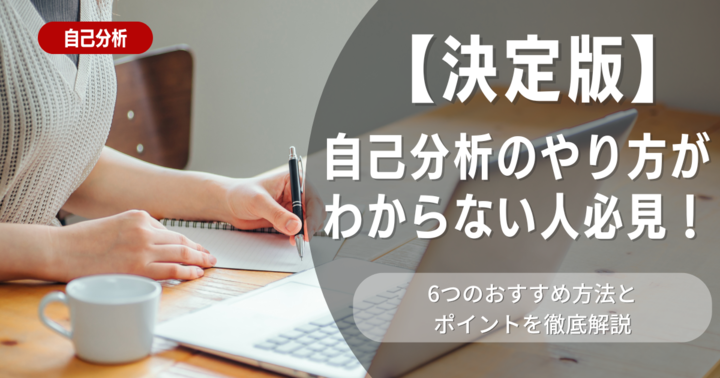就活全落ちの特徴と原因!これからできる挽回方法も解説
2024/10/8更新
はじめに
就職活動において志望している企業、全て落ちてしまうなんてことは必ずしもないとは限りません。
進路が決まらず時間が経過していくと不安や恐怖が募る一方でしょう。
全落ちしてしまった際には、あなたご自身が否定されたような感覚に陥り、モチベーションが低下してしまうかもしれません。
そのような経験をしないように、就職活動をするにあたって対策を練ることは欠かせません。
希望通りにコマを進められるように、本記事では以下の内容について解説していきます。
- 就活における全落ちとは
- 就活で全落ちしてしまう人の特徴
- 就活全落ちの原因
- 全落ちを避けるべく事前準備
- 就活全落ちからの挽回方法
役立つ情報が満載となっていますので、ぜひ最後までご覧ください。
上京を志す地方学生ならジョーカツ!
あなたのキャリアを加速させるチャンス!
無料で利用できる快適な個室シェアハウス、
東京までの交通費サポート付き
首都圏の注目企業への就活ならジョーカツ
首都圏の学生ならスタキャリ!
理想のキャリアを実現へと導く第一歩!
あなたにピッタリのキャリアアドバイザーを選び、
自分にマッチする優良企業をご紹介
首都圏企業のES添削から面接対策まで、就活ならスタキャリ
就活における全落ちとは

就活における”全落ち”とは、エントリーした企業全てから不採用となることを指します。
全落ちの状況は時期によって異なり、大学4年生の6月前後で分けられます。
6月以前は就活の前半期で、全落ちしても諦めるには早すぎます。まだエントリーできる企業が多く残っているため、粘り強く続けることが大切です。
一方、6月以降は就活後半期となり、全落ちすると絶望感を味わいやすくなります。
しかし、年間を通じて学生募集を行う企業もあるため、ここでも諦めるのは早いでしょう。就活は自分次第です。他人と比較せず、自分のペースで進めることが重要です。
時期が遅くなるほどエントリーできる企業は減少しますが、最後まで情報収集を怠らず、諦めずに取り組みましょう。
就活で全落ちしてしまう人の特徴

就活に励んでいても、どうしても全落ちしてしまう方はいらっしゃいます。
ここでは、そのようになってしまう事例の特徴をピックアップして紹介していきます。
どのような特徴があるのか参考にしてみてはいかがでしょうか。
エントリー数が少なすぎるまたは絞り込みすぎ
エントリー数を絞りすぎてしまっている場合、全落ちしてしまう可能性は必然的に高まります。
応募した企業数自体が少ないことで、選考を進めていく母数が減少し、内定がゼロになる危険性が高まります。
志望している業界や業種が決まっている方は、他の業界の企業にはエントリーしないことがあると思いますが、絞りすぎてエントリー数が少なすぎるとリスクが生じてしまうことがあります。
やみくもにエントリーする必要性はありませんが、ある程度のエントリー数は必要でしょう。
学生の平均的なエントリー数は20社前後と言われています。時間は有限です。
あまり多くの企業に手を出しすぎても対策を練る時間が少なくなってしまいます。
ご自身の考えや都合に合わせて何社にエントリーするのかという限度について考えておくことも、就活対策に1つになるかもしれません。
大手や有名企業などの就職難易度の高い企業を受けている
大手企業あるいは有名企業など多くの学生が志望している企業は、人気があることから必然的に選考倍率が高くなる傾向があります。
また、そのような名の知れた企業であると合格水準が高い企業であることや、選考フローが多い企業、選考にあたっての基準が高い企業などがあります。
上記の理由からも、内定をもらえる可能性が他の企業と比べると低いと言えるでしょう。
大手企業や有名企業を軸にした就活を行っているとレベルが高いため、全落ちになってしまう可能性が高くなります。
ブランド力のある企業は、キラキラ見え憧れる気持ちは分かりますが、企業名のみで勝負すると難しい部分もあります。
あなたご自身がやりたいことを重視した就活に励むことをおすすめします。
基本的な選考対策ができていない
当たり前の話ですが、基本的な選考の対策が練れていないと内定まで辿りつける可能性は減少します。
筆記試験対策、業界・企業研究、面接対策の準備は決して怠ってはいけません。
業界・企業研究を行わずに面接に臨む就活生が実際にいるそうです。
そのような姿勢では、採用側はこれから一緒に働いていきたいとは思えないと考えられるはずです。
また、それ以前に、就活マナーを守れていない場合は、更に内定に繋げることは難しいと言えるでしょう。
第一印象は大事な要素になります。
身だしなみ、清潔感、言葉遣いなどやるべきことは多岐にわたりますが、1つずつ着実に準備をしておきましょう。
業界・業種がばらばら
先ほど解説した業界・業種を絞りすぎている場合とは対照的に業界・業種がばらばら過ぎても、どの選考にも受からずに全落ちしてしまう危険性があります。
就活軸が決まっておらず、目についた求人を手あたり次第で応募している方は、この業界・業種がばらばらに該当しているでしょう。
面接時には、就活の軸を聞かれることが鉄板です。
その際に、浅い回答しかできず望んでいる結果は得られないでしょう。
その場で考えたことを言っても、深堀をされたら採用側は簡単に相手を見抜くでしょう。
就活の軸をしっかりと定め、業界・業種を絞りすぎず、絞らなさすぎずに基準を決めて就活に臨みましょう。
自己分析ができていない
就活の基本とも言える自己分析ができていない場合も、就活で全落ちしてしまう可能性があります。
自己分析ができていないと、やりたいことや将来像が不明確なため、準備不足や応募先である企業とのミスマッチに繋がってしまいます。
そのほかに、自己分析ができていないと選考において自分自身の強みなどうまく伝えることができずに、採用者からも評価をされにくくなります。
自己分析も就活では大事な要素になるため、おろそかにせず、しっかりと考えるようにしましょう。
自己分析のやり方がわからない方は、以下の記事をチェックしてみてください。
選考フェーズごとの対策ができていない
就活では、書類選考、適性検査、一次面接、二次面接、三次面接以降の過程を経て最終面接などを受験するといった様々なフェーズがあります。
この選考過程があることから、単に就活全落ちと言っても、人それぞれで落ちてしまう選考フェーズが異なります。
落ちてしまった際には、どこのフェーズにて何が良くなかったのかを分析をすることが大事になります。
そこの対策をしないと、違った企業でも同じような理由で選考が進まなくなる可能性が生じてしまいます。
このように、選考フェーズごとの対策ができていないと、それまでの選考をスムーズに突破できたとしても落ちてしまい、結果的には全落ちに繋げってしまうこととがあるはずです。
コミュニケーション力が不足している
就職活動において全落ちしてしまう方の中には、グループディスカッションや面接でうまく発言できないなどコミュニケーション能力が不足してしまっている傾向があります。
就活の過程のみならず就職してからも業務の内容を指示されるなどコミュニケーションは必須になります。
入社後からもコミュニケーション能力は求められるため、選考時には採用側は質問に対して的確に回答できるのか否か就活生にコミュニケーション能力をチェックします。
グループディスカッションにおいては、単にたくさん発言することがコミュニケーション能力不足しているわけではないという訳ではありません。
そこで求められるコミュニケーション能力は、面接官や周囲の就活生が話していることを的確に理解して、それに対して分かりやすく回答できることです。
自分自身をアピールしたいがゆえに、相手のことを考慮せず長々と話すことや相手の発言機会を奪ってまで積極的に発言することは避けるべきです。
発言量が少なすぎる、あるいは多すぎずということがないように、その場の雰囲気を読んで回答する立ち回りを可能な限り意識して臨みましょう。
企業が求めている人物像と適していない
たとえ優秀な就活生であっても、企業が求めている人物像とかけ離れすぎていると、採用されることは難しいと言えます。
よって、ご自身の適正と相性の悪い企業をエントリーしていることや、企業に対するアピールの方向性が合っていないと選考通過が難しくなります。
自分自身と企業の両方を理解して、企業がどのような人材を求めているのか、または自分にはどのような企業が合っているのかを考えてアピールする必要があるでしょう。
企業が求めている人材に関しては、それぞれの企業のHPにて求めている人材を記載されていることが多々あります。
1つの基準にもなるため、怠らずにそこの確認をすることをおすすめします。
以上のように、就活で全落ちしてしまう特徴について8つ紹介させていただきました。
これらすべてを解消することで選考をスムーズに行える可能性が高くなることでしょう。
先ほども申し上げましたが、万が一、全落ちしてしまってもチャンスはまだあります。
簡単に諦めることなく粘り強く就活に励むことが内定をゲットできる肝です。
就活全落ちの3つの原因
就活全落ちには、いくつかの共通する原因があります。
これらの原因を理解し、対策を立てることで、就活の成功確率を高めることができます。
- 準備不足
- 自信がない
- 企業と合わない
それぞれの原因について、詳しく見ていきましょう。
準備不足
準備不足は、就活全落ちの最も一般的な原因の一つです。
就職活動は、自己分析から業界研究、エントリーシート作成、面接対策まで、多くの準備が必要です。
しかし、全落ちする学生は往々にしてこれらの準備に十分な時間をかけていません。
準備不足は、エントリーシートの質の低下や面接でのパフォーマンス低下につながります。就活の各段階で必要な準備を洗い出し、計画的に取り組むことが重要です。
早めに準備を始め、十分な時間をかけることで、自信を持って就活に臨めるようになります。
自信がない
自信のなさは、就活全落ちの原因です。
自信がないと、エントリーシートや面接で自分の強みを十分にアピールできません。
また、自信のなさは態度や表情にも表れ、面接官に悪印象を与える可能性があります。
自信のなさは、往々にして自己理解の不足や過去の失敗体験から生じます。
自己分析を深め、自分の強みや成功体験を再確認することで、自信を取り戻すことができます。
また、小さな目標を設定し、達成感を積み重ねていくことも自信回復に効果的です。
企業と合わない
企業との不適合も、就活全落ちの一因です。企業は、自社の理念や文化に合う人材を求めています。
しかし、全落ちする学生は往々にして自分と企業との適合性を十分に考慮せずに応募しているでしょう。
企業との不適合は、志望動機の薄弱さや面接での違和感につながります。
自己分析と並行して、企業研究を深めることが重要です。
企業の理念や文化、求める人材像を理解し、自分との適合性を慎重に検討しましょう。
全落ちを避けるべく事前準備
就活をするにあたり、誰しもがスムーズに内定をもらいたいと考えるでしょう。
では、全落ちをできるだけ避ける事前準備はどのようなことがあると考えますか。
就職の全落ちを防ぐサポートを受けてみる方法があります。
大学の就職課
大学にある就職課では、大学生が就活を行う際に様々な手厚いサポートを行っています。
履歴書の作成・添削や面接練習やアドバイスといったサポートを受けることができます。
また、就職課では、企業との就職イベントやインターンシップの情報提供や実際にそこで参加できるイベント等を提供してくれます。
就職課の方と相談しながら一緒にイベントやインターンシップの概要を知ることができるメリットがあります。
こちらの就職課は、大学内に設置されているため、学生は気軽に就職について悩みや相談することができます。
就活時期が近づくに連れて就職課を利用する学生が増加するため、あらかじめ予約をするようにしましょう。
早い時期から相談に行っている学生は想像以上に多くいます。
早めに活用してはいかがでしょうか。
就活エージェント
就活エージェントは、就活を支援することに特化したプロが集まっています。
こちらの就活エージェントは、就職を希望している方が希望する企業や職種を絞り込んで、マッチングする企業を提案してくれます。
企業・職種以外の提案以外にも、自己分析や面接対策におけるアドバイスを客観的かつ的確に行ってくれるため、充実してご自身の長所や短所を見つめ直すことができます。
無料で利用できるものがあるため、その中からご自身に適した就活エージェントを選びましょう。
就活エージェントが行っている説明会なども開催されているため、そちらに行って雰囲気を肌で感じてから考えてみるのも良いでしょう。
スカウトサイト
スカウトサイトは、自分が希望する企業や職種を絞り込んで、企業からスカウトを受けることができるサービスのことです。
登録後にプロフィールなどを記載し、それらが企業の求める人材とマッチすると企業からアクションしてくれることが、スカウトサイトのメリットです。
そうなると、0から書類応募するよりも選考突破確立は高くなります。
今まで知らなかった業界からのオファーを受けられる可能性もあるため、視野を広げるきっかけになるでしょう。
気になった方はスカウトサイトを活用してみてはいかがでしょうか。
全落ちを防ぐ手段は上記のようにいくつかあります。
一人だけでは難しい部分もあるため、心強いモノを活用して就活することをおすすめします。
就活全落ちからの挽回方法4選
就活全落ちを経験しても、適切な対策を取ることで挽回は十分に可能です。
ここでは、就活全落ちからの効果的な挽回方法を4つ紹介します。
- 自己分析をやり直す
- 業界研究を深める
- エントリーシートを見直す
- 面接練習を重ねる
それぞれの方法について、詳しく解説していきます。
自己分析をやり直す
自己分析のやり直しは、就活全落ちからの挽回の第一歩です。
深い自己理解は、説得力のある自己PRや明確な志望動機の基礎となります。
全落ちした場合、自己分析が不十分だった可能性が高いため、改めて丁寧に行う必要があるでしょう。
自己分析では、過去の経験を振り返り、自分の価値観や強み、弱みを客観的に分析します。性格診断テストや適性検査を活用したり、友人や家族に自分の印象を聞いたりするのも効果的です。
自己分析を通じて自分の特徴を明確にし、それを就活に活かす方法を考えましょう。
業界研究を深める
業界研究を深めることは、就活全落ちからの挽回に不可欠です。
深い業界理解は、志望動機の説得力を高め、面接での質疑応答力を向上させます。
全落ちした場合、業界研究が不足していた可能性があるため、より詳細な調査が必要です。
業界研究では、業界全体の動向や各企業の特徴、最新のトレンドなどを調べます。
新聞やビジネス誌、企業のウェブサイトなどを活用し、幅広い情報を収集しましょう。
また、OB・OG訪問や企業説明会に積極的に参加し、現場の生の声を聞くことも重要です。
エントリーシートを見直す
エントリーシートの見直しは、就活全落ちからの挽回に効果的な方法です。
全落ちした場合、エントリーシートに改善の余地がある可能性が高いため、徹底的な見直しが必要です。
見直しの際は、自己PRや志望動機が具体的かつ魅力的に書かれているか確認します。
また、文章の論理性や表現の適切さもチェックしましょう。
第三者に添削してもらうことで、客観的な視点からの改善点を見つけることができます。
面接練習を重ねる
面接練習の積み重ねは、就活全落ちからの挽回に大きな効果があります。
面接は、応募者の人柄や能力を直接評価できる重要な機会です。
全落ちした場合、面接でのパフォーマンスに課題があった可能性が高いため、集中的な練習が必要です。
面接練習では、想定質問に対する回答を準備し、実際に声に出して練習します。
友人や家族、就職支援センターのスタッフなどに面接官役をお願いし、模擬面接を行うのも効果的です。
練習を重ねることで、自信を持って面接に臨めるようになります。
さいごに
いかがでしたでしょうか。
これまで、就活における全落ち、全落ちしてしまう特徴、全落ちを避ける事前準備について見てきました。
就活はこれまでの受験とは異なり、規模感が大きくなり、エントリーする人も増えライバルが増えます。
思い描いていた結果と異なることは多々あるでしょう。
そのような際には、現実を受け入れられるかどうかで、その後の行動が大いに変わってきます。
あなたご自身の性格をしっかりと把握したうえで、志望する業界・業種・企業を選定していきましょう。
不安なことや、恐怖心はあることは正直な所だと思います。
少しでもそれらを解消して就活に励めるように、大学の就職課や就活エージェント、スカウトサイトなどを活用してみてはいかがでしょうか。
本記事を参考にしていただけたら幸いです。