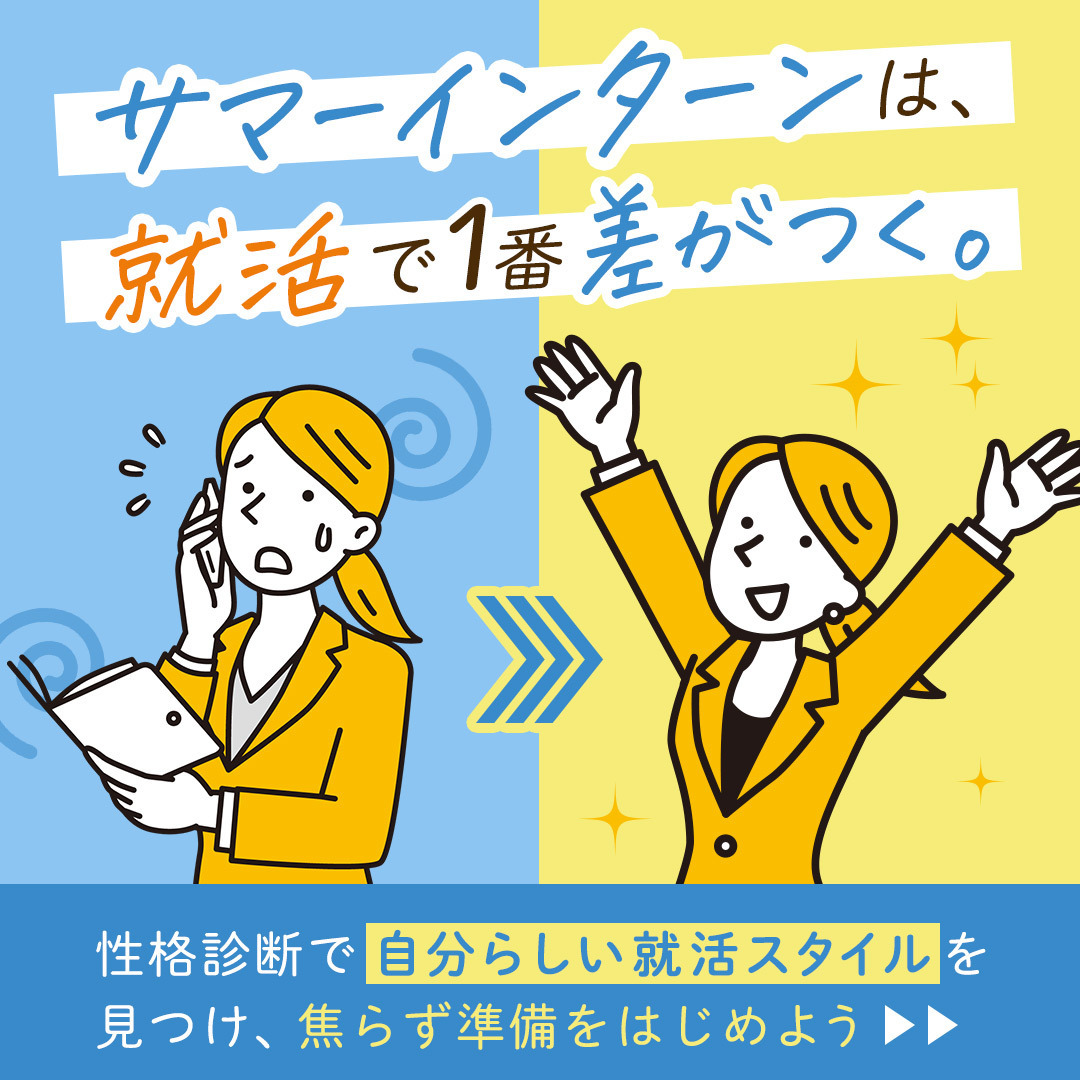大学を辞めると就職に影響する?その後の進路やメリットを解説
2024/9/25更新
はじめに
「大学を辞めたいけれど、その後の進路や就職に悪い影響を与えるか心配」
大学を辞めるか悩んでいる、もしくは大学を辞めた人の中には、このような悩みを抱いている人も多いでしょう。
大学を辞めるか悩んでいる場合は、就職に与える影響とその後の進路を理解した上で、焦らずに決断する姿勢が大切です。
この記事では、大学を辞めるメリットとデメリットについて解説しています。
大学を辞める人のその後の進路や就職に与える影響・コツについても解説しているため、ぜひ最後までご覧ください。
- 大学を辞める場合の就職に与える影響について知りたい
- 大学を辞めるメリットとデメリットを把握したい
- 大学を辞める場合、その後の進路を知りたい
上京を志す地方学生ならジョーカツ!
あなたのキャリアを加速させるチャンス!
無料で利用できる快適な個室シェアハウス、
東京までの交通費サポート付き
首都圏の注目企業への就活ならジョーカツ
首都圏の学生ならスタキャリ!
理想のキャリアを実現へと導く第一歩!
あなたにピッタリのキャリアアドバイザーを選び、
自分にマッチする優良企業をご紹介
首都圏企業のES添削から面接対策まで、就活ならスタキャリ
大学を辞めることが就職に与える影響は3つ

大学を辞めるべきか悩んでいる就活生にとって、就職にどんな影響を与えるか気がかりになっている人も多いでしょう。
大学を辞めると、以下3つの面で就職に影響を与えます。
- 最終学歴が高卒になるため大卒より選択肢が狭まる
- 面接官が抱く印象が悪くなる
- 空白期間がある場合はさらに印象が悪くなる
大学を辞めると企業にマイナスな印象を与えてしまうでしょう。
本当に大学を辞めるべきか、以下の内容を参考に検討してください。
最終学歴が高卒になるため大卒より選択肢が狭まる
大学を辞めると、最終学歴が高卒になります。
大手企業の総合職やメーカーの開発職などは、大卒以上の人材を募集要件にしているケースが多く、高卒では応募できないでしょう。
また、大卒と比べて平均賃金も低く、正規雇用の求人数も減少します。
大学を辞めて最終学歴が高卒になるだけで、就職の選択肢が狭まってしまうことは、マイナスな影響と感じる人も多いのではないでしょうか。
就活で大手企業の総合職やメーカーの開発職などを希望している人は、大学を辞めるのではなく卒業する選択肢がおすすめです。
面接官が抱く印象が悪くなる
大学を辞めると、履歴書には「〇〇大学 自己都合により中途退学」などと大学を中退したことを明記する必要があります。
面接官は、履歴書やエントリーシートの内容を元に採用面接を進めるため、大学中退が明記してあると少なからず印象が悪くなってしまうでしょう。
また、大学を辞めた理由についても面接で聞かれるケースも多いです。
大学を辞める理由は人それぞれですが、ポジティブな印象になるように伝える必要があります。
大学を辞めた理由とその背景、中退したことで得られた学びや今後の目標を明確に伝えましょう。
表現を工夫することで、面接官に大学を中退した事実をポジティブな印象で伝えられるはずです。
空白期間がある場合はさらに印象が悪くなる
大学を辞めるか悩んでいる人の中には、大学を辞めた後次の進路に進むまで何もせずのんびり過ごしたいと考えている人もいるのではないでしょうか。
大学でのストレスや精神疾患をはじめとする持病の悪化が大学を辞める理由であれば、大学を辞めてから一定期間休むことも必要です。
健康状態が回復してから就活を始めても、中退した理由を面接官に明確に伝えられれば、中退理由が就職にマイナスな影響を与えることはないでしょう。
しかし「大学の講義がつまらなかった」など、自分に落ち度があり中退する場合は、空白期間を作らないようにするのがおすすめです。
空白期間を作ってしまうと、面接官は「何もせずダラダラと過ごすような人材なのか」とマイナスな印象を受けるでしょう。
大学を辞めて空白期間を作って就活する場合は、面接の際に、以下の3点をしっかりと面接官に伝えてください。
- 空白期間にしていたこと
- 空白期間中に感じた壁や苦悩
- どのような気持ちや考え方・行動で壁や苦悩を乗り越えたか
簡潔にまとめて伝えることで、中退後の空白期間も自己成長につなげられる人材として、面接官にポジティブな印象を与えられるでしょう。
大学中退でも就職はできる!6つの就活ポイント伝授

大学を辞めると、少なからず就職にマイナスな影響を与えます。
しかし、大学を辞めて中退したからと言って、就職できないわけではありません。
ここから紹介する6つのポイントを活用しながら、自分とマッチする企業を見つけて就活を成功させてください。
- 学歴不問・未経験者歓迎求人に応募する
- 就職エージェントを活用する
- 応募先企業の企業研究は必ず行う
- 大学を中退した理由を正直に伝える
- 就職に活用できる資格を取得する
- 倍率の低い仕事も視野に入れる
1つずつ、詳しく解説します。
学歴不問・未経験者歓迎求人に応募する
大学を辞めると、最終学歴が高卒になり、大卒は名乗れません。
必然的に、大卒を応募条件に設定している企業には応募できなくなります。
大学を辞めて就活をする際は、学歴不問で未経験者歓迎と明記されている求人に積極的に応募してみましょう。
比較的規模が大きい企業でも、職種によっては学歴不問かつ未経験者でも応募ができる求人が出ているケースがあります。
高卒で未経験でも応募できる求人の中から、自分の適性を活かせる企業を見つけて、就活を成功させてくださいね。
就職エージェントを活用する
大学を辞めて就活に臨む際は、就職エージェントを活用しましょう。
就職エージェントとは、就活を全面的にサポートしてくれるサービスです。
適性を活かせる企業を紹介してくれるだけでなく、履歴書やエントリーシートの添削や面接日時の調整などさまざまなサポートをしてくれます。
大学を中退した理由や今後どうしていきたいか、進路の希望もヒアリングした上で、あなたに合った企業を見つけてくれるでしょう。
大学を中退して1人で就活するのが不安、という方におすすめのサービスです。
応募先企業の企業研究は必ず行う
大学中退後、就活で企業に応募する際は、必ず企業研究を実践してください。
大学を中退しても、就活の流れは変わりません。
まずは自己分析で自分の強みや人柄を客観的に理解し、どんな仕事をしていきたいかキャリアプランを立てます。
その上で、自分の適性を活かせそうな企業を絞り出し、それぞれの企業について徹底的に調べましょう。
企業の公式HPはもちろん、新卒・中途採用ページに掲載されている企業の情報を事細かにチェックし、企業への理解度を深めておくのがおすすめです。
企業研究を行うことで、入社後のギャップを最小限に抑えられます。
企業にとっても早期離職は避けたいと考えていますので、お互いのために応募前の企業研究は欠かさず行ってください。
大学を中退した理由を正直に伝える
大学中退後、就活で面接に臨む場合は、大学を中退した理由を正直に伝えましょう。
自分に落ち度があって大学を中退した場合でも、理由を偽ることは避けてください。
面接では嘘が通用して内定をもらっても、後々嘘がバレてしまい、結果として内定が取り消されてしまうケースも考えられるからです。
面接で大学中退理由を問われた際は、中退した理由とその背景・中退したことで得られた学びや今後の目標をしっかり伝えましょう。
大学を中退した理由を正直に伝えることで、面接官にポジティブな印象を抱いてもらえやすくなります。
就職に活用できる資格を取得する
自分が希望する業界や企業を絞った際に、資格があった方が有利だと判断した場合は、資格を取得するのもおすすめです。
IT業界であれば基本情報技術者やITパスポート、事務職や営業職であればMOS(Microsoft office Specialist)などの資格が挙げられます。
どの資格も取得しておくと、企業にスキルとしてアピールできるでしょう。
しかし、入社後に資格取得制度を活用して資格を取得すると、かかった試験費用を会社に負担してもらえるケースもあります。
入社時に高いスキルを求めず、入社後スキルを身につけてほしいという方針の企業も存在するため、まずは就活に注力することをおすすめします。
倍率の低い仕事も視野に入れる
大学を辞めて就活に臨む際は、倍率の低い仕事も視野に入れてみましょう。
倍率の低い仕事とは、他の仕事と比べて人手が不足していたり、人気がなかったりする仕事のことです。
具体的には、建築関係や医療、介護などの福祉サービス業などが挙げられます。
人手不足が深刻な業界の求人では、学歴不問で未経験でも歓迎するような文言が多く記載されているケースが多いです。
自分が志望する業界以外に、倍率の低い仕事も視野に入れながら、就活を進めてみるのがおすすめです。
大学を辞めるメリットはある!5つ紹介

大学を辞めると聞くと、デメリットが多いイメージを受けますが、メリットも存在します。
大学を辞めるメリットとデメリットは、以下のとおりです。
| メリット | デメリット |
|
|
ここでは、大学を辞めるメリット5つについて、詳しく解説していきます。
学費を支払う義務がなくなる
大学を辞めるメリットとして、学費を支払う義務がなくなることが挙げられます。
大学に通うには、決して少ないとは言えない金額の学費を支払い続ける必要があります。
文部科学省が発表した「国公私立大学の授業料等の推移」によると、国公立大学の1年間の学費は約50万円、私立大学の1年間の学費は約90万円です。
大学に通う人の中には、一人暮らしをする人も多く、その場合は学費に加えて生活費が負担となるでしょう。
実際に大学を中退した人の中でも、金銭的な理由で中退せざるを得なかったという人は多く存在します。
年間を通して負担の大きい学費を支払う義務がなくなることは、大学を辞める大きなメリットと言えるでしょう。
大学のストレスから解放される
大学にまつわるストレスから解放されることも、大学を辞めるメリットとして感じる人も多いでしょう。
「大学の授業に興味が沸かない」「学びたい分野を学べない」「勉強についていけない」など、さまざまな理由で学業不振に陥る人も多いです。
また、学校や部活動での生活に馴染めず、人間関係のストレスで精神的な病を抱えてしまう人も、最近では多いようです。
大学のストレスが原因で辞めるか悩んでいる場合は、まずは大学に設置されている相談室や心療内科などを活用して悩み事を相談してみましょう。
発達障害などが原因で集団生活に馴染めない人は、大学の障害学生支援室などを活用することで、サポートを受けられる可能性もあります。
すぐに大学を辞める決断はせず、積極的に支援制度や施設を活用して、悩みを解消していく方法がおすすめです。
自由な時間を活用してやりたいことに集中して取り組める
大学を辞めると、講義や部活動に費やす時間がなくなり、自由な時間を手に入れられます。
自分が本当にやりたいことに集中して取り組める環境を得られることも、大学を辞めるメリットと言えるでしょう。
学業よりも集中して取り組みたいことがある人であれば、大学を辞めることをメリットに感じられるはずです。
しかし、大学に在学しながら、自分の工夫次第でやりたいことに集中して取り組める場合もあります。
すぐに大学を辞める決断はせず、学業と両立できないか、よく考えて慎重に進路を決める姿勢を持ちましょう。
周囲の環境や人間関係を断ち再出発できる
大学を辞めることで、周囲の環境や人間関係を再出発できる点も、大学を辞めるメリットの1つです。
「部活動やサークルでの人間関係に疲れた」「大学に通う意味がわからなくなった」という人にとっては1番のメリットに感じるでしょう。
大学を辞めて異なる大学へ入学し直したり、他の進路を選んだりすることで、新たな気持ちで再出発できる可能性が高いです。
しかし、安易な気持ちで大学を辞めてしまうと、中退したことを後悔する可能性もあります。
後悔しないためにも、すぐに大学を辞める決断はせずに、1度踏みとどまってみましょう。
自分が大学に進学した理由や専攻を選んだ理由について深掘りすることで、大学を辞める以外に今の状況を改善できる解決策が見つかるかもしれません。
すぐに働く場合は同学年より早く社会人経験ができる
大学を辞めてすぐに働く場合は、同学年より早く社会人経験ができることも、大学を辞めるメリットとして挙げられます。
特に、経済的な理由が原因で大学を辞めるか悩んでいる人にとっては、大きなメリットとして感じるのではないでしょうか。
働きに出ることで、スキルを身につけながらお給料ももらえます。
ただし、大学に在学しながらでも、企業のインターンシップやアルバイトで社会人経験は可能です。
また、同学年より早く社会人経験を積めるとは言え、新卒で働き始める同級生と比べて大きな差が出るとは言いにくいでしょう。
何より大学を辞めると高卒になってしまうため、学歴を重視する企業への就職はほぼ不可能となります。
大学を辞めることが本当にメリットになるのかをよく考えた上で、決断することをおすすめします。
大学を辞めるデメリット5つも理解しよう

大学を辞めるメリットを紹介しましたが、やはりデメリットも存在します。
大学を辞めるメリットとデメリットは以下のとおりです。
| メリット | デメリット |
|
|
大学を辞めるデメリットは6つです。
1つずつ詳しく解説していきます。
最終学歴が「高卒」になる
大学を辞めるデメリット1つ目は、最終学歴が高卒になることです。
最終学歴が大卒か高卒かによって、応募できる求人や平均賃金に差が生じます。
大手企業の総合職やメーカーの商品開発職・エンジニア職などは、大卒以上に絞って募集しているケースが多いです。
大学を中退し最終学歴が高卒になるだけで、応募できる求人数が限られてしまうことは、大きなデメリットとして挙げられるでしょう。
また、大卒と比べて平均賃金や正規雇用が少ないことも、就職の際のデメリットとして感じる人も多いはずです。
大手企業やメーカーの開発職などへの就職を希望している場合は、大学を辞める選択肢よりも、大学を卒業する選択肢をおすすめします。
大学での人間関係が継続できなくなる
大学での人間関係が継続できなくなることも、大学を辞めるデメリットの1つです。
大学を中退してしまうと、在学中に仲の良かった友人と、大学での共通の話題や価値観で盛り上がる場面が減少してしまうでしょう。
大学中退後に就職する場合は、大学に通い続けている友人との環境や生活面で違いを覚え、そのまま疎遠になることも考えられます。
ただし、大学を中退しても関係を継続できる人もいるため、大学を辞めると必ず人間関係が継続できなくなる、と思い込むのは避けてください。
経歴にブランク(空白期間)が生じる
大学を辞めると、今後の進路について悩むだけで実際に行動できないブランク(空白期間)が生じる可能性があります。
経歴にブランクが生じると、就活の際に理由を問われたり、今後の人生に焦りや不安を抱えたりとストレスを抱えやすくなるでしょう。
健康状態の悪化により大学を中退した場合は、そもそも「何もできない」ためにブランクが生じるケースもあります。
この場合はブランクが必要だったとプラスにアピールできますが、多くの場合は経歴にブランクがあると面接官にマイナスな印象を与えてしまいます。
ブランクを生じさせないためにも、なるべく大学を辞める前に、その後の進路を明確にしてスムーズに移行できる準備をしておきましょう。
辞め癖がつく可能性がある
大学を辞めることで、辞め癖がつく可能性があることもデメリットです。
辞め癖とは、何か1つでもつらく感じるとすぐに逃げ出してしまい、1つの物事を長く継続できない癖を指します。
辞め癖がついてしまうと「とにかく辞めたい」という思いから、冷静な判断ができないまま何事もすぐに辞めてしまう可能性が高くなります。
大学を辞める理由を明確にせず、ただ「つらいから」という理由で辞めてしまうと、その後就職できたとしても長く継続できない可能性があるのです。
自分の適性を活かせる企業で長期間働くためにも、大学を辞めたいと思う理由や自分のやりたいことを客観的に理解しましょう。
生涯年収に差が出る
大学を辞めると、大卒と比較した際、生涯年収に差が出てしまうこともデメリットとして挙げられます。
大卒と高卒の平均賃金は、以下の通りです。
| 最終学歴 | 平均賃金 |
| 大学院 | 約47万円 |
| 大学 | 約37万円 |
| 高等学校 | 約28万円 |
大卒と高卒で、10万円以上の差が出るのが現状です。
大学を辞めることで、同学年よりも早く社会人として働けますが、結果として大卒の方が給与面で良い待遇を受けられることになります。
正規雇用についても大卒以上の求人が多いため、将来を見据えた判断として、大学を辞める判断が自分に適しているのかよく考えましょう。
大学を辞める前にやってほしい2つのこと

大学を辞めることが就職に与える影響や就活のポイント、メリット・デメリットについて解説しました。
ここでは、大学を辞める前にやってほしい2つのことを解説します。
辞める以外に方法がないかを考える
大学を辞める以外に、方法がないか考えてみましょう。
大学を辞めるデメリットでお伝えしたとおり、大学を辞めると最終学歴は高卒になります。
大卒と比べて就職の選択肢が狭まるだけでなく、生涯年収にも差が開いてしまうでしょう。
起業や資格取得をしたい場合は在学しながらでもできる可能性もあります。
病気や事故による体調不良であれば、休学する選択肢がおすすめです。
経済的な理由で在学が困難な場合は、大学の学生課に相談してみてもいいでしょう。
学生生活に馴染めないのであれば、アルバイトや部活動・外部の団体に所属して友達を作る方法もあります。
大学を辞めるのは最終的な方法として、それまでに大学に在学しながらでも問題を解決できないか考えてみましょう。
信頼できる大人に相談する
大学を辞めるか悩んでいる場合は、信頼できる大人に相談してみましょう。
両親や兄姉、社会人の先輩や友人など、できれば社会経験があって広い視野で客観的にアドバイスしてくれる人がおすすめです。
自分だけの狭い視野で大学を辞める判断はせず、信頼できる大人に必ず相談し、大学を辞める以外の方法がないか考えてみてください。
さいごに
この記事では、大学を辞めると就職にマイナスな影響を与えるのか、就活のポイントについて解説しました。
大学を辞めると最終学歴が高卒になるだけでなく、履歴書に大学中退と明記しなければならず、面接官にマイナスな印象を与えます。
大学を中退して就活に臨む際は、面接時に大学を中退した理由について正直に伝える姿勢が大切です。
大学を中退した理由とその背景、中退から得られた学びと今後の目標を簡潔にまとめて伝えることで、面接官にポジティブな印象を与えられるでしょう。
また大学を中退して就活に臨む場合は、学歴不問かつ未経験でも応募できる仕事に積極的に応募するのがおすすめです。
高卒の場合は、大卒と比べて就職の選択肢が狭まってしまうため、学歴不問や未経験歓迎求人の中から自分とマッチする企業を見つけましょう。
大学を辞めると自由な時間ができるメリットがある反面、「最終学歴が高卒になる」「大卒と比べて生涯年収に差が開く」などのデメリットも存在します。
大学を辞めるか悩んでいる場合は、家族や先輩など身の回りの信頼できる大人に相談し、慎重に検討しましょう。
この記事があなたの役に立つことを願っています。