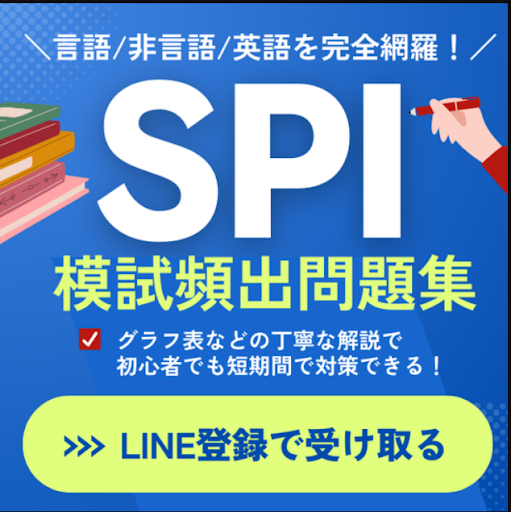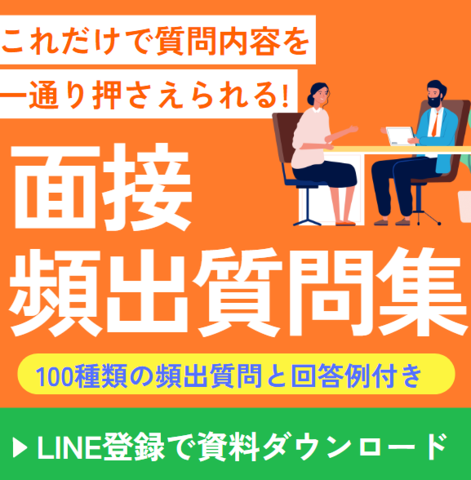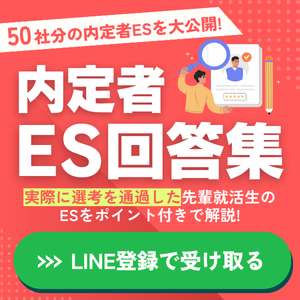【元人事が解説】刺さる自己PR生成4ステップを例文で解説
2023年11月28日更新
はじめに
「そもそも自己PRって何なの?」
「自己PRの作り方を知りたい」
「刺さる自己PRの例文を見てみたい」
など、ESや面接で必ず出てくる自己PRについて気になりますよね。
しかも、面接の場合は、
「まずは自己PRを3分程度で語ってください」
と冒頭で求められますので、緊張している中でシドロモドロだけは避けたいですよね。
そんなあなたに朗報です。
本記事では、
・自己PRを企業が求める理由
・自己PRで意識すべきポイント
・刺さる自己PRを作るための型と例文
・【奥義】自己PR伸縮法
・絶対に避けるべき自己PRのNGパターン
など、あなたが知りたい情報を満載しています。
10分後には自己PRに関するすべての疑問や悩みを払拭できますので、最後まで一気にお読みくださいね。
そもそも自己PRとは
自己PRとは何なんでしょう?
「自分を売り込むためのものでしょう?」
「自分の情報を伝えるためのもの?」
「面接官との関係づくりのため?」
など、色々な意見があると思いますし、どれも正解です。
私の人事経験を通じて出した答えは、
「私はあなた方が求める人材ですよ」と端的にアピールするためのツール
だと捉えています。
もともと、人事にとってESや面接は「企業が求める人材にマッチしているかどうかを見極めるツール」なんです。
つまり、自己PRを皮切りに「求める人物像に適合しているのか?」という確認作業が始まるわけです。
「なるほど、わかりました。それでは自己紹介や長所とはどう違うんですか?」
そうですよね、気になるところですね。
それぞれの違いを「求められる内容」と「企業側の目的」に沿って整理しましたので、下表で確認しておいてくださいね。
| 区 分 | 求められる内容 | 企業側の目的 |
| 自己PR | ・強み ・強みを裏付けるエピソードや具体例 ・学んだことや経験値 ・活躍理由と採用理由 | 求める人物像とのマッチング度を把握 |
| 自己紹介 | ・氏名 ・大学名、学部、学科 ・簡単な志望理由 ・趣味 など | 基本情報の確認 |
| 長 所 | ・生来の資質や性格 ・仕事に対する取り組み姿勢 | 自分を客観的に把握しているかの確認 |
企業が自己PRを求める3つの理由
自己PRを作る前に企業側が学生に自己PRを求める理由を押さえることが何にも増して重要です。
それがわからないと、的外れで場違いな自己PRをしてしまうからです。
私の人事の経験上、自己PRを求める理由は大きく3つに集約できます。
プレゼンテーション能力を測りたい
1つ目の理由として、プレゼンテーション能力がどのくらいのレベルなのかを確認しています。
私の経験上、自己PRさせるとコミュニケーション能力がある程度把握できます。
仕事では理論的に自分の意見を言えることがコアスキルとなるので、自己PRの出来栄えから逆算して、この学生は入社後に活躍できる人材なのかをまずは品定めしています。
質問のネタを収集したい
もう1つの目的としては、自己PRを通じて、もっと具体的に知りたいことや、引っ掛かった疑問などのネタを集めています。
自己PRは面接冒頭に行いますので、やはり学生側も緊張しています。
なので、自己PRで収集したネタを掘り起こして聞くことにより、その場を温めることに役立ちますので、学生の緊張をほぐすためのツールとしても自己PRを活用していますね。
求める人物像と合致しているかを見極めたい
これは自己PRだけでなく、面接のすべての質問に共通していますが、その企業が求める人物像に合致しているかどうかを見極めるための先鞭をつけるために活用しています。
「求める人物像=その会社が採用したい人物像」です。
自己PRで人柄や価値観、能力などがある程度掴めますので、求める人物像とのマッチング度を確認するためのファーストステップとして役立てていますね。
自己PRで意識すべき3つのポイント
「企業側が自己PRさせる理由はわかりました。それでは、自己PRする際に意識すべきポイントとかありますか?」
大きく3つありますので、1つずつ簡単に説明しておきましょう。
「採用理由」と「活躍理由」を意識する
冒頭で、自己PRとは「私はあなた方が求める人材ですよとアピールするためのもの」と定義しましたが、そのためには「採用理由」と「活躍理由」をセットで伝える必要があります。
「採用理由」と「活躍理由」の意味は下記のとおりです。
・採用理由=御社があなたを採用する理由
・活躍理由=入社してから活躍できる理由
ここでは、2つをセットで「ベネフィット」と呼びますが、「相手が得たい結果」だったり、「求める未来像」を語る必要があるわけですね。
求める人物像に寄せる
八重もすると、自己PRでは「自分が、自分が…」と独善的になりがちですが、自分が強みだと思っていることが案外、企業側が求めていない要素だったりします。
先ほどの、「採用理由」や「活躍理由」も「求める人物像」と乖離していれば、いくら熱弁をふるったところで、相手にされなくなるだけです。
そうなると本末転倒なので、必ず「求める人物像」から逆算して、「採用理由」や「活躍理由」をアピールすることが大切だということですね。
その他の内容と一貫性を持たせる
それから、人事は自己PRだけで合否を決定しているわけではありません。
志望理由やガクチカ、逆質問など、面接の中のすべての質問に対する受け答えを総合して判断しているわけです。
なので、すべての受け答えに一貫性がなければいけません。
たとえば、自己PRで「好奇心旺盛です」と言っておきながら、長所で「1つの事柄に集中できることです」と答えた場合、論理矛盾を起こしますよね。
そうなると、面接官は
「嘘をついてる…」
「どっちが本当なんだ?」
といった猜疑心を抱く可能性がありますので、すべての答えに一貫性を持たせる意識を持つことが重要ですね。
刺さる自己PRを生成する4ステップ
「自己PRを作る際に意識すべきことはわかりましたが、実際問題、どのように作ればいいですか?」
武道でもなんでも、「型」がないと効率が悪く、我流で進めていくことになりますので、まずは「型」をマスターする必要があります。
刺さる自己PRを作ろうと思えば、下記の4ステップの型を覚えてください。
| ステップ | 型 | 内 容 |
| ステップ1 | 結 論 | 私の強みは〜です。 |
| ステップ2 | 具体例・ エピソード | 具体的には、〜の場でこの強みを発揮しました。 |
| ステップ3 | 学んだこと・ 習得したスキル | この経験から〜を学びました。(習得しました) |
| ステップ4 | ベネフィット | なので、御社ではこの強みを活かして活躍できるんです。 |
この型を使えば、一端の自己PR文が完成しますが、各ステップで少し解説を加えておきましょう。
【ステップ1】結論
結論のポイントは、「端的に興味深く」です。
自己PRの結論は、漫才でいうところの「つかみ」になりますので、「ぜひ、次を聞いてみたい」と思わせる状態に引き込まなくてはなりません。
つまり、ありふれた言葉や平凡な単語で、気をこっちに向かせる必要があります。
そのために、
・誰も使わないような言葉を意識して使う
・強い単語を使う
といったテクニックを駆使して、興味性を持たせていきます。
たとえば、
「私の強みは、忍耐力です」
よりも、
「私の強みは、風雪を耐え忍ぶ防風林ような耐久力です」
といったほうが何だか興味をそそりますよね。
もし、気の利いた単語が思い浮かばない場合は、「類義語辞典」を利用することをおすすめします。
類義語辞典は、あなたの知らないパワー単語を数多く発見できますので有用ですよ。
【ステップ2】具体例・エピソード
次に、結論を下支えするために、その強みを象徴する具体例やエピソードを繰り出さなければなりません。
この具体例やエピソードがないと、客観性が生まれないので、信憑性が薄れてしまうのです。
ここでのポイントは、具体性を追加することで物語を映像化することです。
そのために、
・5W1H
・数値
・第3者や権威の声
・5感を使った表現
・たとえ話
などを使って、情景をアリアリと映し出してあげて下さい。
【ステップ3】学んだこと、習得したスキル
【ステップ3】はなくても、ストーリーは完結しますが、できればそのエピソードや体験を通じて、「何を学んだのか」、「どんなスキルを習得したのか」を強調することで、面接官の印象に残りやすくなります。
字数や持ち時間に余裕があるなら、挿入しておきたいパーツですね。
【ステップ4】ベネフィット
最後はベネフィットでクロージングしましょう。
「なので、御社で採用したほうがいいですよ」
「なので、御社で活躍できるんです」
という最後のトドメで、「採用理由」や「活躍理由」を示してあげて、面接官の背中を押してあげるステップにあたります。
以上、自己PRの刺さる「型」を4ステップに分けて解説してきました。
とはいえ、例文がないとイメージが湧かないと思いますので、次のチャプターで例文をお示ししますね。
自己PR例
自己PRに使う強みは大きく「自分に関わる強み」、「他人に関わる強み」、「仕事に関する強み」の3つに区分できます。
したがって、各強みに基づいて、それぞれ例文をこしらえていきますね。
自分に関する強み編
「自分に関する強み」は
| 継続力、実行力、集中力、主体性、成長意欲、忍耐力、粘り強さ、積極性、責任感、達成意欲、好奇心、柔軟性、上昇志向、チャレンジ精神、ストレス耐性、情熱 など |
がありますが、「継続力」をモチーフに自己PR文を作成していきますね。
【継続力をアピールする自己PR例文】
| 私は持ち前の継続力で、長期的な目標に向けて、努力を地道に積み上げる強みがあります。【結論】これまで学業やスポーツ、趣味など、さまざまな分野で目標達成に向けて継続的な努力を行ってきましたが、ここではスポーツを例にエピソードを紹介します。 高校時代までひ弱だった私は、大学入学を機に肉体的に強靭な体質を築き上げたいと考え、用具などに比較的費用のかからないランニングを始めることを決意しました。 毎朝5時からランニングを行う目標を立て、雨の日も風の日も継続したことにより、最初は1kmを走るのもやっとでしたが、次第に距離を延ばすことができ、半年後には10kmを走破できるようになっていました。 それからは走るスピードを意識しながら、15km、20kmと着実に距離を拡大し、地域で開催されているフルマラソンにエントリーするまでに至りました。 そのフルマラソン初チャレンジでは単に完走を果たすだけでなく、3時間を切ることに成功しました。【エピソード】 マラソンを通じて継続的な自助努力で高い壁を乗り越えて、その先へ行ける自信を獲得した瞬間でした。【学んだこと】 御社では、どんな難題にも真正面から取り組み、諦めずに努力することで確実に成果へとつなげ、企業成長に貢献したいと考えています。【ベネフィット】 |
他人に関する強み編
次に他人に関する強みから自己PRを作っていきます。
他人に関する強みは下表のとおり、
| 素直さ、真面目さ、協調性、傾聴力、巻き込み力、堅実さ、リーダーシップ、気配り力、 寛容力、わかりやすく伝える力、人を育てる力、約束を守る、親しみやすさ など |
がありますが、この中から「傾聴力」をテーマにして自己PR文を作成してみます。
【傾聴力をアピールする自己PR例文】
| 私は人とのコミュニケーションにおいて「傾聴力」を重視しています。【結論】 高校時代に自分が話したいことだけを話して、相手の話に耳を貸さない習性が災いして、友達の信頼を損ねた経験を機に、「聞き上手に徹すること」を自分に言い聞かせました。 それからさらに、私の傾聴力は大学で所属しているボランティアサークルで磨かれました。 ボランティア活動の一環で高齢者施設を訪れ、お爺ちゃんやお婆ちゃんとお話する機会に恵まれましたが、寂しがり屋で自分の話を聞いて欲しいお年寄りには私の傾聴力が大いに歓迎されました。 たとえば、あるお爺ちゃんに対して、亡くなった奥様との馴れ初めを聞いているうちに、堰を切ったように話し始め、感慨にふけながら話す思い出話を1時間ほど聞いていたことがあります。 話し終えたお爺ちゃんは「こんな年寄りのくだらない話をよく延々と聞いてくれたね。ありがとう。おかげで、その日に戻れた気がして嬉しかったよ」と涙まで流して喜んでくれました。【エピソード】 この経験により、「聞くことで貢献できる」ことの大切さを学びました。【学んだこと】 御社では常に相手の立場に寄り添い、傾聴力を通じて相手との信頼関係を構築し、チームワークを重視する中で、組織力で大きな成果を生み出したいと考えています。【ベネフィット】 |
仕事に関する強み編
最後のパターンとして、「仕事に関する強み」から自己PRを作っていきます。
「仕事に関する強み」は、
| 論理的思考力、企画力、想像力、分析力、正確性、問題発見力、問題解決力、提案力、 着想力、構想力、スピード、計画力、チームビルディング力、調整力、プレゼン力 など |
がありますが、ここでは「問題発見力」と「問題解決力」をセットでアピールする自己PR文を作成します。
【問題発見力と問題解決力をアピールする自己PR例文】
| 私の強みは本質的な問題を発見し、適切に解決できる力です。【結論】 この強みはアルバイト先の学習塾で発揮されました。 私は最下位クラスの中学生のクラスを任されていましたが、受け持った当初は全く生徒の成績が伸びずに悩みあぐねていました。 しかし、ある書籍の中で「人間には学習タイプがあること」を学び、勉強ができないのではなく、生徒に合った教え方になっていなかったことに気付きました。 それまでは、全員一律でポイントだけを説明し、問題を解く形式の授業を行っていましたが、塾長からの許可を得て生徒に合った個別の教え方に切り替え、検証しました。 具体的には、「なぜ」がわからないと学習が前に進まない「なぜタイプ」には理由や根拠を中心に教え、「何」を重視する子には「言葉の定義や成り立ち、背景」を説明しました。 また、「どのように」がわからないと学習できない生徒には方法論をメインで説明していき、「今すぐタイプ」には教える前に問題を解かせて、後から説明するようにしました。 すると、生徒の目が次第に輝きだし、勉強に対する興味が湧いてきたのか、以前よりも前のめりになって学習するようになりました。 結果として、私の受け持った全生徒の5科目の平均点が前年比30ポイントアップした時は嬉しさのあまり生徒と握手を交わしていました。【エピソード】 この経験を通じて得た力を駆使し、見えない本質的な問題をあぶり出して、的確な解決策で改善を講じ、御社の成長に寄与したいと考えています。【獲得したスキル→ベネフィット】 |
【奥義】自己PR伸縮法
「自己PRはせっかく作ったんだけど、企業によって1分だったり、3分だったりして困るんですよね。何かいい対処法はないですか?」
そうですよね、企業によって「持ち時間」や「指定文字数」が異なるので、頭の悩ませどころですよね。
今回特別に自己PR伸縮法を伝授しますので、そんな悩みを一気に解消してください。
一般的に持ち時間と文字数の関係は、下記が目安だと言われています。
・30秒:150~200字程度
・1分:300字程度
・3分:900字程度
先ほどの例文は600字レベル(2分相当)に値しますので、今回は先ほどの「塾講師の例文」を使って、1分と3分バージョンにチャレンジしてみますね。
まずは1分バージョン(300字程度)を作成してみます。
【問題発見力と問題解決力をアピールする自己PR例文(1分バージョン)】
| 私の強みは本質的な問題を発見し、適切に解決できる力です。 具体的には、アルバイト先の塾の講師業で、生徒の成績が伸び悩んでいたため、塾長と相談しながら、一律的な教え方から各生徒の学習タイプに沿った教育手法に思い切って変更しました。 たとえば、「なぜタイプ」の生徒には理由を、「何タイプ」には成り立ちや背景を説明することにより、頓挫していた学習がスムーズに流れるようになりました。 結果として、生徒は学習に対して前向きになり、全生徒平均で5科目30ポイントアップを実現できました。 この経験により獲得した「潜在的で本質的な問題を炙り出し、的確な解決策で改善する力」を駆使し、御社の成長に寄与したいと考えています。(300字) |
いかがでしょうか?
確かに文字数は半分に減っていますが、600字の内容と同じニュアンスが伝わってくると思います。
ポイントは、無駄な肉(なくても問題ない文字)をそぎ落とし、骨格(エッセンス)だけを残すことです。
したがって、
「これ、必要ないかな?」
「これがなくても、文章として通じるな」
など、出し入れを行うことで目標文字数に近づくはずです。
次に、同じ内容で、3分バージョン(900字)に挑戦してみます。
【問題発見力と問題解決力をアピールする自己PR例文(3分バージョン)】
| 私の強みは、現象面から本質的な問題を発見し、適切に解決できる力です。 この強みは大学2年から始めたアルバイト先の学習塾で発揮されました。 私が最初に受け持った中学生のクラスは成績が最下位のクラスでしたが、いくら頑張って教えても、自分が思い描いたように生徒の成績が伸びずに悩みあぐねていました。 どうにか打開できないかと、同僚に相談したり、塾長にアドバイスをもらったりして、授業に取り入れてみたものの、残念ながら一向に生徒達の成績は伸びませんでした。 そんな現状が進展せずに悶々としていたある日、偶然に図書館で見かけたオックスフォード大学の学術研究論文の中で「人間には学習タイプがある」ことを知り、天と地がひっくり返るほどの衝撃を受けました。 それは生徒に学習能力がないといった理由ではなく、私自身がその生徒に合った教え方を行使できていなかったことを痛感させられた一瞬でした。 それからは塾長と教え方について何度も協議しながら最終的には同意を得たうえで、全員一律でポイントだけを教えて問題を解かせる形式の授業から、生徒の学習タイプに沿った個別の教え方に切り替え、1年間検証することにしました。 具体的には、「なぜ」がわからないと学習が前に進まない「なぜタイプ」には理由や根拠を中心に教え、「何」がわからないと学習がストップしてしまう「何タイプ」には言葉の定義や成り立ち、背景を前面に押し出して説明しました。 また、「どのように」がわからないと学習できない「どのようにタイプ」には方法論や手順をメインに説明していき、「今すぐタイプ」には教える前に問題を解かせて実感させた後から説明を行うようにしました。 すると、次第に生徒の目が輝き出し、勉強に対する興味が湧いてきたのか、以前よりも前のめりで楽しそうに学習する姿が垣間見られるようになりました。 結果として、新しい教育手法を導入して1年後には、私の受け持った全生徒の5科目の平均点が前年対比30ポイントアップという快挙を成し遂げました。 この経験で獲得した力を駆使し、見えない本質的な問題をあぶり出して、的確な解決策で問題を改善につなげ、御社の成長に寄与したいと考えています。(900字) |
いかがでしょうか?
ストーリー自体はそんなに変わりありませんが、文字数は1分の自己PRの3倍になっていますね。
文字数を増やすコツは、「具体性を追加すること」です。
刺さる自己PRの型で説明した「ステップ2」のテクニックを参考にして、具体性を増してみてください。
自己PRのNG例
最後に自己PRのNG例を見ておくことで、反面教師として効用があると思いますので、5パターン紹介しておきます。
①企業が求める人物像と乖離している
いくら理路整然と自己PRを語っても、「相手が求めていないもの」であれば、そっぽを向かれます。
相手が求めていないものを執拗に熱く語られても、押し売りと同じで気持ちが離れるだけです。
したがって、企業が求める人物像にフォーカスして自己PRするのは定石ですね。
➁エピソードに具体性がない
結論を下支えするエピソードに具体性がないと説得力を持ちませんね。
5W1Hを意識して、できるだけ映像で相手の脳裏にビジュアル化できるように工夫しましょう。
➂強みを1つに絞り切れていない
アレもコレもと欲張って、強みを複数盛り込むのは避けましょう。
この行為は、「虻蜂取らず」になって1つ1つのエピソードが薄まり、返ってインパクトがなくなります。
面接官も「いったい、どこをアピールしたいんだろう?」と頭が混乱するだけなので、1つに絞って具体性を追加しながらアピールしましょう。
➃ありふれた強みになっている
面接官は1日に何人、何十人という学生を相手に面接を行っています。
その中で、誰もが使いそうな強みだと、さして印象に残りません。
候補者の中から選んでもらうのが目標ですから、他の学生が使わない差別化された強みを強調するようにしましょう。
➄主観的な成果になっている
「私自身はたぶん成功したと自負しています」と言われても、根拠がないので信憑性に欠けますよね。
それが数字で示せていたり、第3者や権威の声など客観的な証拠があると、真実味を帯びますね。
なので、客観的な成果を示せるように心掛けましょう。
おわりに
以上、本記事では自己PRを企業側が求める理由から、刺さる自己PRの型を使った例文や自己PRで意識すべきポイントまで、元人事目線で解説してきました。
本文では触れませんでしたが、自己PRは面接の冒頭で第1印象を決定づける重要なパーツです。
その自己PRでヘマすると、その印象に引きずられて、先入観を持ったまま面接官が評価するようになります。
そんな失策だけは避けたいので、ぜひ本記事で解説したテクニックに倣って、存分にアピールしてほしいと思っています。
本記事があなたの自己PRに資すれば、幸いです。
今回も最後までお読みいただき、ありがとうございました。