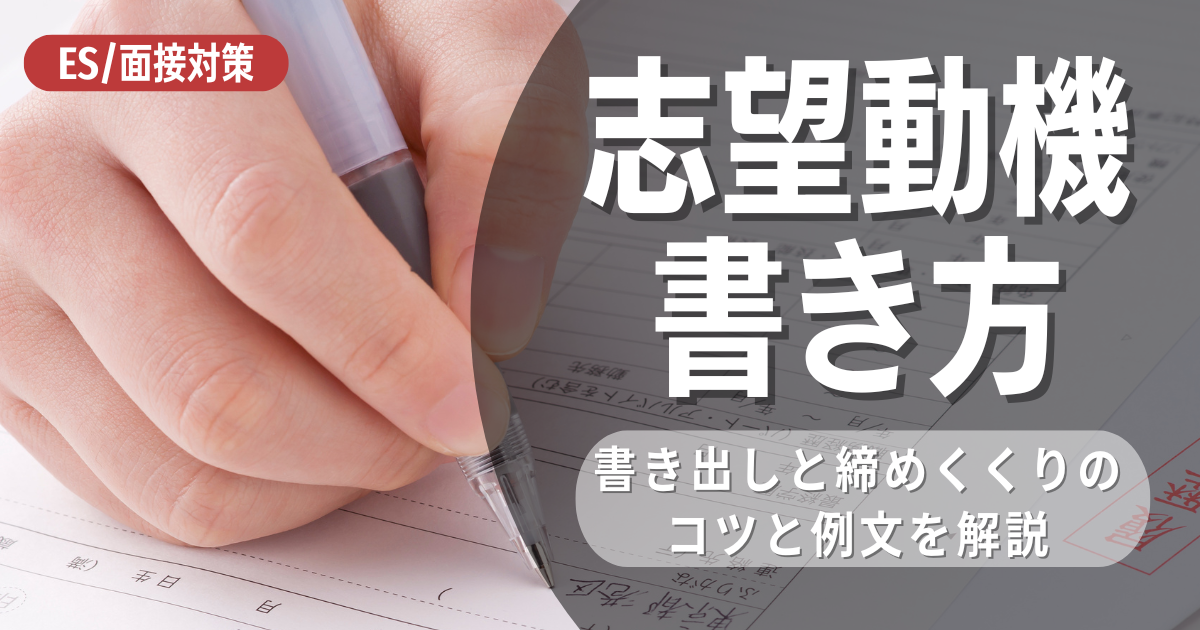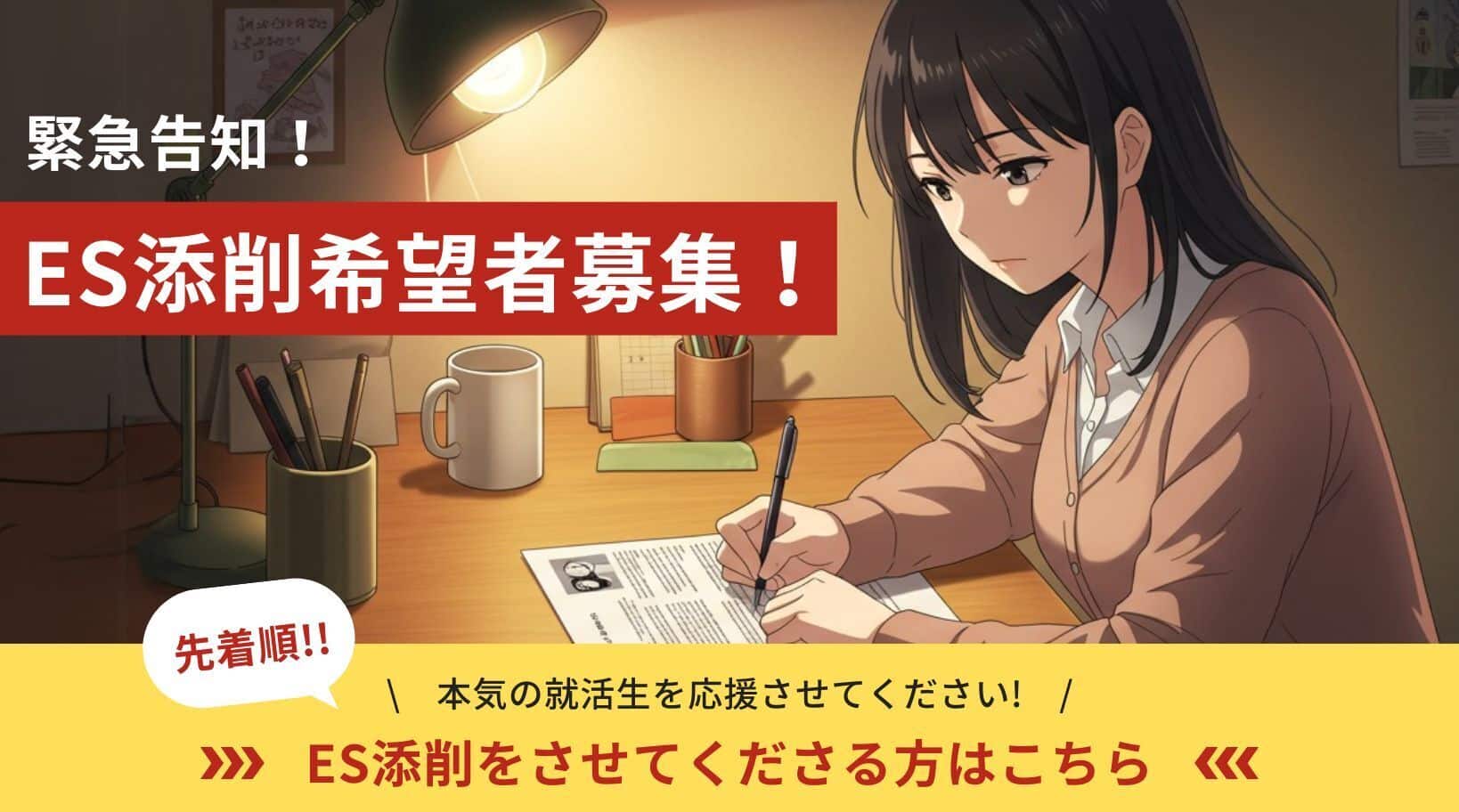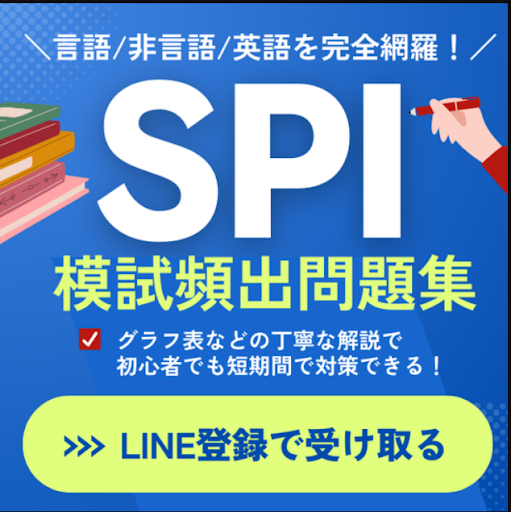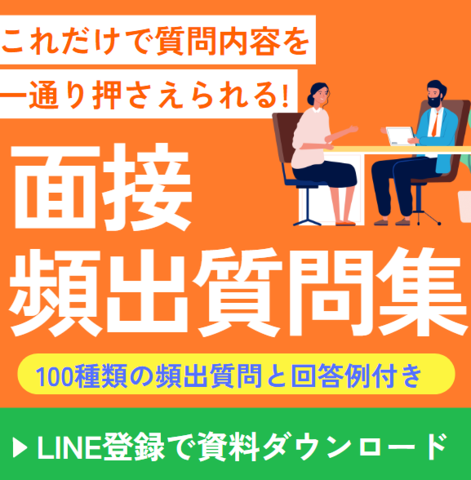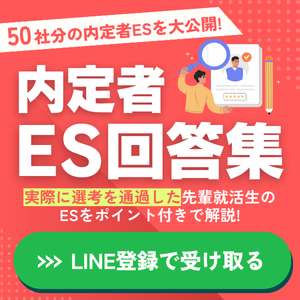志望理由書の書き方は簡単!誰でも上手く書けるようになる方法
2025/2/5更新
はじめに
選考が始まると、エントリーシートと一緒に「志望理由書」の提出を求められることがありますよね。
「志望理由書って、何を書けばいいの?」
「そもそも書き方がわからない…」
エントリーシート対策の情報はたくさんあるのに、志望理由書となると、なかなか見つからない…そんな悩みをお持ちの方もいるかもしれません。
志望理由書とは、その名の通り、あなたが企業を選んだ理由をまとめた書類です。
書き方の基本ポイントさえおさえれば誰でも簡単に書けるようになります。
そこでこの記事では、志望理由書の書き方の基本や企業が求めていること、書き方のポイントなどをわかりやすくご紹介します。
この記事は以下のようなかたにむけて書いています。
- 志望理由書の書き方に悩んでいる
- 志望理由書を書く機会が初めてで、何から始めればいいかわからない
- 複数の企業に応募する中で、志望理由書を使い回していないか不安
- 企業ごとに合わせた志望理由書を書きたい
以下の記事でも「志望理由」について解説しています。あわせてお読みください。
志望理由書の書き方ルール
ではさっそく、志望理由書の作成に入っていきましょう。
書き方のポイントを、4つのステップに分けてご紹介します。
- 結論を最初に伝える
- 結論に至った理由を伝える
- 理由に紐づくエピソードを伝える
- 入社後のビジョンを伝える
それぞれのステップを詳しく解説します。
①結論を最初に伝える
志望理由書を書く上で最も大切なのは、結論から述べることです。
最初に結論を述べずに理由から入ると、「何を伝えたいのか」が明確になりません。
とくに、緊張する面接のような場面だと話しが脱線しやすくなってしまいます。
小説などとは違い、できるだけ簡潔に思いを伝える面接の場では「結論ファースト」がルールです。
ただし、志望理由書の場合、「貴社を志望します」だけでは結論としては不十分です。
「〇〇の理由から貴社を志望します」というように、必ず具体的な理由を添えるようにしましょう。
長々と説明するのではなく、ワンメッセージで簡潔に伝えることがポイントです。
②結論に至った理由を伝える
次に、なぜその結論に至ったのか、その背景を説明していきます。
ここで役立つのが、企業研究の成果です。
「XXXXを△△できるという理由から、私は貴社を志望し、入社後は〇〇で活躍したいと考えています」というように、こちらも一文を目安に理由を伝えましょう。
もし一文にまとめるのが難しいと感じる場合は、まだ企業分析や自己分析が十分でないのかもしれません。
志望理由が明確になるほど、一文で表現しやすくなります。
一文で表現できない場合は、自己分析や企業分析に立ち返って、再度検討してみることをおすすめします。
③理由に紐づくエピソードを伝える
①②は簡潔にまとめることが重要ですが、③では具体的なエピソードを詳しく説明することが大切です。
なぜ②のような考えに至ったのか、自身の経験を交えながら伝えていきましょう。
エピソードは、過去の経験はもちろん、企業説明会やOB・OG訪問での気づきでも構いません。
志望理由はガクチカとは異なり、「企業を志望する理由」を説明するものです。
そのため、最近の出来事が志望理由につながっていても全く問題ありません。
「入社したい」と思ったきっかけが明確に伝わるエピソードを選びましょう。
④入社後のビジョンを伝える
最後に、入社後にどのように活躍し、貢献していくのかを具体的に示しましょう。
志望理由書では、入社後のビジョンを伝えることは非常に重要です。
「入社したい」という気持ちだけでなく、入社することで企業にもたらされるメリットを明確にしましょう。
新卒採用は「ポテンシャル採用」であるため、即戦力としての活躍は求められていません。
時間をかけて成長していくことを前提に、どのような形で企業に貢献できるのか、その可能性を具体的に示すようにしましょう。
志望理由書から企業が知りたいこと
企業は、志望理由書を通して、単なる入社希望以上のことを知りたいと考えています。
具体的には、以下の5つのポイントがあります。
- 入社意欲・熱意
- 入社後の目標
- 企業に対する理解
- あなたの強み・能力
- 熱意と企業への貢献意欲
それぞれの内容を詳しく解説していきます。
①入社意欲・熱意
企業はまず、あなたがどれだけその会社に入社したいのかを知りたいと思っています。
熱意あふれる志望理由書は、入社後のモチベーションの高さ、ひいては活躍の可能性を示すからです。
具体的なエピソードや経験を交えながら、なぜその企業でなければならないのか、入社後にどんな貢献をしたいのかを熱意を持って伝えましょう。
あなたの言葉は、企業への強い興味と入社への熱意を示す重要な要素となります。
②入社後の目標
入社がゴールになってしまってはいけません。
企業は、あなたが将来どのような目標を持ち、どのように活躍したいと考えているのかを知りたいのです。
現時点で詳細な計画を立てることは難しいかもしれません。
しかし、入社後にどんな分野で貢献したいのか、将来のビジョンを具体的に示すことが大切です。
それは、企業が求める「主体性」と「成長意欲」を示す重要な要素となるでしょう。
③企業に対する理解
なぜその企業を選んだのかを伝えるには、企業研究が欠かせません。
企業を選んだ理由は、あなたの熱意の根拠となるからです。
企業の事業内容、強み、将来性などを理解し、なぜ他の企業ではなくその企業なのかを明確にしましょう。
具体的な事業内容への共感、企業の強みに対する憧れ、将来性への期待など、あなたの心に響いた点を具体的に示すことが重要です。
志望理由書で企業への深い理解を示すことは、あなたの熱意を伝える上で非常に効果的です。
④あなたの強み・能力
企業は、あなたを採用することでどんなメリットがあるのかを知りたいと考えています。
そのためには、自己分析を通して自分の強みや能力を明確に把握し、それを具体的なエピソードや実績とともにアピールすることが重要です。
コミュニケーション能力が高い」とアピールする場合、具体的なエピソードを交えて説明することで、説得力が増します。
たとえば学生時代にアルバイトリーダーとして活躍した例などを挙げ、具体的なエピソードと成果を結びつけてみましょう。
そうすることで、あなたの強みが企業にとって価値のあるものであることを伝えられます。
⑤熱意と企業への貢献意欲
企業は、単に知識やスキルを持っているだけでなく、入社後も積極的に学び、成長し続けようとする意欲を持った人材を求めています。
つまり、あなたの熱意と、企業への貢献意欲を具体的に示すことが重要なのです。
あなたがこれまでどのように努力してスキルを習得してきたかもポイントになります。
あるいは、入社後にどのようなスキルを身につけ、どのように会社に貢献したいと考えているのかなどを具体的に述べましょう。
そうすることで、熱意と貢献意欲を効果的に伝えられます。
また、企業の理念やビジョンに共感し、その実現に向けて積極的に取り組みたいという姿勢を示すことも重要です。
志望理由書の書き方の注意点

志望理由書は、あなたの熱意と能力をアピールする絶好のチャンスです。
しかし、書き方によっては、せっかくのチャンスを逃してしまうかもしれません。
ここでは、志望理由書作成における3つの重要ポイントをご紹介します。
- 指定された文字数の9割程度で記入する
- 書き直しがないようにする
- 言葉遣いに注意する
以下で詳しく解説していきます。
①指定された文字数の9割程度で記入する
志望理由書は、あなたの情熱と能力を企業に伝える貴重な書類です。
だからこそ、文字数は単なる「目安」ではなく、あなたの「本気度」を示すバロメーターとなります。
指定文字数を満たすことはもちろん大切ですが、8割未満の記述では「熱意が足りない」「企業研究が不十分」といったマイナスの印象を与えかねません。
逆に、文字数オーバーも要点がぼやけ、読み手の負担を増やしてしまいます。
では、最適な文字数はいくつなのでしょうか。
経験豊富な採用担当者によると、指定文字数の「9割」がベストです。
9割を目安に、あなたの熱意と能力を最大限に伝えましょう。
それが、内定獲得への第一歩となるはずです。
②書き直しがないようにする
注意点の2つ目は、書き直しを避けることです。
とくに手書きの場合は、書き直しや修正液の使用は避け、一発勝負のつもりで臨みましょう。
書き直しが多いと、書類全体が雑然とした印象になり、あなたの丁寧さや誠実さを疑わせてしまいます。
企業指定の用紙が入手困難な場合は、事前に下書きを作成し、誤字脱字やレイアウトをしっかりと確認しておくことがポイントです。
パソコンなどを使って下書きを作成して、その後清書をするという方法も良いかもしれません。
落ち着いて丁寧に書き進め、読みやすい志望理由書を作成しましょう。
③言葉遣いに注意する
志望理由書は面接と違って、書面の文章で自分の熱意を表現します。
だからこそ、正しい日本語で敬意を示すことが大切です。
普段の会話とは異なり、書面では「御社」ではなく「貴社」など、より丁寧な表現を用いるよう注意しましょう。
また、尊敬語や謙譲語の使い分けも重要です。
慣れない言葉遣いに不安を感じるかもしれませんが、事前に辞書やマナー本などで確認し、自信を持って書き進めましょう。
正しい日本語は、あなたの誠実さや学習意欲をアピールする強力な武器となります。
志望理由を考えるために必要なこと
志望理由書は、あなたの熱意と企業への理解度をアピールする絶好のチャンスです。
しかし、単に「この企業で働きたい」と書くだけでは、採用担当者の心を動かすことは難しいでしょう。
そこで、今回は志望理由を考える上で特に重要な3つの要素を掘り下げてご紹介します。
①自己分析を行う
志望理由を考える第一歩は、自分自身を深く見つめる「自己分析」です。
企業研究に没頭する前に、まずは自分自身の強みや弱み、興味や価値観を明確にしましょう。
自己分析というと、「自分のことは自分が一番よく知っている」と思いがちですが、実はそうではありません。
客観的な視点で自分を見つめ直すことで、新たな才能や魅力を発見できる可能性があります。
自己分析は、単なる自己理解にとどまりません。
企業との共通点を見つけ、あなたの強みを活かせるフィールドを見つけるための重要なプロセスです。
また、面接で効果的な自己PRを行うためのエピソード選びにも役立ちます。
だからこそ、自己分析は徹底的に行いましょう。
②企業研究を行う
自己分析で自身の強みや価値観を明確にした後は、いよいよ企業研究の出番です。
企業研究は、あなたの夢を実現するための舞台選びとも言えます。
まずは、企業のホームページを隅々までチェックしましょう。
事業内容、企業理念、社員インタビューなど、様々な情報に触れることで、企業の雰囲気や文化を感じ取れるはずです。
さらに、上場企業であれば「統合報告書」などの財務情報も確認しましょう。
企業の経営戦略や財務状況を理解することで、将来性や安定性を見極めることにもつながります。
業界全体の動向や競合企業との比較も忘れずに行ってください。
業界内での立ち位置や競争環境を把握することで、面接での質問にも自信を持って答えることができます。
③実際に働いている人に声を聞く
自己分析と企業研究で得た知識を、さらに深めるためには、実際に働く社員の声を聞くことが有効です。
ホームページや資料からは得られないリアルな情報が役立ちます。
このようなリアルな声は、志望理由をより具体的に、より説得力のあるものへと昇華させてくれるでしょう。
OB・OG訪問制度などを活用し、積極的に社員との接点を持つことも大切です。
企業によっては、人事担当者が社員との面談をセッティングしてくれる場合もあります。
ためらわずに問い合わせてみましょう。
企業の個性に合わせた志望理由書の書き方
ここまでで紹介した、ルールや注意点を理解したところで、実際に企業に合わせた志望理由書の書き方を見ていきましょう。
企業研修の成果や自己分析の深さを示す場でもあります。
ここでは、業界や企業規模別に具体的な対策をご紹介しますので、参考にしてください。
ベンチャー企業
ベンチャー企業は、変化の激しい環境でスピーディーに成長していくことが求められます。
そのため、新しいことに挑戦したい、成長したいという意欲を強くアピールしましょう。
また、自分のスキルや経験を活かして、企業の成長にどのように貢献できるかを具体的に示すことも重要です。
キーワードは「成長」と「貢献」をポイントにアピールするとよいでしょう。
そのためには、過去の経験や実績、または企業の事業やビジョンに共感した具体的なエピソードを交えながら、入社への熱意を伝えます。
入社後にどのようなキャリアを築きたいか、どのような目標を達成したいかを明確に示すことで、企業への貢献意欲をアピールできるはずです。
多くのベンチャー企業は、将来のビジョンを共有できる人材を求めています。
大手企業
大手企業は、企業理念やビジョンを重視する傾向があります。
企業研究を通じて、企業の理念やビジョンに共感した点、または自身の価値観と共通する点を具体的に述べましょう。
入社後にどのようなキャリアを築きたいか、どのような目標を達成したいかを具体的に示すことで、企業への貢献意欲をアピールできます。
大手企業を志望する理由として、安定した環境で働きたい、社会に貢献したいといった軸がある場合は、その点を明確に伝えましょう。
ただし、企業の事業内容やビジョンとの関連性を意識することが重要です。
大手企業は、長期的な視点でキャリアを考えられる人材を求めています。
外資系企業
外資系企業は、グローバルな視点や多様な文化への理解を持つ人材を求めています。
海外経験や語学力、異文化コミュニケーション能力などをアピールしましょう。
一般的に、外資系企業は、主体性を持って積極的に行動できる人材を求めていることが多いです。
過去の経験や実績を通じて、自身の主体性や積極性をアピールしましょう。
たとえば、英語をはじめとする語学力は、外資系企業で働く上で必須のスキルです。
TOEICのスコアや留学経験など、具体的な実績をアピールするのもよいでしょう。
外資系企業は、独自の企業文化を持つ場合があります。
その場合は、企業研究を通じて、企業文化への理解を示し、適応能力をアピールしましょう。
志望理由の書き方に関するよくある質問
志望理由書の作成で行き詰まった時、誰しも疑問や不安を抱えるものです。
Q.志望理由書の使いまわしはOK?
A.就活を効率化したい一心で、「オープンESのように志望理由書も同じ内容を使いまわしできないだろうか?」と考えた経験がある方もいるかもしれません。
しかし、結論から申し上げると、志望理由書の使いまわしは避けるべきです。
一部だけ企業に合わせて変更するのも、できれば避けましょう。
志望理由は、エントリーシートに記載する自己PRのエピソードとは異なり、企業ごとに異なるものであるべきです。
もし異なる理由がないのであれば、企業分析が不十分である可能性があります。
使いまわした志望理由は、少しでも整合性が取れていないと企業に見抜かれてしまうリスクが高いです。
手間はかかりますが、企業への熱意を伝えるためには欠かせないプロセスと言えるでしょう。
Q.志望理由書のフォーマットはないと言われたのですが…
A.「志望理由書のフォーマットは特にない」と言われた場合、自分でフォーマットから作成しなければなりません。
しかし、具体的なイメージが湧かないまま作成するのは、ハードルが高いと感じる方もいるでしょう。
最も手軽にフォーマットを見つける方法は、Web上で「志望理由書 フォーマット」などと検索してみることです。
中途採用向けのフォーマットが多く見つかるかもしれませんが、就活生が利用しても問題ありません。
また、Web上のフォーマットを利用したからといって、企業の評価が下がることもありませんのでご安心ください。
Web上のフォーマットを利用しない場合は、Wordなどで作成することも可能です。
レポートを作成するような形式で記入しても問題ありません。
大切なのは、決まった形式にとらわれず、相手が読みやすいように分かりやすく志望理由を伝えることです。
さいごに
この記事では、志望理由書の基礎知識から書き方のポイントを詳しく解説しました。
就活中はなかなか書く機会のない志望理由書。
いざ書こうとすると、戸惑ってしまう方も多いかもしれません。
しかし、書き方のルールを理解すれば、意外と自由度が高いことに気づかれたのではないでしょうか。
ポイントを押さえれば、恐れることはありません。
志望理由書は、企業への入社意欲を伝える非常に重要なツールです。
面接でも志望理由は伝えられますが、志望理由書は、より深く熱意を伝える貴重な機会となります。
ぜひ、志望理由書を書く機会があれば、前向きに挑戦してみてください。
あなたの熱意が伝わる、魅力的な志望理由書を作成し、選考を勝ち抜きましょう。