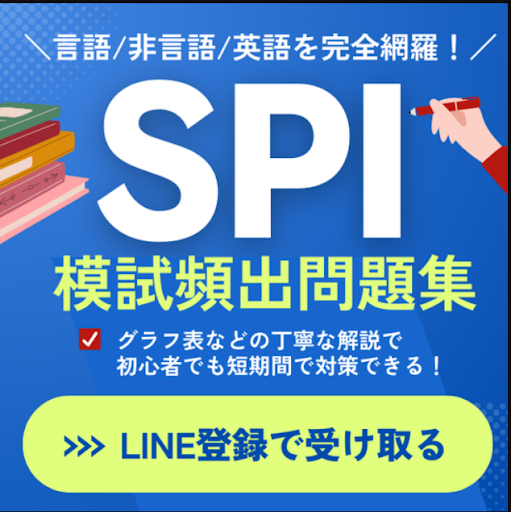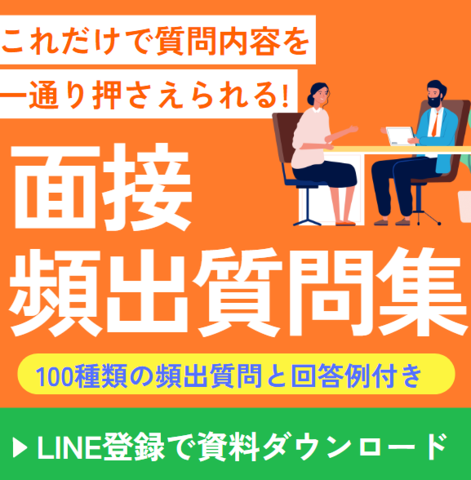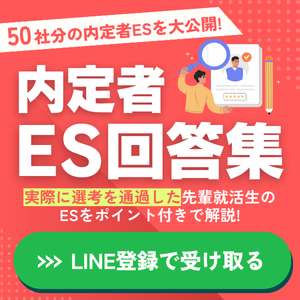会社説明会の質問例文集!ポイントや注意点を徹底解説
2024/9/25更新
はじめに
就活をしている学生にとって、まず第一関門といえるのが「会社説明会」です。
会社説明会は、直接企業の方と会うことができ、社風や社員の雰囲気を肌で感じられます。
そんな会社説明会の中で、必ず設けられている時間が「質問」の時間です。
この質問の時間をいかに有効に使うかが、就活で成功をつかむ鍵だといえます。
とはいえ、「一体どのような質問をすればよいのか」「この質問は失礼にあたるのではないか」と堂々巡りで、質問ができない就活生もいることでしょう。
そこで、本記事では会社説明会の質問例文を集めました。
あわせてポイントや注意点も解説していくので、ぜひ参考にしてください。
この記事は以下のような方に向けて書いています。
- 会社説明会に参加する予定の就活生
- 会社説明会でどういった質問をするべきか思い浮かばない
- 会社説明会での注意点を知りたい
- 会社説明会を有意義な時間にしたい
これを読めば、待ち受けている会社説明会に安心して参加できるはずですよ。
上京を志す地方学生ならジョーカツ!
あなたのキャリアを加速させるチャンス!
無料で利用できる快適な個室シェアハウス、
東京までの交通費サポート付き
首都圏の注目企業への就活ならジョーカツ
首都圏の学生ならスタキャリ!
理想のキャリアを実現へと導く第一歩!
あなたにピッタリのキャリアアドバイザーを選び、
自分にマッチする優良企業をご紹介
首都圏企業のES添削から面接対策まで、就活ならスタキャリ
会社説明会で質問するメリット

まず、会社説明会で質問をすることで、就活に対してどういったメリットがあるのかをみていきましょう。
具体的には以下のようなメリットがあります。
- 自分のことを印象付けられる
- 会社に関する情報収集ができる
- ライバルを知るきっかけになる
それぞれの内容を詳しくみていきましょう。
自分のことを印象付けられる
会社説明会で質問をすることで、企業側に自分のことを印象付けられます。
多くのライバルがいる就活では、いかに自分を印象付けるかが鍵です。
積極的に質問をすることで、あなたの熱意をアピールできます。
とくに「何か質問はありますか」と言われた際、周りの様子をうかがわずに挙手ができたら、より印象をつけられるはずです。
「自社に入社したいという意欲がある」と感じてもらえることは、就活において大きなメリットとなります。
ぜひ、積極的に挙手をして質問をするようにしてください。
会社に関する情報収集ができる
企業のホームページや採用情報だけでは、知り得ない情報まで収集できることも会社説明会で質問することのメリットです。
もちろん口コミサイトなどでも得られる情報がありますが、リアルタイムで働いている社員の声を聞くことができるのが、会社説明会の良さだといえます。
会社説明会における質問内容は自由です。
疑問に感じることがあれば、失礼にあたらないような範囲でなんでも質問してみましょう。
ライバルを知るきっかけになる
ほかの就活生の質問内容を聞くことで、どのような考えをもったライバルがいるのか知るきっかけになります。
内定獲得前は、仲間といえどライバルです。
同じ企業を目指すライバルたちが、どういった質問をするのかをよく聞いておくようにしましょう。
もしかしたら、自分では思いつかなかった方向性から、質問を投げかける就活生がいるかもしれません。
良いところは自分に取り入れ、次の会社説明会で活かすことも大切です。
会社説明会の質疑応答の時間は、就活の秘訣が詰まった宝箱のようなものです。
時間を無駄にすることなく、有意義に過ごすようにしてください。
会社説明会で使える質問例文集
では、実際に質問するとなると、どのような質問が良いのでしょうか。
- 選考に関する質問
- 入社後のキャリアパスに関する質問
- 社風に関する質問
この3つに大きく分けて、例文を紹介していきます。
選考に関する質問
選考フローは、採用サイトや会社説明会の中で説明されることがほとんどです。
そのため、事前に「選考フローについて質問しよう」と考えていても、質疑応答の時間にはすでに疑問が解決している場合が多いのではないでしょうか。
一度説明されたことを何度も聞くと「話を聞いていない就活生だ」と思われかねません。
そのため、選考に関して質問する場合は、さらに深い部分を聞く必要があります。
例文
- 選考プロセスにおいて、特に重視されるポイントはどこでしょうか?
- 過去の選考で、特に評価された学生の共通点は何でしたか?
- 選考期間中に、社員の方と交流する機会はありますか?
- 内定後のフォロー体制や、入社までの準備について教えてください。
- 選考の結果は、どのくらいの期間で通知されますか? また、選考結果に関するフィードバックはいただけますか?
採用サイトでは、求める人材像など抽象的な部分しか記載されていないケースがほとんどです。
せっかくの会社見学なので、さらに踏み込んだ部分まで質問しても失礼にはあたりません。
具体的な情報を聞き出すことで、面接で活かすことができ有利に就活を進められるでしょう。
入社後のキャリアパスに関する質問
入社後のキャリアパスについては、採用情報で明記されていないことがほとんどです。
その企業で長く働くのであれば、知っておきたいポイントのひとつでもあります。
キャリアパスが用意されている会社、自身でキャリアパスを描く必要があるがそのためのサポートが充実している会社とさまざまです。
資格取得支援制度などが充実している企業なら、夢や目標に向かって企業と一緒に前進していけます。
採用に関する質問だけでなく、その後の働き方について質問することでより熱意をアピールすることになり、好印象を与えられるはずです。
質問例
- 貴社では、新入社員のキャリアパスはどのように考えられていますか?
- 入社後、どのようなスキルや経験を積むことで、キャリアアップを目指せますか?
- 社内での異動や、職種転換の機会はありますか?
- 社員のスキルアップを支援する制度や研修はありますか?
- 過去に、新入社員からキャリアアップした社員の事例を教えていただけますか?
社風に関する質問
会社説明会に行くことで、社風を肌で感じられます。
会社説明会でマイナスな返答をする担当者はいませんが、自分に合った社風なのかを再度確認しミスマッチを防ぐためにも、質疑応答で聞いておくことをおすすめします。
企業の方に直接社風を聞くことで、より具体的なイメージをつかめるはずです。
「思っていた雰囲気と違った」と入社後のギャップを感じないためにも、会社見学の段階でしっかり見極めておくとよいでしょう。
例文
- 貴社ならではのユニークな社風や文化はありますか?
- 社員同士のコミュニケーションは、どのような雰囲気で行われていますか?
- 貴社で活躍している社員に共通する特徴や価値観はありますか?
- 社員のワークライフバランスに対する考え方は、どのようなものですか?
- 入社前と入社後で、社風やカルチャーに関する印象にギャップはありましたか?
- 社員同士の親睦を深めるためのイベントなどはありますか?また、参加率はどのくらいでしょうか?
企業によっては忘年会や夏のイベントなど、社員同士の親睦を深めるイベントが開催されていることがあります。
こういったイベントへの参加率や雰囲気を聞くことも大切です。
強制参加を余儀なくされる企業なども少なくありません。
イベントに対して苦手意識を感じる就活生にとって、入社後のストレスにつながりかねないため、事前に確認しておくことは大切です。
質問した際「もし開催されたら参加しますか?」などと聞かれたら、断らず参加する意思を伝えるようにしましょう。
質疑応答の時間は、先輩社員とのコミュニケーションの時間です。
それを忘れないように心がけてください。
業界全体に関わる質問
業界全体に関する質問をすることで、より深く企業について知ることが可能です。
抽象的な質問ではなく、ニュースなどを取り上げ、具体的な質問を投げかけるようにしましょう。
「業界研究をしっかりしてきたんだな」と関心を持ってもらえるかもしれません。
業界内において、その企業がどういった立ち位置なのかを知ることにもつながり、就活がスムーズに進むようになるはずです。
例文
- 最近、〇〇業界ではXXのような動きがあるとニュースで見ましたが、貴社ではこの動きをどのように捉え、どのような影響があると考えていますか?
- 〇〇業界の今後の展望について、貴社はどのように考えていますか? また、その中で貴社が目指すポジションや役割は何でしょうか?
- 貴社が考える、〇〇業界における競争優位性や独自性は何でしょうか?
- 〇〇業界で活躍するために、特に重要だと考えるスキルや経験は何でしょうか?
- 〇〇業界の課題や今後の成長に向けて、貴社はどのような取り組みを行っていますか?
このような質問で、業界全体の動向を踏まえつつ企業の戦略や将来性、競争力などを理解することが可能です。
とはいえ、業界に関する質問は業界研究をしっかりと行わないとできないものです。
会社説明会だと甘くみず、しっかりと対策を行ってから参加することが大切だといえます。
会社説明会で質問する際のポイント
質問の例文をいくつかみたところで、質問する際のポイントをみていきましょう。
- まずは自分の名前を名乗る
- 質問内容はシンプルにする
- 回答に対してお礼を伝える
- プラスアルファの質問は周囲の様子も気に掛ける
基本的なことではありますが、このポイントを意識することで、より失礼のない質疑応答の時間にできるはずです。
それぞれを詳しくみていきます。
まず自分の名前を名乗る
質問をする際は、いきなり質問を始めるのではなく、まずは、自分の名前と大学名を名乗りましょう。
名乗り方としては、「お話ありがとうございました。〇〇大学のXXと申します。1点質問をよろしいでしょうか」といった形で質問の導入を行うと印象が良いでしょう。
緊張はするかもしれませんが、席を立ち上がり大きな声でハキハキと話すように意識しましょう。
質問内容はシンプルにする
質疑応答の時間は限られていますので、できるだけシンプルに質問をするようにしましょう。
長々と話すのではなく、本当に聞きたい部分を抽出して質問するのがおすすめです。
あれこれ余計なことを付け加えると、「何を聞きたいのか」と質問をされる側も困惑します。
本当に聞きたかった答えが聞けないかもしれません。
簡潔にまとめるのが苦手な方は、この記事で紹介した例文を参考に質問を考えてみてください。
回答に対してお礼を伝える
当たり前のことですが、回答に対しては必ず「ありがとうございました」とお礼を伝えましょう。
質疑応答の際に緊張していると忘れてしまう方も少なくありません。
また、そのまま長い説明にうつった際などは、とくに最後のお礼を言い忘れがちです。
「このような回答でよろしいでしょうか?」と相手から聞かれてしまう可能性もあります。
回答をもらい内容に納得したら、こちらから大きな声でお礼を伝えることが大切です。
「非常にわかりやすいご説明、ありがとうございます」などと、お礼以外の一言も添えるとよりよいでしょう。
プラスアルファの質問は周囲の様子も気にかける
人事の回答を聞いた上で、さらに質問が生まれる場合もあることでしょう。
そのようにプラスアルファの質問をする際は、周囲の様子も気にかけてください。
ほかにも質問したい就活生がいる場合は、一度引き下がり再度確認するのもおすすめです。
また、会社説明のあとにも面接の場や企業説明会など、質疑応答の時間は必ず設けられます。
そのときまで質問をとっておくのもよいでしょう。
「以前会社説明会で、質問させていただいた〇〇のご回答に関して、お聞きしたいことがあります」と伝えることで、より熱意をアピールできる可能性もあります。
万が一ほかの質問が出ない場合には、「重ねて質問してしまって恐縮ですが…」などの文言を添えて、改めて質問するのもおすすめです。
会社説明会で質問する際の注意点

ポイントがわかったところで、より注意すべき点をご紹介します。
質疑応答で失礼な対応をしないように、確認しておいてください。
自分だけの質問時間ではないことを考慮する
最も大切なのは、自分だけの質問時間ではないという意識を持つことです。
先ほどポイントでも解説したように、プラスアルファの質問があるからといって質疑応答の時間を独占するのはやめましょう。
会社説明会は、複数の就活生が参加し再開されている場です。
「ライバルと差をつけたい」という意気込みは大切ですが、だからといってほかの就活生への配慮は忘れてはいけません。
「たくさん説明するほどよい」という場ではないということを理解し、企業側から声がかからない限り、質疑応答は一人ひとつだと考えておきましょう。
最低限の下調べは行っておく
調べればわかることを質問するというのは、時間の無駄にもなります。
「ホームページにも書いてあるとおりですが…」などと言われてしまっては、恥をかくことになるでしょう。
そうならないためにも、事前に下調べを行うことは非常に大切です。
もし、資料やホームページに記載されていることを再度質問したい場合は、「〇〇にも掲載されておりましたが…」と前置きし、さらに深い部分についての答えを確認するようにしましょう。
万が一見落としが不安な場合には、「どこかに記載がある場合は、見落としていて申し訳ございません」などの文言を付けるのもおすすめです。
自己アピールはしない
質疑応答の時間は、自己アピールの時間ではありません。
例えば、「私は御社の△△で〇〇なところがよいと思っているのですが、XXXは実際どのようになっているでしょうか?といった質問は、「私は~~がよい」という主張を混ぜている時点で、自己のアピールだと受け取られる可能性があります。
質問内容はできるだけシンプルに、過度に自己のアピールは行わないよう心掛けましょう。
会社説明会の質問に関するQ&A
それでは最後に、会社説明会における質問に関するQ&Aに回答していきます。
質問は積極的にしたほうが良い?
質問は積極的にするに越したことはありません。
「一番最初に質問をする」という意気込みで挑んでください。
先人を切って質問をすることは、積極性をアピールすることにつながります。
就活はライバルと自分との戦いです。
多くの就活生が挙手をした場合、そのなかの一人として埋もれてしまうかもしれません。
質疑応答の時間を使って印象を残したいと考えている方は、できるだけ率先して挙手をするようにしましょう。
質問をすることで人事の評価は上がる?
質問をしたからといって、人事からの評価が上がるわけではありません。
ただし、積極性や情熱をアピールできることに間違いはないでしょう。
あなたが人事だった場合、何も質問をせずうつむいている学生と、目をキラキラさせて質問をしてくれる学生、どちらを採用したいと考えるでしょうか。
評価が上がるとは言い切れませんが、積極的に質問する姿勢は、確実にあなたの魅力を伝えられます。
ただし、あくまでも会社に関する疑問を解消する場であることを忘れないでください。
自己PRをする場ではありません。
このことに注意をして、質疑応答の時間を有効活用しましょう。
さいごに
本記事では、会社説明会での質問例文から、そのポイントや注意点、メリットまで徹底的に解説しました。
会社説明会で質問をすることは、就活においてメリットが多くあります。
とはいえ、簡潔に質問内容を伝えることや、調べてわかることは聞かないなど、注意点がいくつかあります。
その場で質問内容を考えるより、事前にいくつか考えておき、会社説明会の内容に合わせて表現や内容をかえるとスムーズに質問ができるでしょう。
難しいと感じる就活生は、この記事で紹介した例文を参考に、質問文を考えてみてください。
会社説明会は自分だけの時間ではないことも念頭におきましょう。
いくつも気になる点がある場合は、会社説明会の質疑応答タイムですべて解決しようとせず、後日連絡をしたり選考の過程で確認したりするのもよいでしょう。
会社説明会で焦って失敗をするような事態を招かないよう、この記事を参考に事前準備をしてから参加してくださいね。