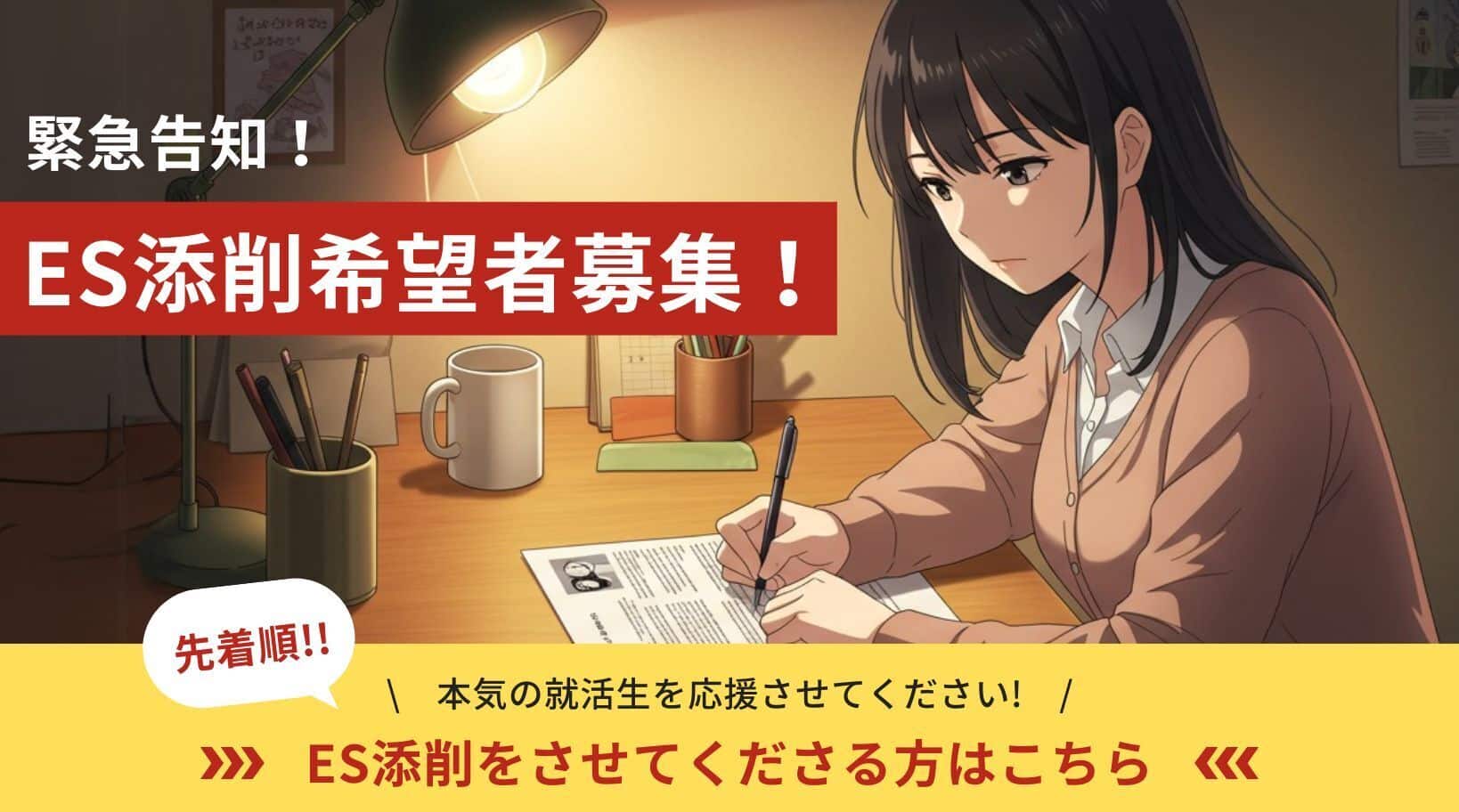自己PRで「協調性」を強みにするには?ポイントや例文を紹介
2025/2/5更新
はじめに
就職活動において、自己PRで協調性をアピールする就活生は多いでしょう。
しかし、適切にアピールしなければ評価にはつながりません。
この記事では、協調性をアピールするときのポイントや注意点、例文まで詳しく解説します。
本記事は、以下のような悩みを抱える就活生を対象としています。
- どうやって協調性をアピールすればいいの?
- 協調性を上手にアピールするポイントを知りたい
- 具体的な例文を知りたい
結論から言うと、協調性は適切にアピールすることで大きな強みとなります。
ぜひ最後まで本記事を読んで、効果的な自己PRの方法を身につけてください。
企業は就活生に「協調性」を求めているのか?
結論から言うと、企業は就活生に「協調性」を強く求めています。
多くの職場では、チームワークや部署間の連携が重要視されており、協調性の高い人材は組織の生産性向上に貢献すると考えられています。
協調性は、円滑な人間関係の構築、効果的な問題解決、そして将来的なリーダーシップの発揮にもつながる重要なスキルです。
また、変化の激しいビジネス環境において、協調性は新しい状況に適応する能力の高さを示す指標にもなります。
そのため、企業は協調性を持つ就活生を高く評価する傾向があります。
自己PRで「協調性」をアピールするメリット
就職活動における自己PRで「協調性」をアピールすることは、企業に対して自分の強みを効果的に伝えるための重要な戦略となります。
協調性は多くの職場で求められる普遍的なスキルであり、適切にアピールすることで採用担当者に好印象を与えることができるからです。
以下では、協調性をアピールするメリットについて詳しく解説します。
円滑な人間関係構築能力をアピールできる
協調性をアピールすることで、職場での円滑な人間関係を構築できる能力を持っていることを示すことができます。
多くの企業では、チームワークや部署間の連携が重要視されており、協調性の高い人材は組織の雰囲気を良好に保ち、生産性の向上に貢献すると考えられています。たとえば、異なる意見を持つ同僚とも建設的な対話ができ、共通の目標に向かって協力できる姿勢をアピールすることで、採用担当者に好印象を与えることができるでしょう。
問題解決能力が証明できる
協調性は単に人と仲良くできるということだけでなく、複雑な問題を解決する能力とも密接に関連しています。
多様な意見や視点を取り入れ、チームで協力して課題に取り組むことができる人材は、企業にとって非常に価値があります。
自己PRで協調性をアピールするときに、過去の経験で協力して困難を乗り越えた具体例を挙げることで、問題解決能力の高さを示すことができるでしょう。
リーダーシップポテンシャルを示せる
協調性の高い人材は、将来的にリーダーシップを発揮できる可能性が高いと評価されることがあります。
なぜなら、チームをまとめ、メンバーの意見を尊重しながら目標達成に導くには、高い協調性が必要だからです。
自己PRで協調性をアピールするときに、グループプロジェクトでのリーダー経験や、メンバーの意見を取りまとめて成果を上げた経験を強調してみましょう。
将来的なリーダーシップポテンシャルを示唆することができます。
適応力の高さを証明できる
協調性の高さは、新しい環境や状況に適応する能力の高さを示す指標にもなります。
企業は常に変化する市場環境に対応する必要があり、そのために柔軟に適応できる人材を求めています。
自己PRで協調性をアピールすることで、異なる背景を持つ人々と協力できる能力や、新しいチームや環境にスムーズに溶け込める適応力の高さを示せるでしょう。
これは特に、グローバル展開している企業や、多様性を重視する組織にとって魅力的な特質となります。
「協調性」がマイナスイメージになるNG例と理由

協調性は上手にアピールすることで大きな強みになりますが、間違ったアピールをしてしまうとマイナスの印象を与えてしまいます。
ここでは、面接やエントリーシートで協調性をアピールするときのNG例文を、それぞれNGである理由とともに紹介します。
NG例文①
私の強みは協調性です。
どんな状況でも周囲の意見に合わせることができ、チームの和を乱さないよう心がけています。
大学時代のグループワークでは、自分の意見を押し付けることなく、常に他のメンバーの意見を尊重し、全員が納得する結論に導くことができました。
この協調性を活かして、貴社でもチームの一員として円滑に仕事を進めていきたいと考えています。
解説:この例文がNGである主な理由は、協調性を過度に強調するあまり、主体性や独自性の欠如を示唆してしまっている点です。
「どんな状況でも周囲の意見に合わせる」という表現は、自分の意見や判断力がないように解釈される可能性があります。
また、「自分の意見を押し付けることなく」という部分も、建設的な意見交換や議論を避けているように受け取られかねません。
企業が求める協調性とは、単に周囲に合わせることではなく、チーム内で適切に自己主張しながらも、他者の意見も尊重し、最適な解決策を見出す能力です。
この例文では、そうした積極的な問題解決能力や創造性も感じられません。
さらに、「チームの和を乱さない」という表現も、必要な対立や建設的な議論を避けているように解釈される可能性があります。
理想的な協調性のアピールでは、自分の意見を持ちつつ、他者の意見も尊重し、チーム全体の目標達成に向けて積極的に貢献できることを示す必要があります。
NG例文②
私は協調性があり、どんな相手とも仲良く付き合うことができます。
学生時代のアルバイトでは、先輩や後輩、お客様とも良好な関係を築き、職場の雰囲気を明るくすることができました。
困っている同僚がいれば、自分の仕事を後回しにしてでも助けるなど、常に周囲との関係性を大切にしています。
この協調性を活かして、貴社でも良好な人間関係を築いていきたいと考えています。
解説:この例文がNGである主な理由は、協調性を単なる人間関係の良好さや親和性と混同している点です。
また、業務の優先順位や効率性を無視した行動を美徳として描いている点も問題です。
「どんな相手とも仲良く付き合う」という表現は、表面的な関係性のみを重視しているように解釈される可能性があります。
ビジネスにおいては、単に仲が良いだけでなく、建設的な関係性を築き、業務の効率化や成果の向上につながる協調性が求められます。
また、「自分の仕事を後回しにしてでも助ける」という部分は、業務の優先順位を適切に判断できない、あるいは自身の責任を果たせないという印象を与えかねません。
協調性は、自身の責任を全うしつつ、チーム全体の成果を向上させるために発揮されるべきものです。
理想的な協調性のアピールでは、良好な人間関係を築きつつも、業務の効率性や成果を向上させる具体的な行動や成果を示すことが重要です。
また、単に人間関係を重視するだけでなく、チームの目標達成に向けて積極的に貢献できることを示す必要があります。
NG例文③
私は協調性が高く、どんな意見の対立があっても、すぐに解決することができます。
学生時代のプロジェクトでは、メンバー間で意見が割れた際、全員の意見を取り入れた折衷案を提案し、対立を回避しました。
常に全員が納得する解決策を見つけることを心がけており、この能力を活かして、貴社でもチーム内の対立を未然に防ぎ、スムーズに業務を進めていきたいと考えています。
解説:この例文がNGである主な理由は、協調性を単なる対立回避や妥協と同一視している点です。
また、建設的な議論や対立の価値を認識していない印象を与えかねません。
「どんな意見の対立があっても、すぐに解決する」という表現は、問題の本質を深く掘り下げずに、表面的な解決を図っているように解釈される可能性があります。
ビジネスにおいては、時として建設的な対立や議論が必要であり、それを通じてより良い解決策や革新的なアイデアが生まれることがあります。
「全員の意見を取り入れた折衷案」や「全員が納得する解決策」という表現も、単なる妥協や中途半端な解決策を示唆しているように受け取られかねません。
真の協調性は、時には困難な決断や一部の意見を採用しないことも含め、最適な解決策を見出す能力を指します。
また、「対立を回避」や「対立を未然に防ぐ」という表現は、必要な議論や意見交換を避けているように解釈される可能性があります。
企業が求める協調性は、対立を恐れずに建設的な議論を行い、そこから最適な解決策を導き出す能力です。
理想的な協調性のアピールでは、異なる意見や対立を恐れずに向き合い、建設的な議論を通じてより良い解決策を見出す能力を示すことが重要です。
また、チームの目標達成のために、時には困難な決断を下す勇気があることも示す必要があります。
「協調性」を魅力的にアピールするためには
先ほど紹介したように、知哉協調性を効果的にアピールするには、具体的なエピソードを交えながら、自身の強みとして説得力のある形で伝える必要があります。
以下では、協調性を魅力的にアピールするためのポイントについて詳しく説明します。
具体的なエピソードの提示
協調性をアピールするときは、抽象的な表現を避け、具体的なエピソードを提示することが重要です。
たとえば、学生時代のサークル活動やアルバイト経験など、実際に協調性を発揮した場面を詳細に説明します。
このとき、どのような状況で、どのように協調性を発揮し、どのような成果が得られたかを明確に伝えることで、面接官に具体的なイメージを持ってもらうことができます。
また、エピソードは一つに絞り、その内容を深掘りして説明することで、より印象に残るアピールとなるでしょう。
主体性との両立
協調性をアピールするときに注意すべき点は、主体性の欠如と誤解されないようにすることです。
単に周囲に合わせるだけでなく、自ら積極的に行動を起こし、チームに貢献した経験を強調します。
たとえば、「チーム内の意見の相違を調整し、新たな解決策を提案した」といった経験を挙げることで、協調性と主体性の両立をアピールできます。
これにより、単なる同調者ではなく、チームの中で建設的な役割を果たせる人材であることを示すことができるのです。
問題解決能力の強調
協調性は、単に人間関係を円滑にするスキルではなく、効果的な問題解決につながる重要な能力でもあります。
協調性をアピールするときは、チームで直面した課題をどのように解決したかを具体的に説明するといいでしょう。
たとえば、「メンバー間の意見の対立を調整し、全員が納得する解決策を導き出した」といった経験を挙げることで、協調性が実際の成果につながることを示すことができます。
伝え方を工夫することで、協調性が単なる性格特性ではなく、ビジネスにおいて価値ある能力であることをアピールできるでしょう。
多様性への対応力
現代の職場環境では、多様な背景を持つ人々と協力して働くことが求められます。協調性をアピールするときは、異なる価値観や文化を持つ人々と効果的に協力した経験を強調するといいでしょう。
たとえば、留学経験や異文化交流の機会での経験を挙げ、どのように相互理解を深め、共通の目標に向かって協力したかを説明します。
これにより、グローバル化が進む企業環境において、柔軟に対応できる人材であることをよりアピールできるでしょう。
成長志向との関連付け
協調性をアピールするときは、それが自身の成長にどのようにつながったかを説明することも効果的です。
チームでの協力を通じて新しいスキルを習得した経験や、他者からのフィードバックを積極的に取り入れて自己改善を図った経験などを挙げます。
こうした説明を加えることで、協調性が単に他者とうまく付き合うためのスキルではなく、自身の継続的な成長と学習につながる重要な要素であることを示すことができます。
「協調性」が好印象を与えるアピール例文

自己PRで協調性をアピールするときは、具体的なエピソードを交えながら、自身の強みとして説得力のある形で伝えることが重要です。
ここでは協調性をアピールするときの例文を3つ紹介します。
これらの例文を参考に、自身の経験や特性に合わせてカスタマイズし、魅力的な自己PRを作成してください。
良い例文①
私の強みは、多様な意見を尊重しながら、チームの目標達成に貢献できる協調性です。
大学のゼミ活動では、異なる専攻の学生たちと共同研究プロジェクトに取り組みました。意見の対立が生じた際、私は各メンバーの専門知識を活かせるよう、定期的な意見交換会を提案し、進行役を務めました。
その結果、多角的な視点を取り入れた独創的な研究成果を生み出すことができ、学内コンペティションで最優秀賞を受賞しました。
この経験から、異なる背景を持つ人々と協力し、それぞれの強みを活かしながら成果を上げることの重要性を学びました。
この協調性を活かし、貴社でも多様なチームの中で積極的に貢献していきたいと考えています。
解説:この例文は、具体的な経験を通じて協調性をアピールしている点が優れています。
大学のゼミ活動における共同研究プロジェクトという具体的な状況を挙げ、そこでの課題と解決策を明確に示しているでしょう。
さらに、その結果として得られた成果も明示しており、協調性が実際の成果につながったことを効果的に伝えています。
最後に、この経験から学んだことと、それを今後どのように活かしたいかを述べることで、自己PRを締めくくっているのが好印象です。
良い例文②
私の特徴は、高い協調性を持ちながらも、必要に応じてリーダーシップを発揮できる点です。
アルバイト先のカフェでは、新人教育係として10名以上のスタッフの指導を担当しました。個々のスタッフの性格や学習スタイルに合わせて指導方法を工夫し、全員が円滑に業務を習得できるよう努めました。
また、スタッフ間の意見の相違を調整し、全員が納得できるシフト体制を提案しました。
その結果、店舗の雰囲気が改善し、顧客満足度が20%向上しました。
この経験から、チームメンバーの個性を尊重しつつ、全体の目標達成に向けてリードすることの重要性を学びました。
貴社でも、この協調性とリーダーシップを活かし、チームの成果向上に貢献したいと考えています。
解説:この例文は、協調性とリーダーシップの両面をアピールしている点が特徴的です。
アルバイト先での具体的な役割と、そこでの取り組みを詳細に説明しています。
また、その結果として得られた具体的な成果を数値で示すことで、自身の貢献を客観的に伝えているのが効果的です。
さらに、この経験から学んだことと、それを今後どのように活かしたいかを述べることで、自己PRに説得力を持たせています。
良い例文③
私の強みは、異文化環境においても発揮できる高い協調性です。
1年間の海外留学中、言語や文化の壁を乗り越え、現地学生との共同プロジェクトに取り組みました。
コミュニケーションの齟齬や価値観の違いに直面した際、私は積極的に対話の機会を設け、お互いの背景を理解し合うことに努めました。
また、チーム内の意見をまとめる役割を買って出て、全員の意見を尊重しながら最適な解決策を導き出しました。
その結果、文化の違いを強みに変え、革新的なアイデアを生み出すことができ、プロジェクトは成功を収めました。
この経験から、多様性を受け入れ、協力することの重要性を学びました。
貴社のグローバルな環境においても、この協調性を活かして活躍したいと考えています。
解説:この例文は、グローバルな環境における協調性をアピールしている点が特徴的です。
海外留学という具体的な経験を挙げ、そこでの課題と、それに対する取り組みを詳細に説明しているでしょう。
また、その結果として得られた成果も明示しており、協調性が実際の成果につながったことを効果的に伝えています。
最後に、この経験から学んだことと、それを今後どのように活かしたいかを述べることで、自己PRを締めくくっているのが印象的です。
さいごに
就職活動における自己PRで協調性をアピールすることは、企業が求める重要なスキルを示す効果的な方法です。
しかし、単に協調性があると述べるだけでは不十分です。
具体的なエピソードを交えながら、主体性や問題解決能力、多様性への対応力、成長志向との関連付けを行うことが重要となります。
また、協調性を過度に強調することで、個性や創造性の欠如、リーダーシップ能力の不足といった誤解を与えないよう注意が必要です。
適切にアピールすることで、チームワークに貢献し、組織の目標達成に寄与できる人材であることを効果的に伝えることができるでしょう。