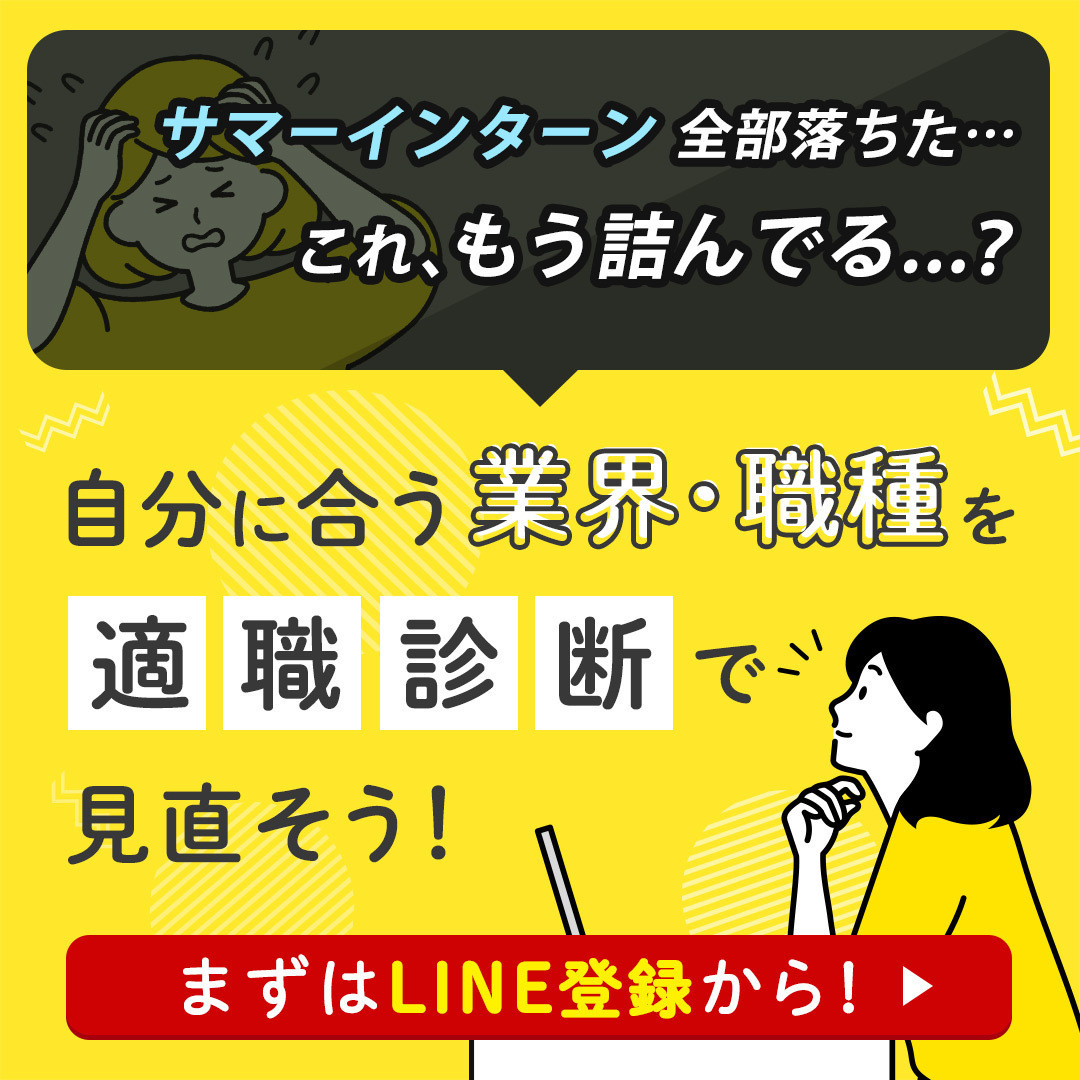既卒の就活が厳しい理由とは?就職するためのポイントや注意点
2024/9/24更新
はじめに
既卒での就職活動は、新卒とは異なる課題や困難に直面することもあるでしょう。
実際に「既卒だと就活が厳しい」「新卒一括採用の壁を越えられるか不安」といった声をよく耳にします。
しかし、実際には既卒ならではの強みや、成功するための効果的な方法が存在します。
本記事では、既卒就活の厳しさの理由や、それを乗り越えるための具体的な戦略、さらには既卒の強みを活かす方法について詳しく解説していきます。
以下のような悩みを抱える既卒の方は、ぜひ最後までお読みください。
- 既卒就活は本当に厳しいの?どうすれば成功できる?
- 面接で卒業後の期間をどう説明すればいいの?
- 既卒でも内定を獲得するためのコツは?
上京を志す地方学生ならジョーカツ!
あなたのキャリアを加速させるチャンス!
無料で利用できる快適な個室シェアハウス、
東京までの交通費サポート付き
首都圏の注目企業への就活ならジョーカツ
首都圏の学生ならスタキャリ!
理想のキャリアを実現へと導く第一歩!
あなたにピッタリのキャリアアドバイザーを選び、
自分にマッチする優良企業をご紹介
首都圏企業のES添削から面接対策まで、就活ならスタキャリ
そもそも既卒とは?

既卒とは、高校や大学、専門学校などの教育機関を卒業後、正社員として就職した経験がない人を指す言葉です。
一般的に、卒業後1〜3年程度の期間にある人々を既卒と呼ぶことが多いでしょう。
明確な定義はありませんが、おおむね25歳くらいまでの若者が該当します。
新卒採用の機会を逃した人や、卒業後すぐに就職せずに別の道を選んだ人たちがこのカテゴリーです。
既卒者の中には、卒業後にアルバイトやパートタイムで働いているフリーターも含まれます。
就職活動において、既卒者は新卒とは異なる立場にあり、独自の課題や機会に直面することになるでしょう。
しかし、近年では既卒採用に積極的な企業も増えており、キャリアの選択肢は広がっています。
既卒者の経験や成長を評価する企業も少なくありません。
既卒の就活が厳しい理由
既卒者の就職活動は、新卒者と比較してより困難な面があります。
これにはさまざまな要因が絡み合っており、既卒者特有の課題が存在します。
以下では、既卒の就活が厳しいとされる主な理由について詳しく解説していきましょう。
企業の新卒一括採用システム
日本の多くの企業では、新卒一括採用システムが主流となっています。
このシステムでは、毎年決まった時期に新卒者を一斉に採用し、社内で育成していく方針を取っています。
そのため、既卒者はこのシステムに組み込まれにくく、採用の機会が限られてしまうのです。
企業側も、既存の教育プログラムや人事制度に既卒者を組み込むことに難しさを感じる場合があります。
スキルや経験の不足
既卒者は、卒業後の期間が空いているため、スキルや経験が不足していると見なされることがあります。
特に、専門的な知識や技術が求められる職種では、この点が大きなハードルとなるでしょう。
また、アルバイトやフリーターなどの経験しかない場合、正社員としての就業経験がないことも不利に働くことがあります。
年齢のミスマッチ
既卒者の中には、同年代の社会人と比べて職歴や経験が少ない場合があります。
これにより、企業側が求める年齢層とのミスマッチが生じる可能性があるのです。
特に、管理職や中堅社員としての採用を想定している場合、既卒者の年齢が適合しないと判断されることもあるでしょう。
モチベーションへの疑問
企業側は、既卒者の就職に対するモチベーションや意欲を疑問視することがあります。
なぜ今まで就職できなかったのか、という点に注目し、本人の能力や意欲に不安を感じる可能性があるのです。
このような先入観が、採用の障壁となってしまうケースも少なくありません。
キャリアプランの不明確さ
既卒者の中には、明確なキャリアプランを持っていない人もいます。
これは、企業側にとって将来的な人材育成や配置の面で不安要素となる可能性があります。
長期的な視点でのキャリア形成が見えにくいことが、採用を躊躇させる原因になることもあるでしょう。
競争の激化
既卒者の就活市場では、新卒者だけでなく、他の既卒者や転職希望者とも競合することになります。
このため、より厳しい競争環境に置かれることになるのです。
特に人気企業や安定した業界では、この競争が一層激しくなる傾向にあります。
既卒が就活で成功するための方法

既卒者の就職活動は、新卒とは異なる課題や機会に直面します。
しかし、適切な戦略と準備を整えることで、既卒者も充実したキャリアをスタートさせることができるのです。
以下では、既卒者が就活で成功するための効果的な方法を詳しく解説していきます。
これらの方法を実践することで、既卒者の皆さんも自信を持って就職活動に臨むことができるでしょう。
自己分析を徹底する
自己分析は就職活動の基礎となる重要なステップです。
既卒者の場合、卒業後の経験や成長を含めた自己理解が必要となります。
自分の強み、弱み、価値観、興味関心を深く掘り下げましょう。
卒業後の期間に取り組んだこと、学んだこと、成長したポイントを明確にすることが大切です。
これにより、自分自身をよりよく理解し、企業にアピールできる点を見出すことができるでしょう。
スキルアップに励む
既卒期間を活用して、就職に役立つスキルを身につけることが重要です。
業界に関連する資格取得や、オンライン講座の受講などが効果的です。
特に、IT関連のスキルや語学力は多くの企業で求められています。
自己投資を惜しまず、積極的にスキルアップに取り組むことで、競争力を高めることができるでしょう。
学んだスキルは履歴書やエントリーシートで具体的にアピールしましょう。
業界研究を行う
志望する業界について深く理解することは、面接で的確な受け答えをするために不可欠です。
業界のトレンド、主要企業の動向、将来の展望などを調査しましょう。
業界専門誌やニュース、企業のウェブサイトなどを活用し、最新の情報を収集します。
この知識は、志望動機を説得力のあるものにし、面接官に好印象を与えるでしょう。
インターンシップに参加する
インターンシップは、実際の職場環境を体験し、業界の理解を深める絶好の機会です。
既卒者向けのインターンシップも増えているので、積極的に参加しましょう。
職場の雰囲気や業務内容を直接体験することで、自分に合った仕事を見つけやすくなります。
また、インターンシップを通じて人脈を広げることも可能です。
この経験は、就職活動において大きな強みとなるでしょう。
人脈を活用する
人脈作りは、就職活動においてとても重要です。
既卒者向けの就活イベントや業界セミナーに積極的に参加しましょう。
同じ立場の人々との交流は、情報交換や励ましあいの場となります。
また、OB・OG訪問を活用し、実際に働いている先輩から貴重なアドバイスを得ることも効果的です。
こうした活動を通じて、隠れた求人情報を入手できる可能性も高まります。
既卒向け求人を活用する
既卒者向けの求人サイトや転職エージェントを利用することで、自分に適した求人を見つけやすくなります。
これらのサービスは、既卒者の特性を理解し、適切なマッチングを提供してくれます。
複数のサービスを併用し、幅広く情報を収集しましょう。
エージェントを利用する場合は、自分の希望や状況を詳しく伝え、的確なアドバイスを受けることが大切です。
面接対策を万全にする
面接は採用の決め手となる重要な機会です。
既卒者特有の質問、例えば「なぜ今まで就職しなかったのか」などに対する回答を準備しておきましょう。
ネガティブな印象を与えないよう、前向きな姿勢で答えることが重要です。
また、模擬面接を繰り返し行い、自信を持って臨めるよう練習を重ねましょう。
適切な身だしなみや態度も、好印象を与える重要な要素となります。
柔軟な姿勢を持つ
就職活動では、柔軟な姿勢を持つことが成功の鍵となります。
希望する業界や職種にこだわりすぎず、幅広い選択肢を検討しましょう。
特に、成長産業や人手不足の業界では、既卒者の採用に積極的な企業も多いです。
また、正社員にこだわらず、契約社員や派遣社員としてのスタートを検討するのも一つの方法です。
まずは社会人としての経験を積み、そこからステップアップを目指すという戦略も効果的でしょう。
就活で活かせる既卒の強み
既卒者の就職活動は、一見不利に思えるかもしれません。
しかし、実際には既卒ならではの強みがたくさんあります。
これらの強みを適切にアピールすることで、就活を有利に進めることができるでしょう。
以下では、既卒者が就活で活かせる主な強みについて詳しく解説していきます。
自己分析の深さ
既卒者は、卒業後の時間を通じて自己分析を深める機会が多くあります。
学生時代には気づかなかった自分の特性や価値観を、より明確に理解していることでしょう。
この深い自己理解は、企業とのマッチングを考える上で大きな強みとなります。
面接では、自分の長所や短所、キャリアビジョンについて、より具体的かつ説得力のある説明ができるはずです。
明確な志望動機
既卒者は、就職に対する思いがより強く、明確になっていることが多いです。
卒業後の経験を通じて、自分が本当にやりたいことや、社会で果たしたい役割について、じっくり考える時間があったはずです。
この明確な志望動機は、企業側にとって魅力的な要素となるでしょう。
熱意と目的意識を持って仕事に取り組む姿勢をアピールできます。
社会経験
アルバイトやインターンシップ、ボランティア活動など、卒業後にさまざまな経験を積んでいる既卒者も多いはずです。
これらの経験は、社会人基礎力の向上につながっています。
コミュニケーション能力や責任感、時間管理能力など、実践的なスキルを身につけていることをアピールしましょう。
企業にとっては、即戦力として期待できる人材だと映るはずです。
学び続ける姿勢
既卒者の多くは、卒業後も自己啓発や学習を続けています。
資格取得や語学学習、オンライン講座の受講など、自己投資を行っている人も少なくありません。
この学び続ける姿勢は、企業が求める「成長意欲」や「向上心」と直結します。
常に新しいことにチャレンジし、成長し続ける姿勢をアピールすることで、企業の心をつかむことができるでしょう。
入社時期が柔軟に対応できる
既卒者は、学生と異なり、柔軟な入社時期に対応できることも強みです。
企業の採用ニーズに合わせて、即座に入社することが可能です。
この柔軟性は、中途採用を行う企業にとって大きなメリットとなります。
特に、急な欠員補充や事業拡大に伴う増員など、タイムリーな採用を求める企業にとっては魅力的な点でしょう。
既卒者の就活の流れ

では、既卒者はどのように就職活動を行うのでしょうか。
既卒者向けの就職活動の方法についてご紹介します。
既卒者向け就活サイトに登録する
最も簡単なのは、既卒者向けの就活サイトに登録することです。
「そんなのあるの?」と思うかもしれませんが、既卒者向けの就活サイトはいくつか存在しています。
既卒者に限定した就活サイトを利用することで、企業とのマッチングの際に「既卒」であることのハードルを一段階下げることが可能です。
既卒者向けの就活サイトに登録している企業は、そもそも既卒者を欲していると言うことができます。
したがって、不安に思うことなくサイトを利用できるため、安心感を持って利用することができるでしょう。
新卒を採用している企業に応募する
新卒を採用している企業に応募するのも、既卒者の就活方法として有効です。
先にご紹介した通り、多くの企業は新卒入社と同様に迎え入れようと思っている場合がほとんどです。
そのため、新卒入社と同様の採用の選考を受けることを拒否する企業は少ないと言えるでしょう。
また、最近では通年採用が広がっており、就職活動をする年齢についても制限がなくなってきています。
したがって、年齢を気にしなくなっている企業が増えているのも事実です。
もちろん面接時には既卒者であることを伝える必要はありますが、応募フローとしては新卒と同じでも問題ないと言えるでしょう。
第二新卒積極採用中の企業に応募する
「第二新卒積極採用中」を掲げる企業に対して、積極的に応募するのもおすすめです。
第二新卒を積極的に募集している企業は、若者を採りたいという意向が高い可能性があり、既卒者であっても受け入れてくれる可能性が高いと言えます。
一方、第二新卒は社会人基礎力はある程度備えていることを前提としているため、その点で既卒者が回答しない可能性があります。
結果として、新卒入社者と同じ扱いとなる可能性が高いですが、応募先として第二新卒枠を活用してみるのはとても有効です。
既卒者が就活するときにやってはいけないこと
既卒者の就職活動には、新卒とは異なる注意点があります。
経験を積んだ分、強みを活かせる可能性もある一方で、避けるべき行動もあるので注意が必要です。
以下では、既卒者が就活する際に絶対にやってはいけないことについて詳しく解説します。
これらの点に気をつけることで、より効果的な就職活動を展開できるでしょう。
卒業後の期間を無駄に過ごしたと言う
卒業後の期間について、「何もしていなかった」と正直に答えてしまうのは避けましょう。
たとえ就職活動をしていなかった期間があったとしても、その時間を前向きに捉え直すことが大切です。
アルバイトやボランティア、自己啓発など、何らかの形で自分を成長させる活動をしていたはずです。
そういった経験を、仕事にどう活かせるかという視点で語りましょう。
面接官は、その期間にどのような努力や学びがあったかに興味を持っています。
新卒と同じ目線で就活をする
既卒者は、新卒とは異なる立場にあることを認識する必要があります。
新卒向けの就活イベントや説明会にこだわりすぎるのは得策ではありません。
むしろ、既卒者向けの求人や中途採用の枠を積極的に探すべきでしょう。
自分の経験や成長を活かせる職場を見つけることが、成功への近道となります。
既卒ならではの強みを活かした就活戦略を立てることが重要です。
空白期間を隠そうとする
履歴書や面接で空白期間を隠そうとするのは、最悪の選択です。
嘘をつくことは、信頼関係を損なう大きな要因となります。
むしろ、その期間に何を学び、どのように成長したかを正直に伝えましょう。
自己分析を深め、空白期間を前向きに捉え直すことで、むしろ強みに変えることができます。
正直に伝えつつ、その経験をどう活かせるかを説明することが大切です。
焦って志望動機が曖昧な応募をする
焦りから、志望動機が不明確なまま多くの企業に応募するのは避けましょう。
企業研究が不十分なまま応募すると、面接での受け答えが曖昧になってしまい、苦戦する可能性が高くなります。
各企業の特徴や求める人材像をしっかり理解し、自分がなぜその企業で働きたいのかを明確にすることが重要です。
質より量ではなく、自分に合った企業を厳選して応募することで、内定獲得の確率が上がるでしょう。
既卒であることを言い訳にする
既卒であることを言い訳にして、消極的な態度を取るのは禁物です。
むしろ、既卒ならではの経験や視点を強みとして捉え、積極的にアピールしましょう。
社会人経験や自己研鑽の時間があったことで、より明確な目標や意志を持って就職活動に臨めるはずです。
自信を持って自分の価値を伝えることが、面接官に好印象を与える鍵となります。
既卒者向けおすすめ就活サービス5選

では最後に、既卒者向けのおすすめ就活サービスをご紹介します。
マイナビジョブ20’sアドバンス
マイナビジョブ20’sアドバンスは、マイナビが展開する既卒者限定のサービスです。
既卒者を対象にしているため、紹介される企業も既卒者を積極採用している企業ばかりで、安心して利用できます。
また、既卒者であっても最短2週間で内定を獲得することができるため、早期で内定を獲得したい人におすすめのサイトです。
ただし、対応エリアが日本国内の主要都市に限られているため、エリアによっては利用できない可能性があります。
Re就活
第二新卒用のサイトとして有名なRe就活ですが、実は20代の転職に強いとされており、既卒者の就活にもとても適しています。
20代・第二新卒・既卒のための転職サイトという紹介文もあり、積極的に活用するのがおすすめのサイトです。
また、全国に展開する学情が運営しているため、どのエリアにお住まいでも利用することが可能です。
DYM就職
フリーター・ニートに向けた就職サイトであるDYM就職は、第二新卒も積極的に活用できる転職サイトです。
一見「有名企業などの求人はないのでは?」と思うかもしれませんが、東証プライム上場企業からベンチャー企業まで、さまざまな企業が掲載されています。
また、面接や内定後のサポートも手厚く受けることができるため、既卒者としての就職活動に不安がある場合にはとてもおすすめです。
DYM就職を軸に、他のサイト利用などを検討してみるのも良いでしょう。
第二新卒エージェントneo
第二新卒エージェントneoは、第二新卒に特化したエージェントです。
中でも28歳までの就職支援実績が高く、専任の就活アドバイザーが丁寧なアドバイスをしてくれます。
面接対策はもちろん、書類添削もしてくれるため、就活初心者でも安心して臨むことが可能です。
また、面接時のフィードバックを受けることができるため、具体的にどのような質問が問題だったかを詳しく知ることができます。
さらに独自のYouTubeなども展開しているため、就活情報をキャッチアップするツールとしてもおすすめです。
リクナビNEXT
転職用のサイトとして知られるリクナビNEXTを、既卒者が利用することも可能です。
既卒者が応募可能な求人には「既卒可」の文言が添えられており、比較的分かりやすい点も大きな特徴と言えるでしょう。
一方で、あくまでも転職がメインのサイトのため、必ずしも既卒者が歓迎されるとは限りません。
確実に既卒者OKの求人サイトを見つけたいなら、まずは既卒者専用のサイトへ登録してみるのがおすすめです。
さいごに
既卒者の就職活動には、確かに独自の課題がありますが、同時に多くの可能性も秘めています。
自己分析を深め、スキルアップに励み、業界研究を行うことで、自分の強みを最大限に活かせる道が開けるでしょう。
既卒ならではの経験や視点を積極的にアピールし、明確な志望動機を持って臨むことが重要です。
焦らず、自分に合った企業を見極めながら、前向きな姿勢で就活に取り組みましょう。
既卒であることを言い訳にせず、むしろ強みとして捉え直すことで、新たなキャリアへの扉が開かれるはずです。
自信を持って自分の価値を伝え、理想の就職先を見つける努力を続けてみましょう。