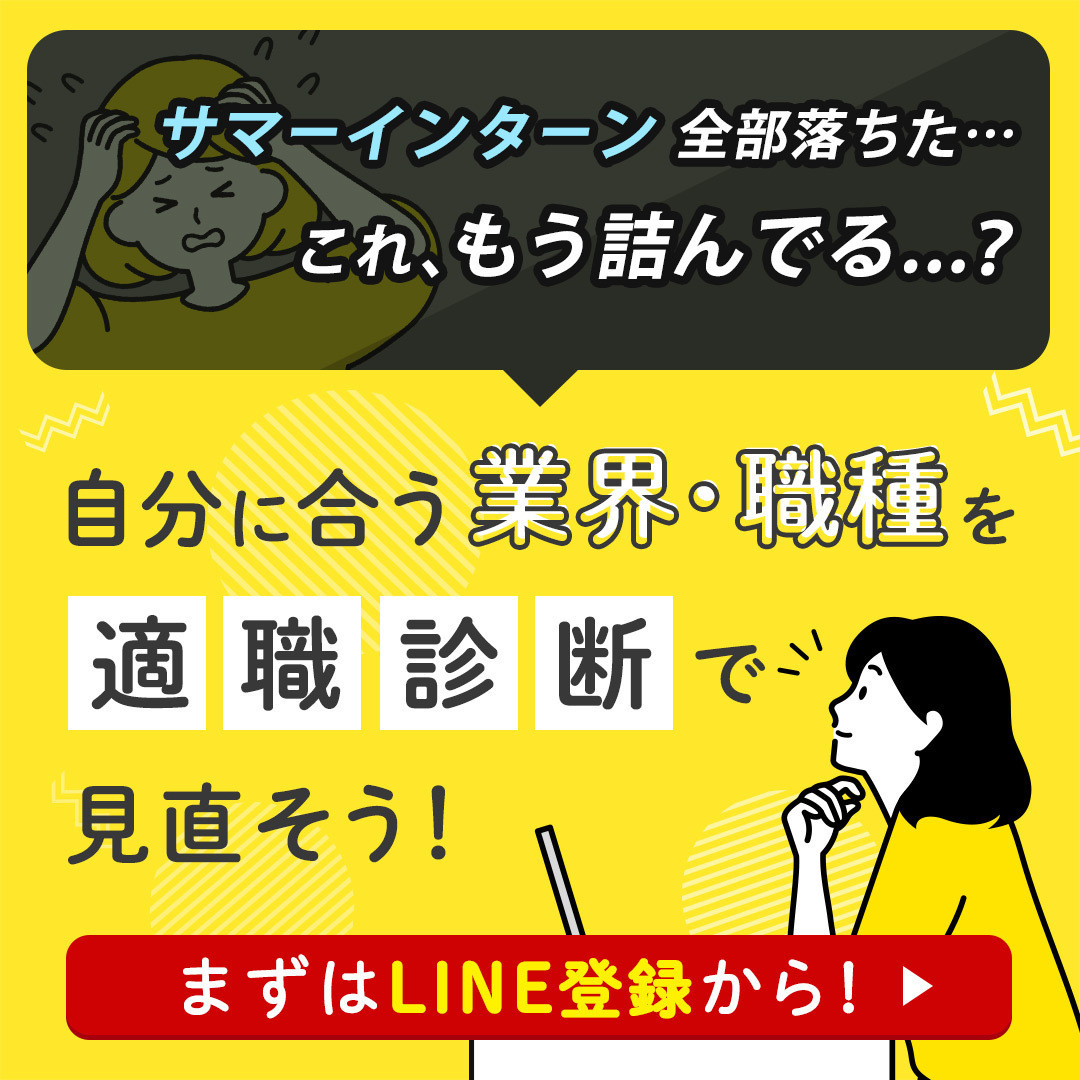【初心者でも安心】給与明細の見方が分かる!活用法を解説
2024/9/24更新
はじめに
就活生の皆さんにとって、「給与」は重大な関心事の一つのはずです。
皆さんが就活を終えて会社に入り、初めての給与をもらうときは感慨深いものになるでしょう。
それは、自分の労働の価値が金銭に反映されたものに他ならず、自身の新たなキャリアの始まりを象徴するものです。
今後、皆さんが会社から示される給与明細には、どのような項目があるのかご存知でしょうか。
- 給与明細の見方を知りたい
- 「給与」と「給料」とは意味が異なるのか分からない
- 税金等、控除される項目の概要を知りたい
この記事では、就活生が今のうちから知っておきたい給与明細の概要について解説します。
10分くらいで給与明細の基本を身に着けることができますので、最後まで読んでくださいね。
上京を志す地方学生ならジョーカツ!
あなたのキャリアを加速させるチャンス!
無料で利用できる快適な個室シェアハウス、
東京までの交通費サポート付き
首都圏の注目企業への就活ならジョーカツ
首都圏の学生ならスタキャリ!
理想のキャリアを実現へと導く第一歩!
あなたにピッタリのキャリアアドバイザーを選び、
自分にマッチする優良企業をご紹介
首都圏企業のES添削から面接対策まで、就活ならスタキャリ
給与明細とは
給与明細とは、支払われた給与の根拠となる、勤怠情報・給与支払額・控除額などの内訳が記載された書類をいいます。
「給与がどのように計算され、どんな控除がされたあとに支払われたか」を説明する内容が記載されています。
会社から社員(従業員)に対して支払われる給与は、総支給額から、社会保険料や税金などを控除した額です。
給与明細の発行
給与明細は、紙もしくは電子データで発行することが会社に対して義務付けられています(所得税法第231条第1項・第2項、所得税法施行令第356条、所得税法施行規則第100条)。
会社により、「末締め15日払い」や「15日締め25日払い」など、給与の締め日と支払日が決まっており、明細には給与の支払期間分の情報が記載されます。
ここにおいて、「締め日と」は、給与の支払い期間の最終日を意味します。
よって、たとえば、末締めなら毎月1日〜月末まで、15日締めなら毎月16日〜翌15日までが給与の支払期間になるというわけです。
給与明細の作成は、企業にとって欠かせない業務の一つです。社員の給与を計算して振り込むだけにとどまらず、給与明細を作成して発行するまでが給与計算業務であるといえます。
給与明細は、会社にとって重要であることは上記のとおりですが、社員にとっても大切なものです。たとえば、社員が住宅ローンを組む際は、金融機関の審査にあたり、提出することが求められます。
加えて、社員が自分の給与額、各種の控除額を正確に理解しておくことは、将来のライフプランを設計するうえで大変重要です。
そのため企業は、給与明細を滞りなく作成して発行できる環境を整える必要があるわけです。
賃金の支払に関するルール
会社から社員に対し、賃金が全額確実に支払われるよう、所定のルールが法定されています(労働基準法第24 条)。
具体的には、次の4つが重要です。
通貨払いの原則
会社は、社員に対する賃金を現金で支払う必要があります。
この場合、会社は社員の同意を得たうえで、支払方法を銀行振込み等にすることができます。
また、労働協約に定めがある場合には、通貨ではなく現物支給をすることができます。
直接払いの原則
会社は、賃金を社員本人に支払う必要があります。社員の親などに代わりに支払うことはできません。
全額払いの原則
賃金は、会社から社員に対し、全額残らず支払われる必要があります。
よって、「積立金」等の名目で強制的に賃金の一部を控除(天引き)して支払うことはできないのです。
ただし、所得税や社会保険料等、法令で認められている分の控除は可能です。
それ以外は、社員の過半数で組織する労働組合、過半数組合がない場合は労働者の過半数を代表する者と労使協定を結んでいる場合は認められます。
毎月1回以上定期払いの原則
会社は社員に対し、毎月1回以上、一定の期日を定めて賃金を支払う必要があります。
このため、「今月分は来月2か月分まとめて払うから」ということは認められないのです。
また、支払日を「毎月20日から25日の間」とすることや「毎月第4金曜日」など変動する期日とすることも認められないのです。
給与明細の記載事項

給与明細には、主として次の5項目を記載します。
- 勤怠
- 給与の支給
- 総支給額
- 控除
- 差引支給額
勤怠
出勤日数や欠勤日数、労働時間など、従業員の勤怠情報に関する項目です。そのほか有給休暇の取得日数や残業時間、深夜労働時間(22〜5時)など、給与計算の根拠として使用した情報を記載します。
なお、給与明細に記載されるのは、締め日を基準とした期間の実績です。たとえば、有給休暇の残日数は締め日時点のものなので、給与支給時点との情報に時間差が発生します。
| 項目分類 | 項目ごとの詳細 |
| 勤怠 |
|
給与の支給
基本給をはじめ、通勤手当や資格手当などの各種手当や割増賃金、勤怠控除など給与の支給に関する情報を記載する項目です。
基本給とは、毎月・毎週などの固定で支払われる賃金を指します。昇給あるいは降給がない場合、毎月一定額が支払われます。
割増賃金とは、時間外労働や休日労働、深夜労働などに対して、通常の賃金に上乗せして支払われるものです。時間外労働には25%、深夜労働には35%など、定められた割増率を適用します。
勤怠控除とは、欠勤や遅刻・早退などで従業員が労働しなかった時間分、あるいは日数分の賃金を差し引くことです。
| 項目分類 | 項目ごとの詳細 |
| 支給 |
|
総支給額
基本給をベースとして、それぞれの従業員に該当する手当や割増賃金、勤怠控除などを足し引きした金額を記載します。いわゆる「額面給与」と呼ばれるものです。
控除
給与から天引きする金額を記載する項目です。健康保険料(40歳以上の従業員は介護保険料も)や厚生年金保険、雇用保険、所得税や住民税など、項目ごとに控除した金額を記載します。企業によっては、労働組合の組合費や従業員持株会の積立金など、独自の控除項目を差し引くこともあります。
| 項目分類 | 項目ごとの詳細 |
| 控除 |
|
差引支給額
総支給額から社会保険料や税金などを差し引いて、従業員に実際に支給する金額です。いわゆる「手取り給与」と呼ばれるもので、支給方法は企業によって異なります。
労働基準法上、原則として給与は現金を手渡しすることとされています。しかし、従業員の同意を得たうえで口座に振り込むことができ、振り込みを採用している企業が一般的です。
給与明細の各項目の意味

それでは給与明細の各項目の内容を説明します。
会社によって差異はありますが、下記の給与明細を基本型として説明を加えます。
| 2024年〇月 給与明細 | 上活 太郎 様 | ||||
| 2024年〇月〇日支給 ****株式会社 | |||||
| 勤務 | 勤務日数 | 欠勤日数 | 有給日数 | ||
| 20日 | 0日 | 1日 | |||
| 支給 | 基本給 | 残業手当 | |||
| 250,000 | 50,000 | ||||
| 通勤費 | 支給額合計 | ||||
| 12,000 | 312,000 | ||||
| 控除 | 健康保険 | 厚生年金 | 雇用保険 | 社会保険計 | 課税対象額 |
| 16,000 | 29,280 | 1,860 | (47,140) | (252,860) | |
| 所得税 | 住民税 | 控除計 | |||
| 6,640 | 15,000 | 68,780 | |||
| 差引支給額 | 243,320 | ||||
勤務欄
勤怠の欄には、実際にその月働いて賃金が発生した時間や日数が記載されます。
| 勤務日数 | 該当月の実際に労働した日数 |
| 欠勤日数 | 該当月に欠勤した日数 |
| 有給日数 | 有給休暇を取得した日数 |
なお、ここで記載される実績は「締め日」の期間となります。
給与明細に表示される有給残数は、勤怠締め日時点までの残数となります。
給与明細の金額が思っていた金額と差がある場合は、勤怠の項目も確認し、誤って控除されている日や、計算されていない残業時間がないか、確認しておきましょう。
支給欄
会社から支払われる給与のすべてが項目ごとに明記されています。
| 基本給 | 給与計算のベースとなる、固定で支払われる賃金 |
| 残業手当 | 所定労働時間を超えて働いた分の賃金 |
基本給は、昇給や降給がないかぎり、毎月同額が支払われます。
残業手当は、所定労働時間を超えた分の賃金が支払われます。
会社によっては「みなし残業」という賃金制度を適用している会社もあります。
みなし残業は一定の残業時間が発生する想定で支払われる固定賃金のことで、「固定残業手当」とも呼ばれます。
残業手当 = 1時間の単価 × 割増率 × 残業時間
1時間の単価 =(月額給与-各種手当*1)÷ 1か月あたりの平均所定労働時間(*2)
(*1)家族手当や通勤手当など、労働と直接的な関係が薄く、個人的事情に基づいて支払われるものが対象
(*2)1か月あたりの平均所定労働時間 = 年間労働日数 × 所定労働時間 ÷ 12
総支給額から控除されるものとして、以下が挙げられます。
- 社会保険料(健康保険・厚生年金保険・介護保険・雇用保険)
- 所得税
- 住民税
社会保険料や税金は法定控除と呼びます。
これらは、法律で定められている控除項目のため、必ず給与から差し引く必要があります。
また、控除欄にマイナスで金額が記載されている場合は支給の金額となります。
多く控除していたものを返金する際に記載されており、年末調整で出た所得税の還付がその代表例となります。
社会保険料
社会保険料は、狭義の社会保険料(健康保険、厚生年金保険、介護保険)と労働保険料(労災保険と雇用保険)から成ります。
社会保険料は、会社と社員で半額ずつ負担しており、社員負担分の保険料は毎月の給与から天引きされるのです。
また、雇用保険料も給与から毎月天引きされていますが、雇用保険料率は毎年変動し、事業によっても異なります。
労災保険は事業主が全額負担のため、給与に影響しません。
このうち、業務外の怪我や病気に見舞われた際に適用される保険制度が健康保険です。
健康保険料の負担額は以下の計算式で求めることができます。
健康保険料率は、加入している健康保険(協会けんぽ、組合健保)と居住する地域によって異なります。
次に厚生年金保険料は、労働者の老齢や死亡、障害について保険給付を行う制度です。
20歳から60歳までのすべての国民が加入しなければならない国民年金のほか、働いている人は厚生年金保険へ加入し、厚生年金保険料も負担する必要があります。
厚生年金保険料も支払っている人は、老後に支給される金額も厚生年金と国民年金を支払った分だけ増えることになります。
なお、厚生年金保険料には国民年金保険料の分も含まれているため、別々に保険料を支払う必要はありません。厚生年金保険料として国民年金分を含めて毎月給与から天引きされます。
所得税
所得税は、その年の1月1日から12月31日の間に得た所得に対して課税される国税です。
会社員の場合は、源泉徴収という方法により、毎月の給与所得から所得税を概算で算出し、控除されることになります。
毎月の所得税はあくまで概算のため、12月の年末調整で、確定した年収を基に所得税を計算しなおすことになり、差額が還付または追徴されることになります。
住民税
住民税は、社員が住民票のある市町村や、都道府県に納める税金をいいます。
住民税は、前年の所得に応じて、税額が決定し、翌年の6月から支払いが始まります。
すなわち住民税は後払いになっているというわけです。
さいごに
給与明細は本記事で解説したようなポイントさえ押さえておけば、就活生としては十分です。
給与明細を受け取って、「あ~、これはこういう意味で支給されてるんだな。こういう理由で天引きされてるんだ」と、その背景や意味がイメージできれば良いでしょう。
今回も最後までお読みいただき、ありがとうございました。