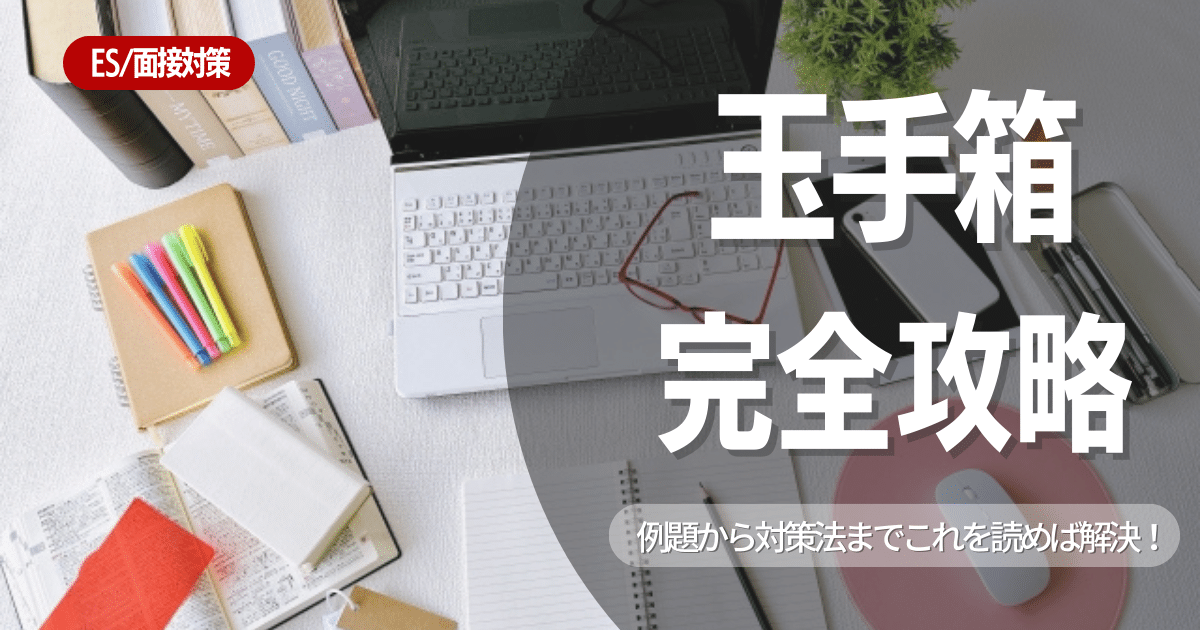玉手箱の言語問題を攻略するコツ3選!勉強方法や例題も紹介
2024年10月10日更新
はじめに
SPIと同じくらいの頻度で実施されることの多いWebテスト「玉手箱」。
テストセンターとは違って自宅で受験できるため、リラックスした気持ちで受けられます。
ただし、きちんと対策をおこなっていなければ、対応できない問題も多いです。安直な気持ちで受けると痛い目にあうことも。問題の種類は限られているので、一つひとつ集中して取り組めば本番までに間に合うでしょう。
今回は、玉手箱の言語問題の特徴を紹介しつつ、コツや対策も解説していきます。
以下のようなお悩みのある学生は必見ですので、ぜひ最後までチェックしてみてください。
- 玉手箱の言語問題の例題を見たい
- 攻略のための勉強法が知りたい
上京を志す地方学生ならジョーカツ!
あなたのキャリアを加速させるチャンス!
無料で利用できる快適な個室シェアハウス、
東京までの交通費サポート付き
首都圏の注目企業への就活ならジョーカツ
首都圏の学生ならスタキャリ!
理想のキャリアを実現へと導く第一歩!
あなたにピッタリのキャリアアドバイザーを選び、
自分にマッチする優良企業をご紹介
首都圏企業のES添削から面接対策まで、就活ならスタキャリ
そもそも玉手箱って?

玉手箱は日本SHL社が実施する適性検査のひとつで、SPIと並んで導入する企業が多いです。
ほかの適性検査との違い
SPIは、リクルートマネジメントソリューションが提供する適性検査です。
SPIは複数の分野の問題が出題されるのに対し、玉手箱では同じ分野の問題しか出題されません。
WEB-CABとWEB-GABは、日本エス・エイチ・エル(SHL社)が提供する適性検査で、CABはエンジニア・プログラマー向け、GABは金融系や商社の試験で用いられることが多いです。
TG-WEBは、ヒューマネージ社が提供する適性検査で、この中でも特に難易度が高いとされています。
玉手箱とSPIのどちらを優先して勉強すべきか知りたい人は、以下の記事を参考にしてください。
問題形式
玉手箱は言語・計数・英語・性格テストの4科目が実施されます。
そこからさらに言語3種類、計数3種類、英語2種類と出題内容が分かれ、それぞれの科目の中から1種類だけ問題が出題されます。
勉強時間と合格ライン
玉手箱で合格を目指すためには、60時間を目安に勉強時間を確保しましょう。
人によってかかる時間はさまざまですが、1〜2ヶ月前から1日あたり1〜2時間コツコツ勉強すれば60時間勉強できるでしょう。
また合格ラインは企業によって違いますが、70〜80%を目標としましょう。
玉手箱の言語問題の特徴
玉手箱の言語問題の特徴は次の通りです。
- 1種類につき復習出題される
- 制限時間が短い
- 問題数が多い
- CAB・GABと似た問題が出題される
難易度の高い問題が出題されるわけではありません。しかし、問題形式や流れを押さえておかなければうまく解答できない可能性があります。それぞれ詳しく見ていきましょう。
1種類につき複数出題される
玉手箱全般に言えることですが、1問目の問題によってその後のパターンが決まります。
たとえば、計数理解で最初の問題が図や表から読み取って解答するものであれば、図表問題が続くでしょう。
長文読解であれば、2問目以降も長文読解です。
のちに解説しますが、言語問題のパターンは3つしかありません。出題形式が多いわけではないため、あらかじめ対策をしておくと安心です。
制限時間が短い
玉手箱の言語問題を含め、設問に対して制限時間が短いです。
論理的読解では、合計32問に対して15分、または52問25分で解答しなければいけません。1問あたり30秒ほどで、とても短いです。
言語問題に限らず、他の設問でも決して余裕のある時間配分ではありません。試験に備えて何度も練習を重ねておく必要があります。
問題数が多い
玉手箱は「素早さ」「正確さ」が求められている問題です。そのため、制限時間のわりに出題数が多い傾向にあります。企業によっては問題数も異なるかもしれませんが、大きく差はないです。
1問1問をじっくり解いている暇はないため、問題と解答パターンをどれだけ身につけているかが勝敗をわけます。
加えて、最後まで集中力を切らさないでやり抜けるのかも重要なポイントです。
問題形式:「論理的読解」「趣旨判定」「趣旨把握」
言語問題の問題形式は下記3パターンです。設問数と時間配分をまとめましたので、よく確認をして対策を立てていきましょう。
| 問題形式 | 設問・時間 |
| 論理的読解 | 32問・15分または52問・25分 |
| 趣旨判定 | 32問・10分 |
| 趣旨把握 | 10問・12分 |
論理的読解は、長文を読み、設問文が論理的に正しいかどうかを判断します。
「設問文の論理性」を問うため、一般常識や自分の意見から正誤を判断するものではありません。また、企業によっては英語での出題もあるそうです。
趣旨判定は、長文を読んで複数の設問に対して適切な選択肢を解答していきます。設問を確認したのちに、該当箇所の文章を読むほうがスムーズに読解できるでしょう。
趣旨把握は、長文を読んだ後に用意されている選択肢から「筆者の訴えにもっとも近いもの」を選ぶ問題です。どの選択肢が正解なのかを吟味するため、趣旨判定と似ている部分があります。
CAB・GABと似た問題が出題される
玉手箱を作成している日本SHL社はCABとGAB形式のテストも作成しています。
そのため、玉手箱でもこれらと似たような問題が出題される傾向にあるのがポイントです。
CABはプログラマーやエンジニア向けの適性試験で、GABは言語・計数から学生の適性を測定する適性検査です。
玉手箱では難しい問題を対策するよりも、1問でも多く解答するためのスピードや効率が求められるでしょう。
玉手箱の言語問題攻略のポイント3選
言語問題を突破するためにはいくつかコツがあります。下記3つは最低限意識してほしいので、この機会にぜひ頭に入れておいてください。

制限時間が限られているのと問題数も多いため、いかに効率よく解答できるかが重要です。上記を意識できると結果にもよい影響をもたらすはず。
すべてに解答する
間違っていてもよいので、すべての設問に解答するのが大切です。時間が足りなくて最後まで解答できない場合もありますが、選択式は選ばなければ得点になりません。
仮に答えがわからなくても、何かしらの選択をしておけば正解になる可能性があります。一方、選択をしなければ得点に結びつく可能性はゼロです。
制限時間が残り少なく、設問にすべて解答できないとわかった段階で、それぞれの解答を選んでいきましょう。
設問を先に読む
何も考えずに長文をそのまま読むと二度手間になる可能性が高いです。
長文を一読しても内容が把握できていないかもしれません。内容を把握できていない状態で設問を読むと、該当箇所をふたたび読まなければなりませんよね。
しかし、設問から先に読めば文章量も少ないので内容把握が容易です。問題意識をもった状態で本文を読めるため、解答も見つけやすいでしょう。
設問が複数ある長文に対しては特に有効なので、覚えておくと時短に繋がりますよ。
一般論で判断しない
長文読解の答えは「長文」にあります。そのため、一般論や自分の意見は通用しません。
たとえば、論理的読解に「現在起きていないこと」「一般論としておかしいこと」があっても「論理的に正しい」なら、正解です。
趣旨把握でも同様に「筆者の訴えている意見」と「一般的な意見」を比べたときに、後者がどれだけ重要でも意味はありません。私情を持ち込まないのがとても大事です。
答えは本文に記されているため、的確に読み解く力が求められます。何度も練習をしていけばコツは掴めてくるので、現段階でしっかりできていなくても大丈夫です。
玉手箱の言語問題で高得点をとるための勉強方法
言語問題の対策に特別な方法はありません。基礎を淡々と積み上げられるかが、合否をわけます。
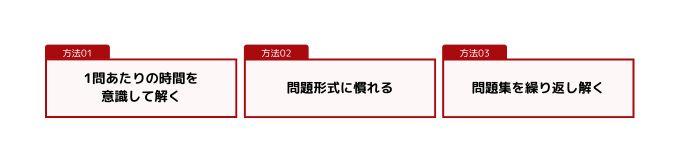
問題形式・設問パターンに慣れておくのも重要な要素です。では、具体的に見ていきましょう。
1問あたりの時間を意識して解く
言語問題は出題数に対して制限時間が短いです。
1問あたりで考えてみると、数十秒で解答しなければいけないものもあります。そのため、時間意識をもって臨まなければ、最後まで解けない可能性も。
まずは制限時間内でどれだけ解答できるかを調べ、次に時間を意識するのがよいです。はじめから時間を意識してもいいですが、焦って正答率が下がるかもしれません。
精度を落とさずスピードをあげていくのが必要です。
問題形式に慣れる
言語問題の3パターンのうち、どれが出題されても対応できるように、問題形式に慣れておくのも重要です。慣れていれば本番で出題されても瞬時に対応できるため、力も発揮しやすいはず。
加えて、選択肢にも慣れておくとよいかと思います。特に、趣旨判定で用意される選択肢「A・B・C」の文言はほぼ変わりないので、事前に把握しておけば時短に繋がるでしょう。
「はじめてみる問題形式・選択肢なのか」「すでに見たことがあるのか」で、解答スピードも大きく変わるため、しっかりと頭の中に入れておいてください。
問題集を繰り返し解く
問題集を反復するのが実はとても大事です。
問題形式・選択肢に慣れるだけではなく、言語問題に適した思考パターンができあがります。
そうすることで、言語問題に対応がしやすくなりますし、問題の解くスピードも向上するでしょう。
同じ問題集を反復し、余裕があれば違う問題集を解いてみるのもいいかもしれません。過去問を試し、実際にどのくらい解けるかを確認するのもおすすめです。
玉手箱の言語問題の例題
玉手箱の形式や勉強方法について理解できたところで、以下では玉手箱で実際に出題された言語問題を見てみましょう。
実際の問題をチェックして本番でどのように解くべきかイメージしながら読み進めてください。
論理的読解(GAB形式)
問題
以下の文章を読んで、設問1つ1つについてA・B・Cのいずれに当てはまるか答えなさい。
A. 本文から論理的に考えて、設問文は明らかに正しい
B. 本文から論理的に考えて、設問文は明らかに間違っている
C. 本文だけでは、設問文が正しいか間違っているかは判断できない
「日本ではデモクラシーの道幅が如何にもせまい。それをひろげる為に、日本にはよその国と違った強い強い前進的な勢力の結集が必要である。それは民主的な人を民主的に生かす為ばかりでなく、ファシストになりたくない人をファシズムから守る為にも必要である。すべての人は生きる権利がある。このことは、すべての人が人間として生きる権利があることにほかならない。そして人間として生きる権利を守ろうとする時、これまでの文化人と勤労者の間に偏見的に置かれた差別は当然消えてしまう。どんな文化人が物価七割の値上げから自由であろう。専門で分れ、文化面、生産面という活動場面で細分されている人民層である間は、抑圧とすべての形での非人間的圧迫に堪える力が弱い。このことは、人民よりも支配者たちがよく知っている。現に労働法の改悪は、日本の労働組合の分裂作業が効果を現わしてからでなければ、とりあげない方がよいと日本の役人が言明している。
文化の為にでも他の生産の為にでも、働いているものは人間的な働きの条件を求める心から、社会が合理的に発展してゆくことを現実的に要求している。戦争で最も大きい傷をうけた日本のすべての女性、職場と家庭の間でますます苦しい立場にいるすべてのまじめな婦人は、世界のどの国の婦人に劣らず、燃える思いを心の中に持っている。そして、一寸見ると近代的に分化しているようでも実は封建的なギルドに陥り、ファシズムに対する抵抗力の弱められている自分たちの状態をそれらの人は急速に克服しようとしている。」
宮本百合子 「前進的な勢力の結集」
問1:前進的な勢力を結集するとファシズムが促進される。
問2:文化人と勤労者の間に偏見的に置かれた差別があると非人間的圧迫に堪える力が弱くなる。
問3:支配者の立場からすると、労働組合が一致団結しているときは労働法の改悪はやりづらい。
問4:日本以外の国の婦人はファシズムに対する抵抗力が弱い。
解答
問1:前進的な勢力を結集するとファシズムが促進される。
答:B. 本文から論理的に考えて、設問文は明らかに間違っている
問2:文化人と勤労者の間に偏見的に置かれた差別があると非人間的圧迫に堪える力が弱くなる。
答:A. 本文から論理的に考えて、設問文は明らかに正しい
問3:支配者の立場からすると、労働組合が一致団結しているときは労働法の改悪はやりづらい。
答:A. 本文から論理的に考えて、設問文は明らかに正しい
問4:日本以外の国の婦人はファシズムに対する抵抗力が弱い。
答:C. 本文だけでは、設問文が正しいか間違っているかは判断できない
趣旨判定(IMAGES形式)
問題
以下の文章を読んで、設問1つ1つについてA・B・Cのいずれに当てはまるか答えなさい。
A. 筆者が一番訴えたいこと(趣旨)が述べられている
B. 本文に書かれているが、一番訴えたいことではない
C. この本文とは関係ないことが書かれている
「問題解決力は、社会生活において必要となる汎用的な資質・能力の一つに位置づけられ、近年では国際的にも重視されている人間の能力の一つである。我が国においても、初等教育からこのような汎用的能力を育成するための検討が、実際に始められている。
現代の諸課題に対応する問題解決力を向上させるために、理数教育と主体的な問題解決力育成のための教育を、初等教育から企業内教育まで一層充実させることが求められるようになった。ここでいう問題解決とは、経験や勘に頼ることなく、データ(事実)に基づく、いわゆる統計的な問題解決を基盤とするものである。このような問題解決力は,学校教育をはじめとするできるだけ早期からの育成が必要であり,このための方法を確立することが急務である。
加えて、問題解決を行う際、その目的設定が大切である。 設定する目的によって、問題解決により実現する姿も、それを受け取る人々の満足も、別次元のものとなるためである。」
山下 雅代「問題解決への目的設定とその解決プロセスの教育に関する研究」
問1. 問題解決力を向上させるためには、できるだけ早期からの育成が必要不可欠である。
問2. 日本では社会生活で必要となる問題解決力の育成を初等教育から実施するための検討がおこなわれている。
問3. ここで言う問題解決力とは、データに基づく統計力であり経験や勘に頼る憶測ではない。
問4. 問題と目的は相対関係にあるが、問題を解決しようとする際には、目標を立てる相互性も備えている。
解答
問1. 問題解決力を向上させるためには、できるだけ早期からの育成が必要不可欠である。
答:A. 筆者が一番訴えたいこと(趣旨)が述べられている
問2. 日本では社会生活で必要となる問題解決力の育成を初等教育から実施するための検討がおこなわれている。
答:B. 本文に書かれているが、一番訴えたいことではない
問3. 問題解決力とは、データに基づく統計力であり経験や勘に頼る憶測ではない。
答:B. 本文に書かれているが、一番訴えたいことではない
問4. 問題と目的は相対関係にあるが、問題を解決しようとする際には、目標を立てる相互性も備えている。
答:C. この本文とは関係ないことが書かれている
趣旨把握
問題
次の文章を読んで、筆者の訴えに最も近いものを選択肢の中から一つ選びなさい。
「Z 世代は他の世代と比べてどのような特徴を持っているのだろうか。William et al.(2010)は、Z 世代は最も新しい世代であると指摘している。2009 年時点において、Z 世代の最も年長者でも 15 歳であり、そのため、この世代を完全に定義できないと述べている。ただし、いくつかの世代的特徴の指摘はされている。特に、「仲間からの受容(peeracceptance)」が Z 世代にとって非常に重要であるという。その影響は髪型や服装の選択などのスタイルに広く見られるという。加えて、SNS が友人関係をより密にするだろうと指摘している(William et al., 2010)。
日本においても、児美川(2013)が若者における仲間との関係について類似した傾向を指摘している。児美川(2013)は、その当時の 20 代の若者を想定し、現代の若者の消費行動について言及している。日本における若者は「失われた 20 年」と呼ばれるバブル崩壊後の低成長時代に幼少期を過ごしており、それが、それ以前の世代との価値観に違いを生んでいる可能性に言及している。また、若者の他者との関わりについては、「仲間への『気遣い』と、場の『空気を読む』ことに細心の注意を払わざるをえない」状況にあり、「仲間内での『承認』を得ることがすべてに優先」し、「そこで『目立ちたい』とするような発想は育ちにくかった」と指摘している。
William et al.(2010)で触れられていた SNS の影響に関連して、Ordun(2015)も若年層ほどインターネットやソーシャルメディアの影響を受けていることに言及している。特に、X 世代やベビーブーマーと比較して若年層の方が SNS のアカウント保有率が高いことを指摘している。Ordun(2015)はこれらを Y 世代の特徴として指摘しているものの、Ordun(2015)における Y 世代は出生年の範囲が広く、William et al.(2010)における Z世代の出生年と一部が重複している。そのため、Ordun(2015)の指摘は Z 世代の特徴とも言える。」
松本 大吾「Z 世代の特徴」
A. Z世代とは1990年代後半から2012年までに生まれた若年層を指し、1981年頃から1990年台後半頃までに生まれた前の世代をY世代と呼ぶ。
B. ソーシャルネットワークメディアの普及は若年層だけでなく、ビジネス面でも注目されており近年ではTiktokなど短尺動画のSNSが注目を集めている。
C. Z世代ではSNS上でどう思われるかよりも、仲間内での受容を強く意識する傾向があるので「気遣い」や「空気を読む」ことが重要である。
D. 承認欲求が強いZ世代は、現実の身近にいる仲間よりSNSや多くの人から称賛される発信者を目指す傾向が強い。
解答
答:C. Z世代ではSNS上でどう思われるかよりも、仲間内での受容を強く意識する傾向があるので「気遣い」や「空気を読む」ことが重要である。
玉手箱の例題をもっと見たい方は、以下の記事もどうぞ。
玉手箱の言語問題に関するよくある質問
最後に、玉手箱の言語問題に関するよくある質問とその答えをまとめました。
- 趣旨判定の言語「B」と「C」の違いってなに?
- 合格ラインは何割くらい?
- 言語問題の注意点ってある?
- 言語問題の注意点ってある?
では、それぞれ具体的に見ていきましょう。
趣旨判定の言語「B」と「C」の違いってなに?
まずはそれぞれの選択肢の意味からおさらいしていきましょう。次をご覧ください。
B:文中で述べられているが、筆者の趣旨ではない
C:本文とは関係ないことが述べられている
上記2つの違いは「関係があるかどうか」です。
「B」の選択肢は、本文と関係はありますが、筆者が訴えたいことではありません。
「C」の選択肢は、本文とはまったく関係ないため、もっとも重要ではないです。
設問に対して解答する選択肢が異なるので、両者の違いをよく整理しておいてください。
合格ラインは何割くらい?
合格ラインは企業によっても異なるため、厳密に発表されているわけではないです。競争率が高い・大手企業などは6〜8割の場合もあります。
一般的な目安としては、まず5〜6割を目指しておくのがよいでしょう。練習テストなどで5割以下なら、早急の対応が必要です。
加えて「どういった問題が苦手なのか」を把握しておくと、効率よく点数を伸ばせます。苦手な問題を重点的に対策すれば点数も大きく変わるため、現状が低くても安心してください。
言語問題の注意点ってある?
注意点を下記にまとめました。
- 次の問いへ移ると戻れない
- 確実に解くのを目標にしない
一度次へ進むと後戻りができないため、限られた時間で選択していかなければいけません。どうしても解答がわからない場合でも、その場で選んで次に進むのが大切です。
正答率のキープを意識し過ぎると、1問ごとの時間配分が崩れていきます。制限時間が短いため、もたもたしていると最後まで解けません。いずれにせよ正答率が落ちてしまうでしょう。
もちろん、正確に解答していくのも重要ですが、まずは「すべてに解答する」を目標にしてください。
玉手箱の見分け方は?
玉手箱を実施しているかどうかは、事前にネットで検索してみてください。
もし情報がない場合は企業から送られてくるテストURLをチェックしてみましょう。
以下のようなURLが含まれていれば、玉手箱の問題となります。
- e-exams.jp/
- e-exams2.jp/
- e-exams4.jp/
さいごに
今回は玉手箱の特徴や高得点をとるための勉強法、攻略のポイントについて解説しました。
玉手箱の言語問題はきちんと対策を練っていれば対応できるものばかりです。
問題形式・選択肢に見慣れないため、はじめは苦労するかもしれません。
しかし、何度も練習を重ねていくことで着実によくなります。
一冊問題集を買ってそれをひたすら解いていくなど、地道な努力によって言語問題攻略の扉は開かれます。
玉手箱やSPIなどのテストは就活の中ではほんの一部に過ぎませんが、大事な将来を決める通過点です。
ここでの努力が未来の自分を導くため、入念な対策を忘れないでやっていきましょう。