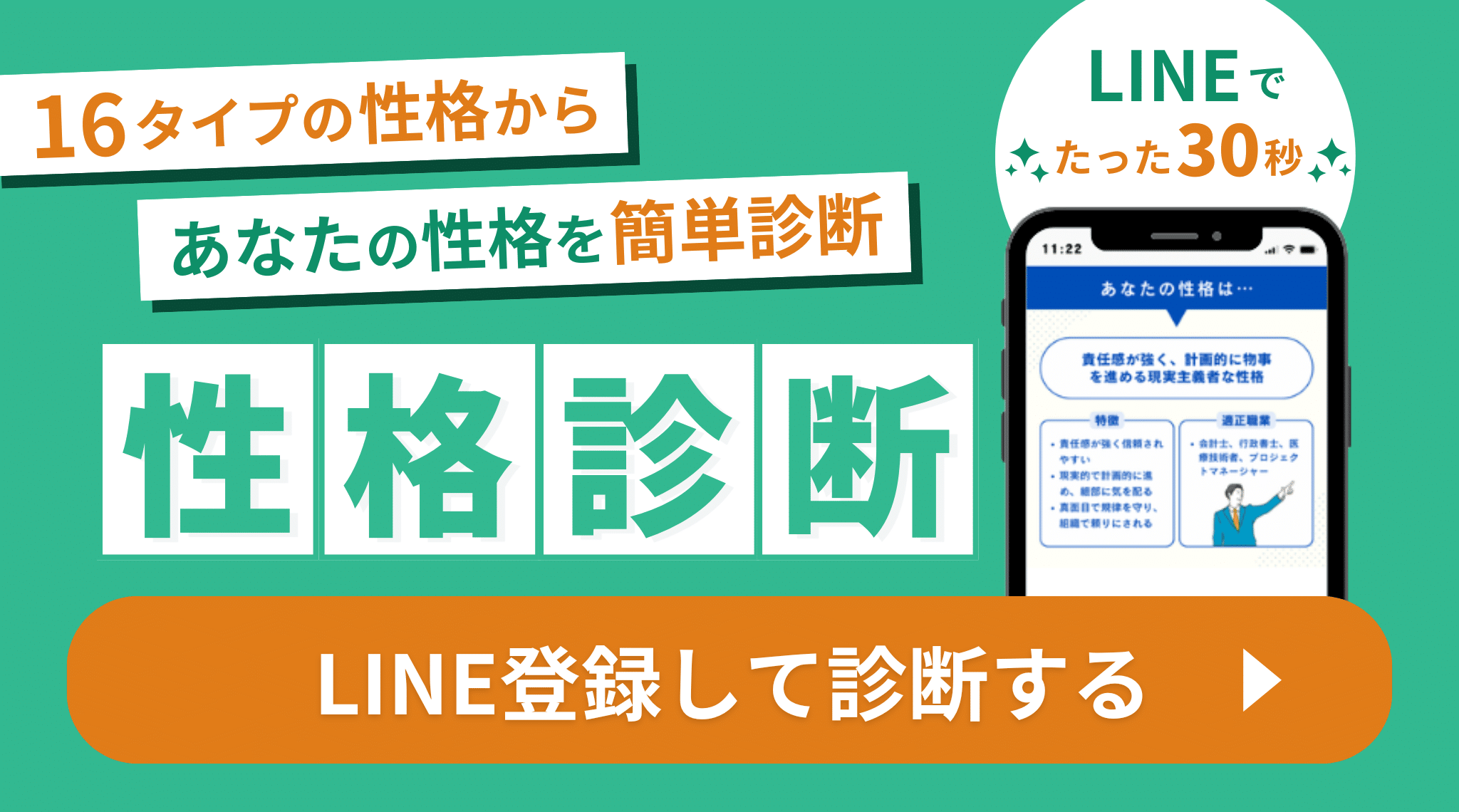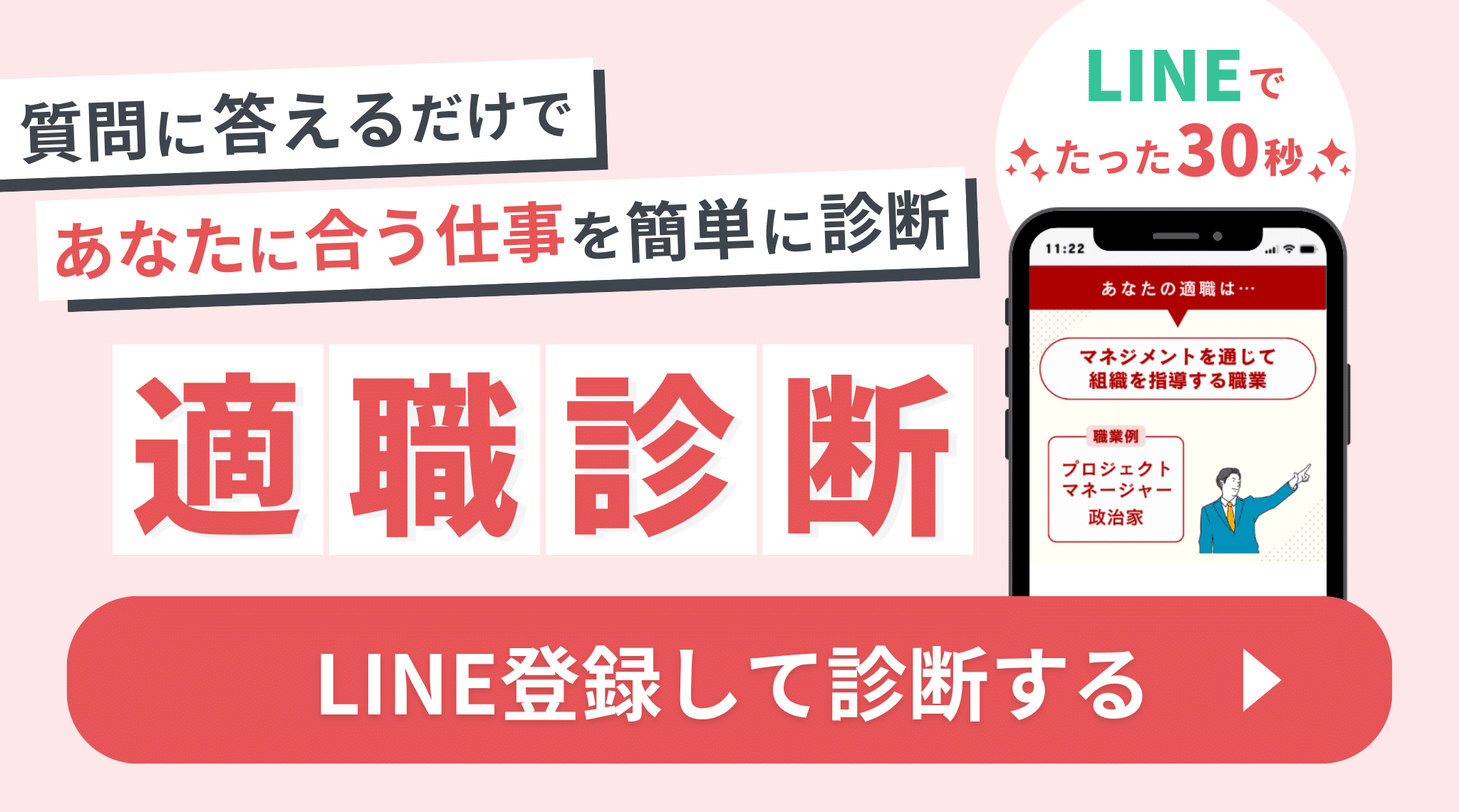【高卒者向け】就活スケジュールとオススメ業界解説!
2024/9/1更新
はじめに
高卒者向けの就職活動のスケジュールは、行政・経済団体(採用する企業)・高校の三者で結ばれている厳密なルールがあります。企業はこのルールに沿った採用活動を行わなければいけません。
そこで今回は高卒の就活について、そもそものスケジュールやルールについてご紹介します。
- 高卒で就活する際のスケジュール
- 高卒で就職するメリット・デメリット
- 高卒で就職する場合におすすめの業界
- 高卒での就職を成功させるポイントと注意点
就活について早めに知識を得ておくことで不安も少なくなるでしょう。
高卒で就職を検討されている方、今回の記事をぜひ参考にして悔いのない就職活動を送ってください。
そもそも高卒の就活はいつから?

高卒者向けの就職活動がスタートするのは3年生の7月頃です。夏休みが始まる1学期の終わりに採用を予定している各企業からの求人票が各高校に公開され、就職活動がスタートします。
7月が本格的なスタートですが、それより前にしっかり準備をするのがおすすめです。以下、高卒者向けの就活スケジュール・流れについて紹介します。
高卒の就活スケジュール・流れ
高卒の就活スケジュールは以下の通りです。
- 4〜6月 興味のある企業のリサーチ
- 7〜9月 三者面談・職場見学
- 9月初旬 履歴書の提出・試験・面接対策
- 9月中旬 入社試験スタート
- 10月 2次募集スタート
高校の種類や都道府県によって若干の違いはありますが、共通事項は多いので流れをここで把握しておきましょう。
以下、それぞれ詳細をみていきます。
4〜6月|興味のある企業のリサーチ
本格的な就職活動のスタートは高校3年時の7月1日に行われる全国一斉の求人票の公開からです。それより以前の4月から6月の間に、興味のある会社や業界について調べておくことが必要です。
進路指導の先生やOBOGの先輩たちなどのアドバイスを受けながら、自身が就職先を選ぶうえでの優先すべきポイントを見つけましょう。そのうえで求人票を確認して、興味・関心のある企業をいくつかピックアップし、応募の候補にあげます。
地元にはどんな会社があるか、自分にあっている仕事は何か、企業研究と合わせて自己分析もこの時期にしっかり行うことをおすすめします。
「自分は何ができるのか?」「自分はどんなことをしたいのか?」といったことを企業の求人票を見ながら、同時に自己分析もします。自己分析は自分自身で振り返ることも重要ですが、進路指導の先生や保護者と一緒にすすめ、他己評価を受けながら一緒に取り組みましょう。
7〜9月|三者面談・職場見学
7月1日から求人票が公開され、就職活動の本格的なスタートです。この時期から担任の先生(進路指導の先生)・保護者との、三者面談がはじまり、自分の就職先を決めていきます。自分がどのような仕事に就きたいか、先生や保護者へ伝え、応募先の絞り込みをすすめましょう。
また、この時期より応募前の職場見学もスタートします。この見学が高校生が行うことができる唯一の直接的な企業研究の場です。
自分が行きたい会社の実際の職場を見学して働くイメージを固めます。実際の職場を見学することで雰囲気を知り、求人票や会社案内だけでは得られない情報をたくさん収集しましょう。
9月初旬|履歴書の提出・試験・面接対策
8月中旬から実施される学校内での選考を経て、8月下旬に応募する会社・企業を1社に決めます。この際、進路指導の教員や担任、保護者としっかり相談して、応募先を決定しましょう。高卒での就活では一人一社の応募がルールなので悔いのない選択が必要です。
9月初旬に履歴書の提出が始まります。履歴書に記入する志望動機には自分の熱意などを込め、さらに試験対策、面接対策などを行っていきます。
9月中旬|入社試験スタート
9月中旬から入社試験が始まります。試験はすべての会社で実施される面接試験の他にも筆記試験、小論文が出題されるところもあり、企業によって様々です。先輩の体験や進路指導の教員から対策方法などをしっかり聞いて本番で実力を発揮できるように準備をおこなっていきましょう。
試験の結果は試験日より約1週間程度で、学校へ採用可否の連絡があります。
10月|2次募集スタート
9月の入社試験で内定が出なかった場合、10月以降にも多くの企業が募集を継続します。(2次募集が10月よりスタート)2次募集用の合同就職説明会などを実施する自治体などもあり、積極的に参加し会社を選ぶことをおすすめします。
10月以降は、一人二社まで応募することが可能です。
高卒で就職するメリット・デメリット

高卒で就職するメリット・デメリットは以下の通りです。
- 高校からの支援が手厚い
- 大卒より早く自立できる
- 大卒よりも多くの経験を積み、スキルを獲得できる
- 生涯賃金が大卒より低くなる可能性がある
- 企業によっては大卒より昇進しにくいケースも
良い面と悪い面を把握することで、内定獲得につながる効果的な対策ができるため、しっかり内容に目を通していってください。
メリット:高校からの支援が手厚い
厚生労働省の調査によると、在学中に就活を実施し、2024年3月高校を卒業した方の就職率は「99.2%」でした。
また過去10年間でも同様に99%を下回ることがなく、継続的に高水準を維持。
理由としては以下の内容が考えられます。
- 高校生の就職活動は、所属する高校からの推薦をうけて応募する「学校斡旋」という形が一般的で、基本的に1人1社のみの選考参加が可能というルールがある。
- それ故、高校からの就活支援が手厚い。
高校卒業後すぐに就職する場合は、大卒で就職する場合より内定にたどり着きやすいといえるでしょう。
メリット:大卒より早く自立できる
大学生が卒業するタイミングで、高卒で就職した方は「4年間」もの社会人経験を先に積むことができます。
そのためアルバイトで生活する方に比べ金銭面で余裕が生まれ、生活を豊かにすることが可能に。
また4年間も働いていれば企業によっては「昇進」も考えられ、組織を統括するリーダーになっていることも十分に考えられるでしょう。
そのため高卒で就職して働くことは、経済面・精神面の両方で「自立」を促します。
メリット:早い段階で多くの経験を積み、スキルを獲得できる
大学生の多くは在学中に「アルバイト」を通して企業で働く経験をするケースが大半ですが、その期間で高卒就職者は「正社員」として週5日かけて働きます。
そして正社員で働くことは「企業に利益をもたらす」必要が生まれるため、戦力として責任ある仕事を任せてもらえます。
ビジネスシーンで使えるスキルの獲得は「実際に経験すること」で養うことができますが、高卒で就職し、努力することで若くして高度なスキルを獲得することができるでしょう。
デメリット:生涯賃金が大卒より低くなる可能性がある
「独立行政法人労働政策研究・研修機構」の調査によると、正社員として60歳までフルタイムで働いた場合の賃金は以下の通りでした。
性別・最終学歴別の生涯賃金
| 性別/最終学歴 | 高卒 | 大卒・大学院卒 |
| 男性 | 2億600万円 | 2億6,190万円 |
| 女性 | 1億4,960万円 | 2億1,240万円 |
特に女性で大きく乖離しています。
所属する企業によって生涯賃金は大きく異なるものの、平均的には高卒と大卒で差が生まれることが多いといえるでしょう。
デメリット:企業によっては大卒より昇進しにくいケースも
学歴を重視する企業の場合は、実力を問わず最終学歴が高卒の社員よりも大卒の社員が先に昇進するケースがあります。
そのため志望企業が学歴重視か、実力主義かをあらかじめ把握することはとても重要です。
高卒就職におすすめの業界
続いて、高卒就職におすすめの業界を紹介します。
以下2つの業界がおすすめです。
- 建設業界
- IT業界
それぞれ、なぜ高卒就職におすすめなのか、詳しくみていきましょう
建設業界
建設業界は人手不足が深刻な業界のひとつです。特に現場職は学歴よりも若さや体力などが重視されることも多く、高卒向け求人が多くあります。
未経験者でも働きながら技術やスキルを身に着けることができやすく、実力次第で昇進も可能です。特にモノづくりが好きな人にとって、やりがいのある業界と言えるでしょう。
建設業界は現場職以外にも、事務職や管理職などがあります。事務職では材料費や人件費などの予算の管理を行ったり、管理職だと工事の施工計画を作成・安全管理のマネジメントなどを担います。
肉体労働のイメージが強い業界ですが、体力・筋力の他にもコミュニケーション能力も必要な職場です。建設業界では若手からベテランまで幅広い年代が働いています。様々な人とのチームワークが求められます。
高卒で採用され若いうちから技術を身につけること建築・土木の業界で長期的に活躍できることも可能です。
建設業界については下以下の記事で具体的に解説しているため、気になる方は目を通してみてください。
IT業界
IT業界も人手不足の業界のひとつ。エンジニアやプログラマーといったIT関連職も高卒者の就職におすすめです。IT業界は人材育成に力をいれており、働きながら技術・スキルを身につけることができるでしょう。
業界自体も急成長をしており、事業拡大に伴って、採用人数も多く高卒者の採用にも積極的です。
IT業界も事業内容は幅広く、インターネット・WEB業界、ハードウエア業界、ソフトウエア業界などさまざまです。それぞれの業界で習得できるスキルもことなっています。若いうちにスキルを身につけてキャリアアップできるのもIT業界の特徴です。
日々、働きながら学び、自己成長できる分野と言えるでしょう。
なお、IT業界についても別記事で解説しているため気になる方はぜひ読んでみてください。
高卒の就活を成功させるには夏休みの時期が重要

高卒での就活を成功させるには、夏休みの過ごし方がとても重要です。1学期の終了頃の7月1日に求人票が公開され、職場訪問をして自分がいきたい会社・業界を検討します。応募する企業は高卒者の採用の場合は1人1社なので、自分にあった企業を考えていきましょう。
夏休みの間に企業研究と自己分析を行います。また、応募する企業を絞りつつ、採用試験対策(筆記試験・面接)も同時並行で取り組まなければいけません。
保護者や担任、進路指導の教員とも相談しながら自分の将来について夏休みの間にじっくり考え、対策を行います。就活の成功のポイントは「夏休みをどれだけ有効活用できたかどうか」が鍵になってくると言えるでしょう。
高卒で就活をする際の注意点
高卒での就職は大卒の就職スケジュール・ルールと異なっています。ここでは、高卒で就活する際の注意点について紹介します。
- 高卒での就活では一人一社までしか受けられない
- 指定校求人に応募する場合は覚悟が必要
それぞれ詳しく、内容を見ていきましょう。
高卒での就活は一人一社までしか受けられない
高卒の就活の特徴の一つとして、一人一社までしか受けられないという点があげられます。
現在、高校生の就職活動は、高校からの推薦をうけて応募する「学校斡旋」という形が一般的になっています。
この学校斡旋を受けての就職が「一人一社制」を採用しているのです。
この一人一社制は毎年、都道府県ごとに学校・行政・経済団体が協議しルールを決めています。
学校が生徒の就職活動をサポートして企業・行政と連携でき、マッチングがすすむという点でメリットがあります。
一方、学校の推薦がないと行きたい会社があっても応募することさえ叶わないというデメリットもあるのです。
ちなみに10月以降の2次募集の際は多くの都道府県で1人2社以上の応募が認められています。(多くは2社まで)
指定校求人に応募する場合は覚悟が必要
高卒者採用で、特定の高校に対して、求人をだす方式として、指定校求人があります。
特定の学校のみの求人となるので、企業と学校との間に信頼関係が築きやすく、学校側としては継続的に生徒を採用してもらえるといったメリットがあるのです。
企業側も、求める人材や社風などを理解したうえで生徒を推薦してもらえます。生徒としても同じ高校の先輩が多く在籍しており、心強いです。
一方、採用されたあとの勤務状況などが悪かった場合、今後卒業した高校に指定校求人がなくなる可能性があります。
後輩や高校に迷惑をかけてしまうこともあるので、応募する際にはある程度の覚悟が必要となるでしょう。
さいごに
今回は高卒での就活・就職について詳しく解説してきましたが、いかがでしたか?
この記事の内容を簡単にまとめます。
- 高卒で就職する場合は、高校3年生の7月頃から就職活動を開始するのが一般的。
- 7月以降のスケジュールは大まかに決まっている。
- 高卒で就職するメリットは「高校からの支援が手厚い」「大卒より早く自立できる」「大卒よりも多くの経験を積み、スキルを獲得できる」の3点。
- 対して高卒で就職する主なデメリット「生涯賃金が大卒より低くなる可能性がある」「企業によっては大卒より昇進しにくいケースがある」の2点。
- 高卒就職におすすめの業界は建設・IT。
- 高卒就職の場合は大卒と異なり、基本的に「1人1社」選考に参加が可能。
高卒の就活は9月初旬に応募がはじまり、9月中旬に入社試験が行われます。
高校生の就活は学校の進路指導の教員や担任、保護者のサポートを受けながら、夏休みにじっくり進路選択のための自己分析を行い、求人票から、職場訪問などを実施し企業研究をすすめます。あわせて筆記試験対策・面接対策などにも取り組むなど、夏休みの過ごし方がとても重要です。
高卒の就職活動は、短期決戦です。今回の記事を参考に、早めに準備をして自分にあった就職先をみつけ、悔いのない就職活動を送ってください。
なお高卒就職でも経歴に関係なく昇進したい場合は「実力主義」の企業を選ぶ必要がありますが、企業の分析については下記で解説しているためぜひ目を通してみてください。