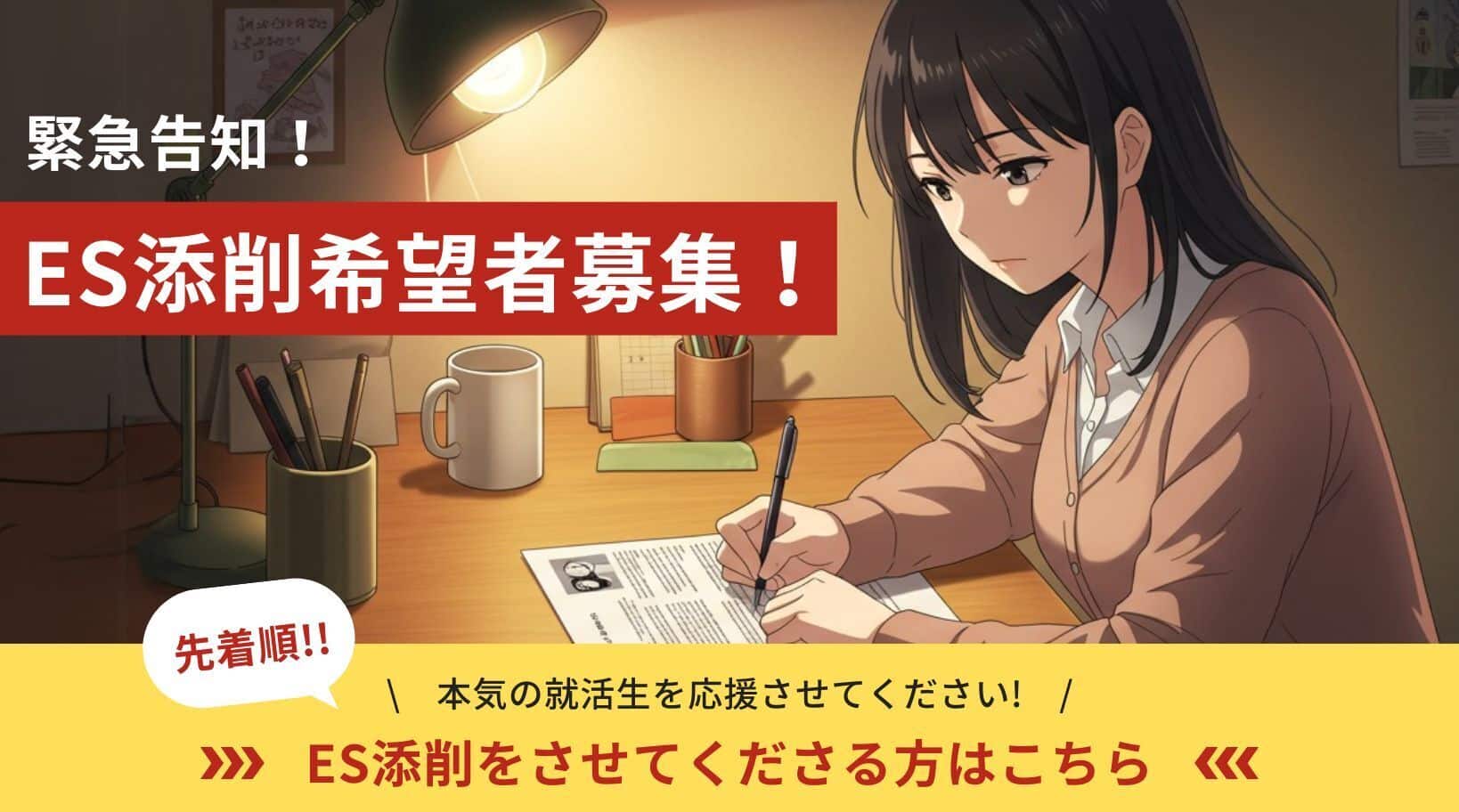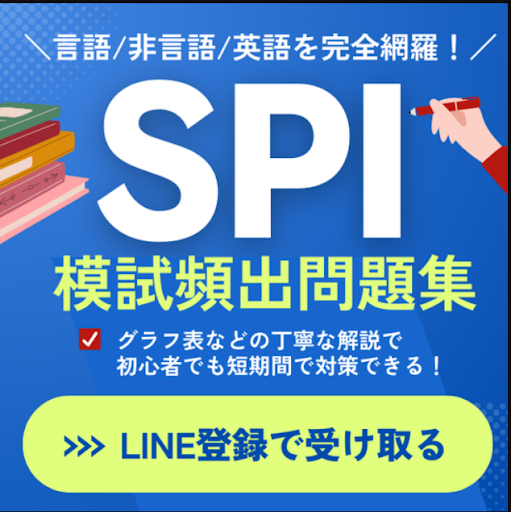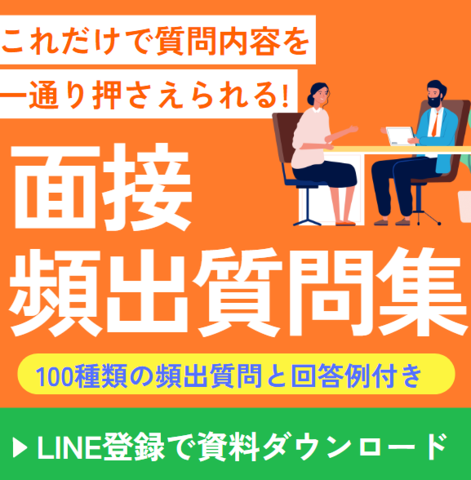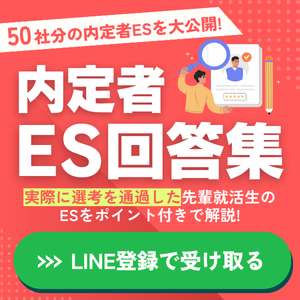インフラ業界の就活攻略法!業界の概要や志望動機のコツを解説
2025/2/5更新
はじめに
インフラ業界は就活生から人気のある業界のひとつです。
業界の安定性や年収の高さ、ワークライフバランスの取りやすさなど魅力が満載な業界ですが、その分ライバルも多く就活難易度が高いのも事実。
そこで本記事では、インフラ業界を目指す学生に向けた業界の概要や動向、メリット・デメリット、志望動機の書き方について徹底解説します。
インフラ業界を目指すものの「どうやってライバルと差別化した志望動機を作ればいいのか分からない」という方は、ぜひ参考にしてください。
インフラ業界とは?
インフラとは基盤という意味である「infrastructure」の略で、インフラ業界とは、人々の社会基盤を支えるサービスを提供する業界を指します。
インフラ業界は生活インフラと交通インフラに分かれています。
- 電力
- ガス
- 石油
- 通信
などの生活に直接関わるインフラであり、これが無ければ、多くの人々の生活に支障が出てしまいます。
- 鉄道
- 高速道路
- 物流
- 海運
などの業態を指し、これらも我々の生活に密接に関わっています。
各業界の主要企業
以下では各業界の大手企業を表にまとめたので、ぜひ参考にしてください。
| 電気業界 | 東京電力ホールディングス 関西電力株式会社 中部電力株式会社 |
| ガス業界 | 東京ガス 大阪ガス 東邦ガス |
| 石油業界 | ENEOSホールディングス 出光興産株式会社 コスモエネルギーホールディングス |
| 通信業界 | 日本電信電話株式会社 ソフトバンクグループ KDDI株式会社 |
| 鉄道業界 | 小田急遠鉄 京急電鉄 東急電鉄 |
| 物流業界 | ヤマトホールディングス 日本郵便 日本通運 |
| 海運業界 | 日本郵船 MOL KLINE |
業界全体が安定している
インフラ業界は人々の生活に密接に関わるので、もともとは国が運営していた会社(NTTやJRなど)も多くあります。そのため、他業界と比べて、ある程度独占が許容されているという特徴があります。
また大規模な工場などの資産が無ければ事業ができないので、参入障壁が高く、新規で参入する企業が少ないです。
これらの理由から、比較的競争性が低いので、インフラ業界は安定しています。
以下表にはNTTグループの営業収益の推移を示していますが、営業収益は堅調であり、コロナショックのあった2020年度においても、売上は安定していることが分かります。
| 年度 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 営業収益 (兆円) | 11.5 | 11.4 | 11.8 | 11.9 | 11.9 | 11.9 |
このように、業界自体が非常に安定しているので、長期的に働き続けたい方にはおすすめの業界です。
インフラ業界の就職難易度
インフラ業界の就職難易度は「高い」です。
というのも、先述の通りインフラは業界全体が安定しており就活生からの人気も非常に高い業界です。
業界は常に一定の需要があり、都市開発や公共事業のプロジェクトが多い場合は募集人数が増える可能性もあります。
インフラ業界のメリット・デメリット
次にインフラ業界のメリットとデメリットについて解説します。就活を進めるうえで、良い面・悪い面を把握しておくことで、入社後のギャップを少なくできるので、ぜひ参考にしてみてください。
メリット
インフラ業界のメリットは以下の2つです。
- 年収が高い
- ワークライフバランスが取りやすい
ひとつずつ解説していきます。
年収が高い
インフラ業界は他業界に比べて、年収が高い傾向にあります。
その理由は、インフラ業界への参入障壁が高いので、ライバルが少なく、安定した収益が見込まれるからです。
2019年の国税庁の調査では、最も平均年収の高かった業種は、インフラ業界である電気・ガス・熱供給・水道業であると報告されています。
| 業種 | 平均年収(単位:万円) |
| 電気・ガス・熱供給・水道業 | 824.2 |
| 金融業、保険業 | 627.0 |
| 情報通信業 | 598.5 |
| 学術研究、専門・技術サービス業、教育、学習支援業 | 517.5 |
| 製造業 | 513.0 |
| 建設業 | 490.6 |
| 運輸業、郵便業 | 435.5 |
| 不動産業、物品賃貸業 | 423.6 |
| 複合サービス事業 | 411.0 |
| 医療、福祉 | 400.8 |
| 卸売業、小売業 | 375.9 |
| サービス業 | 359.0 |
| 農林水産・鉱業 | 296.9 |
| 宿泊業、飲食サービス業 | 259.6 |
安定して高収入を得たい方にとって、インフラ業界はおすすめです。
ワークライフバランスが取りやすい
高年収である理由と近いですが、業界自体が安定しており、仕事内容も他業界に比べ、変動することが少ないため、比較的ワークライフバランスが取りやすいことも大きなメリットのひとつです。
仕事内容の変動が少ない理由としては、新規サービスを提供するよりも、社会基盤を安定して提供することが、インフラ業界に最も求められていることだからです。
厚生労働省が、平成27年に1週間の就業時間が60時間以上の雇用者の割合を業種別に調査したところ、電気・ガス・熱供給・水道業の割合はわずか3.6%であり、全業種中で上位3番目の結果でした。
| 業種 | 1週間の就業時間が60時間以上の雇用者の割合(%) |
| 電気・ガス・熱供給・水道業 | 3.6 |
| 医療・福祉 | 3.4 |
| 複合サービス業 | 3.4 |
| 金融業、保険業 | 5.5 |
| 製造業 | 7.0 |
| 不動産業、物品賃貸業 | 8.6 |
| 生活関連サービス業、娯楽業 | 8.8 |
| 学術研究、専門・技術サービス業 | 9.2 |
| 情報通信業 | 9.2 |
| 宿泊業、飲食サービス業 | 9.2 |
| 教育、学習支援業 | 11.2 |
| 建設業 | 11.5 |
| 運輸業、郵便業 | 18.3 |
このように、他業種に比べ、残業時間も少ないため、プライベートの時間を確保したい方におすすめの業界です。
デメリット
インフラ業界のデメリットは以下の2つです。
- リモートワークに向いていないことが多い
- 新規事業が少ない
順番に解説していきます。
リモートワークに向いていないことが多い
インフラ業界は、NTTやJRなどのように、もともと国営の企業も多く、比較的古い社風であることが多いです。
またインフラ業界でのトラブルは国民の生活に直結するため、緊急性が高く、現場で突発対応をしないといけないこともしばしばあります。
そのため、リモートワークの導入率が比較的低い傾向にあることは、デメリットのひとつと言えるでしょう。
総務省の業種別のリモートワーク実施率調査によると、電気・ガス・熱供給・水道業の実施率は28.4%で、情報通信業の55.7%に比べ、かなり低い水準となっています。
どのような部署に配属されるかにもよりますが、リモートワーク中心の働き方を希望する方には向いていないかもしれません。
新規事業が少ない
インフラ業界の第一の使命は、エネルギーや通信などの社会基盤の安定供給です。
そのため、設備のメンテナンスや、トラブル対応などがメインの仕事となり、新規事業を進める機会は、他業種に比べ少ないという特徴があります。
ベンチャーなどのように、新技術や革新的なサービスの開発を希望している方には、物足りなく感じてしまう可能性があるので、しっかりと自分に向いているか自己分析をすることをおすすめします。
インフラ業界に入社するための志望動機を書くポイント

インフラ業界は就活生の中でも人気の業界なので、就職するためには、志望動機をしっかりと固めておく必要があります。
今回はインフラ業界の志望動機を作るうえで、特に重要な3つのポイントを解説しますので、ぜひ参考にしてみてください。
具体的には以下の3つです。
- なぜその業界にしたのか
- なぜその企業にしたのか
- どのように企業に貢献していきたいか
順番に解説していきます。
なぜその業界にしたのか
なぜその業界にしたのかということをしっかりと言語化するようにしましょう。
企業は就活において、就活生がどの程度自社に対して、入社の熱意があるかどうかを見ており、その熱意を確認するための方法として志望動機があります。
この志望動機が曖昧では、企業に熱意を伝えることができないため、しっかりと言語化しておく必要があります。
まずは自己分析をやってみよう
説得力のある志望動機を作成するには、入念な自己分析が必要です。
自己分析をすることで、「私は〇〇な性格なので、××の事業を実施しているインフラ業界でやりがいを見いだせると感じた」などのように、インフラ業界を志望する理由付けができるようになります。
納得感のある志望動機を作成するうえで、自己分析は必須です。
こんな志望動機はNG
インフラ業界の魅力として、安定していることや福利厚生が充実していることが挙げられますが、これをそのままインフラ業界への志望動機にするのは避けましょう。
上記のような志望動機にすると、自分本位な印象を与え、熱意が伝わりづらくなるからです。
「国民の社会基盤を支えることにやりがいを感じた」などのように、ポジティブな印象を与えるような志望動機にするように心掛けましょう。
なぜその企業にしたのか
インフラ業界を志望する理由が決まったら、つぎはインフラ業界の中でも、なぜその企業なのかということもしっかりと言語化しておきましょう。
しかし、インフラ業界の仕事内容は似通っていることが多く、なかなか言語化に苦しむこともあると思います。
そんな時は、「企業理念」に着目しましょう。
企業は自社の企業理念に共感する方を探しています。
仕事内容は同じでも、何のためにその仕事をするのか、という理念は企業によってさまざまです。
入念な自己分析の後に、同業他社の企業理念を比べて、「私は〇〇な性格なので、御社の××という企業理念に強く共感しました」というように志望動機を書ければ、非常に説得力のある志望動機にすることができます。
どのように会社に貢献するか
民間企業は利益を出すことを目的としており、そのためにあなたが貢献できることを説明できるようにしておきましょう。
これも自分がどのようなスキルを持っているかどうかという自己分析と、どのような事業を行っているかという企業研究が必要となるので、しっかりと事前調査をしたうえで作成するようにしてください。
エントリーシートの選考通過率をアップさせる方法に関しては、以下の記事でも解説されています。
志望動機の作り方と合わせてチェックしておきましょう。
【内定者のエントリーシートを大公開】
先輩就活生のエントリーシートを見れば選考通過のヒントが得られるかも?!
「エントリーシートに正解はあるのか」「書き方が良く分からない…」こんなことを考えたことはありませんか?
就活生にとって、エントリーシートは第一関門ともいえるものです。
今回は、内定者のエントリーシートを20社分用意しました。
各エントリーシートにはポイント付きで解説しています。
エントリーシートに行き詰っているなら、必ず参考になるでしょう。
内定者のエントリーシートを見る機会は、ほとんどありません。
このチャンスを逃したくない就活生は、ぜひチェックしてください。
インフラ業界の動向
インフラ業界の動向について紹介します。
インフラ業界は分野によっては政治的な動きや気候によって動向やトレンドが左右されるので、しっかりチェックしておきましょう。
エネルギー業界(電気・ガス・石油)
エネルギー業界は現在、厳しい状況に直面しています。
ウクライナ情勢の悪化でLNGの価格が急騰し、利益を出すのが難しくなっているのが現状です
新電力会社の中には倒産する企業もあるほどです。
LNGの価格高騰によって各社の値上げは続きますが、しばらくこの状況は続くと予想されています。
水道業界
人口減少に伴う売上低下や施設の老朽化による維持管理コストの増加が緊急の課題となっています。
売上低下に対処すべく、水道事業は経済発展区域の東南アジアや経済発展が著しい中国への海外進出を進めています。
また事業のデジタル化を推進し、現場のシステムの管理、水道使用量の計測、配水の見直しなどで時間やコストの削減に努めています。
鉄道・航空業界
鉄道業界も航空業界も、2020年の新型コロナウイルスの影響で売上が大きく落ち込みました。
しかし、鉄道業界では、2021年の旅客数が2019年のコロナ前の75%まで回復し、新幹線に限れば50%まで回復しました。
航空業界でも2021年には旅客数が増加し、ANAは2022年上半期に黒字を達成しました。JALも2022年上半期は赤字でしたが、前年同期と比べて赤字が縮小し、2022年7月~9月の四半期決算では黒字となりました。
通信業界
通信業界の売上は、2017年から2021年までほぼ横ばいだったものの、2020年の政府から携帯電話料金の引き下げ要請によって大手3社がそれぞれ格安プランを発表しました。
この動きは当初よりも落ち着くと考えられていますが、5GやIoTビジネスの展開によって今後も各社の競争はしばらく続くでしょう。
インフラ業界に向いている人の特徴

続いて、インフラ業界に向いている人の特徴について解説します。
責任感が強い人
責任感が強い人は、インフラ業界に向いています。
インフラ業界は人々の生活の基礎となるサービスを支えているため、ほんの少しのミスでも人々の生活に影響が出てしまうこともあります。
そのため、常に緊張感と責任感を持って業務に取り組める人材はインフラ業界向きと言えるでしょう。
正確な仕事が得意な人
インフラ業界では、マニュアル通りに仕事ができる正確性が重要です。
マニュアルに従わない仕事をすると、多くの人々の生活に影響が出てしまう可能性もあります。
コツコツと正確に仕事ができる人は、インフラ業界を目指すべきでしょう。
社会貢献できる仕事がしたい人
先述の通り、インフラ業界は人々の生活に密着したサービスを提供しています。
そのため、仕事を通じて社会全体に貢献しているという実感を強く得られる仕事でもあります。
社会や人々のために働きたい意欲がある人は、インフラ業界向きだと言えるでしょう。
安定性の高い仕事に就きたい人
インフラ業界は福利厚生が充実していたり経営面も安定したりしていることから、長く働ける業界としても知られています。
ただし、電力・ガス業界については小売自由化で競争が激化しているため注意が必要です。
また鉄道・航空業界もコロナ禍を脱却してから売上の黒字転換を目指している最中なので、ライフワークバランスに関してはうまくとれない可能性があります。
インフラ業界の先輩の本音
最後に、実際にインフラ業界で働いた方の本音を見てみましょう。
就職ジャーナルが、インフラ業界で働く212人に以下のようなアンケートを実施しています。
インフラ業界の一番の魅力は「安定感」
インフラ業界の一番の魅力は?という質問に対して、最も多かった回答は「業界の安定感」次いで、「待遇・福利厚生」でした。
やはり、参入障壁が大きく、ライバルの少ない安定感に魅力を感じている方が最も多いようです。
半数以上が入社後にギャップを感じている
入社後のギャップはあった?という質問に対しては、「とてもギャップがあった」「ややギャップがあった」と回答した方の合計は、51.9%と、半数以上の方がギャップを感じているという結果でした。
その理由として最も多かったのが、「仕事内容」という結果でした。
インフラ業界は規模が大きい分、業務内容も細分化されているため、希望の職種に付けない可能性も多いということは認識しておく必要があるようです。
約6割がこれからもインフラ業界で働くことを希望
これからもインフラ業界で働き続けたい?という質問に対して、「働き続けたい」「どちらかというと働き続けたい」と回答した方の合計は58%で、約6割の方が今後も働くことを希望している結果となりました。
やはり、年収の高さや手厚い福利厚生などに満足している方が多い印象でした。
インフラ業界の就活に関するよくある質問
最後にインフラ業界の就活に関するよくある質問をまとめたので、ぜひ参考にしてください。
インフラ業界の就活の軸って何をアピールすればいい?
インフラは人々の生活に欠かせないサービスを提供しています。
そのため「人々の生活を支える仕事がしたい」「社会貢献がしたい」という軸がマッチしやすいでしょう。
理系の方が有利?
インフラ系の業界への就職においては、文系か理系かどうかはあまり関係ありません。
特定の専門職・技術職への就職に関しては理系の大学や学部である必要がありますが、インフラ業界にはほかにも営業や事務、マーケティングなどさまざまな職種があります。
文系でもチャレンジできる職種があるので、気になる企業があればエントリーしてみましょう。
まとめ
この記事では、インフラ業界の基本情報と、志望動機を書くためのポイントについて解説しました。
インフラ業界は人々の生活に密接に関わっているため、景気の影響を受けにくく、安定しており、かつ社会的意義が大きいため、やりがいのある魅力的な業界です。
その分ライバルも多いですが、この記事で紹介したポイントを押さえれば、就活を有利に進めることができますので、ぜひ参考にしてみてください。