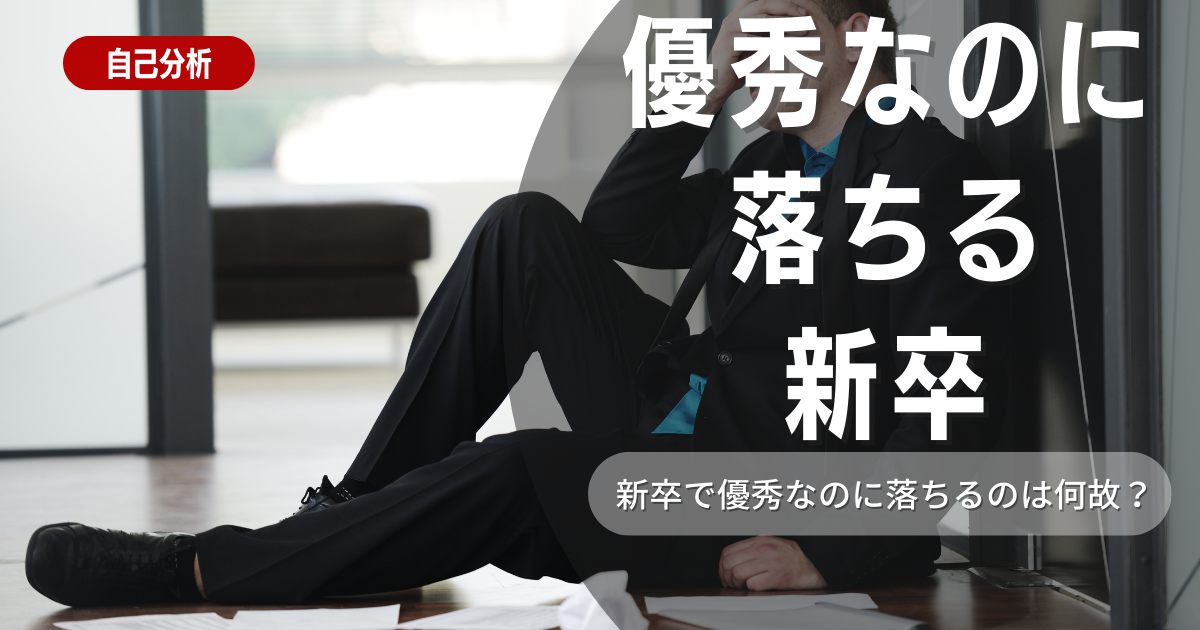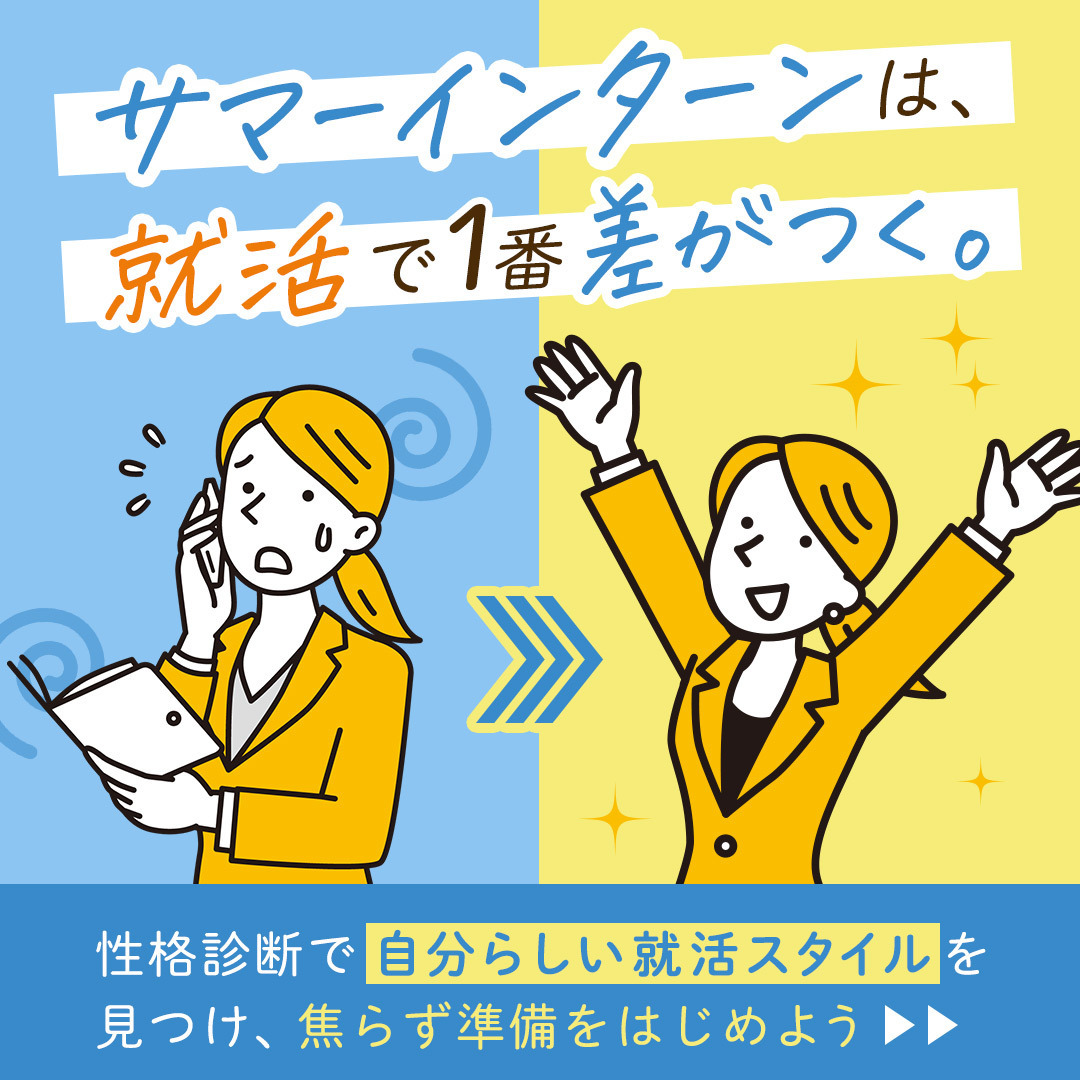【これで解決!!】使い勝手のいい就活ノートの選び方・書き方
2024/8/27更新
はじめに
「就活ノートを作ったほうがいいと聞いたけれど、選び方と書き方がわからない…」
就活を始めると「就活ノート」を作ることを勧められる学生もいるでしょう。
さまざまな業界や企業を調べていくと、情報がありすぎてうまく整理できなくなることがあります。
そこで、「就活ノート」を活用することで、情報を見やすくし就活をスムーズに進めることができます。
- 就活ノートのメリットを具体的に知りたい
- 就活ノートはどんなものを使っているの?
- 就活ノートにはどんなことを書けばいいのか教えて欲しい
この記事を最後まで読めば、就活ノートの具体的な書き方がわかり、情報収集の時間を大幅に削減することができます。
ジョーカツでは、他の人より優れた経験があるのに面接で不採用が続く原因についても解説しているので、気になる方は以下のリンクを参考にしてください。
上京を志す地方学生ならジョーカツ!
あなたのキャリアを加速させるチャンス!
無料で利用できる快適な個室シェアハウス、
東京までの交通費サポート付き
首都圏の注目企業への就活ならジョーカツ
首都圏の学生ならスタキャリ!
理想のキャリアを実現へと導く第一歩!
あなたにピッタリのキャリアアドバイザーを選び、
自分にマッチする優良企業をご紹介
首都圏企業のES添削から面接対策まで、就活ならスタキャリ
就活ノートの選び方
就活ノートを作ろうとしても、どんなものを使えばいいのか悩む人も多いでしょう。
就活ノートの種類としては、以下が挙げられます。
- ノート
- ルーズリーフ
- 手帳
- アプリ
選ぶときの注意点として、スマホアプリよりも紙媒体のものを選ぶことをおすすめします。
企業によっては、スマホをいじっていると「この学生はまじめに話を聞いているのか?」と誤解するケースがあるからです。
おすすめの就活ノートの大きさは、A5サイズ(A4の半分)またはA6(文庫本)サイズ程度です。
就活中は、会社説明会やインターンなど持ち歩くシーンが多いため、ある程度書き込みやすく携帯しやすいサイズを選びましょう。
就活ノートの書き方

就活ノートに記入する内容は、以下の6つを書くのがおすすめです。
- 自己分析
- 業界分析
- 企業分析
- 就活イベント・選考スケジュール
- 選考結果・印象・感じたこと
- 就活の振り返り・活動記録
原則、就活ノートに書く内容は就活に関する情報であればどんなことを書いても問題ありません。
上記の5つの項目を書くべき理由について、このセクションで解説します。
自己分析
1つ目は自己分析です。
これまでの経験や自分の長所・短所といった自己分析結果を就活ノートに書き出すことで、自分がどういった人物なのかを知ることが可能です。
エントリーシートを書く時の参考にしたり、面接前の時間を使って自己PRや志望動機、企業選びの軸を確認できたりします。
具体的には下記のような内容をまとめておくといいです。
- 企業選びの軸
- 自分の長所・短所
- 学生時代に力を入れたこと
- 趣味・特技
- 他己分析の結果
例えば、自分の短所が頑固な性格だとしても、裏返して見れば真面目な性格という長所が発見できます。
エントリーシートを書く時や面接前の時間を使って志望動機、企業選びの軸を確認でき、就活をスムーズに進められるでしょう。
業界分析
2つ目は業界分析です。
業界ごとに情報を整理しておけば、予備知識を持って会社説明会などに参加でき、説明の理解やインプットが格段に向上します。
具体的には下記のような情報を整理しておきましょう。
- 市場規模
- 事業内容・ビジネスモデル
- 仕事内容
- メリット・デメリット
- 安定性・将来性
- 業界内のトップ企業
- 関連業界・業種
業界研究が不足していると、自分と相性が悪い業界を誤って志望してしまい、ミスマッチが起きる危険性があります。
新卒入社した会社から転職することもできますが、可能であれば最初から自分に合った業界で働きたいでしょう。
早期退職をしないためにも、業界研究・業界選びは慎重に行ってください。
企業分析
3つ目は企業分析です。
企業ごとに情報を整理しておけば、企業の強みや弱み、業界におけるポジション、事業に関する考え方などをリサーチした上で、就活イベントや選考に臨めます。
単なるデジタル情報や、少し調べれば手に入る情報だけでなく、OB訪問や会社説明会でしかわからない情報や、その場で自分が感じたことや気付くことが可能です。
疑問点、魅力などをメモしておくことがコツです。
最低限下記の内容を押さえておきましょう。
- 経営理念
- 事業内容
- 過去の業績
- 競合他社との違い
- 企業研究を行う行う中なかで生じた疑問点
- 魅力的に感じた要素
- 選考情報
- 社員の名前・部署
少し調べれば手に入る情報だけでなく、OB訪問や会社説明会でしかわからない情報や、その場で自分が感じたことなどをメモしておくことがコツです。
企業に応募する時は、働いている社員の名前・部署のようなその企業でしか使用できない情報を使うことで、熱意の高さをアピールできるでしょう。
深く企業研究したタイミングでしか抱かない感想もあるので、メモに残しておけば後に役立ちます。
就活イベント・選考スケジュール
4つ目は就活イベントや選考スケジュールです。
就活ノートのメリットでもお伝えしたように、就活ノートがあれば、1冊のノートにスケジュールをまとめられます。
同時並行に進行する複数社の選考日程を時系列で一元管理でき、抜け漏れ防止に役立つのです。
学生生活では就活だけでなく、アルバイトや授業の日程などを整理しておきましょう。
日程を記録しておかないと情報が煩雑になってしまい、余裕がなくバタバタしてしまいます。
就活ノートに書くべき具体的な日程は下記の通りです。
- インターンシップの日程
- 会社説明会の日程
- エントリーシートの締切日・提出日
- 適性検査の日程
- 面接の日程
スケジュール管理は社会人の必須スキルなので、スケジュール管理が甘いと社会人としての基礎マナーができてないという印象を与えてしまいます。
日程調整でミスをしてしまい、内定が得られないともったいないです。
スケジュールはしっかりと管理するようにしましょう。
基礎的な部分でマイナス評価を防ぐためにも、スケジュール管理は徹底してください。
選考結果・印象・感じたこと
最後は選考結果・印象・感じたことです。
選考結果や説明会で印象に残った言葉、気づいたことづき、感じたことをメモしておきましょう。
どの企業がどこまで選考まで進んだのか、説明会を受けてさらに選考に進みたいと感じたのかを書くことで、振り返りがしやすくなります。
以下のようなことを書いておきましょう。
- インターンシップで行ったこと
- OB・OG訪問で感じたこと
- 面接で聞かれた質問・回答内容
- 面接でうまくいかなかったこと
- 面接を通して企業に抱いた感想
選考情報をメモしておかないと、採用・不採用となった原因を追認できません。
原因がわからなければ、またゼロの状態から選考に臨むことになり、なかなか改善されず、内定を得にくくなります。
うまくいかなかったことや次回の改善点があれば、メモに残して対策を立てるようにしましょう。
就活の振り返り・活動記録
6つ目は、就活の反省やどんな業界・企業を受けてきたのかです。
「なかなか内定が貰えない」「内定を持っている友人がいて焦る」など、就活をしているとうまくいかないことが出てくるでしょう。
応募している業界・企業の規模が自分に合っていない可能性があるため、一度見つめ直す時間をとってください。
- 今、就活を始めてどのくらい経ったのか
- 今後どんな企業を受けていくのか
- 企業の規模(知名度、事業規模、営業所の数、社員数、資本金など)
- いつまでに内定が欲しいのか
- 何社受けたのか
- 選考はどこまで進んだのか
- 内定が出た企業はいくつなのか
就活では内定を得ることが重要ですが、それ以上に入社してからどんなキャリアを築きたいのか、どんな仕事をしたいのかも考えておくことも大切です。
就活をしていく中で活動記録を残しておくと、どんな業界に魅力を感じているのかがわかり、自分の傾向が把握できます。
就活の結果から、応募する業界・企業を変えて今後のプランを練り直しましょう。
就活ノートを作るときの注意点
就活ノートを作るときの注意点は以下の3つです。
- 企業の情報を漏らさないようにしよう
- ノートはきれいに作らない
- 余白をとっておく
情報を記録する際、情報をうまくまとめきれず、管理しづらくなる場合があります。
また、就活では企業の情報を取り扱うケースもあるので、ノートの紛失には気をつけましょう。
このセクションでは、絶対に外せない部分について具体的に解説します。
企業の情報を漏らさないようにしよう
企業の情報を雑に扱い、情報を漏洩しないようにしてください。
ライバルである同業他社に優秀な人材をとられないためにも、選考スケジュールやインターンの情報を非公開にしている可能性もあります。
例えば、IT業界に属するベンチャー企業のA社が、就職活動の早期化を受けて早めにインターンを開始していたとします。
他の企業が同じタイミングでインターンを開始してしまうと、知名度や企業の規模から、インターンの募集枠を満たせない恐れがあるのです。
すでに公開している情報であれば問題ないですが、応募先の企業があえて情報を伏せている場合もあるので、むやみに外部に漏らさないようにしましょう。
ノートはきれいに作ろうとしない
ノートは何度も振り返りをするため、見やすくする必要はありますが、過度にきれいに作る必要はありません。
マーカーを使って見やすくしたり、どう書けばいいのか悩んでいたりすると、必要な情報を書き損じてしまうリスクがあるからです。
ノートはあくまで就活に必要な情報を忘れないために書くので、本来の目的を見失わないようにしてください。
きれいに書くことはこだわらず、わかりやすく情報をまとめることを優先しましょう。
余白をとっておく
ノートに企業の情報を記録するときは、スペースを多めにとっておくことをおすすめします。
会社説明会やインターンに参加するにつれ、応募先の企業の情報はどんどん増えていくからです。
最初にノート一面にぎっしり書いてしまうと、ページを飛ばして新たな情報を書くことになるので、後で見返すときに見落としてしまう恐れがあります。
最初に余白をとっておくと書きやすいです。
もし余白をとっていたにもかかわらずスペースが足りなくなってしまったら、付箋やルーズリーフで追記する方法もあります。
就活ノートって本当に必要なの?

就活ノートと聞いて、「ノートを作るのは面倒」「大事なことは覚えておくから大丈夫」 と考える就活生も多いでしょう。
しかし、就活では平均20〜30社ほどに応募しています。
似たような名前・事業内容の企業が多くある中で、ノートなしで情報を分けるのは難しいです。
自分にとって必要な情報を集めたり、日程を管理したりすることで、何度も情報を調べ直す必要がなくなります。
企業説明会などの日程が重なり、ドタキャンするリスクも避けられるでしょう。
就活を効率良く進める上で、就活ノートは必要不可欠です。
就活ノートを作るメリット3つ

就活ノートを作るメリットは大きく3つあります。
- 自分の考えを整理できる
- 企業分析に役立つ
- スケジュールを管理できる
就活ノートは原則、就活に関係する情報は抜け漏れなく全て書くようにすべきですが、実際は大変です。
そのため、最低限書いておくべき情報について紹介します。
自分の考えを整理できる
就活を進めていく中で、自分の心情や考えを定期的に書いてみましょう。
頭の中で考えているだけではわかりませんが、紙に書き出してみると、自分の中で変化が出てくる可能性があるからです。
例えば、「入社する企業を決める上で福利厚生が絶対条件」と考えている就活生がいたとします。
ところが、ある会社の社長の話を聞いて、下記のように心境が変わる可能性があるでしょう。
「やはり使命感をもって仕事に携わらないとやりがいがない」
「給料が多少安くても、自分の得意が発揮できる分野で仕事がしたい」
このように、就活を始める前の考え方と、ズレが出てくることもあるのです。
このケースのように就活ノートにメモしておくと、企業選びの優先順位は「福利厚生の良し悪し」ではなく、「やりがい」であったことに気づくことがあります。
企業分析に役立つ
企業理念や会社の規模、売上などをリストアップしましょう。
情報を表にしてまとめると見やすくなるだけでなく、他の企業との比較もしやすく、改めて企業の強みや特徴がわかります。
例えば、ある企業を調べた時は以下のように表にすると、情報を整理しやすいです。
【例】
| 項目 | 内容 |
| 事業内容 | 新しい経理業務に特化したアプリの開発 |
| 経営理念 | 未来の可能性を広げ、持続可能な社会の実現に貢献する |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 従業員 | 324名(正社員:256名) |
会社説明会やOB/OG訪問を行い、インターネットでは得られないような生の情報は、抜け漏れがないようにすると他のライバルと差をつけられます。
選考スケジュールを一元管理できる
就活が始まると、複数の会社から企業説明会や面接など色んなイベントが同時平行で進んでいきます。
その時、別々にスケジュール管理するとダブルブッキングが生じたり、締め切り期限を過ぎたりする恐れがあるのです。
例えば、8/23にA社の4dayインターンに参加する予定だったものの、B社の書類選考が通り、急に企業から電話がきたとします。
8/23に面接の日程を組んで後で予定が重なっていると気づくと、再度日程の調整を交渉するといった余計な手間が増えます。
それを回避するためにも、スケジュールはまとめて管理しておいて下さい。
中にはスケジュール帳を分けて管理する就活生もいますが、1冊ですべてが把握できる就活ノートのほうが圧倒的に便利です。
就活ノートQ&A
就活ノートに関する頻出の質問をQ&A形式で回答します。
Q1:就活ノートを複数冊もってはいけない?
A1:情報をすぐに確認できるように就活ノートは1冊で管理しましょう。
就活ノートが何冊もあると持ち運びが不便ですし、情報を整理しづらくなって手間と時間がかかります。
Q2:就活ノートはどんなサイズを選んだらいいの?
A2:就活ノートは持ち運びしやすいA5・A6サイズがおすすめです。
A5はA4の半分のサイズ、A6は文庫本サイズです。
就活中は立ったままメモする場合もあるので、持ちやすいサイズにしましょう。
ただし、字を書くスペースが小さくて書きにくい人は、快適に使用できるサイズを選んでください。
Q3:就活ノートの作成はいつから始めたらいいの?
A3:開始時期は3年生の夏を基準にして下さい。
インターンシップやOB訪問など、就活イベントの開始前までには準備しておきましょう。
早めにノートを用意しておけば、直前に慌てずにすみます。
Q4:どんな内容を書けばいいですか?
A4:自己分析、業界分析、企業分析、就活イベント・選考スケジュール、選考結果・印象・感じたこと、就活の振り返り・活動記録の6つは記録に残しておきましょう。
Q5:A4以外に書いたほうがいい内容はありますか?
A5:説明会に登壇された人事の方や社員の名前、応募先の企業のビジョンなどを書くことをおすすめします。
応募先の企業で働いている人と働きたい、または憧れているといった内容を書けば、オリジナルの志望動機になります。
企業のビジョンを知ることで、どんな能力を持った人材を欲しいのかがわかるでしょう。
例えば、海外に事業を展開したいと分かれば、語学力がある学生が採用されやすいと推測できます。
自分のやりたい仕事と強みと照らし合わせて、役立ちそうな情報なら何でもメモしておいてください。
まとめ
本記事では就活ノートの選び方や書き方について解説してきました。
就活は平均20〜30社の企業の選考を受けることになり、多くの情報を扱うことになります。
情報収集の手間と時間を効率良く行わないと、いくら時間があっても足りません。必要な時に確認できるように就活ノートを作成しましょう。
情報を抜け漏れなく扱い、他の学生と差をつけ就活を勝ち抜ければ、自分の第一志望の企業から内定が得られます。
以下のリンクでも就活で役立つ記事を掲載しているので、気になった記事を読んでみてください。