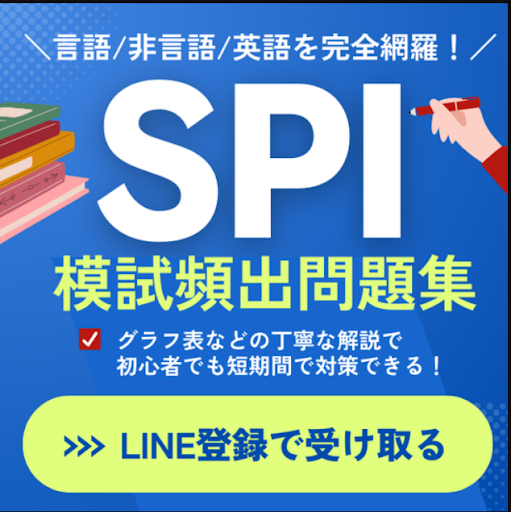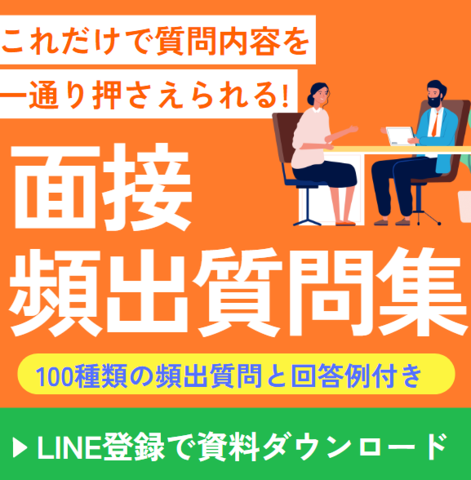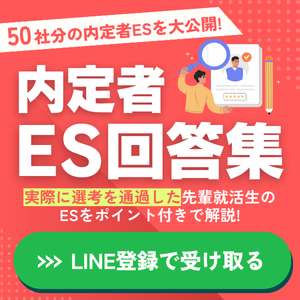面接で聞かれる「座右の銘」とは何か?その選び方と答え方
2024/10/7更新
はじめに
就活での面接を迎えるにあたり、志望企業から「座右の銘」を問われることに戸惑いを感じる就活生も多いことでしょう。
「なぜその質問がされるのか?」
「どのように答えれば良いのか?」
面接官は、単なる言葉選び以上のものを見ています。
この質問を通じて、あなたの価値観や人柄、そして企業文化との相性を見極めているのです。
この記事では、面接で好印象を与える「座右の銘」の選び方や、効果的な答え方を解説します。
あなたが面接で自信を持って答えられるように解説をしますので、参考にしてみて下さい。
- 自分に自信がなく、面接での質問に対する答え方に迷っている就活生
- 面接官の意図が理解できず、不安を感じる就活生
- 自分に合った「座右の銘」を見つけられない就活生
【言語/非言語/英語完全網羅】SPI初心者でも対策できる資料配布中!
SPIなどに自信がない。
SPIが原因で選考に進められない。
そんな学生のためにまとめたものがSPI頻出問題集です。
SPIの出題範囲である言語/非言語/英語といった問題を完全網羅しています。
丁寧な解説付きなので、今から勉強する人でも安心して取り組めます!
面接で聞かれる「座右の銘」とは何か?理解すべき基礎

「座右の銘」とは、個人の信念や価値観を一言で表現した言葉です。
その人の人生や行動の指針となります。
この言葉は、人生の様々な場面で自分を奮い立たせたり、困難を乗り越える際の道しるべとして重要な役割を果たすのです。
多くの人にとって、座右の銘は日々の行動を方向づけ、目標に向かって進むための強い意志を支えるものとなっています。
以下、座右の銘の意味やその重要性について見ていきましょう。
歴史的背景
「座右の銘」という言葉は、日本の文化に深く根付いた概念で、もともとは古代中国の思想や哲学に由来しています。
「座右」とは、文字通り「座る場所の右側」を意味し、古代中国においては、自分が座る右側にいつも置いておく大切な言葉という意味で、使われていました。
この言葉が日本に伝わり、自分の行動や考えを戒めるために、常に心に留めておく言葉として「座右の銘」として広まったのです。
人生を方向づける道しるべ
座右の銘は、人生の羅針盤としての役割を果たします。
例えば、「七転び八起き」という言葉は、何度失敗しても再び立ち上がる強い意志を持つ人を象徴します。
このような言葉を座右の銘に持つことで、困難な状況や逆境に直面した際に、自分自身を励まし、前に進む勇気が与えられるでしょう。
座右の銘は、その人の人生を方向づける道しるべとなり、進むべき道を示してくれます。
価値観の明確化
座右の銘は、自分の価値観や人生観を明確にするための強力なツールです。
「自分に厳しく他人に優しく」という座右の銘を持つ人は、他者に対して寛容であると同時に、自己鍛錬の重要性を認識していることを示します。
座右の銘を通じて、自分の信念や価値観を言語化するので、自己理解を深められるでしょう。
また、座右の銘を持つことにより、自分がどのように成長して行きたいか明確にでき、その方向に向かって努力する意欲が高まります。
心の支えとしての役割
座右の銘は、単なる信念の表現にとどまらず、心の支えとなる役割も果たします。
困難な状況に直面したときや、自分の力に自信を失いかけたとき、座右の銘はその人の心を強く支えてくれる存在です。
心の中に座右の銘を持つことで、逆境に立ち向かう勇気が持ち続けられるでしょう。
コミュニケーションのツール
座右の銘は、自己表現の一部としても活用できます。
面接やビジネスの場で、座右の銘を紹介することにより、自分の価値観や信念を簡潔に伝える手段となるのです。
「座右の銘を教えてください」という質問は、面接官が就活生の価値観や性格を理解するために用いられることが多く、この答え方によって自己アピールできます。
例えば、「一日一善」を座右の銘とする人は、日常的に他者を思いやり、自分の行動に責任を持つ姿勢を示せるでしょう。
面接で「座右の銘」を聞かれる理由と意図
面接で「座右の銘」を質問されるのは、企業が就活生の価値観や人柄、行動原則を理解し、自社との適合性を見極めるためです。
上述したように、座右の銘はその人の人生哲学や信念が凝縮されており、面接官はそれを通じて就活生の思考や行動基準を把握しようとします。
以下、具体的な理由について解説しますので、参考にしてください。
価値観や人柄を深く理解するため
座右の銘を企業が質問をする理由は、就活生の価値観や人柄を深く理解することです。
就活生がどのような人柄であるかを、知るための手がかりになります。
価値観は個々の行動や決断に大きく影響します。
企業側には、座右の銘を通じて、就活生の本質的な部分を理解しようとする意図があります。
行動規範や仕事に対する姿勢を評価するため
企業が「座右の銘」を訪ねるもう一つの理由は、就活生がどのような行動規範を持ち、仕事にどのように取り組むかを評価するためです。
例えば、「凡事徹底」という座右の銘を掲げる就活生は、細かいことにも注意を払い、徹底的に取り組む姿勢を持っていると感じます。
こうした人は、どのような小さな仕事であっても責任を持ち、常に高い水準を求めるため、企業はその姿勢を評価します。
また、「失敗は成功のもと」という座右の銘を持つ人であれば、失敗を恐れずにチャレンジを続ける積極的な姿勢が伺えるでしょう。
企業はこのような情報を通じて、就活生が職場でどのように振る舞い、業務を進めるかを、より具体的にイメージできるのです。
企業との相性を見極めるため
また、面接官が座右の銘を質問する背景には、就活生の価値観や行動基準が企業の文化や価値観とマッチするかを確認する意図もあります。
企業にはそれぞれ独自の文化や理念があり、それと就活生の考え方や価値観が一致するかどうかは、長期的な雇用関係において重要なポイントです。
例えば、競争心を重視する企業であれば、「勝って兜の緒を締めよ」という座右の銘を持つ就活生は、好意的に受け取られるかもしれません。
一方で、チームワークや協調性を重視する企業では、「和を以て貴しとなす」を掲げる就活生が高く評価される可能性があります。
このように、企業と就活生の間で価値観が一致しているかどうか、見極めるために座右の銘の質問が行われるのです。
入社後の活躍を予測するため
さらに、座右の銘は、就活生の考え方や行動の基準を示すものであるため、企業はその情報を基に、入社後の活躍を予測します。
例えば、「失敗は成功のもと」という座右の銘を持つ就活生は、新しいプロジェクトや未知の分野に積極的に挑戦し、困難な状況でも前向きに対処する姿勢が期待されます。
また、「一日一善」を座右の銘としている人は、毎日の小さな努力を積み重ねる姿勢を持ち、チームにポジティブな影響を与える可能性が高いと判断されます。
このような観点から、面接官は就活生の座右の銘を通じて、どのように活躍するか、どのように組織に貢献するかを想像しやすくなるのです。
面接で「座右の銘」を尋ねる質問は、単なる趣味的な興味ではなく、就活生の内面的な特性や行動基準を理解し、企業との適合性を見極めるための重要な手段です。
就活生は、自分の価値観や行動基準を具体的に示す座右の銘を選び、それを通じて企業との相性を確認するのが大切です。
面接で好印象を与える「座右の銘」の選び方

面接での成功には、選び抜かれた「座右の銘」が大きな役割を果たします。
座右の銘はあなたの価値観や人生観を一言で表すものであり、それが面接官に強く響くことで、あなたの個性や信念が印象付けられるのです。
しかし、選び方を間違えると、期待とは逆にマイナスの印象を与えるリスクもあるため、注意が必要です。
以下、就活生が面接で好印象を与えるために最適な「座右の銘」の選び方について、具体的な方法を解説します。
自分の経験や志望企業の理念に沿った座右の銘を選び、面接でのアピール力を最大限に引き出しましょう。
自分の経験や個性に関連するものを選ぶ
座右の銘は、自分の内面や経験を表現するための強力なツールです。
面接官は、座右の銘を通じてその人となりを感じ取ります。
そのため、自分の経験や個性に関連するものを選ぶのが、まず第一のポイントです。
例えば、学生時代に部活動でリーダーシップを発揮した経験があるなら、「仲間を信じて前進する」「共に成長する喜び」といったフレーズを選ぶことで、その経験を効果的に伝えられます。
また、具体的なエピソードを用いて、なぜその座右の銘が自分にとって重要なのかを説明することで、より説得力を持たせられるでしょう。
自分の性格や価値観を反映させた座右の銘を選ぶのも大切です。
例えば、「継続は力なり」という言葉が、自分が持つ粘り強さや忍耐力を表している場合、面接官にあなたの堅実さや努力を惜しまない姿勢をアピールできます。
逆に、自分の性格に合わない座右の銘を選ぶと、面接官に不自然さを感じさせ、印象に残るのが難しくなるため、慎重に選ぶ必要があります。
志望企業の企業理念と近いものを選ぶ
面接では、志望企業の企業理念や、価値観に共感していることを伝えることが求められます。
そのため、座右の銘を選ぶ際には、企業の理念やビジョンに近いものを選ぶと効果的です。
例えば、企業が「革新」や「挑戦」を重視している場合、「案ずるより生むが易し」といった座右の銘が適しています。
どんなことにおいても、実際にやってみると心配していたほど難しくなく、案外簡単にできるものだという意味のことわざです。
行動力があり、アクティブな印象を抱きます。
面接官に対して、あなたが企業文化や目標にフィットしている印象を与えられるでしょう。
さらに、志望企業の具体的な事例をリサーチし、その企業の求める人物像に合った座右の銘を選ぶのも有効です。
例えば、志望する企業が「チームワーク」「協調性」を重視している場合、「一人は皆のため、皆は一人のため」といった座右の銘を選ぶと、企業文化に対する理解と共感を示せます。
このように、座右の銘を通じて自分と企業の価値観の一致を強調するので、面接官により好印象を与えられるのです。
仕事の内容や役割に活かせるものを選ぶ
座右の銘が具体的な仕事内容や、その役割に直結するものであるのも重要です。
企業が求めるスキルや能力に合致する座右の銘を選ぶので、面接官に「この人はこの仕事に最適だ」と感じてもらえます。
例えば、営業職に応募する場合、「顧客第一」「信頼はすべての基本」という座右の銘が、顧客に対する姿勢や仕事への取り組み方を示すものとして有効です。
また、プロジェクト管理やチームリーダーとしての役割が求められる場合には、「計画に勝るものはない」「成功への鍵は準備にある」といったフレーズを選んでみてはどうでしょう。
あなたがその役割に対する理解を深め、適応力があるのをアピールすることができます。
このように、仕事の具体的な内容に関連する座右の銘を選ぶことで、面接官に対してポジションに適した人物であるという印象を与えられるでしょう。
座右の銘を選んだ理由を伝える際のポイント
座右の銘を面接で伝える際には、その選択理由をしっかりと述べるのが不可欠です。
単に「好きだから」「感動したから」といった表面的な理由では、面接官にあなたの深い考えや信念を伝えるのは難しいでしょう。
代わりに、その座右の銘がなぜ自分にとって重要であるのか、どのような経験や価値観とリンクしているのかを具体的に説明します。
例えば、「失敗を恐れない」という座右の銘を選んだ理由を、「大学時代に参加したプロジェクトで、多くの失敗を経験しながらも、諦めずに取り組むことで、最終的には大きな成果を上げられた」と面接官にあなたの姿勢や成長意欲を、具体的に伝えることができます。
具体例を用いて、座右の銘の背景や意味を説明するのは、面接での説得力を高める方法の一つです。
面接に臨む前に座右の銘を見直し、自分の強みを最も効果的に伝えるための準備を整えましょう。
面接で使えるおすすめの「座右の銘」
面接で「座右の銘」を尋ねられた際に、単に有名な言葉を選ぶだけでなく、どのようにその言葉を選び、どのように活用するかが重要です。
以下、いくつかのおすすめの座右の銘とその使い方を紹介します。
これらを参考に、自分に合った言葉を選びましょう。
言うは易くおこなうは難し
言葉にするのは簡単だが、実際に行動に移すのは難しいという意味です。
このことわざは、行動力や実行力をアピールしたいときに使えます。
「私は常に言葉だけでなく、行動で結果を示すよう努めています」という形で、このことわざを使ってみましょう。
実際のエピソードを絡めると説得力を高められます。
虎穴に入らずんば虎子を得ず
リスクを取らなければ、大きな成果を得られないという教訓です。
このことわざは、挑戦する精神を強調したい時に効果的になります。
例えば、「私は困難な課題にも積極的に取り組み、結果を出してきました。この精神は『虎穴に入らずんば虎子を得ず』ということわざに表れていると思います」と述べると、挑戦心をアピールできます。
初志貫徹
最初に立てた目標を最後まで貫き通すことを意味します。
この四字熟語は、粘り強さや目標達成意欲を伝えるのに適しているでしょう。
「私はどんな困難な状況でも、最初に決めた目標を諦めずに、達成するのを信条としています。そのため、『初志貫徹』は私の座右の銘です」といった形で使うと良いでしょう。
不撓不屈
どんな困難にも屈しない強い意志を表します。
この四字熟語は、逆境に負けない姿勢をアピールしたい時に有効です。
例えば、「私はこれまで多くの挑戦を乗り越えてきました。その経験から得た教訓が『不撓不屈』です」と説明すれば、面接官に粘り強さを印象づけられます。
千日の稽古をもって鍛となし、万日の稽古をもって錬となす(宮本武蔵)
宮本武蔵のこの言葉は、継続的な努力が重要であることを示しています。
努力の積み重ねを重視する人に向いているでしょう。
「私は日々の努力を重ねることを大切にしています。宮本武蔵の『千日の稽古をもって鍛となし、万日の稽古をもって錬となす』という言葉が、私の行動指針です」と述べれば、面接官に強い印象を残せます。
一時の成敗は長い人生、価値の多い生涯に於(お)ける泡沫のごときものである(渋沢栄一)
この言葉は、長期的な視点を持つことの重要性を教えてくれます。
入社後のチャレンジ精神をアピールしたい場合に使えるでしょう。
「私は失敗を恐れず、長期的な視点で物事を捉えるように心がけているのです。このため、渋沢栄一の言葉を座右の銘としています」といった使い方が有効です。
Stay Hungry, Stay Foolish(スティーブ・ジョブズ)
「現状に満足するな、小賢しくなるな」という意味のスティーブ・ジョブズの言葉は、新しい挑戦を恐れない姿勢を示す際に最適です。
「私は常に新しいことに挑戦し続ける姿勢を大切にしています。ジョブズの『Stay Hungry、 Stay Foolish』という言葉は、私のモットーです」と述べれば、好奇心と挑戦心を強調できます。
何事も、成し遂げるまではいつも不可能に見える(ネルソン・マンデラ)
ネルソン・マンデラのこの言葉は、困難に直面しても諦めない心を伝えるのに最適です。
「私は困難な状況でも目標を持ち続けることを大切にしています。マンデラの言葉は、その精神を象徴しているのです」と説明すれば、強い意志をアピールできます。
座右の銘は、面接で自分の価値観や信念を効果的に伝えるための強力なツールです。
自分に合った言葉を選び、その意味や背景を具体的なエピソードとともに伝えることで、面接官に好印象を与えられるでしょう。
ぜひ、この記事を参考にして、自分だけの座右の銘を見つけてください。
さいごに
この記事では、面接で「座右の銘」を尋ねられた際の選び方と、効果的な答え方について解説しました。
座右の銘は単なる言葉以上の意味を持ち、個人の価値観や人生観を示す重要なツールです。
そのため、面接で好印象を与えるためには、自分の経験や志望企業の理念に沿った座右の銘を選びましょう。
その理由を具体的なエピソードと共に説明するのが鍵となります。
また、面接官は座右の銘を通じて、就活生の価値観や人柄を理解し、企業との適合性を見極めています。
今後の面接に向けて、自分に合った座右の銘を見つけ、それを効果的に伝える準備を進めましょう。
自分の信念や考え方をしっかりと持ち、それを伝える力を養うことで、面接での成功をより確実なものにできるのです。