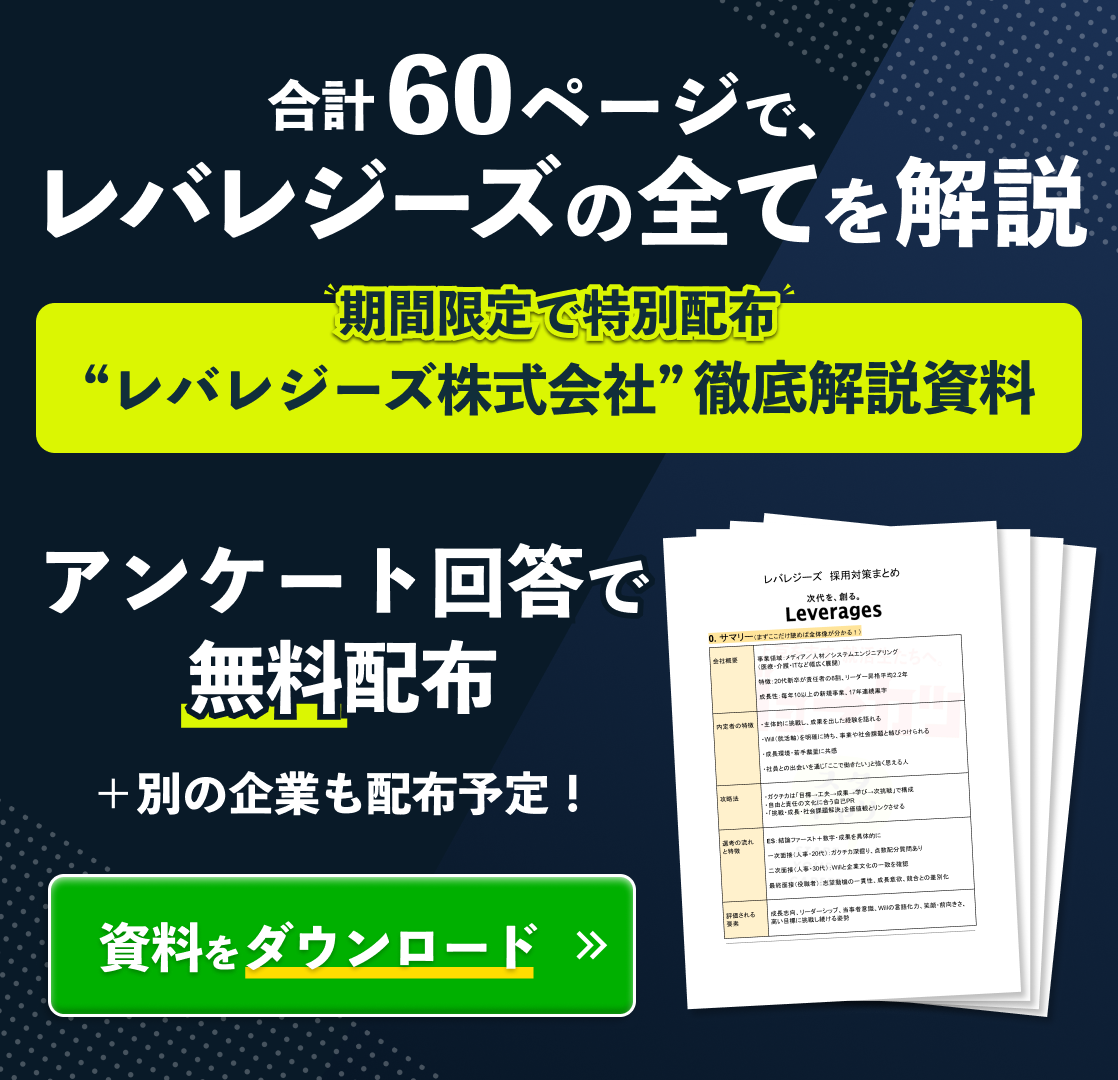自分に向いている業種を知るには?就活生に向けて解説
2024年6月20日更新
はじめに

就活生の皆さんの中には、将来についての明確な目標をまだ探している途中で、具体的にどのような業種に就職すればいいのか分からなく悩んでいる方もいるのではないでしょうか。
また、世の中の仕事が多種多様で溢れているため、逆にどれを選べばいいのか困っている人もいるでしょう。
結論としては、自分に向いている業種を知るためには「自己理解を行なったり適職診断ツールを利用する」「自分に向いていない業種を知ること」が大切になります。
視野を広げて多くの選択肢を持つことも大切です。
この記事を通して、自分が生き生きと働きつづけられるような仕事に就きましょう。
上京を志す地方学生ならジョーカツ!
あなたのキャリアを加速させるチャンス!
無料で利用できる快適な個室シェアハウス、
東京までの交通費サポート付き
首都圏の注目企業への就活ならジョーカツ
首都圏の学生ならスタキャリ!
理想のキャリアを実現へと導く第一歩!
あなたにピッタリのキャリアアドバイザーを選び、
自分にマッチする優良企業をご紹介
首都圏企業のES添削から面接対策まで、就活ならスタキャリ
自分に向いている業種に悩む就活生の悩みとは
就活を始めるに当たって、まず自分がどのような業種を理想としているのかから考える就活生は多いと思います。
ですがいざ探してみると、自分に向いている業種が分からないという壁にぶつかる人もいるでしょう。
そのような就活生の悩みを洗い出してみました。
業種自体に何があるか分からない
業種自体何があるか分からなくて困っている就活生の方もいるでしょう。
この世には多くの業種があります。
さらに、AI事業などの少し前にはあまり見当たらなかった新しい業種も生まれています。
まずは就活の情報を調べてみる、自分が少しでも興味があると感じた業種の企業のHPを覗いてみるなど、業種を知るための行動を起こしてみましょう。
自分の強みや弱みが分からない
自分の強みや弱みが分からないからどんな業種が向いているのかも分からない、と悩んでいる就活生の方もいますよね。
まずは、自分がどのような物事について自信を持って取り組むことができたのか、またはどのような状況で気持ちが怯んでしまいうまく物事を進められなかったのか、具体的なエピソードをアウトプットしてみましょう。
周りの人が喜んでくれたこと、逆に自分での主導が難しく周りの人の助けがないと実現が難しかったことなども考えてみると、自分の強みや弱みが見つかるかもしれません。
自分がどのような仕事をしたいのかが分からない
自分がどのような仕事をしたいのかが分からないため、仕事探しが困難になっている就活生もいるでしょう。
まずは、自分がどのような業種に興味を持っているのか、その業種の中で自分に向いていそうな仕事や取り組みたい仕事があるのかを調べてみましょう。
こちらでも情報収集能力が大切です。
自分に向いている業種を知るためにすべきこと
自分に向いている業種を知るためにすべきことについて解説します。
まずは自分を知ることが大事です。
どのような業種があるのか業界や企業分析も行いましょう。
自己理解によって自分を知ること
自分に向いている業種を知るためには、まずは自己分析を行なって自分を知ることから始めましょう。
- 自分は何をしているときに楽しく取り組めているのか
- どのような事で人に頼られた経験があるのか
- 仕事において将来はどのような目標があるのか
- 苦手で気が進まない事は何か
- ワークスタイルで重視するものは何か
これらの項目から、具体的に書き出してみてください。
自分が理想とする業種が明確になってくるはずです。
周りの人に聞いてみる
自分のことというものは、自身では把握しきれないものです。
そのため、周りの人に自分はどのような仕事が合っていそうなのか、聞いてみるのも手です。
自分だけでは分かり得なかった面も見えてくるかもしれません。
就活を進める過程にある面接でも、周りの人の評価について聞かれる機会もあるかもしれないため、身近な親しい人に確認してみてください。
他に適職診断ツールなどを利用するのも良いでしょう。
業界理解や企業理解を行なってみること
自分が気になる、知ってみたいと思う業界や企業の情報を集めて、理解を深めましょう。
- どのような事業内容なのか
- 企業のビジョンは何なのか
- 企業はどのような人材を求めているのか
- 自分はこの企業にどのように貢献できるのか
- その業界や企業にはどのような職種があるのか
就活を進めていく上で、業界や企業を深く知ることはとても重要です。
後々のエントリーシートや面接にも深く絡んでくるためです。
最初は軽く確認するだけでも構いませんので、ぜひ行なってみましょう。
就活の情報を収集する
自分に向いている業種が分からない現状の場合、まずは就活の情報を収集しましょう。
大学3年生であれば、夏のインターン情報から調べてみることがおすすめです。
1dayで選考なしの気軽に参加できるインターンもあります。
気になる企業のインターンに選考がある場合は、就活準備を始めるきっかけにもなりますよ。
インターンの時期を過ぎている場合は、就活サイトで企業説明会をチェックしましょう。
まずは就活について知ることが、自分に向いてる業種を知ることの一歩として重要になります。
自分に向いていない業種を知ることも大切
自分に向いている業種についてばかり調べてしまうかもしれませんが、自分に向いていない業種を知ることも大切です。
仕事というものは人生において期間が長く、人生に占めるウェイトも重いです。
もし自分に合ってない職業を選んでしまった場合、無理をすることによって心身によくない影響が出る可能性があります。
自分にも企業にとっても、良い影響を与えません。
転職をするにも、元の業種に近い職種から選ぶことが多いため、最初の就職先は苦痛にならないものを選びましょう。
そのため自分のネガティブな面も把握し、向いていない業種を知っておくことをおすすめします。
社会人になっても仕事について悩むことを知っておく
仕事というものは、実際働き出してみないと自分に合っているのかは分からない部分は多いです。
実際に、社会人の方の中にも自分に合っているかどうか悩んでいたり、自分に向いているのか疑問に感じている状況の中で働いている人も多数います。
参考までに、周りの社会人の人に今の仕事が合っているか聞いてみてもいいでしょう。
絶対に向いている仕事に就かなければならないという訳ではない、ということがわかるかもしれません。
選ぶ業種の視野を広く持つことをおすすめします。
自分に向いている業種を知るメリット

自分に向いている業種を知るメリット3点について解説します。
大きなメリットは、仕事にやりがいを持って楽しむことができる点ですね。
楽しく仕事ができる
自分に向いている仕事に就くと、楽しい気持ちで仕事ができるでしょう。
楽しい気持ちで仕事をすることのメリットは創意工夫も生まれ、モチベーションを保って仕事ができる点です。
注意すべき点としては、いくら楽しい仕事であっても、辛いと感じる瞬間はあるということです。
向いてる仕事の、自分にとってマイナスになる面についても向き合ってみましょう。
企業に貢献がしやすい
自分に向いている仕事をする場合、先ほど記述したとおり楽しく仕事をすることができるでしょう。
前向きに仕事に取り組めるため、結果として良い業績を生み出し、企業に貢献しやすくなります。
企業に貢献することは企業だけではなく、自分の将来を見据えても、人事からの評価や転職時に有利に働くため、自分に向いている業種を知ることは重要でしょう。
苦難を乗り越えやすい
大抵の仕事には苦難が待ち受けています。
苦難にぶつかったときに、向いていないと感じている仕事をしている場合はモチベーションを保てず、壁を乗り越えることが困難になる場合があります。
しかし、自分に向いていると感じる仕事の場合は、解決策を見出しやすく苦難を乗り越えやすいです。
タイプ別の向いている業種について解説
その人の性格などのタイプによって向いている業種は異なります。
注意点として「業種」は「職種」とは異なり、その企業が行なっている事業分野のことを指しています。
一例を挙げますので、ぜひ参考にしてください。
※総務省の「日本標準産業分類」では、大分類、中分類に分けられています。
几帳面な人に向いている業種
時間をきっちりと守り、必要事項を事細かくメモをする、事前準備もしっかり行うなどの几帳面な人に向いている業種です。
- 経理事務
例として金融業の数字を扱う業種が几帳面な人には向いているでしょう。
また、経理事務はどの企業にも必ずいるため興味を持った業界の経理事務を検討してみてください。 - 技術者
几帳面な人には手先を細やかに使う技術職を必要とする専門・技術サービス業もおすすめです。
ものづくりの仕事は、品質を保ちながら製品を出荷することが需要になるためです。
几帳面な人ならば、製品のわずかな差異にも気づくことができるでしょう。
上昇志向が強い人に向いている業種
仕事で成果を出し続け、常にスキルアップも怠らない上昇志向が強い人に向いている職業です。
- 営業職
営業職はノルマがある業種も多く、目標が明確に示されている場合もあるため、結果の出し甲斐がある職業です。
既存の顧客営業ではない金融業、保険業や不動産業などが上昇志向が強い人に向いているでしょう。
営業はほとんどの業種にもある上に、AIには変えられない仕事とも言われています。 - 経営コンサルタント業
経営コンサルタントは、企業の業務内容や経営の状況を把握し、戦略や改善方法について助言をする仕事です。
様々な顧客を相手にするため、情報や知識を常にブラッシュアップする必要があります。
責任感が強い人に向いている業種
責任感が強く、物事に対してじっくり考えてから判断する人に向いている業種です。
- 教師などの教育系の業務
生徒には色々なタイプの子がいるため、対応する方法も様々で大変な一面があります。
しかし責任感が強い人は、生徒に寄り添い、熱意と責任感を持って生徒を良い未来へと導こうとするため、合っているでしょう。 - 弁護士などの法務系の業種
人の人権を守ることで、社会正義を実現する弁護士の仕事は責任が強い人に向いている仕事と言えるでしょう。
同時に人を平等に見て、冷静に判断する目も持ち合わせていることが望まれます。
人と関わることが好きな人に向いている業種
人と関わることが好きな、コミュニケーション能力が高い人に向いている業種を紹介します。
- 宿泊業・飲食サービス業
宿泊業や飲食サービス業は、お客様に快適な時間を過ごしてもらえるようなサービスを提供するお仕事です。
直接感謝の言葉をもらったり、喜びを感じられます。
一方で問題になっているカスハラについては、最近では従業員を守ろうという動きが出ているため、今後は改善されていく可能性が高いです。 - 生活関連サービス業、娯楽業
クリーニング、理容、美容、娯楽業のサービス業も、お客様に喜んでもらえることにやりがいを感じる業種です。
相手に対する、身だしなみや言葉遣いも洗練されます。
自分に向いている業種を知るためのおすすめツールを紹介
自分に向いている業種を知るために理容したいおすすめツールをご紹介します。
ハローワークといった公的機関で利用できるものから、民間のツールまであります。
自己診断ツールjobtag
厚生労働省が商標を登録をしている職業情報提供サイトです。
500以上の職業をタスク、スキル、ジョブなどの視点から「見える化」しています。
「職業適性テスト(Gテスト)」は、就業した経験が少ない人や、自分に向いている職業に悩んでいる人に特に有用です。
VRT職業レディネステスト
ハローワークで受けられる検査です。
中学生から社会人まで、自分の進路を探求して将来の生き方や職業を考えることを助けてくれます。
「職業興味」「基礎的志向性」「職務遂行の自信度」の3つの検査から測定します。
大学生向けには、「職業興味別リスト」と「基礎的志向性別リスト」の2種類の職業リストが用意されており、結果と照らし合わせてキャリアプランの参考にすることが可能です。
VIP職業興味検査
ハローワークで受けられる検査です。
6つの興味領域が分かります。
- 現実的
- 研究的
- 芸術的
- 社会的
- 企業的
- 慣習的
5つの傾向尺度も分かります。
- 自己統制
- 男性-女性
- 地位志向
- 稀有反応
- 黙従反応
上記の興味領域と傾向尺度がプロフィールで表示されることで、就職活動だけでなく、今後のキャリアについての参考にもなるでしょう。
リクナビNEXT
就活大手サイトのリクナビが提供する適職診断です。
誰でも3分間の所要時間で簡単にできるものと、リクナビNEXT会員限定の「グッドポイント診断」の2種類があります。
グッドポイント診断の結果は、リクナビNEXTからの企業応募時に添付することが可能です。
マイナビNEXT
就活大手サイトのマイナビが提供する適職診断になります。
マイナビ会員限定の「適性診断MATCH plus」では、自己分析と今後の自身の方針に関する情報を得ることが可能です。
少し手間がかかりますが、診断結果の精度が高いと評判を得ています。
キャリアパーク
就活大手サイトキャリアパークが提供する「My analytics」は、自己分析ツールですが、適職を提示してもらうことも可能です。
問題数が比較的少ないため、気軽に実施できる点が魅力です。
自分に向いている職業か判断するポイントとは

自分が向いている職業を決めるのは、家族や友人、適職診断ではなく、自分です。
向いている職業をどのように判断すべきなのかについて解説しますね。
適職診断を信頼しすぎない
自分がどのような業種に向いているか悩んでいると、適職診断の結果に頼りたくなるでしょう。
しかし、適職診断も絶対に正解を出してくるとは限りませんし、様々なタイプがあります。
あくまで自分の仕事を決めるためのツールのひとつとして、参考程度にしておくほうが良いです。
また自分の適職だけではなく、自分が向いていない業種についても目を向けて判断をしましょう。
様々な方法で調べて知ること
この記事でも自分に向いている業種を知るための色々な方法を紹介していますが、ひとつ、ふたつ程度の方法だけで決めないことをおすすめします。
調べる場合は、できる限り多くの方法で調べ、総合してから判断をしましょう。
自分を枠にはめすぎないこと
自分に向いている職業について調べて方向性が固まってくると、向いている業種以外のものが見えなくなってくるかもしれません。
しかし、自分を枠にはめて業種を絞りすぎるのは自身の将来の選択肢を狭めることにもつながりかねません。
また、他の業種にも興味を持つことで自分に向いていそうな業種との違いなども知ることができ、就活でのエントリーシートや面接で活かされる場合もあるでしょう。
特に情報収集をしている段階では、様々な業界について知っておくことをおすすめします。
業界も変化し続けることを理解しておくこと
どの職業においても、近年のAIやIT技術の発達などにより業界の業務内容も変化を遂げています。
例えば、スーパーに買い物に行くだけでも、レジがセルフやQRコードの読み取りなどで従業員がいなくても支払いができる店舗が増えています。
レストランでも従業員の代わりにロボットが料理を運ぶ店舗もあります。
これらの光景は数十年前までには見られなかったことです。
他の業界でも、この様に数十年変わるだけで取り組む内容がガラッと変わっている、または変わろうとしている動きがあります。
この様に業界は現状維持ではなく、常に変化し続けることを理解しておきましょう。
おわりに
就活生に向けて、自分に向いている業種を知るために必要なことについて解説しました。
就活の準備段階では、まだ自分がどんな仕事をしたいのか、そもそもどのような業種があるのかが分からない人もいるでしょう。
まずは、どの様な業種があるのかを知り、自分がその中でどの様な仕事に興味があるのかを調べましょう。
同時に、自分に向いていない業種も調べましょう。
一例ではありますが、タイプ別の向いている業種についても紹介しましたので、ぜひ参考にしてください。
向いてる職業を調べる際には、適職診断も利用してみましょう。
一種類だけではなく何種類かを使い、結果を総合して適職を判断することも重要になります。
自分に向いている職業を判断する時は、適職診断などの結果を信頼しすぎずに広い視野で行いましょう。
技術の進化により、業界も職業も変化していくことが予測されます。
自分が将来どのような仕事に携わりたいのか、どの様なワークライフバランスをとりたいのかも考えましょう。