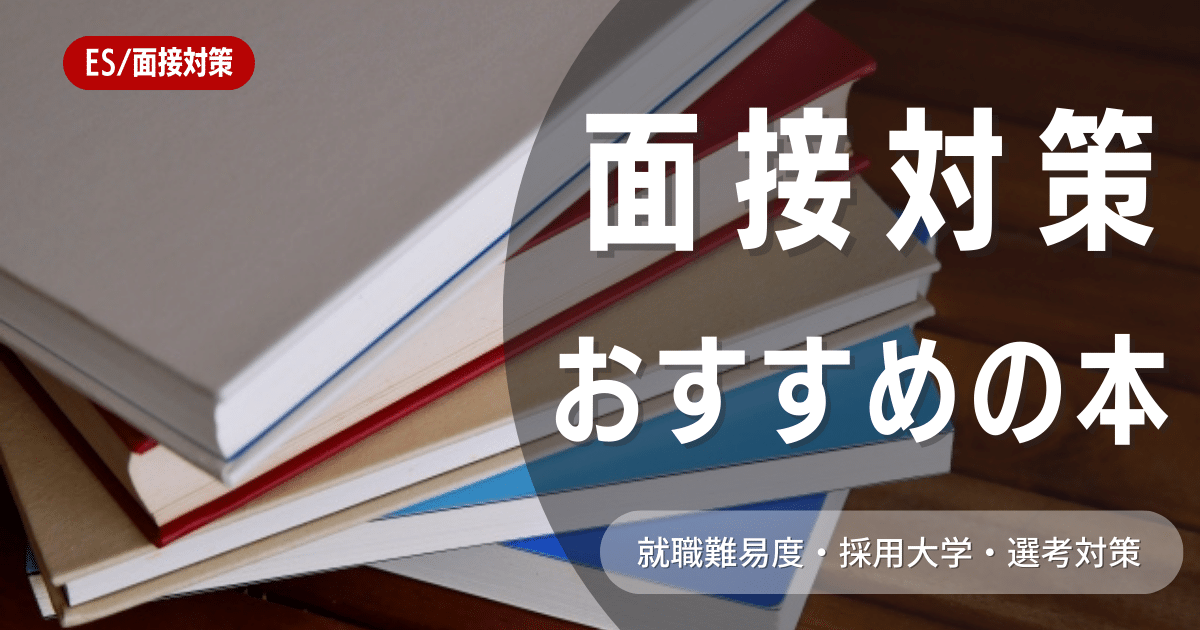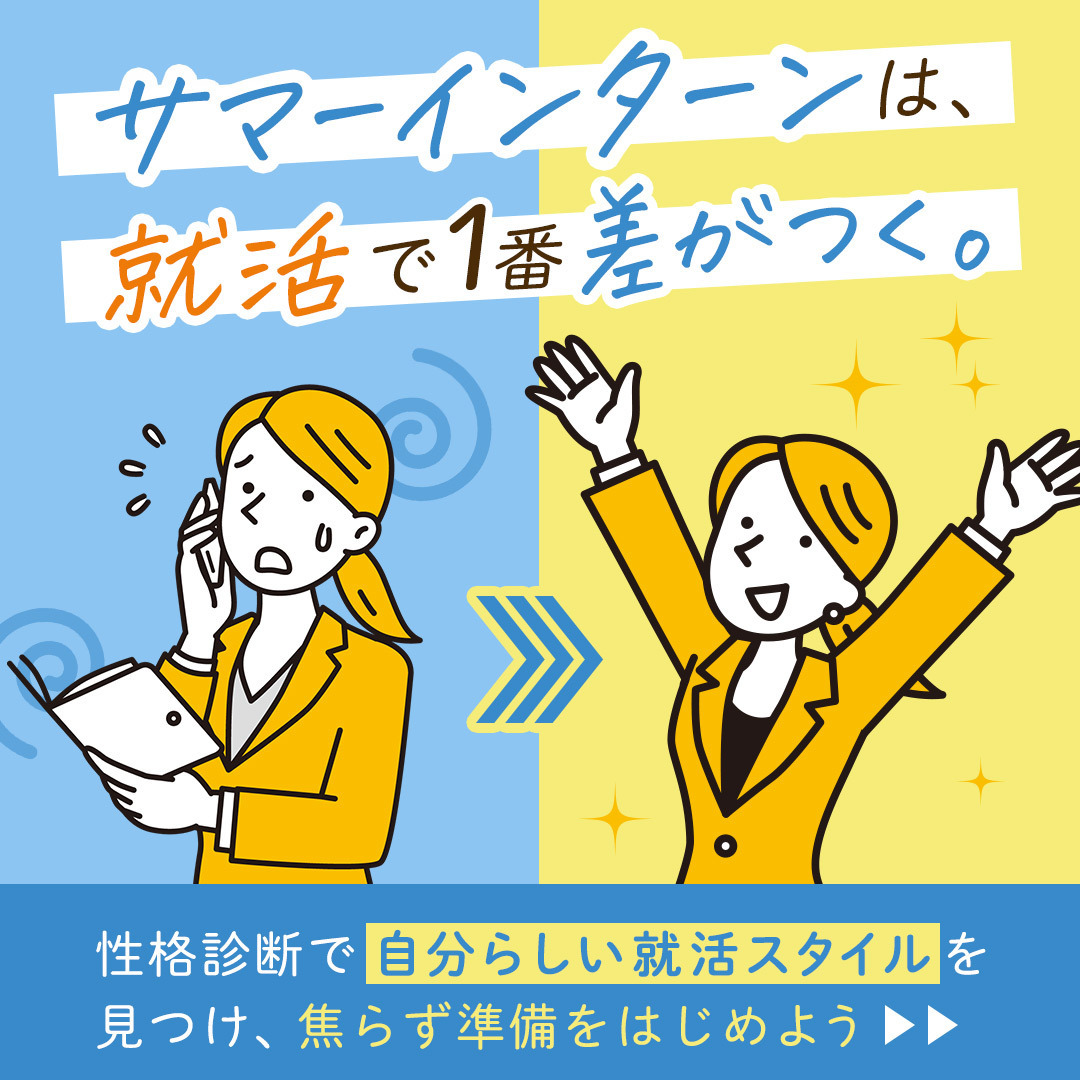【完全版】就職活動はいつから?スケジュールと選考対策を解説
2024/10/20更新
はじめに
経団連は2018年10月9日、採用活動の解禁日などを定めた就活ルールの廃止を発表しました。
今後は経団連にかわり、政府が主導してルールを定めます。
就活ルールが変わることによって、就活生や企業側にはどのような影響が出るのでしょうか。
本記事では、就活ルールが変更にともなう影響や、今後の就活でやるべきことを紹介します。
以下のようなお悩みのある学生は必見ですので、ぜひ最後までチェックしてみてください。
- そもそもが就活ルールがどのようなものか知らない
- 結局のところ、いつから就活を始めるべきか知りたい
- 選考突破のための詳しい対策が知りたい
上京を志す地方学生ならジョーカツ!
あなたのキャリアを加速させるチャンス!
無料で利用できる快適な個室シェアハウス、
東京までの交通費サポート付き
首都圏の注目企業への就活ならジョーカツ
首都圏の学生ならスタキャリ!
理想のキャリアを実現へと導く第一歩!
あなたにピッタリのキャリアアドバイザーを選び、
自分にマッチする優良企業をご紹介
首都圏企業のES添削から面接対策まで、就活ならスタキャリ
そもそも就活ルールとは?

就活ルールとは企業の採用活動に関して、経団連(=日本経済団体連合会)の会員企業が守るべきルールのことです。
現行のルールでは入社前年の3月に会社説明会が解禁され、6月に面接解禁、10月に内定が解禁されるのが流れとなっています。
大学生に当てはめると、3年生の終わりにあたる3月から就職活動が始まり、4年で迎える年末までに就職活動が終わっているということです。
しかし、経団連に加入している企業以外は、就活ルールを守る必要はありませんでした。
それに、加盟している企業であっても、就活ルールを破ったとしても罰則はありません。
じつは就活ルールには罰則等はありません。
就活ルールをわざわざ守っているようでは、ほかの企業に出し抜かれてしまうわけです。
就活ルールは、これまでに度々変更が行われてきました。
その度、企業や学生の双方から不満の声が出ていたことも廃止の要因になったとされています。
就活ルールはすでに意味を成しておらず、面接解禁と同時に内定を出す企業も多いため、今回の廃止は当然の流れといった見方もあります。
そして、就活ルールを守らず早期採用を行う企業が出現することで、優秀な学生が取られ、市場に現れなくなってしまうことが危惧されました。
他の企業も学生を確保しようと早期採用を行い始め、またそれを見てさらに早い時期から採用を行うなど、早期化の歯車が止まらない状態となってしまったのです。
就活ルールが廃止されるのはいつから?

日本における就活ルールは、2021年卒業生から廃止され、政府主導の下で新たな方針が策定されました。
経団連がルールを廃止した背景には、外資系企業やIT企業などが早期に採用活動を始めることで、経団連加盟企業が人材獲得競争で不利になるという懸念があります。
就活ルールの廃止により、企業は採用活動のスケジュールを自由に設定できるようになりましたが、一方で、学生側には早期からの就職活動が求められるようになりました。
ですが、就活ルールの廃止により、学業への影響を懸念する声もあります。
大学側からは、学生が早い段階で就職を意識し、学業がおろそかになる可能性が指摘されています。
政府主導の新たなルールは、企業に対する拘束力が弱いとされており、実質的な就活の早期化が進むでしょう。
特に、通年採用の拡大が予想され、企業によっては大学3年生の秋から採用活動を開始する動きも見られます。
これにより、学生は自ら積極的に情報収集し、就職活動に備える必要があります。
就活ルールの廃止は、企業にとっても採用戦略を見直す契機となっているようです。
人材不足が深刻化する中、自社の求める人材を確保するための戦略策定がますます重要となっています。
企業は、就活ルールの変更にかかわらず、柔軟に対応し、変化に適応する姿勢が求められています。
就活はいつからすべき?26卒以降の就活スケジュール

それでは、就活ルールの廃止によって学生は今後どのような動きをすべきでしょうか。
26卒以降の就活スケジュールの内容をまとめるので、ぜひ参考にしてください。
大学3年生の4~6月から始めるのがおすすめ
26卒以降は大学3年の4〜6月ごろからサマーインターンの応募が始まります。
企業の中には、インターンシップへの参加で選考が優遇されることもあるので、興味のある企業や業界のインターンシップ情報はこまめにチェックしておきましょう。
また、インターンに参加するための選考がある場合はこの時期から面接やエントリーシートの対策をしておいてください。
志望企業の選考が始まる半年前には始めるべき
遅くとも、志望する企業の選考が始まる半年前までには就活をスタートさせるのがおすすめです。
本選考の対策として自己分析や業界研究、OB・OG訪問などが挙げられます。
特に志望する企業が決まっていない場合は、まずはなんとなく興味がある業界の動向や特徴、有名な企業について調べておきましょう。
就活ルールの廃止による学生側のメリット
就活ルールの廃止により企業は採用活動のスケジュールを自由に設定できるようになりましたが、一方で学生にとっても新たなメリットが生まれました。
就活ルールが廃止されることによって、学生にはどんなメリットがあるのでしょうか。
- 余裕を持って就活ができる
- 就職留年しにくくなる
- 就活中の自由時間も増える
余裕をもって就活ができる
就活ルールの廃止は、採用選考のスタートラインがなくなったことを意味します。
それによって、就職活動期間は長期化するでしょう。
就職活動が長期化すれば、その期間内にさまざまな企業を知ることができます。
ミスマッチを防げるだけでなく、自分にとって最適な企業に就職できる可能性が増すでしょう。
就職留年しにくくなる
就職活動の長期化によって、志望度の高い企業にチャレンジする期間が延びます。
そのため、就職留年を回避する要因にもつながります。
就職留年の主な理由は、就職活動に対する準備不足がほとんどだからです。
時間的余裕が生じるため、泣く泣く志望する企業をあきらめるケースは減るでしょう。
就活中の自由時間も増える
自由な時間が増えることも挙げられます。
早期に内定を獲得できるため、残りの時間を自らの自由時間に用いることが可能になります。
例えば留学や、資格の取得など社会人になるまでにやっておきたいこと、やり残したことに取り組むことが可能です。
就活ルールの撤廃は言い換えると通年採用の増加です。
就活生にとっても選択肢の幅が広がり、自分の志望する業界への就活がよりしやすくなるといえるでしょう。
しかし、デメリットも存在します。
就活の早期化によって内定の時期が早くなり、将来の選択肢の幅を狭めてしまう可能性もあります。
そのため「就活の早期化=メリットだらけ」と捉えてはいけません。
また、早期化に伴って学生の本業である学業に支障をきたす可能性があります。
就活と学業のバランスを見誤ると留年なんてことにも…。
先ほど、早期の内定獲得により自由な時間が増えることを挙げましたが、就活の長期化によって自由な時間がなくなるということも考えられます。
意識の高い学生にとっては就活の早期化はメリットが多いですが、自分の目標が定まっていない一般的な学生からすると、大きな負担と労力を強いられるでしょう。
では一方、企業側はどうなのでしょうか?
就活ルール廃止による企業への影響
就活ルールが廃止されることで、学生だけでなく企業側にもさまざまな影響が及びます。
以下では、就活ルールの廃止によって企業の今後の動向にどのような変化が起こるのかを見ていきましょう。
- 優秀な人材を早期獲得しやすくなる
- 採用コストが増加する
- 内定辞退者が続出する
優秀な人材を早期獲得しやすくなる
就活ルールの撤廃によって、優秀な学生の獲得がいち早く行えることが挙げられます。
長期化することによって学生との接触機会が増え、より自社に沿った学生を選び抜くことができるでしょう。
採用コストが増加する
しかし、企業側(特に中小企業)にはマイナスが多くなってしまっています。
まず、採用コストが膨大になってしまいます。
現状のルールの場合、就活ルールに則って就活生が動いていたため、短期間にまとめて採用活動を行うことで人材の確保ができました。
しかし、通年採用となってしまったいま、人事の負担は増え、就活生を自らアプローチして確保する必要が生じます。
細かく分けると内定辞退者の増加、人材確保がより困難になる、広告宣伝費の増加が挙げられます。
内定辞退者が続出する
優秀な学生に対して早期内定を出せることは、確かに大きなメリットと言えます。
しかし、学生は多くの企業から早期内定をもらうと、長い就職活動期間を使ってじっくりとベストな選択をとるようになります。
そのため、いかに企業が努力しても辞退者が増加してしまうのです。
大手企業が一斉に採用活動を行うため、認知度の低い中小企業は淘汰されてしまう可能性があります。
そこを補うために、認知拡大の意味を込めて広告宣伝費を割きます。
しかし、就活ルールの撤廃によって長期化してしまった就活期間の影響で、広告宣伝費の費用がかさみ、企業には大ダメージとなることでしょう。
早期採用にもデメリットはあります。
採用の基準がどうしても「潜在能力」や「伸びしろ」など期待値でしかないということです。
大学4年間でその人材がどう成長するのかは誰もわからないため未知なのです。
就活を成功させるための対策

先ほどまでの学生、企業の2者にとって、それぞれ就活ルール撤廃が及ぼす影響について説明してきました。
就活生のメリットとデメリットに関しては表裏一体なため、メリットの部分を生かせるように就活を行えば問題ありません。
では、具体的に私たちは就活を行うために何をすべきなのでしょうか?
主に「インターンシップに参加」「自己分析」「仕事研究」「エントリー」「ES・筆記試験・面接」「内定」に分けられます。
- インターンシップに参加する
- 自己分析をする
- 業界・企業研究をする
- エントリーシート対策をする
- 適性検査対策をする
- 面接対策をする
インターンシップに参加する
就活ルールの撤廃に伴うインターンシップ参加の増加
就活ルールの撤廃に伴い、近年のインターンシップに参加する学生の数の増加はさらに加速することでしょう。
インターンシップを通じて就業体験することで、社会人として組織の業務で求められる能力がわかり、仕事に活かせる自分の強みが明確になります。
インターンシップは、自己分析にも仕事研究にも役立つ貴重な機会です。
インターンシップに参加するメリットを簡単に紹介します。
- 仕事理解:業務の内容が具体的に理解
- 自己理解:自分の適性や課題が発見
- スキル理解:仕事で必要とされる能力や専門性に関しての理解
- 人脈:ペルソナとなる社会人や他校の学生との出会い
- 就活準備:ESや面接などの実践経験
近年の企業側の流れとして人材不足と採用難に伴い、インターンシップを実施する企業が増加しています。
内定は1つに絞る必要がありますが、インターンシップに制限はありません。
あなたに合った業界や企業に出会うために、さまざまなインターンシップに参加しましょう!
自己分析をする
自己分析は、自分に対する理解を深めることです。
学生生活やこれまでの人生を振り返り、自分自身のことについて深掘りをする作業です。
自己分析を通じて、以下のことがわかります。
- 自分は社会人としてどんなことをやりたいのか
- 自分は何ができるのか
- 何が自分を突き動かすモチベーションになっているのか
エントリーシートや面接など自分をアピールする場での武器が見つかるでしょう。
また、自己アピールは以下のポイントをふまえて深掘りしておくのがおすすめです。
- 何を経験したのか?
- なぜその経験や選択をしたのか?
- 具体的にどう行動したのか?
- その経験で学んだことは何か?
業界・企業研究をする
先ほどの自己分析を通じて自分の興味、能力、価値観、そして自らの強みが明らかになってきたら、次のステップです。
自分がどんな業界、そしてどんな仕事で活かせるのか、それを知るために「業界・企業研究」を進めましょう。
これは後々の就職活動でも必ず聞かれる質問です。
しかし、何を軸に考えればいいのかわからないと思います。
まずは
- なぜその業界を選ぶのか
- その企業を選ぶ理由は何か
- なぜその職種に就きたいのか
の3つの観点で仕事研究を進めていきましょう。
そして仕事研究といっても細かく3つに分かれます。
「業界研究」「企業研究」「職種研究」の3つです。
業界研究
業界研究では普段接している商品などを手始めに、幅広く業界を見渡してみてください。
普段接している商品はBtoC(BusinesstoConsumer)の業界の商品です。
しかし、社会には企業向けに商品やサービスを提供しているBtoB(BusinesstoBusiness)の業界やメルカリなどユーザー同士のCtoC(ConsumertoConsumer)にも目を向けてみてください。
企業研究
業界が同じといっても、企業規模はもちろん、事業内容や経営方針、社風や職場の雰囲気、待遇なども各企業によって大きく異なります。
業界を絞っただけでは面接などで詰められてしまいます。
「この業界にこういった観点で絞りました。その中で、なぜこの企業を志望するのか?」まで解像度を高くした理由を持っておきましょう。
自らの主張ももちろん大切ですが、企業側の観点を持っておく必要があります。
各企業の強み、弱み、他社との違いなどをしっかり調べましょう。
職種研究
職種についての研究も進めましょう。
企業には事務系、営業系、技術系など、さまざまな職種があります。
同じ職種であったとしても企業の規模や特化している事業によって仕事内容や求められる能力、そして専門性は異なります。
企業ごとにどんな職種があり、どんな特徴があるのか、そしてどのように仕事を進めるのかまで調べ尽くしましょう。
エントリーシート対策をする
そして、エントリーシートでも面接でも必ず確認されるのが「自己PR」と「志望動機」です。
自己PRは、自らを企業に売り込むために自身の強みをまとめたものを指します。
自身の強みを知るために、先ほどの自己分析が重要なのです。
良い自己PRを作るためには、自己分析で洗い出した自らの長所や強みとしてアピールできる事柄を記載することが重要です。
その際にできるだけ具体的に書くようにしましょう。
あなたが描いているエピソードを、面接官は間近でみていたわけではありません。
お互いがイメージしている情景を一致させるためにも、なるべく数字などを用いて具体的に作成しましょう。
そして、自らの強みと志望企業での接点も記載することが重要になります。
自らの長所は志望企業のどんな部署でどのように生かせることができるのかをイメージさせることで、採用担当者が採用したいと思わせることが大切です。
そして、志望動機です。
志望動機とは「私がなぜその会社に入りたいか」を端的にまとめたもののことです。
エントリーシートや面接で説得力ある志望動機が表現できるよう、就活サイトの企業情報や志望会社のホームページだけでなく、リアルな情報を大切にしましょう。
リアルな情報を手に入れる方法としてはインターンシップへの参加、そしてOBOG訪問が挙げられます。
自らの足を動かしてどこにも載っていない生の情報を手に入れましょう。
エントリーシートの注意点は以下の通りです。
- 自らの個性や人柄がわかること
- 経験談は、できるだけ具体的に記述すること
- 自分の言葉で記述すること
- 等身大の自分を表現すること
- 自分の強みが仕事にどう活きるのか
の5つです。
適性検査対策をする
エントリーシートを提出し、選考を通過すると筆記試験を受検するケースがあります。
問題の分野は、語彙や文章読解力を問う「言語」、計算力や論理的思考力を測る「非言語」、そして「性格適性」の3種類です。
業界や企業によっては「外国語」や「時事問題」などの一般常識や論作文関連の出題もあります。
受験前に過去の筆記試験の出題傾向を確認し、対策を練りましょう。
無料で適性検査対策ができるおすすめサイト・アプリは、以下の記事で紹介しています。
面接対策をする
筆記試験を通過した後はいよいよ面接です。
面接といっても対面形式の1対1だけではありません。
学生1人に対して15〜20分ほどで学生の回答をもとにした質問を行う個人面接。
2〜3人同時に面接を行う集団面接。
さらに6〜8人で1つのグループを作り、与えられたテーマについて討議するグループディスカッション形式。
まれな例ですが、自分の研究内容を説明するプレゼンテーション型面接。
これは研究職や開発職など、職種別の採用で行われることが多いです。
以下の記事では面接対策に役立つおすすめの本を紹介しているので、選考通過率を高めたい人はぜひ参考にしてください。
就職活動の時期に関するよくある質問
就活ルールの廃止によって学生や企業も今までと違う動き方となるため、さまざまな不安や疑問が残る学生も多いかと思います。
最後に就職活動の時期に関するよくある質問をまとめたので、ぜひ参考にしてください。
理系学生の就活スケジュールは?
理系は学校推薦か公募のどちらで就活をするかによってスケジュールが異なります。
学校推薦の場合は大学3年生・院生1年の2〜3月からエントリーを開始し、学内選考で選ばれることで企業推薦が行われます。
公募の場合は一般的な就活スケジュールと変わりません。
企業はいつまで採用活動をしている?
近年では大学4年の3月末まで採用をしている企業や、通年採用を導入する企業もあります。
内定が出ないといって焦らずに、このようなチャンスのある企業を探してみてください。
さいごに
今回は就活ルールの廃止によって起こりうる影響を就活生、企業の双方から解説しました。
そして、私たちはどういった就活のステップを踏むのか、何を観点として進めていくべきかが理解できたかと思います。就活ルールの撤廃によって企業の選考スケジュールは早期化しているため、大学3年生はコーポレートサイトや就活サイトをこまめにチェックして常にアンテナを巡らせておきましょう。
就活生からの目線ではなく、多角的に就活を捉え、良い就活を行ってください!