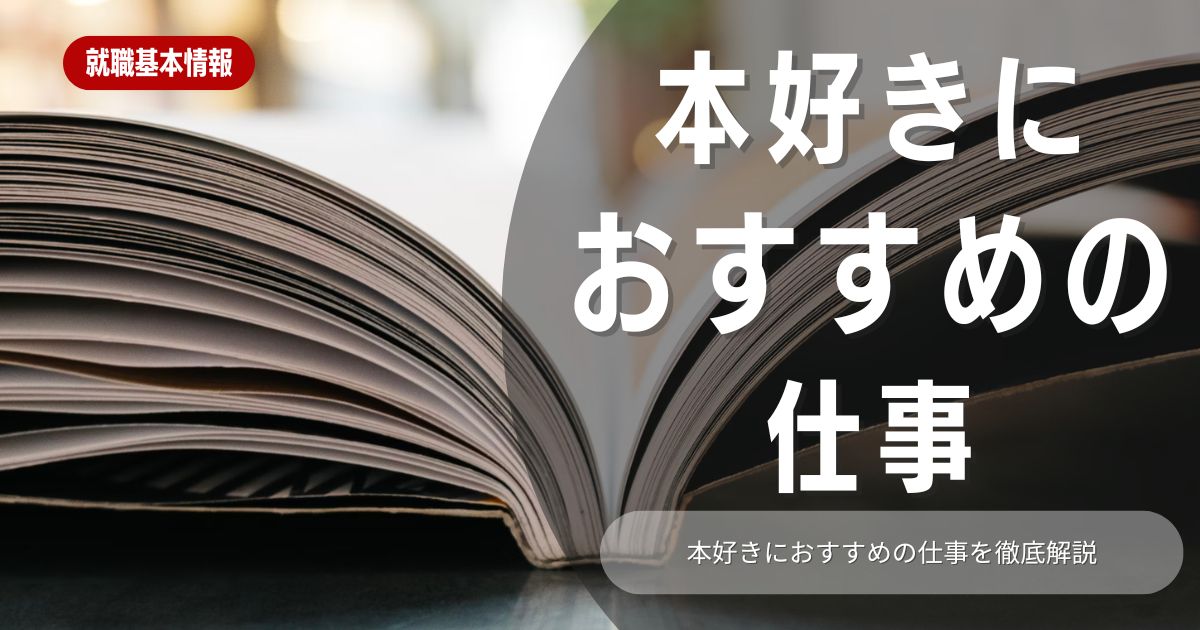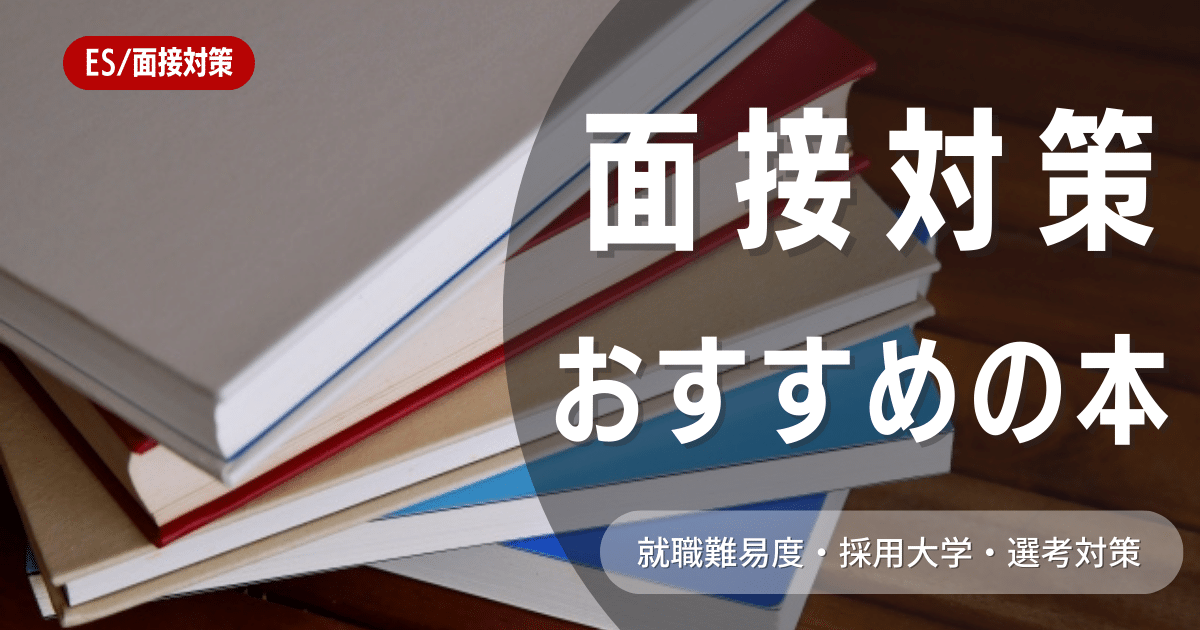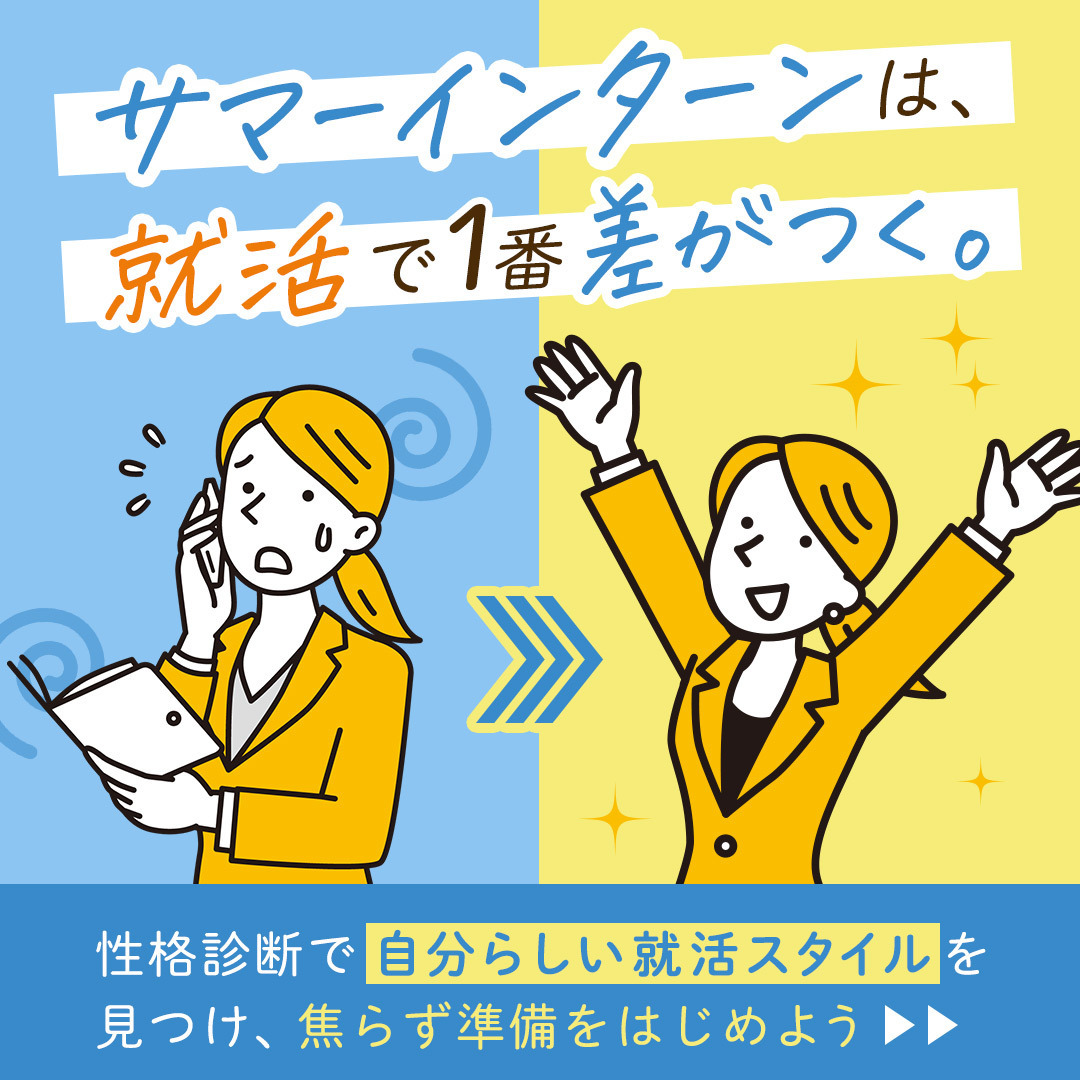面接で「最近読んだ本は?」と質問されたら?答え方のコツを解説
2024/10/20更新
はじめに
就活の面接で「最近読んだ本を教えてください。」と聞かれることがまれにあります。
重要度が低いぶん、いざ質問されるとあえて難しい本を提示するべきなのか、普段読んでいる本で良いのか返答に迷ってしまいますよね。
志望度の高い企業に就職するため、しっかりと対策しておくことが大事です。
そこで本記事は、以下のような就活生を対象に、面接で「最近読んだ本」について質問されたときの答え方について解説します。
- 面接で「最近読んだ本」について質問されたらどう答えるべき?
- 読書の習慣なんてないから、聞かれたらどうしよう
- 最近読んだ本について面接で聞かれるのはどういった意図があるの?
【言語/非言語/英語完全網羅】SPI初心者でも対策できる資料配布中!
SPIなどに自信がない。
SPIが原因で選考に進められない。
そんな学生のためにまとめたものがSPI頻出問題集です。
SPIの出題範囲である言語/非言語/英語といった問題を完全網羅しています。
丁寧な解説付きなので、今から勉強する人でも安心して取り組めます!
面接で最近読んだ本について聞く5つの理由
本章では、企業が面接で「最近読んだ本」を質問してくる意図について解説していきます。
企業がこの質問を問う目的は、大きく分けて次の5つです。
- 説明能力を図りたい
- あなたの知識量が知りたい
- 読書習慣があるのか確認したい
- あなたの興味を抱いている分野を知りたい
- アイスブレイクがしたい
説明能力を測りたい
まず考えられるのは、「就活生のプレゼンテーション能力を知りたい」ということです。
質問の意図が就活生の説明能力を判断するための材料だった場合、あなたがどんな本を読んだかは関係ありません。
社会人になれば、社内会議や顧客への営業、取引先との商談など、さまざまな側面でプレゼンテーション能力が必要になってきます。
概要の説明から入るのか、相手がどれくらい知っているかを測るため、「〜は知っていますか?」というように、ワンクッション置いてからトークを始めるのか。
あるいは、いきなり内容や、印象的な場面の説明から入り、話に緩急をつけるのか。
同じ内容を語るにしても、話し方次第で、相手への印象もまったく異なってきますね。
そのため、面接官は「最近読んだ本」というテーマで、就活生のトークスキルを判断しているのです。
読書習慣があるのか確認したい
プレゼンテーションスキルの次に面接官が見ているのは、「日頃から読書習慣があるのかどうか」「自発的に学ぶ意識を持っているのか」です。
学生時代から読書を通じ、知識を蓄える習慣を持っている人間は、社会人になってからも自ら足りない部分を補うために「自発的に収集活動を行う、読書を通じて学ぶ姿勢を持っている」と判断されます。
すなわち、「自ら学ぶ姿勢を持っているので、吸収も早く、成長スピードも早い、とても伸び代のある人材」として、高評価されるようになるのです。
ノースキルの人材を雇う「新卒採用」という場面ならではの視点、とも言えますね。
もし質問されている時点で感づいたら、単に本を読んでいることを伝えることに加えて「なぜその本を読んでいるのか」を伝えるようにしましょう。
知識量が知りたい
面接官は「あなたの知識量があるのか、あなたに知的好奇心があるか」を見ています。
社会人として働くことになると、必要なスキルはその業界の専門分野だけでは足りません。
取引先やクライアントと話を合わせるために、幅広い知識が求められる機会が増えるでしょう。
特に近年の傾向として、そのような状況を反映し、「自身の知識のストックを用いて、仕事をこなす人材」が求められるようになっています。
日頃から読書を行っている人間は、読書量に比例して知識のストック量が多くなります。
特に、学術的な書物が好きな人は、自分の知識の幅をアピールする良い機会になることでしょう。
あなたの興味を抱いている分野を知りたい
場合によっては選考を度外視して、就活生のことを知るために「最近読んだ本は?」と質問する面接官もいます。
面接官は、エントリーシートと面接を通じてあなたの合否を判断するわけですが、たったそれだけでは、あなたがどんな人間かなど分かるはずもありません。
この場合、読み手の思考や属性を投影する「本のジャンル」が重要になってきます。
特に個人面接では、学生の回答を元に深掘りを行うため、最初の糸口としてあなたの関心事を知ろうとする場合が多いです。
本好きな人におすすめの職種は以下の記事で解説しているので、仕事選びの参考にしてみてください。
アイスブレイクがしたい
さまざまな目的を解説してきましたが、そのどれとも違っている場合があります。
それはアイスブレイクです。
アイスブレイクとは、初対面の人に対して軽い雑談やゲームをして、緊張をほぐすことを意味します。
企業側が就活生の緊張をほぐしてあなたの素の状態を引き出すために、この質問を用いる場合があります。
面接で「最近読んだ本は?」に回答するための4STEP
これまで、「最近読んだ本」について問う5つの意図について見てきました。
続いて、実際にどのように回答すれば良いのか、その型を押さえましょう。
- 結論
- 動機
- 概要
- 学び
それぞれを文章にして表現すると、以下のようになります。
結論:「私が最近読んだ本は△△が書いた○○です。」
動機:「本を読むことになった経緯」
概要:「選んだ本の概要」
学び:「本から得た知識は何どのように活かされているか」
以下ではそれぞれのステップについて、具体的な解説をしていきます。
結論
まず、具体的な本のタイトルとその著者を述べましょう。
本のタイトルと著者名を簡潔に答えて、次に進みます。
動機
次に、その本を読んだ理由を説明します。
個人的な興味関心、ゼミの課題だったから、友人やメディアの影響など、動機を明確に伝えると良いでしょう。
概要
本に書かれている内容をまとめます。
主題や著者の意図を200文字程度でまとめ、詳細は掘り下げすぎないように注意しましょう。
学び
最後にその本から得た学びについて説明します。
この本によってどのような価値観が生まれ、それを企業にどのように活かしていきたいのかを説明します。
面接の「最近読んだ本」におすすめの本のジャンル

ここからは、就活の面接での「最近読んだ本」の返答におすすめの本のジャンルを紹介します。
- ビジネス書
- 自己啓発書
- 小説
- ノンフィクション
- 科学書
- 歴史書
- 自然科学書
- 芸術関連書
ビジネス書
面接で「最近読んだ本」としてビジネス書を挙げることは、特にビジネス職や管理職を目指す場合にとても効果的です。
ビジネス書は、業界の最新動向や成功事例、リーダーシップのスキルなどを学ぶのに役立ちます。
これらの本を読むことで、候補者が業界のトレンドに敏感であり、自己成長を重視していることを示すことができます。
さらに、具体的なエピソードや学びを面接で共有することで、自分の考えや価値観を伝えることができ、面接官に強い印象を与えられるでしょう。
自己啓発書
自己啓発書は、個人の成長や自己改善を目指す人にとってとても有益です。
面接でこのジャンルの本を紹介することで、自分自身を高める意欲があることを示すことができます。
自己啓発書は、モチベーションの向上や目標設定、時間管理の方法など、日常生活や仕事に役立つスキルを得られるのが魅力です。
面接官に対して、自己啓発に取り組んでいる姿勢を示すことで、前向きで成長志向のある人物であることをアピールできます。
小説
小説を最近読んだ本として紹介することも、面接での良い選択肢です。
特に文学や創造性を重視する職種においては、小説を読むことで得られる洞察力や想像力が評価されることがあります。
小説は、異なる視点や文化を理解する手助けとなり、感受性や共感力を高められるでしょう。
面接で小説を紹介する際には、その作品から得た教訓や感銘を受けた部分を具体的に説明することで、深い理解力と分析力をアピールできます。
ノンフィクション
ノンフィクションは、現実のできごとや人物に基づいた内容で、知識を深めるのに適しています。
面接でノンフィクションを紹介することは、知的好奇心が旺盛であることを示す良い方法です。
歴史、科学、政治、社会問題など、さまざまなテーマに触れることで、幅広い知識を持っていることをアピールできます。
特に、自分の専門分野に関連するノンフィクションを読むことで、専門性の高さを示すことができます。
科学書
科学書は、論理的思考や分析力を高めるのに役立ちます。
面接で科学書を紹介することは、問題解決能力やクリティカルシンキングを持っていることを示すことができます。
科学書は、具体的な事例やデータに基づいた説明が多く、実証的なアプローチを学ぶのに効果的です。
面接官に対して、科学的な視点から物事を考える力をアピールすることで、論理的な判断力を持つ人物であることを印象付けることができます。
歴史書
歴史書を最近読んだ本として挙げることで、過去のできごとから学びを得る姿勢を示すことができます。
歴史書は、時間を超えた視点を提供し、現在の社会や文化を理解する手助けとなるでしょう。
面接で紹介する際には、その内容が現代にどのように影響を与えているかを説明することで、深い洞察力と歴史的な視野を持っていることをアピールできます。
歴史に対する理解を示すことで、長期的な視点を持っていることを強調できます。
自然科学書
自然科学書は、自然界の法則や現象についての理解を深めるのに役立ちます。
面接で自然科学書を紹介することで、自然や環境に興味を持っていることを示せるでしょう。
これらの本は、観察力や探究心を高めるのに役立ち、科学的なアプローチを学ぶことができます。
面接官に対して、自然科学に対する理解や興味を示すことで、好奇心旺盛で知識を追求する姿勢をアピールすることができます。
芸術関連書
芸術関連書を最近読んだ本として紹介することは、創造性や感性を重視する職種において特に有効です。
芸術関連書は、視覚的な美しさや表現力を高める手助けとなります。
面接で紹介する際には、作品やアーティストから受けた影響やインスピレーションについて具体的に説明することで、独自の視点や感性をアピールできます。
芸術に対する理解を示すことで、クリエイティブな思考を持つ人物であることを印象付けることができるでしょう。
面接対策におすすめの本は以下の記事で紹介しているので、ぜひチェックしてみてください。
面接で「最近読んだ本は?」の例文
構成がわかったところで、続いて実際の例文を見てみましょう。
まず最初に、SHOWROOMでおなじみの前田裕二さんの著書、「メモの魔力」を例にとって見ていきましょう。
私が最近読んだ本は、前田裕二さんの「メモの魔力」です。(結論)
以前から前田さんの生き方や哲学に関心があり、店頭に並んでいたので読むことにしました。(動機)
この本は、メモについての話かと思いきや、メモを通じて自分の思考をクリアにする方法が紹介されています。(概要)
私もこの本を通じて、自分のメモから自分の潜在意識に対する気づきや、将来の方向性について思考を深めることができました。(学び)
こちらの例は、普段から前田さんを代表とした若き経営者起業家に関心があることのアピールになります。
また、最後の質問は、「自分が将来やりたいこと」とリンクしているので、面接官から深掘りの質問をされたとしても、答えることはそこまで難しくないはずです。
面接で「最近読んだ本は?」のNG回答ポイント
続いて、悪い例文を見ていきましょう。
NGな回答としては、大きく次の3つです。
- 「本は読まない」
- 「目的意識なしに、ただ趣味感覚で読んだ本」
- 「読んでいない本を“読んだ“と嘘をつく」
「本を読まない」という回答がNGなのは、明白ですよね。
自分から「読書習慣(学習意欲)はない」と宣言しているようなもの。
面接官も、こちらにアピールチャンスを与える目的もあって質問してきているのに、そもそも会話自体が成立しなくなってしまいます。
また、趣味の延長線上で選んだ本も、あまり印象が良くありません。
先ほど解説したように、「最近読んだ本」をわざわざ聞いているのは、5つの意図があります。
ですので、こちらも何の気なしに、本当に「ただ読んだ本」を答えてしまうと、とても浅い印象を与えてしまいかねません。
もちろん、そこにきちんと意義を見いだせれば問題はありません。
企業側の意図をくみ取った方が、面接官を満足させられる回答に近づくはずです。
また、”嘘をつく”のは、言語道断。
百戦錬磨の面接官からすれば、こちら側の嘘など簡単に見破られてしまうでしょう。
それに「大事な場面でも嘘をつくなんて、社会人になったときに虚偽の報告や記録改ざんをしかねないのではないだろうか」と、信用を失ってしまいます。
さいごに
今回は「あなたの最近読んだ本を教えてください」という質問を通じて、面接官の意図を5つの観点から解説しました。
そして私たちはどう答えれば良いのか、それぞれの観点に基づいて回答方法を取り上げました。
企業がなぜこの質問をするのか、質問の意図を汲み取って上手にアピールできるように回答内容を考えてみてください。
この質問が全てではありませんが、面接官の視点を意識することは、志望企業から内定をもらう近道になる可能性があります。
深掘りしすぎてはNGですが、「こう答えたら、面接官はどのように感じるだろうか?」を意識しながら、回答するようにしましょう!