就活でポートフォリオはどうする?内容や作成方法、例文を紹介
2024年3月20日更新
はじめに
就活でポートフォリオの提出が求められるなか、学生たちが抱える疑問の一つに、「ポートフォリオって具体的に何?」というものがあります。
ポートフォリオは、自己や自身の作品を効果的に紹介するための資料集であり、これが就活において力強いアピール材料となります。
通常、ポートフォリオの作品紹介部分が焦点に当たります。
しかし、就活では学生個々の個性や人柄も重視されるため、自己紹介部分の充実も大切です。
ただし、自己紹介の作成は一筋縄ではいかず、ポイントを押さえなければなりません。
そうでなければ、履歴書と同様に平凡な内容になり、他の学生たちとの差別化が難しくなってしまいます。
この記事では、まず初めにポートフォリオが何か、その基本的な概念を整理します。
そして、具体的な例文を交えながら、自己紹介の制作ポイントを紹介していきます。
これによって、学生たちはポートフォリオの本質を理解し、自らの魅力や特徴を効果的にアピールできるようになるでしょう。
自分らしいポートフォリオの制作を通じて、就活の舞台で際立つ存在となりましょう。
この記事は以下のような点を知りたい就活生を対象にしています。
- ポートフォリオって何?
- ポートフォリオの具体的な作成方法は?
- ポートフォリオの例文が知りたい
就活でポートフォリオの作成に悩んでいる方は、ぜひ最後までご覧ください。
上京を志す地方学生ならジョーカツ!
あなたのキャリアを加速させるチャンス!
無料で利用できる快適な個室シェアハウス、
東京までの交通費サポート付き
首都圏の注目企業への就活ならジョーカツ
首都圏の学生ならスタキャリ!
理想のキャリアを実現へと導く第一歩!
あなたにピッタリのキャリアアドバイザーを選び、
自分にマッチする優良企業をご紹介
首都圏企業のES添削から面接対策まで、就活ならスタキャリ
ポートフォリオの概要

初めにポートフォリオとは何なのかを簡単に紹介します。
ポートフォリオとは
ポートフォリオは、クリエイターやアーティストが自身の実績を効果的にアピールするための重要なツールです。
転職や就職活動の際の選考材料として利用されるほか、SNSなどで自らの活動を発信する際にも有用です。
また、アーティストの場合は個展などでポートフォリオブースを設置することが一般的です。
一般的には、ポートフォリオは「作品集」のように捉えられがちですが、元々は「書類入れ」を指す言葉だったと言われています。
すなわち、すべての作品をただまとめるのではなく、転職面接用途や個展での使用など、目的や用途に合わせて最適な内容を選定し、わかりやすく整理する必要があります。
ポートフォリオの制作には時間がかかるため、多くの人が過去に作成したものを再利用することが一般的ですが、本来は受け手に合わせて毎回最適なポートフォリオを構築する必要があります。
素晴らしい作品を持っていても、それが相手に響かなければ新しい仕事やチャンスに繋がりません。
したがって、「自己満足のポートフォリオ」ではなく、「相手の心を動かすためのポートフォリオ」を目指しましょう。
どんなポートフォリオにおいても、この考え方を心に留めておくことが重要です。
ポートフォリオの構成
ポートフォリオは、以下の4つの項目から構成されています。
- 目次
- 自己紹介
- 作品
- 連絡先
これらの項目のうち、ポートフォリオの質を向上させる上で特に重要なのは作品と自己紹介です。
作品によって実績やスキルをアピールすることも重要ですが、就活では「一緒に働く人としてどうか」といった人間性や個性も注目されます。
このため、自己紹介の項目がどれだけ魅力的かがポートフォリオ全体の印象を左右します。
就活のポートフォリオで自己紹介の内容は
基本情報
基本情報欄では、主に氏名、生年月日、希望職種、大学・学部などの基本的な情報を記載します。
このセクションは、履歴書の記載内容とほぼ重なる部分と言えます。
また、履歴書に添付する顔写真は、採用担当者に自分の姿をイメージしやすくする一助となります。
顔写真がない場合よりも、視覚的な印象が強まり、記憶に残りやすくなります。
そのため、基本情報には顔写真を添えることが効果的で、採用担当者とのコミュニケーションをスムーズに進める手段となります。
基本情報欄を記載する際の注意点として、情報を単なる羅列にとどめず、自己のアイデンティティやセンスを感じさせるようなレイアウトやデザインに工夫することが挙げられます。
単なるテキストの列挙ではなく、情報の配置やフォントの使い方などに気を使い、採用担当者に自分らしい印象を伝えることが大切です。
過去経歴
過去経歴のセクションでは、これまでの社歴や経験した業務、自身の人生における重要なターニングポイントなどを簡潔にまとめることが求められます。
特に新卒就活の際には、クリエイティブ系や開発系のアルバイト経験や、大学時代に学んだ内容、どのような作品を制作したか、また受賞歴があればそれらを具体的に記載すると良いでしょう。
このセクションでは、作品そのものに焦点を当てるのではなく、「作品作りに影響を与えた自身の経験や出来事」や「作品制作においてどのような役割を果たしたか」などにフォーカスを当てることが重要です。
過去の経歴を振り返りながら、自身の成長やスキルの向上に寄与したポイントを強調し、採用担当者に自分の専門性や貢献度をアピールできるよう心がけましょう。
これにより、過去の経歴が将来の仕事にどのように寄与するかを明示し、ポートフォリオ全体の一貫性を保つことができます。
スキルセット
スキルセットのセクションでは、保有するスキルについて詳細に記述します。
たとえば、PhotoshopやIllustratorなどのデザインツールの利用スキル、HTML/CSSを用いたコーディングのスキル、またC言語やJavaScriptといったプログラミング言語のスキルなどを挙げましょう。
これに加えて、「どの程度のスキルを有しているのか」を伝えるために、以下のような工夫がポイントとなります。
スキルの程度を表現する方法
星の数やレーダーチャートを活用して、各スキルの習熟度を視覚的に示すことで、採用担当者にスキルの強さを直感的に伝えることが可能です。
作品の紹介
各スキルをどのように活かして作品を制作したかを具体的に説明することで、スキルの実践経験や能力をアピールできます。
スキルの習得時期
各スキルをいつ頃から習得し、どれくらいの期間でそのスキルを向上させたかを明示することで、成長過程やスキルの継続的な向上に対する姿勢を示すことができます。
資格の記載
スキルの習熟度を裏付けるために、関連する資格や認定を取得したことを明記することで、スキルの信頼性を高めることができます。
志望企業の求めるスキルに焦点を当て、その企業にとって特に重要なスキルについて詳しく説明することで、アプリカントとしての適性をより明確にアピールできます。
趣味や特技
趣味や特技のセクションでは、自分が真剣に打ち込んでいる活動や継続的に行っていることにフォーカスして紹介しましょう。
この部分は、自己表現とともに企業とのコミュニケーションのきっかけを提供するポイントとなります。
趣味や特技の具体的な内容を詳細に記載することで、自身の個性や好奇心、努力する姿勢をアピールできます。
また、企業側も候補者が社風や働く環境に適応できるかどうかを知りたいと考えており、趣味や特技を通じてその一端を伝えることができます。
たとえば、趣味が写真撮影であれば、どのような被写体に興味を抱いているかや、最近挑戦した写真のプロジェクトについて触れることができます。
また、特技が言語学習であれば、どの言語に焦点を当てており、どのような学習方法を取っているかなどを具体的に述べましょう。
これにより、趣味や特技が単なるリストではなく、あなたの個性や積極的な姿勢を示す手段となり、企業との関係構築に寄与します。
自己PR
自己PRでは、簡潔に自身の強みや入社後の展望、目標などを伝え、採用担当者に自身の存在価値を伝えることが求められます。
この際、企業が求める人物像や仕事の特徴に焦点を当て、自分の強みがその仕事にどのように適応されるかを具体的にアピールすることが重要です。
たとえば、その企業が重視する価値観やスキルに基づいて、自身の経験や能力を強調すると、採用担当者はあなたがチームやプロジェクトにおいてどれほど価値を提供できるかを見極めやすくなります。
その際、具体的な実例やエピソードを交えることで、説得力を増し、あなたの強みがどれだけ実際の業務に貢献できるかを示唆できます。
自己PRはあくまで相手に「なぜこの人を採用すべきか」を納得感をもって伝える場です。
従って、企業とのマッチングや貢献度に焦点を当て、採用担当者にとっての決め手となる要素をしっかりとアピールすることが肝要です。
就活のポートフォリオで作品の紹介方法は
作品紹介パートには、以下の要素が必要です。
- 作品画像
- 作品タイトル
- 作品の概要説明(プロジェクト名、担当した役割など)
- 作品の見どころ
- 作品作成時の注力ポイントやエピソード
- 作品の成果
各作品を履歴書のように捉えると分かりやすいでしょう。
作品紹介パートでは、作品の魅力とその舞台裏に潜むエピソードをできるだけわかりやすく、簡潔に伝えることが求められます。
このセクションは、自身の制作物を魅力的に紹介し、ポートフォリオ全体の印象を高めるための重要な要素です。
就活でのポートフォリオ作成時の注意点は
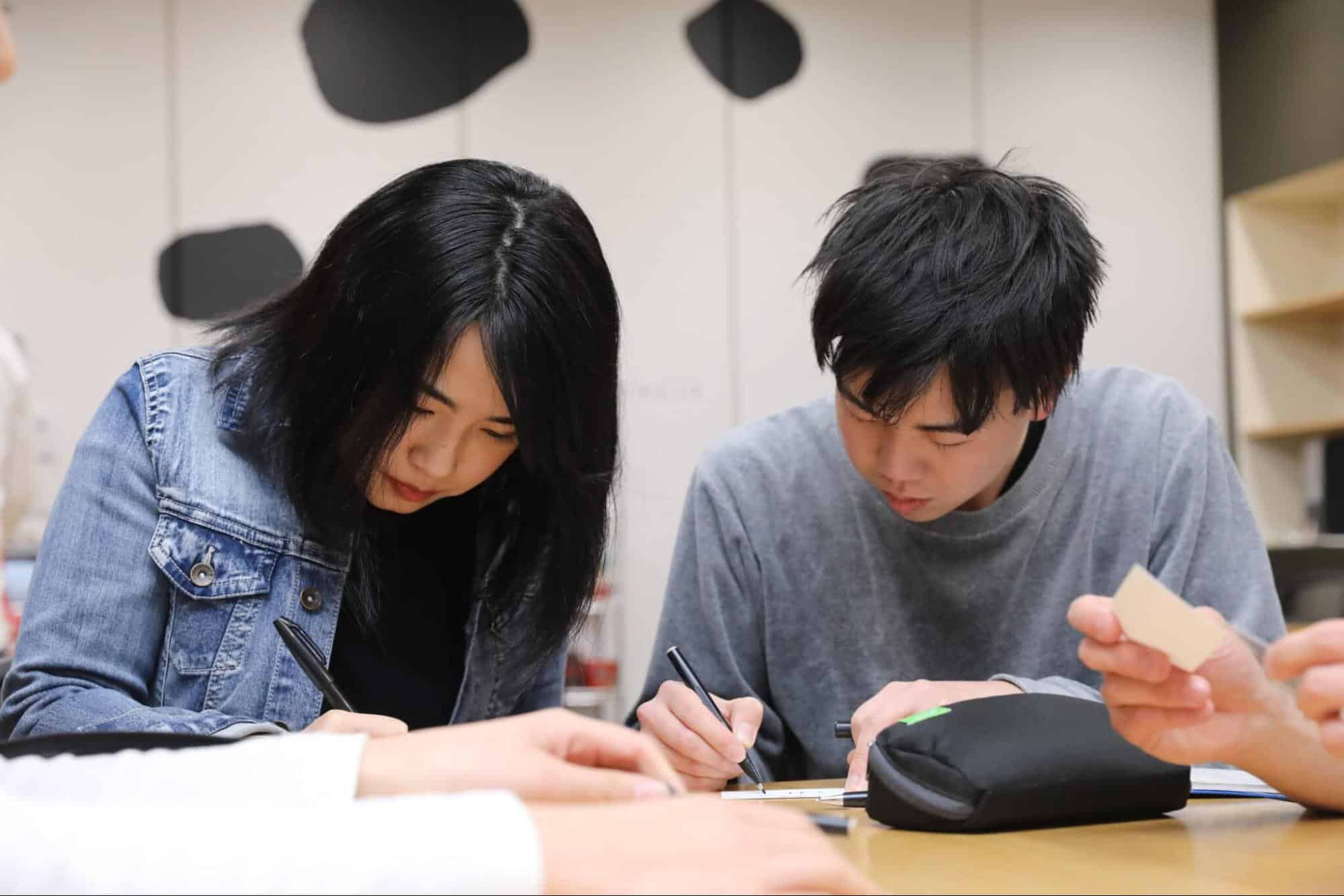
ポートフォリオ作成時に注意したい点をまとめました。
ぜひ参考にしてください。
作品を単に羅列しない
就活において、ポートフォリオは就活生の「制作スキル」や「個性」をアピールする貴重な手段です。
これに加えて、現実の業務において不可欠な「問題解決能力」「プレゼン能力」「コミュニケーション能力」なども採用担当者にアピールする重要な要素となります。
単に作品を羅列しただけでは、就活生の実力や特徴を効果的に伝えることが難しく、書類選考で落選するリスクが高まります。
選考を勝ち抜くためには、ポートフォリオの作成に時間と労力をかけ、魅力的かつ効果的にアピールできる仕上がりを目指しましょう。
企業に合わせて内容を変える
次に、企業に応じてポートフォリオに載せる作品を慎重に選定しましょう。
たとえば、WEBデザイナーのポジションに応募するのであれば、WEBサイトのデザインを中心にアピールするのが効果的です。
これによって、企業が求めるスキルに合致した作品を通じて、就活生の専門性を際立たせることができます。
また、紹介する作品の順番にも工夫が必要です。
採用担当者は多くのポートフォリオを確認しなければならないため、最初に目を引くインパクトのある作品や完成度の高い作品から紹介すると良いでしょう。
複数のジャンルの作品を披露する場合は、企業の雰囲気や求められるスキルに適した順番で作品を配置するようにしましょう。
作品の量に注意する
一方で、ポートフォリオに載せる作品の数はバランスが重要です。
理想的な作品数は5~10作品前後であり、各作品に1ページ(または見開き1ページ)を充て、総ページ数を15~20ページに抑えることが望ましいです。
作品数が多すぎると、各作品への注目が薄れ、印象が弱まる可能性があります。
逆に、作品数が少なすぎると、採用担当者が就活生の実力を適切に評価することが難しくなります。
簡潔にまとめる
特に自己紹介は、簡潔にまとめることが肝要です。
過度な情報量は逆効果となり、アピールしたいポイントが埋もれてしまい、採用担当者にとっても理解しにくくなります。
担当者は制限された時間内で多くのポートフォリオを確認しなければならないため、長文で内容が分かりにくいポートフォリオまでじっくりと見ることは難しいでしょう。
読み手が「この学生はこういう感じなんだ」と迅速に理解できるように、要点を絞り込み、余分な情報は取り除くことが重要です。
要点を的確に伝え、採用担当者に印象を残すことが必要です。
その際、箇条書きは非常に有効です。
箇条書きを使用することで、情報が整理され、わかりやすい形でアピールポイントを提示することができます。
シンプルで効果的な自己紹介を心がけ、採用担当者に与える印象をポジティブに保ちましょう。
誤字脱字やファイルの形式に注意する
最後に、ポートフォリオの提出方法やファイル形式、誤字脱字にも留意する必要があります。
企業によって異なる提出方法が存在し、最近では紙媒体よりもデータ形式で提出する場合が増えています。
提出する際には、指定されたファイル形式や容量などを確認し、適切に対応しましょう。
指定された形式以外で提出すると、選考の対象外となる可能性もあるため、注意が必要です。
自分らしさをアピールする
ポートフォリオにおいて、自分自身の個性を際立たせることも重要です。
以下は、自分らしさを引き立てるためのアイデアです。
これらの工夫を通じて、独自のアプローチで個性をアピールしていきましょう。
自分の作品と同じような世界観のデザインにする
自分の作品と同じ雰囲気やテーマ性をポートフォリオ全体にも取り入れることで、一貫性が生まれます。これにより、見ている人が「この人の世界観がよく分かる」と感じやすくなります。
提出形式の中で、自分らしくアレンジできる箇所を探す
指定の提出形式がある場合でも、その中で自分の特徴や好みを反映させられるポイントを見つけましょう。
たとえば、自己紹介のページを自身の作品とリンクさせ、統一感を持たせることができます。
形や素材にこだわることも、ポートフォリオに独自性と印象を加える手段です。
四角ではなく丸や三角、またはファー、布などの非伝統的な素材を取り入れることで、視覚的なインパクトを高められます。
これらの工夫によって、ポートフォリオはより自分らしさを表現し、印象深いものとなるでしょう。
就活のポートフォリオで自己紹介の例文は

就活で求められるポートフォリオにおいて、自己紹介の例文を紹介するので、ぜひ参考にしてください。
例文1
初めまして、○○と申します。(生年月日)生まれ、(出身地)出身の(学部・学科)出身です。
私はデザインに情熱を持ち、(専攻や関連のアルバイト・プロジェクト経験)を通じて、クリエイティブなアイデアを形にすることが得意です。
特に(特定の分野や技術)に興味を持ち、それを駆使して問題解決に挑むことが日常茶飯事です。
(過去の実績やプロジェクト)では、(具体的な業績や成果)を挙げ、(学びや得たスキル)についても触れることで、私のデザインにおけるアプローチやスタイルを理解していただけるかと思います。
また、(趣味や特技)では(趣味や特技に込めた思いや活動)を通じて、私がどのような価値観や考え方を持っているのかを知っていただけると嬉しいです。
ポートフォリオを通じて、私のデザインに込めた情熱やクリエイティブな視点を感じていただければ幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。
例文2
こんにちは、○○です。(生年月日)生まれ、(学部・学科)出身の(学生・職業)です。
私は常に新しいチャレンジに興味津々で、デジタルマーケティングの世界で自分を試し、成長してきました。(学校や職場)での経験を通じて、戦略的なマーケティングとクリエイティブなアプローチがビジネスにどれほど影響を与えるかを学びました。
特に(特定のプロジェクトやスキル)において、(具体的な業績や成果)を上げることができ、その経験を通じてデータ分析やストーリーテリングのスキルを磨きました。また、(業界の最新トレンドや技術)に敏感であり、それを取り入れることでプロジェクトの革新性を高めています。
(趣味や特技)では(趣味や特技に込めた思いや活動)を通じて、私がどのような価値観を持っているのかをお伝えできればと思います。
このポートフォリオを通じて、私のマーケティングにおける姿勢やスキルに少しでも興味を持っていただければ嬉しいです。何かご質問がありましたら、お気軽にお知らせください。
まとめ
この記事では、就活で求められることがあるポートフォリオについて、概要、作成方法、注意点などを解説してきました。
初めに、基本情報や過去経歴、スキルセット、趣味や特技、そして自己PRなど、ポートフォリオに含まれる要素を具体的に把握しました。
これにより、ポートフォリオの全体像が明確になり、構築すべき要素が理解できるようになりました。
その後、各要素ごとに具体的な作成ポイントや注意事項を指摘し、読者が自身のポートフォリオをより魅力的かつ効果的に仕上げる手助けとなる情報を提供しました。
特に、自己紹介やスキルセットの記載方法、趣味や特技のアピール方法については、具体例や工夫のアイデアを交えながら理解を深めました。
また、ポートフォリオの提出に際しては、企業によって異なる指示があることも確認し、適切なフォーマットやファイル形式で提出することの重要性に触れました。
これにより、読者は企業ごとの要望に的確に応えるポートフォリオを構築する際のポイントを押さえることができます。
総じて、本記事を通じて就活におけるポートフォリオ作成の基本から具体的なアプローチまでを理解し、自身のアピール力を最大限に引き出す手段としてポートフォリオを活用する一助となるでしょう。








