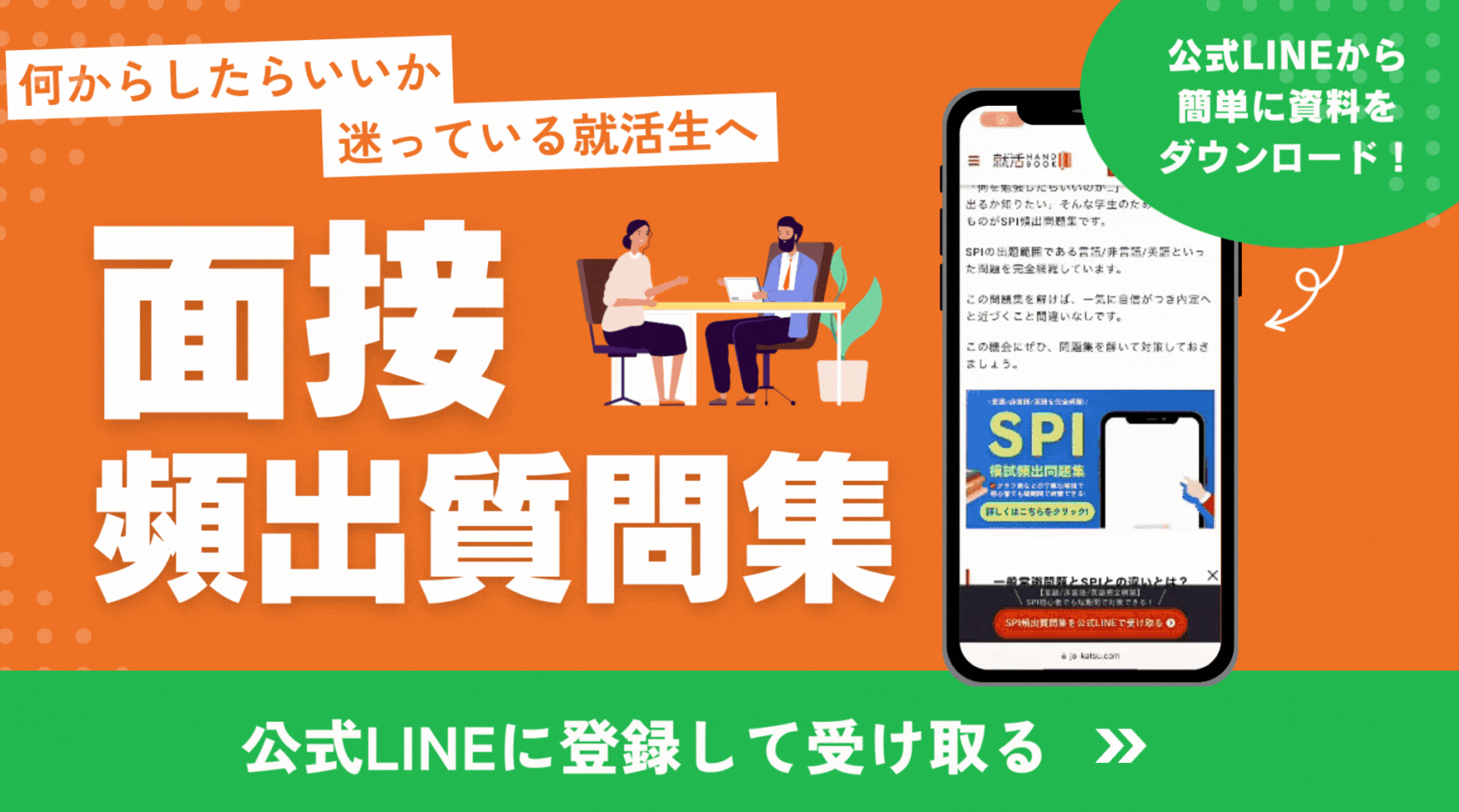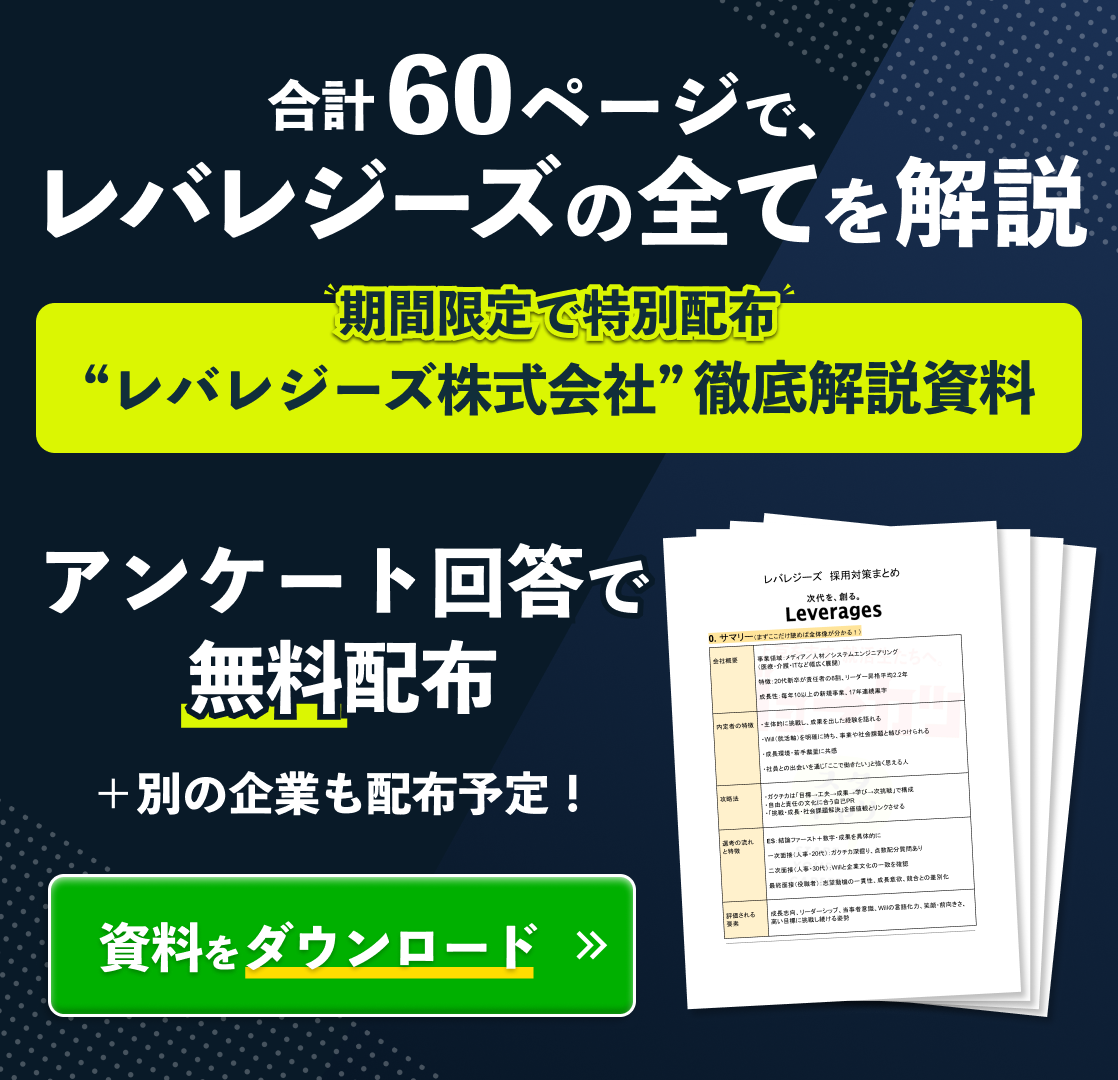口頭試問がわからないときはどうすべき?対策法や例を紹介
2024/3/20更新
はじめに
就活の選考スタイルは多岐にわたり、その一環として口頭試問があります。
通常、選考の形式としては、書類選考や面接、グループディスカッションなどが思い浮かぶかもしれませんが、近年では口頭試問を導入する企業も増加しています。
したがって、口頭試問に対する対策は不可欠であり、事前の準備を怠ると、スムーズな進行が難しくなり、不合格の可能性も高まります。
就活を成功させるためには、細部にわたる対策が重要であり、可能性のある要素にはどんな小さな点にも注意を払う必要があります。
また、口頭試問の選考が行われていなくても、対策は無駄にならず、他の選考でも活かすことができます。就活で行われる「口頭試問」について、基本的な定義から攻略方法まで理解していきましょう。
この記事は以下のような点を知りたい就活生を対象にしています。
- 口頭試問って何?
- 口頭試問についてわからないときどうすればよいか
- 口頭試問で良い印象を与えるにはどうればよいか
口頭試問に興味がある方は、ぜひ最後までご覧ください。
【面接頻出質問集】100種類の回答例をいつでもスマホからチェックできる!
面接対策に悩んでいる方にピッタリの面接頻出質問集を用意しました。
質問と回答例は、全部で100種類あります。
口頭試問の概要

初めに口頭試問とはどんな面接の形式なのかを簡単に紹介します。
口頭試問とは
口頭試問は、面接官からの質問に対して口頭で答えていく試験の一形態です。
通常、時事問題や一般教養に関する質問が多く、学生の知識や学力を測定することが主な目的となります。
この試験では、単に知識や能力だけでなく、回答の内容やその表現方法、さらにはわからない場合の対応力など、筆記試験では測りきれない要素も評価されます。
つまり、単なる情報の把握だけでなく、それをどれだけ的確かつまりどのように伝えるかが重要とされています。
また、自身の意見や考えを明確に表現できるかどうかも評価の対象となります。
たとえば、時事問題に関する質問が出る場合、単なる事実の把握だけでなく、その問題に対する自分なりの意見や立場をしっかりと伝えることが求められることもあります。
また、トピックが専門的な場合は、その分野における専門的な知識や見識も問われることがあります。
したがって、口頭試問に対する準備は、単なる事前知識の充実だけでなく、意見や考えを明確にまとめ、それを自信を持って表現できるようなスキルも同様に重要です。
対策を怠らず、様々なシナリオに備えることで、口頭試問による選考を成功させる可能性が高まります。
口頭試問と通常の面接の違い
採用担当者からの問いに対して口頭で答えるという点で、口頭試問と面接は一般的に類似しています。
このため、これらを混同する人が多いのは理解できますが、厳密には異なる点を理解しておくべきです。
最も大きな違いは、出題される問題の性質にあり、口頭試問では問題が提示され、一定の知識や発想力を駆使して解決を目指します。
それに対して、面接の場合は自己に焦点を当て、知識や発想力を問われるよりも、過去の経験や人柄がより中心になることが一般的です。
具体的な問題に対して回答するのが口頭試問であり、「○○という問題について、あなたはどう思いますか?」のような実践的な問いに対する解答が求められます。
一方で、面接では、「学生時代、どのようなことを経験しましたか?」といった過去の経験に基づいた質問が頻出し、自分自身に関する情報や過去の実績に基づく回答が期待されます。
このような違いを考えると、口頭試問と面接の性格には明確な違いがあることが理解できます。
口頭試問がわからないとき
口頭試問がわからないときはどうすれば良いのでしょうか。結論、わからないと言うべきです。
口頭試問は基本的に難しい選考の一環であり、時には質問の内容や意図が不透明な場合もあります。
こうした状況では、率直に分からない旨を伝え、不明瞭な点について詳細に尋ね、理解を深めた後に回答に移るのが賢明です。
質問内容を正確に理解せずに適当な回答をすると、まったく意図が通らない回答になり、場合によっては評価が得られない可能性があります。
さらに、的外れな回答は問題解釈力が不足していると見なされ、悪い印象を与える可能性も考えられます。
口頭試問では質問の本質を正確に理解することが前提条件であり、それができていない状態で回答するのは危険です。
質問内容に疑問が生じた場合は、その点を明確にすることで評価が下がることはありません。
知識を装った回答をすることは避け、正直な姿勢で臨むことが重要です。
口頭試問で好印象を与えるには

口頭試問で好印象を与えるためのポイントについて、3つ挙げて説明していきます。
自分の言葉で話す
自分の言葉で話しましょう。
自分自身の個性を際立たせるためには、他人の意見を参考にする場合でも、その際に自分がどのように感じたのか、どのように考えたのかといった主観的な視点を交えることが肝要です。
また、客観的な事実を述べる場合も同様で、それに対する自身の意見や考え方を掘り下げて説明することで、より深い洞察が伝わり、好印象を与えやすくなります。
問題の解決策を提示する際には、他者の意見や客観的な事実を参考にすることがあります。
これらのアプローチは完全に誤ったものではありませんが、全ての問題にこれらの手法だけを用いて答えると、自己表現が十分に伝わりにくくなります。
単に意見や事実を提示するだけではなく、その背後にある自分の思考や価値観を明示的に伝えることで、対話の深化が図られます。
これにより、面接や口頭試問などでの印象はより深みを増し、独自性をアピールすることができるでしょう。
自分らしさを的確に表現することが、成功に繋がる重要な要素と言えます。
声のトーンに気を配る
口頭試問では、回答の内容だけでなく、話し方も印象形成において極めて重要なポイントとなります。
たとえどれほど論理的で洗練された意見を持っていても、小さな声でぼそぼそと話してしまうと、面接官が聞き取りにくいというだけでなく、自信がないと受け取られる可能性も潜んでいます。
言葉遣いや発音、話すスピードなどは、面接官が快適に聞き取りやすいかどうかに大きく影響します。
しっかりとした声量や明瞭な発音で意見を述べることは、自信や説得力を伝える上で非常に効果的です。
逆に、適切な話し方を怠ると、優れた回答が十分に発揮されない可能性があります。
緊張感や緊張を和らげる工夫も必要です。
たとえば、事前に模擬面接を行い、自分の発声や表現に自信をつけることができるでしょう。
口頭試問においては、回答内容と話し方の両方を磨くことが、良い印象を与え、成功につながる秘訣と言えるでしょう。
姿勢や表情に気を配る
難しい質問に対してスマートに答えることができなくても、正しい姿勢や前向きな表情を備えた学生は、明るい印象や意欲的な印象を与えやすくなります。
特に緊張すると、背中が丸まってしまったり、表情が硬直してしまったりすることがあります。そうした状態では、印象が損なわれる可能性が高まります。
姿勢や表情は、単なる身体の動きだけでなく、内面の状態や感情をも反映します。
縮こまった姿勢や硬い表情は、不安や緊張感を相手に伝える可能性があります。
逆に、背筋を伸ばし、積極的な表情を心がけることで、自分の自信やポジティブなエネルギーを相手にアピールできるでしょう。
また、難しい質問に正確に答えることが難しい場合でも、明るい態度や意欲的な様子は、対話相手に好感を与えます。
このようなポジティブな印象は、時に質問に対する理解不足を補ってくれることもあります。
したがって、難しい状況でも姿勢や表情に気を付け、自らのポジティブな一面をアピールすることは、成功に向けた重要なステップとなります。
口頭試問の対策法は
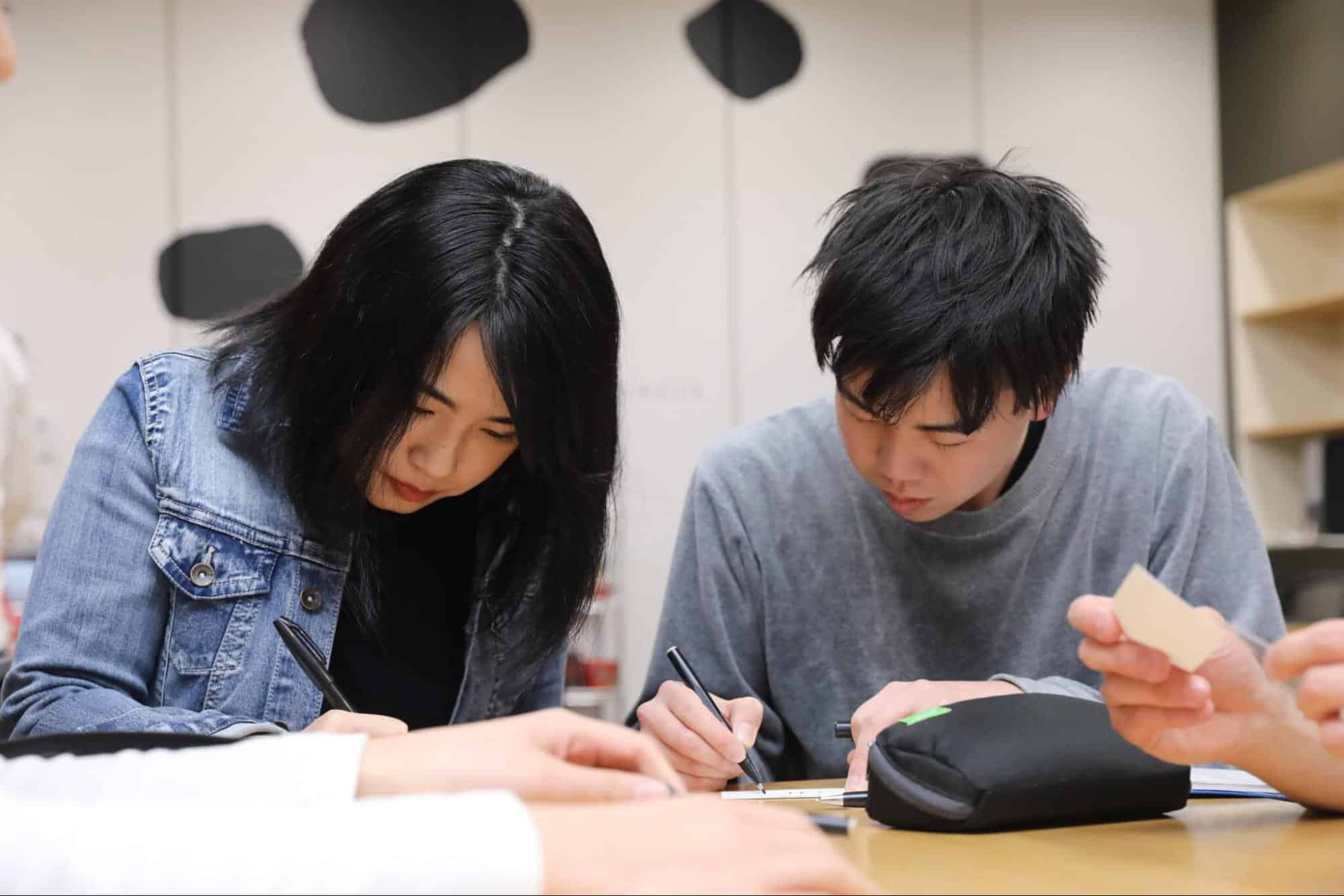
口頭試問の事前対策について、3つを挙げて説明していきます。
リラックスする
リラックスできるように練習をしておきましょう。
口頭試問には緊張感がつきものであり、その雰囲気から難しく感じられることがよくあります。
ただし、イメージだけで緊張感を抱くことは避けるべきです。
難易度を先入観で高く設定してしまうと、当日に緊張が高まり、思考がスムーズに働かなくなる可能性が増します。
リラックスした状態で臨むことが、スムーズな回答を導き出す鍵となります。過度な緊張は思考の障害になりかねないため、注意が必要です。
ただし、完全に緊張しない状態も望ましくありません。
ある程度の緊張は、集中力を高め、パフォーマンスを向上させる助けになります。
問題は、過度な緊張がパフォーマンスを制約する場合です。
自分にとって適切な程度の緊張を認識し、それを受け入れることが重要です。
自信がつくまで十分な事前対策を行うことも、リラックスの一環として考えられます。
緊張を受け入れ、それをプラスに変えるためには、難しく受け止め過ぎず、自信をつけるための準備を怠らないことが大切です。
適切な緊張とリラックスのバランスを見つけ、自分の最高のパフォーマンスを引き出せるよう心がけましょう。
たとえば、模擬面接を行うことが対策として挙げられます。
慣れた環境であれば、適度にリラックスをすることができるでしょう。
質問の意図を理解する訓練をする
口頭試問において成功するかどうかは、質問の意図を正確に理解できるかどうかが鍵となります。
質問の意図を正確に把握できないと、回答の方向性が誤ってしまい、たとえ正解が出たとしても、企業が期待していた回答にはなり得ません。
口頭試問では何らかの問題が提示され、それに対して口頭で解決策を示すことが基本的な構図ですが、単に解決策を示すだけでは手放しで高い評価を得ることは難しいのが現実です。
的確な解決策を提示することはもちろん重要ですが、さらに進んで「企業が求める的確な解決策」を提供する必要があります。
質問を表面的に理解するだけでなく、その質問を通じて企業が何を知りたがっているかまで考察し、深層に潜む意図を読み取りながら回答を構築することが不可欠です。
質問の奥にある企業の期待や課題を把握し、それに応じて的確で戦略的な回答を提示することが、高い評価を得る鍵となります。
問題解決能力だけでなく、洞察力や柔軟性も求められるため、深い思考と戦略的なアプローチが求められる口頭試問においては、的確な質問の理解が成功への一歩と言えるでしょう。
事前に知識を得ておく
上手に口頭試問に回答するためには、時事問題や対象となる業界に対する理解を深め、基本的な知識を身につけることが不可欠です。
口頭試問の質問は通常、実際の問題や業務に即して出題されることが多く、基本的な知識がないと質問の内容を理解することが難しい場合もあります。
質問の意味を尋ねること自体は問題ありませんが、それが一般的な常識や業界の基礎的な範囲内であるならば、事前の準備不足が印象に残り、評価を下げる可能性があります。
質問に対する巧みな回答だけでなく、分からない質問に対してもマイナスの印象を与えないようにするためにも、基本的な知識を事前に身につけておくことが必要です。
口頭試問は知識をベースにして、自身の考え方やアイデアを組み合わせて問題の解決策を提示するものです。
そのため、しっかりと基礎部分を築くことが、成功への確かな一歩となります。
特に、その業界に関する知識を得るためには、企業研究が不可欠です。
企業が置かれている状況や業績、市場の動向などを調査し、インタビューの際に使える情報を把握することが重要です。
関連する記事や資料を参考にすることもおすすめです。
しっかりと準備を重ね、自信を持って臨むことで、口頭試問を成功に導くことができます。
口頭試問に備えた対策として、日常的に目にするニュースを選んで誰かに話し、自分の考えを述べることが有益です。
これにより、自分の言葉で情報を整理し、論理的な思考を養うことができます。
また、相手の意見にも耳を傾けることで、新たな視点や気づきを得ることができるでしょう。異なる意見や視点からのフィードバックは、口頭試問においても役立つことがあります。
さらに、テレビ番組を通じて世の中の出来事を考察することもおすすめです。
解説者や専門家の意見を聞くことで、問題やテーマに対する多様な立場やアプローチを知ることができ、それが口頭試問で求められる柔軟性や知識の幅を広げる手助けとなります。
これらの対策は、口頭試問において問われる時事問題や業界に関する質問に対する洞察力や深い理解を養うために効果的です。
自らが情報に触れ、他者との対話を通じて考えを磨くことで、的確かつ柔軟な回答が可能になります。
口頭試問においては、日頃の積み重ねが自信となり、自分の言葉で的確に伝える力を発揮できるようになります。
4 5


口頭試問の例
口頭試問の評価ポイントを理解しても、「具体的にはどのような質問が出題されるのか」という疑問を抱えている方もいるかもしれません。
以下では、口頭試問でよく見られる質問傾向と具体的な質問例について解説します。
これにより、どのような問題に対処するかを理解し、自分の考えを事前に整理しておくことが重要です。
時事問題について
時事問題に触れるだけでなく、独自の見解を述べることを心がけましょう。
筆記試験では試験日前に問題を作成できますが、口頭試問はその場で面接官からの質問が行われるため、試験当日の最新ニュースが出題される可能性もあります。
ですので、口頭試問の当日もニュースを確認することをお勧めします。
- 少子高齢化についてどう思いますか
- 最近、どのようなニュースが気になりますか?
一般常識について
一般常識をテストする問題は、社会人として必要な基本的な一般教養があらかじめ備わっているかを評価するために使われます。
適切な一般教養があると、他のビジネス関係者と円滑にコミュニケーションをとることができ、失礼な印象を与えずに済むでしょう。
- 取引先とのメールのマナーを教えてください
- 電話をする時に気をつけるべきことを教えてください
志望企業について
志望企業に関する質問は、応募者が企業研究を十分に行い、業界に深く理解を持った上でなぜその企業を選んでいるのかを評価するためになされます。
企業側も、十分な企業研究を行っていない学生を採用することで、入社後のギャップや早期離職のリスクを回避し、また入社意欲の低い学生に内定を出してしまうことを避けるために、志望動機や選考理由について丁寧に質問します。
徹底的な業界研究や企業研究を行い、巧みにその知識を活かして回答することで、入社に対する真摯な意欲をアピールすることが重要です。
- 当社のSDGsについて考えていることは何ですか
- 当社の企業理念について意見はありますか
まとめ
この記事では、口頭試問について概要、わからないとき、好印象の与え方、対策法、例を解説してきました。
口頭試問に対して難しいとの印象が根強く、実際にここで詰まる人は決して少なくありません。
通常の面接とは異なる形式ゆえ、戸惑いがちであることは理解されますが、口頭試問が特に難解なものであるというわけではありません。
重要なのは、事前の準備が整っているかどうかや、面接との区別が明確であるかといった点です。
口頭試問でつまずきやすいのは、事前の準備が不足していたり、通常の面接と混同してしまったりすることが原因です。
正しい答えを的確に提示できるように、事前に十分な知識を蓄え、面接との相違点を明瞭に把握しましょう。
何が問われているのか、どのような評価が行われているのかを理解することで、口頭試問の難しさに対するイメージが軽減されるでしょう。
緊張感を抱きつつも、リラックスした状態で試験に臨み、問われた知識や思考力を巧みにアピールすることが肝要です。
このような心構えと準備をもとに、口頭試問を成功に導くために努力しましょう。
また、わからないときは臆せずにわからないと言うようにしましょう。
わからないときは、不明瞭な点について詳細に尋ね、理解を深めた後に回答に移るのが賢明です。