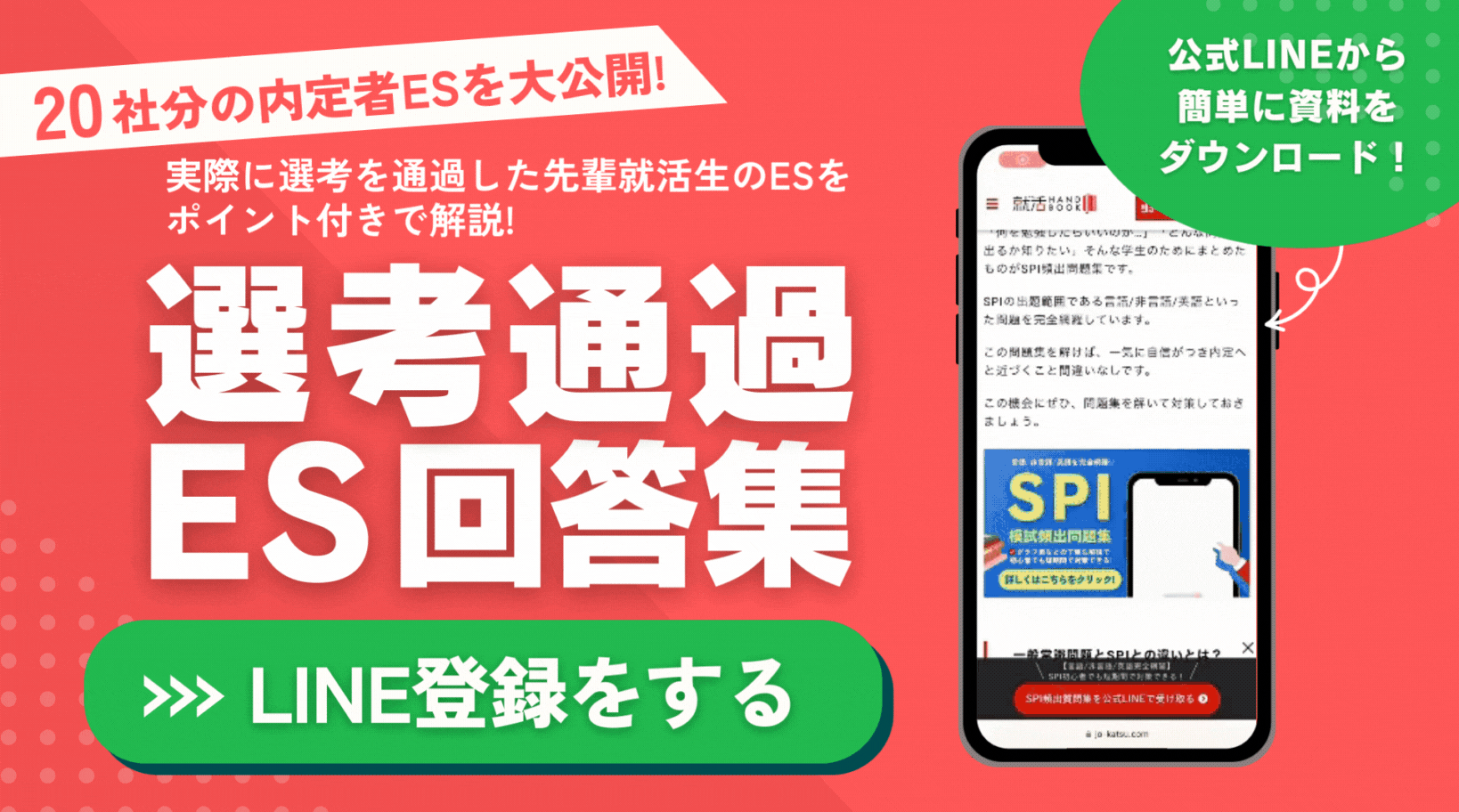志望動機で「やりがい」を伝えるには?納得感ある言い換えと例文
2025/12/28更新
就職活動の志望動機で「やりがいを感じる」と答える人は多いですが、この言葉だけでは採用担当者に熱意や個性が伝わりづらく、抽象的な印象を与えてしまいます。
この記事では「やりがいを感じる」と効果的に伝えるための言い換え表現や構成のコツ、さらに職種別の例文5選を紹介します。あなたの「やりがい」を具体的な言葉に変え、共感される志望動機を完成させましょう。
【選考通過したエントリーシートを大公開】先輩就活生のエントリーシートを見れば選考通過のヒントが得られるかも?!
「エントリーシートに正解はあるのか」「書き方が良く分からない…」こんなことを考えたことはありませんか?
就活生にとって、エントリーシートは第一関門ともいえるものです。
今回は、選考を通過したエントリーシートを20社分用意しました。
各エントリーシートにはポイント付きで解説しています。
志望動機で「やりがい」をそのまま使うのはなぜNG?
志望動機で「やりがい」をそのまま使うのがNGとされる理由は以下の3つです。
- 抽象的で具体性に欠ける
- 企業への貢献度が見えない
- 他の応募者との差別化ができない
多くの就活生が口にする「やりがいを感じたい」という言葉ですが、実はこの言葉をこのまま使うと採用担当者にマイナスの印象を与えることがあります。それぞれについて詳しく解説するのでご覧ください。
抽象的で具体性に欠ける
「やりがい」は人によって意味が異なります。達成感・貢献・成長など幅広い概念を含むため具体的なイメージが伝わりにくく、結果的に「熱意が薄い」「企業理解が浅い」と印象を与え、評価を落としてしまう可能性があります。
志望動機でやりがいを伝えるにはできるだけ具体的に話をする必要があるでしょう。
企業への貢献度が見えない
企業が志望動機として知りたいのは「あなたが何をしたいか」だけでなく、「入社後にどのような貢献をしてくれるのか」という点です。
単に「やりがいを感じたい」と伝えるだけでは、自分の満足を優先しているように聞こえ、企業にとってのメリットが伝わりません。
あなたの「やりがい」が企業の求める人材像や事業内容とどう結びつき、具体的な行動や成果に繋がるのかを明確に示す必要があるでしょう。
他の応募者との差別化ができないから
多くの応募者が「やりがい」という同じ言葉を使うため、印象が残りにくくなります。他の応募者と差別化し採用担当者の印象に残るためには、あなた自身の経験や価値観に基づいた独自の言葉で表現し、具体性を持たせることが必要です。
「やりがい」を軸にした志望動機への採用担当の本音と評価ポイント
採用担当者は、就活生の「やりがい」に関する志望動機をどのように捉えているのでしょうか。多くの学生が「やりがい」を口にする中で、響く志望動機とそうでない志望動機には明確な違いがあります。
採用担当者が抱く「やりがい」志望動機への懸念
「やりがい」という言葉に、採用担当者は時に懸念を抱くことがあります。それは「受け身な印象を与える可能性がある」という点です。仕事は与えられるものではなく、自ら課題を見つけ解決し、価値を創造していくプロセスが必要です。
単に「やりがいを感じたい」という姿勢では、「困難な壁にぶつかったときに逃げてしまうのではないか」「主体性に欠けるのではないか」との印象を与えることになるでしょう。
高評価につながる「やりがい」志望動機のポイント
一方で、高評価に繋がる「やりがい」志望動機には共通のポイントがあります。それは、「具体性」「一貫性」「企業との接続」の3つです。
| 評価ポイント | 内容 |
| 具体的なエピソードで裏付けられているか | どんな状況で」「どんな行動をし」「どのような感情を得たか」を具体的に行動と結果をセットで示すと、あなたの価値観や強みが明確に伝わります |
| 自己分析と企業分析に一貫性があるか | あなたの過去の経験や価値観(自己分析)と、その企業で実現したいこと(企業分析)が論理的につながっているかどうかが重要です。なぜその企業でなければ、あなたの「やりがい」が最大限に発揮できないのか、明確な理由を説明できると良いでしょう。 |
| 企業への貢献と結びついているか | あなたの過去の経験や価値観(自己分析)と、その企業で実現したいこと(企業分析)が論理的につながっているかどうかが重要です。なぜその企業でなければ、あなたの「やりがい」が最大限に発揮できないのか、明確な理由を説明できると良いでしょう。 |



「やりがいを感じる」を魅力的に言い換える!厳選表現と例文
「やりがいを感じる」を具体的に言い換えることで、あなたの志望動機は格段に魅力的になります。ここでは、状況別の言い換え表現とそれらを活用した一言例文を紹介します。
1.成果や達成感を重視する場合
- 目標を達成したとことに大きな喜びを感じる
- 努力が成果として現れた瞬間に達成感を感じる
- 課題が解決して貢献できたときに充実感を覚える
一言例文:
2.成長や学びを重視する場合
- 新しい知識を吸収して成長を実感する
- 困難を乗り越えたときに自分の成長を感じる
- 未経験の領域に挑戦し、視野を広げる
一言例文:
3.他者貢献や社会貢献を重視する場合
- 人の役に立ち、感謝されることに喜びを感じる
- 社会貢献できる仕事に価値を見出す
- チームの一員として成果に貢献する。
一言例文:
4.情熱や探究心を重視する場合
- 興味のある分野を深く追求できる
- 新しい発想を形にできる
- 未知の課題に挑戦できる
一言例文:
志望動機で「やりがい」をアピールする構成3ステップ
志望動機で「やりがい」をアピールする構成3ステップは以下のとおりです。
- ステップ1:あなたの「やりがい」の源泉を明確にする
- ステップ2:企業の事業・職務と「やりがい」を結びつける
- ステップ3:過去の経験と将来の貢献を語る
志望動機で「やりがい」を効果的に伝えるためには、単に言葉を言い換えるだけでなく、論理的で分かりやすい構成が不可欠です。ここでは、採用担当者に響く志望動機を作成するための3つのステップを紹介します。
ステップ1:あなたの「やりがい」の源泉を明確にする
あなた自身がどのような時に「やりがい」を感じるのか、その源泉を明確に言語化します。これは自己分析の最も重要な点と言えるでしょう。
- どんな時に達成感を得ましたか?
- 誰かに感謝された経験はありますか?
- 苦労を乗り越えて嬉しかったことはありますか?
これらの具体的なエピソードを書き出し、共通点から「自分にとってのやりがい」をあなた自身の言葉で定義づけましょう。
ステップ2:企業の事業・職務と「やりがい」を結びつける
次に、ステップ1で明確にしたあなたの「やりがい」が、志望する企業の事業内容や職務内容とどのように結びつくのかを具体的に説明しましょう。
- 企業の理念や事業内容のどこに共感しますか?
- 自分のやりがいはどの業務で力を発揮できそうですか?
これらの目線を含め、自分の考えるやりがいを業務内容や企業理念にリンクさせることが重要です。
ステップ3:過去の経験と将来の貢献を語る
ステップ1で定義したあなたの「やりがい」を、PREP法(結論→理由→具体例→結論)やSTAR法を使うと論理的な説明ができるでしょう。
- 結論:私にとってのやりがいは、▢▢です。
- 理由:大学時代の〇〇の経験において、〇〇という課題を〇〇で解決しました。
- 具体例:この経験を活かし、御社の△△事業に貢献したいと考えています。
上記の3ステップを踏むことで、単なる「やりがいを感じる」という抽象的な言葉が、あなたの個性と企業への理解そして貢献意欲を示す強力な志望動機へと昇華されるでしょう。
【職種別】「やりがいを感じる」志望動機の例文5選
ここでは、具体的な職種を想定し「やりがいを感じる」を魅力的に言い換えた志望動機の例文を5つ紹介します。あなたの志望する職種に合わせて参考にしてください。
例文1:営業職(成果×顧客貢献)
私は顧客の課題を理解し、解決策を提案して成果に繋げることに最もやりがいを感じます。大学時代のフットサルサークルで、「初心者でも楽しめる企画が少ない」という課題を特定し、経験者と初心者がペアを組んでの交流戦やミニレッスンを導入する施策を実行しました。結果的に前年度比150%の新規メンバー獲得に繋がり、参加者からも「こんな企画を待っていた」との言葉をいただきました。
この経験から、相手のニーズに応え具体的な行動で成果を出すことに喜びを実感しました。御社の営業職においても、顧客の潜在的なニーズを引き出し最適な方法を提供することで、顧客企業の成長に貢献したいと考えています。私の強みである傾聴力と課題解決力を活かし、信頼されるパートナーとなることで御社の事業拡大に貢献します。
例文2:企画職(アイデアの具現化と市場への影響)
私のやりがいは、自身のアイデアが具体的な形となり、それが市場やユーザーに受け入れられたときです。大学のゼミ活動では、地域活性化をテーマにしたプロジェクトで、地元の商店街と連携したSNSプロモーション企画を立案しました。若年層の集客不足という課題に対し、商店街の隠れた魅力を発掘する「〇〇商店街食べ歩きマップ」を制作し、Instagramでの発信を提案・実行したことで、結果的にマップ掲載店舗の売上が平均10%向上しイベントには前年比200%の来場者を記録しました。このとき、自分のアイデアが地域に活気をもたらし、人々に喜びを提供できたことに大きな充実感を覚えました。
御社の企画職では、既存の枠にとらわれない柔軟な発想力と、論理的な思考力で市場のニーズを捉え、革新的なサービスやプロダクトの企画に挑戦し、ユーザーに新たな価値を与えることで御社に貢献します。
例文3:技術職(困難な課題解決と技術進化への貢献)
私が仕事で最もやりがいを感じるのは、困難な技術的課題を粘り強く探求し解決へと導く過程、そしてその成果が製品の品質向上や社会貢献に直結する瞬間です。
大学では、AIによる画像認識技術の研究に取り組んでいました。特に、低画質画像からの高精度な物体検出という難題に対し、既存の手法では限界がありました。そこで私は、深層学習モデルのアーキテクチャ改良とデータ拡張手法の最適化を試行錯誤。数ヶ月間、エラーの壁にぶつかり続けましたが、諦めずに論文を読み込み、実験を繰り返した結果、従来比15%の精度向上に成功し、学会での発表にも繋がりました。この経験を通じて、技術的な困難を乗り越え、自身の知識とスキルで新たな価値を創造できることに大きな喜びと充実感を覚えました。
御社の技術職においては最先端の技術動向を常にキャッチアップし、持ち前の探求心と課題解決能力を活かし、御社が注力されてる「御社の技術分野」で高性能で信頼性の高い製品開発に貢献します。
例文4:サービス職(顧客体験の向上とチーム連携)
私はお客様の期待を超えるサービスを提供し忘れられない体験を創造できたときと、そのプロセスでチームと一体感を共有できたときに大きなやりがいを感じます。
ホテルでのアルバイト経験があります。ある日、小さなお子様連れのお客様がチェックインされ、お子様が体調を崩されていることに気づき、マニュアルにない状況でもすぐにフロント責任者に報告し、提携している医療機関の手配とお子様向けの消化に良い食事の準備を提案しました。お客様からは「そこまでしてくださるとは思わなかった」と感謝され、後日に御礼の手紙をいただきました。この経験から、お客様一人ひとりに寄り添い期待を超えるサービスを提供することの喜びとチームで連携することの重要性を学びました。
御社のサービス職では、お客様のニーズを先読みし、最高の顧客体験を提供することに尽力したいです。私の強みである観察力とホスピタリティ精神を活かし、チームメンバーと協力しながら、御社のブランド価値向上に貢献します。
例文5:研究開発職(未解明領域の探求と新発見)
私が仕事で最もやりがいを感じるのは、まだ誰も手をつけていない未解明な領域に挑戦し自身の知的好奇心を満たしながら、新たな発見や知見を創出できたときです。
大学院では、地球温暖化の原因となる温室効果ガスの新たな吸収技術に関する研究を行っています。初期段階では、期待通りの結果が出ず実験の失敗が続きました。しかし、国内外の最新論文を徹底的に読み込み、指導教員や他分野の専門家との議論を重ね、実験プロトコルの抜本的な見直しを実施しました。結果的に、これまで見過ごされていた特定の条件下での吸収効率の大幅な改善を発見し、学術雑誌に論文が掲載されるに至りました。この経験から、未知の現象を解明し人類の課題解決に貢献できることに深い喜びと充実感を覚えました。
御社の研究開発職においては、私の探求心と粘り強さを活かし、最先端の研究テーマに臆することなく挑戦したいと考えております。特に【(御社の研究分野)】における新たなブレークスルーを生み出し、長期的な視点で社会に貢献できる研究成果を創出していくことに情熱を注ぎたいです。
まとめ:あなたの「やりがい」を採用担当者に響かせるために
「やりがいを感じる」という言葉は便利ですが、そのままの表現に留まっては相手には伝わらず、多くの応募者の中に埋もれてしまうリスクがあります。大切なのは、自分の経験・価値観・企業への貢献を一貫して語ることです。
本記事で紹介した言い換え表現や構成、職種別の例文を参考に、自分自身の言葉で、説得力のある志望動機を作成しましょう。あなたの「やりがい」が企業への貢献と結びついたとき、採用担当者の心にもきっと響くはずです。