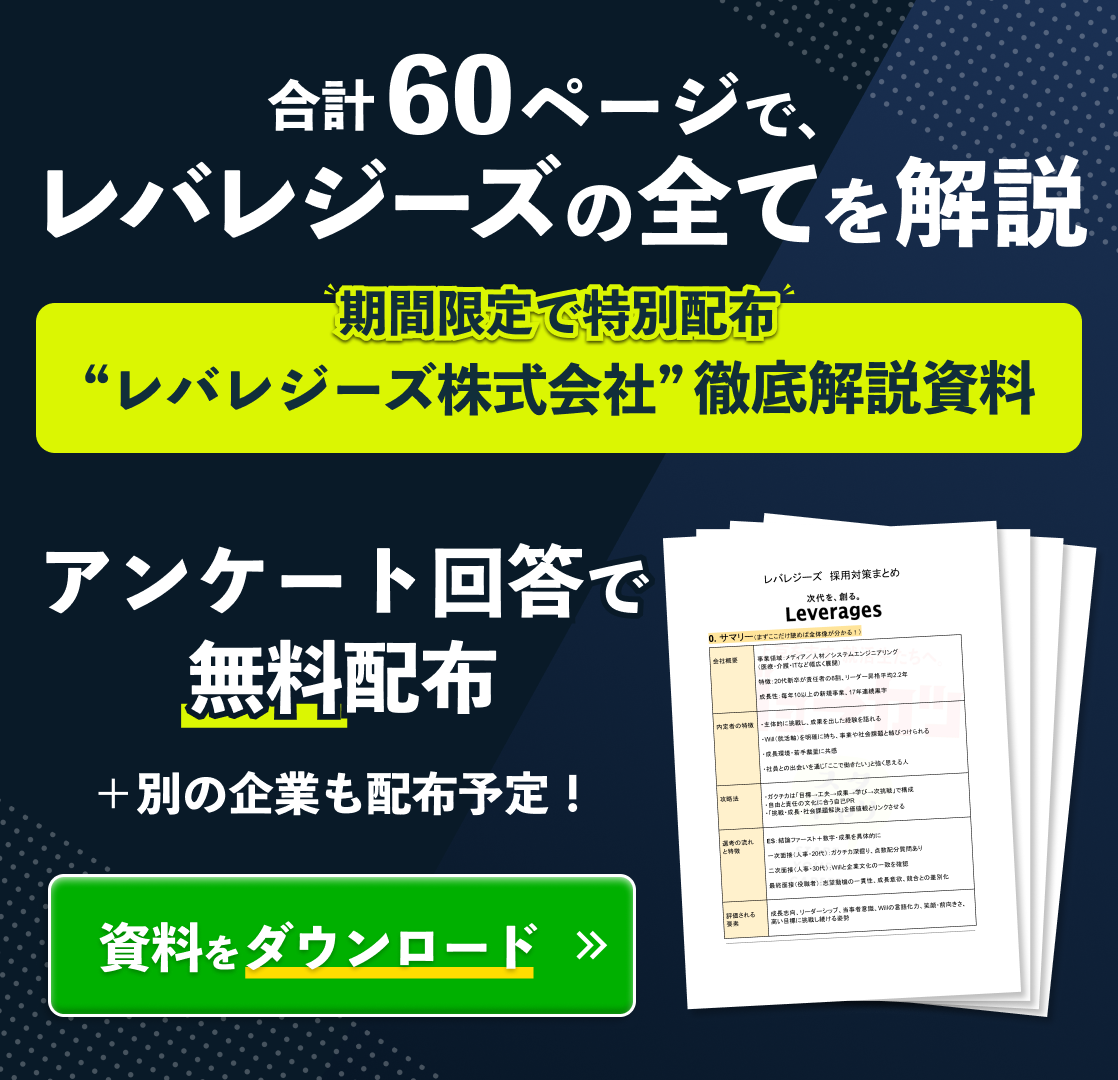大手企業の定義とは?大手企業で働くメリットと内定の秘訣を解説!
2025/8/26更新
はじめに
就職活動において「大手企業で働きたい」と考える学生は多いものの、「大手企業の定義」は曖昧です。
法律により明確な定めはなく、資本金5億円以上や従業員規模、知名度など複数の要素から判断されます。
本記事では、大手企業の一般的な定義を整理しつつ、働くメリット・注意点をデータで解説します。
大手企業に向いている人の特徴や内定を得るための戦略も紹介しているため、自分に合うキャリアを見極めるためにご活用ください。
上京を志す地方学生ならジョーカツ!
あなたのキャリアを加速させるチャンス!
無料で利用できる快適な個室シェアハウス、
東京までの交通費サポート付き
首都圏の注目企業への就活ならジョーカツ
首都圏の学生ならスタキャリ!
理想のキャリアを実現へと導く第一歩!
あなたにピッタリのキャリアアドバイザーを選び、
自分にマッチする優良企業をご紹介
首都圏企業のES添削から面接対策まで、就活ならスタキャリ
大手企業とは
実は「大手企業」には、法律上の明確な定義はありません。
ただし、就職活動やビジネスの場では、一般的に以下のような要素を満たす企業を大手企業と呼ぶケースが多くなります。
- 資本金が5億円以上
- 従業員数が1,000人以上
- 社会的な知名度や認知度が高い
たとえばテレビCMを出している、全国規模で事業を展開している、業界内での売上シェアが大きいなどの要素も、大手企業と判断される目安です。
また、複数の法律や制度上の基準を参考とするケースもあります。
中小企業基本法における基準
中小企業には明確な法律上の基準があります。
中小企業基本法によると、業種ごとに以下のように区分されています。
| 業種 | 中小企業の定義(資本金) | 中小企業の定義(従業員数) |
| 製造業・建設業・運輸業 | 3億円以下 | 300人以下 |
| 卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
| 小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 |
| サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
引用元:中小企業庁「中小企業者の定義」
たとえば、製造業の場合は「資本金3億円以下」「従業員300人以下」が中小企業の目安です。この「中小企業の基準を超える企業」を「大手企業」と呼ぶことがあります。
会社法における「大会社」の定義
会社法では、「資本金5億円以上または負債総額200億円以上」の株式会社を「大会社」と定義しています(会社法第2条6号)。
これは、会計監査人の設置義務や計算書類の公開など、会社運営上の義務が追加される基準です。そのため、大会社に当てはまる企業を、大手企業と呼ぶことがあります。
租税特別措置法における「大規模法人」の基準
租税特別措置法では、資本金1億円超または従業員数1,000人超の法人を「大規模法人」と位置づけ、税制上の特例(中小企業向け優遇措置など)の対象から除外しています。
大手企業とよく比較される企業規模【表で解説】
大手企業の特徴を理解するには、その他の企業区分との違いも押さえておくことが大切です。
以下は「中堅企業」「中小企業」「小規模企業」「有名企業」との主な違いをまとめた比較表です。
| 区分 | 法的定義の有無 | 主な基準(資本金) | 主な基準(従業員数) | 備考 |
| 大手企業 | なし(慣習的) | 5億円以上(目安) | 1,000人以上(目安) | 明確な基準はないが、中小企業の基準を超える規模 |
| 中堅企業 | なし(通称) | 中小企業以上 | おおむね2,000人未満 | 中小と大企業の中間。成長途上の企業が多い |
| 中小企業 | あり | 業種別に上限あり | 業種別に上限あり | 中小企業基本法に基づく明確な定義あり |
| 小規模企業 | あり | 特に定義なし | 5~20人以下(業種による) | 中小企業のうち、さらに規模が小さい企業 |
| 有名企業 | なし(通称) | 問わない | 問わない | 知名度ベース。テレビCMや話題性で広く認知される企業 |
下記は、各区分の特徴と補足説明です。
- 中堅企業
明確な法律上の定義はないものの、中小企業よりも規模が大きく、大手企業に届かない中間層の企業を指します。従業員数ではおおむね300~2,000人程度が目安とされることが多く、成長企業や地場の優良企業も含まれます。
- 中小企業
中小企業基本法による定義があり、業種ごとに資本金や従業員数の上限が設けられています。製造業であれば「資本金3億円以下、従業員300人以下」が基準です。2024年版の中小企業白書によりますと、国内の中小企業は336万4891社、日本の企業の約99.7%が中小企業に該当します。
- 小規模企業
中小企業のなかでも、従業員数が特に少ない企業です(例:商業・サービス業では従業員5人以下)。経営者と従業員の距離が近く、柔軟な意思決定が可能ですが、資金面や人材確保には課題も多いのが実情です。
- 有名企業
企業規模や資本金とは関係なく、一般的に認知度の高い企業を指します。テレビCMの放映、SNSでの話題性、人気商品の販売などで広く知られていれば、従業員数が少なくても「有名企業」として扱われることがあります。
参照:
日本経済新聞 「中小企業とは 日本企業の99.7%、業況は足踏み」
中小企業庁「中小企業者の定義」
九州経済産業局「中堅企業の成長促進
会社法 第2条第6号
国税庁「No.5432 措置法上の中小法人及び中小企業者」
大手企業で働く7つのメリット
大手企業での勤務を魅力に感じる学生は多いことでしょう。
ここでは、代表的な7つのメリットを整理しました。
自分にとってのメリットや優先度を考えることで、キャリア選択の判断材料になります。
- 福利厚生が充実している
- 社会的に信用が高い
- 将来性と安定感がある
- 年収が高い傾向がある
- 教育制度が整っている
- 年間休日が多い
- 有給休暇を取得しやすい
大手企業での勤務を魅力に感じる学生は多いことでしょう。
ここでは、代表的な7つのメリットを整理しました。
自分にとってのメリットや優先度を考えることで、キャリア選択の判断材料になります。
福利厚生が充実している
大手企業の大きな魅力のひとつが、福利厚生の充実です。
中小企業にも住宅手当や慶弔休暇、健康診断といった制度は整備されていますが、大手企業ではさらに幅広い仕組みが導入されている傾向があります。
たとえば以下のような制度は、多くの大手企業で整備されています。
- 住宅手当・家賃補助
- 慶弔休暇・慶弔見舞金
- 育児休業・介護休業制度
- 健康診断や人間ドックの費用補助
- 社員食堂・社宅・託児所などの施設
これに加えて、大企業ならではの施策として「カフェテリアプラン」や「企業型確定拠出年金(DC)」など、従業員のライフスタイルに合わせて選べる柔軟な制度も導入されています。
実際の調査では、従業員300人以上の企業では20種類以上の福利厚生を導入している割合が4割を超えることが報告されています(労働政策研究・研修機構)。一方で、中小企業では「カフェテリアプラン」や「企業型年金制度」の導入率が大企業に比べて大幅に低い傾向が見られます(例:従業員300人未満の企業での導入率は大企業の1/10以下)。
一般的な制度に加えて多様な選択肢がある点は、大手企業で働く大きなメリットです。
参照:労働政策研究・研修機構「企業における福利厚生施策に関する調査」
社会的に信用が高い
大手企業で働くことは、社会的な信用力の高さにつながります。企業規模や知名度により、信頼度を左右されるケースとして、次の場面が挙げられます。
- 個人客や法人客に営業をするとき
- 銀行で住宅ローンやクレジットカード審査を受けるとき
- 将来的に転職活動をするとき
金融機関や取引先が重要視するのは、相手企業や勤め先の安定性です。
内閣府の統計(令和2年/2020年)では、資本金1億円以上の大・中堅企業における年間倒産件数は2015年以降、毎年100件未満という安定した数字が続いています。
一方で、倒産全体の中で中小・零細企業(特に売上10億円未満)が占める割合は非常に高く、経営基盤が弱い企業ほど倒産リスクが高い構造です。
つまり、勤め先が大手企業であること自体が、社会的信用の証になりやすいと言えます。
もちろん、中小企業に勤めていても個人の努力次第で信頼を得ることはできます。
ただし大手企業は「企業のネームバリュー」が信用を後押しするため、仕事や生活のさまざまな場面で有利になりやすい点は、大きなメリットといえるでしょう。
参照:内閣府「第3章 ポストコロナに向けた企業活動の活性化と課題」
将来性と安定感がある
大手企業には、働く人が感じる「将来性」と「安定感」を支える仕組みや資源が整っています。
経済産業省の調査によると、日本全体の研究開発費のうち上場100社が77%を占めています。
大企業ほど技術革新や新規事業への投資を継続できる体制の裏付けと言えるでしょう。
下記は企業規模別の平均勤続年数です。
| 大企業 | 中企業 | 小企業 | |
| 男女計 | 13.4年 | 12.4年 | 11.3年 |
| 男性 | 15.3年 | 13.8年 | 12.2年 |
| 女性 | 10.1年 | 10.0年 | 9.5年 |
引用:令和5年賃金構造基本統計調査 結果の概況「企業規模別」
男女の平均勤続年数とともに、大企業が中小企業を上回っており、大企業は長期的に安心して働ける基盤が整っていることを示しています。
下記は従業員規模別の管理職平均勤続年数です。
| 従業員 100~999 人 | 従業員 1,000 人以上 | |
| 部長 平均勤続年数 | 22.4 年 | 25.8 年 |
| 課長 平均勤続年数 | 20.4 年 | 23.0 年 |
管理職に限った場合も、大企業は中小企業に比べ平均勤続年巣が高いことがわかります。
このデータより、大企業は「将来を見据えた成長への投資」と「長く働ける安定した制度」の両方を兼ね備えていると言えるでしょう。
年収が高い傾向がある
大手企業に勤める大きなメリットのひとつが、給与水準の高さです。
ブランド力や資金力のある大手企業は、従業員により高い給与を支払う余力があります。
厚生労働省「賃金構造基本統計調査(令和6年・2024年)」によると、企業規模が大きいほど平均賃金が高い傾向が見られます。
| 企業規模 | 平均年収(男性) | 平均年収(女性) |
| 大企業(1,000人以上) | 4,034,000円 | 2,966,000円 |
| 中企業(100~999人) | 3,556,000円 | 2,713,000円 |
| 小企業(10~99人) | 3,245,000円 | 2,555,000円 |
企業規模による年収の差は、男性のほうが高めです。長期的に見ても生活基盤や将来設計に大きな影響を与えるでしょう。
もちろん職種や業界によっても違いはありますが、給与水準の高さは大手企業を目指す上での代表的なメリットです。
教育制度が整っている
大手企業は毎年多くの新入社員を採用するため、研修や教育制度が整備されてる点も特徴です。
新入社員研修から階層別研修、資格取得支援まで幅広く用意されており、安心してスキルを身につけられる環境があります。
厚生労働省の「能力開発基本調査(令和5年度)」によると、従業員1,000人以上の企業の83.6%が正社員に対するOFF-JT(社外研修)を実施しています。
一方、従業員100~299人規模の企業では76.1%にとどまり、中小企業との差は明確です。
また、大企業ではOJT(職場内訓練)とOFF-JTの両方を組み合わせて実施するケースが多く、学びながら実務を経験できる仕組みが整っています。
これにより、以下のようなメリットがあります。
- 社会人としての基本マナーやビジネススキルを体系的に学べる
- 専門知識を段階的に習得できる
- 失敗を最小限に抑えつつ実務経験を積める
このように、大手企業の教育制度は「入社後の成長を支える仕組み」として機能しており、就活生にとっては安心できるポイントといえます。
年間休日が多い
大手企業は労働環境が整備されていることが多く、年間休日の日数も中小企業より多い傾向があります。休日が多いことでライフワークバランスを保ちやすく、心身のリフレッシュにもつながります。
厚生労働省「就労条件総合調査(令和6年・2024年)」によると、企業規模ごとの労働者 1 人あたりの平均年間休日数は次のとおりです。
| 企業規模(従業員数) | 平均年間休日数 |
| 1,000人以上 | 119.4日 |
| 300~999人 | 117.4日 |
| 100~299人 | 114.7日 |
| 30~99人 | 112.2日 |
このように、企業規模が大きいほど休日数が多くなる傾向が見られます。特に1,000人以上の大企業では、平均で年間119日以上の休日が確保されています。
休日が多ければ、プライベートが充実し、自己研鑽の時間も取りやすくなる点もメリットです。
有給休暇を取得しやすい
大手企業は従業員数が多いため、業務の分担体制が整っており、有給休暇を取得しやすい傾向があります。人員に余裕があることで、個人が休んでも業務が滞りにくいのが理由です。
厚生労働省「就労条件総合調査(令和6年・2024年)」によると、企業規模ごとの有給休暇取得率は以下のとおりです。
| 企業規模(従業員数) | 有給休暇取得率 |
| 1,000人以上 | 67.0% |
| 300~999人 | 66.6% |
| 100~299人 | 62.8% |
| 30~99人 | 63.7% |
企業規模が大きいほど有給休暇の取得率も高めです。
有給休暇をきちんと取得できる環境は、仕事とプライベートを両立するうえで非常に重要です。就活生にとっても、入社後の働き方をイメージする大切な指標となるでしょう。
大手企業への就職を目指す際の5つの注意点
大手企業には数多くの魅力がある一方、応募者も集中します。
文部科学省や就職情報サイトの調査でも、大手企業は新卒採用における人気が非常に高く、中小企業に比べて採用倍率が高い傾向があります。
つまり「就活難易度が高い」という前提を理解しておくことが大切です。
そのうえで、入社後に直面しやすい注意点として、以下のような点が挙げられます。
- 人間関係が複雑になりやすい
- 業務範囲が限定されやすい
- 裁量やキャリア形成に制約がある
- 転勤の可能性が高い
- 必ずしも自分に合うとは限らない
人間関係が複雑になりやすい
大規模組織では社員数が多いため、人間関係の調整が求められるケースが考えられます。
特に上下関係や部門ごとの文化の違いから、次のような課題を感じる人もいます。
- 部署ごとに派閥ができやすい
- 上司の意向に従わざるを得ない場面が多い
- 社員数が多いため、気の合う人ばかりとは限らない
多様な人と働く経験は成長につながる一方で、環境によってはストレス要因にもなり得ます。
業務範囲が限定されやすい
大手企業では分業体制が進んでおり、担当業務が明確に分けられる傾向があります。
専門性を高めやすい反面、次のようなデメリットを感じる場合があります。
- 「決められた範囲の業務しか任されない」と感じやすい
- 他部署との兼務など幅広い経験が得にくい
- 業務全体の流れを把握しづらい
裁量やキャリア形成に制約がある
大手企業は制度やルールが整っている一方で、個人の裁量権が限られることもあります。
特に昇進やキャリア形成については「年功序列」の傾向が残る企業も少なくありません。
総務省の調査によると、課長職の平均年齢は男女合わせて48.8歳、部長職は52.7歳 です。
大企業ではポスト数が限られているため、昇進までに時間がかかる傾向があります。
一方で中小企業は社員数が少ない分、比較的若いうちから役職を経験できるケースも少なくありません。
「早く責任ある立場を経験したい」と考える人には、もどかしさを感じることがあるでしょう。
転勤の可能性が高い
全国や海外に拠点を持つ大手企業では、転勤が発生しやすいのも特徴です。
独立行政法人 労働政策研究・研修機構の調査から、会社の規模と転居を必要とする人事異動の割合は比例していることがわかります。
| 会社規模 | 転居を必要とする人事異動がある企業の割合 |
| 1,000 人以上 | 89.8% |
| 300~999 人 | 79.0%、 |
| 100~299 人 | 44.6%、 |
| 30~99 人 | 17.9% |
引用:
独立行政法人 労働政策研究・研修機構 企業における転勤の実態に関するヒアリング調査
転勤の有無は、ライフスタイルや家庭環境に影響を及ぼすこともあるため、慎重に判断する必要があります。
必ずしも自分に合うとは限らない
大手企業は福利厚生や安定性といった魅力がある一方、すべての人に適しているとは言えません。個人の性格や人生の目標によっては、合わないと感じる可能性があります。
下記は大企業に対する不満の一例です。
- 新しい挑戦をしたい人にとっては保守的に感じられる
- 意思決定のスピードが遅いと感じる場合がある
- 大きな組織だからこそ「歯車の一部」と感じてしまうことがある
就職活動では「有名だから」「安定しているから」だけでなく、自分の価値観やキャリアプランに合っているかを見極めることが重要です。
大手企業に採用される就活生の4つの特徴
大手企業に採用される学生にはいくつかの共通点があります。
ここでは代表的なポイントを紹介します。
- 基礎的な学力が高い
- 学力や専門性を活かせる
- 論理的に考える力・コミュニケーション能力がある
- 主体的に行動し成果を出した経験がある
基礎的な学力が高い
大手企業は応募者数が多いため、人事が全てのエントリーシートに目を通すことは困難です。
そのため、企業は公言していないものの、まず学歴や学力で一定のフィルターを設けるケースは少なくありません。
一定以上の偏差値の大学の学生であることは、応募時に有利に働く可能性が高いです。
ただし、東大や早慶の学生全員が書類審査を通るわけではない点も注意しておきましょう。
学力や専門性を活かせる
大手企業では、大学や大学院で培った学力や専門知識が評価されやすい傾向があります。
理系であれば研究内容や実験の経験がそのまま技術職に結びつきやすく、文系でも語学力・会計知識・法務知識などが即戦力として活用可能です。
また、大手企業は研修制度やジョブローテーション制度が整っているため、基礎的な学力や専門知識を持つ学生ほど、入社後に伸びやすい環境があります。
論理的に考える力・コミュニケーション能力がある
大手企業の面接や選考では、グループディスカッションやケース面接が重視されます。
ここで問われるのは「物事を論理的に整理し、相手にわかりやすく説明できる力」です。
また、大手企業の業務は多くの人と関わりながら進めるため、協調性やコミュニケーション能力は必須です。
リーダーシップを発揮するだけでなく、周囲の意見を尊重し、チーム全体として成果に貢献できる学生が評価されます。
内閣府の調査では、企業が「採用したい学生の人物像」として「コミュニケーション能力が高い」「協調性がある」が7割以上、「論理的思考力が高い」も2割以上を選択しています。
この結果からも、人柄だけでなく思考の組み立て方が評価対象になっていることがわかります。
主体的に行動し成果を出した経験がある
大手企業は「指示を待つのではなく、自ら動ける人材」を高く評価します。
日本経団連の2022年調査では、企業が新卒に期待する資質として「主体性」が84.0%で最も高く、次いで「チームワーク・協調性」が76.9%という結果でした。
このことからも、大手企業で評価されるのは「与えられた仕事をこなす学生」ではなく、課題を見つけて解決に向けて動ける学生です。
アルバイトで売上改善の工夫をした、ゼミで研究テーマを主導したなど、自分から動いて成果につなげた経験を具体的に示すと効果的です。
大手企業の内定を得るための3つの戦略
大手企業の内定を得るためには、戦略的に就活を進める必要があります。
ここでは、内定に近づける可能性が高まる3つの戦略と具体的な実践ポイントについて解説します。
- 一貫性を持った就活を行う
- 企業研究を徹底する
- 人材不足の業界を狙う
一貫性を持った就活を行う
志望動機や自己PRの一貫性は、選考で重視される点です。
たとえば「挑戦する姿勢」をアピールするなら、学生時代の経験、志望する企業の強み、将来のキャリア像まで一貫して結びつけましょう。
面接官は「話がつながっているか」「企業と学生の方向性が合致しているか」を見ているため、自分の軸を整理し、明確にしておくことが重要です。
▼アクションの具体例
- 自己PR・ガクチカ・志望動機のキーワードを共通化する
- ES提出前に「チェックリスト」を用意して、矛盾のないかたちに整える
- 面接準備に向けて志望動機をキャリアプランに紐づけた説明を考えておく
ESで差をつけるためのチェックリスト
- 最初に結論が書かれており、主張が明確になっている
- 志望企業ならではの特徴や事業内容と、自分の経験が結びついている
- 数字や成果など、具体的なエピソードで強みを裏付けている
- 自己PR・志望動機・ガクチカに一貫性がある
- 一文が長すぎず、丁寧で自然な言葉選びができている
企業研究を徹底する
大手企業の選考では、「なぜうちの企業なのか」という問いへの答えが求められます。
業界研究だけでなく、志望企業の事業内容、強み、今後の方針を具体的に調べておきましょう。
▼確認しておきたい資料例
- 企業の公式サイト(トップメッセージ・採用情報)
- IR情報・中期経営計画
- ニュースリリース・日経新聞記事
- 競合他社との比較表や強み・弱みの整理
「他社と使い回しの志望動機」はすぐに見抜かれてしまいます。自分なりの視点で言語化し、差別化できる志望動機を持つことが内定への近道です。
人材不足の業界を狙う
同じ大手企業でも、業界によって採用難易度には差があります。
特にIT、建設、介護・医療といった人材不足が深刻な業界は、大手企業でも比較的採用の門戸が広い傾向があります。
厚生労働省の「有効求人・求職・求人倍率」によれば、2024年12月の有効求人倍率の全体平均は1.19倍です。
一方
- 保安職業従事者:5.29倍
- 建設・採掘従事者:4.15倍
- 専門的・技術的職業従事者:2.11倍
業界ごとの人材ニーズに大きな差があることがわかります。
▼アクションの具体例
- 志望業界を広げる/視野をずらすことでチャンスを広げる
- IT企業の中でも「インフラ系」や「SaaS系」など、伸びている分野を狙う
- 介護・医療の業界でも大手法人・経営母体の安定性に注目する
「大手=狭き門」と思い込まず、人材ニーズが高い業界に注目する視点を持つことで、内定獲得の可能性を高められます。
参照:
まとめ
大手企業の定義は「従業員数」や「資本金」などの基準で整理できますが、就活生にとっては「自分が会社でどのように成長できるか」が大切です。
大手企業の社会的信用や安定感といった強みは魅力的ですが、一方で転勤や裁量権の少なさなど注意点もあります。
この記事で紹介した特徴や戦略を理解することで、単に「大手だから安心」という視点にとどまらず、自分に合った働き方を考えるきっかけになるはずです。
もし大手企業を目指すなら、採用される人材の特徴や就活戦略を意識して行動することが、内定への近道になります。
大手企業に挑戦するかどうかを決めるのはあなた自身です。
定義を知り、メリット・デメリットを整理したうえで、自分らしいキャリアの第一歩を踏み出してください。