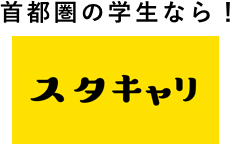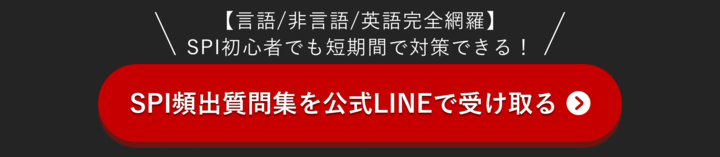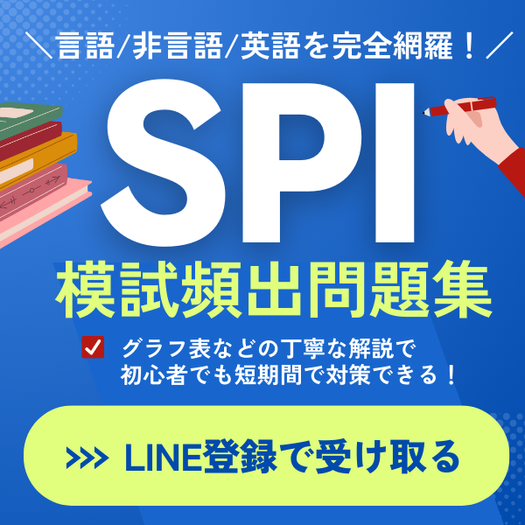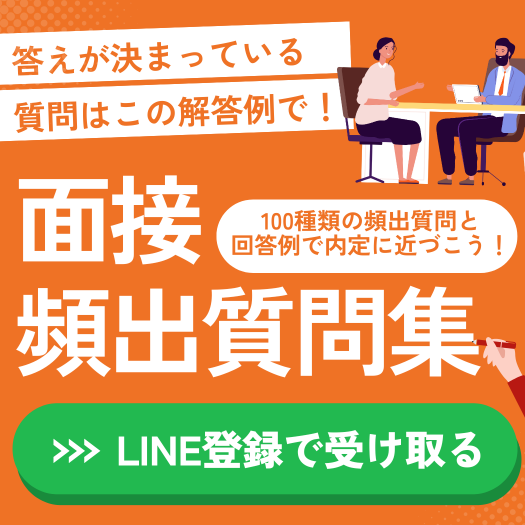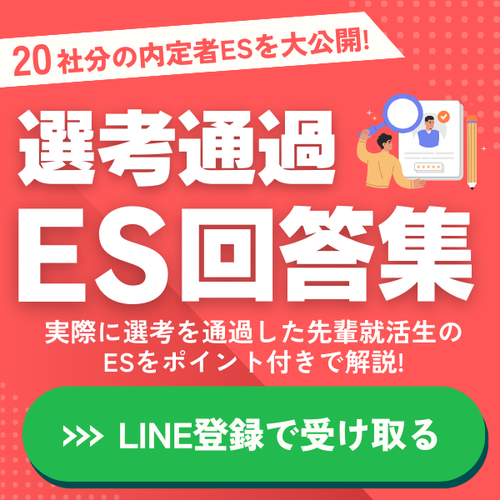就活のネタは日常で見つけられる!ネタ作りに役立つ戦略4選!
この記事を読んでいる中には、
「ガクチカとかESとかの就活のネタがない…どうしよう」
と考えている人もいるのではないでしょうか?
そこで本記事では、就活のネタ作りに悩んでいる学生向けに、就活のネタ作りが必要ない理由を解説していきます。
本記事が就活のためのネタ、ガクチカやESのエピソードに悩んでいる人の参考になれば幸いです。
就活ネタを自分で見つけられない!
という方、人に頼ってみるのも「アリ」です。
1..日常生活の中から就活のネタ作りをする3個のメリット
まず前提として、就活に特別なネタ作りは必要ありません。
その理由としては、他人と比較するこでスペックで自分を判断しているからです。
「僕はFラン大学だからこの企業は無理だ」
「私はTOEIC500点だからこの外資系は無理だ」
と考えたことはありませんか。
上記のような思考の原因として、自分のスペックを他人と比較していることが挙げられます。
確かに「良い大学」や「高い語学力」はその人が努力してきた証ですし、誇りを持って就活するべきだと思います。
しかし、スペックという意味では社会人から見ると大差のないケースも多く、スペックを比較することは、就活おいては必要ないことだといえます。
他人と比較せず、自分なりのエピソードを見つけてアピールに繋げましょう。
比較することを辞めれば、自分のなりのエピソードが自然と見つかるはずです。
スペックをアピールするのは肉付け程度で大丈夫です。
他人と比較することなく、等身大の自分を選考の場で表現することを心がけましょう。
特別な就活のネタ作りをする必要はありません。
2-1.ネタの絶対数が増える
就活のネタ作りを日常生活の中から行うようにするメリットの1つに、ネタの絶対数が増えることが挙げられます。
もちろん、サークルやアルバイトといった経験がある方がネタの数も増えますが、現実的には数的な意味において限界があるといえます。
「質さえクリア出来ていればいいんじゃないの?」
みたいな意見もあるかと思いますが、就活で話す経験談は複数持っておくのが基本です。
実際、企業も質的な観点と数的な観点の両サイドからエピソードの深掘りが行われます。
そのため、複数のエピソードを用意しておいて損はないので、日常生活にも目を向けて見るようにしましょう。
2-2.正直な印象を与えることができる
ESや自己PRで日常生活での体験談を伝えることは、正直な印象を与えることにも繋がります。
現在の就活では、就活生達が自己分析を行い、ESや面接で使えるネタを探し出す傾向にあります。その結果、「サークルの部長で話し合いをまとめた」「アルバイトで後輩の意教育を行った」など似たり寄ったりの内容になってしまいがちです。
もちろん、嘘をついたり話を捏造したりすることは論外ですが、
「うーん、また同じような話か。」
と人事担当者がエピソードの信ぴょう性を疑ってしまうこともあります。
一方、日常生活の中から見出したエピソードを述べる学生の数は少なく、正直な印象を与えることができます。
その結果、話を聞いてもらいやすくなることも珍しくありません。
2-3.思考力のアップに繋がる
日常生活の中でエピソードを探そうとすると思考力がアップするかもしれません。
エピソードを探すということは、何かしらの行動を取った時に、その行動が就職活動で使えると認識しなくてはなりません。
その上、そのエピソードをES的な視点や面接的な視点で練り直す必要があります。
このように日常生活のエピソード話すためには思考力が重要になるので、思考力のアップが期待できます。
2.それでも就活のネタ作りに不安な人が取るべき戦略
とはいえ、「日常生活の中のネタじゃ不安」あるいは「日常生活の中からネタを探すなんて難しい」と感じている人もいるのではないでしょうか?
そこで本章では、就活のネタ作りに不安に不安な人が取るべき戦略を解説していきます。
2-1.就活のネタ作り①長期インターンに参加する
まず、オススメは長期インターンです。
ただ、インターンといっても大企業が2,3日実施するようなものは違います。
イメージはベンチャー企業で半年とか1年といった単位で働いている感じです。もっというと、なるべく人数が少ない企業がいいでしょう。
潰れてもインターンなのでノーリスクです。
オススメの理由としては、社員に近い状態でビジネスを体感できるからです。
基本的に創立間もないベンチャー企業は、常に人材不足に悩まされ、正社員を十分に雇うことができなかったりします。そのため、インターン生であっても「ノースキルの人材」として育成してくれる場合が多いです。
事実、ベンチャー企業でのインターン経験は十分就活のネタになるはずです。
さらに、長期インターンでは給与が発生します。
多くはアルバイトのような時給制を採用しており、学びながらお金を得ることができます。
自分の将来につながる体験をしながらお金まで稼げるのは大きなメリットでしょう。
また、長期インターンでは大学の学生以外の社会人との交流ができます。
あらたなコミュニティに参加することで、自分の価値観や世界観を広げられる可能性があることも魅力です。
ただ、インターンとは名ばかりで「ただの雑用係」みたいな役割だと時間の無駄になります。その辺はしっかりとリサーチするなど、自分で役に立ちそうな仕事内容であるか判断しましょう。
長期インターンの探し方はこちらの記事がおすすめです。
https://jo-katsu.com/campus/4601/
2-2.就活のネタ作り②アルバイト
就活のネタ作りに、アルバイトはぴったりです。
実際に労働をしてその対価として給与をもらえるアルバイトは、仕事の体験の中でのさまざまなネタを見つけられるでしょう。
アルバイトの中で学んだことや、工夫したことなどをアピールポイントにできるため、書類作成や面接に活かしやすいです。
ネタ作りにアルバイトを選ぶ場合には、できる限り就活に有利なアルバイトをするといいでしょう。
就活に有利なアルバイトの選び方はこちらの記事をご覧ください。
https://jo-katsu.com/campus/4300/
2-3.就活のネタ作り③ボランティア
ボランティアでの経験は就活のネタ作りとしては王道の経験です。
それ故に、他の就活生との差別化が難しくもあります。
どのようなボランティアを行ったかよりも、その経験の中で何を学んだのか、どのように主体性をもって取り組んだのかが重要です。
目的意識をもって取り組み、有意義な経験を積むことで就活のネタに活用できるでしょう。
就活でボランティアでの経験をアピールする方法はこちらの記事をご覧ください。
https://jo-katsu.com/campus/4438/
2-4.就活のネタ作り④日常生活の見方を改める
最後に、日常生活の見方を改めることも就活のネタ作りになるといえるでしょう。
1章で述べたように、日常生活の中のエピソードであっても就活のネタには十分になり得ます。
しかし、普段の生活をぼーっと過ごしているようでは、良いエピソードを見いだすことは難しいです。
そのため、日常生活の見方を改めるなどして「普段からネタが落ちていないか」とアンテナを張る必要があります。
例えば、バイト先の客数が減っているという経験があったとします。
そんなときに、「お客さん少なくて楽できるな」と思ってしまってはネタになりません。
見方を改めて、「なぜお客さんが減ったのだろう」と考えるようにしてみましょう。
そして、その原因をあなたなりに推測し、その原因への対策を提案、実行することで主体的に物事に取り組んだというネタができます。
さらに、成果が出ればそれらの数値などをアピールポイントにも活用できるでしょう。
成果が出なければ、トライ&エラーを繰り返し粘り強くチャレンジすれば長所としてもアピール可能です。
面接の際の上京就活を
シェアハウス、交通費の面から支援!
4.ネタ作りなしでも就活で高評価を得るポイント
繰り返しになりますが、就活のネタ作りは必要ありません。
とはいえ、エピソードの伝え方には留意するべきです。
そこで本章では、特別なネタ作りをしなくても高評価を得るためのポイントについて解説していきます。
4-1.就活ではネタ作りよりもESや自己PRの構成を意識する
ESや自己PRの構成を意識するようにしましょう。
実際、エピソードを求められるのはESや自己PRの時は多いと思います。
「じゃあ、どんな構成にすれば良いの?」
結論、論理的に書くことです。
ESや自己PRの基本的な構成としては、
①結論…1番伝えたいことを最初に持ってくる
②理由…①の結論に至った理由を簡潔に述べる
③具体例…実際の経験や体験を伝える
④結論…もう一度結論を伝える
上記のような構成だと相手に伝わりやすいです。
このような手法をPREP法といいます。
PREP法を用いることで、簡潔にあなたのアピールポイントを相手に伝えられるようになるでしょう。
PREP法についてはこちらの記事でより詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。
https://jo-katsu.com/campus/4550/
4-2.就活ではネタ作りよりも人柄もアピールできるような内容にする
就活では人柄もアピールできるように伝える必要もあります。
確かに、飛び抜けた経験を持っている学生は一定数いますが、就活生のうちのどの程度が驚くような経験をしているでしょうか?
100人中1人でも、びっくりするような経験を持つ就活生がいれば多い方でしょう。
そのため、大半の就活生は人柄や熱意も企業にアピールしていくことが求められます。
同じテーマで伝えようとしても、人が違えば印象は大きく変わってきますよね。
自分のどのような人柄を伝えることがベストなのか考えてみましょう。
面接対策の壁打ちも
ジョーカツのキャリアアドバイザーと!
まとめ 他人と比較するのは禁物
本記事では、就活のネタ作りに悩んでいる学生向けに、就活にネタ作りが必要ない理由を解説してきました。
就活のネタで悩んでいる人は、他人と比較してしまっていませんか?
確かに、ライバルや同じレベルの仲間で切磋琢磨することで成長できるのは間違いありません。
しかし、就活のネタに関しては他人と比較してしまうのは禁物です。
比較することはやめて、選考の場で等身大の自分を表現するようにしましょう。
等身大の自分を表現しようとすれば、ネタに使えそうな体験や経験も自然としゅう増えてくるはずです。
本記事が就活のためのネタ、ガクチカやESのエピソードに悩んでいる人の参考になれば幸いです。