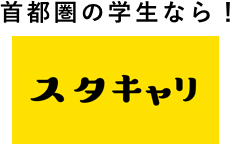【就活】教えて!面接の合格フラグってどんな反応?
2023年2月8日更新
はじめに
就活で面接を受けだすと、合否について不安になることが多いのではないでしょうか?
「さっきの面接、受かっているかな…?」
「結果が早く知りたいけど、なかなか届かない…」
そんな時に、面接に合格したかどうかが分かる「合格フラグ」があれば、合否が出るまでの時間を少しだけ安心して過ごせるのではないでしょうか?
そこで本記事では、そもそも「合格フラグ」は何かということをはじめ、面接で「合格フラグ」を見つけるポイントを詳しくご紹介します。
この記事を読むことで、面接官の本当の「合格フラグ」が分かるはずです。
面接の結果が中々出なくて悩んでいたり、「あの面接官の反応は確実に合格だと思ったのになぜか落ちた」といった経験がある人はぜひ最後まで読んでみてくださいね。
面接に「合格フラグ」は存在する?
「そもそも面接で合格フラグがあるかどうか分かるの?」と思っている人がいるかもしれませんが、面接によっては明らかに「合格フラグ」だと確信できる場合があります。
実際にこの記事を読んでいる人の中で、過去に面接経験がある場合には、「振り返るとあれば合格フラグだった」と思い出せる人もいるのではないでしょうか。
面接の場で「合格フラグ」を見つけた場合には、合否連絡が届くまで多少安心して過ごすことができるかもしれません。ぜひこの記事を今後の参考にしてくださいね。
面接で明らかな「合格フラグ」が立ちにくい理由
一方で、面接を受けたことはあるものの、明らかな「合格フラグ」は感じたことがないという人も多いのではないでしょうか?
なぜ面接で「合格フラグ」を感じにくいのでしょうか?
その理由を見ていきましょう。
他の面接官との合意が必要だから
最終面接の際に、面接官ひとりの意向で合否で判断を決定できることは多くありません。
そのため、他の面接官との合意を取る時間を考慮して敢えて就活生に何も感じさせないようにしているのかもしれません。
特に最終選考になると、その場ですぐに合否が伝えられることはほぼありません。
そのため、特別な印象を与えないように面接官が意識している可能性があります。
他にも良い候補者の面接を控えているから
企業には、採用する人数に上限があります。
中途の場合には上限に関係なく「良い人がいれば採用する」という指針の企業は多くありますが、新卒の場合は人数の上限がある場合がほとんどです。
なぜなら、新卒は「ポテンシャル採用」と言われるように、現時点で実力は分からないものの、期待値を考慮した採用が行われるためです。
そのため、もしかすると別の誰かとあなたがボーダーラインで戦っているかもしれません。
そのような場合には、ライバルとなる就活生の面接が終わるまで、合否を保留にする場合があります。
このような場合だと、面接官は合格や不合格の雰囲気は一切出さないでしょう。
SPIなどの懸念が払しょくしきれないから
面接の前には、SPIなどの適性検査を受検していることが多いです。
そのため、SPIの結果などを受け、面接を行うことが多々あります。
それまでの面接の結果やSPIの出来が良くても、それぞれに一貫性がない場合には合否がすぐに決まらない場合があります。
面接は面接ごとに主張することを変えるのではなく、一貫した主張を行うことが大切です。この意識を持つ就活生は多いですが、自身の性格とSPIで示されている性格の乖離にまで思考が及ぶ就活生は多くありません。
もちろんSPIの結果などは個人に開示されないため、想定することが難しいと言えます。
しかし面接で「合格フラグ」がないことが続く場合には、自分の主張を一度見直してみるのが良いかもしれません。
「合格フラグ」があるとしたらどんなこと?
では、実際にはどのような「合格フラグ」が想定されるのでしょうか。
代表的な例をご紹介します。
次回選考のアドバイスがある
最終選考以前の面接の場合、次回以降の選考のアドバイスがあれば「合格フラグ」です。
次回以降の選考のアドバイスがあるということは、「あなたを合格させてあげたい」という面接官の思い以外の何物でもありません。
面接官の立場に立つと、就活生のポテンシャルが高いにも関わらず、自分以外の面接官との相性が悪く落とされてしまうほど悲しいことはありません。
そのため、就活生へのフィードバックだけではなく、次回の選考の攻略方法を合わせて伝えることで、可能な限り合格に導こうとしているのです。
癖が強かったり、好きな学生のタイプがはっきりしている面接官が控えている場合には、このように気を利かせてくれる面接官がいる場合があるでしょう。
他社の選考状況を詳細に聞かれる
他社の選考状況を詳細に聞かれたなら、それは「合格フラグ」と言って良いでしょう。
面接官がどうしても採用したい就活生の場合、他社の具体的な選考状況を確認することは必須事項です。他社の選考状況を鑑みて合否を伝えるタイミングを検討したり、他の企業へ決めてしまいそうな場合には何らかの手を打つ必要があります。
そのため、他社の選考状況を詳しく聞くという行動は、ほぼ「あなたを合格にしたい」「あなたに内定を出したい」というサインなのです。
しかし企業によっては、そもそも他社の選考状況を積極的に聞くことをタブーと捉え、全く触れてこない場合も少なくありません。企業によって差が出る部分なので、既に面接を受けた人や口コミなどを確認し、企業の傾向を掴んでおくことが必要です。
入社後のイメージを詳細に聞かれる
「入社後にどのような部署で働きたいか」「(地方学生の場合)入社が決定したらいつ頃上京する予定か?」などの入社後に関する具体的な質問をされた場合、「合格フラグ」が立っていると言えるでしょう。
入社後に関する質問はどの面接でもされる可能性がありますが、具体性を伴えば伴うほど、面接官が入社を切望している可能性があります。
「入社後はどのような部署で働きたいですか?」といったよくある質問ではなく、実際に企業で働くイメージが具体化されるような質問が多い場合が「合格フラグ」のサインです。
「さっきの面接、入社後について詳しく聞かれたな…」と感じる場合には、合格を期待して待っておくのが良いかもしれませんね。
実は「合格フラグ」ではない可能性があるのはどんなこと?
一方で一見すると「合格フラグ」のようですが、実は違うことがある場合に注意が必要です。
「合格フラグかと思ったら実は違うこと」をいくつかご紹介しましょう。
面接時間が長い
面接時間が長い場合、一般的に「合格フラグ」とされることが多いですが、実は十分な注意が必要です。もちろん「合格フラグ」である場合はありますが、合否のボーダーライン上にいて、面接官が質問を通じて合否を判断中である場合があります。
時間は長く面接しているにも関わらず「合格フラグ」ではない場合、面接官が何度も似たような質問をしてきたり、回答を「そんなに?」と思うぐらい深堀りされるという兆候があります。
また、何度も違う角度の質問をたくさんされる場合も注意が必要です。
面接を通じて「確実に不合格」の状態ではありませんが、「確実に合格」ではないことが確かな状態です。だからこそ、どれだけ質問されてもひとつずつ真摯に回答する姿勢を示すことが重要になります。
面接の雰囲気が良い
面接の雰囲気が良い場合、「合格フラグ」が立ったと喜びたくなるのではないでしょうか。
しかし、不合格の面接の方が面接の雰囲気が明るい場合があるため、注意が必要です。
また、最初から雰囲気が「明るすぎる」場合には、すでに不合格であることが決まっている場合も少なくありません。
「不合格にするなら、なぜ明るい雰囲気をつくるの?」と思うかもしれませんが、決してあなたを騙そうとしてそのような態度になっているわけではありません。
面接官の立場に立つと、「目の前の就活生の友人」や「10年後に成長した目の前の就活生」が面接を受ける可能性があると、その人たちに悪い印象を与えるわけにはいきません。また、口コミサイトの評判なども気にする必要があります。
そのため、できる限り良い雰囲気で面接を行った方が企業としての評判が良いことは間違いありません。
だからこそ、雰囲気が良い時ほど「目の前の自分」ではなく、「周囲の誰かや未来の自分」を気にされていることを懸念する必要があります。
面接官から応援される
具体的なアドバイスではなく、面接官からの応援がある場合は、「不合格フラグ」である場合がほとんどです。
一見するとこちらも「次の面接に向けて頑張ってね」といったニュアンスに感じるかもしれません。しかし本当に合格してほしい就活生には、面接の攻略法のような合格へのアドバイスが送られます。具体性が無く応援の場合には、「うちの企業は落ちちゃうけど、他の企業の面接を頑張ってね」というニュアンスが強いでしょう。
「面接官は酷いことをする」と思うかもしれませんが、面接官がこのような声かけをする場合は就活生の人物的な魅力が高い場合が多いです。一方で能力が足りなかったり、合わなかったりすることが多いことから不合格になることが多いと言えるでしょう。
このような応援をされた場合は落ち込みすぎず、面接官の言葉を素直に受け取って他の選考に全力を注ぐのがおすすめです。
結果が出るまで時間がかかる
面接の場はスムーズに終了したのに、結果が出るまでに時間がかかる場合は注意が必要です。他の就活生と比較されているか、不合格ゆえに連絡に時間をかけられている可能性があります。
合否連絡は、事前に企業から指定がない限りどれだけ長くても1週間程度です。
1週間を過ぎても連絡がない場合には、企業の人事担当者へ連絡を取ってみるのも良いでしょう。
企業としては、どうしても合格者の連絡が優先されやすい傾向があります。
そのため、なかなか連絡が来ない場合は「不合格フラグ」が立っている可能性が高いでしょう。
面接で「合格フラグ」を勝ち取るには?
では、面接で「合格フラグ」を勝ち取るにはどのような行動をするべきでしょうか?
具体例を2つご紹介します。
全ての選考に全力で臨む
最も大切なのは、全ての選考に全力で臨むことです。
「この企業は第一志望ではないから」
「この企業の選考は通過しやすいと聞いたから」
こんな理由で選考に常に全力ではない就活生は多くいます。
しかし全力でないことは面接官から見ると一目瞭然です。そのため、必然的に不合格となる可能性が高くなります。
また、面接の振り返りをしようとしても「あの時は全力ではなかったから」という理由で正しい振り返りができなくなってしまいます。
常に面接には全力で臨むからこそ、正しい振り返りができることを念頭に置いて臨みましょう。
正直な回答をする
面接ではつい自分を取り繕いたくなりますが、取り繕うほどに結果がぶれてしまうというリスクがあります。常に自分に正直な回答をすることで、回答のぶれを防ぎ一貫性を持たせることが可能になります。
また、正直に答えることでSPIなどの適性検査との乖離が少なくなり、面接官から見て不思議に思うことも少なくなります。適性検査などでは想像以上に個々人のキャラクターが反映されるため、常に正直な回答をしておくことが無難です。
自分で自分の首を絞めてしまうような発言をしないよう、十分に注意しましょう。
合格フラグ」はあくまでも参考程度にしておこう!
いかがでしたか?
本記事では、そもそも「合格フラグ」は何かということをはじめ、面接で「合格フラグ」を見つけるポイントを詳しくご紹介してきました。
この記事を読んでから過去の面接を振り返ると、「あれは確かに合格フラグだった」と感じることがあるのではないでしょうか。
面接官もひとりの人間だからこそ、よく観察して見てみると実は反応が分かりやすかったりします。「合格フラグ」を常に見抜くことは難しいですが、何となく察知できるようになるだけでも心にゆとりが生まれるのではないでしょうか。
これから面接を控えている人はぜひ「合格フラグ」を見つける気持ちで、面接に臨んでみてはいかがでしょうか。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。